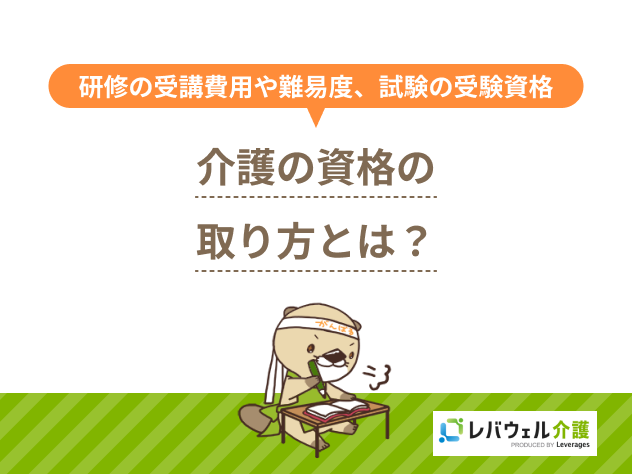
この記事のまとめ
- 介護の資格の取り方は、「スクールに通う」「試験に合格する」の2通りある
- 介護職員初任者研修は、「通信」か「通信と通学」で130時間で取得できる
- 介護福祉士実務者研修に受講要件はなく、450時間の講座修了で取得できる
「介護の資格ってどうやって取るの?」と気になる方もいるでしょう。介護の資格は、通信講座や通学講座を受講して取得する方法と、試験を受験して取得する方法があります。この記事では、介護職員初任者研修など、代表的な介護の資格の取り方を解説。試験の有無や難易度、受験資格、資格取得にかかる費用などもご紹介します。働きながら資格を取る方法もまとめたので、介護業界で活躍したい方は、ぜひ参考にしてください。
介護資格の種類31選!取得方法やメリットを解説します →レバウェル介護の資格スクールはこちら介護資格の取り方は主に2通り
介護資格の主な取り方は、「介護スクールに通う」「受験資格を満たして試験を受ける」の2通りです。介護スクールの講座受講のみで取得できる資格や、受験要件を満たしたうえで試験に合格することで取得できる資格などがあります。
介護業界で活躍したい方は、スキルアップやキャリアアップのためにも、資格の取り方を押さえておきましょう。
1.介護スクールの通信講座や通学講座を受講する
指定のカリキュラムを受講することで取れる介護の資格は多くあります。代表的な介護資格の「介護職員初任者研修」「介護福祉実務者研修」も、研修を修了することで取得可能です。介護職員初任者研修など、修了試験を設けている資格もありますが、研修で学んだ内容を確認するテストなので、難易度は低いでしょう。
介護スクールでは、専用の通信教材で学んだり、実務経験のある講師から直接教わったりできます。そのため、無資格や未経験でも挑戦しやすい資格の取り方といえるでしょう。
2.受験資格を満たしたうえで試験を受けて合格する
試験に合格することで取得できる介護系の資格も多くあります。誰でも受験できる資格だけではなく、介護職としての実務経験や下位資格の取得など、受験に要件が定められている資格もあるでしょう。たとえば、介護福祉士やケアマネジャーの試験は、介護業界における実務経験などが受験資格となっています。
働きながらスキルアップしたい方は、実務経験が求められる専門的な資格を取ることを、キャリアの目標にすると良いかもしれません。
▼関連記事
【福祉系のおすすめ資格一覧】20種類を紹介!取得方法や難易度も解説
働きながら資格を取る方法教えます
取得する介護資格は難易度で選ぶのがおすすめ
介護の経験が浅い方は、「介護職員初任者研修→介護福祉士実務者研修→介護福祉士」の順番で資格を取得するのがおすすめです。介護福祉士を取得した後は、キャリアプランに応じて、ケアマネジャーや認定介護福祉士、認知症ケアに特化した資格などを取ると、より専門性を磨けます。
介護福祉士実務者研修には受講要件がないので、すでに介護業界で働いている無資格の方は、取得を検討してみても良いかもしれません。未経験から受講できますが、介護職員初任者研修といった初歩的な資格から徐々にレベルを上げていけば、学習内容を理解して吸収しやすいでしょう。介護職の資格取得の順番が気になる方は、「介護の資格はどんな順番で取ればいい?取得方法やメリットも解説!」の記事もチェックしてみてください。
介護業界は無資格から働けますが、資格を取得することで、仕事の幅が広がったり業務をスムーズに行えたりします。資格取得のタイミングは人それぞれなので、就職前や転職後など、時間をつくれるときにチャレンジしてみると良いでしょう。
次項からは、それぞれの介護資格の取得方法や受験資格、難易度などを解説するので、ぜひ参考にしてください。
介護職員初任者研修の取り方
介護職員初任者研修の講座は、「通学130時間」もしくは「通信と通学合わせて130時間(通信40.5時間まで)」です。カリキュラム修了後に1時間程度の筆記試験があり、合格すれば介護職員初任者研修を取得できます。筆記試験の難易度は低めで追試可能なので、比較的取得しやすい資格といえるでしょう。
介護職員初任者研修とは、介護職としての倫理や必要な知識、介護技術などを基礎から学べる公的資格です。取得すれば、1人で身体的なケアを行えるようになるので、ホームヘルパーとして働けたり、業務の幅が広がったりします。
初任者研修を取りたい方必見!
レバウェル介護の資格スクールについて知る(新宿校)
介護職員初任者研修の受講要件
介護職員初任者研修に受講要件はありません。介護の基礎を総合的に学べる資格なので、未経験の方や介護業界で働き始めて間もない方におすすめです。介護職として働きながら取得したい方は、「介護職員初任者研修は働きながら取れる!取得する方法とメリットを解説」の記事も参考にしてみてください。
介護職員初任者研修の取得に必要な費用・期間
介護職員初任者研修の受講料は約4~10万円で、取得にかかる期間は1~4ヶ月程度です。介護業界で働きながら取得する場合、費用の補助・受講日の調整など、職場や自治体から支援を受けられる場合もあります。
▼関連記事
介護職員初任者研修の費用を解説!資格取得の支援制度やスクールの選び方
介護職員初任者研修のカリキュラム
厚生労働省の「介護員養成研修の取扱細則について(p.2)」によると、介護職員初任者研修のカリキュラム130時間の内訳は、以下のとおりです。
| 科目 | 研修時間 |
| 1.職務の理解 | 6時間 |
| 2.介護における尊厳の保持・自立支援 | 9時間 |
| 3.介護の基本 | 6時間 |
| 4.介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | 9時間 |
| 5.介護におけるコミュニケーション技術 | 6時間 |
| 6.老化の理解 | 6時間 |
| 7.認知症の理解 | 6時間 |
| 8.障害の理解 | 3時間 |
| 9.こころとからだのしくみと生活支援技術 | 75時間 |
| 10.振り返り | 4時間 |
| 合計 | 130時間 |
参考:厚生労働省「介護員養成研修の取扱細則について(p.2)」
介護職員初任者研修では、講義と演習を通して介護職に必要なスキルを習得します。認知症や障がいについて学ぶ科目もあるので、介護職として働く場合、職場を問わず活かせる資格です。
出典
厚生労働省「介護職員・介護支援専門員」(2024年7月3日)
▼関連記事
介護職員初任者研修とはどんな資格?受講費用を抑える方法や取得のメリット
先に資格を取りたい方へ
無料相談はこちら介護福祉士実務者研修の取り方
介護福祉士実務者研修の講座は、「通学450時間」もしくは「通信と通学合わせて450時間」です。学習時間が長いため、通信と通学を併用して取得する人が多い傾向にあります。修了試験は義務付けられておらず、全カリキュラムを修了することで取得可能です。試験を実施するスクールもありますが、難易度が低く追試できる場合が多いため、比較的取得しやすいでしょう。
介護福祉士実務者研修の受講要件
介護福祉士実務者研修の受講に要件はないため、無資格や未経験の方も受講できます。介護の基礎に加え、介護計画を作成するための知識や医療的ケアなど、専門的な内容も学ぶ研修です。介護に関する基礎知識や経験があれば、実際の業務に当てはめて考えられるので、理解しやすいでしょう。そのため、介護職として働き始めてから取得する人も少なくありません。
介護過程IIIという科目では、事例検討を通して介護過程の展開を学び、根拠に基づいた介護計画を立案するスキルを身につけます。介護福祉士実務者研修を取得すれば、介護過程の知識を証明できるため、訪問介護事業所のサービス提供責任者になることが可能です。
介護福祉士実務者研修の取得に必要な費用・期間
無資格で介護福祉士実務者研修を受講する場合、取得まで最短6ヶ月ほどかかります。費用は約14~22万円です。介護職員初任者研修を取得していれば、共通科目130時間が免除されるので、最短3ヶ月前後、およそ7~19万円で、介護福祉士実務者研修を取得できます。
介護福祉士実者研修の受講にかかる費用について詳しく知りたい方は、「介護福祉士実務者研修の費用はいくら必要?お得に資格を取得する方法を解説」をご参照ください。
▼関連記事
実務者研修取得の最短期間は?介護福祉士国家資格を取る方法も解説!
介護福祉士実務者研修のカリキュラム
厚生労働省の「実務者研修の指定基準について(p.8)」によると、介護福祉士実務者研修のカリキュラム450時間の内訳は、以下のとおりです。
| 科目 | 時間 |
| 人間の尊厳と自立 | 5時間 |
| 社会の理解l | 5時間 |
| 社会の理解ll | 30時間 |
| 介護の基本l | 10時間 |
| 介護の基本ll | 20時間 |
| コミュニケーション技術 | 20時間 |
| 生活支援技術l | 20時間 |
| 生活支援技術ll | 30時間 |
| 介護過程l | 20時間 |
| 介護過程ll | 25時間 |
| 介護過程lll(スクーリング) | 45時間 |
| 発達と老化の理解l | 10時間 |
| 発達と老化の理解ll | 20時間 |
| 認知症の理解l | 10時間 |
| 認知症の理解ll | 20時間 |
| 障害の理解l | 10時間 |
| 障害の理解ll | 20時間 |
| こころとからだのしくみl | 20時間 |
| こころとからだのしくみll | 60時間 |
| 医療的ケア | 50時間 |
| 合計 | 450時間 |
参考:厚生労働省「実務者研修の指定基準について(p.8)」
「社会の理解」では、介護や障がい者支援に関係する法律などを学びます。「発達と老化の理解」は、身体的な発達や老化だけではなく、心理的な成長についても勉強する科目です。なお、介護過程IIIと医療的ケアの演習は、必ず通学で履修しなければなりません。
出典
厚生労働省「介護福祉士養成施設等における「医療的ケアの教育及び実務者研修関係」」(2024年7月3日)
▼関連記事
介護福祉士実務者研修とは?資格取得のメリットや初任者研修との違いを解説
介護福祉士の取り方
介護福祉士は、介護福祉士国家試験に合格し、資格登録をすることで取得できる国家資格です。取得すると、利用者さんの心身の状況に応じた高度な介護ができるようになるだけではなく、職員の指導やサービスの管理に役立つスキルも身につきます。そのため、介護福祉士は、介護職としてスキルアップしたい方や、介護のプロを目指す方におすすめの資格です。
なお、介護福祉士国家試験には、受験資格が設けられています。以下で受験資格を得るルートを解説するので、介護福祉士に興味がある方はチェックしてみましょう。
介護福祉士国家試験の受験資格を得る3つのルート
介護福祉士国家試験の受験資格を得る主な方法は、「実務経験ルート」「養成施設ルート」「福祉系高校ルート」の3通りです。
1.実務経験ルート
実務経験ルートでは、「介護等の業務の実務経験3年以上」「介護福祉士実務者研修修了」という2つの条件を満たすことで、介護福祉士国家試験を受験できます。実務経験に該当するのは、介護職員やホームヘルパー、看護助手などとして、実際に介護を行った期間です。
介護福祉士の実務経験ルートについては、「社会人として働きながら介護福祉士になるには?資格取得のルートを解説!」に詳しくまとめています。
2.養成施設ルート
養成施設ルートでは、介護福祉士養成課程のある短期大学や専門学校などに2年以上通うことで、介護福祉士国家試験の受験資格を得られます。福祉系大学等・社会福祉士養成施設等・保育士養成施設等のいずれかを卒業している方は、介護福祉士養成施設に1年以上通えば、介護福祉士試験を受験可能です。
資格取得にかかる期間は最短1~2年と短いものの、養成施設を卒業するまでには、100~200万円程度の学費がかかります。養成施設ルートは、「高校から進学して介護福祉士になりたい」という学生の方や、「介護福祉士の勉強に集中したい」という方におすすめです。
3.福祉系高校ルート
福祉系高校ルートでは、必要な単位を修めて福祉系高校等を卒業する場合に、介護福祉士国家試験の受験資格を得られます。高校に通いながら介護福祉士の資格を取りたい方は、福祉系高校ルートを選ぶと良いでしょう。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格」(2024年7月3日)
▼関連記事
介護福祉士の受験資格を得るルートを解説!必要な実務経験や試験概要は?
介護福祉士の取得に必要な費用・期間
2024年度の介護福祉士国家試験の受験手数料は18,380円。資格登録にかかる費用は、登録免許税9,000円・登録手数料3,320円の計12,320円です。介護福祉士を取得するためには、受験手数料や資格登録の費用だけではなく、「実務者研修の受講料」もしくは「養成施設や福祉系高校の学費」が必要になるでしょう。
介護福祉士の取得にかかる費用は、「介護福祉士の資格取得にかかる費用は?受験料や実務者研修の受講料金を解説」の記事でもご紹介しているので、あわせてご覧ください。
前述したように、介護福祉士国家試験の受験資格を得るためには、実務経験ルートや福祉系高校ルートの場合は3年、養成施設ルートの場合は最短1~2年かかります。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験申し込み手続き」(2024年7月3日)
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[資格登録]新規登録の申請手続き」(2024年7月3日)
介護福祉士国家試験の概要
下記では、介護福祉士国家試験の出題範囲や難易度を解説します。
介護福祉士国家試験の出題範囲・合格基準
公益財団法人社会福祉振興・試験センターの「[介護福祉士国家試験]合格基準」によると、介護福祉士国家試験の出題範囲となっている科目群は、次のとおりです。
- 1.人間の尊厳と自立、介護の基本
- 2.人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術
- 3.社会の理解
- 4.生活支援技術
- 5.介護過程
- 6.こころとからだのしくみ
- 7.発達と老化の理解
- 8.認知症の理解
- 9.障害の理解
- 10.医療的ケア
- 11.総合問題
主に介護福祉士実務者研修の学習科目が、試験範囲です。介護福祉士国家試験の合格点は、60%程度の得点を基準として、その年の問題の難易度によって補正されます。合格するには、合格点を満たすことと、上記11科目群すべてで得点することが必要です。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]合格基準」(2024年7月3日)
介護福祉士国家試験の合格率
厚生労働省の「第36回介護福祉士国家試験合格発表」によると、2024年1~3月に行われた介護福祉士国家試験の合格率は、82.8%でした。介護福祉士国家試験は、養成施設や実務者研修などで勉強した方が受験することもあり、比較的合格率が高くなっています。実務経験ルートで介護福祉士を取得する場合、「仕事と勉強を両立させるのが大変そう」と感じるかもしれませんが、計画的に学習に取り組むことで合格を目指せるでしょう。
介護福祉士の取得難易度が気になる方は、「介護福祉士国家試験の合格率は?資格の取得難易度と第36回の結果も解説!」も確認してみてください。
出典
厚生労働省「第36回介護福祉士国家試験合格発表」(2024年7月3日)
▼関連記事
介護福祉士とは?仕事内容や資格の取得方法、試験概要をわかりやすく解説!
認定介護福祉士の取り方
認定介護福祉士を取得するには、養成研修を受講して認定を受ける必要があります。認定介護福祉士養成研修には要件が定められており、介護福祉士としての実務経験などがなければ受講できません。
なお、認定介護福祉士とは、一般社団法人認定介護福祉士認証・認定機構が認定する、介護福祉士の上位資格です。
認定介護福祉士養成研修の受講要件
認定介護福祉士認証・認定機構の「認定介護福祉士になるには」によると、認定介護福祉士養成研修を受講するには、以下のすべての条件をクリアする必要があります。
- 介護福祉士としての実務経験が5年以上ある
- 介護福祉士ファーストステップ研修といった研修を100時間以上修了している
- 研修実施団体の課すレポート課題や受講試験で、一定の水準の成績を修めている(免除の場合あり)
- ユニットリーダーやサービス提供責任者としての実務経験がある
認定介護福祉士養成研修の受講要件は、実務経験や研修歴などです。上記の必須要件のほかにも、「居宅・施設系サービスの両方における生活支援の経験があることが望ましい」とされています。研修の実施団体によっては、追加の要件が設けられている場合もあるので、事前に調べておきましょう。
高度なスキルが求められる認定介護福祉士は、介護福祉士としてさらに専門性を高め、介護業界の課題解決に注力したい方におすすめの資格です。
出典
認定介護福祉士認証・認定機構「認定介護福祉士になるには」(2024年7月3日)
認定介護福祉士の取得に必要な費用・期間
認定介護福祉士の資格取得には、前述した介護福祉士の取得費用にプラスして、研修の受講料などがかかります。認定介護福祉士養成研修の受講費用は、科目や実施主体によって異なりますが、全カリキュラムを受講するには30~60万円ほどかかるようです。必要な期間も研修の実施期間によって異なりますが、およそ2~3年かけてすべてのカリキュラムを修了する場合が多くなっています。
認定介護福祉士養成研修のカリキュラム
認定介護福祉士養成研修は、I類とII類に分かれています。認定介護福祉士養成研修I類は、全345時間のカリキュラムで、医療やリハビリ、福祉用具などについて学ぶ内容です。認定介護福祉士養成研修II類は、全255時間のカリキュラムで、介護福祉士ができる地域へのアプローチなどを学習します。
認定介護福祉士になるためには、認定介護福祉士養成研修I類とII類すべての科目を履修しなければなりません。通学が必要な科目が多く、研修の開催は少ないため、取得したい方は早めにリサーチを始めることをおすすめします。
出典
認定介護福祉士認証・認定機構「認定介護福祉士養成研修について」(2024年7月3日)
▼関連記事
認定介護福祉士とは?期待される役割や資格取得に必要な研修を解説
ケアマネージャー(介護支援専門員)の取り方
ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)への合格後、研修を受講し、資格登録をすることで、ケアマネジャーの資格を取得できます。ケアマネジャー試験を受験するには、介護・医療・福祉などの分野における実務経験が必要です。
ケアマネジャー試験の受験資格
ケアマネジャー試験の受験資格は、大きく分けて2通りあります。1つ目は、介護福祉士・社会福祉士・看護師といった特定の国家資格等に基づく実務経験を5年以上積むこと。2つ目は、生活相談員や支援相談員、相談支援専門員などとして、相談援助の実務経験を5年以上積むことです。国家資格等に基づく業務もしくは相談援助業務に5年以上従事することで、ケアマネジャー試験を受験できます。
ケアマネジャーの主な仕事内容は、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成です。利用者さんの生活が充実するよう、アドバイスや調整を行いたい人は、ケアマネジャーの資格取得を目指すと良いかもしれません。
また、受験のために実務経験が求められるため、介護業界で長期的に活躍したい方のキャリアパスとしてもおすすめです。ケママネジャーは信頼性や知名度の高い資格なので、取得すると給与がアップする可能性も高いでしょう。
ケアマネジャーの取得に必要な費用・期間
ケアマネジャーの取得にかかる費用は、都道府県によって異なります。東京都の2024年の費用を例に挙げると、受験にかかる費用は、受験手数料12,400円と振込手数料148円の計12,548円です。介護支援専門員実務研修の受講料は、44,600円(非課税)、資格登録にかかる費用は2,500円となっています。また、ケアマネジャー試験の受験資格を得るために国家資格等を取得する場合は、その分の費用もかかるでしょう。
前述したように、ケアマネジャーの受験資格を得るためには、特定の分野における実務経験が5年以上必要です。たとえば、介護福祉士からケアマネジャーを目指す場合、介護福祉士の取得に最短2~3年かかり、資格登録をしてから5年以上の実務経験を積まなければなりません。無資格からすぐに取得できる資格ではないので、長期的なキャリアプランを考えておくと良いでしょう。
▼関連記事
ケアマネジャーになるには?最短で何年?試験の受験資格や取得の流れを解説
ケアマネジャー試験の概要
ここでは、ケアマネジャー試験の出題範囲や難易度を解説するので、介護業界でのキャリアアップに興味がある方は、ぜひご一読ください。
ケアマネジャー試験の出題範囲・合格基準
ケアマネジャー試験は、介護支援分野25問、保健医療福祉サービス分野35問で構成されます。出題は五肢複択のマークシート方式です。
介護支援分野と保健医療サービス分野のそれぞれで70%以上得点することが、ケアマネジャー試験の合格基準となっています。ただし、具体的な合格点は問題の難易度によって補正されるため、各分野で70%以上得点しても必ず合格できるとは限りません。
ケアマネジャー試験の合格率
厚生労働省の「第26回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」によると、2023年10月に行われたケアマネジャー試験の合格率は21%でした。国家資格や実務経験がある方が受験して、5人に1人ほどしか合格していないことを考えると、難易度は高いといえます。
ケアマネ試験の合格率や勉強法については、「ケアマネ(介護支援専門員)の合格率はどれくらい?難易度や試験の対策方法も」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
出典
東京都福祉保健財団 ケアマネジャー専用サイト「令和6年度 東京都介護支援専門員実務研修受講試験」(2024年7月3日)
厚生労働省「第26回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」(2024年7月3日)
▼関連記事
ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどんな仕事?業務内容や役割を解説!
主任ケアマネージャー(主任介護支援専門員)の取り方
ケアマネジャーの上位資格である「主任ケアマネジャー」を取得するには、主任介護支援専門員研修の受講が必要です。主任介護支援専門員研修の受講には、要件が定められています。
主任介護支援専門員研修の受講要件
厚生労働省の「「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正について(p.2)」によると、主任介護支援専門員研修の受講要件は、以下のいずれかを満たすことです。
- ケアマネジャーとしての実務経験が通算5年(60ヶ月) 以上ある
- 「ケアマネジメントリーダー養成研修修了」または「認定ケアマネジャーの資格保有」という条件を満たしており、ケアマネジャーとしての実務経験が通算3年 (36ヶ月) 以上ある
- 主任介護支援専門員に準ずる者として、地域包括支援センターに勤務している
- 十分な知識と経験を有する介護支援専門員であると、都道府県から認められている
ケアマネジャーとして実務経験を積むことで、主任ケアマネジャーの資格を取得できます。なお、上記のほかに、都道府県が実情に応じて受講要件を設定することもあるようです。
主任介護支援専門員は、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどで活躍しています。支援をするための課題が多い利用者さんを担当するなど、ケアマネジャーのなかでも専門的な業務を行う仕事です。そのため、幅広い利用者さんを支援するスキルを身につけたい方や、ケアマネジャーの指導に関わりたい方が目指すと良いでしょう。
主任ケアマネジャーの取得に必要な費用・期間
主任ケアマネジャーを取得するまでには、ケアマネジャーになるための費用と、主任介護支援専門員研修の受講料が必要です。研修の受講料は都道府県によって異なります。
東京都介護支援専門員研究協議会の「令和6年度東京都主任介護支援専門員研修の実施について」によると、2024年度の東京都における主任介護支援専門員研修の受講料は、52,600円です。
主任介護支援専門員研修の修了には、6ヶ月前後かかります。主任ケアマネジャーになるには、ケアマネジャーとして3~5年勤務してから、研修を修了しなければならないため、計画的に取得を目指しましょう。もっと詳しく知りたい方は、「最短で主任ケアマネジャーになる方法とは?受験資格や研修費用も解説」の記事をご覧ください。
出典
東京都介護支援専門員研究協議会「令和6年度東京都主任介護支援専門員研修の実施について」(2024年7月3日)
主任介護支援専門員研修のカリキュラム
厚生労働省の「「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正について(p.2)」によると、主任介護支援専門員研修のカリキュラムは、以下のとおりです。
- 主任介護支援専門員の役割と視点
- ケアマネジメントの実践における倫理的な課題に対する支援
- ターミナルケア
- 人材育成及び業務管理
- 運営管理におけるリスクマネジメント
- 地域援助技術
- ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実現
- 対人援助者監督指導
- 個別事例を通じた介護支援専門員に対する指導・支援の展開
主任介護支援専門員研修では、ケアマネジメントの実践だけではなく、人材育成や管理業務、地域援助など、福祉に貢献するための幅広い科目を学ぶようです。研修時間は70時間以上と定められています。
出典
厚生労働省「「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正について」(2024年7月3日)
▼関連記事
主任ケアマネとは?求められるスキルや資格を取得するメリットを解説!
介護業界でのスキルアップに役立つ資格の取り方
ここでは、「認知症介護基礎研修」「福祉用具専門相談員」「喀痰吸引等研修」などの資格の取り方をご紹介します。認知症ケアや医療的ケアの知識を得てスキルアップしたい方は、参考にしてみてください。
認知症介護基礎研修の取り方
認知症介護基礎研修は、インターネットで3時間程度の研修を受講することで取得できます。勤務先の介護事業所を通じて、受講を申し込むのが一般的です。
無資格の介護職は、入職から1年以内に認知症介護基礎研修以上の研修を受講する必要があります。「無資格で介護職になったけど、初任者研修や実務者研修はハードルが高い」と感じる方は、とりあえず認知症介護基礎研修を取得すると良いかもしれません。
認知症介護基礎研修は、その名のとおり認知症ケアの基本を学ぶ内容です。認知症の基礎知識は介護職に必要不可欠のため、研修の修了が義務付けられています。
▼関連記事
介護職は無資格で働けなくなるの?認知症介護基礎研修の義務化について
福祉用具専門相談員の取り方
福祉用具専門相談員の資格は、福祉用具専門相談員指定講習を受講し、修了試験に合格することで取得できます。講習は計50時間、6~7日程度で修了可能。オンラインで開催するスクールもあります。福祉用具専門相談員指定講習は、受講要件が定められていない場合が多いようです。
また、介護福祉士や社会福祉士、看護師などの特定の資格を保有する方は、講習を受けなくても福祉用具専門相談員として働けます。
福祉用具専門相談員は、介護ベッドや車いすなどの福祉用具を取り扱う専門職です。福祉用具が必要な利用者さんに対し、適切な福祉用具の選定を行ったり、使用方法を伝えたりする役割があります。福祉用具専門相談員の仕事に興味がある方は、「福祉用具専門相談員とはどんな職種?仕事内容や必要な資格、年収を解説!」の記事をご参照ください。
喀痰吸引等研修の取り方
喀痰吸引等研修は、第1号研修~第3号研修に分かれています。それぞれ、定められた基本研修と実地研修を修了することで取得できます。
喀痰吸引等研修とは、介護職員等がたんの吸引や経管栄養を行うために必要な資格です。最上位である第1号研修を取得すれば、介護職員等が行える医療的ケアのすべてに対応可能。第2号研修の場合は行えるケアの範囲が限られ、第3号研修の場合は行えるケアの内容と相手が限られます。
実際に医療的ケアを行うためには、該当する喀痰吸引等研修を修了したうえで、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けなければなりません。また、勤務する事業所が、「登録特定行為事業者」として登録していることも求められます。
出典
厚生労働省「喀痰吸引等研修」(2024年7月3日)
▼関連記事
喀痰吸引等研修とは?講義内容や介護職員が受講するメリットも解説
認知症ケア専門士の取り方
認知症ケア専門士は、認知症ケア専門士認定試験に合格して研修動画を視聴し、資格登録することで取得できます。試験の受験資格は、「過去10年間において、3年以上認知症ケアの実務経験があること」です。実務経験に職種の定めはないため、介護従事者だけではなく、医療関係者なども受験できます。
認知症ケア専門士になるには、第1次試験と第2次試験の両方への合格が必要です。第1次試験は、4分野・計200問。五肢択一方式で出題されます。各分野で70%以上得点できれば合格です。第2次試験は計3題の論述試験で、第1次試験の全分野に合格した人が受験できます。
認知症ケア専門士を取得すると、認知症の利用者さんに対するアセスメントのスキルや、医療的なアプローチに関する知識が身につくでしょう。そのため、認知症の利用者さんと関わることが多い、グループホームのスタッフなどにおすすめの資格です。
認知症ケア専門士については、「認知症ケア専門士とは?認定試験の合格率と難易度、資格の取得方法を解説!」の記事にもまとめています。
出典
認知症ケア専門士認定試験「試験概要:受験資格」(2024年7月3日)
▼関連記事
【認知症介護の資格一覧】取得方法や試験の難易度、習得できるスキルを解説
レクリエーション介護士の取り方
レクリエーション介護士は、2級と1級があります。レクリエーション介護士2級は、通信講座や通学講座、団体研修などで取得可能です。受講要件はないので、誰でもチャレンジできます。テキストやDVDで学習した後に、添削課題を提出し、試験で60点以上得点できれば合格です。通信講座の場合はおよそ3ヶ月、通学講座の場合は最短2日で取得できます。
レクリエーション介護士1級は、2級を保有する方が対象です。取得するには、通学講座の受講、試験への合格、現場実習という3つの段階を踏む必要があります。通学講座は、全4日間です。試験は実技と筆記があり、それぞれ60%以上正答すれば合格です。現場実習では、自身の職場以外の介護事業所3施設で、レクリエーションを行います。
レクリエーション介護士は、「新しいレクリエーションが思い浮かばない…」「もっとレクリエーションを盛り上げて楽しんでもらいたい」という方におすすめの資格です。学習内容は、デイサービスなどの介護施設での仕事に役立ちます。
▼関連記事
レクリエーション介護士とは?資格の概要や試験内容を分かりやすく解説
介護予防運動指導員の取り方
介護予防運動指導員の資格は、介護予防運動指導員養成講座を受講し、修了試験に合格することで取得できます。
介護予防運動指導員養成講座を受講できるのは、「2年以上の実務経験があり、初任者研修や実務者研修を修了している」「看護師や介護福祉士など、特定の国家資格がある」という要件のいずれかを満たす人です。講座は計33時間で、講義と演習に分かれています。このうち講義は、e‐ラーニングで受講できる場合もあるようです。
介護予防運動指導員の資格は、デイサービスや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、比較的介護度が低めの利用者さんと関わる職場で、特に役立つでしょう。
▼関連記事
介護予防運動指導員のメリットとは?資格の概要と取得方法もご紹介!
介護事務に関する資格の取り方
介護事務に関する資格には、介護事務管理士(R)やケアクラーク(R)などがあります。介護事務管理士(R)とケアクラーク(R)は、試験に合格することで取得可能で、受験資格は設けられていません。
介護事務の仕事は資格がなくても行えますが、介護報酬請求や介護保険などに関する知識・スキルが求められます。そのため、資格を取得しておけば、業務に活かせたり、就職に有利になったりするでしょう。
介護事務に関する資格は、介護事務の仕事がしたい方や、介護事業所の運営に携わりたい方、ケアマネジャーなどにおすすめです。
▼関連記事
介護事務管理士とはどんな資格?取得するメリットや試験概要、難易度を解説
介護の資格を働きながら取得する方法
介護業界で働きながら資格を取得する方は多くいます。働きながら資格取得を成功させるには、無理のない学習スケジュールを立てることが大切です。以下では、仕事と両立させやすい資格取得の方法をご紹介します。
週1ペースで介護資格のスクールに通う
介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修には、通学が必須の科目があります。働きながら取得する場合は、通信講座を併用しつつ、通学は週1回ペースにすると、資格取得にかかる負担を減らせるでしょう。
通学が必要な資格を取得する場合、通学のペースに加え、講座の振替ができるのかなども確認しておくと安心です。体調不良や仕事の都合で受講できない日があるときに、無料で振替対応してくれるスクールだと、無理せず取得しやすいといえます。
先に資格を取りたい方へ
無料相談はこちら自分のペースで通信講座を受講する
社会人の方には、レクリエーション介護士2級のように、通信講座のみで取得できる資格もおすすめです。添削課題で評価をもらえたり、質問に対応してもらえたりする通信講座もあるので、サポート体制や評価方法をチェックしたうえで選ぶと良いでしょう。
通信講座の場合、標準学習期間や合計時間を参考に受講のスケジュールを立てると、スムーズに資格を取得できます。課題提出や在宅試験に期日が設けられている場合もあるので、受講前に必ず確認しておきましょう。
スキマ時間に勉強して試験を受ける
受験資格を満たして試験を受け、合格することで取得できる「認知症ケア専門士」なども、働きながら資格を取りたい方におすすめです。身につけたいスキルに応じた資格を選ぶと良いでしょう。試験の範囲や難易度を確認して、スケジュールに余裕をもって勉強を進めるのが、合格するためのポイントです。
また、公的な資格である介護福祉士やケアマネジャーも、実務経験が要件の一つなので、働きながら取得する人が多い傾向にあります。介護福祉士の実務経験ルートの場合は「実務者研修の修了(受験資格)」、ケアマネジャーの場合は「試験合格後の介護支援専門員実務研修の修了」が求められるため、完全に独学で取得することはできません。
研修時間や勉強時間の確保が必要になるので、働きながら合格を目指す場合は、資格取得に協力的な職場を選ぶと良いでしょう。
▼関連記事
働きながら取得しやすい介護の資格とは?必要な期間や方法、費用も解説!
介護の資格を就職前に取得する方法
「働きながら資格を取るのは大変そう…」と感じる場合、介護資格を取得してから就職する選択肢もあります。無資格・未経験で介護業界に就職すると、「介護技術がなくて不安」「仕事を覚えるのが大変」と感じるかもしれません。いきなり介護職になるのが心配な方は、就職前に資格を取ることを検討すると良いでしょう。
費用負担やスケジュール確保の難しさが気になっている場合、ハローワークの職業訓練を利用して資格を取得する方法もあります。職業訓練とは、主に離職者の資格取得を支援する制度です。条件を満たせば、失業手当などの給付金を受給しながら通学できるため、資格取得に専念できる点がメリットです。
また、独自で資格取得支援制度を設けている自治体もあります。介護資格の取得をサポートする制度について詳しく知りたい方は、「介護職員初任者研修を無料で取得する方法は?メリットや支援制度を解説」の記事もご参照ください。
介護資格の取り方である「通信」と「通学」の違い
介護の資格講座には、自宅で受講できる通信講座と、スクールで学習する通学講座があります。それぞれの学習方法のメリットを、以下で解説します。
通学講座を選ぶメリット
通学講座を選ぶメリットは、短期間で集中して資格を取得できることです。決められた日数で確実に講座を修了できるので、少しでも早く資格を取得したい方は、通学講座を選ぶと良いかもしれません。
また、通学講座には、「直接講師に質問でき、疑問をすぐに解消できる」「一緒に学ぶ受講生がいるため、モチベーションを保ちやすい」というメリットもあります。
通信講座を選ぶメリット
通信講座を選ぶメリットは、自分のペースで勉強を進められることです。仕事やプライベートが忙しい場合も、時間があるタイミングで学習に取り組めます。
たとえば、初任者研修や実務者研修には通学必須の科目がありますが、取得の負担を減らすために、通信講座の併用も可能です。自身の学習スタイルや生活に合わせて、上手に通信講座を活用すれば、資格を取得しやすいでしょう。
「無資格で介護業界に転職するのは不安…」「無理なく通えるスクールで学びたい」という方には、レバウェルスクール介護(旧 きらケアステップアップスクール)がおすすめです。介護や福祉の業界で実際に働く講師から授業を受けられるので、資格の勉強をしながら、介護職の仕事内容もイメージできます。就業に関する相談やサポートも可能です。週1日の介護職員初任者研修のコースなら、無理なく通いやすいでしょう。資格取得について話を聞いてみたい方は、ぜひ気軽にご相談ください。
先に資格を取りたい方へ
無料相談はこちら介護の資格を取得するメリット
介護の資格を取得すると、下記のようなメリットがあります。
- 介護に関する専門的な知識・スキルが身につく
- 資格手当や昇給によって給料がアップする可能性がある
- 役職に就くなど、キャリアアップできるチャンスが増える
- 介護業界での就職・転職に有利になる
「初任者研修を取得すると、1人で身体介護ができる」「実務者研修を取得すると、サービス提供責任者になれる」「介護福祉士を取得すると、認定介護福祉士やケアマネジャーを目指せる」など、資格取得のメリットは豊富です。介護の資格を取得すると、スキルが身につくだけではなく、キャリアアップや昇給のチャンスも増えます。
介護業界でのキャリアアップに有効な資格の組み合わせ
複数の資格を取得すれば、仕事の幅がさらに広がります。介護・福祉業界でキャリアアップしたい方におすすめの資格の組み合わせを、以下でチェックしてみましょう。
介護職員初任者研修+レクリエーション介護士
介護業務全般に携わるために必要な「介護職員初任者研修」に加え、「レクリエーション介護士」を取得すれば、介護職としてさらに活躍できるでしょう。初任者研修で学ぶコミュニケーション技法と、レクリエーションに関するスキルの両方が身につけば、介護施設での仕事に役立ちます。
介護職がレクリエーションを工夫することで、利用者さんの認知機能や身体機能の維持・向上に貢献できるでしょう。
介護福祉士+ケアマネジャー(介護支援専門員)
介護福祉士を基礎資格としてケアマネジャーになる方は多くいます。介護福祉士がケアマネジャーになると、介護現場の状況を理解したうえでケアプランを作成できるため、介護職と連携しやすいでしょう。
介護福祉士として培った観察力があれば、利用者さんの機能低下や病状回復などを敏感に察知できます。また、認知症の方や高齢者、障がいのある方などに対応するコミュニケーション能力も、ケアマネジメントに活かせるでしょう。
介護福祉士+保育士
介護福祉士と保育士の資格の組み合わせは、障がいのある子どもの支援に携わりたい方におすすめです。放課後等デイサービスなどにおいて、障がいのある子どもやその保護者の支援を行いたい方は、取得を検討すると良いかもしれません。
介護福祉士と保育士は、ダブルライセンスを目指しやすいのが特徴です。介護福祉士が保育士試験を受ける場合、「社会的養護」「子ども家庭福祉」「社会福祉」の科目が免除されます。なお、保育士試験を受けるには、学歴もしくは実務経験の要件を満たさなければなりません。
また、保育士養成施設等を卒業した方は、介護福祉士養成施設に1年通えば、介護福祉士試験の受験資格を得られます。
▼関連記事
【障がい者支援に役立つ資格一覧】取得方法や難易度、習得できるスキルは?
介護資格の取り方に関するよくある質問
ここでは、介護資格の取り方に関するよくある質問に回答します。「資格を取りたいけど大変そう…」「取得しやすい資格はある?」と気になっている方は、チェックしてみてください。
介護の資格は無料で取得できますか?
介護職員初任者研修といった資格は、無料で取得できる場合があります。「介護職に転職する前に、ハローワークの職業訓練を利用して取得する方法」「職場の介護事業所に受講費用を負担してもらう方法」などがあるようです。働きながら無料で資格を取りたい場合は、資格取得支援に力を入れている職場を選ぶと良いでしょう。「介護の資格を安く取りたい!「初任者研修」と「実務者研修」を無料or割引で受講する方法」の記事では、介護系の資格をお得に取得する方法を解説しています。
介護の資格は独学で取れるの?
独学で取れる介護の資格もあります。たとえば、無資格の介護職が主な受講対象である「認知症介護基礎研修」は、インターネットを使って1日で取得可能です。レクリエーション介護士2級は、通信講座の受講と課題提出を行い、在宅試験に合格することで取得できます。なお、「介護職員初任者研修」や「介護福祉士実務者研修」は、通学が必須の科目があるので、独学では取得できません。
介護資格の取り方や難易度が知りたいです!
介護職の入門的な資格である「介護職員初任者研修」は、130時間のカリキュラムを受講し、修了試験に合格すれば取得できます。学習期間は1~4ヶ月ほどで、無資格・未経験の方も取得しやすい資格です。初任者研修の上位資格である「介護福祉士実務者研修」は、450時間のカリキュラムと医療的ケアの実習を修了することで取得できます。修了試験は義務付けられていませんが、修了には6ヶ月ほどかかるため、初任者研修よりは取得の難易度が高いでしょう。介護の資格の難易度は、「介護の資格の難易度を種類ごとに解説!取得方法や試験の合格率、要件とは?」の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
まとめ
介護の資格の取り方は主に2通りで、スクールの講座を受講する方法と、試験に合格する方法があります。「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者研修」は、無資格や未経験の方も、講座を修了することで取得可能です。介護福祉士やケアマネジャーの資格は、実務経験といった要件を満たし、試験に合格して登録を行えば、取得できます。
働きながら資格を取る場合、余裕のあるスケジュールを設定することで、負担を減らせるでしょう。通学が少ない講座を選んだり、勤務先の介護事業所に協力してもらったりすれば、無理なく資格を取得できます。
「資格を取得してから介護業界に転職したい」という方は、ハローワークの職業訓練や自治体の資格取得支援制度を活用するのがおすすめです。先に資格を取得しておくことで、未経験でも基礎が身についた状態から仕事を始められます。
「介護業界って実際どんな感じなの?」「資格をいつ取るべきか迷っている」など、介護の仕事に関する疑問やお悩みがある方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界を専門とする就職・転職エージェントです。介護業界で初めて働く方や、キャリアアップを目指す方などの、総合的なサポートを実施しています。求人の紹介だけではなく、職場見学のセッティングや面接対策のお手伝いも可能です。サービスは無料なので、「資格取得や求人の情報を聞いてみたい」という方は、ぜひご活用ください。
働きながら資格を取る方法教えます
先に資格を取りたい方へ
無料相談はこちら 未経験可の介護求人はこちら
未経験可の介護求人はこちら