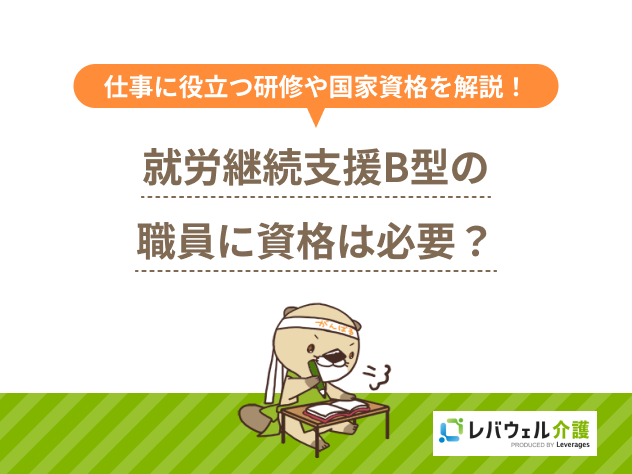
この記事のまとめ
- 就労継続支援B型事業所の職員に要件はないが、資格を取れば支援に活かせる
- 就労継続支援に役立つ介護の資格は、初任者研修や難病患者等ホームヘルパー
- 生活支援員におすすめの資格は、「知的障害を理解するための基礎講座」など
「就労継続支援B型の職員に必要な資格はあるの?」と気になる方もいるでしょう。就労継続支援B型事業所の職員に必須要件はありませんが、資格を取得すれば支援に活かせます。この記事では、就労継続支援の職員におすすめの資格を21種類ご紹介。それぞれの資格で身につく知識や取得方法を解説します。「資格を取得してスキルアップしたい」「就労継続支援B型事業所への転職を成功させたい」という方は、ぜひご一読ください。
就労継続支援B型事業所の職員に資格は必要?
就労継続支援B型事業所の職員に必須の資格はないため、無資格や未経験から働ける職場も少なくありません。
資格を取得するメリットは、障がいのある方に適切な支援ができるようになることです。そのため、長期的に福祉関係の仕事をしたい方や、キャリアアップを目指す方は、資格を取得すると良いでしょう。
なかには、求人に保有資格の条件を定めている職場もあります。また、就労継続支援B型事業所のサービス管理責任者になるには、実務経験を積んで研修を受けなければいけません。資格があれば、応募できる求人の選択肢を増やせることも、メリットの一つです。
▼関連記事
障害者施設で働くにはどんな資格が必要?仕事内容や働くメリットも紹介
今の職場に満足していますか?
就労継続支援B型事業所の職員におすすめの資格一覧
就労継続支援B型事業所の職員におすすめの資格を、以下の表にまとめました。
| 資格の特徴 | 資格・研修の名称 |
| 介護系の公的資格 | ・介護職員初任者研修 ・介護福祉士実務者研修 ・介護福祉士 ・難病患者等ホームヘルパー養成研修 |
| 福祉系の公的資格 | ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・社会福祉主事任用資格 |
| 相談援助に活かせる公的資格 | ・相談支援従事者初任者研修 ・サービス管理責任者研修 ・介護支援専門員(ケアマネジャー) |
| 生活支援員におすすめの資格 | ・普通自動車第一種運転免許 ・ケアクラーク(R) ・知的障害を理解するための基礎講座 ・発達障害コミュニケーション指導者 ・公認心理師 |
| 職業指導員・作業指導員におすすめの資格 | ・キャリアコンサルタント ・産業カウンセラー ・作業療法士 |
| 業務に活かせるその他の資格 | ・調理師免許 ・MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト) ・介護福祉経営士 |
就労継続支援B型の仕事には、介護や福祉系の公的資格をはじめ、さまざまな資格を活かせます。就きたい職種や働きたい職場、身につけたいスキルなどを考え、自分に合った資格を選びましょう。次項からは、それぞれの資格の特徴や取得方法を解説します。
就労継続支援B型の職員に役立つ介護系の公的資格
ここでは、就労継続支援B型の仕事に活かせる、介護系の公的資格について解説します。生活支援員や職業指導員として、利用者さんと適切なコミュニケーションを取ることに役立つ資格です。
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修では、介護職員としての基礎知識を学習します。介護施設や障害者施設で働く方や、転職を検討している方が、最初にチャレンジすることも多い資格です。
介護職員初任者研修で身につく知識・技術
介護職員初任者研修を受講すると、福祉の仕事に携わるうえでの基礎となる職業倫理や介護技術が身につきます。講義だけではなくグループワークなどの演習も行い、障がいのある方や高齢者との会話に活かせるコミュニケーション技法も学ぶ内容です。
介護職員初任者研修のカリキュラムについては、「介護職員初任者研修の内容を解説!筆記試験や実技テストの難易度、取得方法」で解説しています。
介護職員初任者研修の取得方法
介護スクールで130時間の研修を受け、約1時間の筆記試験に合格すれば、介護職員初任者研修を取得できます。筆記試験の難易度は低めで、万が一不合格になってしまっても、追試できる場合が多いようです。
介護職員初任者研修は、通信で受講できる科目と通学が必須の科目があります。資格取得にかかる期間は1~4ヶ月程度です。働きながらでも資格を取得しやすいよう、通学を週1回だけにしているスクールもあります。
介護職員初任者研修には受講要件が設けられていないため、無資格・未経験から取得できるのが特徴です。
出典
厚生労働省「介護職員・介護支援専門員」(2024年9月11日)
▼関連記事
介護職員初任者研修とはどんな資格?受講費用を抑える方法や取得のメリット
初任者研修を取りたい方必見!
レバウェル介護の資格スクールについて知る(新宿校)
介護福祉士実務者研修
介護福祉士実務者研修は、前述の初任者研修の上位にあたる資格です。その名のとおり、介護福祉士になるために必要な知識を習得できます。
介護福祉士実務者研修で身につく知識・技術
介護福祉士実務者研修の学習内容は、「社会保障制度」「障がいの種類や特性」「難病の種類や症状」などです。介護過程という科目では、利用者さんの情報収集や課題分析を行うスキルも習得します。
自信をもって適切なケアができるようになりたい方や、介護福祉士を目指したい方におすすめの資格です。介護福祉士実務者研修について詳しく知りたい方は、「介護福祉士実務者研修とは?資格取得のメリットや初任者研修との違いを解説」の記事をご覧ください。
介護福祉士実務者研修の取得方法
介護スクールを利用して、450時間のカリキュラムと医療的ケアの演習を受講することで、介護福祉士実務者研修を取得できます。介護過程IIIと医療的ケアの演習は通学が必須ですが、そのほかの科目は通信で受講可能です。
介護福祉士実務者研修も、受講要件がないため誰でも取得を目指せます。学習時間が長いため、無資格・未経験から取得する場合は6ヶ月以上かかるようです。
出典
厚生労働省「介護福祉士養成施設等における「医療的ケアの教育及び実務者研修関係」」(2024年9月11日)
▼関連記事
介護福祉士実務者研修は働きながら取れるの?資格を取得する方法を解説
介護福祉士
介護福祉士は、介護分野における唯一の国家資格です。福祉業界での信頼性が高いので、取得すると給与アップにつながることも少なくありません。また、介護福祉士の資格があれば、福祉施設への就職や転職にも有利に働くでしょう。
介護福祉士の取得で身につく知識・技術
介護福祉士を取得すると、障害者支援に関連する法律や制度の知識が身につきます。障がいの特性に応じたコミュニケーションや支援を行うスキルも習得できる、専門性の高い資格です。このほか、チームケアのスキルや地域福祉に関する知識も学べます。
介護福祉士の詳細は、「介護福祉士とは?仕事内容や資格の取得方法、試験概要をわかりやすく解説!」の記事にまとめています。
介護福祉士の取得方法
介護福祉士は、介護福祉士国家試験に合格することで取得できます。この介護福祉士試験を受けるためには、受験資格を満たさなければなりません。
受験資格を満たす主な方法は、「実務経験ルート」「養成施設ルート」「福祉系高校ルート」の3通りです。最も受験者数の多い実務経験ルートの場合、「実務者研修修了」「介護業務等の実務経験3年」という2つの条件を満たすことで、介護福祉士試験を受験できます。
なお、就労継続支援B型事業所における実務経験では、介護福祉士試験の受験資格を満たせない可能性があるので注意しましょう。
介護福祉士を目指す場合、「介護福祉士を取得してから就労継続支援B型事業所で働く」「養成施設ルートで介護福祉士試験を受験する」など、資格の取得ルートを含めたキャリアプランを検討することが重要です。
介護福祉士の取得に興味がある方は、「介護福祉士の受験資格を得るルートを解説!必要な実務経験や試験概要は?」で受験資格についてチェックしておきましょう。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験」(2024年9月11日)
難病患者等ホームヘルパー養成研修
難病患者等ホームヘルパー養成研修とは、難病を患う方の多様なニーズに対応し、適切な支援を行うための資格です。ホームヘルパーの仕事だけではなく、難病のある方と関わる際にも活かせます。
難病患者等ホームヘルパー養成研修で身につく知識・技術
難病患者等ホームヘルパー養成研修では、難病の各疾患や、関連する医療制度・福祉サービスについて学びます。具体的には、パーキンソン病や全身性エリテマトーデス、ALS(筋萎縮性側索硬化症)など、患者数が多い難病に関する知識を習得可能です。また、難病を患う利用者さんの心理的なケアやご家族の支援を行うスキルも身につけられます。
難病患者等ホームヘルパーの取得方法
難病患者等ホームヘルパー養成研修は、入門課程・基礎課程I・基礎課程IIに分かれています。このうち、基礎課程I・基礎課程IIを実施しているスクールが多いようです。
基礎課程Iを受講するには、介護職員初任者研修以上の資格が求められます。基礎課程IIの受講には、介護福祉士実務者研修以上の資格が必要です。それぞれ、初任者研修や実務者研修を修了する見込みがある方も受講できます。一般的に、基礎課程Iは4時間、基礎課程IIは6時間のカリキュラムです。
出典
厚生労働省「難病患者等ホームヘルパー養成研修事業の運営について」(2024年9月11日)
▼関連記事
介護資格の種類31選!取得方法やメリットを解説します
就労継続支援B型の職員に役立つ福祉系の公的資格
就労継続支援B型の職員に役立つ福祉系の公的資格である「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」について、以下で解説します。
社会福祉士
社会福祉士は、日常生活に困難を抱える方の相談に乗り、助言するための国家資格です。ソーシャルワーカーとして働く際に求められることが多く、保有していると相談援助のスキルを高く評価されます。
社会福祉士の取得で身につく知識・技術
社会福祉士を取得するには、福祉に関する幅広い知識が必要です。そのため、資格を取得する過程で、高齢者福祉や児童・家庭福祉、貧困に対する支援などの知識が身につくでしょう。相談援助を行ううえで必要な法制度の知識や、心理的ケアの方法も学習します。
社会福祉士の資格があれば、複数の課題を抱える利用者さんの包括的な支援や、地域福祉の改善といった専門的な役割を担うことも可能です。
社会福祉士の取得方法
社会福祉士は、受験資格を満たして社会福祉士国家試験を受験し、合格することで取得できます。社会福祉士試験の受験資格を得るルートは、大きく分けて「福祉系大学ルート」「短期養成施設ルート」「一般養成施設ルート」の3通りです。社会福祉に関する科目の履修や、相談援助の実務経験という要件を満たすことで受験できます。
社会福祉士の資格については、「社会福祉士資格を取得する7つのメリットとは?取得方法やルートも解説!」の記事でも解説しているので、あわせて参考にしてください。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「社会福祉士国家試験」(2024年9月11日)
精神保健福祉士
精神保健福祉士は、精神障がいのある方の社会生活を支援するための国家資格です。保有していると、社会福祉に関する知識や、精神障がいのある方に対する相談援助のスキルの証明になります。
精神保健福祉士の取得で身につく知識・技術
精神保健福祉士の資格取得では、精神疾患の種類や症状、治療法などを学びます。精神障がいのある方の就労準備や定着へ向けた支援の知識、ソーシャルワークに必要なスキルも習得可能です。そのため、精神保健福祉士の資格は、就労など社会生活に課題がある方の支援に活かせます。
精神保健福祉士の取得方法
精神保健福祉士は、精神保健福祉士国家試験に合格することで取得できます。精神保健福祉士試験の受験ルートは、「保健福祉大学ルート」「短期養成施設ルート」「一般養成施設ルート」のいずれか。精神保健福祉に関する科目の履修や、相談援助の実務経験が求められます。
精神保健福祉士国家試験の受験資格について詳しく知りたい方は、「ソーシャルワーカーに必要な資格の取り方や難易度は?職種別の要件も解説!」をご覧ください。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「精神保健福祉士国家試験」(2024年9月11日)
社会福祉主事任用資格
社会福祉主事は、福祉事務所や児童相談所などの行政機関で働くために必要な任用資格です。障害者施設や高齢者施設で相談援助を行う際に、社会福祉士・精神保健福祉士と並んで要件になることも多くなっています。
社会福祉主事任用資格の取得で身につく知識・技術
社会福祉主事任用資格を取得する際に、社会福祉や障害者支援、心理学などについて学びます。そのため、資格を取得すれば、身体障がい・知的障がい・精神障がいがある方に対し、自立支援や相談援助を行うための知識が身につくでしょう。
社会福祉主事任用資格の取得方法
大学や養成機関、通信教育、都道府県講習会において、社会福祉に関する科目を履修することで、社会福祉主事任用資格を取得できます。通信教育や養成施設、都道府県講習会などの対象者はそれぞれ異なるので、取得するときは自身に合った方法を選びましょう。
なお、社会福祉士や精神保健福祉士の資格保有者は、すでに社会福祉主事の任用要件を満たしています。
出典
厚生労働省「社会福祉主事任用資格の取得方法」(2024年9月11日)
▼関連記事
【福祉系のおすすめ資格一覧】20種類を紹介!取得方法や難易度も解説
就労継続支援B型の職員に役立つ相談援助系の公的資格
ここでは、就労継続支援B型における相談援助に役立つ「相談支援従事者初任者研修」「サービス管理責任者研修」「介護支援専門員(ケアマネジャー)」の資格をご紹介します。
相談支援従事者初任者研修
相談支援従事者初任者研修は、相談支援専門員として、障がいのある方の「サービス等利用計画」を作成するための資格です。相談支援従事者初任者研修は、サービス管理責任者として個別支援計画を作成する際にも役立ちます。
なお、相談支援専門員になるには、相談支援従事者初任者研修の修了に加え、3~10年の実務経験が必要です。
相談支援従事者初任者研修で身につく知識・技術
相談支援従事者初任者研修は、目標設定から評価までの相談支援プロセスのスキルを習得し、障害者支援をマネジメントするための資格です。利用者さんの意思を尊重し、計画作成を行う知識を学べます。相談支援従事者初任者研修を受講すれば、障がいのある方が、強みを活かして社会生活を送ることを支援するスキルが身につくでしょう。
相談支援従事者初任者研修の取得方法
相談支援従事者初任者研修は、42.5時間のカリキュラムを修了することで取得できます。受講にあたって必須の要件はありませんが、相談支援に従事する予定の方を対象者とする自治体が多いようです。相談支援専門員として配置される予定の方の受講が優先される場合もあります。
出典
東京都福祉局「相談支援従事者研修」(2024年9月11日)
サービス管理責任者研修
サービス管理責任者研修は、就労継続支援B型事業所などに配置義務がある「サービス管理責任者」の要件となる資格です。サービス管理責任者研修の修了に加え、相談支援従事者初任者研修の講義の一部(11.5時間)を受講するなどの要件を満たせば、サービス管理責任者として従事できます。
サービス管理責任者研修で身につく知識・技術
サービス管理責任者研修は、サービス管理責任者等基礎研修とサービス管理責任者等実践研修に分かれています。
基礎研修の学習内容は、個別支援計画の意義やプロセス、利用者主体のアセスメントなどです。講義と演習により、サービス管理責任者として個別支援計画を作成するための実践的なスキルを身につけます。
実践研修の学習内容は、モニタリング手法や職員の指導、多職種連携・地域連携などについてです。受講することで、利用者さんに質の高いサービスを提供するためのスキルを習得できるでしょう。
サービス管理責任者研修の取得方法
サービス管理責任者研修は、「サービス管理責任者」や「児童発達支援管理責任者」として従事する予定の方を対象とする自治体が多い傾向があります。
基礎研修を受講するためには、1~6年の実務経験が必要です。基礎研修を受講することで、サービス管理責任者の一部の業務に携われるようになります。
一般的に、実践研修を受講するには、基礎研修受講後に2年以上の実務経験が必要です。実践研修を修了することで、サービス管理責任者として従事できます。
出典
東京都福祉局「サービス管理責任者研修」(2024年9月11日)
介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護支援専門員は、ケアマネジャーとして働くために必要な資格です。取得することで、介護支援や保健医療福祉について、高い専門性があることを証明できます。介護福祉士や社会福祉士が、キャリアアップのために取得することも少なくありません。
介護支援専門員の取得で身につく知識・技術
介護支援専門員を取得する過程では、介護保険やケアマネジメントの知識が身につきます。そのため、利用者さんの相談に乗り、課題解決の方法をアドバイスしたり、相談支援専門員と連携したりするのに活かせるでしょう。高齢の利用者さんがいる就労継続支援B型事業所では、介護支援専門員のスキルが特に役立ちます。
介護支援専門員の取得方法
介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)に合格し、87時間の研修を受けることで、介護支援専門員の資格を取得できます。
ケアマネジャー試験を受験するには、「特定の国家資格等に基づく業務の実務経験」または「相談援助の実務経験」が5年以上必要です。特定の国家資格等には、介護福祉士や社会福祉士、看護師・准看護師などが含まれます。また、相談援助で要件を満たせるのは、障害福祉サービス事業所の相談支援専門員や、介護施設の生活相談員などです。
ケアマネジャーの資格に興味がある方は、「ケアマネジャーになるには最短で何年?介護支援専門員の受験資格を解説」の記事もご参照ください。
出典
公益財団法人 東京都福祉保健財団「ケアマネジャー専用サイト」(2024年9月11日)
就労継続支援B型の生活支援員におすすめの資格
就労継続支援B型事業所における日常生活の支援や、相談・助言などに役立つ資格を、下記にまとめました。生活支援員として幅広く活躍したい方は、参考にしてください。
普通自動車第一種運転免許
車で利用者さんの送迎を行う就労継続支援B型事業所で働く場合、普通自動車第一種運転免許を活かせるでしょう。なかには、運転免許を応募要件とする求人もあります。
就労継続支援B型事業所に通所する方法は、「利用者さんが一人で通う」「ご家族やグループホームの職員が送迎する」「事業所の職員が送迎する」など、施設や利用者さんによってさまざまです。運転業務の有無は事業所によって異なるので、運転に自信のない方や免許がない方は、求人の仕事内容や必須資格を確認して応募しましょう。
ケア クラーク(R)
ケア クラーク(R)は、一般財団法人 日本医療教育財団が認定する資格で、主に介護事務の仕事に役立ちます。
ケア クラーク(R)の取得で身につく知識・技術
ケアクラーク(R)の資格取得では、介護報酬請求事務のスキルに加え、ソーシャルワークやコミュニケーション技法、障がいのある方への援助に関する知識も習得できます。
そのため、就労継続支援B型事業所において、障害福祉サービス費の請求業務などの事務作業に携わる場合に役立つでしょう。福祉に関する知識は、生活支援員として利用者さんの相談に乗る際に活かせます。
ケア クラーク(R)の取得方法
ケア クラーク(R)を取得するには、ケアクラーク技能認定試験への合格が必要です。要件はなく、誰でも受験できます。ケアクラーク技能認定試験は毎月行われているため、取得のチャンスは多いでしょう。
介護事務に活かせる資格を取得したい方は、「介護事務に資格は必要?合格率や取得方法、仕事に活かせるスキル」もご一読ください。
出典
一般財団法人 日本医療教育財団「ケアクラーク技能認定試験(ケア クラーク(R))」(2024年9月11日)
知的障害を理解するための基礎講座
「知的障害を理解するための基礎講座」は、公益財団法人 日本知的障害者福祉協会が開催しています。
知的障害を理解するための基礎講座で身につく知識・技術
知的障害を理解するための基礎講座では、障害福祉に関する制度や障害の理解、知的障がいのある利用者さんの意思決定の支援・権利擁護などについて学習します。就労支援B型事業所の利用者さんのなかでも、知的障がいのある方は特に多いため、生活支援員などの仕事に活かせる資格です。
知的障害を理解するための基礎講座を修了する方法
知的障害を理解するための基礎講座は、6ヶ月の通信教育を受ければ修了できます。テキストや動画で学習し、確認テストで復習するという流れです。レポート課題では、知的障害福祉の実務経験のある講師に対して質問もできます。
知的障害を理解するための基礎講座に受講要件は定められておらず、知的障がいのある方の支援を基礎から学べるため、初心者にもおすすめです。
出典
公益財団法人 日本知的障害者福祉協会「知的障害を理解するための基礎講座」(2024年9月11日)
発達障害コミュニケーション初級指導者
発達障害コミュニケーション初級指導者は、一般社団法人 日本医療福祉教育コミュニケーション協会が認定する資格です。
発達障害コミュニケーション初級指導者の取得で身につく知識
発達障害コミュニケーション初級指導者の講座を受講すると、発達障がい・知的障がいの特性や関係する法制度、就労支援などの知識が身につきます。資格を取得すれば、障害特性を理解して適切な支援を行えるようになるでしょう。
発達障害コミュニケーション初級指導者の取得方法
講習会・オンライン講座・DVD視聴のいずれかの方法で学習し、レポート課題に合格すれば、発達障害コミュニケーション初級指導者を取得できます。講座は5時間以上で、1~2日で受講する場合が多いようです。発達障害コミュニケーション初級指導者の講座に受講要件はないため、誰でも取得を目指せます。
出典
一般社団法人 日本医療福祉教育コミュニケーション協会「発達障害コミュニケーション指導者」(2024年9月11日)
公認心理師
公認心理師は、心理学の分野で唯一の国家資格です。心理学に基づくカウンセリングを行うために役立ちます。
公認心理師の取得で身につく知識・技術
公認心理師になる過程では、障害者支援に関する法律や障がいのある方への合理的配慮、就労支援などについて学びます。さまざまな方のカウンセリングに対応できるコミュニケーション技術も習得可能です。
公認心理師の取得方法
公認心理師試験に合格することで、公認心理師の資格を取得できます。
公認心理師試験には受験資格があり、専門科目の履修や実務経験などが必要です。具体的には、「4年制大学で指定科目を履修し、大学院で指定科目を履修」「4年制大学で指定科目を履修し、プログラム施設で2年以上の実務経験を積む」などの要件を満たすことで、公認心理師試験の受験資格を満たせます。
出典
一般財団法人 公認心理師試験研究センター「公認心理師試験」(2024年9月11日)
就労継続支援B型の職業指導員におすすめの資格
以下では、就労継続支援B型事業所で、職業指導員や就労支援員の仕事に活かせる資格をご紹介します。「利用者さんの就労の力になりたい」という方は、ぜひご一読ください。
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタントは、職業選択やキャリア形成を支援するための国家資格です。
キャリアコンサルタントの取得で身につく知識・技術
キャリアコンサルタントの資格を取得すると、適性のある職業のアドバイスや、能力開発の指導などを行うスキルが身につきます。また、地域社会や事業所などの環境改善に向けた連携もできるようになるでしょう。
就労継続支援B型の仕事では、通所継続や一般就労への移行の支援、カウンセリングなどにスキルを活かせます。
キャリアコンサルタントの取得方法
キャリアコンサルタントの資格を取得するには、キャリアコンサルタント試験への合格が必要です。
キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が指定するキャリアコンサルタント講習の過程を修了することで受験できます。また、キャリアアドバイザーなどとして3年以上の実務経験がある方や、キャリアコンサルティング職種の技能検定に合格した方も受験が可能です。
出典
厚生労働省「キャリアコンサルタントになりたい方へ」(2024年9月11日)
産業カウンセラー
産業カウンセラーは、一般社団法人 日本産業カウンセラー協会が認定する資格です。
産業カウンセラーの資格取得で身につく知識・技術
産業カウンセラー養成講座では、カウンセリングに役立つ傾聴スキルや、心理学・精神医学、キャリア形成の支援などについて学びます。職場環境の改善や人間関係を開発するスキルも習得可能です。
就労継続支援B型事業所では、利用者さんのキャリアの相談対応や精神的なケア、作業環境の改善などの業務に活かせます。産業カウンセラーは、福祉の仕事をする人が取得している実績がある資格です。
産業カウンセラーの取得方法
産業カウンセラー試験に合格することで、産業カウンセラーの資格を取得できます。産業カウンセラー試験には受験資格があり、産業カウンセラー養成講座(R)を修了して受験するルートが一般的です。
産業カウンセラー養成講座(R)は、104時間のうち90時間以上出席し、提出課題や確認テストで評価基準を満たすことで修了できます。受講方法は、「通学のみ」「オンラインのみ」「通学28時間とオンライン76時間」の3パターン。受講期間は、6ヶ月もしくは10ヶ月です。
受講開始時点で18歳以上であれば、学歴や職歴を問わず、産業カウンセラー養成講座(R)を受験できます。
出典
一般社団法人 日本産業カウンセラー協会「産業カウンセラー養成講座(R)」(2024年9月11日)
作業療法士
作業療法士は、身体障がいや精神障がいのある方に対し、動作の指導や訓練などを行うための国家資格です。
作業療法士の取得で身につく知識・技術
作業療法士を取得すると、作業の特性・過程・環境を分析し、改善を図るスキルが身につきます。就労環境の整備や就労継続支援などについても学ぶ資格です。そのため、就労継続支援B型事業所において、職業指導員・作業指導員といった職種として働く場合に役立つでしょう。
作業療法士の取得方法
作業療法士の資格は、要件を満たして作業療法士国家試験を受験し、合格することで取得できます。作業療法士試験の受験資格を得る一般的なルートは、大学・短大・専門学校などに3年以上通い、作業療法士養成課程を修了して卒業することです。
出典
厚生労働省「作業療法士国家試験の施行」(2024年9月11日)
就労継続支援B型の職員に役立つその他の資格
ここでは、就労継続支援B型事業所の職員が、利用者さんの支援や、事務作業・営業活動などに活かせる上記以外の資格をご紹介します。生産活動の支援などの参考にしてください。
調理師免許
調理師免許があれば、利用者さんの生活支援や、食品に関わる生産活動の指導に活かせます。
調理師免許の取得で身につく知識・技術
調理師免許を取得すると、食品衛生や栄養管理、調理などのスキルが身につきます。
就労継続支援B型事業所では、生活支援として調理や栄養指導を行う際に、調理師免許のような関連性の高い資格が役立つでしょう。また、そうざい製造・菓子製造・パン製造・飲食店などの生産活動をサポートする場合も知識を活かせます。
調理師免許の取得方法
調理師免許は、調理師試験に合格することで取得できます。調理師免許の受験資格があるのは、中学卒業以上で、2年以上調理業務に従事したと認められる人です。
出典
公益社団法人 調理技術技能センター「調理師試験について」(2024年9月11日)
MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)
MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)は、マイクロソフト社が主催する資格です。Word、Excel、PowerPointなどの試験科目があり、さらにソフトのバージョンごとに資格が分かれています。
MOSの取得で身につく知識・技術
MOSを取得すると、文書作成や表計算、プレゼンテーション資料の作成など、受験する試験科目に関するスキルが身につきます。
PCスキルは、業務の管理といった事務作業を行う際に役立つでしょう。また、就労継続支援B型の利用者さんが、PCを使った生産活動を行う場合は、職業指導にもPCスキルを活かせます。
MOSの取得方法
MOSの資格は、試験に合格することで取得できます。WordやExcelの試験は、一般レベルと上級レベルに分かれているようです。いずれの資格も、受験に要件は設けられていないので、自身に合った種類・レベルの試験を選んで受験できます。
介護福祉経営士
介護福祉経営士は、一般社団法人 日本介護福祉経営人材教育協会が認定する資格です。
介護福祉経営士の取得で身につく知識・技術
介護福祉経営士を取得すると、介護福祉サービスに関する知識に加え、福祉施設の経営に必要な組織運営やマーケティングのスキルが身につきます。就労継続支援B型事業所では、目標工賃達成指導員やサービス管理責任者、管理者といった職種の業務に特に役立つ資格です。
介護福祉経営士の取得方法
介護福祉経営士の資格は、2級と1級に分かれています。
介護福祉経営士2級は、資格認定試験に合格することで取得可能です。成年被後見人・被保佐人でなければ、学歴や年齢を問わず受験できます。
介護福祉経営士1級資格認定試験を受験できるのは、2級に合格している正会員の方です。1級試験に合格し、介護福祉経営士実践研修を修了することで、介護福祉経営士1級として資格登録できます。
介護福祉経営士の詳細が知りたい方は、「介護福祉経営士とは?資格認定までの流れを解説【管理職候補者必見です!】」をご参照ください。
出典
一般社団法人 日本介護福祉経営人材教育協会「介護福祉経営士:受験と資格認定について」(2024年9月11日)
▼関連記事
【障がい者支援に役立つ資格一覧】取得方法や難易度、習得できるスキルは?
就労継続支援B型事業所の職員が資格を取得するメリット
就労継続支援B型事業所の職員が資格を取得すると、次のようなメリットがあります。
- 専門性の高い支援を行える
- 自信をもって根拠に基づいた支援ができる
- 無資格よりも就職に有利になる
「難病に関する資格」「知的障がいに関する資格」「職業指導に役立つ資格」などを取得すれば、専門分野に特化したスキルが身につきます。関わる利用者さんや自分の職種を加味して資格を選ぶことで、実務に活かせるでしょう。
資格を取得してスキルアップすることで、自信をもって支援に携われたり、転職の際にスキルをアピールできたりするのもメリットです。
無資格で就労継続支援B型事業所への就職を成功させる方法
無資格から就職する場合、入職後の資格取得やスキルアップへの意欲をアピールするのがおすすめです。また、求人だけではなく事業所のWebサイトなどからも情報を集め、支援方針への共感や業務に活かせるスキルを、採用担当者に伝えましょう。
就労継続支援B型の仕事内容への興味や、その事業所で働きたい理由を整理し、具体的な志望動機を作成するのも、就職成功のためのポイントです。
▼関連記事
【障害者施設の志望動機の例文】新卒・未経験者・経験者の履歴書の書き方
就職前に就労継続支援B型の仕事について確認しておこう
就労継続支援B型事業所への就職を検討している方は、業務内容や仕事の魅力をチェックしておきましょう。仕事への理解を深めることで、履歴書や面接で効果的なアピールができます。
就労継続支援B型事業所の職員の仕事内容
就労継続支援B型事業所の職員は、軽作業や清掃、菓子製造など、利用者さんが取り組むさまざまな生産活動の指導・支援を行います。利用者さんの仕事を受託・請負するための営業活動や、関係者との連携なども業務の一環です。また、利用者さんが安定した生活を送れるよう、ご本人やご家族の相談にも対応します。
就労継続支援B型事業所で活躍する職種は、利用者さんの技術指導を行う「職業指導員」や、日常生活を支援する「生活支援員」などです。また、管理者やサービス管理責任者といった、管理職としてサービスのマネジメントを行う職種も働いています。
就労継続支援B型の仕事の魅力
利用者さんの社会参加や自立を支援できるのが、就労継続支援B型の仕事の魅力です。利用者さんが目標を達成して喜ぶ姿や、できなかったことができるようになる過程などを、身近で見られます。そのため、利用者さんへの貢献を実感できるやりがいがあるでしょう。また、利用者さんの将来を見据えたケアを行うのも特徴です。
今の職場に満足していますか?
就労継続支援B型事業所の職員によくある質問
ここでは、就労継続支援B型事業所の職員によくある質問に回答します。就労継続支援B型の仕事に携わっている方や、就職・転職を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
就労継続支援B型の仕事の取り方を教えてください!
就労継続支援B型事業所が仕事を取るには、施設の取り組みを地域住民や企業に知ってもらう必要があります。仕事を確保するために、WebサイトやSNSの運用、パンフレットの配布などで営業を行う場合が多いようです。複数の事業に携わったり、生産性を上げて受注量を増やしたりすることで、利用者さんに安定して生産活動を提供できるでしょう。
就労継続支援B型の実務経験で介護福祉士を受験できる?
職業指導員・作業指導員・就労支援員・目標工賃達成指導員・賃金向上達成指導員などの職種の実務経験では、介護福祉士試験の受験資格を満たせません。就労継続支援B型事業所の生活支援員で、「主たる業務が介護等の業務」の場合は、介護福祉士試験の受験資格を満たせます。就労継続支援事業所で働いていて、介護福祉士を取得したい方は、勤務先に確認・相談してみてください。
就労継続支援B型事業所の職員の給料はどれくらい?
厚生労働省の「令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果(p.80)」によると、就労継続支援B型事業所で働く福祉・介護職員(常勤)の平均給与は279,990円でした。福祉・介護職員とは、生活支援員や職業指導員などの職種です。
なお、就労継続支援B型事業所の福祉・介護職員の給与は、2021年12月からの1年間で、16,580円上がりました。障害福祉サービス等報酬改定の影響などにより、福祉・介護職員の処遇改善は今後も続くと期待できます。
出典
厚生労働省「令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」(2024年9月11日)
まとめ
就労継続支援B型事業所の職員として働くために、必須の資格はありません。しかし、障害者支援には、障がいの理解やコミュニケーション能力が求められるため、資格を取得すれば業務に役立てられるでしょう。
就労継続支援B型の仕事に活かせる資格は、「介護職員初任者研修」「サービス管理責任者研修」「知的障害を理解するための基礎講座」などです。自身のスキルや身につけたい知識を考えて、チャレンジする資格を選びましょう。
資格を取得するメリットは、専門性の高い支援ができるようになることです。また、就職の際に、資格が有利に働く可能性もあります。
無資格から就労継続支援B型事業所に就職する場合は、施設の情報収集をしたり、自身のスキルを整理したりすることが大切です。応募先の仕事内容を把握し、活かせる経験やスキルを上手にアピールできれば、就職成功につながるでしょう。
「就労継続支援B型事業所で働きたい」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)をご利用ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護・福祉業界に特化した就職・転職エージェントです。障害者施設の採用事情に詳しいアドバイザーが、求職活動をサポートいたします。「資格取得や今後のキャリアについて考えたい」といった相談も歓迎です。サービスは無料なので、福祉業界での就職活動やキャリア相談にご活用くださいね。
今の職場に満足していますか?
 介護福祉士実務者研修のスクールの情報を見てみる
介護福祉士実務者研修のスクールの情報を見てみる