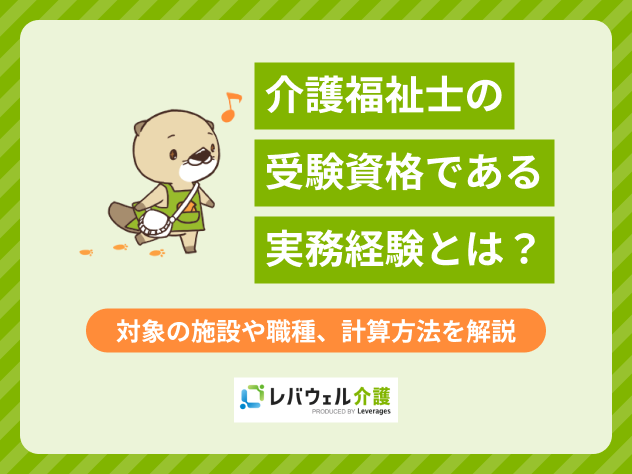
この記事のまとめ
- 働いて介護福祉士の受験資格を得るには、実務経験と実務者研修の修了が必要
- 受験資格として必要な実務経験は、従業期間3年以上と従事日数540日以上
- 短時間勤務の場合も、介護等に従事した日はすべて1日分の実務経験になる
「介護福祉士国家試験の受験資格の実務経験って、どれくらいの期間が必要なの?」と気になる方もいるでしょう。実務経験ルートで介護福祉士国家試験の受験資格を得るには、「3年以上の実務経験」と「実務者研修の取得」が必要です。この記事では、受験資格である介護の実務経験の期間や計算方法を解説します。実務経験の対象となる施設・事業所と職種も紹介するので、介護福祉士の取得を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
介護福祉士とは?仕事内容や資格の取得方法、試験概要をわかりやすく解説!介護福祉士の受験資格を得るには実務経験が必要
介護福祉士国家資格の受験資格を得る方法は各ルートで異なります。実務経験ルートで介護福祉士国家試験を受験するには、「介護福祉士実務者研修の修了」と「介護等の業務の実務経験3年以上」が必要です。介護等の業務とは、身体的・精神的な障がいなどにより日常生活に支援を要する方に対する介護、および介護者に対して指導を行うことを指します。
介護福祉士は、専門的な介護の知識やスキルが身についていることを証明できる資格です。資格取得によって、コミュニケーション方法や認知症・障がいへの理解を深めることができます。社会人として働きながら介護福祉士の取得を目指す方は、介護職員として実務経験を積みながら試験勉強を進めましょう。
▼関連記事
介護福祉士の受験資格を得るルートを解説!必要な実務経験や試験概要は?
社会人として働きながら介護福祉士になるには?資格取得のルートを解説!
働きながら資格を取る方法教えます
介護福祉士国家試験の受験資格の実務経験は3年以上
介護福祉士試験の受験資格である実務経験3年とは、「従業期間3年以上かつ、従事日数540日以上」のことです。 介護施設に3年以上在職していたとしても、休職などにより介護業務に従事していない期間がある場合は、受験資格を満たせない可能性があります。
「自分はいつ介護福祉士国家試験を受験できるの?」と気になっている方は、以下で詳細を確認してみましょう。
従業期間:3年以上(1,095日以上)
従業期間とは、実務経験に該当する施設・事業所に在職している期間のことです。介護福祉士国家試験を受験するには、3年(1,095日)以上、対象の施設・事業所に所属して、介護等の業務に従事する必要があります。従業期間は、年次有給休暇や欠勤、産前産後休暇・介護休暇などの休職期間を含めて計算が可能です。従業期間をいつ満たせるのかは、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの「受験資格 – 従業期間計算表」で確認できます。
従事日数:540日以上
従事日数とは、実務経験の対象となる施設・事業所で、実際に介護等の業務を行った日数のことです。介護福祉士国家試験を受験するには、実務経験に該当する職種として540日以上働く必要があります。介護等の業務を行っていれば、資格の有無に関わらず、勤務していた期間を従事日数として計算可能です。しかし、研修や出張、事務作業を行った日など、介護等の業務を行っていない日は、従事日数にカウントされないので注意しましょう。
介護福祉士国家試験は「実務経験見込み」でも申し込みできる
介護福祉士国家試験実施年度の3月31日までに、従業期間と従事日数という実務経験要件を満たす見込みがあれば、「実務経験見込み」として試験に申し込めます。
実務経験見込みの方は、介護福祉士国家試験に申し込む際に「実務経験見込証明書」の提出が必要です。そして、受験資格の実務経験を満たした時点で、「実務経験証明書」を提出します。
複数の事業所を掛け持ちしていて従事日数内訳証明書を作成する場合は、これまでの勤務実績や労働条件をもとに、出勤日数を推測して実務経験を満たせる日付を記載しましょう。
介護福祉士の受験に必要な実務経験証明書については、「実務経験証明書の提出が必要」で後述しているので、あわせてご覧ください。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験+実務者研修」(2024年7月5日)
介護福祉士の受験資格である実務経験の計算方法
「パートでも実務経験に含まれるの?」「転職したときは、どう計算すれば良いの?」と実務経験の計算方法に悩む方もいるでしょう。ここでは、ケース別の実務経験の計算方法を解説します。実務経験の計算方法にお悩みの方は、ぜひ確認してみてください。
パート勤務の介護職員の計算方法
パート・アルバイトや派遣社員などの方も、介護等の業務の実務経験が3年以上があり、実務者研修を取得すれば、介護福祉士国家試験の受験資格を満たせます。短時間勤務でも1日として実務経験の日数にカウントできるので、通常どおりに計算すれば実務経験の日数を算出できるでしょう。非常勤で勤務日数が少なく、自分の従事日数が分からないという方は、職場に確認してみてください。
転職経験がある介護職員の計算方法
転職して複数の職場で介護等の業務を行っていた場合、これまでの実務経験を合わせて計算できます。前職で2年以上、現職で1年以上働いていれば、3年以上の実務経験を満たすことが可能です。また、現在は福祉・介護の仕事に就いていなくても、過去に実務経験の対象施設や事業所で3年以上働いていれば、介護福祉士試験の受験資格を満たせます。
なお、今の職場だけで「従業期間3年以上かつ従事日数540日以上」をクリアできる場合は、前の職場の実務経験を合計する必要はありません。
掛け持ちしている介護職員の計算方法
複数の施設で仕事を掛け持ちしている方も、実際に介護等の業務に従事した日数を計算しましょう。1日で複数の施設を掛け持ちしている場合、1日として計算します。たとえば、同じ日に施設Aと施設Bで働いたとしても、従事日数は1日です。働いた日数を受験資格として求められているので、複数の職場を同じ日に掛け持ちしても、2日分として計算できることはありません。
なお、同一期間に仕事を掛け持ちしている方は、それぞれの職場の「従事日数内訳証明書」が必要になります。
介護福祉士の受験資格である実務経験の対象となる施設は?
介護福祉士国家試験の受験資格の対象となる実務経験の分野は、以下の5つです。
- 児童分野
- 障害者分野
- 高齢者分野
- その他の分野
- 介護等の便宜を供与する事業
実務経験の対象になるのは、障がいのある方や高齢者の方などにサービスを提供する分野・事業です。
以下で、各分野の対象となる施設・事業所と職種を紹介するので、介護福祉士国家試験の受験を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
児童分野で受験資格となる施設・事業と職種
公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 児童分野」によると、児童分野で介護福祉士国家試験の受験資格となる施設・事業と職種は、以下のとおりです。
|
実務経験の対象となる施設・事業 |
実務経験の対象となる主な職種 |
|
・知的障害児施設 |
・保育士 |
|
・保育所等訪問支援 |
・訪問支援員 |
参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 児童分野」
障がいのある子どもの介護に直接関わる人は、児童分野における実務経験で介護福祉士試験を受験できるでしょう。ただし、実務経験となる施設・事業と職種として定められていても、細かな条件がついている施設や職種もあります。介護福祉士を目指す方は、自身の業務が実務経験の対象となるのか確認しておきましょう。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 児童分野」(2024年7月5日)
障害者分野で受験資格となる施設・事業と職種
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 障害者分野」障害者分野で介護福祉士国家試験の受験資格となる施設・事業と職種は、以下のとおりです。
|
実務経験の対象となる施設・事業 |
実務経験の対象となる主な職種 |
|
・障害者デイサービス事業(2006年9月までの事業) |
・介護職員 |
|
・居宅介護 |
・訪問介護員 |
参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 障害者分野」
障害者総合支援法に関係する施設・事業が対象です。なお、「保育士」「生活支援員」「指導員」「精神障害者社会復帰指導員」「世話人」などとして、実務経験を満たすには、施設に介護職員がおらず、主な業務として「介護等の業務」と明記されている必要があります。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 障害者分野」(2024年7月5日)
▼関連記事
障害者支援施設とは?仕事内容や一日の流れ、高齢者介護との違いを解説!
高齢者分野で受験資格となる施設・事業と職種
公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 高齢者分野」によると、高齢者分野で介護福祉士国家試験の受験資格となる施設・事業と職種は、以下のとおりです。
|
実務経験の対象となる施設・事業 |
実務経験の対象となる主な職種 |
|
・老人デイサービスセンター |
・介護職員 |
|
・指定訪問介護 |
・訪問介護員 |
|
・指定訪問看護 |
・看護補助者 |
参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 高齢者分野」
老人福祉法・介護保険法に関係する施設・事業が、実務経験の対象です。高齢者分野の場合も、「介護等の業務」を主に行う職種として実務経験を積めば、介護福祉士試験を受験できます
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 高齢者分野」(2024年7月5日)
その他の分野で受験資格となる施設・事業と職種
公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 その他の分野」によると、実務経験に該当するその他の分野は、「病院または診療所」「生活保護法関係の施設」「その他の社会福祉施設等」の3つで構成されています。
病院または診療所
同サイトによると、病院または診療所において、介護職員・看護補助者・看護助手などとして介護等の業務をメインで行う場合も、介護福祉士試験の実務経験要件を満たせます。なお、ベッドメーキングや検体の運搬など、介護に直接関わらない業務しか行わない場合は、実務経験として認められません。
▼関連記事
介護福祉士の受験資格に看護助手の実務経験も含まれる?職種の違いも解説!
生活保護法関係の施設
介護福祉士国家試験の受験資格となる「生活保護法関係の施設」での実務経験に該当する施設と職種は、以下のとおりです。
|
実務経験の対象となる施設 |
実務経験の対象となる主な職種 |
|
・救護施設 |
・介護職員 |
参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 その他の分野」
生活保護法関係の救護施設や更生施設で働く介護職員や介助員の経験も、受験資格である実務経験の対象です。ただし、ほかの分野の対象施設・事業所と同様に、介護等の業務を行わない場合は、実務経験にカウントされません。
その他の社会福祉施設等
介護福祉士国家試験の受験資格となる「その他の社会福祉施設等」での実務経験に該当する施設・事業と職種は、以下のとおりです。
|
実務経験の対象となる施設・事業 |
実務経験の対象となる主な職種 |
|
・地域福祉センター |
・介護職員 |
|
・原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業 |
・原爆被爆者家庭奉仕員 |
|
・家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行なう場合に限る) |
・家政婦 |
|
・訪問看護事業(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業) |
・看護補助者 |
参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 その他の分野」
上記のように、設置数が少ない社会福祉施設で働く方も、介護等の業務に従事していれば、実務経験として認められる場合が多いようです。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 その他の分野」(2024年7月5日)
介護等の便宜を供与する事業で受験資格となる事業と職種
公益財団法人社会福祉振興・試験センターの「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 介護等の便宜を供与する事業」によると、介護等の便宜を供与する事業分野で介護福祉士国家試験の受験資格となる事業と職種は、以下のとおりです。
|
実務経験の対象となる事業 |
実務経験の対象となる主な職種 |
|
・地方公共団体が定める条例、実施要綱等に基づく事業 |
・介護職員 |
参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 介護等の便宜を供与する事業」
介護保険法・障害者総合支援法の基準該当以外で、受験資格の実務経験の対象になる事業もあります。ただし、条件が定められているので、「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 介護等の便宜を供与する事業」を確認しておくと安心です。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲 介護等の便宜を供与する事業」(2024年7月5日)
介護福祉士の受験資格に含まれない職種
主たる業務が介護等の業務と認められない職種では、介護福祉士国家試験の受験資格である実務経験を満たせません。受験資格の対象とならない職種を以下にまとめているので、確認してみましょう。
- 生活相談員、支援相談員など、相談援助業務を行なう職種
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 計画作成担当者
- サービス提供責任者
- 福祉用具専門相談員
- 医師
- 看護師、准看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- あん摩マッサージ指圧師
- 心理指導担当職員
- 作業指導員
- 職業指導員
- 就労支援員
- 目標工賃達成指導員
- 賃金向上達成指導員
- 事務員
- 調理員
- 栄養士
- 介護施設で働く警備員や運転手
介護事業所で働く生活相談員やケアマネジャー、サービス提供責任者などの職種は、介護福祉士の受験資格の対象外です。ただし、介護業務を兼務していて、従事日数540日以上を満たす場合は、介護福祉士試験の実務経験要件を満たせます。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲」(2024年7月5日)
介護福祉士試験を実務経験で受験する際の注意点
ここでは、介護福祉士試験を実務経験ルートで受験する際の注意点を解説します。実務経験を積む以外に必要な準備をまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
実務経験証明書の提出が必要
「実務経験証明書」は、受験資格である従業期間・従事日数を満たしていることを証明する書類です。受験申し込みの際に、申込書と一緒に提出しなければいけません。
実務経験証明書を作成するのは、受験する本人ではなく勤務先の代表者です。転職した方は、前の職場の実務経験証明書も必要になる可能性があるので、余裕をもって準備しましょう。
また、実務経験証明書と申込書以外にも、「受験手数料払込証明書貼付用紙」「受験用写真等確認票」「従事日数内訳証明書」「実務者研修修了証明書の原本」の提出が必要です。
介護福祉士実務者研修の修了が求められる
実務経験ルートで受験する場合は、実務経験を積むだけではなく、介護福祉士実務者研修を修了しなければ、介護福祉士国家試験を受験できません。
介護福祉士実務者研修を取得するには、450時間20科目のカリキュラムの修了が必須です。取得まで6ヶ月程度かかるため、介護福祉士国家試験の受験年度の3月末までに取得できるよう、スケジュールの調整を行いましょう。
「介護職員初任者研修」「ホームヘルパー1級・2級」「介護職員基礎研修」などを過去に修了した方は、その分のカリキュラムが免除されるので、比較的短期間で介護福祉士実務者研修を取得できます。なお、「ホームヘルパー1級・2級」「介護職員基礎研修」はすでに廃止されている資格なので、新たに取得することはできません。
▼関連記事
実務者研修取得の最短期間は?介護福祉士国家資格を取る方法も解説!
余裕を持った学習スケジュールを立てる
介護福祉士国家試験に合格するためには、余裕を持って受験日までの学習スケジュールを立てることが大切です。
厚生労働省の「第36回介護福祉士国家試験合格発表」によると、2024年に実施された介護福祉士国家試験の合格率は、82.8%でした。合格率は高い傾向にありますが、2割程度は不合格になっている人もいるので、計画的に学習スケジュールを立て、コツコツと試験勉強を進めましょう。
介護福祉士国家試験の学習スケジュールや受験対策は、「介護福祉士の資格は独学で取得できる?受験対策と学習期間とは」の記事で解説しているので、あわせてご一読ください。
出典
厚生労働省「第36回介護福祉士国家試験合格発表」(2024年7月5日)
介護福祉士を取得するメリット
実務経験を積んで介護福祉士を取得すると、「給与がアップする」「転職で有利になる」などのメリットがあります。以下では、介護福祉士を取得するメリットを解説するので、ぜひご覧ください。
給与がアップする
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.157) 」によると、介護福祉の平均給与は331,080円です。無資格者の平均給与は268,680円で、介護福祉士の平均給与のほうが6万円以上高くなっています。平均年収で比較すると、無資格者との給与差は約75万円もあるように、介護福祉士を取得すると収入アップが見込めるでしょう。また、給与がアップすることで、仕事へのモチベーションも高まるかもしれません。
出典
厚生労働省「介護従事者処遇状況等調査結果」(2024年7月5日)
できる仕事が増える
介護福祉士になると、フロアリーダーや職員の指導係など、任される仕事が増え、仕事のやりがいを感じられるでしょう。できる業務の幅が広がることはキャリアアップにもつながります。やりたい介護を実現できるようになり、提供する介護サービスの質も向上するでしょう。
転職で有利になる
実務経験を積んで介護福祉士を取得すると、専門的な介護の知識やスキルがあることを証明できるので、転職をする際に有利になるでしょう。介護福祉士以上の資格を応募要件とする求人にも応募できるようになるので、応募可能な求人が増え、より多くの選択肢の中から自分に合った職場を探すことができます。
介護福祉士を取得するメリットは、「介護福祉士資格は意味ない?いらないといわれる理由や取得のメリットを解説」の記事でも解説しています。
介護福祉士の受験資格に関するよくある質問
ここでは、介護福祉士の受験資格に関するよくある質問に回答します。「私の実務経験で受験資格を満たせるの?」と気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。
介護福祉士の受験資格である実務経験3年とはどのような計算方法なの?
介護福祉士の受験資格である実務経験は、「従業期間3年以上(1,095日以上)」と「従事日数540日以上」です。従業期間は、施設・事業所に在職している期間のことで、産休・育休、介護休暇などの期間も含まれます。従事日数とは、働いた日数のことです。休日だけではなく、研修や事務作業などで介護業務を行っていない日も、従事日数には含まれません。なお、短時間勤務の場合も、1日の実務経験として算定できます。
介護福祉士の受験資格には看護助手の実務経験も含まれますか?
介護福祉士の受験資格である実務経験には、看護助手の実務経験も含まれます。パートの看護助手でも、従業期間・従業日数の要件を満たせば受験要件を満たすことが可能です。介護福祉士の資格取得支援を行っている病院もあるので、看護助手の方もキャリアアップ・給与アップのために、介護福祉士の取得を目指してみると良いでしょう。
介護福祉士の実務経験証明書は前の職場の分も必要?
今の職場だけで実務経験3年かつ540日以上を満たせない場合は、前の職場の実務経験証明書も必要です。基本的に、実務経験証明書の作成は、事業所の代表者に依頼します。しかし、前の職場がすでに廃業しているときは、自身で書類を用意することになるでしょう。いずれの場合も、早めに確認して作成の準備をすることが大切です。「介護福祉士試験に必要な実務経験証明書とは?入手場所や作成方法を解説!」の記事では、実務経験証明書作成の流れを解説しているので、あわせてご覧ください。
まとめ
介護福祉士国家試験を実務経験ルートで受験する場合、受験資格として「3年以上の実務経験」と「介護福祉士実務者研修の修了」の両方を満たす必要があります。介護福祉士を受験するのに必要な実務経験3年とは、従業期間3年(1,095日)かつ従事日数540日以上のことです。介護福祉士試験は、実務経験を満たす見込みの状況でも受験の申し込みが可能。介護福祉士国家試験が実施される年の3月末までに受験資格を満たす予定の方は、試験に申し込めます。
介護福祉士の受験資格として必要な実務経験を積めるのは、児童分野・障害者分野・高齢者分野などの施設や事業所などです。施設や職種によっては、条件が定められていることもあるので、自分の仕事が実務経験に当てはまるのか、事前に確認しておくと良いでしょう。
「実務経験を積んで介護福祉士の資格を取得したい」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)へご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化したエージェントです。介護等の実務経験の対象となる施設の求人を多数取り扱っています。ヒアリングをもとに希望条件に合った求人をご提案。専任のアドバイザーがサポートするので、介護業界でのキャリアプランを相談することも可能です。サービスはすべて無料なので、お気軽にお問い合わせください。
働きながら資格を取る方法教えます
 障害者施設の求人はこちら
障害者施設の求人はこちら