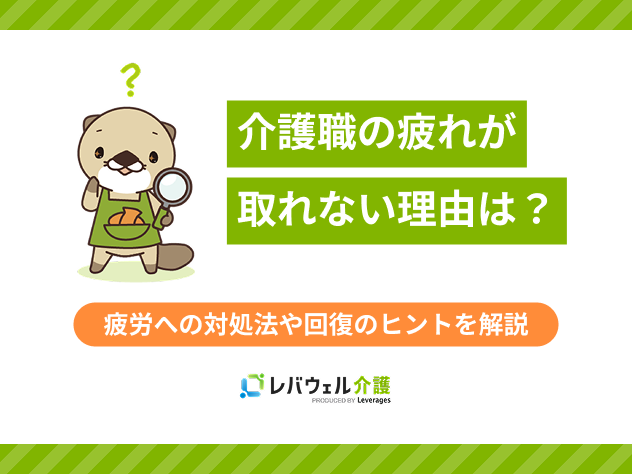
この記事のまとめ
- 介護職の疲れが取れない原因は、人間関係の悪さや身体的なきつさがあるから
- 疲れても介護職を続ける理由は、景気に左右されないなどの魅力があるから
- 疲労解消には、リラックス法を見つけることや体調管理に気を配ることが大切
「介護職の疲れが取れない理由は?」と気になる方もいるかもしれません。介護職は、人間関係が悪いことや事業所の運営方針に合わないこと、身体介護や夜勤に体力を使うことなどから、精神的・身体的な負担を感じる場合があります。この記事では、介護職の疲労を解消するヒントや、仕事を続けるメリットをご紹介します。疲れが取れないとお悩みの方は、ぜひご一読いただき、疲労回復の参考にしてください。
介護職の疲れの原因
介護職として働いていると、精神的・身体的な疲れが溜まる場合があります。なぜ疲れてしまうのか、主な原因をまとめました。
職場の人間関係が悪い
介護職は基本的に特別な資格や経験が求められないため、未経験歓迎であることが多く、さまざまな経歴・価値観を持った人が集まります。元々介護について学んできた人もいれば、全く知識がない状態で入職する人もいて、ケアのやり方1つを取っても意見が相容れないことがあるようです。
お互いを認め合い、その都度最良の選択ができれば良いですが、実際にはなかなか難しいことも。介護職同士の仲が良くても、看護師や理学療法士などの他職種と上手に連携を図れないケースもあります。人間関係に気を遣い、疲弊してしまう人は少なくないようです。
事業所の運営方針が合わない
就職先を選ぶ際、企業の理念や行動指針を参考にするのは基本です。介護施設でもその基本は変わらず、求人に応募する前には事業所のWebサイトの採用ページで理念を見たり、職場環境を確認したりするでしょう。しかし、事業所の方針に共感して就職しても、いざ入職してみるとその方針と違ったやり方での業務を求められるケースがあるようです。
「個々の要望を汲み取り寄り添ってケアを行う」という方針を打ち出しているのに、実際は要望があっても事務的に対応しているなど、理想とのギャップがあることで、精神的に疲れてしまう場合もあるのかもしれません。
身体的にきつい
着替えや清拭の介助、入浴介助、排泄介助、車椅子への移乗の介助など、利用者さんの身体を支えて行う業務が多いのが、介護職の特徴。特に入浴介助は、体力を使う業務で、「入浴介助の日は疲れ切ってしまう」という人もいるようです。ほかの業務でも比較的動き回る傾向にあり、介護職には一定の体力が求められます。
身体的な疲労から限界を感じたり、長くは勤められそうにないと感じたりして、他職種への転職を検討する介護職もいるようです。
育児との両立が難しい
身体的な疲れが取れないと、家庭と仕事を両立させることが難しくなるでしょう。身体的な疲労感があっても、自分だけ、またはパートナーとの生活を維持するのにはそれほどの支障を感じない人もいます。しかし、仕事で疲労が蓄積されている状態で、家に帰って小さな子どものお世話をする場合、体力的な限界を感じる場合があるようです。
子どもの体調によっては急な欠勤を余儀なくされる場合もありますが、事業所の雰囲気次第では休みづらいこともあるかもしれません。また、正職員の介護職は夜勤を求められる場合もあり、スケジュール調整が大変になることも。子育てを行う介護職の方にとって、職場環境は疲労度に大きく影響するといえます。
▼関連記事
介護の仕事に疲れてもう辞めたい…疲れたときの対処方法
その悩み、解決できるかも
疲れても介護職を続ける理由
介護職を続けている人の多くは、人間関係の問題や業務に多少の大変さがあっても、仕事を続けるだけのメリットがあると感じているようです。今、転職しようか迷っている方もそうなのではないでしょうか?介護の仕事の魅力を、以下で再確認してみましょう。
キャリアアップに学歴が関係ない
近年では多様性が重視されるようになってきたものの、学歴によって、採用や給与、キャリアに影響がある企業もあるようです。介護職は、学歴よりも、スキルや人柄、意欲が重視される傾向があります。学歴に関係なく採用が行われることも多く、スキルを身につけたり経験を積んだりすれば、キャリアアップしていくことが可能です。
現在では、国を挙げて介護業界におけるキャリア制度の見直しが行われており、正しい評価が期待できるようになってきています。無資格・未経験で働き始めた場合も、資格を取得したり勤続年数を重ねたりすれば、昇進や昇給を目指せるでしょう。
景気に左右されない
介護職は、ほかの業界の仕事に比べて景気に左右されにくい傾向があります。高齢化が進む現在の日本では、将来的にも継続して介護職の需要は高い見込みです。今後、業務のやり方の見直しなどがあったとしても、ニーズがなくなって職を失う可能性は低いでしょう。
やりがいを感じられる
介護職は、利用者さんの生活に密接に関わる仕事のため、感謝の言葉を直接かけられる機会が多く、人の役に立っている実感を得られるようです。また、利用者さんの身体機能の回復を一緒に喜べたり、最期のひとときを見守れたりと、人生のターニングポイントに立ち会える貴重な経験ができることを魅力に感じる人もいます。
自分の頑張りによって利用者さんやご家族に貢献できるので、日々やりがいを感じられる職業といえるでしょう。
▼関連記事
介護士のやりがい・魅力13選!介護の仕事を選ぶ理由や価値観も解説します
疲れが取れない介護職が疲労を解消するヒント
「身体的な疲れが取れない」「精神的なストレスが溜まっていてつらい」という介護職の方に向けて、身体的・精神的な疲労を解消するための方法を解説します。
さまざまな価値観を認めて自分の糧にする
人間関係のトラブルに有効なのは、相手の価値観を認めてみることです。なかなか難しいことではありますが、それ以上に他人を変えるのは困難です。すべての意見を受け入れて我慢する必要はありませんが、「そういう意見や考え方もあるのか」と捉えると気持ちが楽になることがあるでしょう。
人の価値観を認めると視野が広がるため、自分を高めていくこともできるかもしれません。大変なことがあっても、介護職としてのスキルアップのチャンスと前向きに受け止めると、ストレスが溜まることを防げます。
自分なりのリラックス法を見つける
日ごろの疲れが取れないため、オフの時間はずっと寝ているという人もいるのではないでしょうか?自宅でしっかり休養を取るのは大切ですが、オフの時間すべてを寝食だけに費やしてしまうと、「なぜ介護職を続けているのだろう…」と感じてしまうかもしれません。
趣味に打ち込んだり、旅行に行ったり、スポーツで身体を動かしたりして気分転換すると、充実感が得られて疲れを溜め込まずに済むでしょう。オフの時間に身体を動かすと余計に疲れてしまう人は、読書をする、ゆっくり入浴する、お茶を飲んでホッとできる時間を作るなど、あくまで無理をしない範囲でのリラックス方法を見つけてみてください。
夜勤前後の体調管理に気を配る
夜勤によって生活リズムが乱れることも、疲れが溜まる要因になります。生活習慣が乱れると、疲れやすくなるだけでなく、健康に悪影響を与えてしまうことも。夜勤をする際は2日ほど前から就寝時間を遅くしてバランスを取る、夜勤明けはしっかり休養するなど、夜勤前後の過ごし方を工夫することで、身体的な負担を軽減できる可能性があります。
また、食事を3食きちんと摂るなど、普段から健康的な生活習慣を心がけることも大切です。
▼関連記事
介護職を長く続けるコツはある?仕事や職場に疲れたときの対処法
職場によっては転職を考えよう
どれだけ改善を図っても、職場によってはそれほど効果が期待できないこともあります。そのような環境で頑張っても、心や身体を壊してしまうことになりかねません。改善の努力をしても、以下のような状態が続いている場合は、辞めたほうが良い可能性があります。
- 違法な医療行為を強要する
- 月に10日以上夜勤がある
- 労働基準法に違反したシフトを組む
- パワハラやいじめがある
- 慢性的な残業や休日出勤がある
- 利用者さんに横暴な態度で接する職員がいる
ご紹介した例に当てはまらなくても、心身の限界を感じたら、早めに休養したほうが良いかもしれません。介護の仕事自体が嫌でなければ、同じ介護業界で転職する選択肢もあります。
レバウェル介護(旧 きらケア)は介護業界での就職を支援するサービスを実施しています。雇用形態、施設形態、職種、お持ちの資格やこだわりの条件から、ぴったりの求人をご紹介することが可能です。登録から入職後のフォローまですべて無料なので、お気軽にご利用ください。
介護職の疲れが取れないことに関する質問
ここでは、介護職の疲れが取れないことに関する質問に回答します。
介護職の疲れが取れない原因は?
介護職の疲れが取れない原因は、入浴介助や排泄介助などの力仕事による、身体的な負担が蓄積されることです。また、人手不足によってほかの業務でも動き回るなどの理由で、体力的なつらさを感じることもあります。就業先の方針と合わなかったり、スタッフの人間関係が良くなかったりする場合は、精神的負担が重くなって疲労が溜まる原因になるでしょう。
介護職で体がきついときの対策とは?
介護職で体がきついときの対策としては、自分に合ったリラックス法を見つけて実行することが有効です。休日にはしっかり睡眠を取るだけではなく、趣味に没頭したり、スポーツで体を動かしたりして気分転換することも効果的でしょう。生活リズムが乱れやすい夜勤前後の体調管理に気を配ることも大切です。詳しくは、「疲れが取れない介護職が疲労を解消するヒント」で解説しているので、ぜひご覧ください。
まとめ
介護職は精神的・身体的に疲れが溜まる場合があります。疲れの原因としては、職場の人間関係が悪いことや、事務所の運営方針が合わないことなどが挙げられるでしょう。また、夜勤や身体介護などに身体的なきつさがあることや、育児と仕事を両立させることに負担を感じる方もいるようです。
介護職の仕事には大変さがある一方で、学歴に関係なくキャリアアップできたり、景気に左右されずに働けたりする魅力があります。疲れが取れない場合は、相手の価値観を認めて自分の糧にしたり、リラックス方法を見つけたりすることで、解消していきましょう。夜勤の負担がある場合は、健康的な生活を心掛ければ負担を軽減できるかもしれません。
もしも、疲労回復に努めてもどうしても職場環境が合わないというときは、転職するという選択肢もあります。お悩みのある介護職の方は、ぜひレバウェル介護(旧 きらケア)をご利用ください。「夜勤のない施設で働きたい」「土日祝日が休みの施設で働きたい」など、ご希望に合わせた求人をご紹介し、転職をサポートいたします。ぜひ気軽にご相談ください。
その悩み、解決できるかも
 ヘルパー・介護職の求人はこちら
ヘルパー・介護職の求人はこちら