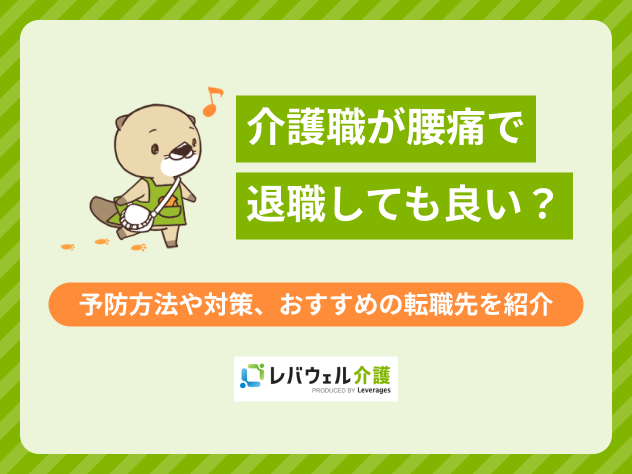
この記事のまとめ
- 介護業務によって腰痛が悪化する場合は、退職をするのも選択肢の一つ
- 介護職員が腰痛で退職する際は、病院を受診して治療に専念したい旨を伝える
- 腰痛に悩む介護職員が転職する際は、腰への負担が少ない職場を選ぼう
腰痛に悩む介護職の方のなかには、退職を迷っている方もいるかもしれません。介護職が担当する業務は腰へ負担がかかるため、腰痛が原因で退職する方は少なくないようです。この記事では、腰痛で退職する基準や退職の流れを紹介。転職先として、腰への負担が小さい職場や職種も解説しています。「腰痛で仕事がつらい」「働き方を見直したい」という方は、参考にしてみてください。
介護職員は腰痛で退職しても良い?
腰痛がつらく仕事に支障をきたしている_場合は、無理をすることでさらに悪化をしてしまうおそれがあるので退職を検討しても良いでしょう。退職のほかに、休職するのも選択肢の一つです。休職して身体介護業務から離れることで、症状の緩和が期待できます。腰への負担が少ない業務への異動を上司に相談してみても良いでしょう。
腰痛に関する通院や休職をする場合は、労災給付を受けられる可能性があります。腰痛の症状が出ている方は、確認しておくと安心です。
業務が原因の腰痛だと思ったら、実は別の病気だったというケースもあります。腰痛が続く場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。
その悩み、解決できるかも
腰痛で退職を悩む介護職員は少なくない
公益財団法人 介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書(資料編p86・p.87)」よると、「労働条件等の悩み、不安、不満等(複数回答)」として介護職員の回答が最も多かったのは「人手が足りない」の58.9%でした。次いで、「仕事内容のわりに賃金が低い」が44.4%、「身体的負担が大きい(腰痛や体力に不安がある)」が39.1%となっています。身体的負担に悩んでいる介護職員は、一定数いるようです。
職種別にみると、「身体的負担が大きい」と感じている介護職員は前述のとおり39.1%で最も多く、続いて訪問介護員が29.4%、ケアマネジャーが28.8%でした。介護従事者のなかでも、介護職員は特に身体的負担が大きいと感じているようです。介護現場では身体的負担や腰痛に悩んで、退職を検討する介護職員は一定数いると考えられます。
出典
公益財団法人 介護労働安定センター「介護労働実態調査」(2025年6月11日)
介護職員が退職を検討する基準とは
腰痛で悩む介護職員のなかには、「腰痛で退職しても良いか分からない」という方もいるかもしれません。退職する基準は人によってさまざまですが、「腰痛が悪化している」「私生活や健康状態に悪影響が出ている」などの場合は転職を検討しても良いでしょう。
ここでは、介護職員が退職を検討する基準を紹介します。退職を迷っている方は、参考にしてみてください。
腰痛が悪化している
通院したり腰痛対策をしたりしても症状が悪化する場合は、退職をして働き方を変えたほうが良いかもしれません。無理して働き続けると、長期間働けなくなるおそれもあります。転職する場合には、転職先で同じような負担が掛からないかを慎重に判断することが大切です。
私生活や健康状態に悪影響が出ている
腰痛によって、日常生活の動作が困難になったり睡眠不足になったりするなどの影響が出ている場合は、退職を含めて働き方を見直したほうが良いでしょう。無理を重ねると、身体的な不調だけでなく、精神的なストレスも蓄積してしまいます。将来的な健康と生活を考えて、自分にあった働き方を検討してみましょう。
職場での理解が得られない
「介護職員は腰痛が当たり前」などと、周囲から理解を得にくい場合は、退職を視野に入れても良いでしょう。腰痛を相談しても身体的負担が大きい仕事を任されるなどと、職場で理解が得られない状況が続くと、症状の悪化や精神的なストレスにつながることがあります。
もし、退職を引き止められるなど、腰痛による退職が理解されない場合は、医師の診断書があると状況の説明がしやすくなるでしょう。
介護職員が腰痛で退職するときの流れ
介護職員が腰痛で退職する場合は、医師の診断を受けたうえで、治療に専念したい旨を伝えます。基本的な退職の流れは、以下のとおりです。
- 1.医師の診断を受け、診断書を発行してもらう
- 2.上司に退職の意思を伝える
- 3.退職日を相談し、決定する
- 4.労災申請をする
- 5.業務の引き継ぎを行う
- 6.職場から借りていたユニフォームや備品を返却する
介護職員が円満退職するには、余裕を持って退職の意思を伝え、計画的に引き継ぎを行うことが大切です。退職を伝える際は、「腰痛が悪化し、業務に支障が出るようになった」「医師の診察を受け、療養が必要と診断された」などと説明すると良いでしょう。
労災申請は退職後でもできますが、事業主が用意する書類などが必要になるため在職中に行ったほうがスムーズです。また、労災申請には、医師の診断書の提出が求められる場合があります。できるだけ早い段階で、診断書の発行を依頼しておくと安心です。
診断書は労災申請だけでなく、職場に事情を説明する際にも役立ちます。
▼関連記事
【介護の転職】円満退職の方法や退職意思の伝え方のポイント
人手不足の職場で仕事を辞めたいと言えない…対処法や転職すべき職場を解説
腰痛に悩む介護職員におすすめの職場と職種
腰痛が理由で転職する場合は、働き方を見直さないと症状が長引いたり悪化したりしてしまうかもしれません。ここでは、身体的な負担が少ない傾向のある職場や職種を紹介します。
腰への負担が少ない職場
「利用者さんの要介護度が比較的低い職場」や「職員1人当たりの負担が少ない職場」「福祉用具や福祉機器を積極的に取り入れている職場」は、身体的な負担が少なめといえるでしょう。以下で、一つずつ解説します。
要介護度が比較的低い職場
自分自身で動ける方が多い職場は、高齢者を抱きかかえたり支えたりする機会が少ないため、腰への負担になる業務も少ないでしょう。「デイサービス」や「デイケア」「一般型のサービス付き高齢者向け住宅」は、要介護度の低い方や自立した高齢者が対象の介護サービスです。そのため、身体的な負担を減らしたい方に向いているでしょう。
職員1人当たりの負担が少ない職場
利用者さんの人数が少なく介護職員が多い職場は、職員1人あたりの負担は少なめです。施設の種類によって異なりますが、多くの介護施設では、利用者さん3人に対して介護職員を1人以上配置することが求められます。利用者さん1人に対して介護職員を4人配置しているなど、基準よりも介護職員を多く配置している職場なら、介護職員1人当たりの負担は比較的少ないでしょう。
なお、介護施設における人員配置基準は、利用者さんの人数に対して必要な職員の人数を定めたもので、時間帯によっては職員数が少ないことがあります。転職の際は、時間帯ごとの介護職員の人数を確認しておくと良いでしょう。職員配置は施設のWebサイトから調べられますが、詳しく知りたい方は、「レバウェル介護(旧 きらケア)」へお問い合わせください。
福祉用具や福祉機器を積極的に取り入れている職場
福祉用具や福祉機器を積極的に取り入れている職場を選べば、身体的な負担を軽減して働くことが可能です。特に、不自然な姿勢になりやすい移乗介助や排泄介助、入浴介助でこれらを利用することで、腰痛の予防につながります。
転職活動の際は、求人先を訪問して現場の様子を見学し、どのような福祉用具や福祉機器が使われているのか確認すると安心です。
腰への負担が少ない職種
ここでは、腰への負担が少ない介護に関わる職種を紹介します。介護職員以外の働き方に興味のある方は、参考にしてみてください。
ケアマネジャー
ケアマネジャーとは、介護を必要とする方が適切なサービスを受けられるように、ケアプランの作成や関係機関との連絡などを行う職種です。介護業務に携わる機会が少ないため、介護業務中心の仕事に比べて腰への負担を減らせるでしょう。
ただし、職場によっては相談対応のために利用者さんの自宅を訪問することがあり、移動による負担はあるかもしれません。
ケアマネジャーとして働くには、介護支援専門員実務研修受講試験の合格と、介護支援専門員実務研修の修了が必要です。詳しくは、「ケアマネジャーになるには最短で何年?介護支援専門員の受験資格を解説」をご覧ください。
介護事務員
介護事務員とは、介護施設や事業所で事務業務を担当する職種をいいます。デスクワークが主なので、身体的負担は少なめです。また、基本的に日勤のみで働けるため、夜勤による身体的負担を減らせるでしょう。
介護事務の仕事に興味のある方は、「介護事務の仕事内容は?未経験からできる?活かせる資格やスキルをご紹介」を参考にしてみてください。
支援相談員・生活相談員
支援相談員・生活相談員とは、介護施設において利用者さんやご家族の相談対応や入退所の手続きなどを行う職種です。どちらも介助業務に関わる機会は少なく、デスクワークが主なので、身体的負担は少ない傾向にあります。
支援相談員・生活相談員の大きな違いは勤務先です。介護老人保健施設で働いているのは支援相談員で、そのほかの介護施設で働いているのは生活相談員と呼ばれています。
▼関連記事
支援相談員とはどんな職種?仕事内容や必要な資格、やりがい、給与を解説!
生活相談員の資格要件は?未経験から目指せる?仕事内容や職場もご紹介
介護職員が腰痛に悩みやすい原因
腰痛が発生する原因は、「動作要因」「環境要因」「個人的要因」「心理的・社会的要因」があり、介護職員の腰痛は、これらが複数絡んでいることがあります。
以下では、介護職員の腰痛の原因を解説。腰痛に悩んでいる方はチェックしてみてください。
動作要因
動作要因とは、腰に加わる過度な負荷によって起こる腰痛のことです。たとえば、「重いものを頻繁に持ち上げる」「腰を深く曲げる」「不自然な作業姿勢が続く」などが挙げられます。移乗介助や入浴介助、排泄介助では、自分よりも重い利用者さんを抱きかかえたり、中腰のまま作業を行うこともあるでしょう。介助業務は、腰への負担が大きくかかります。
環境要因
環境要因とは、身体に負担がかかる環境により起こる腰痛のことをいいます。具体的には、「作業する足場が滑りやすい」「介助を行う場所が狭く動きにくい」などです。入浴介助を行う際に浴室が滑りやすかったり、利用者さんの部屋が狭く動きにくかったりすると、腰痛を引き起こす原因になることがあります。
個人的要因
個人的要因とは、年齢や体質、筋力など個人が持つ特性に起因して起こる腰痛のことです。腰椎椎間板ヘルニアなどの既往歴なども個人的要因に分類されます。また、筋力の低下や十分な休息がとれない場合も、腰痛の原因になるようです。
心理的・社会的要因
職場でのストレスも、腰痛の発生と関連しているようです。たとえば、「職場の人間関係が悪い」「やりがいを感じられない」「忙しくてイライラする」などが挙げられます。精神的ストレスが続くと、腰痛が長引く場合があるようです。
出典
厚生労働省「介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ」(2025年6月11日)
介護職員の腰痛対策
腰痛対策をすることで、腰痛の緩和・予防ができます。ここでは、介護職員向けの腰痛対策を紹介。腰痛に悩んでいる介護職員は、参考にしてみてください。
身体への負担が少ない姿勢と動作を意識する
介助業務を行う際は、中腰や身体をひねった姿勢など、不自然な姿勢を長時間とらないように気をつけることが大切です。たとえば、「屈むときは腰ではなく、ひざを曲げる」「ベッドの高さを上げて作業しやすい環境を整える」などを意識すると良いでしょう。作業時の姿勢に気をつけることで、腰への負担を軽減できます。
身体への負担が少ない動作を理解するには、ボディメカニクスが役立つでしょう。ボディメカニクスとは、身体の構造と力学の原理を応用して、身体への負担を減らす技術や考え方のこと。ボディメカニクスを学ぶことで、腰への負担が少ない動きを身につけられます。
ボディメカニクスについては、「ボディメカニクスの8原則を解説!介護現場で活用して腰痛を予防しよう」もご覧ください。
福祉用具や福祉機器を活用する
福祉用具や福祉機器を使うことで、身体への負担を軽減でき腰痛予防につながるでしょう。腰痛予防に有効な福祉用具・福祉機器には、リフトやスライディングボード、スタンディングマシーンなどがあります。利用者さんを抱きかかえるという動作を減らせるので、腰痛に悩んでいる方も働きやすくなるでしょう。
もし、勤務先で福祉用具・福祉機器を導入していない場合には、上司や管理者に相談してみても良いかもしれません。自治体によっては、介護機器の導入に必要な経費の一部を補助する制度があります。
腰痛ベルトやコルセットを使う
腰痛の対策には、腰痛ベルトやコルセットの使用も有効です。これらを使用することで、腰にかかる負担を軽減したり、腰の動きをサポートしたりしてくれます。腰痛ベルトやコルセットには、さまざまな種類があるため、使用用途や腰痛の症状、身体のサイズに合ったものを選ぶようにしましょう。
腰痛に効果的なストレッチをする
腰痛が悪化する前に、日々のストレッチを行うことも大切です。介護業務に取り組む前には準備体操をし、腰痛になるリスクを抑えましょう。仕事の合間にも、椅子に座りながら・手すりに掴まりながら手軽なストレッチを行えば、業務中に蓄積した疲れをリフレッシュできます。
また、入浴中や入浴後など、筋肉がほぐれているときにストレッチをするのも有効です。疲れを翌日に持ち越さないよう積極的な体操を心がけ、日々の腰痛対策に取り組みましょう。
しっかり休息をとる
腰痛を緩和・予防するには、作業による身体への負担を減らすことだけでなく、蓄積した疲労を回復させることも大切です。日常的に睡眠や休養が不足すると、身体への負担が増してしまいます。慢性的な疲れは、腰痛につながることもあるようです。適切な環境で休憩をとったり、十分な睡眠時間を確保したりするようにしましょう。
▼関連記事
【介護職員の腰痛対策】痛みの原因と予防法、正しい介助方法について解説!
介護職員の腰痛は労災認定される?
「労災保険制度」とは、業務や通勤が原因で怪我や病気、障害、死亡事故などが生じた場合に、労働者本人や遺族に対して、必要な保険給付を行う制度です。
介護職員の腰痛は、労災として給付が受けられることがあります。ここでは、介護職の腰痛について「労災認定されるポイント」と「労災が認められにくいケース」を解説。腰痛に悩んでいる方は、チェックしてみてください。
労災認定されるポイント
介護職員の腰痛は、仕事が原因で発症したことが認定されれば、労災が適用される可能性があります。たとえば、「移乗介助で利用者さんを抱きかかえているときに、腰痛が発症した」や「日常的に腰に負担がかかる仕事をしており、負担が蓄積され腰痛を発症した」などの場合は、労災認定されることがあるようです。
腰痛が発症したら、医師の診断を受けて診断書を書いてもらいます。その後、診断結果を職場へ伝えて、労働基準監督署に申請しましょう。
介護職員の腰痛の場合は、治療費や薬代、通院時の交通費などの給付を受けられる「療養補償給付」や、療養で仕事ができないときに給付を受けられる「休業補償給付」が受けられる可能性があります。
▼関連記事
介護職の腰痛は労災認定される?欠勤や退職する場合についても解説!
労災が認められにくいケース
業務との因果関係が不明瞭な場合や、プライベートでの日常生活が原因だと疑われる場合は労災は受けられません。プライベートで発生した腰痛は、労災保険の対象外となります。
また、ぎっくり腰は日常的な動作で発生するものとして、業務中に発生しても労災が認められにくい傾向にあるようです。ただし、状況によって認定の結果は異なるため、まずは医師や勤務先に相談してみると良いでしょう。
介護職で腰痛に悩む方によくある質問
ここでは、介護職における腰痛の悩みに関する質問を紹介します。腰痛に悩む介護職員はチェックしてみてください。
介護職員が腰痛で退職するのは甘えですか?
介護職員が腰痛で退職することは、甘えとはいえません。腰痛を我慢して仕事を続けると、腰痛が悪化し、長期間働けなくなるおそれもあります。介護職員が腰痛で退職することは、身体を守るための適切な判断といえるでしょう。
腰痛が原因で転職する場合は、腰への負担を軽減できる職場や仕事を選ぶことが大切です。転職を検討している方は、「腰痛に悩む介護職員におすすめの職場と職種」も参考にしてみてください。
腰痛で仕事を辞めるときは診断書は必要ですか?
腰痛で仕事を辞める際に、診断書の提出は必須ではありません。ただし、労災申請をする場合は診断書が必要です。また、勤務先によっては提出を求められたり、状況説明に役立ったりすることがあります。受診時に診断書を依頼しておくと、そのあとの手続きをスムーズに行えるでしょう。
診断書は診察の際に、医師へ「診断書を発行してほしい」と伝えると作成してもらえます。
まとめ
介護職員で腰痛が続く場合は、退職を視野に入れて働き方を見直すことが大切です。無理をして働き続けると、腰痛が慢性化し長期間働けなくなるリスクが高くなるおそれがあります。「腰痛対策をしているが腰痛が悪化している」「腰痛によって日常生活に影響が出ている」「勤務先での理解が得られず働くのがつらい」という場合は、自分の健康を守るために働き方を見直したほうが良いでしょう。
転職する場合は、腰への負担が少ない職場や職種を選ぶことで、腰痛の悪化を予防できます。「腰への負担が軽い職場に転職したい」「今後、身体介護を続けられるか不安」という方は、「レバウェル介護(旧 きらケア)」へご相談ください。
レバウェル介護(旧 きらケア)のキャリアアドバイザーは、求人先へのヒアリングをこまめに行っているため、業務内容や職場の雰囲気を把握しています。利用者さんの要介護度や導入している福祉用具や福祉機器など、求人票からは分からない情報を含めて、あなたに合った職場をご提案することが可能です。また、これまでの経験を活かしたキャリアチェンジのアドバイスもできます。サービスはすべて無料なので、お気軽にお問い合わせください。
その悩み、解決できるかも
 デイサービスの求人一覧ページはこちら
デイサービスの求人一覧ページはこちら