Clik here to view.
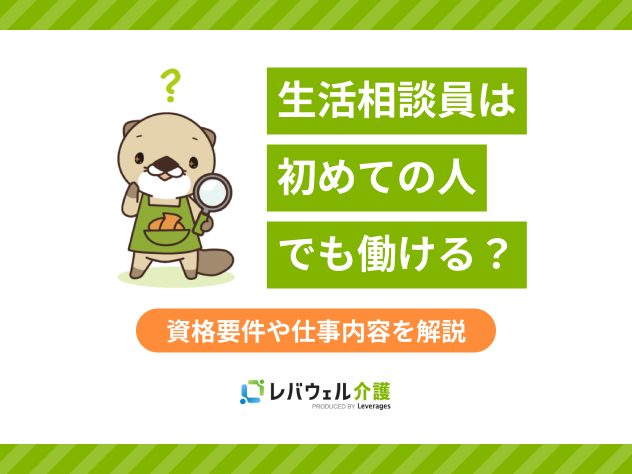
この記事のまとめ
- 社会福祉士などの資格があれば、初めてでも生活相談員として活躍できる
- 生活相談員の仕事に必要なスキルは、理解力や説明力など
- 生活相談員への転職を成功させるには、応募要件や配置人数を確認しよう
「生活相談員は初めてでも働けるの?」と気になる方もいるでしょう。社会福祉士などの資格があれば、介護業界が初めてでも生活相談員として活躍できます。この記事では、生活相談員になるための資格要件を解説。生活相談員の仕事内容や必要なスキル、仕事に慣れるコツなども紹介します。生活相談員への転職を成功させる方法にも触れているので、参考にしてみてください。
生活相談員は初めてでも目指せる?
生活相談員は、初めてでも資格があれば十分に目指せます。無資格から生活相談員になる場合は、介護業界における実務経験や資格取得が求められるのが一般的です。下記で、生活相談員として働くための要件を確認していきましょう。
生活相談員になるには資格が必要
生活相談員の資格要件は、自治体によって異なります。基本的に、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格が必要なことが多いようです。なかには、無資格でも一定の実務経験があれば、生活相談員として働ける自治体もあります。
生活相談員の資格要件と取得方法
生活相談員として働くには、下記のいずれかの資格が必要です。
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉主事任用資格
- 自治体が定める資格
ここでは、それぞれの取得方法などを説明していきます。
社会福祉士
社会福祉士は、相談援助のスキルを証明する国家資格です。社会福祉士になるには、社会福祉士国家試験に合格して資格登録をしなければなりません。
公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの「[社会福祉士国家試験]受験資格」によると、社会福祉士国家試験の受験要件として、大学での指定科目の履修や相談援助の実務経験、養成施設への通学などが定められています。たとえば、大学に通わずに受験要件を満たすには、「4年以上の相談援助の実務経験」と「1年以上の一般養成施設への通学」が必要です。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[社会福祉士国家試験]受験資格」(2024年9月20日)
精神保健福祉士
精神保健福祉士も相談援助のスキルを証明する国家資格で、精神障がいのある方の支援に特に活かせるのが特徴です。取得するには、精神保健福祉士国家試験への合格が求められます。
公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの「[精神保健福祉士国家試験]受験資格」によると、精神保健福祉士国家試験の受験要件は、大学での指定科目の履修や相談援助の実務経験、養成施設への通学などを満たすことです。
たとえば、一般大学を卒業している場合、一般養成施設に1年以上通うことで、精神保健福祉士国家試験を受験できます。大学に通わない場合の受験要件は、「4年以上の相談援助の実務経験」と「1年以上の一般養成施設への通学」です。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[精神保健福祉士国家試験]受験資格」(2024年9月20日)
社会福祉主事任用資格
社会福祉主事任用資格は、「社会福祉主事の仕事に就くための資格」のこと。社会福祉主事とは、都道府県や市区町村の福祉事務所で、社会福祉のサポートを行う職員です。
基本的に、社会福祉主事任用資格は、公務員が社会福祉の業務を行うための資格ですが、介護施設で働く職種の要件として準用されることもあります。
社会福祉任用資格を取得する方法は、下記の5つです。
- 大学や短期大学において指定科目を修めて卒業する
- 特定の通信教育課程(1年)を修了する
- 指定養成機関を修了する
- 都道府県が実施する講習会を修了する
- 社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を取得する
通信教育や講習会などを受けて社会福祉の知識を身につけることで、社会福祉主事任用資格を取得できます。
出典
厚生労働省「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」(2024年9月20日)
Image may be NSFW.
Clik here to view. 社会福祉主事任用の求人一覧ページはこちら
社会福祉主事任用の求人一覧ページはこちら
自治体が定める資格
上記に挙げた3つの資格に加え、ケアマネジャーや介護職員としての一定の実務経験を、生活相談員になる要件としている自治体もあります。
たとえば、仙台市の「生活相談員の資格要件について」によると、仙台市の生活相談員の要件は下記のとおりです。
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉主事任用資格
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 特別養護老人ホームやデイサービスなどの施設において、相談援助や介護・看護業務に3年以上従事した経験のある者
仙台市のように、相談援助や介護業務などの実務経験を積むことで、生活相談員として働ける自治体もあります。実務経験を積んで生活相談員になりたい方は、自身が働く地域の資格要件を確認してみましょう。
生活相談員の資格要件について詳しく知りたい方は、「生活相談員の資格要件は?未経験から目指せる?仕事内容や職場もご紹介」「ソーシャルワーカーに必要な資格の取り方や難易度は?職種別の要件も解説!」も参考にしてみてください。
出典
仙台市「生活相談員の資格要件について」(2024年9月20日)
生活相談員とはどんな仕事?
生活相談員には、施設の利用者さんが、安心して可能な限り自立した生活を送れるよう、相談援助や連絡・調整などを行う役割があります。施設を利用する際の説明や契約手続きも、仕事の一つです。
ここでは、生活相談員の職場や仕事内容を紹介します。
生活相談員の職場
生活相談員の主な職場は、下記のとおりです。
- 特別養護老人ホーム
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- デイサービス
- 障害者施設
施設形態や事業所の規模によって、生活相談員の配置人数は異なります。生活相談員の配置義務がある介護施設では、利用者さん100人に対して生活相談員1人が基準なので、1~2人程度を配置する施設が多いようです。
なお、老健(介護老人保健施設)で相談援助を行う職種は、「支援相談員」と呼ばれます。
生活相談員の仕事内容
生活相談員の仕事内容は、利用者さんやご家族の相談対応や契約手続きなどです。生活相談員の主な業務を、以下にまとめました。
- 施設の入所や退所に関わる説明や契約手続き
- 利用者さんやそのご家族の相談対応
- 利用者さんに合ったサービスを提供するための連絡・調整
- 介護報酬請求などの事務作業
介護報酬請求は、生活相談員が行う施設もあれば、管理者や事務職員が行う施設もあります。また、職場によっては、生活相談員が介護業務を兼務することもあるようです。
生活相談員の仕事内容については、「生活相談員とはどんな仕事?必要資格や給料、やりがいをご紹介!」の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
生活相談員の1日のスケジュール
ここでは、特別養護老人ホームで働く生活相談員のスケジュール例を紹介します。生活相談員の仕事内容は職場によって異なるため、参考程度にご覧ください。
| 時間 | 仕事内容 |
| 午前8時30分 | 出勤し、1日の予定やメールの確認。朝礼に参加する |
| 午前9時 | 入居者さんの相談対応 |
| 午前10時 | サービス担当者会議に参加する |
| 正午 | 入居者さんの食事の準備を行う |
| 午後1時 | 休憩 |
| 午後2時 | 入居希望者さんの対応。施設の案内や説明をする |
| 午後3時 | メールの確認と返信。問い合わせの対応をする |
| 午後4時 | 報告書の作成など、事務作業を行う |
| 午後5時30分 | 明日の予定を確認し、退勤する |
生活相談員の勤務時間は基本的に日勤のみで、介護職と兼任する場合以外は夜勤がありません。また、生活相談員の仕事はルーティンではなく、毎日優先順位を決めて臨機応変に対応します。
▼関連記事
生活相談員は未経験・無資格でもなれる?資格要件や求人の有無を解説!
Image may be NSFW.
Clik here to view. 生活相談員の求人一覧ページはこちら
生活相談員の求人一覧ページはこちら
生活相談員の仕事に必要なスキル
生活相談員の仕事には、「相手のニーズを把握する理解力」「分かりやすく伝える説明力」「円滑に業務を進めるタスク管理能力」が求められます。下記で解説するので、初めて生活相談員になる方は、参考にしてみてください。
相手のニーズを把握する理解力
生活相談員には、相談者の話を聞き、ニーズを正しく把握する理解力が必要です。施設の利用者さんや利用希望者の方のなかには、何に困っているのかをうまく伝えられなかったり、潜在的なニーズに気づいていなかったりする方もいます。
相手が悩みを話しやすい状況を整えるコミュニケーション能力や、相談者の生活課題を発見する観察力があれば、利用者さんのニーズを理解できるでしょう。生活相談員の仕事が初めてでも、福祉に関する資格や経験があれば、相談援助に活かせます。
分かりやすく伝える説明力
契約内容や介護保険制度などの説明を行う生活相談員の仕事では、分かりやすく伝える説明力も大切です。生活相談員が分かりやすい説明を行えば、利用者さんは安心してサービスを利用でき、契約後に「聞いていない」と言われるなどのトラブルも避けられるでしょう。ほかの職種と連携を取る際も、説明が分かりやすければ短時間で相手に理解してもらえるので、業務効率が上がります。
説明力を上げるには、「話の要点をまとめてから伝える」「主語を省略しない」「聞きとりやすい速さで話す」ことがポイントです。また、専門用語ではなく、相手に意味が伝わる言葉を使うことも意識しましょう。
円滑に業務を進めるタスク管理能力
生活相談員は、利用者さんやご家族のニーズをヒアリングしたうえで、施設の職員、外部の機関などと連携し、さまざまな介護方針やサービスの提案をします。多方面とのやり取りが多いので、1つの業務が滞ってしまうと、ほかの仕事が止まってしまうこともあるでしょう。そのため、自分が抱えている業務の進捗や期限を確認し、適切な優先順位で計画的に仕事を進めるスキルが必要です。
初めて生活相談員として働く場合は、業務の優先順位を把握するのに難しさを感じることがあるかもしれません。タスク管理に慣れるためには、先輩に聞いて業務の優先順位を把握したり、ToDoリストやスケジュール帳を活用したりすると良いでしょう。
生活相談員に初めてなった人が仕事を進めるコツ
生活相談員には専門的な知識が求められるため、経験が浅いと仕事に悩むこともあるでしょう。ここでは、初めて生活相談員になった人に向けて、仕事をスムーズに進めるためのコツを紹介します。
利用者さんの話を丁寧に聞く
生活相談員の仕事で大切なのは、利用者さんやご家族など、相談者の話を丁寧に聞くことです。生活相談員の仕事に慣れていなくても、丁寧に話を聞くことで相談者との信頼関係を構築できます。
利用者さんの話を聞くときのポイントは、「相手を否定しない」「話をさえぎらずに最後まで聴く」などです。介護現場で活かせる傾聴スキルについては、「介護で役立つ傾聴スキルとは。共感を示すコミュニケーションの方法」の記事を参考にしてみてください。
書類作成を効率化する
初めて生活介護員の仕事をする方は、介護計画書やモニタリング報告書などの作成に時間がかかってしまうことがあるようです。書類の作成が苦手な場合は、文書作成の効率化を図ってみましょう。
たとえば、「利用者さんの日常の出来事をこまめにメモしておく」「よくある場面は文章のテンプレートを作っておく」「記録に使える表現や言葉をまとめておく」などが有効です。書類作成を効率化できれば、仕事の負担を軽くできます。
▼関連記事
介護記録の上手な書き方のコツとは。基本や例文を解説!
他職種への理解を深め多職種連携を円滑にする
生活相談員が仕事をスムーズに進めるには、多職種への理解を深めることが大切です。生活相談員の仕事は、管理者やケアマネジャー、介護職員、看護職員など、多くの職種との連携が求められます。それぞれの職種が持つ専門知識や方向性の違いを理解しておかないと、認識のずれが生じ、円滑な連携が難しくなってしまいます。
もし、「ほかの職種との連携がうまくいかない」と悩んだら、こまめにコミュニケーションをとり、お互いの価値観や方向性をすり合わせましょう。ほかの職種と良い関係性が築ければ、業務をスムーズに進められるようになり、仕事の質が上がります。
仕事のストレスをため込み過ぎない
初めて生活相談員として働く方は、慣れない仕事からストレスをため込んでしまいがちです。生活相談員の仕事を長く続けるには、自分に合ったストレス解消方法を見つけて、仕事のストレスをため込み過ぎないようにしましょう。
生活相談員がストレスをためない方法としては、「仕事の優先順位を決めて、忙しいときは断る」「職場で相談できる相手をつくる」などがあります。生活相談員がストレスを軽減させる方法は、「生活相談員がストレスを感じる原因とは?解消法や転職のポイントもご紹介!」の記事でも紹介しているので、参考にしてみてください。
生活相談員が初めての仕事に慣れるためにできること
生活相談員が初めての仕事に慣れるには、介護現場に積極的に出ることや、介護保険制度を把握することを意識してみましょう。生活相談員の仕事をこなせるか不安に感じている方は、チェックしてみてください。
介護現場に積極的に出る
生活相談員はデスクワークが多いですが、積極的に介護現場に関わることで、利用者さんが抱える問題に気づく能力や、相談援助における提案力などを向上させられるでしょう。また、介護職員や看護職員とコミュニケーションをとって良い関係性を築ければ、情報共有がしやすくなります。
介護保険制度を把握する
生活相談員の仕事に慣れるには、介護保険に関する知識や自施設で提供可能な介護サービスなどを理解しておくことも重要です。生活相談員は、制度に関する説明をする機会が多いため、自分がしっかり理解していないと、相手に伝わりません。また、3年ごとに介護報酬改定が行われるため、常に最新情報を把握しておく必要もあります。
生活相談員のキャリアパス
生活相談員としての相談援助の経験を活かして、ケアマネジャーや管理職にキャリアアップする方は少なくありません。ここでは、ケアマネジャーと管理職の資格要件を紹介します。
ケアマネジャーを目指す
特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの特定の施設において、生活相談員としての実務経験を5年かつ900日以上積むことで、介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)の受験資格を得られます。
注意点として、ケアマネジャー試験に合格するだけでは資格を取得できません。試験に合格したら、研修の受講が必要です。「介護支援専門員実務研修受講試験への合格」と「介護支援専門員実務研修の修了」を満たすと、ケアマネジャーとして資格登録ができます。
ケアマネジャーの資格に興味がある方は、「ケアマネジャーになるには最短で何年?介護支援専門員の受験資格を解説」の記事もご覧ください。
出典
東京都福祉保健財団 ケアマネジャー専用サイト「令和6年度 東京都介護支援専門員実務研修受講試験」(2024年9月20日)
管理職になる
生活相談員の経験を活かして、施設長や管理者になる道もあります。
有料老人ホームやデイサービスの施設長・管理者には、必須の資格要件がありません。そのため、生活相談員としての経験があれば、キャリアアップを目指せるでしょう。
また、特別養護老人ホームの施設長になるには、「社会福祉主事の要件を満たす」「社会福祉事業に2年以上従事する」「社会福祉施設長資格認定講習会を受講する」のいずれかが必要です。そのため、社会福祉主事任用資格で生活相談員になった方や、特定の施設で2年以上の実務経験がある方は、施設長を目指せるでしょう。
管理職へのキャリアアップに興味がある方は、「施設長とは?なるために必要な資格はある?仕事内容や年収も解説!」も参考にしてみてください。
出典
厚生労働省「施設長の資格要件等」(2024年9月20日)
生活相談員への初めての転職を成功させるには
生活相談員への初めての転職を成功させるには、「資格要件を満たす」「生活相談員が複数いる職場に応募する」「未経験可の求人を狙う」などがポイントです。下記で詳しく説明します。
生活相談員の資格要件を満たす
まずは、生活相談員の資格要件を満たします。生活相談員の資格要件は自治体によって異なるため、自分が働きたい地域の資格要件をチェックしましょう。養成機関への通学など、条件を満たすのに時間がかかる場合には、要件を満たしやすい自治体で働くのも選択肢の一つです。
生活相談員が複数いる職場に応募する
初めて生活相談員として働く際は、生活相談員が複数いる職場への転職がおすすめです。生活相談員の配置人数が1人の場合、引継ぎの期間にすべての仕事を覚えなければなりません。2人以上配置されている職場なら、聞きながら仕事を覚えていけるので安心です。規模の大きい施設は、生活相談員を2人以上配置している傾向にあります。
転職活動の際に、施設ごとの配置人数を調べるのは大変に感じるかもしれません。求人を見ても生活相談員の配置人数が分からない場合は、介護業界に特化した転職エージェントのレバウェル介護(旧 きらケア)にお問い合わせください。
未経験可の求人を狙う
未経験可の求人は、未経験者の受け入れ態勢が整っている傾向にあります。教育制度やフォロー体制が整った環境なら、初めて生活相談員になる方も安心して仕事を覚えられるでしょう。
ただし、未経験者を募集している求人のすべてが、教育制度やフォロー体制が整っているとは限りません。転職する際は、事前にしっかり調べておきましょう。
正社員以外の選択肢も視野に入れる
パートやアルバイトで一定の経験を積んでから正社員を目指すのも、選択肢の一つです。生活相談員は各施設に1人ほどしか配置していないため、介護職員ほど求人は多くありません。そのため、パートやアルバイトなど、条件を広げることで応募先が探しやすくなります。
転職エージェントを活用する
生活相談員への転職が初めての方には、転職エージェントの利用をおすすめします。転職エージェントとは、求職者の希望条件や経歴に合った求人を提案してくれるサービスです。求人サイトには記載されていない求人を扱っていることがあるため、豊富な選択肢から転職先を選べるというメリットがあります。
レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護施設の求人の提案だけでなく、必要書類の添削や面接対策、応募先とのやり取りの代行なども幅広くサポート。初めての転職する方も、安心して転職活動を行えます。
生活相談員に関するよくある質問
ここでは、生活相談員に関するよくある質問を紹介します。生活相談員の仕事に興味がある方は、チェックしてみてください。
生活相談員に向いている人とは?
「コミュニケーションスキルがある」「人の役に立つのが好き」「周囲と連携がとれる」などの特徴に当てはまる方は、生活相談員に向いているでしょう。なお、これらに当てはまらないと向いていないというわけではありません。未経験の方も、意欲的に学ぶ姿勢を忘れずに経験を積んでいけば、自然と必要なスキルが身についていくでしょう。
生活相談員に向いている人の特徴については、「生活相談員の仕事は大変?向いている人の特徴と辞めたいときの対処法を解説」でも説明しているのでご覧ください。
生活相談員は資格なしでもなれる?
生活相談員に資格なしでなれるのかは、自治体によります。基本的に生活相談員の仕事に就くには、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」のいずれかが必要です。このほか、自治体によっては、介護の実務経験などを要件の一つとして定めていることもあります。
生活相談員の資格要件については、この記事の「生活相談員は初めてでも目指せる?」も参考にしてください。
まとめ
「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」のいずれかの資格があれば、介護業界が初めての方も、生活相談員として働くことが可能です。また、自治体によっては、実務経験の要件を満たせば、資格なしで生活相談員に従事できる場合もあります。生活相談員を目指す方は、まずは自分が働きたい自治体の要件を確認しましょう。
生活相談員の仕事内容は、利用者さんやご家族の相談対応や契約手続きなどです。担当する仕事の範囲は施設ごとに異なるので、転職の際は業務内容を確認したうえで応募しましょう。
「生活相談員として働けるか不安」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。介護業界の転職事情に詳しい専属のアドバイザーが、希望条件やキャリアプラン、経歴をヒアリングしたうえで、あなたに合った求人をご提案いたします。また、自分では応募先に聞きにくい、「生活相談員の配置人数」「教育体制」「労働条件」なども、アドバイザーからお伝えすることが可能です。サービスはすべて無料なので、お気軽にお問い合わせください。
登録は1分で終わります!
アドバイザーに相談する(無料)