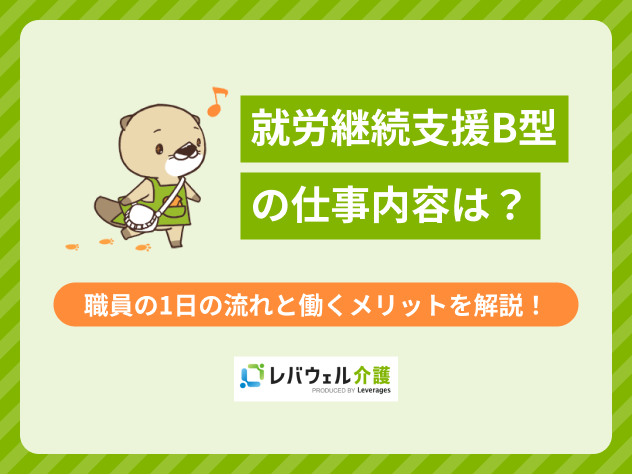
この記事のまとめ
- 就労継続支援B型の仕事内容は、利用者さんの生産活動や日常生活の支援
- 就労継続支援B型の仕事には、利用者さんの社会活動を支援できる魅力がある
- コミュニケーション能力が高い人は、就労継続支援B型の仕事に向いている
障害者支援に興味があり、「就業継続支援B型の仕事について知りたい!」という方もいるでしょう。就労継続支援B型事業所の職員の主な仕事内容は、障がいのある利用者さんの生産活動を支援することです。この記事では、就労継続支援B型の支援内容や1日の業務の流れ、職種ごとの役割などを解説します。就職・転職するメリットや向いている人の特徴もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型とは、障がいや難病があり、一般企業で働くのが困難な方の就労を支援する障害福祉サービスです。障害者総合支援法に基づき、仕事を行ううえで課題がある利用者さんの就労の機会を確保したり、知識・スキルの習得をサポートしたりします。
就労継続支援B型の利用者さんは、雇用契約を結ばずに就労するのが特徴です。労働基準法が適用されず、労働義務が生じないため、体調に合わせて利用者さんのペースで活動できます。週1回、短時間から通える場合も少なくありません。
利用者さんの就労や生産活動に対して支払われるお金は、給料ではなく工賃と呼ばれます。就労継続支援B型の利用者さんの行う生産活動は、労働ではないため、工賃は一般的な賃金より低いようです。また、就労継続支援B型は障害福祉サービスのため、世帯収入が一定以上あると、利用料金の負担が発生します。
就労継続支援B型の対象者
就労継続支援B型は、身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病により、就労に課題がある方が利用しています。
厚生労働省の「就労継続支援B型に係る報酬・基準について≪論点等≫(p.1)」によると、就労継続支援B型の対象者は、以下のとおりです。
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者
厚生労働省「就労継続支援B型に係る報酬・基準について≪論点等≫(p.1)」
(1)企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
(2)50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
(3)(1)及び(2)に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
つまり、「就労していたものの、年齢や体力を理由に労働が困難になった方」「就労面の課題が明らかになっている方」などが、就労継続支援B型事業所の対象者です。
就労継続支援B型を利用する条件
就労継続支援B型を利用するためには、市区町村の障害福祉課に申請し、障害福祉サービス受給者証を取得しなければなりません。障害者手帳は不要で、障害支援区分の認定を受けていない方も多く利用しています。また、就労継続支援B型の利用に年齢制限はありません。
就労継続支援B型の利用者に多い障害種別
厚生労働省の「就労継続支援B型に係る報酬・基準について≪論点等≫(p.4)」によると、就労支援B型の利用者として最も多いのは、知的障がいのある方で48.2%です。次いで精神障がいのある方が39.6%、身体障がいのある方が11.9%となっています(2022年12月時点)。
同資料(p.3)によると、10代~65歳以上まで幅広い年齢層の方が、就労継続支援B型を利用しており、40代以上の方が増加傾向にあるようです。自宅から通う方や、障害者グループホームから通う方などがいます。
就労継続支援B型とほかの就労支援サービスの違い
就労継続支援B型に近いサービスとして、就労継続支援A型や、就労移行支援があります。下記で、障がいのある方が利用できる就労支援サービスを比較してみましょう。
| サービスの種類 | 就労継続支援B型 | 就労継続支援A型 | 就労移行支援 |
| 雇用契約の有無 | なし | あり | なし |
| 対象者 | 雇用契約に基づく就労は困難だが、就労を通じて知識やスキルの維持・向上が期待できる方 | 一般企業で仕事をするのは困難だが、適切な支援により、雇用契約に基づく就労ができる方 | 一般就労を希望し、支援により就労の実現が見込める方 |
| 支援内容 | 就労・生産活動の機会の提供や、一般就労への移行に向けた支援 | 就労の機会の提供や、一般就労への移行に向けた支援 | 就労のための訓練や適性に応じた職場探し、就労後の定着の支援 |
| 年齢制限 | なし | 原則18~64歳※65歳以上で利用を継続できる場合もある | 原則18~64歳※65歳以上で利用を継続できる場合もある |
| 利用できる期間 | 制限なし | 制限なし | 最大24ヶ月まで※必要性が認められた場合は、最大1年延長できる |
| 1人あたりの工賃(2021年度) | 月額平均16,507円 | 月額平均81,645円 | 就労ではないため、基本的に工賃の支給はない |
参考:厚生労働省「就労継続支援B型に係る報酬・基準について≪論点等≫」「就労継続支援A型に係る報酬・基準について≪論点等≫」「就労移行支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」
就労継続支援B型とそのほかの就労支援サービスは、対象者や支援内容、工賃などが異なります。「就労継続支援B型で職業訓練をして、ほかのサービスに移行する」「就労継続支援A型から、柔軟に活動できるB型に変更する」など、状況に応じたサービスを利用可能です。
出典
厚生労働省「第38回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年9月4日)
今の職場に満足していますか?
就労継続支援B型事業所で働く職員の仕事内容
ここでは、就労継続支援B型事業所の職員の仕事内容を解説します。「ほかの障害者施設の仕事とどう違うの?」と気になっている方は、ぜひご一読ください。
利用者さんの生産活動の支援
就労継続支援B型の職員の主な仕事は、利用者さんの生産活動を支援することです。利用者さんが安心して作業できる環境を整え、就労をサポートします。作業を支援するだけではなく、利用者さんの適性に応じて仕事を配分することも重要です。
利用者さんが行う生産活動の内容
厚生労働省の「就労継続支援事業における生産活動の活性化に関する調査研究(p.22)」によると、就労継続支援B型の利用者さんが行う生産活動には、以下のようなものがあります。
- 部品の組み立て・検品・袋詰めなどの軽作業
- 清掃
- 織物や縫製などの雑貨製造
- 菓子製造
- 農業
- 空き缶やペットボトルのリサイクル
- パン製造
- 飲食店
- 入力・Web制作などPC関連の作業
利用者さんは、事業所内での就労のほか、清掃や農業などの施設外就労や、PC作業などの在宅就労を行う場合もあります。就労継続支援B型では、受託・請負・事業運営といった形で、利用者さんに生産活動を提供するようです。生産した物の販売まで行う事業所もあります。
職員が利用者さんに行う支援の例
就労継続支援B型の職員は、利用者さんには難しい作業工程を担当します。販売先や納品先の企業とのやり取り・調整も仕事内容です。また、作業場の環境や導線の整備も行います。
具体的には、障がいの特性で作業内容の理解が難しい利用者さんに対し、イラストで説明するなど、理解してもらうための工夫を行うことが、職員の役割です。また、作業の段取りを忘れてしまう利用者さんに対し、作業の流れを書いた紙を渡し、チェックしながら進めてもらうといった支援も行います。
施設外就労のための連携
ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどと連携し、利用者さんの施設外就労の機会を確保するのも、就労支援B型事業所の役割です。利用者さんの希望を確認し、スキルや適性を把握したうえで、就労先への連絡などを行います。
一般就労などへの移行に向けた支援
就労継続支援B型事業所では、就労継続支援A型や就労移行支援、一般就労などへの移行に向けた支援も実施します。まずは利用者さんの希望を聞き、状況を把握。そして、仕事を行ううえで必要なスキルや知識の習得をサポートします。
具体的には、一般就労に近い環境を整えたり、施設外就労を活用して利用者さんに合った仕事を見つけたりするのが職員の業務です。また、職場探しの支援なども行います。
日常生活の支援
利用者さんが安定して就労できるよう、生活習慣の改善に向けた支援も行います。たとえば健康管理では、主治医と連携するだけではなく、受診に同行する事業所もあるようです。また、お金の使い方の指導なども実施し、利用者さんの社会生活に貢献します。
利用者さんやご家族の相談への対応
利用者さんやご家族の相談に乗るのも、就労継続支援B型の職員の業務の一環です。利用者さんから多い相談としては、施設内の人間関係や就労に関する不安などが挙げられます。職員は、利用者さんに寄り添って話を聞くことが大切です。
また、ご家族が悩みを抱え込まないための支援も行います。相談に対応するだけではなく、ご家族が日中安心して過ごせるよう、施設での利用者さんの様子を伝えることもあるでしょう。利用者さんやご家族から相談があったら、職員や関係者に共有して、支援に活かします。
個別支援計画(就労継続支援B型計画)の作成
利用者さんが就労継続支援B型を利用するために、個別支援計画を作成するのは、事業所で働くサービス管理責任者の役割です。計画書には、利用者さんの基本情報や援助方針、長期目標と短期目標、利用者さんの役割、支援内容などを記載します。
適切なサービス計画の立案には、個々のニーズや障がい特性、心身の状況などの情報収集が欠かせません。課題分析をして個別支援計画を作成したら、目標達成のための支援を行いながら、適切な計画になっているかもチェックします。
余暇活動の支援
利用者さんの交流やリフレッシュを目的として、余暇活動を支援することもあります。たとえば、ボウリングやバーベキュー、旅行などのレクリエーションを実施する事業所があるようです。レクリエーションは、社会生活を送るうえで重要なコミュニケーション能力の向上にもつながります。
利用者さんの送迎
利用者さんを車で送迎する事業所で働く場合、運転や付き添いも仕事内容です。車での送迎ではなく、最寄り駅やバス停までの送迎を行う事業所もあります。送迎業務の有無は事業所によって異なるので、転職の際は確認しておくと良いでしょう。
出典
厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(2024年9月4日)
▼関連記事
障害者支援施設とは?仕事内容や一日の流れ、高齢者介護との違いを解説!
就労継続支援B型事業所の1日の仕事の流れ
就労継続支援B型事業所の職員のスケジュール例は、以下のとおりです。具体的なスケジュールは施設ごとに異なるので、参考までにご覧ください。
| 時間 | 仕事内容 |
| 午前9時 | 出勤・申し送り |
| 午前9時30分 | 利用者さん通所。生産活動の準備 |
| 午後10時 | 朝礼・生産活動の開始。利用者さんの支援 |
| 正午 | 休憩 |
| 午後1時 | 生産活動の支援 |
| 午後2時 | 利用者さんとの面談 |
| 午後4時 | 利用者さん退所 |
| 午後4時30分 | 片付け・翌日の準備 |
| 午後5時30分 | ミーティング。利用者さんの情報を共有 |
| 午後6時 | 退勤 |
就労継続支援B型事業所の働き方の特徴として、夜勤がないことが挙げられます。利用者さんの通所前に出勤して準備を行い、退所後に片付けをして退勤する場合が多いでしょう。職員が環境整備を行うことで、利用者さんがスムーズに生産活動に取り組めます。
就労継続支援B型事業所の職員の配置基準
就労継続支援B型事業所の職員の配置基準は、以下のとおりです。
| 職種 | 配置基準 |
| 職業指導員生活支援員 | 事業所にそれぞれ1人以上利用者さん10人に対して職業指導員もしくは生活指導員1人以上 |
| サービス管理責任者 | 事業所に1人以上。利用者さん60人以上の場合、40人またはその端数を増すごとに1人追加で配置 |
| 管理者 | 事業所に1人。業務に支障がなければほかの職種との兼務可 |
就労継続支援B型事業所には、職業指導員・生活支援員・サービス管理責任者・管理者の配置が必要です。
基本的な配置基準は、利用者さん10人に対して職業指導員・生活支援員1人以上ですが、これより手厚い人員配置で運営している事業所も少なくありません。上記のほか、目標工賃達成指導員などの職種を配置している施設もあります。
出典
厚生労働省「第38回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年9月4日)
就労継続支援B型事業所の職種別の仕事内容
ここでは、就労継続支援B型事業所の職種別の仕事内容を解説します。「職業指導員と生活支援員の違いが知りたい」という方は、仕事選びの参考にしてください。
職業指導員の仕事内容
職業指導員は、技術指導や訓練を行い、就労に必要な知識やスキルの習得をサポートする職種です。就労の支援を行う事業所において、利用者さんの生産活動を支える重要な役割を担います。生活支援員などと連携し、利用者さんが安心して生産活動に取り組める環境を提供するのが、職業指導員です。
生活支援員の仕事内容
生活相談員の仕事内容は、日常生活の相談に乗ったり、自立のための指導を行ったりすることです。利用者さんに寄り添い、安定した社会生活を送れるようサポートします。利用者さんが、無理なく就労を続けるためには、希望の確認やご家族・関係機関との連携が重要です。
サービス管理責任者の仕事内容
サービス管理責任者の主な仕事内容は、個別支援計画の作成です。相談支援事業所や就労移行支援事業所などの関連機関と連携し、利用者さん一人ひとりに適した計画を立案します。
施設内の職業指導員・生活支援員とも連携し、利用者さんの状況を把握するのも重要な仕事です。適切な支援を行えるよう、定期的に計画の評価や見直しを実施します。また、職員に支援方法のアドバイスを行うのも、サービス管理責任者の役割です。
管理者の仕事内容
就労継続支援B型事業所の管理者は、サービスの管理や改善を行います。具体的な仕事内容は、シフト管理や、利用者さんの就労機会を確保するための営業活動などです。利用者さんが安心して過ごせる環境や、職員が働きやすい環境を整え、スムーズにサービスを提供できる体制をつくります。
就労継続支援B型の仕事に役立つ資格
就労継続支援B型の職業指導員や生活支援員になるための要件はなく、無資格から就業できます。しかし、資格を取得すると、キャリアアップや給与アップにつながるメリットがあるでしょう。以下では、就労継続支援B型の職員におすすめの資格をご紹介します。
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修では、介護技術やコミュニケーション技法、障がいの種類などを学びます。利用者さんに寄り添ってケアを行うスキルが身につく資格で、特に生活支援員として働きたい方におすすめです。
介護職員初任者研修には受講要件がないため、無資格・未経験から取得できます。興味がある方は、「介護職員初任者研修とはどんな資格?受講費用を抑える方法や取得のメリット」もチェックしてみてください。
初任者研修を取りたい方必見!
レバウェル介護の資格スクールについて知る(新宿校)
介護福祉士
介護福祉士は、介護技術や福祉に関する知識があることを証明する国家資格です。資格取得の過程で、障がいの原因疾患や特性についても学ぶため、利用者さんに対する理解を深められます。
介護福祉士を取得するには、介護福祉士国家試験への合格が必要です。試験の受験資格を得るのに、養成施設に通う場合は最短1~2年、働きながらの場合は最短3年かかります。介護福祉士の資格について詳しく知りたい方は、「介護福祉士の受験資格を得るルートを解説!必要な実務経験や試験概要は?」の記事をご覧ください。
社会福祉士
社会福祉士は、社会生活に課題がある方の相談に乗る際に役立つ国家資格です。社会福祉士のもつ障害福祉サービスについての豊富な知識は、サービスの提供や関係機関との連携に活かせます。
社会福祉士を取得するには、社会福祉士国家資格への合格が必要です。試験の受験資格を得るには、大学や養成施設への通学、実務経験などが必要で、1~5年程度かかります。社会福祉士については、「社会福祉士資格を取得する7つのメリットとは?取得方法やルートも解説!」の記事にまとめているので、興味がある方はご一読ください。
精神保健福祉士
精神保健福祉士は、精神障がいのある方の相談援助を行うスキルや、社会福祉に関する知識を証明する国家資格です。そのため、精神障がいのある方と関わる場合に特に役立つでしょう。社会福祉士と同様、精神保健福祉士国家試験の受験資格を得るのにも、1~5年程度かかります。
作業療法士(OT)
作業療法士は、身体障がいや精神障がいのある方などが、日常生活に必要な動作を行えるよう、機能回復を支援するための国家資格です。取得すれば、障がいに応じた訓練や指導を行えるため、特に職業指導員の仕事に活かせるでしょう。なお、作業療法士国家試験を受験するには、作業療法士養成校に3~4年通う必要があります。
サービス管理責任者
サービス管理責任者として個別援助計画を作成するためには、サービス管理責任者の資格が必要です。資格取得により、利用者さんに対するアセスメントのスキルや、障害福祉サービスに関する実践的な知識があることを証明できます。
サービス管理責任者になるための研修を受けるには、3~8年(有資格者は最短1年)の実務経験が必要です。障害者総合支援法に基づくサービスを提供する事業所には、サービス管理責任者の配置が義務付けられています。
普通自動車第一種運転免許
普通自動車第一種運転免許があれば、利用者さんの送迎を行う事業所で働く場合に活かせます。なかには、運転免許を必須とする求人もあるので、免許がない方や運転に不安がある方は、応募の際に要件や仕事内容をしっかりと確認しておきましょう。
▼関連記事
障害者施設で働くにはどんな資格が必要?仕事内容や働くメリットも紹介
【障がい者支援に役立つ資格一覧】取得方法や難易度、習得できるスキルは?
就労継続支援B型の仕事に必要なスキル
就労継続支援B型の職員には、障がいに関する知識やコミュニケーション能力が必要です。利用者さんに適切な対応を行うことは、信頼関係の形成にもつながります。障害者支援のスキルは働きながら磨けるので、未経験の方も前向きに業務に取り組めば、専門性を身につけて活躍できるでしょう。
▼関連記事
介護職員として身につけるべき知識を紹介!スキルアップに必要な資格も解説
就労継続支援B型事業所で働くメリット
就労継続支援B型の仕事には、やりがいやメリットが多くあります。以下で確認してみましょう。
利用者さんの社会活動を支援できるやりがいがある
「社会参加したいけど、一般企業で働くのは難しい」という気持ちを抱える利用者さんの自己実現を支援できるのが、就労継続支援B型の仕事の魅力です。安心して就労できるよう支援し、利用者さんの笑顔を見たり感謝の言葉をもらったりしたときに、やりがいを感じることも多いでしょう。
障がいに対する理解が深まる
利用者さんと接するなかで、障がいに関する理解を深めることができます。実際に身近で支援することで、知的障がいや精神障がいのある方はどのようなときに不安に感じるのか、身体障がいのある方が就労するうえでの課題は何かなどにも気づけるでしょう。
就労継続支援B型事業所で働きながらスキルアップすれば、福祉業界でのキャリアアップを目指すこともできます。障がいのある方に対する自立支援のスキルを身につけたい方は、やりがいを感じながら働けるでしょう。
生活リズムを保って仕事ができる
就労継続支援B型事業所には、生活リズムを保って働ける魅力もあります。日中活動を行う通所型の施設なので、夜勤はありません。また、土日祝日休みの施設を選べば、仕事とプライベートを両立させやすいでしょう。
入所型の施設に勤務していて、「勤務時間がバラバラで仕事と家庭を両立させるのが難しい」と感じている方などは、働きやすいと感じる可能性があります。
体力的な負担が小さい
就労継続支援B型の利用者さんは、支援を受けて就労できる方なので、比較的自立度が高めです。職員が身体介護を行うことはあまりないため、ほかの障害者支援施設や高齢者施設と比べ、体力的な負担が小さい傾向にあります。
就労継続支援B型事業所は、「福祉の仕事をしたいけど体力に自信がない」という方も、活躍しやすい職場といえるでしょう。
需要が安定しており仕事がなくなるリスクが少ない
就労継続支援B型のサービスは需要が高く、利用者さんは年々増加しています。そのため、仕事がなくなるリスクが低く、安定して働けるでしょう。国としても、障がいのある方の地域生活の支援に力を入れているため、就労支援の仕事は今後も高いニーズが見込まれます。
▼関連記事
介護職に就くメリットとは?未経験からでも介護業界は目指せる!
就労継続支援B型の仕事のきついところ
障がいのある方と接することに慣れていないと、「どう対応して良いか分からない」と感じる可能性があります。利用者さんは自分の状況や気持ちを伝えられない場合があり、最初はコミュニケーションがうまくいかないこともあるかもしれません。
就労継続支援B型の仕事が未経験の場合、少しずつ慣れていけば問題ないので、一人で無理をしないことが大切です。周りの職員に相談しながら仕事をすれば、「なぜ利用者さんが不安そうにしているのか」「どのように対応したら安心してもらえるか」などが分かるようになっていくでしょう。
就労継続支援B型の仕事の大変な面と対処法は、「就労継続支援B型の職員はきつい?仕事が大変と感じる理由や対処法を解説!」にまとめているので、不安な方はチェックしてみてください。
就労継続支援B型の仕事に向いている人の特徴
以下の特徴に当てはまる方は、就労継続支援B型の仕事に向いている可能性が高いでしょう。
- コミュニケーション能力が高い
- 焦らず落ち着いて行動できる
- すぐに結果が出なくても目標に向けて努力できる
就労継続支援B型の仕事は、利用者さんが困っているときや予想外のことが起きたときに、冷静に対処できる人に向いているでしょう。また、長期的な目で見て利用者さんの支援ができる人にも向いています。
上記はあくまでも一例なので、当てはまらなくても問題ありません。仕事へ意欲があれば、スキルは後から付いてくるので、興味がある方はあまり気負わずにチャレンジしてみるのがおすすめです。
▼関連記事
障害者施設の仕事のやりがいとは?サービス内容や向いている人の特徴を解説
就労継続支援B型事業所の平均給与
厚生労働省の「令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果(p.80)」によると、就労継続支援B型事業所で働く福祉・介護職員の平均給与は、279,990円でした。障害者支援に携わる福祉・介護職員全体の平均給与は312,310円です。
夜勤がないことや、身体的な負担が比較的軽い傾向にあることから、就労継続支援B型事業所の職員の給与は、全体平均よりも低いと考えられます。転職の際は、給与や福利厚生、仕事内容などの詳細を確認し、自分が納得して働ける条件か見極めましょう。
障害者施設の給料事情を詳しく知りたい方は、「障がい者施設の給料は上がる?2024年の処遇改善や年収アップの方法とは」もご覧ください。
出典
厚生労働省「令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」(2024年9月4日)
就労継続支援B型事業所に転職する際のポイント
就労継続支援B型事業所への転職を成功させるためには、自分の行いたい支援と事業所の方針が一致しているのか、チェックすることが大切です。
利用者層や生産活動の内容を確認することで、支援内容もある程度把握できます。たとえば、「知的障がいの方のみが利用する施設」「障害支援区分が高めの方も利用する施設」など、事業所によって利用者さんは異なります。障害種別や障害支援区分、年齢などに応じた支援を行うため、利用者層によって求められる知識や身につくスキルも異なるでしょう。
「就労継続支援B型事業所で働きたい」「ほかの仕事と迷っている」など、就職・転職に関するお悩みは、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護・福祉業界に特化した転職エージェントです。キャリアアドバイザーから、求人先の詳しい情報を伝えることもできるので、転職を成功させやすいでしょう。事前の職場見学のセッティングも行っています。サービスはすべて無料なので、ぜひ利用してみてくださいね。
今の職場に満足していますか?
就労継続支援B型の仕事内容に関するよくある質問
ここでは、就労継続支援B型の仕事内容に関するよくある質問に回答します。「利用者さんの支援はどんな感じ?」と気になっている方は、ご一読ください。
就労継続支援B型で割り振る仕事がないときはどうする?
就労継続B型で利用者さんに任せる仕事がないときは、原因を考えて対策するのがおすすめです。仕事自体がないのか、利用者さんが対応できる作業がないのかで、対処法は異なるでしょう。仕事自体がない場合は、新たな事業に取り組んでみるといった対策があります。一方、仕事はあるけど利用者さんが対応するのが難しい場合、利用者さんのスキルアップを支援したり、分業してできる部分をやってもらったりすると解決するかもしれません。
就労継続支援B型事業所が行う生産活動の種類は、「利用者さんの生産活動の支援」で解説しているので、あわせて参考にしてください。
就労継続支援B型は精神障がいのある方も対象ですか?
就労継続支援B型事業所は、精神障がいのある方も利用しています。精神障がいのある利用者さんは、知的障がいのある方の次に多く、近年増加傾向にあるようです。ただし、実際の利用者層は施設ごとに異なります。就労継続支援B型事業所で働く場合は、自身のやりたい支援と事業所の運営方針にギャップがないか、事前に確かめておきましょう。
この記事の「就労継続支援B型の対象者」では、施設の利用条件や利用者層を解説しています。
就労継続支援B型事業所は儲かるの?
厚生労働省の「就労継続支援B型に係る報酬・基準について≪論点等≫(p.9)」によると、就労継続支援B型事業所の収支差率の平均は11.9%です。就労継続支援B型事業所は、経営がうまくいけば、利益を上げられます。ただし、事業所を運営するには、営業やマネジメントなど、経営に関するスキルが必要です。また、福祉に関する知識も求められます。利用者さんを集め、職員を確保し、生産活動を提供する必要があるので、簡単に儲かるとはいえないでしょう。
福祉施設の開設に興味がある方は、「介護事業所を立ち上げるために必要なことは?開業までの流れを解説」の記事もご参照ください。
出典
厚生労働省「第38回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年9月4日)
まとめ
就労継続支援B型は、障がいや難病がある方の就労を支援する障害福祉サービスです。職員は、利用者さんの職業指導や生活支援を行い、生産活動をサポートします。また、相談対応やレクリエーションなども仕事内容です。日中活動を支援する施設なので、夜勤はありません。
就労継続支援B型事業所で働く職種は、職業指導員や生活支援員、サービス管理責任者などです。職業指導員や生活支援員になるための要件はないので、無資格や未経験から転職できます。サービス管理責任者には、実務経験や研修の修了が必要です。
就労継続支援B型の仕事には、コミュニケーション能力や冷静な対応力、障がいに関する知識などを活かせます。
「障害者施設の仕事についてもっと知りたい!」という方や、「自分に向いている福祉の仕事はある?」と気になっている方は、レバウェル介護(旧 きらケア)をご活用ください。専任のアドバイザーが、希望条件や不安な点を伺い、あなたにぴったりの求人をご提案いたします。転職するか悩んでいる方の相談も歓迎なので、気軽にご利用くださいね。
今の職場に満足していますか?
 障害者施設の求人はこちら
障害者施設の求人はこちら