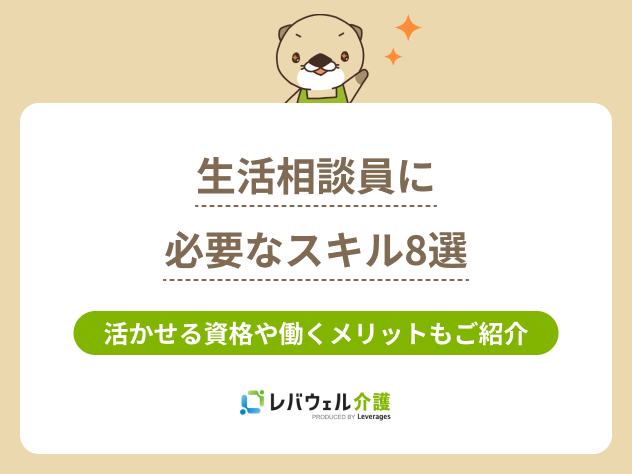
この記事のまとめ
- 生活相談員に必要なスキルは、コミュニケーション能力や連携するスキルなど
- 生活相談員の仕事は、資格要件を満たせば未経験から挑戦できる
- 生活相談員に向いているのは、人の役に立ちたい人や、責任感が強い人
「生活相談員に必要なスキルには、どんなものがあるの?」と気になる方もいるでしょう。生活相談員の仕事に求められるスキルは、コミュニケーション能力や多職種と連携するスキル、法律・制度に関する知識などです。この記事では、生活相談員に必要なスキルや、習得するための方法を解説します。働くメリットや向いている人の特徴もご紹介するので、ぜひチェックしてみてください。
生活相談員に必要なスキル・知識
ここでは、生活相談員に必要なスキルや知識をご紹介します。スキルや知識を習得するための方法もまとめたので、生活相談員を目指す方はチェックしてみてください。
利用者さんから信頼されるコミュニケーション
利用者さんやご家族、多職種と信頼関係を築くには、コミュニケーション能力が必要です。以下では、コミュニケーション能力を高めるために必要な要素を解説します。
傾聴力
利用者さんやそのご家族の気持ちを聞き出すための傾聴力は、生活相談員に必要なスキルです。じっくりと話を聞き、利用者さん自身も気づいていない課題が分かれば、より良い支援やアドバイスを行えるでしょう。また、相手のペースで話を聞くことで、「親身に相談に乗ってくれる」という好印象にもつながります。
共感力
生活相談員には、相手に寄り添う共感力が求められます。専門知識だけを頼りに相談対応をすると、利用者さんの要望に添えず、適切な支援につながらないこともあるでしょう。相手の立場に立って考えるスキルがあれば、利用者さんやご家族の悩みに寄り添ったケアを提供できます。
多職種と連携するスキル
生活相談員の仕事をこなすうえでは、介護職員やケアマネジャー、管理者など、多職種との連携が必要です。職種間の連携が円滑であれば、利用者さんに質の高い介護サービスを提供できるでしょう。
多職種への理解
多職種と円滑に仕事をするには、職種ごとの働き方を理解したり、状況をヒアリングしたりすることが必要です。ほかの職種の事情を理解することで、適切な連携・調整を行えます。
こまめな報連相
スムーズに連携するには、こまめで正確な情報共有も必要です。職種間の情報共有が雑だと、サービスの質を安定させられなかったり、利用者さんへの対応が不十分になったりするおそれがあります。利用者さんに施設を信頼してもらうには、丁寧な報連相が重要です。
法律や制度に関する知識
生活相談員には、介護保険法や福祉に関する制度についての専門知識が求められます。介護施設は、介護保険制度に基づいてサービスを提供するので、窓口としての役割を担う生活相談員には、必須の知識です。なお、介護保険制度は3年ごとに見直しが行われます。改正がサービスに影響することもあるので、勉強し続ける姿勢が大切です。
臨機応変に対応する力
生活相談員は、さまざまな悩みを持つ利用者さんと関わります。利用者さんの介護度だけでなく、性格や家庭の事情に合わせた相談援助が必要です。柔軟な対応をするスキルがあれば、より満足度の高いサービスを提供できるでしょう。
営業力
生活相談員は、施設の稼働率や経営指標を考慮し、利用者を確保する必要があるので、営業力が求められます。施設の魅力や特色をしっかり伝えられると、利用者さんが興味をもって、入所や通所を検討してくれるでしょう。また、利用者さんに自施設を勧めてもらえるよう、ケアマネジャーや医療ソーシャルワーカーといった職種と関係を築いておくことも重要です。
ストレス管理能力
悩みがあるときは、一人で抱え込まずに上司や先輩に相談したり、休日に心身をしっかり休めたりなど、自分のストレス管理を行う必要があります。
利用者さんやご家族、多職種などと関わり、さまざまな人をつなぐ生活相談員は、板挟みに合って調整が難しいこともあるでしょう。仕事が思うようにいかないときも、相談できる相手がいることや、自分なりのリフレッシュ法があることで、ストレスをため込まずに働けます。
メンタルヘルスケアの知識
利用者さんやそのご家族には、精神的な問題を抱えている方も少なくありません。メンタルヘルスケアの知識があれば、適切に対処できる。現場の介護職員や自分のストレス管理にも応用できる。メンタルヘルスケアに関する研修も開講されているので、気になる方はチェックしてみてください。
倫理観と守秘義務の理解
生活相談員は、福祉の専門職としての倫理観を身につける必要があります。利用者さんやそのご家族には、家庭環境や経済的な事情など、複雑な問題を抱えている方もいるでしょう。生活相談員は、どのような背景を持つ方に対しても、職業倫理に基づいて適切に対応するスキルが求められます。また、守秘義務を理解し、利用者さんやご家族のプライバシーを守ることも重要です。
登録は1分で終わります!
アドバイザーに相談する(無料)スキルがなくても生活相談員に転職できる?
生活相談員は、資格要件を満たせば、未経験から応募できる職種です。未経験から生活相談員として働く場合、はじめのうちはスキル不足で悩むことがあるかもしれません。しかし、相談援助のスキルは、経験を積むことで身につけられます。業務をこなしながら徐々に慣れていけるので、まずは気負わず挑戦してみるのも良いでしょう。
「生活相談員に必要なスキルが足りていないかも…」と不安な方は、教育体制が整備されている傾向にある「未経験者歓迎の求人」に応募するのがおすすめです。
▼関連記事
生活相談員の仕事は初めての人でも働ける?資格要件や仕事内容を解説
生活相談員に必要な資格
「生活相談員」という名前の資格はなく、自治体ごとに定められた要件を満たすことで、生活相談員の求人に応募できるようになります。次の3つの資格のいずれかを保有していれば、どの自治体でも生活相談員として働くことが可能です。
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉主事任用資格
以下で、それぞれの資格について解説します。
社会福祉士
社会福祉士とは、日常生活に支援が必要な方の相談援助を行うための、専門知識や技術があることを証明する国家資格です。年に1回開催される「社会福祉士国家試験」に合格することで取得できます。試験内容は、19科目からなる筆記試験です。
受験要件を満たす方法は、「福祉系大学ルート」「短期養成施設ルート」「一般養成施設ルート」の3つに分かれています。いずれの場合も、一定期間の通学により、相談援助の知識を学ぶことが必要です。
社会福祉士の受験要件については、「ソーシャルワーカーに必要な資格の取り方や難易度は?職種別の要件も解説!」の記事で解説しているので、ぜひご一読ください。
精神保健福祉士
精神保健福祉士とは、精神障がいのある方の相談援助や社会復帰の支援を行うための、知識や技術を証明する国家資格です。取得することで、生活相談員に必要な、福祉全般に関する知識も身につくでしょう。
受験要件を満たし、精神保健福祉士国家試験に合格したのち、資格登録することで、精神保健福祉士を名乗ることができます。試験内容は、18科目からなる筆記試験です。
精神保健福祉士国家試験の受験要件を満たす方法は、大きく分けて「保健福祉大学ルート」「短期養成施設ルート」「一般養成施設ルート」の3通り。具体的にはどのような要件なのか、以下で一部を確認してみましょう。
- 保健福祉系大学等(4年間)で指定科目を履修
- 保健福祉系短大等(3年間)で指定科目を履修し、相談援助の実務経験を1年積む
- 社会福祉士の資格を取得し、短期養成施設等に6ヶ月以上通う
- 4年制の一般大学等を卒業し、一般養成施設等に1年以上通う
指定科目の履修や相談援助の実務経験が、精神保健福祉士の受験資格となっています。さまざまな受験ルートがあるため、自分の学歴や実務経験に応じた方法を選びましょう。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「精神保健福祉士国家試験」(2024年10月4日)
社会福祉主事任用資格
社会福祉主事とは、福祉事務所などの職員として任用されるための資格です。生活相談員など、福祉施設の職員の要件としても準用されています。
社会福祉主事任用資格は、大学や通信教育、養成機関、講習会で指定科目を履修することで取得可能です。また、社会福祉士や精神保健福祉士といった資格を保有している場合も、社会福祉主事の任用要件を満たせます。
出典
厚生労働省「社会福祉主事任用資格の取得方法」(2024年10月4日)
▼関連記事
生活相談員の資格要件は?未経験から目指せる?仕事内容や職場もご紹介
生活相談員として働くメリット
生活相談員として働くメリットは、夜勤なしで働けることや、身体的な負担が少ないことなどです。それぞれについて、以下で解説します。
夜勤なしで働ける
基本的に、生活相談員は日勤のみで働きます。そのため、「家庭の事情で夜勤には入れない」という方も働きやすいでしょう。ただし、施設によっては介護業務を兼務する場合もあります。夜勤があるか気になる方は、事前に業務範囲や勤務形態を確認しておきましょう。
身体的な負担が少ない
生活相談員の業務はデスクワークが中心のため、介護職員よりも身体的な負担が少ない傾向にあります。介護業務を兼務する場合も、介護職員よりは現場で働く割合は少なめになるでしょう。「加齢や持病で体力に自信がない…」という場合は、生活相談員の働き方はメリットといえます。
キャリアアップにつながる
生活相談員の経験は、ケアマネジャーや施設長・管理者へのキャリアアップに活かすことが可能です。たとえば、相談援助業務の実務経験が5年以上あれば、介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)を受験できます。
また、施設長や管理者の要件は施設によって異なりますが、介護業界における一定以上の実務経験や福祉系の資格が求められることが多いようです。
生活相談員に向いている人の特徴
「生活相談員に興味があるけど、自分にできるか不安…」という方もいるでしょう。ここでは、生活相談員に向いている人の特徴をまとめました。自分に当てはまる特徴があるか、チェックしてみてください。
人の役に立ちたい
「人の役に立ちたい」という気持ちがある方は、生活相談員としてやりがいを感じながら働けるでしょう。たとえば、現場の介護職員から、業務や人間関係について相談されたときに、親身に対応することで、信頼関係を構築できます。人のために考えて動ける人は、生活相談員として、職員や利用者さんを支えられるでしょう。
責任感が強い
生活相談員は、利用者さんが快適にサービスを利用できるよう、幅広い業務をこなす職種のため、責任感が必要です。利用者さん一人ひとりに向き合って、必要な支援が行き届くために責任をもって業務にあたれる人は、生活相談員として活躍できます。
チームワークを大切にできる
生活相談員は、多職種と連携して業務をこなすため、チームワークを大切にできる人に向いています。円滑で丁寧な連携・調整を行えれば、生活相談員として周囲から信頼を得られるでしょう。
生活相談員のスキルについてよくある質問
ここでは、生活相談員のスキルについてよくある質問にお答えします。生活相談員への転職を考えている方は、参考にしてください。
生活相談員は資格なしで応募できる?
生活相談員として働くためには、社会福祉士・精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかの資格を求められるのが一般的です。ただし、自治体によっては、ほかの福祉系の資格や一定以上の実務経験があれば、生活相談員として従事できる場合もあります。求人に応募するときは、募集要項を確認しておきましょう。
生活相談員の資格要件については、「生活相談員は未経験・無資格でもなれる?資格要件や求人の有無を解説!」の記事で解説しているので、ぜひご一読ください。
生活相談員に向いてない人の特徴は?
責任感がない人は、周囲に「生活相談員に向いていない」と思われてしまうかもしれません。生活相談員の対応や説明が、入所の決め手になることもあるため、責任感を持って仕事をすることが求められます。介護サービスの窓口として、利用者さんやそのご家族への対応を行うことが、生活相談員の役割です。
生活相談員の適性については、この記事の「生活相談員に向いている人の特徴」で解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
まとめ
生活相談員に必要なスキルは、コミュニケーション能力や多職種と連携するスキル、介護保険に関する知識などです。自治体が定める要件を満たせば、未経験から生活相談員に就職・転職できます。経験を積むことで得られるスキルもあるため、興味がある方は気負わず挑戦してみるのがおすすめです。
生活相談員への転職を考えている方は、介護業界を専門とする転職エージェントの「レバウェル介護(旧 きらケア)」にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、あなたの希望条件をヒアリングし、ぴったりの求人をご紹介します。介護業界に精通したアドバイザーが、採用担当者と直接連絡を取っているため、ここだけの求人をご紹介することが可能です。サービスはすべて無料なので、お気軽にお問い合わせください。
登録は1分で終わります!
アドバイザーに相談する(無料) 未経験可の介護求人一覧
未経験可の介護求人一覧