Clik here to view.
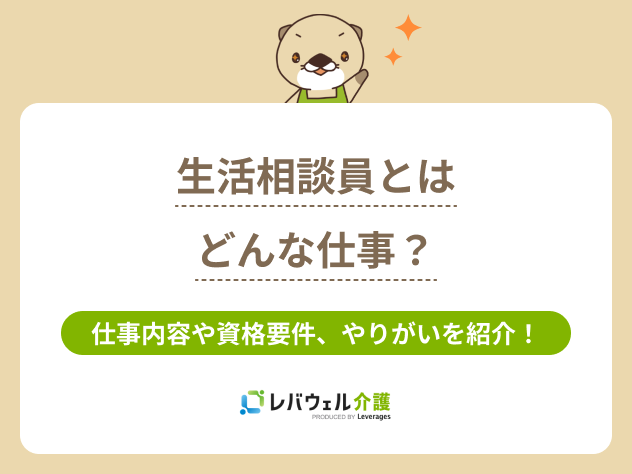
この記事のまとめ
- 生活相談員とは、利用者さんと関係者の間に入って相談対応や調整を行う職種
- 生活相談員の仕事内容は、施設の利用を希望する方への案内や契約手続きなど
- 生活相談員として働くメリットは、給与アップや生活リズムが乱れにくいなど
介護業界での転職を考えている方の中には、「生活相談員とはどんな職種?」気になっている方もいるでしょう。生活相談員の仕事は、主に利用者さんやご家族の困りごとや課題をヒアリングし、より良い介護サービスに繋げていくことです。この記事では、生活相談員の仕事内容や1日のスケジュールを解説。働くメリットややりがい、仕事で大変に感じることも紹介します。生活相談員への転職を迷っている方は、参考にしてみてください。
介護業界で働く職種一覧!仕事内容から必要な資格までご紹介生活相談員とは
Clik here to view.

生活相談員とは、介護施設の利用者さんが適切な介護サービスを受けられるように、利用者さんと関係者との間に入って、相談・連絡・調整を行う職種です。主に、介護職員やケアマネジャー、医療ソーシャルワーカーと連携し、利用者さんの支援方針の検討・調整などをします。
そのほか、利用者さんやご家族からの相談対応や、入退所に関わる契約手続き、現場職員のケアの相談対応なども、生活相談員の仕事です。利用者さんやご家族の声を現場に伝えて反映させたり、利用者さんの状況をケアマネに報告してケアプランの見直しに繋げたりするなど、利用者さん・介護現場・関係機関をつなぐ架け橋として、重要な役割を担っています。
詳しい仕事内容については、後述する「生活相談員の主な仕事内容」でも解説しているので、チェックしてみてください。
生活相談員とケアマネジャー(介護支援専門員)の違い
生活相談員は、相談援助により利用者さんの抱える課題を把握して、ケアマネジャーや介護職員に共有することが主な役割です。一方、ケアマネジャーはケアプラン(介護サービス計画書)を作成して援助の方針を決め、利用者さんが必要な介護サービスを利用できるように手配します。下記で、生活相談員とケアマネジャーの違いを表にまとめました。
| 生活相談員 | ケアマネジャー | |
| 仕事内容 | 相談援助関係機関との連絡・調整 | ケアプランの作成関係機関との連絡・調整 |
| 職場 | 入所型・通所型の介護施設 | 居宅介護支援事業所 入所型の介護施設多機能型の介護施設地域包括支援センター |
| サービスを提供する対象 | 介護施設の利用者さん利用者さんのご家族 | 介護保険サービスの利用者さん(要介護認定・要支援認定を受けた方) |
| 必要な資格 | 社会福祉士精神保健福祉士社会福祉主事任用資格※自治体によって異なる | 介護支援専門員 |
業務内容の違いのほか、勤務先や資格にも違いがあります。生活相談員とケアマネジャーの違いについて詳しく知りたい方は、「生活相談員とケアマネの違いを解説!仕事内容や職場、必要な資格、給与は?」をご覧ください。
生活相談員と介護職員の違い
生活相談員と介護職員の大きな違いは、仕事内容です。前述したように、生活相談員は、相談援助や関係機関との連携といった業務を主として行います。
一方、介護職員は、利用者さんの日常生活のサポートが主な役割です。介護職員の業務範囲は施設や事業所によって異なりますが、基本的に食事介助や入浴介助などの身体介護、掃除や洗濯などの生活援助を行います。
介護職の仕事内容については、「介護職の仕事内容とは?資格は必要?やりがいやメリットもご紹介」の記事で紹介しています。
今の職場に満足していますか?
生活相談員の主な仕事内容
介護施設の利用者さんを総合的に支援する生活相談員の仕事内容は、多岐にわたります。主な業務を下記で確認してみましょう。
施設の利用を希望する方の対応
生活相談員は施設の利用を希望する方に対して、施設の利用に関する説明などを行います。具体的には、居室や共有スペースの案内、施設が提供するサービスの内容や料金の説明、利用開始までの流れなど。利用を希望する方が施設を訪れて説明を受けるのが一般的ですが、状況によっては、利用者さんが暮らす自宅や施設などに、生活相談員が訪問することもあります。
入退所に関する手続き
入所や退所に関する契約手続きも、生活相談員の仕事です。利用を希望する方に、契約の説明をし、契約手続きを行います。特別養護老人ホーム(特養)の場合は、入居の可否や優先順位を検討する入所判定会議に参加し、入居を希望する方の情報共有を行うことがあるでしょう。
利用者さんが退所する場合は、退所の手続きや退所日時の調整などを行います。
利用者さんやご家族の相談対応
利用者さんやそのご家族から相談があれば、生活相談員が主となって対応します。相談を聞くだけでなく、より良い介護サービスが受けられるように、利用者さんのニーズに合わせて各関係者に働きかけるのが仕事です。
相談内容は多岐にわたりますが、日常生活や支援方針などがあります。利用者さんのなかには、施設内の人間関係や今後の生活に不安を抱える方もいるようです。介護サービスに関すること以外にも、利用者さんに寄り添う丁寧な対応が求められます。
介護施設のスタッフとの連絡調整
利用者さんやそのご家族から受けた相談は、介護現場やケアマネジャー、看護職員などの各方面と対応策を検討し、可能な範囲内で現場に反映するように調整します。必要であれば、医療機関や地域の行政機関と連携して支援を行うこともあるでしょう。
関係各所への連絡調整
生活相談員は、医療機関や行政機関など、外部の関係各所と連絡・調整を行います。ケアプラン会議への参加や通所介護計画書の作成など、施設形態によって業務内容は異なりますが、ケアマネジャーを主とする各方面の関係者と利用者さんの情報を共有し、今後の支援方針を検討します。
介護報酬請求などの事務作業
介護報酬請求や施設への問い合わせ、面会予約の受付などの事務作業を生活相談員が行うこともあります。ただし、施設によっては事務員が行う場合も。業務範囲は職場によって異なることに留意しておいてください。
現場の介護業務の兼務
自治体や施設形態によっては、介護職と生活相談員の兼務は可能です。生活相談員は、相談業務と介護業務を兼務する場合があります。特に、介護職員の人手が不足している施設では、生活相談員も現場に出る可能性が高いでしょう。
そのほかの業務
デイサービスの場合、生活相談員も介護職員と一緒に利用者さんの送迎や体調チェック、レクの企画や実行などを行うことがあります。新規利用者が集まらない場合は、ケアマネへ営業をすることもあるようです。
生活相談員の主な職場
生活相談員の主な職場には、下記があります。
ここでは、生活相談員の主な職場を3つ紹介します。
特別養護老人ホーム(特養)
特別養護老人ホームとは、原則、要介護3以上の認定を受けた65歳以上の方を対象とした入所施設です。主な提供サービスは、食事介助や入浴介助、排泄介助などの身体介護や療養上の世話など。終の棲家として、入居する方が多い傾向にあるようです。
特別養護老人ホームの生活相談員は、利用者さんと施設をつなぐ窓口として活躍しています。詳しくは、「特養の生活相談員とは?仕事内容は大変?役割と必要な資格、給料も解説」をご覧ください。
デイサービス
デイサービスは、主に自宅で生活する方が日帰りで介護サービスを受けられる通所施設で、入浴介助や食事の提供などをしています。また、身体機能の維持や回復、QOLの向上を目的とした多様なレクリエーションも提供しているのが特徴です。
デイサービスの生活相談員は、ケアマネジャーなどとの連絡や調整、介護業務などを主に担当しています。デイサービスに興味のある方は、「デイサービス相談員の仕事内容、必要な資格とは?」もチェックしてみてください。
有料老人ホーム
有料老人ホームは、民間企業が運営する高齢者向けの住まいで、「介護付き」「住宅型」「健康型」の3種類があります。有料老人ホームの提供サービスは、見守りや食事の提供、身体介護など。ただし、施設によって提供サービスは異なります。
「介護付き」「住宅型」「健康型」の3種類のうち、生活相談員の配置を定められているのは、「介護付き」のみです。有料老人ホームについては、「有料老人ホームとは分かりやすく言うとどんな施設?種類や入居条件を解説!」で解説しているので、参考にしてみてください。
Image may be NSFW.
Clik here to view. 生活相談員の求人一覧ページはこちら
生活相談員の求人一覧ページはこちら
生活相談員の配置基準
生活相談員の配置人数は、1つの施設に1~2人程度で、介護職員よりも少ないのが実情です。ここでは、生活相談員の配置基準をまとめました。
| 介護施設 | 生活相談員の配置基準 |
| デイサービス | 事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1人以上(生活相談員の業務には、サービス担当者会議、地域ケア会議も含められる) ※生活相談員か介護職員のうち1人は常勤 |
| ショートステイ | 利用者さん100人につき1人以上(常勤換算)※生活相談員のうち1人は常勤(定員が20人未満の併設事業所を除く) |
| 特別養護老人ホーム | 利用者さん100人につき1人以上 ※生活相談員のうち1人は常勤、専従が原則 |
| 介護付き有料老人ホーム | 利用者さん100人につき1人以上(常勤換算) ※生活相談員のうち1人は常勤 |
大勢の利用者さんが入居する介護施設は、利用者さん100人につき1人以上、生活相談員の配置が義務付けられています。
出典
第228回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料(2024年10月21日)
第229回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料(2024年10月21日)
第221回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料(2024年10月21日)
Image may be NSFW.
Clik here to view. 生活相談員の求人一覧はこちら
生活相談員の求人一覧はこちら
生活相談員の1日のスケジュール
ここでは、特養で働く生活相談員の1日のスケジュール例を紹介します。施設によってシフトの時間帯は異なる可能性がありますが、転職を考えている方は参考にしてください。
| 時間 | 業務内容 |
| 午前9時 | 出勤、朝礼、業務の確認 |
| 午前9時30分 | 利用者さんの相談対応、新規の契約手続き |
| 午前11時 | ご家族の方の相談対応 |
| 正午 | 休憩 |
| 午後1時 | 介護職員やケアマネジャーとの情報共有、意見交換 |
| 午後3時 | サービス担当者会議への出席 |
| 午前4時 | 関係各所への連絡 |
| 午後5時 | 書類や記録の作成 |
| 午後6時 | 退勤 |
生活相談員は夜勤がない場合が多く、生活リズムを保ちながら勤務しやすい職種です。ただし、介護業務を兼務する場合は、生活相談員も夜勤に出る可能性があります。
▼関連記事
生活相談員には残業がある?向いている人の特徴や大変さを知ろう!
生活相談員の平均給与
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.119)」によると、生活相談員・支援相談員の平均給与額は、常勤で34万2,330円、非常勤で30万6,260円でした。内訳は以下のとおりです。
| 月給・常勤 | 月給・非常勤 | |
| 平均給与額 | 34万2,330円 | 30万6,260円 |
| 平均基本給額 | 21万4,470円 | 23万3,930円 |
| 平均手当額 | 7万1,450円 | 3万7,240円 |
| 平均一時金額 | 5万6,420円 | 3万5,090円 |
参考:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.119)」
生活相談員として働く場合、基本給だけではなく、手当や一時金の有無も確認して職場を選ぶと良いでしょう。なお、生活相談員の給与は、働く介護施設ごとに異なるので、平均給与は参考程度にご覧ください。
出典
厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2024年10月21日)
▼関連記事
生活相談員の給料は安い?高い?仕事内容から平均年収まで
生活相談員として働くメリット
生活相談員として働くメリットには、「給料アップが期待できる」「生活リズムが乱れにくい」「身体介護による身体的負担が少ない」などがあります。下記で解説するので、転職を迷っている方は、参考にしてみてください。
給与アップが期待できる
前述した厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.119)」によると、介護職員(月給・常勤)の平均給与額は31万7,540円でした。生活相談員の平均給与額は34万2,330円なので、介護職員から転身すれば2万円程度の給与アップを狙えるでしょう。
自治体が定める資格要件を満たせば、介護職から生活相談員への転職が可能です。この記事の「生活相談員になるための資格要件」では、生活相談員に求められる資格を解説しているので、興味のある方はチェックしてみてください。
出典
厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2024年10月21日)
生活リズムが乱れにくい
生活相談員は、日勤のみのシフトで仕事をする傾向があります。基本的に夜勤がないため、生活リズムを保ちやすいのがメリットです。「介護業界で働きたいけど、夜勤に入るのは体力的にきつい…」という方に向いている仕事だといえます。また、日勤のみの勤務であれば、労働時間が一般的な会社と変わらないため、友人や家族との予定を合わせやすくなるのも魅力でしょう。
ただし、介護職と兼務している場合は夜勤に入ることがあるので、日勤のみで働きたい方は事前の確認が必要です。
身体介護による身体的負担が少ない
生活相談員は、デスクワークが多い仕事です。介護職員と比較して、身体介護による身体的負担が少ない傾向にあります。腰痛などの持病がある場合は、生活相談員の働き方はメリットになるでしょう。
なお、職場によっては、利用希望者さんの自宅などを訪問する際の移動手段が、自転車の場合があります。持病や体力などに不安がある方は、仕事中の移動手段を確認しておくと安心です。
キャリアアップに役立つ
生活相談員としての経験は、ケアマネジャーや施設長などへのキャリアアップに活かすことが可能です。ケアマネジャーの試験を受ける際の要件の一つに、「相談援助業務に従事した期間が5年以上かつ900日以上あること」が定められており、生活相談員として経験を積むことで、ケアマネジャー試験の受験資格が得られます。
また、生活相談員は施設の稼働率や職員の状態など、全体を見るスキルが身に付きます。将来施設長を目指す人は、施設運営を学ぶ機会になるでしょう。
施設長になる要件は、施設の種類によって異なります。施設長へのキャリアアップに興味のある方は、「施設長とは?なるために必要な資格はある?仕事内容や年収も解説!」を参考にしてみてください。
出典
公益財団法人 東京都福祉保健財団「令和6年度 東京都介護支援専門員実務研修受講試験」(2024年10月21日)
生活相談員が大変だと思うこと
ここでは、生活相談員が大変だと思うことを紹介します。「生活相談員は大変なの?」と気になる方は、チェックしてみてください。
クレーム対応によるストレスがある
サービスや施設に対してのクレームがあったときは、生活相談員が対応することがあります。利用者さんやご家族からだけでなく、地域の方々からクレームが入ることも。多方面に配慮しなければならないため、精神的なつらさを感じてしまう人もいるでしょう。1人で対応しきれなくなったときは施設長や上司に相談し、1人で抱え込まないことが重要です。
業務範囲が広い
生活相談員は、介護職員と比べて業務の幅が広い傾向にあります。相談業務だけでなく、入退所の手続きや書類作成、申請手続きなども仕事の範囲です。介護職と兼務する場合は介護業務もこなす必要があるため、さらに業務の範囲は広がるでしょう。「マルチタスクが苦手」という方にとっては、仕事に大変さを感じる可能性があります。
板挟みになりやすい
生活相談員は各方面との調整役を担っているため、利用者さんや施設の職員、福祉機関との板挟みになる場合があり、「仕事が大変」と思うことがあるようです。
たとえば、利用者さんやご家族が望むことと、施設で対応できることがかみ合わないときなどは、板挟みになりやすいでしょう。生活相談員は、利用者さんやご家族の意思を尊重しつつ、現場の職員の意見を聞き、支援の方向性などをすり合わせていくことが求められます。
▼関連記事
生活相談員の仕事は大変?向いている人の特徴と辞めたいときの対処法を解説
生活相談員のやりがい
生活相談員のやりがいには、「利用者さんの悩みや不安に寄り添える」「さまざまな仕事に携われる」があります。ここでは、生活相談員として働くやりがいを紹介するので、参考にしてみてください。
利用者さんの悩みや不安に寄り添える
生活相談員は、利用者さんやご家族が抱える課題を解決できたときや、自分の対応によって利用者さんに良い傾向が見られたときなどにやりがいを感じるようです。「現場だけでなく、広い視野で利用者さんやご家族に寄り添いたい」という方は、生活相談員の仕事にやりがいを感じられるでしょう。
さまざまな仕事に携われる
前述のとおり、生活相談員は相談対応のほか、多方面への連絡調整や契約関係の業務なども行います。施設によっては、介護業務を兼務したり訪問営業を担当することも。介護知識だけでなく、介護報酬や介護保険制度、契約関係など、さまざまな知識が求められます。「幅広いスキルや知識を身につけたい」という方にとって、生活相談員の仕事はやりがいを感じられるでしょう。
生活相談員に向いている人の特徴
ここでは、生活相談員に向いている人の特徴をまとめました。「自分に適性があるか知りたい」という方は、ぜひチェックしてみてください。
利用者さんやご家族の相談に親身に対応できる人
生活相談員は、人の悩みに寄り添える人が向いています。相談業務のポイントは、利用者さんやご家族が、悩みや不安を打ち明けやすい環境を作ること。生活相談員には、傾聴力や本音を引き出す力が求められます。気持ちに寄り添いながら親身になって相談に乗れる人は、生活相談員として活躍できるしょう。
責任感を持って業務に取り組める人
責任感を持って仕事に取り組める人は、生活相談員に向いています。もし、無責任な態度で仕事をした場合、相談者に「真摯に向き合ってもらえていない」といった印象を与え、良好な信頼関係を築けません。さらに、施設全体のサービスの低下につながるおそれもあります。生活相談員は、利用者さんやご家族、施設が抱える課題に対して、最後までやりきる責任感の強さが必要です。
コミュニケーション能力が高い人
相談者さんからの相談対応をしたり、多方面と連携したりして仕事をする生活相談員は、コミュニケーションが欠かせません。特に相談業務では、利用者さんやご家族の情報や思いを引き出すためにも、高いコミュニケーションスキルが求められます。コミュニケーション能力に自信がある方は、そのスキルを活かしながら生活相談員として活躍できるでしょう。
客観的に物事を判断できる人
生活相談員は、利用者さんと介護職員の間に立つ存在といえます。相談対応では、どちらかに偏った提案ではなく、中立の視点を持つことを求められることもあるでしょう。クレーム対応でも客観的に物事を判断し、冷静に対応しなければなりません。そのため、客観的に物事を判断できる人は、生活相談員に向いているといえるでしょう。
チームワークを大切にできる人
チームワークを大切にして仕事ができる人は、生活相談員に向いています。生活相談員は、ケアマネジャーや介護職員などとの連携が必須。他職種と信頼関係を築くことが重要です。人との関わり合いを大切にして仕事ができる人は、スムーズに業務を進められるでしょう。
生活相談員になるための資格要件
生活相談員になるための資格要件は、自治体ごとに決められています。生活相談員になるには、下記のいずれかを満たすことが必要です。
それぞれの資格については、下記で説明します。
社会福祉士
社会福祉士は、福祉の相談援助に関する知識や技術があることを証明する国家資格です。社会福祉士になるには、社会福祉士国家試験に合格したうえで資格登録をする必要があります。
公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの「社会福祉士国家試験」によると、社会福祉士国家試験の受験要件は、「大学での指定科目の履修」や「相談援助の実務経験」「養成施設への通学」が定められています。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「社会福祉士国家試験」(2024年10月21日)
精神保健福祉士
精神保健福祉士は精神障害を専門に、相談業務や社会復帰の支援を行います。社会福祉士と同様に国家資格です。精神保健福祉士国家試験に合格したうえで、資格登録をすることで精神保健福祉士を名乗ることができます。
公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの「精神保健福祉士国家試験」によると、精神保健福祉士国家試験を受験するには、「大学での指定科目の履修」や「相談援助の実務経験」「養成施設への通学」が必要です。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「精神保健福祉士国家試験」(2024年10月21日)
社会福祉主事任用資格
「社会福祉主事任用資格」とは、「社会福祉主事の仕事に就くための資格のこと」です。一般的に社会福祉主事任用資格は、公務員が社会福祉の業務を行うための資格を指しますが、介護業界で働く職種の要件として定められていることがあります。
社会福祉主事任用資格を取得するには、下記のいずれかを満たさなければなりません。
- 大学や短期大学において、指定科目を修めて卒業する
- 特定の通信教育課程(1年)を修了する
- 指定養成機関を修了する
- 都道府県が実施する講習会を修了する
- 社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を取得する
資格がない場合は、養成機関へ通学したり講習会を修了することで、社会福祉主事任用資格が得られます。
出典
厚生労働省「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」(2024年10月21日)
自治体が定める資格
社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格以外に、各自治体で生活相談員の要件を定めていることがあります。自治体によって要件が異なるため、転職の際は、応募先の職場がある自治体の資格要件を調べておきましょう。
無資格から生活相談員になれる?
介護施設における一定の実務経験があれば、生活相談員に従事できる自治体もあります。無資格の場合は、実務経験が問われることが多いようです。ここでは、仙台市を例に解説します。
仙台市の「生活相談員の資格要件について」によると、生活相談員として従事できる資格要件は、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」のほかに、「介護支援専門員(ケアマネジャー)」「指定の施設において、3年以上相談業務もしくは、介護・看護業務に従事したことがあること」です。仙台市の場合、無資格でも実務経験があれば、生活相談員として働ける可能性があることが分かります。
「無資格から相談員になりたい」という方は、通勤できる範囲に要件を満たす自治体があるかチェックしてみましょう。
出典
仙台市「生活相談員の資格要件について」(2024年10月21日)
▼関連記事
生活相談員の仕事は初めての人でも働ける?資格要件や仕事内容を解説
生活相談員の仕事の将来性
日本では、高齢化により今後も介護サービス利用者の増加が見込まれ、介護業界の需要もますます増していくと予想されます。特に、介護や福祉に関する専門知識を有する生活相談員は、高齢者福祉に欠かせない存在であり、将来性のある職種だといえるでしょう。
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「老人福祉施設生活相談員」によると、有効求人倍率は8.59倍とあります。生活相談員は不足しているうえに、資格要件があり誰でもできる仕事ではないので、生活相談員の経験があれば貴重な人材として歓迎されるでしょう。生活相談員としての経験はキャリアアップにも役立つため、転職を迷っている方は前向きに検討してみることをおすすめします。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「老人福祉施設生活相談員」(2024年10月21日)
生活相談員を目指す方によくある質問
ここでは、生活相談員についてよくある質問に、Q&A方式でお答えします。「生活相談員についてもっと知りたい!」という方は、ぜひご覧ください。
介護施設の生活相談員とは、どのような職種ですか?
生活相談員は、主に介護施設の窓口として、サービスの利用を希望する方に提供サービスの説明をしたり契約手続きをしたりします。そのほか、利用者さんの相談対応や関係機関への連絡・調整、他職種との連携なども生活相談員の役割です。
生活相談員の仕事内容に興味のある方は、この記事の「生活相談員の主な仕事内容」を参考にしてみてください。
生活相談員になるには資格が必要ですか?
生活相談員の要件は自治体や都道府県ごとに定められており、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかを求められる傾向にあります。自治体によっては、一定の実務経験があれば無資格から働ける場合もあるようです。
生活相談員の資格要件については、「生活相談員の資格要件は?未経験から目指せる?仕事内容や職場もご紹介」をご覧ください。
まとめ
生活相談員は、利用者さんやご家族の相談に乗り、適切な介護サービスを提供できるよう調整する職種です。主な仕事内容として、介護施設の利用に関する手続きや、関係者との連絡・調整が挙げられます。
生活相談員の資格要件は自治体によって異なりますが、基本的には福祉系の国家資格や、介護に関する資格が必要です。介護・相談業務の実務経験を要件にしている自治体もあり、無資格から目指せることもあります。
「生活相談員として働きたい」「介護業界でどのようなキャリアを積むか迷っている」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)をご利用ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した転職エージェントです。専任のアドバイザーが、あなたのご希望や悩みを丁寧にヒアリングし、「生活相談員を目指すには何から始めれば良い?」「将来的にケアマネを目指すこともできるの?」といった疑問にもお答えします。
サービスはすべて無料なので、介護業界での転職やキャリアアップを考えている方は、気軽にご相談ください。
今の職場に満足していますか?