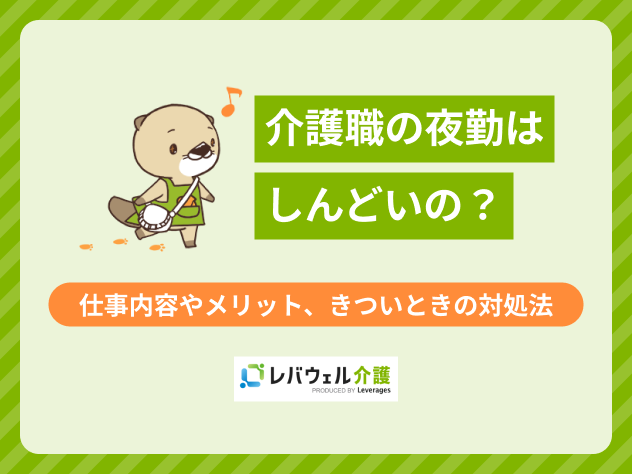
この記事のまとめ
- 夜勤の介護職員の仕事内容は、食事の準備や身体介助、夜間の巡回など
- 介護職の夜勤がしんどいと感じる理由は、労働時間の長さや職員の少なさ
- 夜勤に入るメリットは、割増賃金や夜勤手当で給料アップを望めることなど
介護職への転職を考えている方のなかには、「介護職の夜勤はしんどいイメージがあるから不安…」という方もいるでしょう。介護職の夜勤がしんどいと言われる理由として、労働時間の長さや職員の少なさが挙げられます。この記事では、夜勤職員の仕事内容や1日のスケジュールをまとめました。介護職の夜勤がしんどいと言われる理由や対処法もまとめたので、介護職の夜勤に不安がある方は、ご一読ください。
介護職の夜勤の仕事内容
ここでは、介護職の夜勤の仕事内容を1日の流れに沿ってまとめました。以下で、それぞれの仕事内容について具体的に解説します。
出勤
出勤したら、日勤者から申し送りを受けます。申し送りでは、利用者さんの日中の様子や体調、留意事項を確認。業務をスムーズに引き継ぐため、しっかり状況を把握しておく必要があります。
夕食・朝食の準備
夜勤では、夕食や朝食の準備を行います。夜勤に入る場合、利用者さまの食事を準備するのは、夕食と朝食の2回です。なお、施設によっては、夕食の準備を日勤の職員と一緒に行うこともあります。朝食の準備は、夜勤に入っている職員がメインで行う場合が多いようです。
食事介助
利用者さまの食事介助を行うのも、夜勤職員の仕事です。まず、利用者さまをトイレや手洗いに誘導し、準備を済ませたら、食事を配膳します。
食事介助では、利用者さまが食べたいものや水分の多いものから少量ずつ提供するのがポイントです。必ず、一口ごとに飲み込んだことを確認しましょう。食事のペースは本人に合わせながら、偏りなくバランス良く提供するといった工夫も必要です。
服薬介助
食前や食後、就寝前などのタイミングで、服薬の介助を行います。利用者さまごとに、薬の種類や数、飲むタイミングが異なるので、しっかりと確認しましょう。服薬する際は、利用者さまの姿勢を整えたうえで介助を行い、薬を最後まで飲み込めたかチェックします。
巡回と利用者さんの安否確認
利用者さんの就寝後、施設内の安全や利用者さまの安否を確認するため、施設内の巡回を行います。巡回の回数は施設によって異なりますが、1時間か2時間おきに行う場合が多いようです。
安否確認では、就寝している利用者さまの呼吸の状態や覚醒状況を確認します。ベッドから落ちている方はいないか、目覚めて起き上がっている方はいないかといった状況も確認しましょう。
ときには、利用者さんの体調が悪く、自分でコールを押したり状況を伝えたりできないこともあるかもしれません。少しでも早く異常に気づくためにも、利用者さまの安否確認は、重要な仕事です。
夜間の体位交換・おむつ交換
夜間に体位交換やおむつの交換を行うのも、重要な仕事の一つです。体位交換では、皮膚の病気を防ぐため、自力で寝返りをうてない方をサポートします。
夜間の排せつ介助業務は、3時間起きにおむつ交換する、排せつを確認した際に交換するなど、施設によって方法はさまざまです。おむつを使用していない利用者さまについては、排せつのタイミングを把握し、トイレへの誘導・介助を行います。
ナースコール対応
夜間に利用者さまからナースコールがあったら、都度対応します。排せつを手伝ってほしい場合や体調が悪い場合など、状況に合わせて柔軟に対応する力が必要です。緊急事態の場合もあるので、ナースコールがあったら迅速に対応しましょう。
緊急時対応
夜勤中に、利用者さんの体調が急変したり亡くなったりした場合、介護職員が対応します。利用者さまの状態を責任者や看護師に報告し、必要があれば救急車の手配が必要です。緊急時の対応マニュアルを用意している介護施設が一般的なので、夜勤に入る場合は確認しておきましょう。
記録業務
夜勤職員は、就寝後の時間を利用して、介護記録の作成や利用者さまの情報を確認します。利用者さまの体調の急変のような緊急対応がなければ、夜間は昼間より余裕のある時間帯です。
日中に終わらなかった業務
巡回の合間に、日中に終わらなかった業務を進めるのも、夜勤職員の仕事です。前述した記録業務のほかにも、備品の管理や日中業務の準備、レクリエーションや委員会活動の仕事など、さまざまな雑務をこなします。
引き継ぎ業務
退勤する前に、夜勤の時間帯の利用者さまの様子や出来事を、日勤のスタッフに引き継ぎます。少しでも普段と違った様子があれば、必ず申し送りしましょう。特に、夜の時間帯は管理者や看護師が不在になる傾向にあるので、出勤してきた他職種にもしっかりと引き継ぎをする必要があります。
今の職場に満足していますか?
介護職の夜勤の1日のスケジュール
ここでは、介護職の夜勤の流れをご紹介します。以下では、2交代制の場合のスケジュールをまとめました。
| 時間 | 仕事内容 |
| 午後5時 | 出勤、日勤から申し送り |
| 午後6時 | 夕食の準備、食事介助 |
| 午後7時 | 口腔ケア、服薬介助 |
| 午後8時 | トイレ誘導、就寝の準備 |
| 午後10時 | 消灯 |
| 午前12時 | 巡回、記録業務、雑務 交代で仮眠 |
| 午前5時 | 起床の準備、更衣のサポート |
| 午前6時 | 朝食の準備 |
| 午前7時 | 食事介助 |
| 午前8時 | 口腔ケア、服薬介助 |
| 午前9時 | 日勤への申し送り、退勤 |
夜勤に入る場合、消灯後の時間に休憩や仮眠をとります。「緊急対応が気がかりで気が休まらない…」という方は、複数人で夜勤に入れる介護施設を選ぶのがおすすめです。
介護職の夜勤シフトと勤務時間
ここでは、介護職の夜勤のシフトについて解説します。介護職のシフト形態や夜勤の回数についてご紹介するので、職場選びの参考にしてください。
2交代制と3交代制の2パターンある
介護職のシフトは、2交代制と3交代制に分けられます。それぞれについて解説するので、自分に合うのはどちらのシフト形態か、チェックしてみましょう。
2交代制
2交代制は、1日を昼と夜の2つの時間に分けるシフト形態です。一般的に、日勤の勤務時間は8時間、夜勤の勤務時間は16時間になります。
夜勤は勤務時間が長く設定されていますが、夜勤明けの翌日が休みになるなど、プライベートの時間を長くとりやすい傾向があるようです。
3交代制
3交代制は、1日を昼・夕方・夜の3つの時間に分けるシフト形態です。日勤、準夜勤、深夜勤に分けられ、基本的にはそれぞれ8時間ずつの勤務になります。
夜勤の場合も8時間での勤務なので、身体的な負担がかかりにくいといえるでしょう。ただし、3交代制の場合、夜勤明けの翌日に出勤になることもあるので、生活リズムを整えるのが難しいと感じる人もいるようです。
▼関連記事
16時間の夜勤はきつい?8時間の場合は?働くメリット・デメリットを解説
夜勤回数は介護施設による
1人のスタッフが夜勤に入る回数は、施設によって異なります。法的には夜勤に入る回数に制限はなく、職員の働き方やシフトの回しやすさから、施設ごとに回数を決めています。目安としては、月に4、5回夜勤を担当するのが一般的です。
介護職の夜勤回数については、「介護職の夜勤回数に上限はある?労働基準法や平均夜勤回数を解説」の記事でも解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
介護職で夜勤のある雇用形態
一般的に、夜勤が含まれる雇用形態は、正社員と夜勤専従の2つです。以下で、それぞれの働き方について解説します。
正社員
正社員の場合、日勤と夜勤の両方に入るのが一般的です。正社員は、非常勤に比べて福利厚生が充実していたり、賞与をもらえたりする傾向にあります。ただし、非常勤よりも休日の融通が利きにくい、残業が多い傾向にあるというデメリットもあります。
夜勤専従バイト
夜勤専従は、夜勤を専門に働く雇用形態です。夜勤専従の介護職員は、パートやアルバイトといった非正規雇用で募集していることが多いでしょう。
夜勤のみで働けるので、生活リズムが乱れにくいのがメリットです。また、夜勤手当がつくため、日勤のパートよりも給与額が高くなりやすいといえます。
▼関連記事
介護の夜勤専従は楽?きつい?仕事内容とメリット、デメリットを解説
介護職の夜勤がしんどいと言われる5つの理由
「介護の夜勤がしんどい」と言われる理由として、労働時間の長さや夜間の職員数の少なさなどが挙げられます。ここでは、介護の夜勤がしんどいと言われる理由を5つまとめました。
1.労働時間が長い
介護の夜勤がしんどいと言われる理由として、労働時間が長いことが挙げられます。2交代制の場合、2時間程度の休憩があるとはいえ、勤務時間は16時間ほどです。夕方に出勤して、翌日の午前中まで勤務するため、日勤に比べると労働時間が長く、しんどいと感じる人がいるようです。
2.職員の人数が少ない
夜勤職員は、配置人数が少ない傾向にあります。以下は、入居施設の夜勤の人員配置基準です。
| 施設名 | 配置基準 |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 2ユニットごとに介護職員または看護職員を1人以上 |
| 老人保健施設(老健) | 看護職員または介護職員の数が利用者20名につき1人以上 |
| グループホーム | ユニットごとに1人 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 泊まりと訪問対応で2人(1人は宿直可) |
夜間は日中よりも業務量が少ないため、介護職員の人数も日勤より少なくなります。夜勤職員や利用者さんの人数次第では、体力的または精神的な負担がかかる可能性があるでしょう。
出典
厚生労働省「厚生労働省「第183回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」」(2024年10月24日)
厚生労働省「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」(2024年10月24日)
厚生労働省「第179回社会保障審議会介護給付費分科会(オンライン会議)資料」(2024年10月24日)
厚生労働省「第218回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2024年10月24日)
身体介護の負担が大きいケース
夜間に身体介護の機会が多い場合、介護職員にかかる負担が大きい可能性があります。介護度が高い利用者さんが多い施設では、夜間のおむつ交換や体位交換の回数も多い場合があるでしょう。少ない職員で複数名の身体介護を行うときは、体力的にしんどいと感じることがあるようです。
精神的な負担が大きいケース
夜勤は少人数で対応するため、緊張感や忙しさから精神的な負担を感じることもあるようです。利用者さんのなかには、認知症の症状などから、夜間に眠れずベッドから離れる方がいることもあります。介護職の目が行き届かないところでの転倒リスクがあるため、緊張感や不安を感じる職員もいるようです。
また、眠れない利用者さんからのナースコールが重なると、対応に追われ、精神的に疲れてしまうこともあるでしょう。
3.変則勤務で体調を崩しやすい
日勤と夜勤の両方に入る場合、変則勤務になり、体調を崩しやすくなることもあるでしょう。生活リズムが整わず、睡眠の質が下がる可能性もあります。体調を崩したり疲れが溜まりやすくなったりすることで、しんどさを感じる方もいるようです。
4.急な休みに対応しづらい
体調不良や家族の都合などで突然休みをとりたい場合、代理の人員が見つからないことも考えられます。介護業界は慢性的な人手不足に陥っており、職員が足りない施設も少なくありません。なかには、家庭の事情で夜勤に入れない職員もいるため、日勤よりも交代できる人員は限られるでしょう。どうしても出勤が難しい場合は、管理者に相談のうえ、調整を依頼してみてください。
5.利用者さんとのコミュニケーションが少ない
夜勤の場合、利用者さまが寝ている時間が長く、コミュニケーションをとれる時間が日勤よりも少なくなります。なるべく利用者さんとコミュニケーションをとりたい人にとっては、やりがいを感じにくいかもしれません。
夜勤がしんどいと言われる理由については、「夜勤はつらい?現役介護士さんが感じる「しんどさ」の度合いとその理由」の記事でも体験談をご紹介しているので、チェックしてみてください。
介護職が夜勤をする5つのメリット
ここでは、介護職の方が夜勤に入るメリットをまとめました。「夜勤はしんどい」と言われる一方で、得られるメリットもあります。働くメリット・デメリットを照らし合わせて、自分に向いているか確認してみてください。
1.就職や転職が有利になる
夜勤をする1つ目のメリットは、介護職への就職や転職が有利になることです。「介護の夜勤はしんどそう…」というイメージから、夜勤の求人は求職者に敬遠されることもあります。応募者が少ない求人の場合、採用される確率が高くなるでしょう。夜勤の有無以外に同じ条件の応募者がいた場合、夜勤に入れるほうが採用されやすいといえます。
また、夜勤に入れると応募できる求人が増えるので、幅広い選択肢のなかから、自分に合った職場を選びやすいでしょう。
2.夜勤手当で給料アップが叶う
夜勤に入るメリットの2つ目は、夜勤手当による給料アップを望めることです。夜勤に入ると、基本給に深夜割増賃金や夜勤手当が加わります。日勤と同じ時間働いても、より高い収入を得られるでしょう。
夜勤をする人には、基本給に加えて、深夜割増賃金が支払われます。厚生労働省の「しっかりマスター 割増賃金編(p.2)」によると、午後10時から翌朝5時までの間は、基本給の25%増しの賃金が支払われる決まりです。
また、法律では定められていませんが、深夜割増賃金に加えて夜勤手当が支給されている施設もあります。日本医療組合連合会が発表している「2023年 介護施設夜勤実態調査結果 (p.28)」によると、正規職員・2交代制の1回の平均夜勤手当は6,365円でした。夜勤手当の金額は施設によって異なり、深夜割増賃金を含む金額の場合も考えられるので、あくまで参考としてご覧ください。
出典
厚生労働省「労基法パンフレット」(2024年10月23日)
日本医療組合連合会「介護施設夜勤実態調査」(2024年10月23日)
3.日勤よりも業務量が少ない
夜勤に入る3つ目のメリットは、日勤と比べて業務量が少ないことです。夜勤の時間帯は、緊急対応がない限り、日中に比べて利用者さまへの対応は少ないといえます。
大変なイメージのある夜勤ですが、入浴介助やレクリエーションといった仕事がない分、「日勤よりも忙しくない」と感じる方もいるようです。
4.プライベートの時間を確保しやすい
夜勤に入る4つ目のメリットは、プライベートの時間が確保しやすいことです。2交代制で夜勤に入る場合、夜勤明けの翌日は休みになる傾向があります。
シフトの組み合わせ方によっては、日勤のみで働くよりも連休がとりやすくなるでしょう。連休をつくって旅行に行ったり、趣味を楽しんだりと、プライベートを充実させやすいといえます。
5.通勤のストレスが小さい
夜勤に入る5つ目のメリットは、通勤時のラッシュに巻き込まれず、スムーズに通勤できることです。基本的に、夜勤職員の出勤時間は16時30分ごろ、退勤時間は深夜や朝9時ごろになります。どちらも通勤ラッシュに巻き込まれにくい時間なので、通勤時のストレスが少ないといえるでしょう。
しんどい介護職の夜勤で負担を減らす方法
夜勤で働く際は、生活リズムが崩れやすいため、身体への負担を減らすことが大切です。以下で、夜勤で疲労を溜めないための工夫をまとめたので、参考にしてください。
1.夜勤中に仮眠をとる
夜勤中に仮眠をとることで、勤務中の眠気を防止できます。夜勤中に2時間程度の仮眠をとると、疲れを軽くすることが可能です。複数の夜勤職員が配置されている場合、ほかの職員と交代で仮眠をとるようにしましょう。
一人で夜勤に入り、十分に仮眠をとれない場合は、10~20分の仮眠でも疲労感を軽減できます。また、「プレッシャーや不安から眠れない…」という方も、目をつむるだけで心身を落ち着けられるので、試してみてください。
2.夜勤明けは早めに寝る
夜勤明けに疲れが溜まっていると感じたら、早めに仮眠をとりましょう。眠気があるときは、2~3時間仮眠をとるだけでも疲労感が軽減します。スマホの光や日光を浴びると寝付きにくくなるので、部屋を暗くするのがおすすめです。
「仮眠をとりたいけど寝付けない…」という方は、「夜勤の寝れない悩みを解決!仮眠を取るコツや睡眠時間、眠気対策などを解説」の記事もチェックしてみてください。
3.夜勤明けの日中は寝過ぎない
夜勤明けに仮眠をとる際は、できるだけ寝過ぎないようにしましょう。夜勤明けだからといって長く寝ると、その日の夜に眠れず、生活リズムが崩れてしまいます。
趣味を楽しんだり、誰かと食事に行ったりする時間をつくると、精神的にリフレッシュできるのでおすすめです。
▼関連記事
介護職の夜勤明けの過ごし方12選!つらいときのリフレッシュ方法も紹介
4.夜勤中の食事は消化の良いものを選ぶ
夜勤中、消化の良い食事をとることで体への負担を減らせます。消化も良くエネルギーに変わりやすい、おにぎりやゆで卵、バナナなどがおすすめです。
また、規則的な食事は体内時計を保つ効果があります。夜間の食事は軽めにして、日中にしっかりと食事をとると良いでしょう。
▼関連記事
夜勤にオススメのご飯をタイミング別に解説!ダイエット中でも大丈夫な食事
5.自分なりに最適な睡眠リズムを見つける
夜間に眠くならず、体調を崩さない睡眠リズムを見つけるのも、夜勤をこなすコツです。夜勤シフト時の睡眠は、人によってベストなとり方が異なります。夜勤前と夜勤中に仮眠をとるほうが良い人もいれば、夜勤明けに長時間寝たほうがスッキリする人もいるでしょう。先輩職員の夜勤準備を参考に、自分に合う睡眠リズムを見つけると、夜勤の負担を減らせるといえます。
緊急時の対応を事前に確認しておく
緊急時に焦らないよう、余裕があるときに対応マニュアルを見直しておきましょう。緊急時の対応や連絡先を確認しておくことで、何かあったときに冷静に対応できるよう、イメージしておくことが大切です。緊急時には医療職の指示をあおぐのが一般的なので、的確な報告・対応ができるよう、冷静に状況を把握するよう心がけましょう。
▼関連記事
介護職の夜勤が不安…覚えておきたい緊急時の対応や心身のケア方法7選
夜勤で働く介護施設を選ぶときの注意点
夜勤をしんどいと感じる度合いは、勤め先によっても異なるでしょう。たとえば、仮眠がしっかり取れる施設と取れない施設では、前者のほうが体が楽に感じるといえます。
以下では、夜勤で働く際に注意したい職場選びのポイントをまとめたので、職場選びの参考にしてみてください。
休憩室や仮眠室があるかを確認する
夜勤がある施設で働く場合、休憩室や仮眠室があるかどうかを確認しましょう。夜勤で働く介護職の方によくある悩みとして、忙しくて休憩が取れないことや、ゆっくりと休めないことなどが挙げられます。だからこそ、施設内に休憩室や仮眠室があるかどうか確認することが大切です。
休憩時間や残業時間を確認する
施設がきちんと休憩時間を確保しているかにも、注意が必要です。実際に介護を行っていると、利用者さまの状況によっては、法定通りの休憩時間が取れないこともあります。
施設を選ぶ際は、休憩を取れない状況が当然になっていないか確認しましょう。そもそも休憩時間を設定しない施設は、労働基準法に違反しているため、避けるのが賢明です。
また、夜勤明けに残業がないかも確認しておきましょう。日勤の人手が足りず、夜勤の人が残業する施設は、職員の負担が大きい環境といえます。
夜勤で働く回数を確認する
夜勤回数が少ない働き方をしたい場合は、月にどれくらい夜勤に入る必要があるのか、確認しておきましょう。介護施設における夜勤の回数に制限はなく、施設によって一人あたりの夜勤の回数はばらつきがあります。
夜勤をしんどいと感じるかどうかは、月にどれくらい夜勤シフトに入るかによっても変わるため、事前に回数を把握しておくことは大切です。
夜勤手当を確認する
給料を重視して職場を選ぶ場合は、夜勤手当がある職場に就職・転職するのがおすすめです。先述したとおり、夜勤では法律で深夜割増賃金を支給することが決まっていますが、別で夜勤手当があるかは施設によって異なります。
どのような手当が支給されるのか、求人の条件をよく読み、分からない点は面接で確認するようにしてみてください。
介護職の夜勤に関するよくある質問
ここでは、介護職の夜勤についてよくある質問にお答えします。「介護職の夜勤での働き方についてもっと知りたい」という方は、ご一読ください。
介護職の夜勤でワンオペするのは違法ですか?
介護職の夜勤でワンオペをするのは、違法ではありません。夜勤職員の配置基準は、介護施設の形態や規模によって異なります。基準を満たしていれば、介護職員が一人で夜勤に入ることも可能です。ただし、一人で夜勤に入ることで、法定の休憩時間を自由に取れない場合は労働基準法違反となります。
休憩が取れなくて困っている人は、「介護の夜勤で休憩なしは違法?ワンオペや16時間勤務は労働基準法違反か」もチェックしてみてください。
16時間夜勤の業務がきついです。負担を減らす方法はありますか?
介護職の夜勤がきつい方は、可能な限り生活リズムを正したり、休日にゆっくり体を休めたりすることを意識しましょう。夜勤中には、仮眠や消化の良い食事をとることが、業務中の負担を減らすために重要なポイントです。また、夜勤のしんどさは施設によっても変わります。
「夜勤で働く介護施設を選ぶ時の注意点」では、少しでも夜勤業務の負担を減らしたい方に向けて、転職前に確認したいポイントを解説しているので、気になる方はご一読ください。
無資格・未経験でも働ける介護夜勤求人はありますか?
無資格・未経験からでも、夜勤のある求人に応募することが可能です。一般的には、日勤業務から覚えて、夜勤入りすることが多い傾向にあります。無資格者は一人で身体介護が行えないため、有資格者と一緒に夜勤に入ることになるでしょう。介護職員初任者研修以上の介護資格を有していると、一人でも夜勤に入れるようになります。
詳しくは、「介護職に無資格OKの夜勤求人はあるの?仕事内容や採用されるコツを紹介」の記事もチェックしてみてください。
まとめ
介護職の夜勤が「しんどい」と言われる理由として、労働時間の長さや職員数の少なさ、疲労が溜まりやすいことなどが挙げられるでしょう。介護職の夜勤はしんどいこともありますが、「採用される可能性が高まる」「収入が増える」「日勤より時間に余裕がある」「プライベートの時間を確保しやすい」など、メリットも多くあります。
これから介護業界への就職・転職を考えている方は、夜勤のメリット・デメリットを知ったうえで、働き方を検討しましょう。
介護業界に興味がある方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した就職・転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたが希望条件を満たす求人をご提案します。また、入職後のギャップをなくすために、事前に有給消化率や残業時間、夜勤の実態などのリアルな情報もお伝えすることが可能です。介護経験がない方にも、人生のトータルサポートを目指したサービスを提供するので、ぜひ気軽にお問い合わせください。
今の職場に満足していますか?
 夜勤のみの介護求人一覧はこちら
夜勤のみの介護求人一覧はこちら