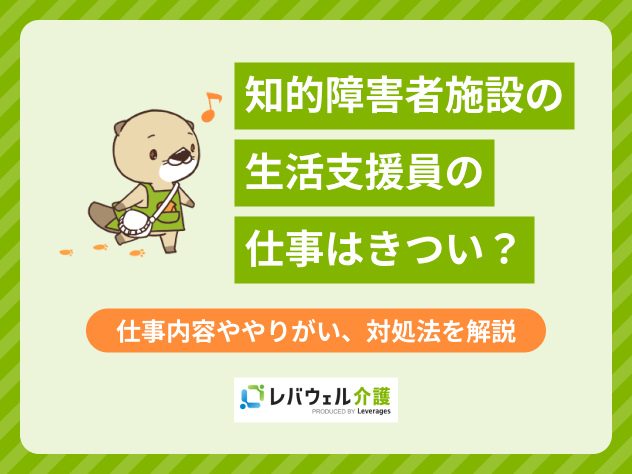
この記事のまとめ
- 知的障害者支援員がきついと感じることは、コミュニケーションの難しさなど
- 知的障害者施設で働く生活支援員のやりがいは、支援法を考える楽しさなど
- 仕事がきついときは、障がいへの知識を深めたり上司に相談したりする
「知的障害者支援員の仕事ってきついの?」と不安を感じている人もいるでしょう。知的障害者施設の仕事は、障がいがある利用者さんのサポートを行うため、コミュニケーションなど、難しいこともあるかもしれません。この記事では、きついといわれる仕事ややりがい、働くメリットなどを解説します。きついと感じるときの対処法も紹介するので、これから転職を検討している方はぜひご一読ください。
知的障害者施設とはどんな職場?
知的障害者施設とは、知的障がいがある方の生活や就労をサポートする施設です。知的障害者施設には、子どもを対象とする施設や大人を対象とする施設があります。
知的障害者施設の種類
「知的障害者施設」という名前の施設はありません。知的障がいがある方の支援を行っている施設を知的障害者施設と呼ぶことがあるようです。
知的障害者施設にはいくつか種類があります。具体的には、施設入所支援や自立訓練、障害者グループホーム、就労継続支援A型・B型事業所など。障がいの程度や利用ニーズによって、適したサービスを利用することが可能です。
それぞれのサービスについては、「障害者支援施設とは?仕事内容や一日の流れ、高齢者介護との違いを解説!」の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
なお、この記事では、知的障がいがある方の支援を行っている施設全般を知的障害者施設と表記します。
知的障がいがある方の特徴
厚生労働省の「知的障害児(者)基礎調査:調査の結果」によると、知的障害は下記のように定義されています。
「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」
引用:厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査:調査の結果」
また、知的障がいがある方の特性として、下記のような傾向があります。
- 相手に何かを伝えることが難しい
- 相手の言葉や気持ちを理解するのが難しい
- 状況に応じた行動を取るのが難しい
- 気持ちの切り替えが難しい
障がいの程度や苦手な領域は個人差があります。生活の多くに介助が必要な人もいれば、就労など組織で生活するための支援を必要としている人もいるでしょう。知的障害者施設では、一人ひとりの利用者さんの個性に合わせて、対応をする必要があります。
出典
厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査:調査の結果」(2024年10月25日)
e-ヘルスネット(厚生労働省)「知的障害(精神遅滞)」(2024年10月25日)
生活支援員の仕事内容
障がいにより一人で生活を送ることが難しい利用者さんの日常生活のお世話を行うのが生活相談員の主な仕事です。利用者さん自身ができることを増やし、自立した生活を送れるように支援することが求められます。
生活支援員の具体的な業務内容は下記にまとめました。
- 利用者さんの見守り業務
- 生活スキルのトレーニング
- 身体介護
- 家事支援
- 健康管理
- レクリエーションの企画、実施
- 就労支援
介助内容や目標とする自立の程度は利用者さんによって異なります。生活支援員は、利用者さん一人ひとりの状態や特性を把握したうえで対応する必要があるでしょう。身体介護を行う場合は、高齢者介護施設より身体的な負担が少ないこともあるようです。
登録は1分で終わります!
アドバイザーに相談する(無料)知的障害者施設の生活支援員がきついと言われる理由
ここでは、知的障害者施設で働く生活支援員の仕事がきついといわれる理由を解説します。「きついって噂があるけど、どんなことが大変なの?」と気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
なお、以下はすべての施設に当てはまるわけではありません。あくまで、参考程度として確認するようにしましょう。
利用者さんとのコミュニケーションが難しい
利用者さんとのコミュニケーションに難しさを感じることがあるようです。知的障害者施設には、言葉や状況を理解するのが苦手な利用者さんが多く、利用者さんが理解しやすい形でコミュニケーションを取ることができないと、意思の疎通が難しいことがあります。
利用者さんに合ったコミュニケーションの取り方は人それぞれなので、良い方法が見つかるまでは、きついと感じることもあるでしょう。思うようにコミュニケーションを取れないことに対してストレスを感じることもあるかもしれません。
利用者さんから暴言や暴力を受ける
知的障がいがある方の中には、強度行動障害の行動が現れる利用者さんがいることもあります。障がいの特性上、自分自身や他人を傷つける行動に出ることも。そのため、対応中に職員が暴力を受けることもあるようです。感情のコントロールができず、暴言を吐かれることもあるので、素直にその言葉を受け止めてしまう人はしんどいと感じてしまうかもしれません。
仕事内容が給与に見合わない
仕事内容に給与が見合っていないと感じる人もいるでしょう。厚生労働省の「令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果(p.79)」によると、障害福祉サービスなどで働く生活支援員の平均給与は、325,450円です。知的障害者支援員は、利用者さんの命を預かる責任ある仕事であり、体力も必要な仕事といえます。
しかし、障害福祉サービスは、公的価格で報酬が決められているため、事業所でサービス料を値上げして給与に反映することが難しいのが現状です。仕事の頑張りが給与に直結するとは限らないので、きついと感じる人もいるでしょう。
出典
厚生労働省「令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」(2024年10月25日)
介護業務の体力的な負担が大きい
個人差はありますが、食事や身支度、入浴、排泄に援助が必要なケースがあります。そのような場合は、生活支援員が食事や排泄、入浴の介助を行う必要がありますが、自分より体重が重い人を抱えたり支えたりすることもあり、体力的に負担を感じる人もいるようです。介護業務は腰への負担も大きく、腰痛に悩まされることもあるでしょう。
利用者さんの見守りに精神的な負担がある
知的障がいがある方の中には、ADHDや自閉症を併発していることがあります。突発的に動いたり、じっとしていることが苦手な方もいるので、危険が及ばないように見守ることが重要です。
特に、外出支援時は、交通事故に合ったりほかの人に迷惑をかけたりしないように気を配る必要があるので、精神的に疲労してしまうことも。利用者さんから目が離せない不安から常に緊張状態になってしまうこともがあるようです。
衛生面でストレスが大きい
衛生に対する意識が弱い利用者さんもいるので、潔癖症の人はきついと感じるかもしれません。重度の知的障がいがある方の場合、自分から排泄を手伝ってほしいと言えない人もいます。排泄に失敗した場合は、職員が排泄物の処理をしなければならないため、慣れないうちはきついと感じることがあるでしょう。
また、食事をこぼしてしまったり、よだれや鼻水が出てしまったりする人もいます。利用者さんの感染症リスクを減らし、安全を確保するために職員が対応する必要がありますが、慣れないうちは抵抗感を覚える人もいるかもしれません。
職場の人間関係が悪い
職員によって、利用者さんの支援に対する考え方が違うことがあり、人間関係に影響が出てしまうことがあります。人には相性があり、「何となくこの人とは合わないな…」と感じることもあるかもしれません。
職場の人間関係が悪いと、分からないことがあっても質問しにくかったり、利用者さんの情報共有がしっかりと行われなかったりする可能性も。価値観の違いから、人間関係がギスギスしてしまうこともあるでしょう。
▼関連記事
障害者施設の職員は給料が高いの?
知的障害者施設で働く生活支援員のやりがい
知的障害者施設の生活支援員がきついといわれる理由を解説しましたが、生活支援員の仕事はきついだけではありません。ここでは、生活支援員のやりがいや働く魅力を紹介するので、ぜひご一読ください。
支援法を考える楽しさがある
利用者さんの状態を観察して、利用者さんの個性や気持ちに寄り添った支援法を考えることに楽しさを感じる人もいるようです。利用者さんの状態が落ち着いたりコミュニケーションがスムーズにできたりすることにやりがいを感じる人もいます。
利用者さんの目標を達成できる
利用者さんによって、課題や目標は異なります。生活支援員は、あくまで利用者さんのサポートが仕事です。利用者さん自身ができることはできる限り本人ができるようにサポートします。目標を定めて、練習を繰り返すことで、成長する場面を見ることができたときはやりがいもひとしおです。
利用者さんと信頼関係を築ける
利用者さんが心を開いてくれたり信頼関係を築けたりすると、やりがいを感じられるようです。知的障がいがある方は、症状によりコミュニケーションが困難なことがあります。うまくいかないと、自分のコミュニケーション方法に自信がなくなることもあるでしょう。しかし、時間をかけて利用者さんと接していけば、次第に利用者さんが心を開いてくれて、通じ合える可能性があります。コミュニケーションが困難であるほど、うまくいったときの喜びも大きいでしょう。
利用者さんやご家族から感謝される
生活支援員が、身体介護や家事支援などを通じて利用者さんの生活をサポートすることに対して、利用者さんやご家族から「ありがとう」と感謝されることがあります。直接感謝の言葉を伝えられると、人の役に立っている実感ができ、仕事のモチベーションも高まるでしょう。感謝されることで、自分が行っている仕事に対して自信がつくこともあります。
▼関連記事
障害者施設の仕事のやりがいとは?サービス内容や向いている人の特徴を解説
知的障害者施設で働くメリット
ここでは、知的障害者施設で働くメリットを解説します。知的障害者施設への転職を検討している方は、ぜひご覧ください。
障がいへの理解が深まる
知的障害者施設で働くことで、障がいの症状への理解や対処法が身につきます。障がいへのケアは、高齢者介護では重点的に学べないスキルです。専門的な知識や技術が身につき、福祉や介護業界での仕事に活かせるでしょう。
介護スキルが身につく
食事介助や排泄介助など、一般的な身体介護の知識やスキルが身につきます。知的障害者施設では、障がいへの対応だけでなく、一通りの介護スキルが身につくので、高齢者介護にも応用することが可能です。介護スキルが身につくと、家族に介護をする際にも役立つでしょう。
コミュニケーション能力が高まる
前述したように、障がいがある方のコミュニケーションは難易度が高い傾向にあり、知的障害者施設で働くことで、コミュニケーション能力を高めることができるでしょう。
コミュニケーション能力は仕事だけでなく、私生活にも活かすことができます。施設によっては、コミュニケーションに関する専門的な研修会やトレーニングを実施していることがあるようです。
施設形態によっては体力的な負担が小さい
就労支援を行う施設では、食事や排泄など基本的な身の回りのことは自分でできる利用者さんが多く、身体介護の機会が少ない傾向にあります。通所型で夜勤もないので、高齢者介護の施設よりも体力的な負担が減ったという声もあるようです。
経験が転職で役立つ
知的障害者施設で身についた障がいへの理解や対応方法、コミュニケーション能力は転職先でも活かすことができます。転職する際に、「即戦力になる」と評価され、選考で有利になる可能性も。知的障害者施設で働いた経験は、福祉業界や介護業界での転職で役立つので、応募先の選択肢も広がるでしょう。
生活支援員の将来性
生活支援員は今後も需要が期待できるので、将来性がある仕事といえるでしょう。最近は利用を希望していても、近くに障がい者施設がなく待機状態になる人も多くいるようです。
都道府県などが作成する障害福祉計画では、障害福祉サービスの充実が推進されており、障害者施設は増えていく可能性があります。施設が増えることで生活支援員が活躍できる機会も増えるでしょう。
また、知的障害者支援員の仕事は専門性の向上が求められるようになり、教育に力を入れていくことが予測されます。
知的障害者施設の生活支援に向いている人の特徴
ここでは、知的障害者施設の生活支援に向いている人の特徴を解説します。「知的障害者施設の仕事に興味があるけど、自分にできるか不安…」という方は、当てはまる特徴がないかチェックしてみてください。
人の気持ちに寄り添える人
前述したように、知的障がいがある方は、自分の気持ちや要望を伝えることが難しいことがあります。そのため、共感したり傾聴したりして、利用者さんの気持ちに寄り添える人が知的障害者施設の生活支援の仕事に向いているでしょう。利用者さんの気持ちに寄り添うためには、コミュニケーション能力が必須といえます。
臨機応変に対応できる人
強度行動障害による行動や突発的なパニックなど、突発的なトラブルが起こることがあります。その際に、冷静に臨機応変に対応できる人は、知的障害者支援員に向いているでしょう。臨機応変に対応するには、障がいへの理解も欠かせません。
向上心がある人
適切な対応をするために、知的障がいの症状や特性、利用者さん一人ひとりの特徴などを覚える必要があります。同じ障がいでも利用者さんによって対処方法は異なるので、学ぶことは多いかもしれません。しかし、向上心がある人は、意欲的に障がいについて学習できるので、知的障害者施設の支援員として成長できるでしょう。
▼関連記事
障害者支援施設で働く心構えとは?介護士さんが気を付けたいポイント
知的障害者施設の支援員の仕事がきついときの対処法
「知的障害者施設の支援員の仕事がきつい…」と感じることもあるかもしれません。ここでは、仕事がきついと感じたときの対処法を解説するので、お悩みの方は参考にしてみてください。
障がいに関する知識を身につける
利用者さんとのコミュニケーションや対応により仕事がきついと感じているときは、障がいに関する知識を身につけると良いでしょう。障がいの種類によって、特性に傾向があります。特性の傾向や観察の観点、一般的な対応方法などについて学ぶことで、困ったときに打開策を考えられるようになるでしょう。また、障がいのある方に対するコミュニケーションスキルを身につけることで、自信がついて仕事へのストレスが軽減するかもしれません。
上司や同僚に相談する
上司や同僚へ相談するのも効果的です。悩みに対して、経験をもとに的確なアドバイスを貰えるかもしれません。利用者さんとの関わり方について相談したり、業務の見直しをしたりしてもらいましょう。上司に相談することで、「仕事の割り振りを見直す」「デジタルツールやロボットを導入する」などの対処法が見つかり、自分だけでは解決しにくい悩みが解消される可能性があります。また、話を聞いてもらうだけで気持ちが楽になることもあるでしょう。
公的な相談センターに相談する
「職場の上司に相談しにくい」というときは、公的な相談センターに相談するのも一つの方法です。職場から離れた第三者に悩みを相談することで、解決へつながることもあるでしょう。
たとえば、東京都では公的な相談センターとして、「福祉のしごとなんでも相談」や「こころスッキリ相談」「介護現場のハラスメント相談」などがあります。お住まいの地域の相談センターを調べてみましょう。
出典
東京都社会福祉協議会「福祉の仕事に関する悩みを相談する」(2024年10月25日)
自分なりの方法でストレスを発散する
ストレスが溜まっていると、精神的な負担が大きくなったり疲労しやすくなったりします。そのため、定期的にストレスを発散することが大切です。ストレスを発散するには、以下のような方法があります。
- 休息をしっかり取る
- 深呼吸をする
- リラックスしやすい環境を整える
- 趣味を楽しむ
- 適度な運動をする
- 友人や家族と話す
身体を休ませることはもちろん、気分転換をすることもストレス解消に効果的です。自分なりのストレス発散の方法を見つけ、適度にリフレッシュして、仕事への活力を得ましょう。
転職を検討する
職場の人間関係や給与への不満など、今の職場では解決しにくい悩みもあるでしょう。解決が難しい場合は、転職を検討するのもおすすめです。ただし、転職したからといってすべての悩みが解決するわけではありません。きついと感じた原因を解消できるような職場を見つけることが大切です。
たとえば、給与に不満があるケースでは、今より給与が高い職場に転職すれば解決するでしょう。しかし、手当の有無やみなし残業制などによっては、収入が減少する恐れもあります。高給与を目指す方は、基本給の金額だけでなく手当や将来的な昇給制度などを確認し、長期的な視点で求人を探しましょう。
登録は1分で終わります!
アドバイザーに相談する(無料)知的障がいがある方とコミュニケーションを取るコツ
前述したように、知的障害者施設で働くうえで、利用者さんとのコミュニケーションに悩むこともあるでしょう。ここでは知的障がいがある方とコミュニケーションを取るコツを紹介するので、ぜひご一読ください。
利用者さんの行動の理由を考える
利用者さんの行動には一つひとつ理由や原因があります。パニックを起こしてしまったり、意思疎通が難しかったりするときは、利用者さんに不安や不快だったことがないか聞いてみましょう。
文章で意見を伝えることができないことがあるので、単語から推察することも重要です。利用者さん本人の口から原因を聞けない場合は、そのときの利用者さんの様子だけでなく、状況や環境も含めて観察してみると良いでしょう。原因が分かれば、次から予防できる可能性があります。
具体的な言葉で伝える
知的障がいがある方は、「あれ」「これ」などの指示語が伝わりにくい場合があります。具体的な言葉でわかりやすく伝えることを意識して会話しましょう。たとえば、「今日はどんな服を着ますか?」という質問をしても意見を伝えられない可能性があります。「今日はこの赤い服と青い服、どちらを着ますか?」と実物を見せながら聞くことで、自分の好きなほうを選択することができ、利用者さんの要望を叶えられるでしょう。
ゆっくり丁寧に話す
言葉の理解や意思表示が苦手な人もいるので、ゆっくり急かさずに会話するように心がけましょう。こちらの話が伝わっていなさそうであれば、繰り返し伝えることも重要です。相手のペースに合わせて、時間をかけてコミュニケーションを取りましょう。
上から目線で話したり、高圧的な態度を取ったりしないようにすることも大切です。ゆっくり丁寧に話すことは有効ですが、その際、子どもへ接するような話し方はせず、対等に向き合う姿勢を持ちましょう。
一度に多くの情報を与えない
一度に多くの情報を与えないようにしましょう。内容が複雑になると理解が難しくなる人もいるので、1つずつ理解してもらうようにします。一度に情報を与えすぎると、混乱してしまったり、優先順位が分からなくなってしまったりすることもあるようです。
また、作業を行う場合も、1つの工程を覚えてから次の工程に入ってもらうようにして、本人のペースで習得できるように工夫すると良いでしょう。
言葉以外の方法も活用する
会話でのやり取りが苦手な方に対しては、イラストやメモ、ジェスチャーなどの視覚情報が有効な場合があります。さまざまなコミュニケーション手段を試して、利用者さんに合う方法を見つけてみてください。また、分かりにくい言葉があれば、利用者さん自身が分かる言葉に置き換えるのも効果的です。
知的障害者支援員についてよくある質問
ここでは、知的障害者支援員についてよくある質問に回答します。知的障害者支援員への転職を検討している方は、ぜひご覧ください。
知的障害者施設に向いていない人はどんな人?
価値観が固定されている人やマイペースな人、コミュニケーションが苦手な人、協調性がない人などは、知的障害者支援員に向いていないといえるでしょう。知的障害者施設では、突発的なパニックへの対応やこだわりが強い利用者さんへのケアをすることがあり、迅速かつ柔軟な対応が求められます。
この記事の「知的障害者施設の生活支援に向いている人の特徴」で、知的障害者施設に向いている人の特徴を解説しているので、ぜひご一読ください。
知的障害者施設の生活支援員になるのに資格は必要なの?
障がい者支援において資格は必須ではありません。しかし、障がい者福祉を行ううえで、「介護福祉士」や「社会福祉士」「強度行動障害支援者養成研修」「重度訪問介護従業者養成研修」などの資格を取得すると業務に役立つでしょう。
詳しくは、「【障がい者支援に役立つ資格一覧】取得方法や難易度、習得できるスキルは?」の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
まとめ
知的障害者施設で働く生活支援員は、利用者さんとのコミュニケーションの難しさや、仕事内容に給与が見合わないことなどをきついと感じるようです。きついこともあるかもしれませんが、支援法を考える楽しさや利用者さんやご家族から感謝されることにやりがいを感じられるでしょう。
知的障害者施設で働くことで、障がいへの理解が深まったり転職で有利になるスキルが身についたりといったメリットもあります。
知的障害者施設の支援員の仕事がきついときは、「障がいに関する知識を身につける」「上司や同僚に相談する」「公的な相談センターに相談する」「ストレスを発散する」などの対処法がおすすめです。今の職場での解決が難しい場合は、転職を検討するのも良いでしょう。
障がい支援を行いたいと考えている方は、「レバウェル介護(旧 きらケア)」へご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した転職エージェントです。障害者施設の求人も多数取り扱っており、希望の求人が見つかるでしょう。専任のキャリアアドバイザーが転職をサポートいたします。転職の悩みや不安もお気軽にご相談ください。
登録は1分で終わります!
アドバイザーに相談する(無料) 障害者施設の求人一覧はこちら
障害者施設の求人一覧はこちら