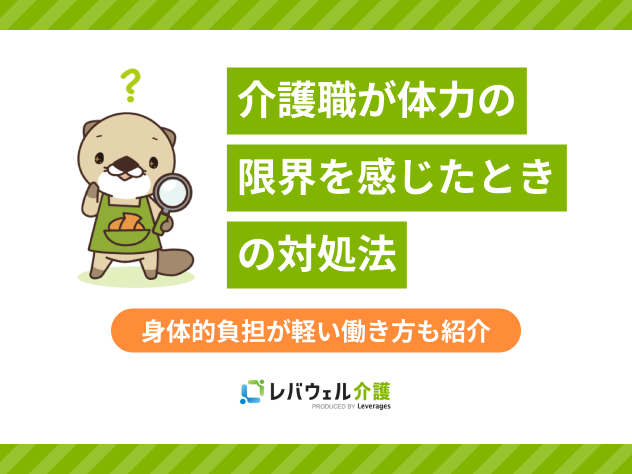
この記事のまとめ
- 多くの介護職員が「腰痛になりやすいなど身体的負担が大きい」と感じている
- 介護職が体力の限界を感じる理由には、力仕事が多いことなどがある
- 介護職で体力の限界を感じたときは、介助を行うときの姿勢を見直してみよう
介護職として働く方のなかには、「体力の限界かも…」と悩んでいる方もいるでしょう。「体力的にきつそう」というイメージから、介護職への転職を迷っている方もいるかもしれません。勤務先によって違いはあるものの、介護職の仕事は一定の大変さがあります。本記事では、介護職で体力的な負担を感じる理由と具体的な対策をまとめました。体力的な負担が少ない職場を選ぶ方法などもご紹介するので、チェックしてみてください。
介護士ってどんなお仕事?仕事内容や働き方、必要な資格、給与などを解説体力的にきついと感じる介護職員は多い
Leverages Medical Care「きらケア介護白書2022(p.11)」で、「介護の仕事で大変だと感じること」を調査したところ、下記のような結果になりました。
引用:Leverages Medical Care「きらケア介護白書2022(p.11)」
アンケート結果によると、58.7%の介護職員が「腰痛になりやすいなど身体的負担が大きい」と回答しています。半数以上の介護職員が、身体的な負担を感じているようです。
また、厚生労働省の「業務上疾病発生状況等調査(令和5年)業務上疾病発生状況(業種別・疾病別)」によると、介護職を含む「保健衛生業」において、負傷に起因する疾病2,403件のうち、腰痛(災害性腰痛)は2,194件とあります。次に腰痛が多い業種は、「商業・金融・広告業」の1,229件なので、介護職の腰痛は、かなり多い傾向にあるようです。
出典
Leverages Medical Care「介護士のキャリアや外国人雇用などに関するレポート「きらケア介護白書2022」を公開しました」(2024年11月13日)
厚生労働省「業務上疾病発生状況等調査(令和5年)」(2024年11月13日)
今の職場に満足していますか?
▼関連記事
介護の仕事に疲れてもう辞めたい…疲れたときの対処方法
介護職が体力の限界を感じる理由
介護職が体力の限界を感じる理由は、「身体介護などの力仕事が多い」「夜勤で生活リズムが乱れやすい」「1人あたりの業務量が多い」などがあります。下記では、介護職が身体的な大変さを感じる理由をまとめました。
身体介護などの力仕事が多い
介護職の体力の限界を感じるのは、力仕事が多いためでしょう。介護職員は移乗介助や入浴介助、排泄介助などの際、利用者さんを支えたり抱え上げたりします。自分より身長が高い方や体重が重い方の介助に入ることもあり、ある程度の筋力や体力が必要です。身体介助をはじめとする力を必要とする仕事は1日に何度も行うため、次第に疲労が溜まり、「体力が限界」と感じることがあると考えられます。
夜勤で生活リズムが乱れやすい
介護職は生活リズムが乱れやすい勤務形態なのも、身体的な大変さを感じる要因となっているようです。利用者さんを24時間ケアする入所施設に勤務する介護職員は、日勤のほかに夜勤があるのが一般的。シフトによって、昼間に働く日や夜間に働く日があるため、生活リズムが乱れやすい傾向にあります。また、2交代制の夜勤は、労働時間が約16時間と長時間になることもあり、疲労が蓄積されやすいようです。
1人あたりの業務量が多い
介護職は業務量の多さから、身体的な大変さを感じることもあるようです。特に人手不足の職場では、利用者さんの身体介護やご家族への対応、レクリエーションの準備、事務作業など幅広い業務を任されることも。職員1人ひとりが抱える業務量が多くなり過ぎると、体力的な負担も大きくなります。
職場によって休日出勤や残業がある
休日出勤や残業が多いと、「体力がもたない」と感じやすくなります。人手不足によりギリギリの人数でシフトを回している職場の場合、急な欠勤者が出た際に、休みの職員が代わりに出勤することがあるようです。また、介護職は利用者さんの生活を支える仕事をしているため、翌日に持ち越せない業務が多く、時間外労働になることも。十分な休息ができないと、疲れやストレスが溜まってしまいます。
精神的な疲れが身体的な不調につながっている
精神的ストレスによって、倦怠感などの体調の不調が起こることがあります。介護職は人との関わりが多いため、人間関係に悩みやすい傾向にあるようです。1人ひとり異なる価値観を尊重しながら、良好な人間関係を築くには気を遣うことが多いでしょう。人によっては、「周囲に気を使い過ぎて疲れてしまう」こともあるようです。
年齢による体力の衰え
年齢が上がるにつれて、体力の衰えを感じる方は少なくありません。スポーツ庁ホームページの「II調査結果の概要(p.11)」には、「男女ともに体力は加齢に伴い低下していく」との記載があります。前述したように、介護職は身体介護などの体力を使う場面が多いため、年齢を重ねるにつれて体力の低下を実感し、介護の仕事を続けていくことに不安を感じる方もいるようです。
出典
スポーツ庁ホームページ「令和5年度体力・運動能力調査結果の概要及び報告書について」(2024年11月13日)
▼関連記事
介護職がつらいと感じる理由は?悩みや不満の対処法、転職の判断基準を解説
介護職で体力の限界を感じたときの対処法
介護の仕事で体力の限界を感じたら、介護技術を身につけたり、先輩や上司に相談したりすると良いでしょう。ここでは、介護職で体力の限界を感じたときの対処法を7つ紹介します。
1.介護技術を身につける
疲労や腰痛の要因の一つとして、無理な姿勢での動作があります。適切な介護技術を見つけることで、身体介護などによる身体への負担を減らせるでしょう。
身体への負担を減らす介助方法を身につけるには、「ボディメカニクス」がおすすめです。ボディメカニクスとは、力学原理を活用した介護技術のこと。ボディメカニクスを取り入れることで、介護職員だけでなく、利用者さんの身体的負担も軽減できます。
ボディメカニクスに興味のある方は、「介護技術の基本!現場で役立つボディメカニクスの知識を身につけよう」の記事もご覧ください。
2.介護職の先輩や上司に相談してみる
仕事で悩んだら、先輩や上司に相談してみるのも一つの手です。先輩や上司も、過去に似たような悩みを抱えていたことがあるかもしれません。相談することで、介助の際の身体の使い方や業務効率を上げる仕事の仕方など、実用的なアドバイスをもらえる可能性があります。
3.福祉用具や介護ロボットを活用する
福祉用具や介護ロボットの活用により、介護職員の業務負担の軽減と安全性の高い介護の提供ができます。介護ロボットにはさまざまな種類がありますが、身体的負担を軽減するには、移乗介助ロボットの活用が効果的でしょう。
とはいえ、介護ロボットは導入コストの問題などから、普及が進んでいないのが実情のようです。厚生労働省の「【介護ロボットの導入・活用支援策】のご紹介」によると、「介護ロボット導入支援事業」として、介護ロボットの導入支援として補助金の交付を行っています。介護ロボットで労働環境の改善が期待できる場合には、施設長に導入を打診してみると良いでしょう。
出典
厚生労働省「介護ロボットの開発・普及の促進」(2024年11月13日)
4.体力づくりやストレッチをする
介護職は無理な姿勢を保たなければならない場面があり、それが、腰痛や筋肉痛の原因となることがあります。無理な姿勢をとったことによる身体的な不調がある場合には、ストレッチをすると、効果的なようです。
また、筋トレなどで筋力を鍛えると、腰痛を予防したり、疲れにくくなったりするなどの効果も。介護職員は、無理のない範囲でストレッチや体力づくりをすると良いでしょう。
5.勤務時間や日数などシフトを調整してもらう
「夜勤に入ると体調を崩してしまう」「腰痛で入浴介助がつらい」という場合は、一度上司や管理者に相談してみましょう。職場によっては、夜勤回数を減らしたり、部署移動をしたりするなどの対応をしてくれることがあります。無理して働き続けると、体調の悪化により介護職として働けなくなるリスクが高くなってしまうので、早めに相談してみることをおすすめします。
6.デスクワークがメインの職種へキャリアアップする
身体介護などによる身体的負担を軽減するには、デスクワークがメインの職種にキャリアアップするのも方法の一つです。介護職からキャリアアップできるデスクワークメインの職種には、「ケアマネジャー」と「生活相談員」があります。職場によって業務範囲は異なるものの、管理業務が中心になるため、身体介護による身体的な負担は軽くなるでしょう。
下記では、ケアマネジャーと生活相談員について解説します。
ケアマネジャー(介護支援専門員)
ケアマネジャーの役割は、介護が必要な方が適切な介護を受けられるように、介護施設や医療機関へ繋げたり、ケアプランを作成したりすることです。書類作成や相談業務が主な仕事になるでしょう。介護職員としての経験が活かせるため、介護職員からキャリアアップする方が多くいます。
ケアマネジャーになるには、「介護支援専門員実務研修受講試験への合格」と「介護支援専門員実務研修の修了」が必要です。介護支援専門員実務研修受講試験を受けるには、「介護福祉士などの国家資格に基づく業務に5年以上従事していること」などが求められます。
詳しく知りたい方は、「ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどんな仕事?業務内容や役割を解説!」を参考にしてみてください。
生活相談員
生活相談員は、特別養護老人ホーム(特養)などの介護施設で、利用者さんやご家族の相談ごとに対応したり、入退所時の契約手続きをしたりします。職場によっては介護業務を行うことがありますが、相談対応が主な仕事です。
生活相談員の要件は自治体ごとに定められており、基本的に「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」のいずれかが求められる傾向にあります。ただし、介護福祉士としての実務経験があれば、生活相談員として働けるなど、自治体によって要件は異なるので、事前の確認が必要です。
生活相談員に興味のある方は、「生活相談員とは?未経験者向けに仕事内容や資格要件、やりがいを解説!」をご覧ください。
7.体力的な負担が少ない職場への転職を検討する
業務量や勤務日数が減らせないなど、今の職場で状況が改善する見込みのないときは、思い切って体力的な負担の少ない職場への転職を検討しても良いでしょう。自分の体調に合った働き方ができる職場に転職できれば、身体的な負担を軽くできます。
次項では、体力的な負担が少なめの職場の特徴をご紹介しているので、参考にしてみてください。
▼関連記事
介護職をやってられないときの解決策や転職先の選び方を解説!
体力的な負担が少ない介護職の転職先
ここでは、体力的な負担が比較的少ない職場を紹介します。転職を検討している方は、参考にしてみてください。
デイサービス
デイサービスとは、主に自宅で生活している方が、日帰りで介護サービスを受けられる通所施設です。動ける利用者さんが多い傾向にあるため、身体介護による負担は軽いでしょう。また、夜勤がないため、生活リズムを安定させやすいのもメリットです。
デイサービスの仕事内容については、「デイサービスの仕事内容は?介護職の役割と1日の流れを解説」で紹介しています。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢の方を対象にしたバリアフリーの賃貸住宅で、「サ高住」とも呼ばれています。サ高住には、「一般型」と「介護型」があり、それぞれ提供するサービスが異なるのが特徴です。このうち、一般型の主な提供サービスは、「安否確認」と「生活相談への対応」なので、業務による身体的負担が軽いでしょう。ただし、職場によって業務内容は異なるので、転職の際は事前に調べることが大切です。
サ高住に興味のある方は、「サ高住の仕事内容とは?働くために必要な資格や向いている人なども解説!」を参考にしてみてください。
訪問介護事業所
訪問介護事業所では、訪問介護員が介護を必要とする方の自宅を訪問し、生活援助や身体介護を行います。訪問介護員は、基本的に1人で訪問してサービスを提供するため、一定の大変さはありますが、自分のペースで仕事ができるのがメリットです。また、一般的な訪問介護事業所は日勤のみなので、体調面の調整もしやすいでしょう。
訪問介護事業所の仕事内容を知りたい方は、「訪問介護とは?仕事内容や必要な資格、働くメリットをわかりやすく解説」をご覧ください。
介護職が体力的な負担を軽減しやすい働き方
ここでは、体力的な負担を軽減しやすい働き方を紹介します。前項とあわせて、参考にしてみてください。
日勤のみで働く
日勤のみのシフトなら、生活リズムが乱れにくいため、夜勤をともなうシフトよりも体力的な負担を減らせるでしょう。先述したような、デイサービスや訪問介護事業所は、基本的に日勤のみで働けます。
しかし、入所施設の正社員は、1ヶ月間の夜勤回数が決まっていることが多いようです。入所施設で日勤のみのシフトで働きたい場合は、夜勤に入れないことを事前に伝えておく必要があるでしょう。また、パートやアルバイトなど、雇用形態の幅を広げれば、柔軟なシフトで働ける可能性が高まります。
▼関連記事
夜勤ができないと介護の仕事は難しい?自分に合った働き方ができる職場の種類
夜勤専従で働く
夜勤専従とは、夜勤のみのシフトで働く雇用形態です。夜間に働くという一定の大変さはありますが、日勤と夜勤のシフトに交互に入るよりも、生活リズムが乱れにくいでしょう。「夜勤は苦ではないが、生活リズムが乱れるのがきつい」という方に向いています。
なお、夜勤に入ると夜勤手当や深夜手当が支給されるため、日勤で同じ時間働くよりも、効率的に給与アップが目指せるというメリットもあります。
夜勤専従の働き方に興味のある方は、「介護の夜勤専従は楽?きつい?仕事内容とメリット、デメリットを解説」をチェックしてみてください。
【転職支援事例】60代で体力が不安…負担が少ない職場探し
下記では、レバウェル介護(旧 きらケア)で、転職した60代後半・経験者の方への支援事例を紹介します。
求職者さまの希望条件は日勤のみ・週3日程度で勤務できるパートのお仕事でした。この先も長く働くことを考えて、体力に過度な負担がかかる業務は避けたいというご要望がありました。
キャリアアドバイザーは、求職者さまが対応できる介護業務と対応が難しい介護業務を確認し、条件に合った求人先へ相談をしました。いくつかの介護施設へ連絡をしたところ、「うちなら介護度1~2の方がメインのユニットに配属できますよ」と、相談に応じてくれる施設が見つかりました。さらに、その施設は入浴介助も2名体制で行うよう業務に融通を利かせてくれたのです。最終的に、求職者は体力的に無理なく働ける転職先を見つけることができました。介護業界に特化した転職エージェントのレバウェル介護(旧 きらケア)では、「身体介護の負担を減らしたい」「業務にこういう配慮をしてほしい」といった、希望条件をヒアリングしたうえで、あなたに合った職場の求人をご提案いたします。求人先の情報収集をこまめに行っているため、求人票だけでは分かりにくい職場環境の情報の提供も可能です。
介護職の身体的負担に関するよくある質問
大変?」「介護の仕事の疲れが取れない」という方は、チェックしてみてください。
介護職の仕事は年齢を重ねて体力が落ちると大変?
年齢を重ねるごとに体力は低下していく傾向にあるため、介護職を続けることを不安に思っている方は一定数います。しかし、業務内容の見直しや介助のテクニックの取得などで、体力面をカバーすることが可能です。
公益財団法人 介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査:労働者調査(p.12~p.13)」によると、介護職で最も多い年齢帯は「45~49歳」で15.2%とあります。続いて、「50~55歳」が14.5%、「40~45歳」は12.8%、「55~60歳」は12.3%です。年齢を重ねても、介護職で活躍している方は多くいます。体力に自信がなければレクリエーションの企画や運営、施設の運営に携わるのも手。自分の体力に見合った職場を探している方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。
出典
公益財団法人 介護労働安定センター「介護労働実態調査」(2024年11月13日)
介護職で仕事の疲れが取れないときはどうすれば良い?
仕事の疲れが取れないと感じたときは、介助をする際の姿勢を見直してみると良いでしょう。身体に負担がかかる姿勢で、介助をしているのかもしれません。適切な姿勢で介助を行うことで身体の負担を軽減し、腰痛の予防もできます。また、ストレッチや筋トレをすることも有効です。
「仕事の疲れが取れない」という方は、この記事の「介護職で体力の限界を感じたときの対処法」も参考にしてみてください。
介護職に体力づくりは必要?
利用者さまの入浴介助や移乗介助といった身体介護を行うには、一定の筋力が必要です。適度な筋トレによる体力づくりをすることで、安心感のある介護を行えるようになるでしょう。筋力をつけることで、腰痛の予防にもなります。「介護職の体力づくりって何をしたら良いの?」という方は、「介護職も筋トレしよう!介護の仕事に筋肉が必要な理由とおすすめメニュー」をご覧ください。
まとめ
Leverages Medical Care「きらケア介護白書2022(p.11)」で「介護の仕事で大変だと感じること」を調査したところ、「腰痛になりやすいなど身体的負担が大きい」と答えた介護職員は58.7%と、半数以上にも上りました。
介護職員が身体的に疲労を感じる主な理由は、身体介護による力仕事があることや夜勤で生活リズムが乱れやすいことなどがあります。対処法は、身体的負担を軽くする介護技術を身につけることや体力づくり・ストレッチをすることなど。自分に合った方法で、対処することが大切です。
「体力に限界を感じているけど、介護の仕事は続けたい」「体力の負担が少ない職場に転職したい」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。介護業界の転職事情に詳しいキャリアアドバイザーが、希望のキャリアビジョンや働き方をヒアリングしながら、あなたに合った職場をご提案いたします。求人サイトには記載されていない求人も豊富に扱っているので、「求人サイトに希望条件に合った求人がない」という場合でも、条件に合った求人に出会えるかもしれません。サービスはすべて無料なので、お気軽にお問い合わせください。
今の職場に満足していますか?
 訪問介護の求人一覧ページはこちら
訪問介護の求人一覧ページはこちら