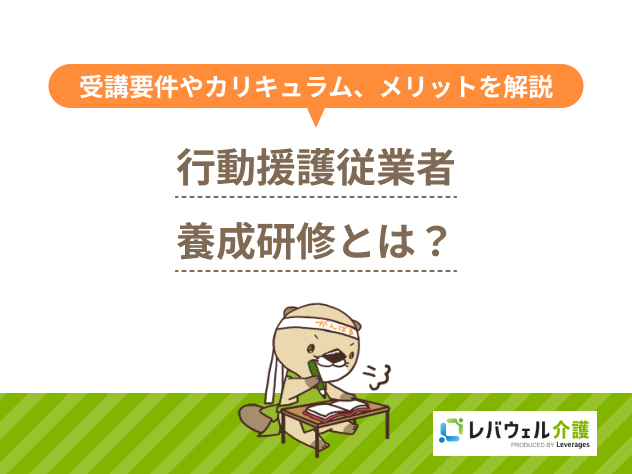
この記事のまとめ
- 行動援護従業者養成研修とは、行動援護に必要な知識や技術を学ぶ講座
- 行動援護従業者養成研修のカリキュラムは、講義10時間と演習14時間
- 行動援護従業者養成研修を取得するメリットは、障がい者支援に活かせること
「行動援護従業者養成研修ってどんな資格なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。行動援護従業者養成研修は、行動障がいのある方の外出を支援するための資格です。この記事では、行動援護従業者養成研修の概要や、行動援護の仕事について解説します。研修の申し込み方法や取得するメリット、活かせる職場もまとめました。行動援護の仕事に興味がある方は、ぜひご一読ください。
介護資格の種類31選!取得方法やメリットを解説します行動援護従業者養成研修とは?
行動援護従業者養成研修とは、行動援護に従事するために必要な資格です。知的障がいもしくは精神障がいがあり、行動するうえでの困難やリスクを抱える方に対し、適切な支援を行うための知識や援護技術を学べます。
厚生労働省の「行動援護に係る報酬・基準について≪論点等≫(p.1)」によると、行動援護従業者として働くには、行動援護従業者養成研修もしくは強度行動障害支援者養成研修(実践研修)の修了と、知的障がいや精神障がいがある方の支援に直接従事した実務経験が必要です。ヘルパーは1年以上、サービス提供責任者は3年以上従事することで要件を満たせます。
厚生労働省の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(p.26)」によると、2027年3月31日までは、資格要件の経過措置が適用されるようです。そのため、介護福祉士・実務者研修・介護職員基礎研修などを修了しており、所定の実務経験があれば、行動援護に携われます。
出典
厚生労働省「第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年11月18日)
厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」(2024年11月18日)
▼関連記事
サービス提供責任者に資格は必要!要件と取得方法、サ責の仕事内容を解説
働きながら資格を取る方法教えます
▼関連記事
【障がい者支援に役立つ資格一覧】取得方法や難易度、習得できるスキルは?
行動援護とは?
行動援護とは、知的障がいもしくは精神障がいがあり、行動に困難や危険が伴う方が利用できる支援です。主に、外出の介助や身の回りのお世話、利用者さん本人や周囲の人の危険を回避するための支援などを行います。
行動援護は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。障がいのある方が社会や地域から孤立せず、基本的人権が尊重された生活を送れるよう、専門的な立場からサポートします。
行動援護の対象者
行動援護の対象者は、「障害支援区分3以上」「障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上」という2つの条件を満たす方です。また、同等の支援が必要と判断されれば、障がいのある子どもも利用できます。
行動関連項目等は、「コミュニケーション」「大声・奇声を出す」「他人を傷つける行為」などに関する支援の必要性についての基準で、0点、1点、2点の3段階で評価する仕組みです。
出典
厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2024年11月18日)
厚生労働省「第1回「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(オンライン開催)」資料」(2024年11月18日)
行動援護のサービス内容
行動援護従業者が提供する主なサービスは、以下のとおりです。
- 外出先での移動介助
- 行動に伴う危険を回避するための援護
- 排泄介助や食事介助など、行動するために必要な介護
行動援護では、利用者さんが安全に外出できるよう、移動に伴う介助を行います。外出中は、利用者さんが苦手とする音やシチュエーションに遭遇して不安を感じないよう、状況の説明や移動ルートの選択をする「予防的対応」を実施。もしも、利用者さんに行動障がいが見られた場合は、適切に対処する「制御的対応」を取ります。また、「身体介護的対応」として、排泄介助や食事介助、更衣介助なども行うようです。
行動援護のサービス対象外の援助
行動援護は、通勤や通学など、通年かつ長期的な外出を目的とした利用はできません。ギャンブルや飲酒など、障害福祉サービスで対応するのに適さない目的の外出も、サービス対象外です。
なお、1日に利用できる行動援護の回数や、1回の利用時間には制限があります。移動支援の併用の可否やサービス範囲などは、自治体ごとに異なるので、事前の確認が必要です。
行動援護従業者養成研修の概要
ここでは、行動援護従業者養成研修の概要を解説します。資格要件やカリキュラム、取得費用などをまとめたので、受講を検討している方は参考にしてみてください。
受講要件
行動援護従業者養成研修には、受講要件がありません。そのため、資格や実務経験がなくても受講可能です。年齢制限も設けられていないので、学生からシニアの方まで幅広い世代の方が挑戦できます。
研修のカリキュラム
行動援護従業者養成研修のカリキュラムは、10時間の講義と14時間の演習で構成されています。基本的に修了試験はないため、カリキュラムを履修すると同時に、行動援護従業者養成研修を取得可能です。
以下では、千葉県の「行動援護従業者養成研修:実施要綱」を参考に、具体的な科目を紹介します。
| 区分 | 科目 | 時間数 |
| 講義 | 強度行動障害がある者の基本的理解 | 1時間30分 |
| 講義 | 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識 | 5時間 |
| 講義 | 強度行動障害のある者へのチーム支援 | 3時間 |
| 講義 | 強度行動障害と生活の組み立て | 30分 |
| 演習 | 基本的な情報収集と記録等の共有 | 1時間 |
| 演習 | 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解 | 3時間 |
| 演習 | 行動障害の背景にある特性の理解 | 1時間30分 |
| 演習 | 障害特性の理解とアセスメント | 3時間 |
| 演習 | 環境調整による強度行動障害の支援 | 3時間 |
| 演習 | 記録に基づく支援の評価 | 1時間30分 |
| 演習 | 危機対応と虐待防止 | 1時間 |
参考:千葉県「行動援護従業者養成研修:実施要綱」
重度訪問介護従業者養成研修(行動障害支援課程)修了者もしくは、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者は、講義や演習の一部が免除になる可能性があります。
講義の内容
講義の主な目的は、行動援護に関する基本的な知識と技術の習得です。たとえば「強度行動障害がある者の基本的理解」では、行動障がいの定義や、知的障がい精神障がいに関する基本的な知識を学びます。
講義で一番多くの時間を割く「強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識」は、制度や支援の枠組み、アセスメント票や支援手順書に対する理解を深める科目です。「強度行動障害のある者へのチーム支援」では、行動障がいのある方をチームや地域で支援する重要性を学びます。
演習の内容
演習は、実際の援護を想定した実践的な学習が中心です。行動障がいがある方とのコミュニケーション方法や、障がい特性のアセスメント、危機対応の方法など、行動支援の技術を身につけます。
受講先の自治体によって研修カリキュラムの免除規定が異なるため、申し込みの際に確認してみましょう。
出典
千葉県「障害福祉に関する研修」(2024年11月18日)
受講費用の相場
行動援護従業者養成研修の受講料は、3~5万円程度が相場です。資格スクールによって受講費用には幅があるため、事前に調べておきましょう。カリキュラムは厚生労働省の基準に沿って構成されるため、受講費用の差によって学習内容が大きく変わることはありません。
なお、職場によっては、資格取得の費用を補助してもらえる可能性があります。介護や福祉の仕事に携わっている方は、勤務先の資格取得支援制度の有無や対象資格などを確認してみると良いでしょう。
▼関連記事
介護職の資格取得支援制度とは?給付金の種類や利用するメリットを解説
取得に必要な期間
行動援護従業者養成研修は、3~5日程度で取得可能です。土日祝日の講座コースがあったり、欠席した場合の振替に対応していたりするスクールもあるので、自分に合った講座を選びましょう。
申し込み方法
行動援護従業者養成研修は、Webサイトや電話、郵送などで受講を申請します。申込書は、Webサイトからダウンロードするほか、資料請求をすることでも入手可能です。申込書を入手したら、必要事項を記入して手続きを行いましょう。
受講先については、インターネットで「行動援護従業者養成研修 都道府県」で検索すると、候補が見つかります。受講日程や費用、手続き方法などをご確認のうえ、無理なく全日参加できる講座を選んでみてください。
なお、科目免除を希望する場合、修了証明書の写しが求められるので、受講先の指示に従って提出しましょう。
行動援護従業者養成研修と強度行動障害支援者養成研修の違い
「行動援護従業者養成研修」と「強度行動障害支援者養成研修」は、受講の目的やカリキュラムの構成が異なります。前述のとおり、行動援護従業者養成研修は、行動援護に携わるための資格です。24時間のカリキュラムで、専門的なスキルを習得できます。
一方、強度行動障害支援者養成研修は、強度行動障がいのある方の支援に携わる方が、必要な知識を身につけるための資格です。基礎研修と実践研修の2段階に分かれており、基礎研修を修了すれば実践研修を受講できます。基礎研修の学習内容は、行動障がいに関する基本的な知識や支援技術です。実践研修では、アセスメントや支援手順書の作成について学びます。基礎研修と実践研修を合わせた時間数は24時間です。
なお、「行動援護従業者養成研修」と「強度行動障害支援者養成研修」の標準カリキュラムは共通。強度行動障害支援者養成研修の基礎研修と実践研修を修了すれば、行動援護従業者養成研修を取得した場合と同じ扱いになります。そのため、どちらを取得すべきか迷う場合は、資格取得の目的やスケジュールなどを考えて選ぶと良いでしょう。
出典
厚生労働省「強度行動障害支援者養成研修事業の実施について(運営要領)」(2024年11月18日)
行動援護従業者養成研修を活かせる職場
行動援護従業者養成研修を取得すると、居宅系の障害福祉サービス事業所のほか、以下のような職場でも活躍できます。
- 障害者支援施設
- 障害者グループホーム
- 障害者福祉サービス事業所
- 放課後等デイサービス
行動援護従業者養成研修の資格は、障がい者施設の仕事にも活かせます。障がいのある方が何に不安を抱えているのか、どのような支援が必要なのかを理解していれば、気持ちに寄り添ったケアができるでしょう。
行動援護従業者養成研修を取得するメリット
行動援護従業者養成研修を取得するメリットは、障がい者支援を提供する職場で広く活躍できることです。
厚生労働省の「障害福祉行政の最近の動向(p.2)」によると、知的障がいのある方は約109万4,000人、精神障がいのある方は約614万8,000人で、増加傾向にあります。知的障がいや精神障がいがある方に対する支援のニーズは高いため、行動援護従業者養成研修を修了していると、即戦力として働けるでしょう。
また、行動援護従業者養成研修は、特定事業所加算の対象となる資格です。そのため、障害福祉サービス事業所への就職・転職に有利に働く可能性があります。資格を取得するとさまざまなメリットがあるので、興味がある方は受講を検討してみてくださいね。
出典
厚生労働省「障害福祉行政の最近の動向(令和6年度報酬改定を中心に)」(2024年11月18日)
出典
厚生労働省「第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年11月18日)
行動援護従業者養成研修についてよくある質問
ここでは、行動援護従業者養成研修についてよくある質問に回答します。受講方法やサービスについてを知りたい方は、確認してみてください。
行動援護従業者養成研修はオンラインで受講できますか?
行動援護従業者養成研修は、完全オンラインで受講できる資格スクールがあります。そのほか、通学とオンラインを組み合わせた講座も。オンライン受講を選んでも、取得条件が変わることはないので、自分に合った講座を選択してみてください。
行動援護と同行援護の違いは?
行動援護と同行援護の大きな違いは、支援対象者です。行動援護は知的障がいやある方や精神障がいがある方が対象ですが、同行援護は視覚障がいがある方を対象となっています。また、援護対象者の基準など、制度上の違いもあるでしょう。
行動援護従業者とガイドヘルパーの違いは?
行動援護従業者とガイドヘルパーの違いは、担当する支援の範囲です。ガイドヘルパー(移動介護従事者)とは、障がいがあり1人で外出するのが難しい方を対象に、外出に必要な支援を行う職種全般を指します。行動障がいのある方の外出に関する支援をする「行動援護従業者」は、ガイドヘルパーの分類の一つです。ガイドヘルパーの詳細は、「ガイドヘルパー(移動介護従事者)とは?必要な資格や仕事内容を解説」の記事にまとめているので、気になる方はぜひご覧ください。
まとめ
行動援護従業者養成研修とは、知的障がいや精神障がいがあり、1人で行動するのが難しい利用者さんを支援するための資格です。障がいに関する専門的な知識や援助技術を学べます。
行動援護の仕事をするには、行動援護従業者養成研修を修了する以外にも、実務経験を積まなければなりません。行動援護サービスとして外出介助を行うだけではなく、行動障がいをを防いだり、適切に対処したりするのも、行動援護従業者の役割です。
行動援護従業者養成研修は、10時間の講義と14時間の演習から構成されます。一般的に修了試験はないので、すべてのカリキュラムを履修することで取得可能です。障がいのある方の支援に活かせる資格なので、興味がある方は取得を検討してみましょう。
「障がい者支援の仕事に興味がある」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護・福祉業界に特化した転職エージェント。障害者支援施設・事業所の求人を多く保有しています。資格やスキルを活かせる職場をご紹介することも可能です。サービスはすべて無料なので、まずは気軽にご利用ください。
働きながら資格を取る方法教えます
 障がい者施設の求人一覧はこちら
障がい者施設の求人一覧はこちら