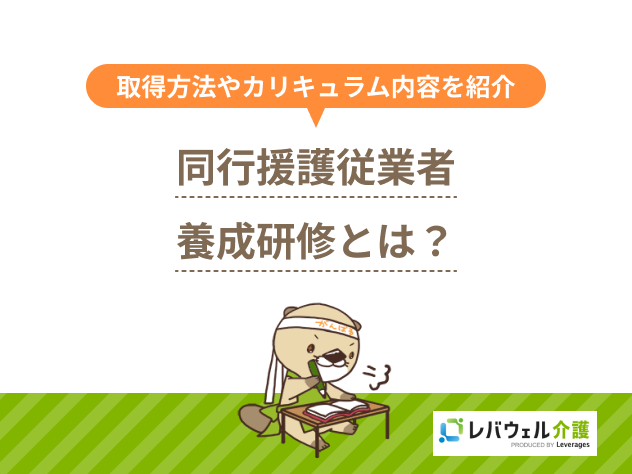
この記事のまとめ
- 同行援護従業者養成研修は、視覚障がいがある方に対する移動支援を学ぶ資格
- 同行援護従業者養成研修は、一般課程と応用過程の2段階に分かれている
- 同行援護従業者養成研修を取得するメリットは、仕事の幅が広がることなど
「同行援護従業者養成研修ってどんな資格なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。同行援護従業者養成研修は、視覚障がいのある方の移動支援に必要な資格で、障害福祉の分野で活躍したい方におすすめです。この記事では、同行援護従業者養成研修の概要を、一般課程と応用課程に分けて解説します。取得のメリットや活躍できる職場も紹介するので、参考にしてみてください。
介護資格の種類31選!取得方法やメリットを解説します同行援護従業者養成研修とは?
同行援護従業者養成研修とは、同行援護を行うために必要な資格で、視覚障がいの特性や外出支援の技術を学べます。同行援護従業者養成研修は、「一般課程」と「応用課程」の2段階です。
一般課程では、視覚障がいがある方に関する基礎知識を習得したり、移動支援の技術を身につけたりします。同行援護従業者養成研修の一般課程を修了することで、同行援護に従事可能です。また、「居宅介護職員初任者研修の修了+直接処遇経験1年以上」といった要件を満たすことでも、同行援護のヘルパーとして働けます。
応用課程は、一般課程で学んだ内容から発展し、より実践的な援護スキルや個別支援計画に関する内容がメインです。同行援護のサービス提供責任者として働くには、応用課程を修了する必要があります。応用課程の修了に加え、介護福祉士の取得や実務経験といった要件を満たすことで、同行援護のサービス提供責任者として従事可能です。
出典
厚生労働省「第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年11月18日)
厚生労働省「社会保障審議会障害者部会(第142回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)合同会議の資料について」(2024年11月18日)
働きながら資格を取る方法教えます
▼関連記事
【障がい者支援に役立つ資格一覧】取得方法や難易度、習得できるスキルは?
同行援護とは?
同行援護とは、視覚障がいがあり、1人で外出するのが難しい利用者さんに同行し、必要な手助けを行うことです。利用者さんの歩行を介助したり、周囲の情報を口頭で伝えたりして、移動を支援します。
同行援護のサービス内容
同行援護では、視覚障がいのある方の外出に必要な支援を行います。主なサービス内容は、以下の4つです。
- 移動介助
- 視覚的情報の提供や代読・代筆による移動の支援
- 外出時に必要な排泄介助
- 外出時に必要な食事介助
移動介助では、歩道や階段、混雑地など、町中を歩く際の危険を考慮したサポートを行います。
また、公共交通機関を利用するときに時刻表を代読したり、お店で商品を予約するときに名前を代筆したりなど、外出に伴う支援もサービスの一環です。外出先で食事を取る場合やトイレを利用する場合は、イスや手すりに案内するなど、不慣れな場所で困らないよう利用者さんを介助します。
同行援護のサービス対象外の援助
同行援護のサービスは、通勤や通学など、通年かつ長期的な外出には利用できません。公的な福祉サービスなので、ギャンブルや飲酒を目的とした外出もサービス対象外です。
また、外出準備に対する援助などの自宅での介助も、基本的には同行援護サービスの対象外です。外出以外に介助が必要な利用者さんは、居宅介護などのサービスを併用することになります。
同行援護とほかの障がい者支援サービスの違い
障がいのある方の移動を支援するサービスとして、「行動援護」や「ガイドヘルプ」もあります。同行援護とほかのサービスの違いを、以下で確認してみましょう。
行動援護との違い
同行援護と行動援護の主な違いは、支援の対象者です。同行援護は、視覚障がいのある方が対象なのに対し、行動援護は、知的障がいのある方と精神障がいのある方を対象としています。
行動援護では、行動するうえで困難があり常時介護が必要な方に対し、危険を回避するための支援や外出時の介護を行います。詳しくは、「行動援護従業者養成研修とは?受講要件やカリキュラム、メリットなどを解説」をご参照ください。
ガイドヘルプの違い
同行援護とガイドヘルプの違いは、支援対象者の範囲です。同行援護は視覚障がいがある方の支援を指すのに対して、ガイドヘルプは、障がいがある方の移動に関する支援全般を指します。
ガイドヘルプには、障害福祉サービスとして全国で提供される同行援護や行動援護のほか、地域生活支援事業として市区町村が提供する移動支援のサービスも含まれるようです。ガイドヘルパーについては「ガイドヘルパー(移動介護従事者)とは?必要な資格や仕事内容を解説」の記事にまとめているので、参考にしてみてください。
出典
厚生労働省「第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年11月18日)
同行援護従業者養成研修のカリキュラム
同行援護従業者養成研修は、厚生労働省が必修科目を定めているので、どのスクールを選んでも、基本的なカリキュラムは共通です。
ここでは、同行援護従業者養成研修の一般課程と応用課程のカリキュラムを解説するので、受講を検討している方は、参考にしてみてください。
一般課程
同行援護従業者養成研修の一般課程では、同行援護を行うために必要な知識や技術を学びます。基本的に修了試験はないため、全カリキュラムを履修することで、同行援護従業者養成研修の一般課程を取得できます。
受講要件
一般課程に受講要件はありません。実務経験がなくても受講できるため、障がい者支援に関する資格を初めて取得する方にもおすすめの資格です。
学習内容
同行援護従業者養成研修の一般課程は、合計20時間のカリキュラムで、講義と演習があります。厚生労働省の「同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について(p.2)」によると、具体的な科目は下記のとおりです。
| 区分 | 科目 | 基本時間数 |
| 講義 | 視覚障害者(児)福祉サービス | 1時間 |
| 講義 | 同行援護の制度と従業者の業務 | 2時間 |
| 講義 | 障害・疾病の理解(1) | 2時間 |
| 講義 | 障害者(児)の心理(1) | 1時間 |
| 講義 | 情報支援と情報提供 | 2時間 |
| 講義 | 代筆・代読の基礎知識 | 2時間 |
| 講義 | 同行援護の基礎知識 | 2時間 |
| 演習 | 基本技能 | 4時間 |
| 演習 | 応用技能 | 4時間 |
参考:厚生労働省「同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について(p.2)」
「障害・疾病の理解(1)」の科目などで、視覚障がいの特性や関係する疾患について学びます。講義で同行援護に必要な基礎知識を習得した後は、「基本技能」「応用技術」の演習で、基本的な移動支援の技術を身につけます。
受講費用の相場
一般課程の受講料は、2万5,000~4万円程度が相場です。受講先の資格スクールや自治体によって受講費用には幅があるので、事前に調べてみましょう。
取得に必要な期間
一般課程の日程は、3~4日程度で組まれている場合が多いようです。受講先によっては、土日のみの研修参加が可能だったり、欠席した場合に振替講義を行っていたりすることもあります。
応用課程
同行援護従業者養成研修の応用課程では、同行援護に活かせるより専門的な知識や技術を学びます。前述したとおり、同行援護を実施する事業所のサービス提供責任者として働くには、一般課程だけではなく応用課程の修了が必要です。一般課程と同様に、基本的に応用課程にも修了試験はありません。
受講要件
応用課程の資格要件として、同行援護従業者養成研修の一般課程を修了する必要があります。ガイドヘルパー養成研修視覚障がい課程を修了している方も、受講要件を満たせる場合があるようです。なお、実務経験は問われないので、資格要件を満たせば受講できます。
学習内容
同行援護従業者養成研修の応用課程では、2時間の講義と10時間の演習を受講します。厚生労働省の「同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について(p.2)」によると、科目と時間数は下記のとおりです。
| 区分 | 科目 | 基本時間数 |
| 講義 | 障害・疾病の理解(2) | 1時間 |
| 講義 | 障害者(児)の心理(2) | 1時間 |
| 演習 | 場面別基本技能 | 3時間 |
| 演習 | 場面別応用技能 | 3時間 |
| 演習 | 交通機関の利用 | 4時間 |
参考:厚生労働省「同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について(p.2)」
応用課程は、一般課程で学んだ知識をより深められるカリキュラムです。講義の「障害・疾病の理解(2)」「視覚障害者(児)の心理(2)」の科目では、医学的な知見も交えながら視覚障がいについて勉強します。
演習は、具体的な外出先を設定したうえで移動支援の技術を学ぶ実践的な内容です。「交通機関の利用」の科目では、実際に公共機関を利用した実習を行います。
受講費用の相場
同行援護従業者養成研修応用課程の受講料の相場は、2~3万円程度です。一般課程に比べると、受講時間が少ない分、受講費用が安い傾向にあります。
取得に必要な期間
応用課程の修了に必要な日数は、2日程度です。受講日程は研修の実施主体によって違いがあるので、全日参加できるか、必ず事前にチェックしましょう。
出典
厚生労働省「社会保障審議会障害者部会(第136回)の資料について」(2024年11月18日)
同行援護従業者養成研修の申し込み方法
同行援護従業者養成研修は、自治体の指定を受けたスクールが実施します。申し込み方法はスクールによって異なりますが、インターネットで応募できる場合が多いようです。Webサイトで情報を確認し、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、受講の手続きを行いましょう。
インターネットで「同行援護従業者養成研修 都道府県」で検索すると、受講先の候補を見つけられます。学習内容や受講費用、研修日程などの概要を確認し、自分の希望する講座を探してみてくださいね。
なお、介護福祉士や介護職員初任者研修など、有資格者の場合、修了証明書の写しが求められる場合も。受講する科目の一部が免除される可能性があるので、必要に応じて準備しましょう。
同行援護従業者養成研修を活かせる職場
同行援護従業者養成研修を活かして働ける主な職場は、以下のとおりです。
- ガイドヘルパー事業所
- 障がい者支援施設
- グループホーム
- 障害福祉サービス事業所
- 在宅介護サービスを行う事業者
同行援護従業者養成研修で得られる知識は、加齢や疾患により視力が衰えている高齢者の介護にも活かせます。
なお、職場によっては、同行援護だけではなく、高齢者や障がいのある方の介護に携わることもあります。そのため、介護職員初任者研修や重度訪問介護従業者養成研修などを取得し、さらなる介護技術を習得すれば、同行援護従業者として活躍できる場が広がるでしょう。
同行援護従業者養成研修を取得するメリット
同行援護従業者養成研修を取得すると、視覚障がいのある方の外出支援ができるようになるため、仕事の幅が広がります。また、視覚障がいや原因疾患に関する知識を学ぶことで、視覚障がいのある利用者さんの気持ちに寄り添えたり、適切な介助を行えたりするのも、メリットです。
同行援護従業者養成研修は、同行援護事業所が特定事業所加算の要件を満たすのに活かせる資格です。そのため、資格があれば、障害福祉サービス事業所への就職・転職に有利になる可能性があります。同行援護従業者養成研修にはさまざまなメリットがあるので、興味がある方は受講を検討してみてください。
同行援護従業者養成研修についてよくある質問
ここでは、同行援護従業者養成研修についてよくある質問に回答します。研修の受講方法や、科目免除があるのかが気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
同行援護従業者養成研修はオンラインで受講できますか?
同行援護従業者養成研修には演習があるので、オンラインのみで修了することはできません。基本的には通学して研修を受けますが、講義をオンラインで受講できるスクールもあるようです。オンライン研修を行っているかは、スクールごとに異なるので、受講スケジュールに不安がある方は確認してみてください。
同行援護従業者養成研修で科目免除になる条件は?
同行援護従業者養成研修(一般課程)の科目免除の条件は、「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業の研修」を修了していることです。自治体によっては、介護福祉士や介護福祉士実務者研修などの有資格者に対しても、科目免除が適用される場合があります。科目免除の対象者や免除科目・時間数などは、研修を申し込む前に確認しておきましょう。
出典
厚生労働省「社会保障審議会障害者部会(第136回)の資料について」(2024年11月18日)
まとめ
同行援護従業者養成研修とは、視覚障がいがあり1人で移動するのが難しい方を支援する「同行援護」に携わるための資格です。外出時に同行して援護するスキルや、視覚障がいに関する専門的な知識を学べます。
同行援護従業者養成研修は、一般課程と応用課程の2段階です。基本的に試験はなく、一般課程を修了することで、同行援護の仕事を担当できます。応用課程は、同行援護のサービス提供責任者に必要なスキルを習得する内容です。
同行援護従業者養成研修を取得すると、ガイドヘルパー事業所など、障害福祉サービスを提供する職場で幅広く活躍できます。そのほか、専門性が身についたり、転職に有利になったりするメリットもあるでしょう。障がい者支援の現場で働くことを検討している方は、取得を検討してみてください。
「障害福祉サービスに興味がある」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)をご活用ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護・福祉業界に特化した就職・転職エージェントなので、障がい者施設・事業所の求人が豊富です。サービスはすべて無料。「新しい業界で働くのは不安…」という方は、相談だけでも大丈夫なので、まずは気軽にお問い合わせください。
働きながら資格を取る方法教えます
 障がい者施設の求人一覧はこちら
障がい者施設の求人一覧はこちら