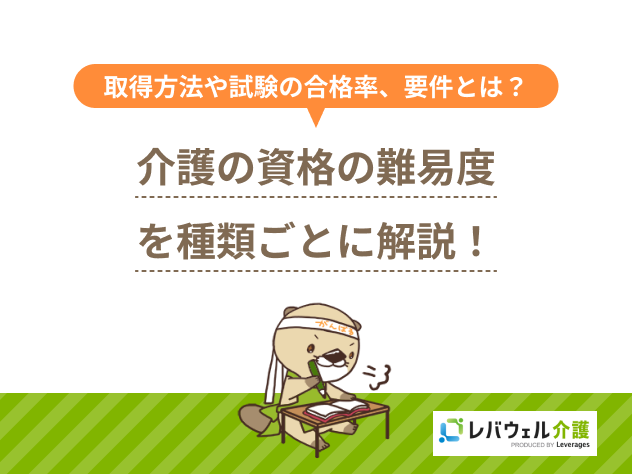
この記事のまとめ
- 介護に関する資格や研修は多数あり、取得の難易度は種類ごとに異なる
- 「認知症介護基礎研修」や「介護職員初任者研修」は初心者におすすめの資格
- 「認定介護福祉士」や「認知症ケア専門士」には、実務経験などの要件がある
介護のスキルを身につけたいと考えている方は、「資格の難易度ってどんな感じ?」と気になるかもしれません。介護に関する資格の難易度はさまざまで、「認知症介護基礎研修」や「介護職員初任者研修」のように比較的取得しやすい資格もあれば、取得に数年かかる資格もあります。この記事では、介護に関する資格の難易度を表で比較。受験資格や試験の合格率など、具体的に解説するので、ぜひ資格取得の参考にしてください。
介護資格の種類31選!取得方法やメリットを解説します →レバウェル介護の資格スクールはこちら介護に関する資格の種類・難易度
介護に関する資格は多くあるため、「どの資格を取得するか迷う」と感じる方もいるでしょう。以下では、介護の資格の難易度をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
介護に関する公的資格の種類・難易度
自治体などが指定・運営する介護の公的資格は多数あります。介護に関する公的資格の種類や取得の難易度を表にまとめたので、チェックしてみましょう。
| 資格・研修の種類 | 取得の難易度 |
| 認知症介護基礎研修 | ・無資格の介護職員が受講できる ・数時間で取得でき、難易度は低い |
| 介護職員初任者研修 | ・誰でも受講できる ・修了試験があるが追試もでき、落ちる可能性は低い |
| 介護福祉士実務者研修 | ・誰でも受講できる ・試験を行うスクールもあるが、落ちる可能性は低い |
| 介護福祉士 | ・試験を受けるには、受験資格を満たす必要がある ・合格率は、約70~80% |
| 社会福祉士 | ・試験を受けるには、受験資格を満たす必要がある ・合格率は、約30~50% |
| 介護支援専門員 (ケアマネジャー) | ・試験を受けるには、受験資格を満たす必要がある ・合格率は、約15~25% |
| 喀痰吸引等研修 | ・要件はないが、介護職の方が受講することが多い ・修了評価があるが、落ちる可能性は低い |
| 福祉用具専門相談員指定講習会 | ・誰でも受講できる ・修了試験があるが追試もでき、落ちる可能性は低い |
| 生活援助従事者研修 | ・誰でも受講できる ・修了試験があるが追試もでき、落ちる可能性は低い |
| 重度訪問介護従業者養成研修 | ・誰でも受講できる(要件があるスクールもある) ・修了試験があるが、難易度は低い |
| 同行援護従業者養成研修 | ・一般課程は要件なし、応用課程は要件あり ・試験はない |
| 行動援護従業者養成研修 | ・誰でも受講できる(要件があるスクールもある) ・試験はない |
| 難病患者等ホームヘルパー養成研修 | ・受講には資格要件がある ・試験はない |
| 移動支援従業者養成研修 (ガイドヘルパー) | ・訪問介護に携わるための資格が要件の場合がある ・試験はない |
介護に関する公的資格は、1日で取得できるものから、数年の実務経験を要するものまで、さまざまです。「介護に関する公的資格の具体的な難易度」でさらに解説するので、気になる資格の難易度を確認してみてくださいね。
首都圏限定!資格取得が無料!
転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!
レバウェル介護の資格スクール介護に関する民間資格の取得難易度
介護に関する民間資格の要件や試験の難易度は、以下のとおりです。
| 資格・研修の種類 | 取得の難易度 |
| 認定介護福祉士 | ・講座を受講するには、要件を満たす必要がある ・試験はない |
| 認知症ケア専門士 | ・試験に合格し、研修動画を視聴すれば取得できる ・受験の要件は、認知症ケアの実務経験3年以上 |
| 認知症ケア指導管理士 | ・試験を受け、合格点を満たせば取得できる ・初級は誰でも受験できる。上級は要件あり |
| 認知症ライフパートナー | ・試験を受け、70%以上得点することで取得できる ・3級と2級は誰でも受験でき、1級は2級取得者が対象 |
| レクリエーション介護士 | ・2級の講座は誰でも受講できる ・1級は、2級取得者が対象で、試験と現場実習もある |
| 介護予防運動指導員養成講座 | ・養成講座を受講するには、要件を満たす必要がある ・60分の修了試験に合格すれば取得可能 |
| 在宅介護インストラクター | ・講座受講後に、在宅で試験を受ける ・試験は70%以上得点すれば合格 |
| サービス介助士 | ・社会人や大学生などが対象で講座の受講要件はない ・検定試験があるが、有料で再試験を受験可能 |
| 介護食士 | ・講習を受講し、試験に合格することで取得可能 ・3級は誰でも受講できるが、2級と1級は要件がある |
| 介護事務管理士(R) | ・認定試験への合格で取得可能で、誰でも受験できる ・合格率は約70% |
| ケアクラーク(R) | ・試験への合格で取得できる。誰でも受験可能 ・学科試験と実技試験の両方で70%得点したら合格 |
介護に関する民間資格には、認知症やレクリエーションに特化したものなどがあります。取得の難易度もそれぞれ異なるので、自身に合った資格を選ぶと良いでしょう。資格取得の難易度を詳しく知りたい方は、「介護に関する民間資格の具体的な難易度」もあわせてご覧くださいね。
▼関連記事
介護の資格はどんな順番で取ればいい?取得方法やメリットも解説!
介護に関する公的資格の具体的な難易度
介護に関する公的資格には、「認知症介護基礎研修」「介護職員初任者研修」「介護福祉士」などがあります。公的資格は、日本全国で活かせるので、介護の仕事に従事するなら積極的に取得すると良いでしょう。以下では、資格取得の難易度や目的などを解説します。
認知症介護基礎研修の難易度
認知症介護基礎研修では、認知症介護の基礎を学びます。学習時間は3時間前後。在宅で受講でき、取得の難易度は低めです。介護職員は、入職から1年以内に認知症介護基礎研修を修了しなければなりません。働きながら取得しやすい資格なので、無資格で介護職員になった場合は、認知症介護基礎研修から挑戦するのも良いでしょう。
出典
認知症介護研究・研修 仙台センター:eラーニングシステム運営事務局「認知症介護基礎研修eラーニングのご案内」(2024年6月25日)
▼関連記事
介護職は無資格で働けなくなるの?認知症介護基礎研修の義務化について解説
介護職員初任者研修の難易度
介護職員初任者研修は、介護の基礎的な知識や技術を身につけるための資格です。130時間のカリキュラムのうち、40.5時間までは通信教育で受講できます。取得にかかる期間は、約1~4ヶ月です。
研修の最後に1時間程度の筆記試験があり、100点中70点以上で合格となります。試験の難易度は低めで、もし不合格になってしまったとしても、追試を受けられるようです。
介護職員初任者研修は誰でも受講できます。そのため、これから介護の仕事を始めたい方や、介護職になったばかりの方、家族の介護をするために勉強したい方などにおすすめです。介護職員初任者研修に興味がある方は、「介護職員初任者研修とはどんな資格?受講費用を抑える方法や取得のメリット」の記事もご参照ください。
出典
厚生労働省「介護職員・介護支援専門員」(2024年6月25日)
▼関連記事
介護職員初任者研修は働きながら取れる!取得する方法とメリットを解説
首都圏限定!資格取得が無料!
転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!
レバウェル介護の資格スクール介護福祉士実務者研修の難易度
介護福祉士実務者研修は、国家資格である「介護福祉士」に必要な知識を身につけるための資格で、介護福祉士国家試験の受験要件の一つとなっています。450時間のカリキュラムのうち、95時間は通学が必須です。無資格で受講する場合、取得に最短6ヶ月かかります。前述の「介護職員初任者研修」などを修了している方は、履修済みのカリキュラムが免除になるため、その分早く取得できる場合があるでしょう。
なお、介護福祉士実務者研修には、修了試験が義務付けられていません。そのため、試験実施の有無はスクールによって異なります。試験がある場合も、学習内容を確認する程度のため、しっかりと受講していれば合格できるでしょう。
実務者研修は、介護福祉士を実務経験ルートで受験する場合に必要な資格です。また、実務者研修を受講すると実践的なスキルが身につくため、介護業界でキャリアアップしたい方におすすめです。実務者研修については、「介護福祉士実務者研修とは?資格取得のメリットや初任者研修との違いを解説」の記事に詳しくまとめています。
出典
厚生労働省「介護福祉士養成施設等における「医療的ケアの教育及び実務者研修関係」」(2024年6月25日)
▼関連記事
実務者研修取得の最短期間は?介護福祉士国家資格を取る方法も解説!
介護福祉士の取得難易度
介護福祉士は、介護分野で唯一の国家資格です。取得するためには、受験資格を満たして国家試験に合格し、資格登録の手続きをする必要があります。介護福祉士は、「介護サービスの質向上に貢献したい」「管理職を目指したい」といった方におすすめです。
介護福祉士国家試験の受験資格
介護福祉士国家試験の受験資格を得る主な方法は、「実務経験ルート」「養成施設ルート」「福祉系高校ルート」の3つです。
実務経験ルートでは、「介護等の実務経験3年+介護福祉士実務者研修修了」で介護福祉士を受験できます。社会人として働きながら介護福祉士を目指す人に人気です。
養成施設ルートでは、専門学校などに2~3年通うことで、介護福祉士試験の受験資格を得られます。最短で介護福祉士になりたい方や、学生の方は、養成施設ルートも視野に入れると良いでしょう。また、福祉系高校ルートは、福祉系高校に通って、介護福祉士試験の受験資格を得るルートです。
介護福祉士を目指したい方は、「介護福祉士の受験資格を得るルートを解説!必要な実務経験や試験概要は?」も参考にしてみてください。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格」(2024年6月25日)
介護福祉士国家試験の難易度・合格率
介護福祉士国家試験は、すべてのルートで実技試験が廃止され、筆記試験のみの実施となりました。合格点は、総得点の60%程度を基準として、その年の問題の難易度で補正されます。また、出題範囲の11科目群すべてで得点することも合格の条件です。出題形式は五肢択一で、マークシート方式となっています。
厚生労働省の「第36回介護福祉士国家試験合格発表」によると、2024年に行われた介護福祉士国家試験の合格率は82.8%でした。国家資格としては高めの合格率なので、しっかりと勉強すれば、取得を目指せるでしょう。介護福祉士国家試験の難易度は、「介護福祉士国家試験の合格率は?資格の取得難易度と第36回の結果も解説!」でもご紹介しています。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]出題基準・合格基準」(2024年6月25日)
厚生労働省「第36回介護福祉士国家試験合格発表」(2024年6月25日)
社会福祉士の取得難易度
社会福祉士は、相談援助のスキルがあることを証明する国家資格です。介護福祉士と同じく、受験資格を満たして国家試験に合格し、資格登録の手続きをすることで、社会福祉士を取得できます。高齢者や障がいのある方、ひとり親家庭など、課題を抱える人の生活を支援したい方は、取得を目指すと良いかもしれません。
社会福祉士国家試験の受験資格
社会福祉士国家試験の受験資格を得るためには、指定の科目を履修したり、相談援助の実務経験を積んだりする必要があります。
これから大学へ進学する学生の場合、最短で受験できるのは、福祉系大学等に4年間通い、指定科目を履修するルートです。このほか、「福祉系大学で基礎科目を履修し、短期養成施設に通うルート」「一般大学で4年学び、一般養成施設に1年以上通うルート」などがあります。
社会福祉士の受験資格の詳細は、「ソーシャルワーカーに必要な資格の取り方や難易度は?職種別の要件も解説!」にまとめているので、あわせて参考にしてください。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[社会福祉士国家試験]受験資格」(2024年6月25日)
社会福祉士国家試験の難易度・合格率
社会福祉士国家試験はマークシート方式です。合格点は、総得点の60%程度を基準とし、その年の問題の難易度で補正されます。また、出題範囲の6科目群すべてで得点することも、合格の条件です。
厚生労働省の「第36回社会福祉士国家試験合格発表」によると、2024年に行われた社会福祉士国家試験の合格率は58.1%でした。新卒者の合格率は、既卒者よりも高くなっています。
社会福祉士国家試験に合格するためには、社会福祉に関する制度や法律を網羅的に理解する必要があるでしょう。試験対策については、「社会福祉士国家試験に合格するための勉強方法7選!独学でも取得できるの?」にまとめています。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[社会福祉士国家試験]出題基準・合格基準」(2024年6月25日)
厚生労働省「第36回社会福祉士国家試験合格発表」(2024年6月25日)
介護支援専門員(ケアマネジャー)の取得難易度
ケアマネジャーの資格を取得するには、受験資格を満たして「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格し、実務研修を修了する必要があります。ケアマネジャーの資格を取得すれば、専門性を証明でき、携われる業務も増えるでしょう。ケアマネジャーとして働きたい方や、給与アップを目指す方などにおすすめの資格です。
介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格
介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格を得るには、介護や福祉の業界で実務経験を積まなければなりません。具体的には、「特定の国家資格等に基づく業務」もしくは「相談援助」の実務経験を5年以上積むことが要件です。
ケアマネジャーは、「特定の国家資格等」に含まれる、介護福祉士や社会福祉士、看護師などが多く取得しています。ケアマネジャーの取得には期間がかかるので、長期的なキャリアパスとして目指すと良いでしょう。たとえば、介護職員がケアマネジャーを目指す場合、介護福祉士を取得してから5年以上の実務経験が必要です。
出典
公益財団法人 東京都福祉保健財団:ケアマネジャー専用サイト「令和6年度 東京都介護支援専門員実務研修受講試験」(2024年6月25日)
▼関連記事
ケアマネジャーになるには?最短で何年?試験の受験資格や取得の流れを解説
介護支援専門員実務研修受講試験の合格率
厚生労働省の「第26回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」によると、2023年10月に行われたケアマネジャー試験の合格率は 21.0%でした。ケアマネジャー試験は合格率が低く、介護系の資格のなかでも難易度が高いといえるでしょう。
ケアマネジャー試験について詳しく知りたい方は、「ケアマネ(介護支援専門員)の合格率はどれくらい?難易度や試験の対策方法も」の記事もチェックしてみてください。
出典
厚生労働省「第26回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」(2024年6月25日)
喀痰吸引等研修の難易度
喀痰吸引等研修の受講に要件はありません。しかし、基本的な介護技術が身についてる方が、医療的ケアに対応できるようになるための研修なので、介護職員としての実務経験がある方の受講が多いようです。
喀痰吸引等研修は、「第1号研修」「第2号研修」「第3号研修」の3つで、研修の種類によって、実施できる医療的ケアが異なります。
第1号研修を修了すると、不特定多数の利用者さんに喀痰吸引や経管栄養の処置が可能です。第2号研修すると、不特定多数の利用者さんに対し、特定の医療的ケアを行えます。第1号研修と第2号研修の違いは、実際に利用者さんに対して行う「実地研修」の課程です。
第1号研修・第2号研修では、基本研修として「講義50時間+シミュレーター演習」を受けたのち、実地研修を受けます。スクーリングは8日前後で、実地研修は5日ほどです。
第3号研修は、特定の障がいのある利用者さんに対して医療的ケアを行うための資格で、基本となる「第1号研修」もしくは「第2号研修」とあわせて取得しなければなりません。また、実際に医療的ケアに携わるには、特定行為の実施者としての登録も求められます。
喀痰吸引等研修の取得にかかる期間は、研修の種類や学習ペースによって異なりますが、一般的に1~4ヶ月程度です。
出典
厚生労働省「喀痰吸引等研修」(2024年6月25日)
福祉用具専門相談員指定講習会の難易度
福祉用具専門相談員指定講習を受講して修了評価試験に合格することで、資格を取得できます。修了評価試験は受講内容の理解度を確認するために実施されるので、難易度はそれほど高くないでしょう。
なお、「福祉用具専門相談員」とは、利用者さんの身体状況や生活環境などに適した福祉用具を提案し、使い方をアドバイスする職種です。「福祉用具専門相談員指定講習会を修了」もしくは「介護福祉士や社会福祉士、理学療法士など要件に該当する国家資格を取得」することで、福祉用具専門相談員として働けます。
出典
公益財団法人 東京都福祉保健財団「福祉用具専門相談員向け講習会」(2024年6月25日)
▼関連記事
福祉用具専門相談員とはどんな職種?仕事内容や必要な資格、年収を解説!
生活援助従事者研修の難易度
生活援助従事者研修のカリキュラムは59時間で、およそ2週間~3ヶ月で取得できます。講座受講後に30分程度の筆記試験がありますが、難易度は低め。万が一不合格になった場合も追試を受けられます。
生活援助従事者研修は、介護職が掃除や洗濯、買い物などをする際に役立つ資格です。取得することで、ホームヘルパーとして生活援助に携われるようになります。短期間で介護の資格を取得したい方や、家族介護や自身の老後のために基礎を学びたい方におすすめの資格です。なお、生活援助従事者研修は実施しているスクールが少なく、開催されていない地域もあるため、受講したい方は自治体のWebサイトを確認しておきましょう。
出典
厚生労働省「介護保険最新情報掲載ページ」(2024年6月25日)
重度訪問介護従業者養成研修の難易度
重度訪問介護従業者養成研修は、「基礎課程」「追加課程」「統合課程」という3つの課程に分かれています。
基礎課程は、障害支援区分4と5の利用者さんに重度訪問介護のサービスを提供するための資格です。追加課程は、障害支援区分6の利用者さんにサービスを提供するための資格で、基礎課程を修了した方を受講対象としています。基礎課程と追加課程は、それぞれ10時間です。
統合課程では、基礎課程と追加課程に加え、喀痰吸引等研修(第3号研修)の内容を学べます。カリキュラムは20.5時間で、3日前後で取得可能です。
重度訪問介護従業者養成研修には修了試験があります。ただし、学習内容を確認する程度のテストなので、難易度は低いでしょう。
なお、介護職員初任者研修や介護福祉士などの資格を保有する方は、新たに重度訪問介護従業者養成研修を修了しなくても、重度訪問介護の仕事に携われます。重度訪問介護については、「重度訪問介護とは?簡単にサービスを説明します!障がい福祉に必要なお仕事」の記事をご覧ください。
同行援護従業者養成研修の難易度
同行援護従業者養成研修は、視覚障がいがある方の移動を支援する「同行援護」に携わるための資格で、一般課程と応用課程に分かれています。
一般課程には要件がないため、誰でも受講可能です。カリキュラムは20時間で、3日程度で取得できます。修了試験は義務付けられていません。
応用課程は、一般課程や関連する研修を修了した方が受講対象です。カリキュラムは12時間で、2日程度で取得できます。なお、応用課程は、同行援護のサービス提供責任者になるための要件の一つです。
出典
厚生労働省「第17回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料」(2024年6月25日)
行動援護従業者養成研修の難易度
行動援護従業者養成研修は、重度の知的障がいや精神障がいがあり、常時介護を必要とする方をサポートするための資格です。基本的に受験資格は設けられておらず、試験もないため、取得しやすいでしょう。カリキュラムは約24時間で、3~4日程度で修了できます。
ただし、実際に行動援護の業務に携わるためには、知的障がいや精神障がいがある方への直接処遇経験が1年以上必要です。
出典
厚生労働省「第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年6月25日)
難病患者等ホームヘルパー養成研修の難易度
難病患者等ホームヘルパー養成研修は、入門課程・基礎課程I・基礎課程IIに分かれていますが、入門課程を実施しているスクールは少ないようです。
基礎課程Iを受講するには、介護職員初任者研修以上の資格が求められます。基礎課程Iのカリキュラムは4時間なので、1日で取得可能。修了試験はありません。
基礎課程IIは、介護福祉士実務者研修や介護福祉士を保有する方が対象です。カリキュラムは6時間なので1日で取得でき、修了試験はありません。
難病患者等ホームヘルパー養成研修は、受講要件を満たしている場合、取得の難易度が低いでしょう。ホームヘルパーとして幅広く活躍したいと考えている方は、取得を検討してみると良いかもしれません。
移動支援従業者養成研修(ガイドヘルパー)の難易度
移動支援従業者養成研修(ガイドヘルパー)は、自治体が実施する資格研修です。全身性障がいのある方をサポートするための研修や、知的障がいのある方をサポートするための研修などがあります。
障がいのある方の移動を支援したい方は、自身が住む地域で実施しているガイドヘルパーの研修を確認しておくと良いでしょう。資格の種類によって研修内容は異なりますが、2~3日程度で修了でき、試験はない場合が多いようです。
出典
東京都福祉局「障害者(児)移動支援従業者養成研修 開講日程の御案内」(2024年6月25日)
▼関連記事
【障がい者支援に役立つ資格一覧】取得方法や難易度、習得できるスキルは?
介護に関する民間資格の具体的な難易度
介護に関する民間資格には、「認定介護福祉士」「認知症ケア専門士」「レクリエーション介護士」などがあります。民間資格は、より専門的なスキルを身につけたい方におすすめです。それぞれの資格の難易度を、以下で確認してみましょう。
認定介護福祉士の取得難易度
受講要件を満たして「認定介護福祉士養成研修」を修了し、認定証の交付を受けることで、認定介護福祉士の資格を取得できます。
認定介護福祉士養成研修の受講要件
認定介護福祉士養成研修を受講するには、次の要件をすべて満たさなければなりません。
- 介護福祉士の資格を取得してから、5年以上の実務経験を積んでいる
- これまでに介護職員が対象の現任研修を100時間以上受講している
- 研修実施団体のレポート課題または受講試験で、一定の水準の成績を修めている(免除の場合あり)
介護福祉士としての実務経験や現任研修の研修歴などが、認定介護福祉士養成研修の受講要件となっています。認定介護福祉士は、さらなるスキルアップやキャリアアップを目指す介護福祉士におすすめの資格です。
出典
認定介護福祉士認証・認定機構「認定介護福祉士になるには」(2024年6月25日)
認定介護福祉士養成研修の難易度
認定介護福祉士養成研修は、I類とII類の全科目(22科目・600時間)を履修することで、修了できます。科目ごとに修了評価が行われるようです。なお、認定介護福祉士養成研修は、実施するスクールが少なく、科目ごとの開催が多いため、資格取得は計画的に行う必要があるでしょう。
認定介護福祉士の資格に興味がある方は、「認定介護福祉士とは?期待される役割や資格取得に必要な研修を解説」の記事もあわせて参考にしてください。
出典
認定介護福祉士認証・認定機構「認定介護福祉士養成研修について」(2024年6月25日)
認知症ケア専門士の取得難易度
認知症ケア専門士の資格を取得するためには、「認知症ケア専門士認定試験」への合格が必要です。試験合格後に、研修動画の視聴と資格登録をすることで、認知症ケア専門士を取得できます。認知症ケア専門士は、その名のとおり認知症ケアの専門知識を深められる資格です。
認知症ケア専門士認定試験の受験資格
認知症ケア専門士認定試験を受けるには、過去10年間に認知症ケアの実務経験が3年以上必要です。資格要件はありません、認知症ケアに携わって入れば職種は問われないため、介護職だけではなくケアマネジャーや医療従事者も受験できます。
出典
認知症ケア専門士認定試験「試験概要:受験資格」(2024年6月25日)
認知症ケア専門士認定試験の難易度
認知症ケア専門士認定試験には、第1次試験と第2次試験があります。第1次試験は4分野で、各分野50問、五肢択一形式です。4分野すべてで70%以上正答すると、第1次試験に合格できます。
第1次試験に合格した方は、第2次試験を受験可能です。第2次試験では、認知症ケアの事例に関する論述問題が3問出題されます。アセスメント能力や認知症の理解などの合格要件を満たすことで、第2次試験に合格できるようです。
なお、認知症ケア専門士認定試験の合格率は50%前後となっています。認知症ケア専門士についてもっと詳しく知りたい方は、「認知症ケア専門士とは?認定試験の合格率と難易度、資格の取得方法を解説!」をご覧ください。
出典
認知症ケア専門士認定試験「試験概要:第1次試験」(2024年6月25日)
認知症ケア専門士認定試験「試験概要:第2次試験」(2024年6月25日)
認知症ケア専門士公式サイト「認知症ケア専門士情報」(2024年6月25日)
認知症ケア指導管理士の取得難易度
認知症ケア指導管理士の資格は初級と上級に分かれています。受験資格や試験について、以下で確認してみましょう。
認知症ケア指導管理士(初級)の難易度
認知症ケア指導管理士(初級)は、資格や実務経験を問わず誰でも受験できます。介護や医療に関わる仕事をしている人が受験する場合が多いようです。試験に合格することで、資格を取得できます。
認知症ケア指導管理士(初級)の試験は60問で、五肢択一のマークシート方式です。合格点は、総得点の7割が基準ですが、問題の難易度によって補正されます。なお、試験の合格率は60%前後です。
出典
一般財団法人 職業技能振興会「認知症ケア指導管理士[初級]」(2024年6月25日)
上級認知症ケア指導管理士の難易度
上級認知症ケア指導管理士の試験は、認知症ケア指導管理士(初級)の資格を持つ方や、指定の資格を保持して初級と併願する方が対象です。
上級認知症ケア指導管理士試験は、一次試験と二次試験で構成されます。一次試験は60問、五肢複択のマークシート方式です。一次試験に合格した場合、二次試験として論述試験を受けます。
一般財団法人 職業技能振興会(資格取得キャリアカレッジ)の「上級認知症ケア指導管理士試験受験者データ」によると、2019年に実施された上級認知症ケア指導管理士試験の一次試験の合格率は7%、二次試験の合格率は95.2%です。また、第1~7回試験の合格率の平均は7.6%。上級認知症ケア指導管理士の資格取得は難易度が高いといえるでしょう。
出典
一般財団法人 職業技能振興会「上級認知症ケア指導管理士」(2024年6月25日)
一般財団法人 職業技能振興会 資格取得キャリアカレッジ「過去の受験者情報」(2024年6月25日)
認知症ライフパートナーの取得難易度
認知症ライフパートナーの資格は、1~3級に分かれており、いずれも検定試験に合格することで取得できます。
認知症ライフパートナー検定試験3級の難易度
認知症ライフパートナー検定試験3級は、学歴・年齢・国籍などを問わず誰でも受験できます。マークシート方式で、3級公式テキストが出題範囲です。100点満点で70点以上得点すれば合格となります。
認知症ライフパートナー3級を取得すれば、認知症の方とのコミュニケーション方法などが身につくでしょう。そのため、介護職だけではなく、認知症の方のご家族や接客業に従事する方など、認知症の方と関わる機会がある方にもおすすめの資格です。
出典
一般社団法人 日本認知症コミュニケーション協議会「認知症ライフパートナー検定試験3級」(2024年6月25日)
認知症ライフパートナー検定試験2級の難易度
認知症ライフパートナー検定試験2級にも、受験資格はありません。3級と併願で受験することも可能です。試験はマークシート方式、出題範囲は2級公式テキストで、100点中70点以上で合格となります。
認知症ライフパートナー2級を取得すれば、認知症の方やご家族に対し、適切な支援・アドバイスを行えるでしょう。そのため、介護従事者として専門的な認知症ケアを行いたい方におすすめの資格です。
出典
一般社団法人 日本認知症コミュニケーション協議会「認知症ライフパートナー検定試験2級」(2024年6月25日)
認知症ライフパートナー検定試験1級の難易度
認知症ライフパートナー検定試験1級を受験できるのは、認知症ライフパートナー2級に合格している人です。
検定試験1級は、前半と後半の2部構成。前半はマークシート方式で、後半は記述式です。前半・後半のそれぞれで70%以上得点すれば、認知症ライフパートナー1級を取得できます。出題範囲は、1級公式テキストに準拠しますが、テキスト外からも出題されるようです。
出典
一般社団法人 日本認知症コミュニケーション協議会「認知症ライフパートナー検定試験1級」(2024年6月25日)
一般社団法人 日本認知症コミュニケーション協議会「「認知症ライフパートナー検定試験」受験要項」(2024年6月25日)
▼関連記事
【認知症介護の資格一覧】取得方法や試験の難易度、習得できるスキルを解説
レクリエーション介護士の取得難易度
レクリエーション介護士の資格は、1級と2級に分かれています。以下でそれぞれの取得難易度を確認してみましょう。
レクリエーション介護士2級の難易度
レクリエーション介護士2級に要件はないため、誰でも取得を目指せます。資格の取得方法は、「通信」もしくは「通学」です。
通信の場合、テキストや動画で学習し、添削課題と筆記試験(在宅)に合格することで、レクリエーション介護士2級を取得可能。筆記試験は選択式の50問で、60点以上得点すれば合格できます。通信で資格を取得するのにかかる期間は、3ヶ月が目安です。
通学の場合は、講習を受講してからテストを受けます。学習内容は通信と大きな違いはないようです。通学であれば、最短2日間ほどでレクリエーション介護士2級を取得できます。
出典
レクリエーション介護士公式サイト「資格取得の流れ」(2024年6月25日)
レクリエーション介護士1級の難易度
レクリエーション介護士1級は、2級を取得した方が対象です。4日間の通学講座を受講したうえで試験に合格し、現場実習を行えば、レクリエーション介護士1級を取得できます。
試験は実技試験と筆記試験です。実技試験では、10分間で介護レクリエーションの実演を実施。100点中60%以上で合格です。筆記試験は、選択問題60問、記述問題4~6問、小論文1問で構成されます。120点満点のうち、正答率60%以上で合格です。
レクリエーション介護士は、レクリエーションのスキル習得に特化した資格なので、デイサービスなどの介護施設で働く方が取得すると、仕事に活かせるでしょう。
出典
レクリエーション介護士公式サイト「レクリエーション介護士1級ガイド」(2024年6月25日)
▼関連記事
レクリエーション介護士とは?資格の概要や試験内容を分かりやすく解説
介護予防運動指導員養成講座の難易度
介護予防運動指導員の資格を取得するためには、「介護予防運動指導員養成講座」を受講しなければなりません。介護予防運動指導員養成講座の受講要件は、以下のいずれかを満たすことです。
- 医師や看護師、介護福祉士など、特定の資格を保有している
- 介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修などを保有していて、実務系経験が2年以上ある
- 上記のいずれかの資格要件を満たす見込みがある
介護予防運動指導員は、医療や介護などに関する資格を保有する方が、介護予防のスキルを磨くために取得する資格といえます。
介護予防運動指導員養成講座は計33時間で、インターネットで受講できる科目も多いため、通学が必要なのは2日間程度です。修了時には60分の試験があり、合格することで資格を取得できます。なお、介護予防運動指導員養成講座の修了試験は、修了から1年間は再受験が可能です。
▼関連記事
介護予防運動指導員のメリットとは?資格の概要と取得方法もご紹介!
在宅介護インストラクターの取得難易度
在宅介護インストラクターの資格は、通信講座を受講したうえで、在宅試験に合格すれば取得できます。講座の受講に要件はありません。学習期間は4ヶ月程度で、試験は70%以上得点すれば合格です。
在宅介護インストラクターは、在宅介護について学べる資格なので、介護職だけではなく、家族の介護を行っている方にも役立つでしょう。
出典
一般財団法人 日本能力開発推進協会「在宅介護インストラクター」(2024年6月25日)
サービス介助士の取得難易度
サービス介助士の資格は、自宅学習をして実技教習を受け、検定試験に合格することで取得できます。自宅学習は、テキストでの勉強と課題の提出です。提出課題は、100点中60点以上で合格で、60点未満の場合は再提出となります。受験対象は「社会人、大学生、専門学校生など」となっており、受験資格は特に設けられていません。
実技教習は、「対面形式で2日間」もしくは「オンライン講座6~7時間+対面形式1日間」です。対面での実技教習の終了後に、50分の検定試験が行われます。検定試験は、3択のマークシートで50問。1問2点の配点で、70点以上の得点で合格です。合格率は8割以上で、もしも不合格になった場合は、試験料を支払えば再受験できます。
サービス介助士の資格は、働きながらでも2ヶ月程度で取得できるようです。試験の合格率が高く、追試も可能なため、取得の難易度は低いでしょう。
サービス介助士は、高齢者や障がいのある方のサポートに役立つ資格なので、サービス業に従事する方などが多く取得しています。もっと詳しく知りたい方は、「サービス介助士とはどんな資格?受講の流れや取得するメリット、更新方法」の記事もご参照ください。
出典
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構 サービス介助士公式サイト「取得の流れ・料金」(2024年6月25日)
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構 サービス介助士公式サイト「資格の特徴」(2024年6月25日)
介護食士の取得難易度
介護食士とは、身体機能に応じた介護食を調理するのに役立つ資格で、1~3級に分かれています。講習会を受講して試験に合格することで取得可能です。以下で難易度をチェックしてみましょう。
介護食士3級の難易度
介護食士3級の講習は誰でも受講できるので、介護の仕事をしていない一般の方が取得することもあります。資格講習は、学科25時間と実習47時間で、80%以上出席することが試験を受験する条件です。筆記試験と実技試験があり、どちらも60点以上取ることで、介護食士3級を取得できます。
介護食士2級の難易度
介護食士2級は、3級を取得している方が対象です。資格講習は、学科16時間と実習56時間。3級と同じく、筆記試験と実技試験で60点以上取ることで、介護食士2級を取得できます。
介護食士1級の難易度
介護食士1級の講習を受講できるのは、「介護食士2級を取得してから、2年以上介護食の調理業務に従事した、25歳以上の方」です。資格講習は、学科32時間と実習40時間で構成されます。下位資格と同様、講習後の筆記試験と実技試験で60点以上取れば、介護食士1級を取得可能です。
なお、介護食士1級の講習を開催している学校は少ないので、取得を目指す方は事前に確認しておきましょう。
出典
公益社団法人 全国調理職業訓練協会「介護食士講座・資格の種類」(2024年6月25日)
公益社団法人 全国調理職業訓練協会「介護食士講座・Q&A」(2024年6月25日)
▼関連記事
介護食士とはどんな資格?取得方法やメリットを詳しく解説
介護事務管理士(R)の取得難易度
介護事務管理士(R)の資格は、介護事務管理士(R)技能認定試験に合格することで取得可能です。受験資格は設けられていません。
介護事務管理士(R)技能認定試験は、学科と実技に分かれています。学科試験は10問で、介護保険制度や介護報酬請求に関する事務について問われる内容です。実技試験は、6問のうち2問を選んで解答するレセプト問題となっています。
介護事務管理士(R)技能認定試験の合格率は70%前後です。合格するには、「総得点の80%以上正答する」「学科・実技試験ともに60%以上得点する」という2つの条件を満たす必要があります。
▼関連記事
介護事務管理士とはどんな資格?取得するメリットや試験概要、難易度を解説
ケアクラーク(R)の取得難易度
ケアクラーク(R)の資格は、ケアクラーク技能認定試験に合格することで取得できます。受験資格はありません。介護事務のスキルを習得するための資格なので、介護事業所の事務職員として働きたい方や、経営に携わる方などにおすすめです。
ケアクラーク技能認定試験は、学科試験と実技試験に分かれています。学科は、択一式の筆記試験で、25問の出題。実技試験は、介護給付費明細書の作成といった問題が2問出題されます。学科試験と実技試験の両方で70%以上得点すれば合格です。
介護事務の資格や仕事に興味がある方は、「介護事務に資格は必要?合格率や取得方法、仕事に活かせるスキル」もチェックしてみてくださいね。
出典
一般財団法人 日本医療教育財団「ケアクラーク技能認定試験(ケアクラーク(R)):試験概要」(2024年6月25日)
介護の資格を取得するメリット
介護の資格を取得すると、キャリアアップを目指せたり、給与アップにつながったりするでしょう。以下では、資格取得のメリットを解説します。
専門的な資格があればキャリアアップを目指せる
介護に関する専門的な資格を取得すれば、役職や専門職に就く要件を満たせる場合もあり、キャリアアップしやすくなるでしょう。たとえば、介護福祉士実務者研修を取得すれば、訪問介護事業所のサービス提供責任者として従事できます。また、社会福祉士といった資格があれば、介護施設の生活相談員になることが可能です。
専門的な資格があれば、新人職員の指導や教育に携わったり、リーダー職に就いたりするチャンスも増えます。できる業務の範囲も広がるため、スキルアップやキャリアアップにつながるでしょう。
給与アップにつながる
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.157)」によると、介護職員(月給・常勤)の保有資格別の平均給与は、以下のとおりです。
| 保有資格 | 平均給与 |
| 無資格 | 268,680円 |
| 介護職員初任者研修 | 300,240円 |
| 介護福祉士実務者研修 | 302,430円 |
| 介護福祉士 | 331,080円 |
| 社会福祉士 | 350,120円 |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 376,770円 |
参考:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.157)」
無資格の介護職員は、有資格者よりも給与が低い傾向にあります。しかし、働きながら初任者研修や介護福祉士、ケアマネジャーの資格を取得すれば、大幅な給与アップも狙えるでしょう。資格を取得したり経験を積んだりすれば、学歴や年齢を問わず給与アップを目指せるのが、介護業界で働く魅力です。
出典
厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2024年6月25日)
▼関連記事
働きながら取得しやすい介護の資格とは?必要な期間や方法、費用も解説!
首都圏限定!資格取得が無料!
転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!
レバウェル介護の資格スクール介護業界での転職に有利に働く
介護に関する資格があれば、より良い条件の求人に応募することが可能です。介護業界への志望度をアピールできるだけでなく、即戦力として評価してもらえることもあります。特に、介護職員初任者研修以上の資格があれば、施設・在宅のどちらでも活躍できる人材として評価されるでしょう。
▼関連記事
介護職員のキャリアパスとは?モデルケースや制度導入のメリットを解説!
介護の資格を働きながら取得する方法
介護業界で働きながら資格を取得するなら、「資格取得支援制度」の活用がおすすめです。職場によっては、資格取得に必要な費用の一部もしくは全額を負担してくれるところもあります。これから介護業界で働きたいとお考えの方は、資格取得支援制度を取り入れている介護施設を探すのも一つの手です。
資格取得支援制度のある職場の求人を探したい方は、介護業界の就職・転職に特化したエージェントのレバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)では、資格取得支援制度を導入している介護事業所の求人を多数取り扱っています。実際の職場の雰囲気や人間関係などを、アドバイザーに聞いてチェックできるので、入社後のミスマッチを防ぐことが可能です。
働きながら資格を取る方法教えます
介護の資格の難易度についてよくある質問
ここでは、介護の資格の難易度に関する質問に回答します。「どれから取得するべき?」「簡単に取れる介護の資格はあるの?」と気になっている方は、ぜひ参考にしてください。
介護に関する資格の難易度をランキングで教えて!
介護に関する公的資格を、取得の難易度が低い順にご紹介します。資格取得にかかる時間や期間、学習内容、試験の難易度で比較したランキングは、以下のとおりです。
- 1.認知症介護基礎研修
- 2.介護職員初任者研修
- 3.介護福祉士実務者研修
- 4.介護福祉士
- 5.介護支援専門員(ケアマネジャー)
「認知症介護基礎研修」は、数時間で取得できる資格なので、難易度は低いでしょう。「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者研修」は、取得に1~6ヶ月ほどかかりますが、試験に落ちる可能性は低い資格です。また、介護福祉士やケアマネジャーの試験を受けるには、特定の実務経験が3~5年必要。試験も年に1回のみしか実施されないため、取得の難易度は高いと感じるかもしれません。もっと詳しく知りたい方は、「介護に関する公的資格の具体的な難易度」もあわせてご一読ください。
独学で取れる介護の資格には何がありますか?
認知症介護基礎研修は、インターネット(e‐ラーニング)で1日で取得可能です。また、独学を希望する方は、「認知症ケア指導管理士(初級)」「認知症ライフパートナー」「在宅介護インストラクター」など、試験への合格のみで取得できる資格を選ぶのも良いでしょう。なお、「介護職員初任者研修」や「介護福祉士実務者研修」は、通学が必須の科目があるので、独学では取得できません。独学で取れる資格の種類や難易度について「介護資格は独学で取れる?取得の方法やメリット、デメリットをご紹介」にまとめています。
介護職員初任者研修の学習内容は難しいの?
介護職員初任者研修は、通学必須の科目が多く、講師に聞きながら学習を進められるため、「難しくてついていけない」と感じる可能性は低いでしょう。介護の初心者が、正しい知識やスキルを身につけるための研修なので、難易度は低めです。いきなり専門的な学習をすることはないので、無資格や未経験の方も、あまり不安に思わず挑戦してみてくださいね。介護職員初任者研修の学習内容は、「介護職員初任者研修の内容を解説!筆記試験や実技テストの難易度、取得方法」の記事で解説しているので、取得を検討している方は、ぜひチェックしてみてください。
まとめ
介護に関する資格は種類が多く、難易度もそれぞれ異なります。たとえば、認知症介護基礎研修は、1日で取得可能です。介護の代表的な公的資格である「介護職員初任者研修」や「介護福祉士実務者」は取得に1~6ヶ月程度かかりますが、誰でも受講できるため、無資格の方もチャレンジしやすいでしょう。
一方、介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)などには試験があり、実務経験などの受験資格が設けられているので、取得には数年かかります。
介護業界は、専門性を磨くための民間資格も多いのが特徴です。介護に関する知識や技術を身につけたい方は、自身の目的に合った資格を取得すれば、スキルアップできるでしょう。
レバウェル介護(旧 きらケア)は、無資格・未経験OKの求人を多く取りそろえています。教育制度の整った職場の求人も紹介可能です。また、介護業界でキャリアアップしたい方の相談にも対応しています。サービスはすべて無料なので、ぜひ気軽にご利用くださいね!
働きながら資格を取る方法教えます
先に資格を取りたい方へ
無料相談はこちら 資格取得支援の介護求人はこちら
資格取得支援の介護求人はこちら