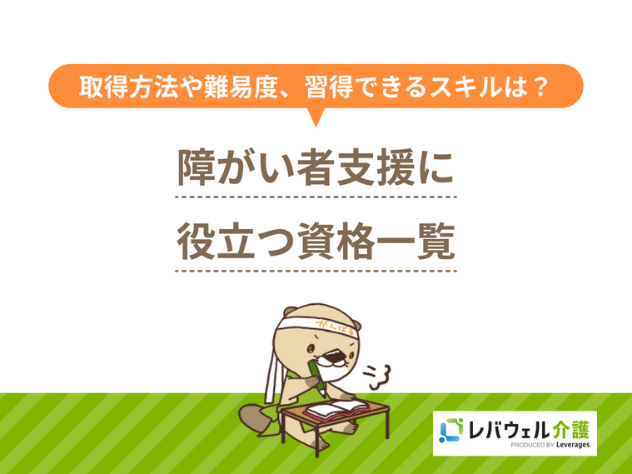
この記事のまとめ
- 障がい者支援に役立つ介護の資格は、介護職員初任者研修や介護福祉士など
- 障がい者支援に特化した公的資格は、強度行動障害支援者養成研修など
- 障がいのある方の訪問介護に役立つ資格は、重度訪問介護従業者養成研修など
「障がい者支援にはどんな資格が必要なの?」と気になる方もいるでしょう。無資格でも障がい者支援を行えますが、介護・相談援助・医療などに関する資格があれば、より専門的なサポートができます。この記事では、障がい者支援に役立つ国家資格11選と公的資格14選を一覧でご紹介。習得したスキルがどのような支援に活かせるのかを解説します。資格の取得方法や難易度もまとめたので、障がい福祉に興味がある方はご覧ください。
今の職場に満足していますか?
障がい者支援に役立つ資格
下記では、障がい者支援に役立つ国家資格11選と公的資格14選をご紹介します。「障がい者支援の仕事をするために資格を取得したい」という方は、どのような資格があるのかチェックしてみましょう。
障がい者支援に役立つ国家資格一覧
障がい者支援に役立つのは、福祉や医療などに関する国家資格です。国家資格11個を一覧にしたのでご覧ください。
国家資格を取得するには、専門科目の履修や実務経験が必要な場合が多くなっています。取得に時間がかかる分、専門性への評価が高いのが国家資格の特徴です。
障がい者支援に役立つ公的資格一覧
障がい者支援には、自治体や公的な機関が運営する公的資格も役立ちます。障がい者支援の仕事に携わりたい方におすすめの公的資格14個は以下のとおりです。
- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士実務者研修
- 強度行動障害支援者養成研修
- サービス管理責任者研修
- 重度訪問介護従業者養成研修
- 同行援護従業者養成研修
- 行動援護従業者養成研修
- 幼稚園教諭
- 教員免許
- 社会福祉主事
- 相談支援従事者初任者研修
- 手話通訳士
- 福祉用具専門相談員指定講習
- 福祉住環境コーディネーター
公的資格は民間資格よりも信頼度が高いので、取得すると一定のスキルがあることを証明できます。公的資格は、無資格や未経験から取得しやすいものが多いのも魅力です。まず初心者向けの公的資格を取得して、さらに上位の公的資格や国家資格の取得を目指せば、段階的にスキルアップできるでしょう。
この記事では、上記でご紹介したそれぞれの資格の取得方法や難易度、どのような支援に活かせるのかを解説するので、ぜひ参考にしてください。
今の職場に満足していますか?
代表的な介護の資格
障がいのある方の生活を身近で支えたい方には、介護系の資格の取得がおすすめです。ここでは、高齢者の方や障がいのある方の支援に役立つ介護の資格を3つご紹介します。
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修では、高齢者の方や障がいがある方のケアの基礎を学べます。研修のカリキュラムは約130時間で、1~3ヶ月程度で取得可能です。要件はないので誰でも受講できます。比較的難易度が低いので、介護・福祉の仕事に興味がある方が、最初に取得することも多い資格です。
介護職員初任者研修については、「介護職員初任者研修とは?費用を抑えて取得する方法や資格のメリットを解説」の記事を参照してください。
介護福祉士実務者研修
介護福祉士実務者研修は、前述の初任者研修の上位にあたる資格です。研修のカリキュラムは約450時間で、取得には6ヶ月程度かかります。実務者研修も受講要件はないので、無資格の方も受講可能です。医療的ケアの科目では、たんの吸引や経管栄養の処置も学ぶので、障がい者支援に役立つでしょう。
介護福祉士実務者研修の詳細は、「介護福祉士実務者研修とは?初任者研修との違いや取得するメリットを解説!」でご確認ください。
介護福祉士
介護福祉士は、介護系で唯一の国家資格。社会福祉士及び介護福祉士法に基づく、名称独占の資格です。介護福祉士国家試験に合格することで、資格を取得できます。介護福祉士は、大学や専門学校に通って受験する方法と、実務経験を積んで受験する方法があります。
厚生労働省の「第35回介護福祉士国家試験合格発表」によると、2023年の介護福祉士国家試験の合格率は84.3%でした。試験を受けるには受験資格を満たす必要がありますが、合格率は比較的高いので、国家資格のなかでは取得のハードルが低めです。
介護福祉士は、福祉系の職場で評価が高い資格で、取得すると転職の選択肢が増えたり、給与アップを狙えたりします。もっと詳しく知りたい方は、「介護福祉士国家資格とは?取得方法や受験資格を解説」を参考にしてください。
出典
厚生労働省「第35回介護福祉士国家試験合格発表」(2024年1月18日)
▼関連記事
介護資格の種類一覧まとめ!取得のメリットや難易度を解説します
障がいのある方の介護・支援に特化した資格
ここでは、障がい者支援に特化した資格を2つご紹介します。障がい者支援の専門的なスキルを身につけたい方は、チェックしておきましょう。
強度行動障害支援者養成研修
強度行動障害支援者養成研修は、自傷行為や暴力など、日常生活において危険な行動障害(強度行動障害)がある方を支援するためのスキルを習得する資格です。基礎研修と実践研修の2つに分かれています。
基礎研修のカリキュラムは約12時間で2日で取得可能です。受講に要件はありませんが、主に障がい者支援に携わる方を対象としています。実践研修の受講要件は基礎研修の修了で、主に計画作成担当者が受講対象です。
強度行動障害の状態にある方の多くは、知的障がいや自閉スペクトラム症の障がい特性から、他人への不信感・不安などを感じながら生活しています。環境を整えて適切な支援を行うことで、強度行動障害の状態を落ち着かせることが可能です。強度行動障害支援者養成研修は、障がいのある方の特性を理解し、穏やかに暮らせるよう支援することに役立つ資格といえます。
出典
公益財団法人東京都福祉保健財団「強度行動障害支援者養成研修事業」(2024年1月18日)
サービス管理責任者研修
サービス管理責任者研修は、障がい福祉サービスを提供する事業所の責任者として働くための資格です。サービス管理責任者になるには、基礎研修と実践研修の両方を修了する必要があります。基礎研修・実践研修にはそれぞれ要件があり、実務経験などが必要なので、両方修了するには3年以上かかるでしょう。
サービス管理責任者は、生活介護や施設入所支援、就労支援など、活躍の場が多くあります。障がいのある児童の支援を指揮する「児童発達支援管理責任者」になる際にも、サービス管理責任者研修の修了が必要です。取得の難易度や担当業務の専門性が高い資格なので、障がい者支援のプロフェッショナルになりたい方は、将来の目標にすると良いかもしれません。
出典
厚生労働省「社会保障審議会障害者部会(第135回)」(2024年1月18日)
▼関連記事
障害者施設で働くにはどんな資格が必要?仕事内容や働くメリットも紹介
今の職場に満足していますか?
障がいのある方の訪問介護に役立つ資格
下記では、障害がある方の訪問系サービスに特化した公的資格を3つご紹介します。自宅で生活する障がい者の方の支援に興味がある方は、ぜひご一読ください。
重度訪問介護従業者養成研修
重度訪問介護従業者養成研修は、障害支援区分4以上で、重度の肢体不自由・知的障がい・精神障がいがある方の訪問介護に特化した資格です。研修は、基礎課程と追加課程に分かれていますが、両方一緒に取得するのが一般的。基礎課程・追加課程・医療的ケアの3つを2~3日で修了できる統合過程を採用しているスクールもあります。
重度訪問介護従業者養成研修の基礎課程を修了したら、障害支援区分4・5の利用者さんに重度訪問介護のサービスを提供可能です。追加課程を修了したら、障害支援区分6までの利用者さんにサービス提供ができるようになります。重度訪問介護従業者養成研修に受講要件はなく、基礎課程・追加課程のどちらも約10時間で取得可能です。
重度訪問介護について詳しく知りたい方は、「重度訪問介護に必要な資格とは?研修のカリキュラムや難易度、費用を解説!」の記事をご覧ください。
同行援護従業者養成研修
同行援護従業者養成研修は、視覚障がいがあり、1人で移動するのが困難な方の外出を支援するための資格です。一般課程と応用課程に分かれています。
一般課程の学習時間は20時間前後なので、3日ほどで取得可能です。誰でも受講でき、取得すると同行援護に携われます。応用課程は、一般課程を修了した人などが受講可能。約12時間のカリキュラムは、公共交通機関を利用する実習といった専門的な内容です。
▼関連記事
同行援護従業者養成研修とはどんな資格?取得方法やカリキュラム内容を紹介
行動援護従業者養成研修
行動援護従業者養成研修は、行動援護に特化した資格です。カリキュラムは24時間前後で、4日ほどで取得できます。行動援護とは、知的障がいまたは精神障がいにより障害支援区分3以上の認定を受け、1人で行動するのが困難な方に、外出時や外出前後の支援を行う仕事です。
▼関連記事
行動援護従業者養成研修とは?受講要件やカリキュラム、メリットなどを解説
出典
厚生労働省「第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年1月18日)
厚生労働省「障害福祉サービスについて」(2024年1月18日)
今の職場に満足していますか?
障がいのある児童の支援に役立つ資格
ここでは、障がいのある児童の支援に役立つ3つの資格をご紹介します。「障がい児やその家族の支援がしたい」と考えている方は、参考にしてください。
保育士
保育士は、児童福祉法に基づく名称独占の国家資格です。指定の大学や専門学校を卒業するか、保育士試験に合格することで取得できます。保育士試験の受験資格を得るには、高校卒業後2年以上実務経験を積むか、一般の大学や専門学校などを卒業する必要があるでしょう。
こども家庭庁の「保育士試験の実施状況(令和4年度)」をもとに算出した2022年度の保育士試験の合格率は約30%なので、取得の難易度は高めと感じるかもしれません。
障がい福祉分野では、発達支援センターや放課後等デイサービスなどで、障がいのある乳幼児の支援や保護者への助言を行う際に役立つ資格です。
幼稚園教諭
幼稚園教諭として働くには、幼稚園教諭の免許状が必要です。免許状には、一種・二種・専修免許状の3種類があります。一種免許状は専門の大学を、二種免許状は専門の短期大学を卒業することで取得可能です。専修免許状の取得には、博士課程の修了が必要になります。幼稚園教諭の資格は、保育士同様、障がいのある幼児が利用する施設で働く際に役立つでしょう。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「幼稚園教員」(2024年1月18日)
教員免許
大学などで所定の単位を履修することで、教員免許状を取得できます。教員免許は、障がいのある児童が通う、放課後等デイサービスでの仕事などに役立つ資格です。なお、特別支援学校の教員として働くためには、追加で「特別支援学校教諭免許状」を取得する必要があります。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「小学校教員」(2024年1月18日)
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「特別支援学校教員、特別支援学級教員」(2024年1月18日)
今の職場に満足していますか?
障がいのある方の相談支援に役立つ資格
障がいのある方が、安心して日常生活を送ったり、必要なサービスを利用したりするために、相談支援は重要な役割を果たしています。以下では、障がいがある方の相談支援に役立つ5つの資格をご紹介するので、「相談援助を通じて障がい者の方に寄り添いたい」という方はご覧ください。
社会福祉士
社会福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく、名称独占の国家資格です。社会福祉士国家試験に合格することで取得できます。受験資格を得るには、福祉系大学等の卒業もしくは相談援助業務の実務経験などが必要です。厚生労働省の「第35回社会福祉士国家試験合格発表」によると、2023年の社会福祉士国家試験の合格率は44.2%でした。
社会福祉士は、障がいのある方が福祉サービスを利用するための相談に乗るなど、障がい福祉の分野で広く活躍しています。適切な相談援助を行うことは、障がいのある方の権利擁護にもつながるので、障がい者支援において重要な役割を担っているといえるでしょう。
社会福祉士の資格については、「社会福祉士資格を取得する7つのメリットとは?取得方法やルートも解説!」の記事にまとめています。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[社会福祉士国家試験]受験資格(資格取得ルート図)」(2024年1月18日)
厚生労働省「第35回社会福祉士国家試験合格発表」(2024年1月18日)
精神保健福祉士
精神保健福祉士は、精神保健福祉士法に基づく名称独占の国家資格です。精神保健福祉士国家試験に合格することで取得できます。保健福祉系大学等の卒業や養成施設等の卒業や、相談援助業務の実務経験などが受験資格です。厚生労働省の「第25回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します」によると、2023年の精神保健福祉士国家試験の合格率は71.1%でした。
精神保健福祉士は、精神科病院などで精神に障がいがある方の相談に乗り、社会復帰や日常生活を支援します。
出典
厚生労働省「精神保健福祉士について」(2024年1月18日)
厚生労働省「第25回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します」(2024年1月18日)
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[精神保健福祉士国家試験]受験資格(資格取得ルート図)」(2024年1月18日)
社会福祉主事
社会福祉主事は、社会福祉施設で特定の業務を行う際に必要になる任用資格です。大学や養成施設の卒業、都道府県講習会の受講などで取得できます。ただし、知的障害者福祉司や身体障害者福祉司になるには、2年以上の実務経験も必要です。
社会福祉主事は、障がいがある方の相談援助に役立つ資格といえます。
出典
厚生労働省「ページ8:福祉主事について」(2024年1月18日)
厚生労働省「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」(2024年1月18日)
公認心理師
公認心理師は、公認心理師法に基づく名称独占の国家資格。2017年に誕生した、心理学に関する唯一の国家資格です。公認心理師国家試験に合格すると取得できます。大学院での科目履修や、4年制大学卒業後に2年以上の実務経験を積むことが受験資格となっており、受験のハードルは高めです。
厚生労働省の「第6回公認心理師試験(令和5年5月14日実施)合格発表について」によると、2023年の公認心理師国家試験の合格率は73.8%でした。
公認心理師の活躍の場は幅広く、障がい者施設だけではなく、教育現場などで障がいのある方の心理的な支援に携わる際にも役立つ資格です。
出典
厚生労働省「公認心理師」(2024年1月18日)
厚生労働省「公認心理師試験の受験を検討されている皆さまへ」(2024年1月18日)
厚生労働省「第6回公認心理師試験(令和5年5月14日実施)合格発表について」(2024年1月18日)
相談支援従事者初任者研修
相談支援従事者初任者研修は、相談支援専門員として働くために必要な資格です。受講するには、相談支援の実務経験が必要になります。また、相談支援専門員として働き続けるためには、相談支援従事者初任者研修の修了後も、5年ごとに研修を受ける必要があるようです。
相談支援専門員は、障害がある方の相談に乗り、サービス利用計画の作成などを行う職種。相談支援事業所や基幹相談支援センターなどで働いています。
相談支援従事者初任者研修の取得方法や相談支援専門員の仕事内容については「相談支援従事者初任者研修の受講資格とは?必要な実務経験や資格概要を解説」「相談支援専門員に必要な資格は?初任者研修や実務経験について解説」をご覧ください。
出典
東京都福祉局「相談支援従事者研修」(2024年1月19日)
▼関連記事
相談援助とは?仕事内容や介護職との違い、必要な資格を解説
今の職場に満足していますか?
今の職場に満足していますか?
障がい者支援に役立つ医療系の資格
障がいのある方が充実した生活を送るうえで、看護師やリハビリ専門職などの医療職は重要な役割を担っています。障がい者支援に役立つ6つの国家資格を下記にまとめたので、「医学的な観点から障がい者支援を行いたい」と考えている方は参考にしてください。
看護師
看護師は、保健師助産師看護師法に基づく業務独占の国家資格です。看護学校で3年以上専門科目を学び、看護師国家試験に合格すれば、看護師免許を取得できます。厚生労働省の「第109回保健師国家試験、第106回助産師国家試験及び第112回看護師国家試験の合格発表」によると、2023年の看護師国家試験の合格率は90.8%でした。
障がい者支援における看護師の仕事内容は、健康管理やリハビリテーションの支援、メンタルケアなどです。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「看護師」(2024年1月18日)
厚生労働省「第109回保健師国家試験、第106回助産師国家試験及び第112回看護師国家試験の合格発表」(2024年1月18日)
▼関連記事
介護福祉士が看護師に転職する方法を解説!カリキュラムは免除されるの?
理学療法士(PT)
理学療法士(PT)は、理学療法士及び作業療法士法に基づく名称独占の国家資格です。専門学校や大学で3年以上専門科目を学ぶと、理学療法士国家試験の受験資格を得られます。厚生労働省の「第58回理学療法士国家試験及び第58回作業療法士国家試験の合格発表について」によると、2023年の合格率は87.4%でした。
理学療法士は、身体の障がいがある方に対して、機能回復や悪化の予防を目的に、リハビリテーションの支援を行う職種です。
出典
公益社団法人日本理学療法士協会「理学療法士を知る」(2024年1月18日)
厚生労働省「第58回理学療法士国家試験及び第58回作業療法士国家試験の合格発表について」
作業療法士(OT)
作業療法士(OT)は、理学療法士及び作業療法士法に基づく名称独占の国家資格です。専門学校や大学で3年以上専門科目を学ぶと、作業療法士国家試験の受験資格を得られます。厚生労働省の「第58回理学療法士国家試験及び第58回作業療法士国家試験の合格発表について」によると、2023年の合格率は83.8%でした。
作業とは、食事やトイレ、家事など、日常生活で行う動作全般のこと。作業療法士は「作業」に重点を置いて、障がいのある方の心身機能の回復を支援します。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「作業療法士(OT)」(2024年1月18日)
厚生労働省「第58回理学療法士国家試験及び第58回作業療法士国家試験の合格発表について」(2024年1月18日)
言語聴覚士(ST)
言語聴覚士(ST)は、言語聴覚士法に基づく名称独占の国家資格です。専門学校や大学で3年以上専門科目を学ぶことで、言語聴覚士国家試験を受験できます。厚生労働省の「第25回言語聴覚士国家試験の合格発表について」によると、2023年の合格率は67.4%でした。
言語聴覚士は、ことばでコミュニケーションを取るうえで障がいがある人や、聴覚に障がいがある人の支援を行います。食べ物を噛んだり飲み込んだりする「嚥下機能」の問題にも対応する職種です。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「言語聴覚士」(2024年1月18日)
厚生労働省「第25回言語聴覚士国家試験の合格発表について」(2024年1月18日)
義肢装具士(PO)
義肢装具士(PO)は、義肢装具士法に基づく業務独占の国家資格です。義肢装具士国家試験の受験ルートはさまざまですが、いずれの場合も義肢装具士養成施設で1~3年学習する必要があります。厚生労働省の「第36回義肢装具士国家試験の合格発表について」によると、2023年の義肢装具士国家試験の合格率は81%でした。
義肢装具士は、医師の指示のもと、身体に障がいのある方が使用する義肢や装具を製作します。義肢とは義手や義足などのことで、装具は麻痺や変形がある方の身体機能を補助するための道具のことです。義肢や装具の製作に携わり、身体に障がいがある人が自立した生活を送るための支援を行うのが、義肢装具士の役割といえます。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「義肢装具士」(2024年1月18日)
厚生労働省「第36回義肢装具士国家試験の合格発表について」(2024年1月18日)
視能訓練士(CO)
視能訓練士(CO)は、視能訓練士法に基づく業務独占の国家資格です。専門学校や大学で1~4年専門科目を学び、視能訓練士国家試験に合格することで取得できます。厚生労働省の「第53回視能訓練士国家試験の合格発表について」によると、2023年の視能訓練士国家試験の合格率は89.3%でした。
視能訓練士は、視能矯正や視能検査を行い、視力や見え方に問題がある方を支援します。小児から高齢者まで幅広い年齢層と関わる仕事です。視覚の発達段階にある小児には視能訓練を行い、正常な視機能の獲得を支援します。視能訓練士は、病院や眼科診療所において、視覚に障がいがある方のサポートを行うための資格です。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「視能訓練士」(2024年1月18日)
厚生労働省「第53回視能訓練士国家試験の合格発表について」(2024年1月18日)
▼関連記事
【福祉系のおすすめ資格一覧】20種類を紹介!取得方法や難易度も解説
障がい者支援に役立つそのほかの資格
ここでは、「手話通訳士」「福祉用具専門相談員指定講習」「福祉住環境コーディネーター」という3つの公的資格をご紹介します。
手話通訳士
手話通訳士は、厚生労働大臣が認定する公的な資格です。手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)に合格して登録すると、手話通訳士になれます。20歳以上または受験する年の年度末までに20歳になる人であれば、誰でも受験可能です。
厚生労働省の「第33回(令和4年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格発表について」によると、2022年度の手話通訳技能認定試験の合格率は13.3%なので、難易度は高いでしょう。
手話通訳士は、聴覚・言語機能・音声機能に障がいがあり、声でコミュニケーションを取るのが難しい方を、手話を活用して支援します。聴覚などに障がいがある方の支援に役立つ資格ですが、手話通訳だけで生計を立てている人は少ないようです。
出典
厚生労働省「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)について」(2024年1月18日)
厚生労働省「第33回(令和4年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格発表について」(2024年1月18日)
福祉用具専門相談員指定講習
福祉用具専門相談員指定講習は、都道府県知事が指定する公的資格です。福祉用具専門相談員として働くために必要になります。講習のカリキュラムは50時間なので、7日ほどで取得できるようです。要件はなく、誰でも受講できます。
福祉用具専門相談員は、障がいのある方やご家族に対して、福祉用具選びのアドバイスや使用方法の説明などを行う職種です。詳しくは、「福祉用具専門相談員とは?仕事内容や資格の取得方法、給与、将来性を解説」の記事をご覧ください。
福祉住環境コーディネーター
福祉住環境コーディネーターは、東京商工会議所が認定する公的資格です。福祉住環境コーディネーター検定試験に合格すると取得できます。1~3級があり、いずれも受験要件はありません。
福祉住環境コーディネーター検定試験2・3級の合格率は35~45%程度です。1級の合格率は約5%とかなり低くなっています。福祉住環境コーディネーターは、障がいのある方の住環境の整備・改善に役立つ資格です。
今の職場に満足していますか?
出典
厚生労働省「障害福祉のお仕事図鑑」(2024年1月18日)
障がい者支援の仕事探しにはレバウェル介護がおすすめ
障がい支援に関わる職場に転職したい方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください!レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護・福祉業界を専門とする転職エージェント。「障害者施設の求人」も多数取り揃えています。専任のアドバイザーがサポートするので、無資格や未経験の方も安心して転職活動を進められるのが利用のメリットです。
「障がい者支援に興味があるけど自分に務まるか不安…」といった方の相談にも対応しています。働きながら資格を取得したい方には、「資格取得支援の介護求人」もおすすめです。サービスはすべて無料なので、ぜひ活用してくださいね。
登録は1分で終わります!
障がい者支援の資格についてよくある質問
ここでは、障がい者支援の資格についてよくある質問に回答します。障がい福祉分野に興味がある方や、資格取得を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
障がい者に関わる仕事で役立つ資格は?
障がい者支援の仕事に役立つ国家資格は、介護福祉士や社会福祉士などです。短期間で資格取得したい方には、「介護職員初任者研修」や「重度訪問介護従業者養成研修」といった公的資格をおすすめします。この記事の「障がい者支援に役立つ資格」で一覧にまとめているので、あわせてご確認ください。
知的障がい者の生活支援員になるにはどんな資格が必要?
知的障がいがある方の生活をサポートする生活支援員には、資格要件が定められていません。そのため、無資格や未経験の方も、知的障がいのある方が利用する施設の生活支援員を目指せるでしょう。ただし、知的障がいがある方の相談援助を行うには、知的障害者福祉司という任用資格が必要です。知的障害者福祉司の要件は、「社会福祉大学等の卒業」や「社会福祉主事任用資格+2年以上の実務経験」などとなっています。社会福祉主事について詳しく知りたい方は、「社会福祉主事」をチェックしてみてください。
まとめ
障がい者支援に役立つのは、介護や医療、相談援助などに関する資格です。国家資格では、介護福祉士や社会福祉士、看護師、理学療法士などが挙げられます。障がい者支援に役立つ公的資格は、「介護職員初任者研修」や「重度訪問介護従業者養成研修」などです。国家資格は取得に時間がかかる分、専門性が高いのが特徴。公的資格は、要件なく取得できるものが多く信頼性が高いので、無資格・未経験の方のスキルアップにおすすめです。
ひと口に障がい者支援といっても、「どのような支援がしたいのか」によって必要なスキルは異なります。「日常生活のサポートがしたい」という方は、介護系の資格を取得すると良いでしょう。社会参加の支援やメンタルケアに携わりたい場合、相談援助に関する資格が役立ちます。医学的なアプローチで障がい者支援をしたい方には、看護師やリハビリ専門職などの医療系の資格がおすすめです。
取得の難易度や活かせる職場は、資格ごとに異なります。「障がい者支援を行うために資格を取得したい」という方は、資格の特徴を理解して取得すれば、実務に活かせるでしょう。
レバウェル介護(旧 きらケア)には、教育制度が充実した障がい者施設の求人もあります。「障がいがある方の生活をサポートしたい」「障がい者施設の働き方を知りたい」という方は、気軽にご相談ください!
登録は1分で終わります!
 初任者研修(ヘルパー2級)の求人はこちら
初任者研修(ヘルパー2級)の求人はこちら