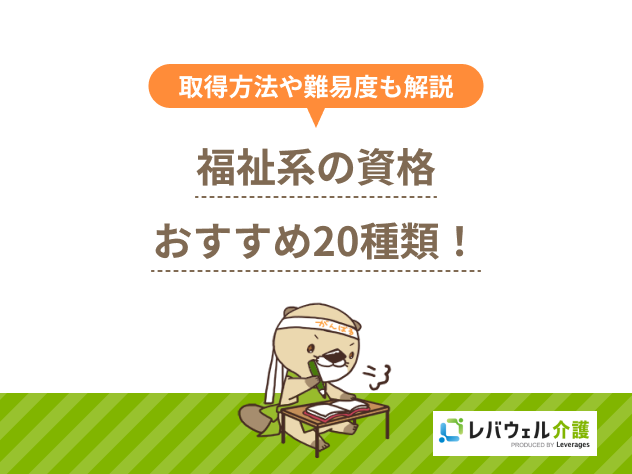
この記事のまとめ
- 介護業界でおすすめの福祉系の資格は「初任者研修」や「実務者研修」
- 相談援助業務におすすめの福祉の資格は「社会福祉士」や「精神保健福祉士」
- 資格を取得するメリットは、スキルアップ・キャリアアップに役立つこと
「福祉系の資格でおすすめのものは?」と気になる方もいるでしょう。福祉系の資格といっても、仕事の種類によっておすすめの資格は異なるため、自分の希望の職種で役立つ資格を取得することが大切です。この記事では、仕事の種類別や状況別のおすすめの資格や取得方法、難易度を解説しています。福祉系資格の取得を考えている方は、資格選びの参考にしてみてください。
介護資格の種類31選!取得方法やメリットを解説します →レバウェル介護の資格スクールはこちら福祉系の仕事の種類
福祉系の仕事と一口にいっても、種類が違えば業務内容は異なります。福祉系の仕事の種類は大きく分けて、以下の4つです。
- 高齢者や障がいのある方を支援する仕事
- 日常生活で困っている人を支援する仕事
- 子どもや親の生活を支える仕事
- 保育医療の面から支援する仕事
仕事によって支援対象者が異なるため、おすすめの資格が異なります。取得する資格を選ぶ際は、自身がどのように福祉の仕事に関わりたいのか、しっかりと考えることが重要です。
働きながら資格を取る方法教えます
▼関連記事
福祉の仕事にはどんな種類がある?介護や児童福祉、医療に関する32の職種
介護業界でおすすめの福祉系資格一覧
介護業界では、高齢により自立した生活が困難になってきた方を対象に支援を行います。介護職は、無資格でも就ける福祉の仕事ですが、資格を持っていれば利用者さんを援助するために必要な知識や技術が身についている証明になるので、積極的に資格を取得すると良いでしょう。資格があると、転職やキャリアアップに有利になったり、給与アップにつながったりする可能性もあります。
介護業界で働く際に役立つおすすめの資格は、以下のとおりです。
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修は、介護職が未経験の方も取得できる資格で、介護の基礎的な技術やスキルが習得できます。介護職の中でも、1人で身体介護を行うホームヘルパー(訪問介護員)になるには、介護職員初任者研修以上の資格が必須です。デイサービスや有料老人ホームなどでも、介護職員初任者研修の資格があれば自分の判断で身体介護を行えるので、取得して損はないといえます。
介護職員初任者研修を取得する方法と難易度
介護職員初任者研修の資格を取得するには、130時間のカリキュラムを「通学講座」か「通学と通信を併用した講座」で学び、筆記試験に合格しなければなりません。筆記試験は、カリキュラムの内容が押さえられていれば合格できる程度の難易度で、万が一不合格になっても追試に受かれば資格を取得できます。
介護職員初任者研修の資格は最短1ヶ月程度で取得でき、働きながらでも3~4ヶ月ほどで取得できるので、初めて福祉の資格を取る方にもおすすめです。
▼関連記事
介護職員初任者研修とはどんな資格?受講費用を抑える方法や取得のメリット
介護職員初任者研修の取得期間はどれくらい?最短で修了する方法を解説
首都圏限定!資格取得が無料!
転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!
レバウェル介護の資格スクール介護福祉士実務者研修
介護福祉士実務者研修は、介護職として働きながら介護福祉士を目指す場合、必要不可欠な福祉の資格です。介護職員初任者研修と同じく未経験者でも取得可能な資格で、基礎から応用まで幅広い介護知識とスキルを身につけられます。たん吸引や経管栄養といった医療的ケアも学べるほか、取得すればサービス提供責任者に就任することも可能なので、介護業界で着実にステップアップしていきたい方におすすめです。
介護福祉士実務者研修を取得する方法と難易度
無資格から介護福祉士実務者研修の取得を目指す場合、450時間のカリキュラムを「通学講座」か「通学と通信を併用した講座」で学ぶ必要があります。学習時間が長いので、通学と通信を併用して取得する人が多いようです。講座後の筆記試験は必須ではありませんが、実施しているスクールもあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。筆記試験を実施しているスクールで不合格になった場合、追試に合格すれば取得可能なので、比較的難易度は低いといえます。
なお、介護職員初任者研修の資格をすでに取得している方は、130時間分のカリキュラムを免除してもらえたり、受講費用を割引してもらえたりします。介護福祉士実務者研修の取得期間の目安は約6ヶ月と長めですが、実務経験を積んで介護福祉士を目指そうと考えている方には必須の資格です。
▼関連記事
介護福祉士実務者研修とは?資格取得のメリットや初任者研修との違いを解説
実務者研修の費用はいくら必要?無料で介護資格を取得する方法はあるのか
介護福祉士
介護福祉士は介護分野における唯一の国家資格です。取得した方は、高齢者福祉や障害者福祉の現場でリーダー的な存在として活躍することも可能。利用者さんの介護を行うだけでなく、高度な介護技術や専門的な知識を活かして職員の指導や教育を担うことができるでしょう。転職やキャリアアップに有利な資格なので、介護職として従事している人に人気があります。
介護福祉士を取得する方法と難易度
介護福祉士の資格を取得するには、介護福祉士国家試験に合格する必要があります。試験を受けるには、「介護福祉士実務者研修の修了+介護業務等の実務経験を3年以上実務経験を積む」「福祉系高校や介護福祉士養成施設に通う」のうち、いずれかの方法で受験資格を満たさなければなりません。
厚生労働省の「第36回介護福祉士国家試験合格発表」によると、2024年に実施された介護福祉士国家試験の合格率は、82.8%でした。合格率が高いため、しっかりと勉強して介護の技術と知識を身につけることで、合格を目指せるでしょう。介護業界でキャリアアップしたいなら、介護福祉士の資格を取得するのがおすすめです。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格」(2024年12月11日)
厚生労働省「第36回介護福祉士国家試験合格発表」(2024年12月11日)
▼関連記事
介護福祉士とは?仕事内容や資格の取得方法、試験概要をわかりやすく解説!
介護福祉士の受験資格を得るルートを解説!必要な実務経験や試験概要は?
介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護支援専門員はケアマネジャーとも呼ばれており、介護に携わる福祉の資格の中でも取得難易度が高いのが特徴です。ケアマネジャーは、介護が必要な高齢者のために要介護認定の書類を作成したり、利用者さんの状況に応じたケアプランの作成を行ったりします。ケアマネジャーには、居宅介護支援事業所で働く居宅ケアマネジャーや介護施設で働く施設ケアマネジャーなどの働き方があり、自分に合った職場を見つけられるでしょう。
ケアマネジャーはデスクワークが多く、現場の職員に比べて利用者さんと接する機会が少なめかもしれません。しかし、ケアプランを考えるには誰よりも利用者さんを把握しなければならないので、やりがいを求めて介護職員からケアマネジャーを目指す人もいます。
介護支援専門員を取得する方法と難易度
ケアマネジャーになるには、介護支援専門員実務研修受講試験に合格したうえで、その後に行われる研修を修了しなければなりません。介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格があるのは、以下のいずれかです。
- 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・看護師・薬剤師などの特定の資格を持っており、その分野で5年以上実務経験を積んだ人
- 介護施設などで相談援助業務に5年以上従事した人
上記いずれかの受験資格を満たすのは簡単ではありません。実務経験の要件を満たし、スクールの通学講座や通信講座を利用したり、独学で勉強したりして試験に合格すれば、介護支援専門員になれるでしょう。
厚生労働省の「第26回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」によると、2023年に実施された試験の合格率は21%で、近年の合格率は20%前後となっています。介護支援専門員実務研修受講試験の難易度は比較的高い傾向にありますが、やりがいを持って福祉の仕事を行いたい人にはおすすめの資格です。
出典
厚生労働省「第26回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」(2024年12月11日)
▼関連記事
ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどんな仕事?業務内容や役割を解説!
ケアマネジャーになるには?最短で何年?試験の受験資格や取得の流れを解説
認知症介助士
認知症介助士は、認知症を患っている方とのコミュニケーションの方法や心構え、適切な対応方法を身につけられる資格です。取得すれば、認知症ケアに特化したグループホームをはじめ、さまざまな介護施設で活躍できるでしょう。超高齢社会である日本では、認知症を患っている方も増えており、認知症介助士の需要が高まっています。
認知症介助士を取得する方法と難易度
認知症介助士を取得するには、検定試験に合格する必要があります。誰でも受験することができ、検定試験は選択肢式の全30問、受験料は3,300円です(2024年12月時点)。検定試験は、試験会場や自宅で受けられます。独学でも資格取得は可能ですが、セミナーを受講して目指す方法もあるので、自分にあった勉強方法を選んでみてください。合格率は80%程度と比較的高いので、「これから介護業界で活躍したい」と考えている方は、積極的に取得を目指してみると良いでしょう。
出典
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「認知症介助士」(2024年12月11日)
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「認知症介助士検定試験」(2024年12月11日)
▼関連記事
【認知症介護の資格一覧】取得方法や試験の難易度、習得できるスキルを解説
介護予防運動指導員
介護予防運動指導員は、東京都健康長寿医療センターが認定を行っている資格です。筋力トレーニングや認知症予防、転倒予防など、利用者さんの身体機能の低下予防のための知識や技術を学びます。介護予防運動指導員は、利用者さん一人ひとりに合った介護予防プログラムを企画し、運動指導を行い、利用者さんのQOL向上に貢献するやりがいのある仕事です。介護予防の専門的な知識やスキルが身につくので、介護業界での転職にも役立つおすすめの資格といえます。
介護予防運動指導員を取得する方法
介護予防運動指導員を取得するには、東京都健康長寿医療センター研究所が定めたスクールの講座を受講する必要があります。研修時間は計33時間で、取得には2~5日程度掛かるようです。受講後に修了試験がありますが、しっかりと勉強しておけば合格は難しくないでしょう。
介護予防運動指導員の講座を受講するには、「介護職員初任者研修の取得と、2年以上実務経験を積んでいること」「介護職員基礎研修課程・介護福祉士実務者研修・介護福祉士・介護支援専門員・社会福祉士いずれかの資格を取得していること」「医療関係の国家資格等を取得していること」などから、いずれかの条件を満たす必要があります。
▼関連記事
介護予防運動指導員のメリットとは?資格の概要と取得方法もご紹介!
レクリエーション介護士
レクリエーション介護士の資格取得では、利用者さんとのコミュニケーション方法やレクリエーションの企画・実施のスキルを身につけられます。レクリエーション介護士は2級と1級に分かれており、1級ではレクリエーションに関するより専門性の高い知識やスキルを身につけることが可能です。
レクリエーション介護士は、「人前に出るのが苦手」「レクリエーションのレパートリーを増やして、もっと利用者さんに楽しんでもらいたい」と考えている方におすすめの資格です。
レクリエーション介護士を取得する方法と難易度
レクリエーション介護士2級を取得するには、講座を受講する必要があります。通信講座と通学講座があるので、自身のスケジュールに合った方法を選択しましょう。レクリエーション2級の講座は誰でも受講できます。
レクリエーション介護士1級を取得するには、講座受講後に実技試験・筆記試験に合格し、現場実習を経験しなければなりません。1級の講座を受講できるのは、2級を取得している方です。
レクリエーション介護士の難易度はそれほど高くありません。より質の高い介護を提供したいと考えている方は、積極的に資格取得を目指してみると良いでしょう。詳しくは、「レクリエーション介護士とは?資格の取得方法やメリットを分かりやすく解説」の記事で解説しているので、こちらもあわせてご覧ください。
介護事務に関する資格
介護事務は、介護の現場をサポートする重要な仕事です。介護サービスの利用料を市区町村に利用者さんに請求するのが主な仕事で、備品管理や書類整理といった一般事務もこなします。現場で働く介護職員と比べ、夜勤や休日出勤が少なく、生活リズムの整った働き方ができるのが特徴です。介護事務の仕事をするうえで特定の資格の取得は必須ではありません。とはいえ、取得すれば仕事に役立てられるので、事務職として福祉に携わりたい方には、資格の取得がおすすめです。
介護事務に関する資格を取得する方法と難易度
介護事務におすすめの資格は、「介護報酬請求事務技能検定試験」「介護情報実務能力認定試験」「介護事務管理士(R)」「ケアクラーク(R)」などです。資格によって取得方法は異なりますが、試験の合格により取得できる傾向があります。事前に勉強し、介護保険や介護報酬請求に関する知識をしっかり身につけておけば、取得はそれほど難しくないでしょう。
介護事務におすすめの資格の取得方法は、「介護事務に資格は必要?合格率や取得方法、仕事に活かせるスキル」で解説しているので、あわせてご一読ください。
▼関連記事
介護事務ってどんな仕事?資格を取得するメリットとは
障害者福祉・保健医療におすすめの福祉系資格
福祉の仕事の中でも障害者福祉や保健医療の分野で活躍したい人には、以下の資格がおすすめです。
作業療法士
作業療法士はOT(Occupational Therapist)とも呼ばれており、生活や仕事に必要な身体機能の回復を促すための、知識や技術を身につけられる国家資格です。障がいがある方の状況に応じ、食事の際の基本動作や家事の動作などの訓練プログラムを立てます。障がいがある方の身体機能の維持・回復を支援するのが主な仕事です。作業療法士は、障害者福祉や高齢者福祉の仕事で活躍したい人にはおすすめの資格といえます。
作業療法士を取得する方法と難易度
作業療法士の資格を取得するには、作業療法士の養成課程のある大学や短大、作業療法士養成施設に3年以上通って受験資格を得てから、作業療法士国家試験に合格する必要があります。
厚生労働省の「第59回理学療法士国家試験及び第59回作業療法士国家試験の合格発表について」によると、2024年の作業療法士国家試験の合格率は84.1%と高い水準でした。
出典
厚生労働省「第59回理学療法士国家試験及び第59回作業療法士国家試験の合格発表について」(2024年12月11日)
理学療法士
理学療法士はPT(Physical Therapist)とも呼ばれており、事故や病気にあった人のリハビリを行ったり、高齢者の身体機能を改善したりするための技術を身につけられる国家資格です。主に運動療法を行い、身体機能の維持や向上を支援します。理学療法士の資格は、障害者福祉や高齢者福祉の現場で、身体に障がいがある方のリハビリに携わりたい人におすすめです。
理学療法士を取得する方法と難易度
理学療法士になるには、大学や専門学校などに3年以上通って受験資格を得た後、理学療法士国家試験に合格しなければなりません。
厚生労働省の「第59回理学療法士国家試験及び第59回作業療法士国家試験の合格発表について」によると、2024年の理学療法士国家試験の合格率は、89.2でした。試験の合格率は年度によってばらつきがあり、約70~90%ほどで推移しているようです。
出典
厚生労働省「第59回理学療法士国家試験及び第59回作業療法士国家試験の合格発表について」(2024年12月11日)
言語聴覚士
言語聴覚士はST(Speech-Language-Hearing Therapist)とも呼ばれており、言語機能や聴覚機能などに障がいのある方の、評価や訓練を行うための国家資格です。医師や歯科医師に指示を仰いで、聴力・言語機能だけでなく、摂食の問題や嚥下障がいについてのアドバイスや訓練も行います。言語聴覚士は、福祉の現場でコミュニケーションや食事摂取などの支援がしたい方におすすめです。
言語聴覚士を取得する方法と難易度
言語聴覚士になるには、指定の大学や養成施設に通ったり、一般大学卒業後に大学院で専攻科に進んだりして受験資格を得た後、言語聴覚士国家試験に合格しなければなりません。
厚生労働省の「第26回言語聴覚士国家試験の合格発表について」によると、2024年の言語聴覚士国家試験の合格率は72.4%でした。試験の合格率は比較的高く、難易度はそれほど高くないといえます。
出典
厚生労働省「第26回言語聴覚士国家試験の合格発表について」(2024年12月11日)
義肢装具士
義肢装具士はPO(Prosthetist and Orthotist)と呼ばれることもあります。医師の指示のもとで義肢や装具を製作したり、利用者さんの身体に合うか確認したりする技能を持つことを証明する国家資格です。高齢者福祉や障害者福祉の分野で、身体に障がいがある方を間接的に支援したい方は、義肢装具士の資格取得を目指す選択肢もあります。
義肢装具士を取得する方法と難易度
義肢装具士になるには、義肢装具士養成施設を卒業してから義肢装具国家試験に合格しなければなりません。
義肢装具国家試験を受験するには、「義肢装具士養成施設で3年以上勉強すること」「大学で1年以上(高等専門学校は4年以上)勉強し、指定の科目を履修したあと、養成施設で2年以上勉強すること」「義肢・装具製作技能士を取得したあと、養成施設で1年以上勉強すること」「外国の義肢装具養成所を卒業した人や免許を取得した人が厚生労働省の認定を受けること」から、いずれかの条件を満たす必要があります。
厚生労働省の「第37回義肢装具士国家試験の合格発表について」によると、2024年に実施された義肢装具士国家試験の合格率は、79.4%でした。専門知識を身につけてから国家試験を受けるためか、合格率は高い傾向にあります。
出典
厚生労働省「第37回義肢装具士国家試験の合格発表について」(2024年12月11日)
看護師・准看護師
看護師・准看護師は、病院やクリニックなどで患者さんを支援するのに必要な資格です。医療機関のみではなく、介護施設でも看護職員は活躍しています。看護師は国家資格ですが、准看護師は各都道府県により発行される免許であり、国家資格ではありません。看護師・准看護師は、「医療面から福祉の役に立ちたい」と考えている方におすすめです。
看護師・准看護師を取得する方法と難易度
看護師資格を取得するには、看護師国家試験への合格が必要です。四年制の看護系大学や三年制の看護系短大、看護師養成所、5年一貫看護師養成課程校いずれかに通うことで、看護師国家試験の受験資格をクリアできます。
厚生労働省の「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験及び第113回看護師国家試験の合格発表」によると、2024年の看護師国家試験の合格率は87.8%でした。
准看護師資格を取得するには、各都道府県で実施される准看護師試験に合格する必要があります。准看護師試験を受けるには、准看護師養成所に2年、もしくは高校の衛生看護科に3年通わなければなりません。
同省の「令和5年度准看護師試験の実施状況」によると、2024年に実施された准看護師試験の合格率は98.2%と、非常に高くなっています。
出典
厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験及び第113回看護師国家試験の合格発表」(2024年12月11日)
厚生労働省「令和5年度准看護師試験の実施状況」(2024年12月11日)
▼関連記事
【障がい者支援に役立つ資格一覧】取得方法や難易度、習得できるスキルは?
相談援助・支援業務におすすめの福祉系資格
日常生活で困っている人や、子どもやその親の生活を支えるために、相談援助を行う仕事もあります。相談援助・支援業務におすすめの福祉系資格を以下で解説するので、チェックしてみてください。
社会福祉士
社会福祉士は、日常生活に課題を抱えるすべての人に対して、相談に乗ったり支援を行ったりするのに役立つ国家資格です。福祉や保健に関する知識を身につけられる資格で、取得すれば、社会福祉協議会や老人ホーム、児童相談所などさまざまな職場で活躍できます。社会福祉士は、相談者の課題の根本的な解決を支援したい方におすすめの資格です。
社会福祉士を取得する方法と難易度
社会福祉士になるには、社会福祉士国家試験に合格しなければなりません。大学を卒業していない方も、実務経験を積んで養成施設を卒業すれば、国家試験を受験できます。幅広い分野で活躍できる分、必要な知識が多いのが特徴です。
厚生労働省の「第36回社会福祉士国家試験合格発表」によると、2024年の社会福祉士試験の合格率は58.1%でした。資格取得を成功させるためには、計画的に勉強することが大切です。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[社会福祉士国家試験]受験資格」(2024年12月11日)
厚生労働省「第36回社会福祉士国家試験合格発表」(2024年12月11日)
▼関連記事
社会福祉士資格を取得する7つのメリットとは?取得方法やルートも解説!
精神保健福祉士
精神保健福祉士は、精神障がいがある方の社会復帰や生活支援を行うための国家資格です。病院の精神科で働く精神保健福祉士は、入院中の相談業務や関係機関と利用者さんの橋渡し役を担います。また、福祉の知識を活かして、介護施設の生活相談員といった職種に就くことも可能です。
精神保健福祉士を取得する方法と難易度
精神保健福祉士になるには、社会福祉士と同じように、一般大学を卒業後に実務経験を積んで養成施設に通ったり、福祉系大学で指定科目を履修したりしなければなりません。
厚生労働省の「第26回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します」によると、2024年の精神保健福祉士の国家試験の合格率は、 70.4%でした。近年の合格率は、60~70%程度で推移しています。精神保健福祉士と社会福祉士の試験内容は一部同じ箇所があり、科目免除が可能なので、社会福祉士を保有する方がチャレンジすることも少なくありません。両方の国家資格を取得することで、より幅広い福祉の仕事で活躍できます。
詳しくは、「精神保健福祉士とは?資格の取得方法や仕事内容、社会福祉士との違いを解説」の記事で解説しているので、こちらもぜひチェックしてみてください。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[精神保健福祉士国家試験]受験資格」(2024年12月11日)
厚生労働省「第26回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します」(2024年12月11日)
臨床心理士
臨床心理士の資格があれば、臨床心理学に基づいて、障がいがある方や高齢者、子どもの問題を心理的側面から支援できます。困っている人を心理的な面からサポートしたい人には、臨床心理士の資格がおすすめです。
臨床心理士を取得する方法と難易度
臨床心理士になるには、大学院や専門職大学院に通って指定の科目を履修してから、臨床心理士国家試験に合格しなければなりません。合格率は約60%とやや高い傾向にありますが、受験資格を満たすまでに時間が掛かるでしょう。
児童福祉司
児童福祉司は、児童相談所で児童やその保護者の相談に対応したり、援助したりするのに必要な任用資格です。
児童福祉司を取得する方法と難易度
児童福祉司になるには、児童福祉司任用資格を取得し、地方公務員試験に合格する必要があります。
児童福祉司任用資格を取得するには、「都道府県指定の養成施設を卒業し、講習会の課程を修了すること」「大学で心理学や教育学など指定の科目を履修し、1年以上相談援助の経験を積むこと」「医師・社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師のいずれかの資格を取得していること」「特定の職種として働き1~2年の実務経験を積むこと」などから、いずれかの条件を満たさなければなりません。
要件を満たして地方公務員試験を受けて合格し、児童相談所に配属される必要があるので、児童福祉司になる難易度は高いといえるでしょう。
出典
e-Gov法令検索「児童福祉法」(2024年12月11日)
福祉住環境コーディネーター
福祉住環境コーディネーターは、高齢者や障がいを抱える方が、快適な生活を送れるように、住宅環境についてアドバイスをする際に役立つ資格です。手すりの設置の提案や介護保険で住宅改修を行う際に理由書を作成したり、介護ベッドや車椅子についてアドバイスをしたりします。
福祉住環境コーディネーターを取得する方法と難易度
福祉住環境コーディネーターになるには、福祉住環境コーディネーター検定試験(R)に合格する必要があります。福祉住環境コーディネーターは1級から3級まであり、いずれの級も誰でも挑戦可能です。
福祉住環境コーディネーター検定試験(R)の2級・3級は、多肢選択式の90分間のテストです。1級は、多肢選択式と記述式の前後半制で各90分の試験を受けます。2023年度の福祉住環境コーディネーター検定試験(R)の合格率は、3級は40.9%、2級は38.1%、1級は14.5%でした。年度によって合格率は異なるので、あくまで参考としてご覧ください。
出典
東京商工会議所「福祉住環境コーディネーター検定試験(R)」(2024年12月11日)
福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員は、高齢者や障がいを抱える方の身体機能や認知機能をヒアリングして適切な福祉用具を提案したり、使用方法を指導したりするために必要な資格です。
福祉用具専門相談員を取得する方法と難易度
福祉用具専門相談員の資格は、福祉用具専門相談員指定講習(50時間)を受講し、修了試験に合格することで取得可能。比較的取得しやすい資格です。また、介護福祉士や社会福祉士、看護師など特定の資格を取得している方は、講習を受けなくても福祉用具専門相談員として活躍することができます。
出典
厚生労働省「第220回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2024年12月11日)
▼関連記事
福祉用具専門相談員とはどんな職種?仕事内容や必要な資格、年収を解説!
ガイドヘルパー(同行援護従業者・行動援護従業者)
ガイドヘルパーは1人で外出することが難しい方をサポートするのに役立つ資格です。ガイドヘルパーは、同行援護従業者や行動援護従業者とも呼ばれています。
ガイドヘルパーを取得する方法と難易度
ガイドヘルパーになるには、「同行援護従業者養成研修」「行動援護従業者養成研修」もしくは、自治体が運営する「全身性障害者移動支援従業者養成研修」などの資格のいずれかを取得する必要があります。
カリキュラムはそれぞれ異なりますが、講座を受講したり、演習を行ったりすることで資格を取得可能。難易度はそれほど高くないので、人の役に立ちたいと考えている方におすすめの資格です。なお、実際に行動援護に携わるためには、実務経験も必要になります。
出典
厚生労働省「第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年12月11日)
東京都福祉保健局「障害者(児)移動支援従業者養成研修 開講日程の御案内」(2024年12月11日)
▼関連記事
ガイドヘルパー(移動介護従事者)とは?必要な資格や仕事内容を解説
【状況別】おすすめの福祉系資格
福祉系の資格を取得するにあたって、自分にとって取得しやすい方法から選ぶのもおすすめです。ここでは、状況ごとにおすすめの福祉系資格を紹介します。
働きながら取得できる福祉系資格
働きながら資格を取得したい人におすすめなのが、介護職員初任者研修、介護福祉士、ケアマネジャーです。実際に介護職として働きながら取得している人が多い傾向があります。また、介護事務に関する資格や認知症介助士も試験に合格するだけで取得できるため、社会人からの取得のハードルが低い傾向にあるでしょう。
独学で取得できる福祉系資格
講習や通学が必要ない福祉系の資格は、自分で勉強して試験に合格すれば、独学でも取得可能です。たとえば、介護福祉士、ケアマネジャー、ケアクラーク、福祉住環境コーディネーターなどが挙げられます。
講習で取れる福祉系資格
試験がなく、講習を受けることで取得可能な福祉系の資格として、レクリエーション介護士2級、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修などが挙げられます。
認知症介護にまつわる資格は、「【認知症介護の資格一覧】取得方法や試験の難易度、習得できるスキルを解説」の記事でも紹介しているのであわせてチェックしてみてください。
受験資格なしの福祉系資格
受験資格がなく、誰でもすぐに受験可能な福祉系資格として、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、ケアクラーク、レクリエーション介護士2級、認知症介助士、福祉住環境コーディネーターなどが挙げられます。身につけたい知識や専門性に合わせて取得する資格を選択しましょう。
介護の実務経験なしで取れる資格
介護の実務経験なしで取れる資格は、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修などが代表的です。これらの資格は、実務経験がない方がキャリアアップや転職のために取得する傾向があります。また、認知症介護基礎研修は、介護の仕事を始める方が1年以内に取得を義務付けられている資格です。実務経験不要で1日で取得できます。
▼関連記事
介護職は無資格で働けなくなるの?認知症介護基礎研修の義務化について解説
取得費用が安い福祉系資格
講座がなく、試験の受験料と手数料のみで取得できる資格は、安く取得しやすい傾向があります。取得費用が安い福祉系資格として、介護福祉士やケアマネジャーなどが挙げられます。介護福祉士の受験料は18,380円、ケアマネジャーは自治体によりますが、2024年度の東京都での受験料は12,548円でした(払込手数料を含む)。
一方、養成学校や大学の卒業が要件となっている資格は、学費が掛かるので時間と費用が掛かる傾向があります。ただし、資格取得支援制度を活用することで安く取得できる場合があります。詳しくは、「介護職の資格取得支援制度とは?給付金の種類や利用するメリットを解説」で解説しているので、こちらもあわせてご覧ください。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]試験概要」(2024年12月11日)
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護支援専門員」(2024年12月11日)
福祉系の国家資格
福祉系の国家資格には、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保健師、助産師、義肢装具士、臨床心理士などがあります。国家資格は名称独占資格や業務独占資格があり、有資格者のみが職種を名乗ったり特定の業務に就いたりすることが可能です。専門性が保障されるので、手に職をつけたい方は取得を目指してみてはいかがでしょうか。
福祉系資格を取得するメリット
福祉系資格を取得するメリットとして、キャリアアップや収入アップなどが挙げられます。ここでは、取得のメリットを詳しく紹介するので、資格取得を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
スキルアップ・キャリアアップに役立つ
福祉系の資格を取得すると、スキルアップやキャリアアップに役立ちます。特に、国家資格を取得していると、現場のリーダーや職員の指導を任されたり、仕事の幅が広がったりする可能性が高まるでしょう。
給料がアップする
保有資格に応じて資格手当がつき、無資格者より給料が高くなる傾向があります。そのため、給料を上げる手段として資格取得を目指す人もいるようです。ただし、手当がつく資格の種類は職場によって異なるので、就業規則を確認してみましょう。
転職が有利になる
資格を持っていることで、その領域の専門性が保証されるため、即戦力とみなされて転職で有利に働く傾向があります。資格が必須要件になっている職種もあるので、なりたい職業がある人は必要な資格を取得しておくと良いでしょう。
適切なケアができるようになる
資格の勉強をする中で、福祉についての知識が身につきます。身につけた知識を現場の業務に活かすことで、利用者さんに対して適切な支援を行えるようになるのもメリットの一つです。
▼関連記事
介護の資格の難易度を種類ごとに解説!取得方法や試験の合格率、要件とは?
福祉の資格を取るなら通信講座がおすすめ
福祉の資格を取得するなら通信講座を利用してみましょう。自宅で試験を受けられたり、カリキュラムを受講したりするだけのものなら、働きながらでも資格を取得できます。通信講座を活用すれば、通学が必要な講座のスクーリング日数を減らせることも。自分のペースで福祉の資格取得を目指したい方は、通信講座の受講を検討してみてください。
福祉系の資格取得に関するよくある質問
ここでは、福祉系の資格取得に関するよくある質問に回答します。「福祉系の資格を取得したいけどどうすれば良いの?」と気になる方は、ぜひご覧ください。
福祉系資格を安く取得する方法はありますか?
制度は下記の制度を活用することで、福祉系資格に掛かる費用を抑えることができます。
- 職場に資格取得制度
- 教育訓練給付制度
- リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業
- ハローワークの職業訓練
ただし、資格の種類や利用条件によっては活用できない場合もあるので、取得したい資格や制度の必須要件を確認してみましょう。
大学生が取得できる福祉系資格はありますか?
福祉系の大学に通っている場合、社会福祉士や精神保健福祉士、介護福祉士を目指しやすいといえるでしょう。介護の仕事をしたい方や、将来ケアマネジャーを目指したい方は、介護福祉士の取得がおすすめです。福祉事業所や医療機関でソーシャルワーカーとして働きたい方や、介護施設の相談員を務めたい方は、社会福祉士が資格要件になっているので取得しておくと良いでしょう。
まとめ
福祉系の資格と一口にいっても、身につけたいスキルによっておすすめの資格は異なるので、自分の目指す職種に合った資格を取得することが重要です。
介護業界で活躍したい方には、「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者」「介護福祉士」がおすすめ。障害者福祉・保健医療に関わる職種に興味がある方は、「作業療法士」「理学療法士」「看護師・准看護師」などを取得すると良いでしょう。相談援助・支援業務を行いたい場合、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「臨床心理士」などの資格がおすすめです。
福祉系の資格を活かして働きたい方は、「レバウェル介護(旧 きらケア)」をご利用ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した就職・転職エージェントです。介護業界の多数の求人を取り扱っており、プロのアドバイザーが転職への不安や悩みなどの相談にも対応いたします。介護業界でのキャリアプランも相談できるため、「未経験・無資格でよく分からない…」という方も安心です。資格取得支援制度のある求人も豊富にあるので、「これから福祉系の資格を取得したい」という方も、お気軽にご登録ください。
働きながら資格を取る方法教えます
先に資格を取りたい方へ
無料相談はこちら