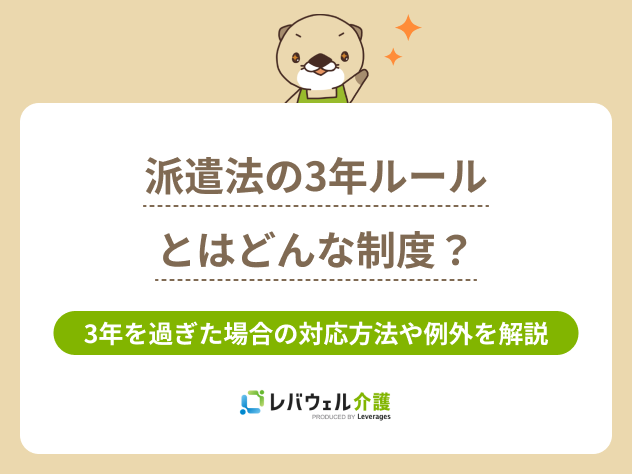
この記事のまとめ
- 派遣の3年ルールとは、派遣社員が同じ職場で働けるのは3年までという法律
- 派遣の3年ルールには、「事業所単位」「個人単位」の2つの期間制限がある
- 派遣社員が3年以上同じ職場に勤務するには、働き方を変える必要がある
「派遣の3年ルールってどんな制度なの?」という疑問をお持ちの方もいるでしょう。派遣の3年ルールとは、「派遣社員として同じ職場で働けるのは3年まで」という法律のことです。この記事では、派遣の3年ルールの対象者や例外となるケースを解説します。3年ルールの目的や、メリット・デメリットもまとめました。派遣社員が3年以上同じ職場で働き続ける方法もご紹介するので、参考にしてみてください。
介護派遣とは?メリット・デメリットや働くまでの流れ、実際に働いている方の声もご紹介社保即日加入できます!
労働者派遣法の3年ルールとは?
労働者派遣法の3年ルールとは、「有期雇用の派遣社員が同じ職場で働く期間が3年を超えてはいけない」という法律のことです。この法律は、2015年9月の労働者派遣法改正により設定されました。
労働者派遣法(第35条の3)では、労働者派遣の期間について次のように記載されています。
派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
有期雇用の派遣社員が同じ勤務先で3年以上働き続けるには、課や部署を異動するか、雇用形態を変更する必要があります。同じ職場で3年以上働く方法は、この記事の「派遣社員が同じ職場に3年以上勤務する方法は?」で解説しています。
出典
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(2024年12月24日)
3年ルールが作られた背景
3年ルールが作られた主な目的は、「派遣社員の雇用の安定」です。以前は、一部の業種には派遣期間の上限が設けられていませんでした。そのため、不安定な雇用形態で働き続けなければならないこともあったようです。そこで、国は3年ルールを設定して派遣先での直接雇用や派遣会社での無期雇用を促し、雇用の安定を目指しました。また、雇用形態による待遇の差を解消する意図もあったようです。
3年ルールの対象者
派遣の3年ルールの対象になるのは、派遣会社と有期雇用契約を結ぶ派遣社員のみです。「登録型派遣」は、有期雇用に該当します。ただし下記の場合は、例外となるのでチェックしておきましょう。
- 年齢が60歳以上である
- 有期プロジェクトに派遣されている
- 日数限定業務に従事している
- 産休・育休・介護休業の代替業務に派遣されている
- 派遣会社と無期雇用の契約を結んでいる
詳しくは、後述する「3年ルールの例外となる派遣労働者」で解説します。
社保即日加入できます!
3年ルールに定められている2つの期間制限とは

派遣の3年ルールに定められている期間制限には、「事業所単位の期間制限」と「個人単位の期間制限」の2つがあります。下記で一つずつ解説するので、違いを理解しましょう。
事業所単位の3年ルール
事業所単位の3年ルールとは、「同一の事業所が派遣労働者を受け入れられる期間は最大3年まで」という制限のことです。途中で派遣社員の入れ替わりがあった場合でも、同一の事務所で派遣社員が働ける期間は3年までとされています。途中から働き始めた派遣社員は、派遣期間が3年未満でも、事業所単位の3年ルールを超えて同じ事業所で働き続けることはできません。
ただし、派遣可能期間が終了する1か月前までに、意見聴取手続きを経て、派遣社員が必要であるという理解を得られた場合は、3年ごとに期間の延長が可能になります。
個人単位の3年ルール
個人単位の期間制限とは、「派遣社員が同じ部署で働ける期間は最大3年まで」という規則です。派遣会社と有期雇用契約を結ぶ派遣社員は、派遣先の事業所における同一の部署に3年以上勤務できません。事業所単位の3年ルールを延長した場合でも、個人単位の3年ルールは適用されます。3年を超えて同じ職場で働きたい場合には、「派遣先に直接雇用してもらう」「派遣会社と無期雇用の契約を結ぶ」などの対策が必要です。
出典
愛知労働局ホームページ「労働者派遣の受入れ期間制限ルールなどにご留意ください:パンフレット(派遣先の皆さまへ)」(2024年12月24日)
▼関連記事
派遣会社の乗り換えは可能?メリット・デメリットや注意点、タイミングを解説
介護派遣の契約更新の連絡が来なくて不安…対処法と通知されない理由を解説
3年ルールの例外となる派遣労働者
ここでは、派遣3年ルールの例外となる5つのケースをご紹介します。下記で解説するので、自分が当てはまるかチェックしておきましょう。
年齢が60歳以上の人
派遣社員として働いて3年が経過した時点で年齢が60歳以上になる方は、派遣の3年ルールの対象外です。60歳以上の方は、派遣先が雇用の継続を希望する場合、同じ職場で働き続けられます。
有期プロジェクトに派遣されている人
期限付きのプロジェクトに従事する派遣社員も、3年ルールの対象外です。有期プロジェクトは、事業のスタート時や拡大時など、3年以内の完了が見込まれるプロジェクトが該当します。
日数限定業務に従事している人
派遣社員として日数限定の業務に従事する場合も、3年ルールの適用外となります。日数限定の業務とは、1ヶ月の勤務日数が常勤の職員の半分以下、かつ10日以下であることが条件です。
産休・育休・介護休業の代替業務に派遣されている人
産前産後休業や育児休業、介護休業などを取得する職員の業務を行うために派遣された場合も、3年ルールは適用されません。休業制度を利用する職員の復職を前提に雇用されるため、3年ルールの対象外になります。
派遣会社と無期雇用の契約を結んでいる人
派遣会社と無期雇用契約を結んでいる方も、3年ルールの対象外です。雇用期間の定めのない契約を結ぶ派遣社員のことで、常用型派遣とも呼ばれます。無期雇用の派遣社員は、長期的な雇用を前提としているため、3年ルールは適用されません。
▼関連記事
派遣介護士最強の働き方を紹介!時間を有効活用できて月収が増える?
派遣社員が同じ職場に3年以上勤務する方法は?
派遣社員として働いている方には、「3年以降も同じ職場で働きたい」という方もいるでしょう。ここでは、派遣社員が3年以上、同じ職場で働き続ける方法を紹介します。
派遣先に直接雇用に切り替えてもらう
派遣社員は、派遣先の会社や法人から直接雇用されれば、同じ職場で働き続けることができます。直接雇用とは、派遣先の事業所と直接雇用契約を結ぶこと。派遣先から「今後も継続して働いてほしい」という要望があり、派遣社員も「このまま仕事を続けたい」という希望があれば、直接雇用の契約を結ぶことが可能です。
直接雇用とは、正社員だけでなく、パート・アルバイト、契約社員なども直接雇用に含まれます。直接雇用契約を結ぶ際は、労働条件を十分に確認しておきましょう。
▼関連記事
介護職は派遣とパートどちらがおすすめ?それぞれの違いとメリットを解説
同じ派遣先で部署を異動する
派遣社員は、3年が経過したときに部署や課を異動すれば、同じ勤務先でまた3年間働けます。直接雇用への切り替えは難しいものの、働き続けてほしい場合、派遣先から異動を打診される可能性があるでしょう。
たとえば、複数の介護施設を併設する勤務先の場合、「特別養護老人ホームで3年間働き、ショートステイに異動する」といった働き方ができます。今の勤務先で働き続けたい派遣社員の方は、派遣先の職場や派遣会社に、異動して働き続ける選択肢はあるか確認してみると良いでしょう。
派遣会社と無期雇用の契約を結ぶ
派遣会社と無期雇用の契約を結ぶことで、3年ルールの対象外となります。契約の更新が不要で、雇用と収入が安定するのが、無期雇用の派遣社員として働くメリットです。一方で、派遣先を選べない場合があったり、ワークスタイルが固定される場合があったりするというデメリットも挙げられます。
雇用契約の切り替えは、派遣会社と派遣社員の合意のもと行われるため、無期雇用派遣が自分に合う働き方なのかを検討することが重要です。また、派遣会社によっては無期雇用の制度がない場合もあるので、事前にチェックしておきましょう。
社保即日加入できます!
労働者派遣法の3年ルールに違反すると罰則があるの?
3年ルールに違反した場合、派遣会社は労働者派遣法第61条第3項の規定により、30万円以下の罰金という罰則を受けることがあります。また、厚生労働大臣による業務停止命令および改善命令といった、行政処分の対象となるでしょう。派遣先の事業所にも行政指導が入る場合があります。
出典
e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(2024年12月24日)
派遣の3年ルールがもたらすメリット
派遣3年ルールは、派遣社員と派遣先の双方にとってメリットがある制度です。ここでは、派遣社員にとってのメリットと派遣先にとってのメリットの2つに分けて解説します。
派遣社員にとってのメリット
派遣の3年ルールのメリットは、派遣社員として働いて3年が経つと、直接雇用や無期雇用などに切り替えられる機会があることです。3年ルールが定められる以前は、何年働けば長期雇用に切り替えてもらえるのか分からないまま、不安定な雇用で働き続けていたケースがありました。
3年ルールにより派遣期間が制限されたことで、3年働けば直接雇用への切り替えができるかどうかが判断できます。これにより、派遣社員はキャリアプランが立てやすくなったのも、メリットといえるでしょう。
派遣先にとってのメリット
3年ルールの派遣先にとってのメリットは、雇用のチャンスが増えることです。期限付きで派遣として雇用してみて、優秀な人材であれば、直接雇用を提案できます。勤務経験のある派遣社員であれば、ミスマッチによる早期離職のリスクを減らせるでしょう。また、派遣社員を直接雇用できれば、新人教育のコストを抑えることもできます。
▼関連記事
介護派遣の実態を知ろう!時給や仕事のメリット・デメリットとは?
社保即日加入できます!
派遣の3年ルールで生じるデメリット
3年ルールは、メリットがある一方でデメリットもあります。ここでは、派遣社員と派遣先にとってのデメリットを紹介するので、確認しておきましょう。
派遣社員にとってのデメリット
派遣社員のデメリットには、「3年で契約が終了される可能性がある」「無期雇用の派遣社員になると直接雇用が難しい」があります。「同じ職場で長く働きたい」と思っている派遣社員にとっては、派遣の3年ルールがデメリットになるかもしれません。
3年で契約が終了する可能性がある
有期雇用の派遣社員は、3年ルールにより最長3年までしか同じ職場で働けません。直接雇用されず3年で契約が終了した場合、新たな職場で仕事を覚えたり人間関係を構築し直したりする必要があり、大変さを感じる可能性があります。今の労働環境や仕事内容に満足して働いている派遣社員にとって、3年ルールはデメリットになり得るといえます。
無期雇用の派遣社員になると直接雇用が難しい
3年ルールによって無期雇用派遣の契約を結ぶと、派遣先から直接雇用してもらえる可能性が低くなるというデメリットがあります。派遣先での正社員登用や直接雇用を目指して、派遣社員として働いている方にとっては、派遣会社と無期雇用契約を結ぶことはデメリットになるかもしれません。
派遣先にとってのデメリット
派遣先にとっての3年ルールのデメリットは、安定して人材を確保し続けるのが難しいことです。自社で経験やスキルを積んだ派遣社員でも、相手の同意がなければ直接雇用できず、3年以降は働いてもらえません。3年ルールにより、最大3年ごとに新たな派遣社員を契約するために、選考や教育などのコストがかかってしまいます。
社保即日加入できます!
3年ルールが適用された派遣社員はどうしたら良い?
「派遣で3年働いたいたあと、同じ職場で働き続けられないときはどうしたら良いの?」と疑問を抱いている方もいるでしょう。ここでは、3年ルールが適用された場合のキャリアの選択肢を紹介します。
同じ派遣会社に違う派遣先を紹介してもらう
3年ルールにより同じ派遣先で働き続けられなくなった場合は、派遣会社に新しい派遣先を紹介してもらいましょう。派遣先を変えれば、最大3年間、新しい派遣先で派遣社員として働くことが可能です。派遣会社は、新しい派遣先を紹介する義務があります。遅くとも契約満了の1ヶ月前までに、派遣会社の担当者へ相談しましょう。
違う派遣会社に乗り換えて職場を紹介してもらう
「派遣社員として働き続けたいけど、今の派遣会社に不満がある」という場合、派遣会社を変えるのも選択肢の一つです。派遣会社を変えることで、自分に合った求人が見つかるかもしれません。働きたい業界や職種に特化した派遣会社であれば、求人が豊富で選択肢が多いため、自分に合う職場が見つかりやすくなります。
1つの派遣会社だけの利用だと、対応や求人が自分に合っているのか判断しづらいので、複数の派遣会社に問い合わせをするなどして、比較してみると良いでしょう。
▼関連記事
介護派遣会社の選び方を解説!仕組みや利用のメリットを知れば失敗しない
派遣以外の雇用形態で働く
「ボーナスをもらって年収を上げたい」「同じ職場で長く働きたい」などの希望がある場合、正社員やパートなどに転職して働くという選択肢もあります。派遣社員として経験済みの仕事であれば、「経験者のみ」や「経験者歓迎」の求人に有利になり、転職先の選択肢を広げられるでしょう。
「正社員として働きたいけど不安」という方は、パートやアルバイトとして転職したあと、正社員登用制度で正社員になる方法があります。ただし、正社員登用制度があれば、どの職場でも正社員に登用されるわけではありません。パートやアルバイトから正社員を目指す場合は、転職先の正社員登用制度の実績や基準などを確認しておくようにしましょう。
▼関連記事
介護派遣は気楽?正社員との違いやメリット・デメリットを解説
 正社員の介護求人一覧はこちら
正社員の介護求人一覧はこちら パート・アルバイトの介護求人一覧はこちら
パート・アルバイトの介護求人一覧はこちら
派遣社員が契約更新時に高評価を得るためにできること
派遣社員が同じ職場で長く働くには、派遣先からの評価が大切です。派遣先での印象が良ければ、3年を限度に契約期間を更新してもらえる可能性があるでしょう。また、会社に貢献する人材だと評価されれば、直接雇用を打診されるチャンスもあります。ここでは、派遣社員が契約更新時に高評価を得るためにできることを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
自身に合った職場で働く
派遣社員として長期的に活躍するには、自分に合った派遣先を見つけることが大切です。自分の強みや経験、スキルを活かせる職場を選べば、即戦力として頼りにされるでしょう。派遣先から必要な人材だと評価されることで、雇い止めに遭う可能性は低くなります。
派遣先でのコミュニケーションを大切にする
派遣先でのコミュニケーションを大切にすることで、周囲との信頼関係を築き、業務を円滑にこなせるようになります。その結果、契約更新時の高評価に繋げられるでしょう。
「派遣社員だから」と、コミュニケーションを怠ってしまうと、トラブルの原因になったり、新たな仕事を任せてもらえなくなったりする可能性があります。特に新しい派遣先では、積極的にコミュニケーションをとるように意識してみましょう。タイミング次第では、自身の経歴や得意分野を伝えることで、適性のある仕事を任せてもらえるかもしれません。
報連相をしっかり行う
報告・連絡・相談を適切に行うことで、業務上のトラブルを防ぎ、業務の質を上げられます。派遣先から仕事態度について良い評価を得ることができ、契約満了まで長く働けるでしょう。
報連相のポイントは、緊急度が高ければすぐに報告すること、優先度が低い場合は相手の作業中を避けてタイミングを見て声をかけるようにすることです。報連相を行うときは、要点をまとめて結論から話すと、伝わりやすくなります。また、「業務の手順は先輩に聞く」「緊急時の相談は上司にする」など、報連相を行う相手を見極めることも大切です。
派遣先で業務改善の提案をする
派遣先の課題に積極的に向き合う姿勢を示すことで、周囲からの評価が上がることがあります。「派遣だから…」と消極的にならず、多様な経験をしてきた派遣社員だからこそ、これまでの経験やスキルを活かすことが大切です。ただし、職場ごとに仕事の方針があるので、まずは上司や先輩に相談してみてから、全体への提案を行うのがおすすめです。
まじめな勤務態度を心がける
派遣社員として長く働くためには、普段からまじめな勤務態度を心がけることが大事です。気を抜き過ぎて、仕事中の私語が多くなると、「口ばかり動かして仕事をしていない」と思われることも考えられます。遅刻が多いと、「時間にルーズでだらしない」という印象を持たれてしまうかもしれません。ときには力を抜くことも必要ですが、職場での評価を落とさないよう、まじめな勤務態度を維持しましょう。
派遣会社の担当者と良好な関係を築く
派遣社員として長く働くには、派遣会社のアドバイザーと良好な関係性を築くことも大切です。不満を抱えながら働き続けるのは、ストレスにつながる恐れがあります。派遣会社のアドバイザーと良好な関係を築ければ、業務上のトラブルや待遇面のお相談がしやすくなり、快適に働き続けやすくなるでしょう。
介護派遣に興味がある方には、介護業界に特化した「レバウェル介護派遣(旧 きらケア介護派遣)」を活用してみませんか?。専任のキャリアアドバイザーがしっかりとヒアリングを行い、豊富な介護求人から、あなたの希望に沿った派遣先をご提案いたします。派遣先で働き始めてからのサポートも充実しており、些細なお悩みも相談しやすいのが魅力です。サービスは無料なので、「介護派遣ってどんな感じ?」と気になる方は、ぜひご活用ください。
社保即日加入できます!
派遣の3年ルールと5年ルールの違いは?
雇用に関する制度には、「3年ルール」のほかに「5年ルール」という制度もあります。3年ルールは派遣社員にのみに適用されるのに対して、5年ルールは有期雇用で働くすべての人のための制度です。ここでは、5年ルールについて解説します。
5年ルールとは
労働契約法の5年ルールとは、「無期転換ルール」とも呼ばれ、「有期契約で5年以上同じ企業で働いた場合、無期雇用に転換できる権利が発生する」という制度です。労働契約法18条第1項で、定められています。派遣社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトなど、有期契約で働く人が対象です。
派遣社員の場合は、派遣会社との雇用契約が合計して5年以上になると適用されます。契約期間が5年を超える場合、派遣社員から無期雇用転換を申し込めば、派遣会社と無期雇用契約を結ぶことが可能です。
出典
e-Gov法令検索「労働契約法」(2024年12月24日)
5年ルール適用のデメリット
無期雇用に転換後、場合によっては勤務時間や給与などの労働条件が変わることがあります。人によっては、「有期雇用のほうが自分に合っていた」と感じることがあるでしょう。無期雇用に切り替える際は、無期雇用で働く場合の労働条件を十分に確認することが大切です。
5年ルールの対象外となる人
合計して5年以上同じ派遣会社と契約していても、無契約期間が6ヶ月以上あると、それ以前の契約期間は通算できません。5年ルールの対象になるのは、「これまでに契約の更新を1回以上している」「現時点で同じ企業と雇用契約を結んでいる」といった条件を満たす有期雇用の職員のみです。
出典
厚生労働省「無期転換ルールについて」(2024年12月24日)
社保即日加入できます!
3年ルールだけじゃない!派遣法改正のこれまで
派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)は、派遣社員の働きやすさを考えて、何度も法改正されてきました。ここでは、これまでの改正の経緯を紹介します。
2015年:特定派遣の廃止
2015年まで派遣事業は、「一般派遣事業」と「特定派遣事業」に分けられていましたが、2015年の労働者派遣法改正で特定派遣事業は廃止され、「派遣事業」に統一されました。
廃止の目的は、派遣社員の雇用の安定と派遣会社の管理の強化です。一般派遣事業は許可制でしたが、特定派遣事業は届出制で比較的規制が緩く、派遣期間の制限がありませんでした。「3年ルールが作られた背景」で触れたように、特定派遣で働く社員は雇用が不安定になる傾向があったようです。派遣事業に統一したことで、すべての労働者派遣事業が許可制となり、派遣社員の保護が強化されました。
上記のほか、2015年の派遣法改正は、「3年ルール」や派遣社員のキャリアアップを目的とした「キャリアアップ措置」、派遣社員と派遣先の社員の待遇の均衡を図るための「均衡待遇の推進」などが行われています。
2020年:同一労働同一賃金
2020年には、雇用形態による不合理な待遇格差をなくすことを目的に、「同一労働同一賃金」が導入されました。同一労働同一賃金とは、「雇用形態にかかわらず、同じ仕事をする労働者は、賃金や手当などの待遇の差を解消しなければならない」という制度です。
派遣社員の場合は、「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」の2種類があります。「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣先の社員の待遇に合わせて、同一労働同一賃金を実現しようとする方式のこと。一方、「労使協定方式」は、派遣会社が定めた労使協定に基づいて待遇を決める方式です。勤務先のエリアで同じ業務に就いている正社員の待遇に合わせて、同一労働同一賃金を図ります。どちらが適用されているかは、派遣会社に問い合わせることで分かります。
2021年:派遣労働者の雇入れ時の説明事項の追加
2021年は、派遣会社に対して、派遣社員を雇用する際の説明義務が強化されました。派遣会社は派遣労働者を雇用する際に、キャリアアップ処置や訓練契約の内容の説明を行わなければなりません。
2015年のキャリアアップ措置により、「派遣会社は派遣社員の教育訓練の実施やキャリアコンサルティングの相談窓口の設置を行わなければならない」としました。しかし、制度はあるものの、受講率が高くない派遣会社もあったようです。そのため、2021年の法改正では、派遣社員のキャリア形成を実現するために、説明義務が強化されたと考えられます。
派遣の就業ルールによくある質問
ここでは、派遣の就業ルールに関するよくある質問に回答します。「3年ルールについて詳しく知りたい」という派遣社員の方はご覧ください。
途中で派遣会社を変更したら3年ルールはどうなりますか?
派遣会社を変えたとしても、同じ派遣先で働く場合は、原則として3年ルールが適用されます。3年を超えて、派遣社員として同じ部署で働くことはできません。
派遣会社の変更については、「派遣会社の乗り換えは可能?メリット・デメリットや注意点、タイミングを解説」の記事も参考にしてみてください。
派遣の3年ルールに抜け道はありますか?
同じ職場・部署で、有期雇用の派遣社員として働く場合、3年ルールの抜け道はありません。派遣として3年以上同じ職場では働けないのが原則ですが、「3年ルールの例外となる派遣労働者」で解説しているケースでは、3年ルールの対象外です。
派遣社員にとって3年ルールはひどい制度なの?
3年ルールに不満のある派遣社員の中には、「辞めたくないのに、3年で仕事を変えないといけないなんてひどい」と思う人もいるようです。3年ルールは、派遣社員の雇用の安定を目的に設定されました。派遣社員にとっては、メリットもあります。
詳しくは、この記事の「派遣の3年ルールがもたらすメリット」を確認してみてくださいね。
派遣の3年ルールはいつから廃止されますか?
2024年12月時点では、派遣の3年ルールが廃止される予定はありません。2015年に派遣法が改正されてからは、派遣社員として同じ部署で3年以上働くことができなくなりました。同じ職場で働き続けるには、派遣先で直接雇用に切り替えるか、派遣会社と無期雇用の契約を結ぶなどの方法をとる必要があります。
詳しく知りたい方は、この記事の「派遣社員が同じ職場に3年以上勤務する方法は?」をご覧ください。
まとめ
派遣の3年ルールとは、「有期雇用の派遣社員として同じ職場で働けるのは3年まで」という法律の通称です。一部例外となるケースはあるものの、派遣社員には原則としてこの3年ルールが適用されます。
派遣社員が3年以上同じ職場で働くためには、「派遣先に直接雇用してもらう」「部署を移動する」「派遣会社と無期雇用契約を結ぶ」など、雇用形態を変える必要があります。派遣の3年ルールが適用された場合は、派遣社員として違う職場に勤務するか、派遣以外の雇用形態で働くようになるでしょう。
レバウェル介護派遣(旧 きらケア介護派遣)を利用すれば、今後どのような働き方がしたいのかというキャリアプランを考えたうえで、派遣先を選べます。「派遣として働いて自分に合った介護施設を見つけたい」「慣れたら雇用形態を変えて働きたい」「派遣としてキャリアを積んでいきたい」など、あなたの希望に沿ったサポートを行うので、ぜひご相談くださいね。
社保即日加入できます!