Clik here to view.
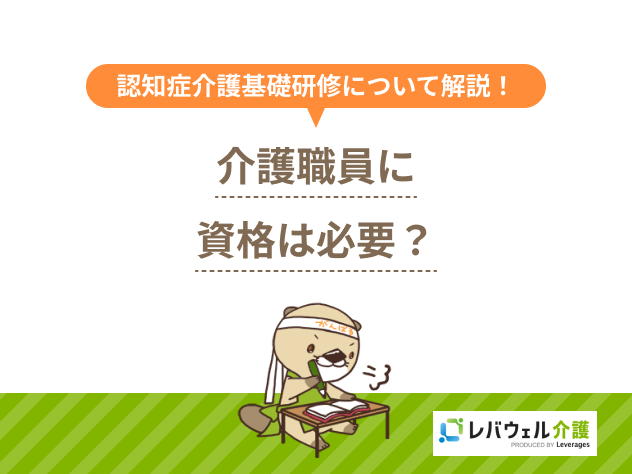
この記事のまとめ
- 介護職員に認知症介護基礎研修の修了が義務付けられ、資格が必要になった
- 介護職員が認知症介護基礎でできる仕事は、生活援助や送迎業務など
- 初任者研修や実務者研修は、介護業界でのスキルアップに活かせる資格
「介護職として働くために資格は必要?」と気になる方もいるかもしれません。2021年度の介護報酬改定により、介護業務に直接関わる職員には、「認知症介護基礎研修」の受講が義務付けられました。この記事では、認知症介護基礎研修の概要を解説します。介護職のスキルアップに活かせる資格や、職種ごとの資格要件もまとめました。資格を取得するメリットもご紹介するので、介護の仕事に興味がある方はご一読ください。
介護資格の種類一覧!取得方法や特徴、メリットを解説します →レバウェル介護の資格スクールはこちら介護職として働くためには資格が必要
介護職として働くためには資格が必要です。
厚生労働省の「令和3年度介護報酬改定における改定事項について(p.12)」によると、2021年度の介護報酬改定によって、2024年4月以降、介護職には「認知症介護基礎研修」の受講が義務付けられ、介護業務に直接関わる職員は無資格では働けなくなりました。新任の介護職については、1年以内に受講することが条件です。
認知症介護基礎研修については、次項で詳しく解説します。
出典
厚生労働省「令和3年度介護報酬改定について」(2024年12月24日)
今の職場に満足していますか?
▼関連記事
介護職は無資格で働けなくなるの?認知症介護基礎研修の義務化について解説
認知症介護基礎研修とは
認知症介護基礎研修とは、介護職が認知症の利用者さんに適切な介護を行うための研修です。認知症に関する基礎的な知識・スキルを身につけ、介護職として専門的なケアを行えるようになることを目的としています。
学習内容
認知症介護基礎研修は、インターネットを使用したeラーニングで受講でき、厚生労働省が標準カリキュラムを定めています。序章と4つの章に分かれており、講義動画を視聴した後、章ごとの確認テストに合格することで修了可能です。各章の学習内容は、以下のとおりです。
| 章 | 学習内容 |
| 序章 | 認知症を取り巻く現状 |
| 第1章 | 認知症ケアにおいて基礎となる理念や考え方 |
| 第2章 | 認知症の定義と原因疾患 |
| 第3章 | 認知症の中核症状と行動・心理症状の理解 |
| 第4章 | 認知症ケアの基礎技術 |
参考:認知症介護基礎研修 eラーニング「認知症介護基礎研修 eラーニングのご案内」
1つの講義動画は、5分~10分程度と比較的短めです。章ごとに行われる確認テストは〇×形式で出題されます。
出典
認知症介護基礎研修 eラーニング「認知症介護基礎研修 eラーニングのご案内」(2024年12月24日)
受講費用・所要時間
受講費用は都道府県によって異なりますが、基本的には3,000円程度で受講できるようです。また、講義動画の視聴に必要な時間は、全体で150分程度となっています。確認テストや自己ワークの時間もあるので、研修全体を通した所要時間は180分程度です。
出典
認知症介護基礎研修 eラーニング「認知症介護基礎研修 eラーニングシステム」(2024年12月24日)
難易度
認知症介護基礎研修の合格率は公表されていませんが、新任の介護職員に向けた基礎的な内容なので、講義は難しくないといえるでしょう。確認テストはしっかり講義動画を視聴していれば答えられるレベルで、不合格になった場合も何度でも挑戦できます。
認知症介護基礎研修の受講が免除になるケース
介護や福祉に関する資格を持っていたり、研修を修了していたりする場合、認知症介護基礎研修が免除になる場合があります。以下で自分に当てはまるものがあるか、チェックしてみましょう。
指定の資格を保有している場合
以下の資格を持っている場合、認知症介護基礎研修を受講しなくても介護職として働くことが可能です。
- 医師、歯科医師
- 薬剤師
- 看護師、准看護師
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
- あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師
- 管理栄養士、栄養士
- 社会福祉士、精神保健福祉士
- 介護福祉士
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護業界で上記の資格を活かして働いていた方は、あらためて認知症介護基礎研修を受講する必要はありません。また、これまで福祉業界や医療業界で働いていた方は、資格を活かしてスムーズに介護職に転職できるでしょう。
指定の研修を修了している場合
以下の研修を修了している方も、認知症介護基礎研修の受講が免除されます。
- 介護職員初任者研修
- 訪問介護員養成研修2級課程(ホームヘルパー2級)
- 介護福祉士実務者研修
- 介護職員基礎研修
- 訪問介護員養成研修1級課程(ホームヘルパー1級)
- 生活援助従事者研修
認知症介護基礎研修は、基本的に介護職員になってから受講します。そのため、介護職になる前に必要な資格を取得したい方は、介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修を取得するのがおすすめです。それぞれの資格については、「スキルアップに活かせる介護資格」で後述するので、あわせて参考にしてください。
なお、訪問介護員養成研修(2級・1級課程)と介護職員基礎研修はすでに廃止されているため、これから受講することはできません。
出典
認知症介護基礎研修 eラーニング「認知症介護基礎研修とは」(2024年12月24日)
認知症介護基礎研修でできる仕事
認知症介護基礎研修を受講すれば介護職として働けますが、それだけでは食事介助や入浴介助、排泄介助といった身体介護を1人で行うことはできません。ここでは、認知症介護基礎研修のみでできる仕事をご紹介します。
介護サービス利用者さんの生活援助
介護サービスの利用者さんの生活をサポートする生活援助の業務は、認知症介護基礎研修の取得のみで対応可能です。生活援助の具体的な仕事内容としては、掃除や洗濯、食事の用意、調理、買い物代行などが挙げられます。
▼関連記事
介護職の仕事内容とは?資格は必要?やりがいやメリットもご紹介
デイサービスなどでの送迎業務
認知症介護基礎研修以外の介護資格がなくても、運転免許があれば、介護施設や事業所で送迎車を運転することが可能です。デイサービス(通所事業所)や小規模多機能型居宅介護事業所では、介護職員が送迎業務を行うことがあります。ただし、移動に介助が必要な利用者さんの送迎は1人で行えない可能性があるので、注意が必要です。
▼関連記事
無資格でできるデイサービスの仕事内容とは?未経験で働くメリットも紹介
介護事業所や介護施設での事務業務
介護保険に関する手続きや書類作成といった事務作業を行うために、必要な資格はありません。認知症介護基礎研修を修了した介護職員の方は、利用者さんの対応についての知識があるので、窓口業務を含めた事務を担当する可能性があるでしょう。
▼関連記事
介護事務の仕事内容は?未経験からできる?活かせる資格やスキルをご紹介
Image may be NSFW.
Clik here to view. 無資格OKの介護求人一覧
無資格OKの介護求人一覧
スキルアップに活かせる介護資格
介護職のスキルアップに活かせる資格として、「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者研修」「介護福祉士」などが挙げられます。それぞれの資格の概要や取得方法を下記にまとめたので、「介護業界で長く活躍したい!」という方は、チェックしてみてください。
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修は、介護業界において基礎的な位置づけで、身体介護や生活援助について実践的に学べる資格です。取得すると、単独で身体介護の業務を行えるので、仕事の幅が広がります。
受講要件
介護職員初任者研修に受講要件はありません。年齢や学歴、国籍に関係なく受講が可能です。介護の資格や経験も問われないため、無資格・未経験の方も取得を目指せます。
研修カリキュラム
介護職員初任者研修を取得するためには、およそ130時間の講習を受講する必要があります。カリキュラムは以下のとおりです。
| カリキュラム | 受講時間 |
| 職務の理解 | 6時間 |
| 介護における尊厳の保持・自立支援 | 9時間 |
| 介護の基本 | 6時間 |
| 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | 9時間 |
| 介護におけるコミュニケーション技術 | 6時間 |
| 老化の理解 | 6時間 |
| 認知症の理解 | 6時間 |
| 障害の理解 | 3時間 |
| こころとからだのしくみと生活支援技術 | 75時間 |
| 振り返り | 4時間 |
| 合計 | 130時間 |
参考:厚生労働省「介護員養成研修の取扱細則について(p.2)」
認知症について以外に、障がいに関する知識や、高齢者とのコミュニケーションのポイントなども学ぶ内容です。なお、介護職員初任者研修を取得するには、受講後の修了試験に合格する必要があります。修了試験は理解力をチェックするためのものなので、講義をしっかり受けていれば合格できるレベルといえるでしょう。
介護職員初任者研修について、詳しくは「介護職員初任者研修とはどんな資格?受講費用を抑える方法や取得のメリット」の記事でご紹介しています。
出典
厚生労働省「介護職員・介護支援専門員」(2024年12月24日)
首都圏限定!資格取得が無料!
転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!
レバウェル介護の資格スクール介護福祉士実務者研修
介護福祉士実務者研修は、新人~中堅の介護職員向けの研修です。介護福祉士を「実務経験ルート」で受験する場合、受験要件の一つになっています。そのため、介護福祉士国家試験の受験を目指す方は、取得しておくと良いでしょう。
受講要件
介護福祉士実務者研修に受講要件はないため、介護職員初任者研修を取得していない方も挑戦できます。初任者研修は無資格から約1~4ヶ月で取得できるのに対し、上位資格である実務者研修は6ヶ月以上かかるので、自身に合った資格を選ぶと良いでしょう。
研修カリキュラム
介護福祉士実務者研修は、およそ450時間のカリキュラムで構成されます。学習内容は以下のとおりです。
| カリキュラム | 受講時間 |
| 人間の尊厳と自立 | 5時間 |
| 社会の理解I | 5時間 |
| 社会の理解 II | 30時間 |
| 介護の基本I | 10時間 |
| 介護の基本II | 20時間 |
| コミュニケーション技術 | 20時間 |
| 生活支援技術I | 20時間 |
| 生活支援技術II | 30時間 |
| 介護過程I | 20時間 |
| 介護過程II | 25時間 |
| 介護過程III | 45時間 |
| 発達と老化の理解I | 10時間 |
| 発達と老化の理解II | 20時間 |
| 認知症の理解I | 10時間 |
| 認知症の理解II | 20時間 |
| 障害の理解I | 10時間 |
| 障害の理解II | 20時間 |
| こころとからだのしくみI | 20時間 |
| こころとからだのしくみII | 60時間 |
| 医療的ケア | 50時間 |
| 合計 | 450時間 |
参考:厚生労働省「実務者研修の指定基準について(p.8)」
カリキュラムは、高齢者介護や障害福祉サービスについて詳しく学ぶ内容です。なお、介護福祉士実務者研修には、修了試験は義務付けられていません。スクールによっては試験を行うこともありますが、学習したカリキュラムから出題されるため、復習をしっかり行えば合格できる難易度といえるでしょう。
なお、介護職員初任者研修やホームヘルパー1・2・3級などの介護の資格を取得済みの方は、一部のカリキュラムが免除になります。
介護福祉士実務者研修について詳しく知りたい方は、「介護福祉士実務者研修とは?資格取得のメリットや初任者研修との違いを解説」もご覧ください。
出典
厚生労働省「介護福祉士養成施設等における「医療的ケアの教育及び実務者研修関係」」(2024年12月24日)
Image may be NSFW.
Clik here to view. 実務者研修(ヘルパー1級)の求人一覧はこちら
実務者研修(ヘルパー1級)の求人一覧はこちら
介護福祉士
介護福祉士は、介護分野における唯一の国家資格です。また、社会福祉士や精神保健福祉士と並ぶ、福祉の三大国家資格の一つでもあります。介護福祉士の資格を取得するには、年に1回実施される介護福祉士国家試験に合格する必要があります。
介護福祉士の役割は、介護のエキスパートとして、介護サービスの品質管理や職員の育成を行うことなどです。
受講要件
介護福祉士国家試験を受験するには、「実務経験ルート」「養成施設ルート」「福祉系高校ルート」「経済連携協定(EPA)ルート」のいずれかの受験要件を満たす必要があります。
働きながら介護福祉士を目指す場合、「実務経験ルート」で受験する方が多いようです。実務経験ルートの場合、実務者研修の修了と3年以上の実務経験が求められます。
介護福祉士の受験ルートについては、「介護福祉士の受験資格を得るルートを解説!必要な実務経験や試験概要は?」で解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
受験科目
介護福祉士国家試験は筆記試験のみで、受験科目は下記のとおりです。
- 人間の尊厳と自立、介護の基本
- 人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術
- 社会の理解
- 生活支援技術
- 介護過程
- こころとからだのしくみ
- 発達と老化の理解
- 認知症の理解
- 障害の理解
- 医療的ケア
- 総合問題
試験に合格するには、「合格点を満たしていること」「上記11科目群すべてで得点していること」の両方を満たす必要があります。合格点は、総得点の60%程度を基準とし、問題の難易度によって補正されるので、注意が必要です。
介護福祉士について、詳しくは「介護福祉士とは?仕事内容や資格の取得方法、試験概要をわかりやすく解説!」の記事をご参照ください。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]合格基準」(2024年12月24日)
▼関連記事
介護の資格はどんな順番で取れば良い?取得方法やメリットも解説!
Image may be NSFW.
Clik here to view. 介護福祉士(介護士)の求人一覧はこちら
介護福祉士(介護士)の求人一覧はこちら
今の職場に満足していますか?
職種ごとに必要な介護資格は異なる
介護業界で働く職種には、資格要件が定められていることもあります。そのため、キャリアアップを目指すなら、資格の取得も視野に入れる必要があるでしょう。
以下で、資格要件のある職種についてまとめたので、気になる職種をチェックしてみてください。
訪問介護員(ホームヘルパー)
訪問介護員(ホームヘルパー)は、基本的には介護職員初任者研修以上の資格が必要です。一般的に、ホームヘルパーは単独で仕事をするため、初任者研修以上の資格が求められます。ただし、生活援助のみ担当する場合は、生活援助従事者研修の資格でも訪問介護に従事可能です。
訪問介護員(ホームヘルパー)について、詳しくは「訪問介護は無資格だとできない?介護職の種類と資格との関係」の記事をチェックしてみてください。
訪問介護のサービス提供責任者
サービス提供責任者とは、利用者さんが適切な訪問介護サービスを受けられるよう支援する職種です。ケアマネジャーが作成したケアプランをもとに、訪問介護計画書を作成したり、介護スタッフに指示出しを行ったりします。
訪問介護事業所でサービス提供責任者(サ責)として従事するためには、「介護福祉士実務者研修」か「介護福祉士」のいずれかの資格が必要になります。また、同等の資格であるホームヘルパー1級や介護職員基礎研修を取得済みの方も、サービス提供責任者として従事可能です。
サービス提供責任者について、詳しくは「サービス提供責任者に資格は必要!要件と取得方法、サ責の仕事内容を解説」の記事もご参照ください。
ケアマネジャー(介護支援専門員)
ケアマネジャーになるには、年に1回実施される「介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)」に合格し、さらに「介護支援専門員実務研修」を修了する必要があります。
ケアマネ試験を受験するには、「相談援助の実務経験5年以上」もしくは「特定の国家資格等に基づく実務経験5年以上」という要件を満たさなければなりません。具体的には、生活相談員の業務や、介護福祉士を取得してからの実務経験などが該当します。
ケアマネジャーとは、ケアプランと呼ばれる介護サービス計画書を作成し、福祉サービスの利用をサポートする職種です。介護施設や居宅介護支援事業所などに勤務しています。
ケアマネジャー(介護支援専門員)について、詳しくは「ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどんな仕事?業務内容や役割を解説!」でご紹介します。
介護資格を取得するメリット
「認知症介護基礎研修以外の資格も取得するべき?」とお悩みの方もいるかもしれません。以下に、介護職員が資格を取得するメリットをまとめました。
- 業務範囲が広がる
- 給与アップにつながる
- 知識・スキルを習得できる
前述のとおり、介護職員初任者研修以上の資格がないと、1人で身体介護ができません。そのため、介護の資格を取得することで、業務範囲が広がるでしょう。職場によっては、資格手当により給与がアップすることもあるようです。
また、資格を取得して専門的な知識やスキルを身につけることで、根拠を持って介護業務にあたれるようになるメリットもあります。
介護資格の必要性に関するよくある質問
ここでは、介護資格の必要性に関するよくある質問にお答えします。「介護職として働くのに資格は必要?」と気になっている方は、参考にしてみてください。
介護職は無資格で働けなくなるって本当ですか?
2021年の介護報酬改定により、介護職員は無資格で働けなくなりました。現在、介護の仕事に従事する職員には、「認知症介護基礎研修」の受講が義務付けられています。ただし、新人の介護職員には入職後1年間の猶予が与えられるため、無資格から介護職の求人に応募することは可能です。認知症介護基礎研修は、全編eラーニングで実施され、1日あれば修了できます。
認知症介護基礎研修については、この記事の「介護職として働くためには資格が必要」をご参照ください。
介護職が無資格でできる仕事はどこまでですか?
利用者さんの身体に直接触れて行う「身体介護」を単独で行うには、介護職員初任者研修以上の資格が必要になります。無資格の介護職員の主な仕事内容は、生活援助や送迎業務、事務作業などです。介護施設の中には資格取得支援制度を設けている職場もあるので、無資格でできる業務を担当しながら資格取得を目指すこともできるでしょう。新任の介護職員は、入職から1年以内に「認知症介護基礎研修」を取得する必要があり、無資格では働き続けられないので注意が必要です。
まとめ
2021年度の介護報酬改定により、介護の仕事に従事する職員には、「認知症介護基礎研修」の受講が義務付けられました。新人の介護職員には入職後1年の猶予が与えられるため、無資格でも介護職の求人に応募することは可能です。
また、介護職員初任者研修以上の資格を取得すると、単独で身体介護ができたり、給与などの待遇が良くなったりするメリットがあるでしょう。
働きながら資格取得を目指す方は、「レバウェル介護(旧 きらケア)」にご相談ください。介護業界を専門とする転職エージェントのレバウェル介護(旧 きらケア)では、あなたのキャリアパスや希望をヒアリングし、ぴったりの求人をご提案いたします。資格取得支援のある職場や、キャリアアップしやすい職場もご紹介することが可能です。サービスはすべて無料なので、お気軽にお問い合わせください。
今の職場に満足していますか?
先に資格を取りたい方へ
無料相談はこちら