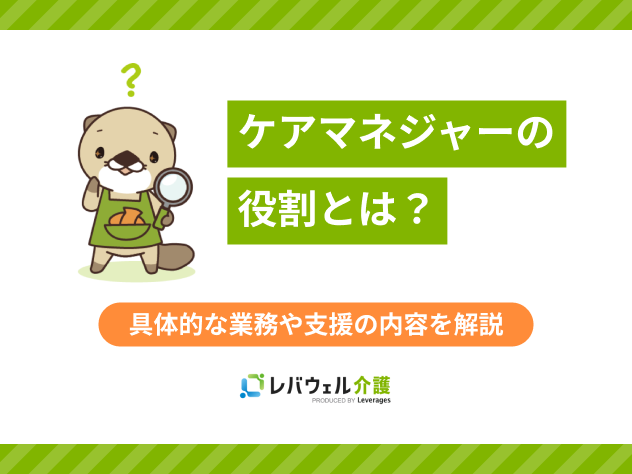
この記事のまとめ
- ケアマネジャーの役割は、利用者さんを適切な介護サービスにつなぐこと
- 施設や居宅介護支援事業所など、職場ごとにケアマネジャーの役割は異なる
- ケアマネジャーの仕事内容は、ケアプランの作成や介護給付費の管理など
「ケアマネジャーの役割が知りたい」という方もいるでしょう。ケアマネジャーの役割は、要介護者・要支援者への相談対応を行い、適切な介護サービスを提供できるよう、関係機関との連絡・調整を行うことです。この記事では、職場ごとのケアマネジャーの役割や、これから求められることをまとめました。具体的な仕事内容もご紹介するので、ケアマネジャーへの転職に興味がある方は、ご一読ください。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどんな仕事?業務内容や役割を解説!今の職場に満足していますか?
ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割とは?
ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割は、要介護者・要支援者の方が、訪問介護やデイサービスといった介護サービスを適切に利用できるよう、サポートすることです。
主に高齢者の相談対応を行い、心身の状況に合わせてケアプランを作成します。自治体や介護事業所などの関係機関との連絡・調整を行うのも、ケアマネジャーの役割です。
出典
厚生労働省「第5回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 資料」(2024年12月26日)
今の職場に満足していますか?
職場別ケアマネジャーの役割
ケアマネジャーの主な職場は、介護施設・居宅介護支援事業所・地域包括支援センターです。介護施設で働くケアマネジャーは「施設ケアマネ」と呼ばれ、居宅介護支援事業所で働くケアマネジャーは「居宅ケアマネ」と呼ばれます。
ここでは、ケアマネジャーの役割や仕事内容を職場別にまとめました。
介護施設で働くケアマネの役割
介護施設で働くケアマネジャーの役割は、入居者さんに対して、適切な介護サービスを組み合わせたケアプランを作成することです。施設ケアマネの特徴は、利用者さんの状態や生活を身近で見守りやすいことといえます。
施設ケアマネの仕事内容は、ケアプランの作成や要介護認定の申請、関係機関との連絡・調整などです。ケアマネジャーの仕事以外に、介護業務を兼務する場合もあります。
施設ケアマネの職場は、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)、有料老人ホーム、グループホームなどです。
▼関連記事
施設ケアマネとは?役割の違いから求人の探し方まで詳しく解説!
 特別養護老人ホーム(特養)の求人一覧はこちら
特別養護老人ホーム(特養)の求人一覧はこちら 老人保健施設(老健)の求人一覧はこちら
老人保健施設(老健)の求人一覧はこちら 有料老人ホームの求人一覧はこちら
有料老人ホームの求人一覧はこちら グループホームの求人一覧はこちら
グループホームの求人一覧はこちら
居宅介護支援事業所で働くケアマネの役割
居宅介護支援事業所で働くケアマネジャーの役割は、福祉サービスなどの社会資源を組み合わせ、介護サービスを利用しながら自宅で暮らす方を包括的に支援することです。居宅ケアマネは、利用者さんが住み慣れた自宅での生活を継続できるよう、関係機関と連携・調整します。
居宅ケアマネの特徴は、施設ケアマネよりも担当する利用者さんが少ない傾向にあることです。その分、利用者さん一人ひとりにじっくりと向き合う必要があります。
主な仕事内容は、利用者さんの家庭環境や健康状態をアセスメント(評価)し、ケアプランを作成することです。本人やご家族の希望をヒアリングしたうえで、訪問看護や訪問介護といった利用する介護サービスの種類を決定します。
居宅ケアマネについて、詳しくは「居宅ケアマネってどんな仕事?役割や施設ケアマネとの違い」の記事をご覧ください。
地域包括支援センターで働くケアマネの役割
地域包括支援センターで働くケアマネジャーは、要支援認定を受けた方や生活に不安のある高齢者の方などが住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、支援を行う役割を担っています。
地域包括支援センターとは、介護や医療、福祉、保健などのさまざまな角度から地域住民をサポートする機関です。主任ケアマネジャーや社会福祉士、保健師が中心となって活躍しています。
地域包括支援センターで働く主任ケアマネの仕事内容は、介護予防ケアマネジメントや地域住民からの相談対応、ケアマネジャーに対する支援などです。地域の高齢者に関する問題全般の解決や、ケアマネジメントの質向上にも貢献しています。
地域包括支援センターのケアマネジャーについて詳しく知りたい方は、「地域包括支援センターのケアマネ業務とは?居宅介護支援との違いも解説」の記事をチェックしてみてください。
これからのケアマネジャーに求められる役割
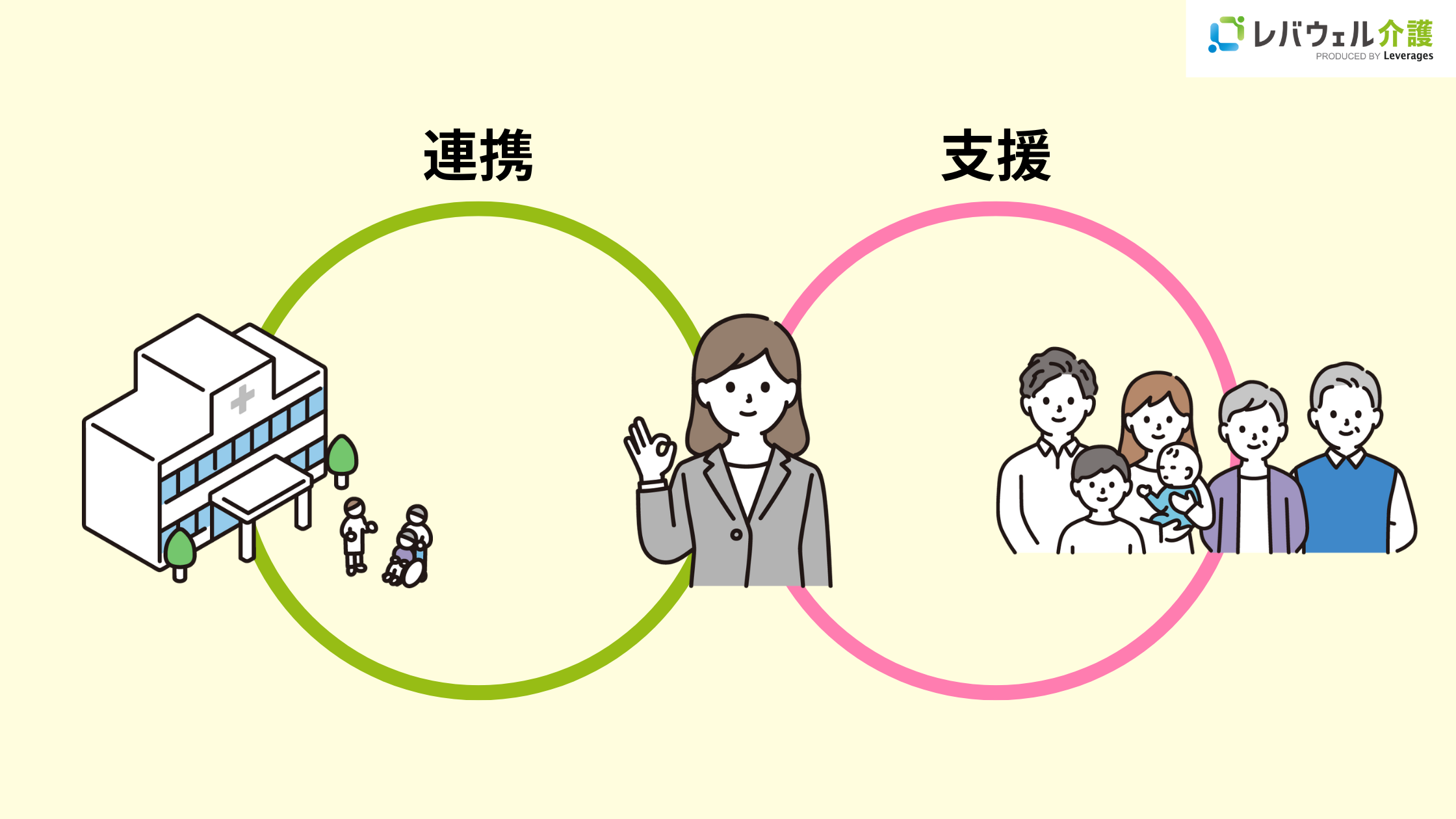
厚生労働省の「「適切なケアマネジメント手法」の手引き(p.6)」によると、理想のケアマネジメントとは、利用者さんが住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、生活全般をサポートする体制を整え、尊厳を尊重した自立支援を行うことです。
ここでは、理想のケアマネジメントを叶えるために、今後のケアマネジャーに求められる役割を解説します。
医療機関・介護事業所との連携強化
介護サービスの種類や対象範囲の広がりに伴い、ケアマネジャーの利用者さんへの対応の幅も広がっています。介護保険制度開始のころと比較して、現在は介護予防ケアマネジメントや在宅での看取り対応、継続的な治療・リハビリなどのニーズが増えてきているようです。
また、多職種との連携を強めて、適切な支援につなげる必要があります。ケアマネジャーは、「利用者さんにどのような支援が必要か」という視点から、多職種と情報・知識を共有して、医療、福祉についても幅広く学び続けることが求められるでしょう。
家族への支援と地域づくり
現在の日本では、高齢化の進行により要介護者が増加し、独居の高齢者や働きながら家族の介護をする方が増えています。そのため、高齢者自身やその家族にくわえて、地域ぐるみで支援を行うことが必要な時代に突入しているといえるでしょう。
介護に悩むご家族への寄り添いや適切な相談対応、地域全体で福祉を支えるための活動を推進することが、これからのケアマネジャーに求められる役割の一つです。
出典
厚生労働省「適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進」(2024年12月26日)
厚生労働省「介護支援専門員資質向上事業」(2024年12月26日)
ケアマネジャー(介護支援専門員)の仕事内容
ケアマネジャーの仕事内容は、ケアプランの作製や介護給付費の管理、関係機関との連絡・調整などです。
ケアプラン作成・実施・管理
ケアマネジャーは、利用者さんの介護度や生活状況、どのような生活を送りたいのかなどを調査し、日常生活における課題や希望に沿ったケアプランを作成します。ケアプランとは、利用者さんがどのような介護サービスを利用するのか、介護サービスの内容やその頻度、方針などを記載した計画書です。
ケアプラン原案の作成後は、利用者さんとそのご家族、医療関係者、介護関係者を集めて「サービス担当者会議」を開催します。ケアプランの内容を話し合い、必要に応じて適宜修正を実施。利用者さんとご家族に最終確認をもらい、ケアプランを正式に決定します。
ケアプランを作成した後に、定期的に利用者さんの自宅を訪問して、適切に介護サービスが提供されているかをモニタリングするのも、ケアマネの仕事の一つです。ケアプラン交付後も、利用者さんの状況に応じて定期的な評価・見直しを行う必要があります。
介護給付費の管理
国民健康保険団体連合会(国保連)に介護給付費を請求するのも、ケアマネジャーの仕事です。まずは介護サービスの費用を請求するために「給付管理票」を作成します。介護事業所のサービス提供実績をチェックして、国保連に介護給付費を請求することで、介護施設や事業所に介護給付費が支払われる流れです。
給付管理は、毎月行います。介護給付費が正しく支給されるためには、スケジュール管理やしっかりとしたチェックが必要です。なお、介護給付費の管理業務は、ケアマネジャーではなく事務員が担当する事業所もあります。
介護事業者と利用者さんの間の調整
ケアマネジャーの仕事内容として、利用者さんと介護サービス事業者の間に入り、必要なサービスがスムーズに提供されるように連携・調整をすることも挙げられます。施設の入退所支援を行ったり、利用者さんから相談を受けた困りごと・クレームを介護事業者に共有して解決を図ったりするのも役割です。
ケアマネジャーが利用者さんの気持ちに寄り添うことで、本当に困っていることやサービスへの不満などの真のニーズを把握し、適切な支援を行えます。
退院支援・医療機関との連携
担当している利用者さんが入院した場合、退院後も必要な介護サービスを受けられるよう、医療機関と連携してケアプランを調整します。ケアマネジャーは、利用者さんの要望や生活上の課題を加味したケアプランを作成するために、退院後の生活を見据えることが必要です。
退院前カンファレンスで多職種と意見交換をしたり、退院前訪問指導への同行をしたりして、利用者さんの様子・病状に関する情報収集を行うこともあります。医療職とケアマネジャーそれぞれの役割をしっかりと理解したうえで、どのようなアドバイスを求めるべきかを考え、積極的に連携することが重要です。
要介護認定の申請
利用者さんやご家族の代わりに要介護認定の申請を行うのも、ケアマネジャーの重要な仕事です。介護サービスを利用するには、自治体に申請して要介護認定を受けなければいけません。要介護認定の申請に慣れているケアマネが代行することで、スムーズに対応できます。
また、要介護認定の変更申請や更新手続きを行い、介護保険サービスの利用を総合的にサポートすることも、ケアマネジャーの役割です。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)job tag「介護支援専門員/ケアマネジャー」(2024年12月26日)
厚生労働省「介護職員・介護支援専門員」(2024年12月26日)
▼関連記事
ケアマネジャーの仕事内容をわかりやすく解説!施設と居宅の業務の違い
ケアマネジャーができない仕事
ここでは、ケアマネジャーの役割に含まれない仕事内容をまとめました。ケアマネの業務範囲に興味がある方は、チェックしてみてください。
家事の代行業務
家事の代行業務は、ケアマネジャーにはできません。相談に対応していると、「買い物をしてほしい」「少し掃除を手伝ってほしい」と頼まれることがあるでしょう。しかし、家事の代行はケアマネジャーの業務ではありません。
ケアマネジャーの仕事は、利用者さんに必要な介護サービスを提案・紹介したり、相談に対応したりすることです。そのため、家事を手伝ってほしいと相談されたときは、訪問介護の利用を検討するか、ご家族が対応できないか相談する必要があります。
通院の送迎
ケアマネジャーは、医療機関との連携や調整を行うため、仕事で病院に行く機会もあります。利用者さんに「病院に行くなら一緒に連れて行ってほしい」と頼まれることもあるかもしれませんが、基本的に通院の送迎はケアマネジャーの業務には含まれません。
第二種運転免許を持っていない人が、登録された営業所ナンバー以外の車に人を乗せて対価を得ると、「白タク」と呼ばれる違法行為になる可能性があります。また、万が一事故があった際に補償されないリスクもあるので、利用者さんを車に乗せて病院に連れて行くことはできません。
介護保険に無関係の行政手続き代行
介護保険に無関係の行政手続きの代行も、ケアマネジャーができない仕事です。ケアマネジャーの仕事内容には、要介護認定や介護サービスなどの申請は含まれますが、介護保険に無関係の手続きは含まれません。
「行政の書類や手紙がよく分からない」という相談に対して、内容を確認することはできますが、書類の申請や手続きはできないため、注意しましょう。
身元保証人の引き受け
ケアマネジャーは、利用者さんの身元保証人を引き受けることができません。身寄りのない利用者さんが入院や入所する際に、ケアマネジャーに身元保証人になってほしいと依頼する場合があるようです。相談を受けたら、自治体の窓口や地域包括支援センターなどに相談するようにしましょう。
利用者さんの金銭管理
ケアマネジャーは、要介護認定の申請や給付管理のために、利用者さんの経済状況をある程度把握しています。そのため、利用者さんの金銭管理を頼まれることがあるかもしれませんが、ケアマネジャーが担当することはできません。
ケアマネジャーが利用者さんの経済状況を把握するのは、あくまで業務をするうえで必要なためです。利用者さんのお金を預かって管理することはトラブルにつながる恐れがあるので、注意しましょう。
▼関連記事
災害時の介護支援専門員(ケアマネージャー)の役割について
ケアマネジャーに必要な資格
ケアマネジャーになるには、「介護支援専門員」の資格を取得する必要があります。資格の概要や取得方法を、以下に詳しくまとめました。
介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護支援専門員(ケアマネジャー)を取得するには、都道府県が実施する「介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)」に合格し、「介護支援専門員実務研修」を修了する必要があります。
介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)
介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)は、都道府県が年に1回実施する試験です。介護支援分野25問、保健医療福祉サービス分野35問の、全60問がマークシート形式で出題されます。合格基準は、各分野で70%以上得点することですが、その年の試験問題の難易度に基づき合格点が補正されます。
ケアマネ試験の受験要件としては、「介護福祉士や社会福祉士、看護師などの国家資格等に基づく業務の実務経験5年以上」または「相談援助業務の実務経験5年以上」のいずれかが必要です。
介護支援専門員実務研修
ケアマネ試験に合格した後に受講する「介護支援専門員実務研修」では、ケアプラン作成などに関する専門知識を、およそ87時間の講義と演習で学びます。都道府県によって受講時間や日数は異なるので、気になる方はチェックしてみてください。
ケアマネジャーの資格については、「ケアマネジャーになるには最短で何年?介護支援専門員の受験資格を解説」の記事で解説しているので、ぜひご一読ください。
主任介護支援専門員
ケアマネジャーの上位資格である「主任介護支援専門員」を取得すると、主任ケアマネジャーとして活躍できます。主任ケアマネジャーの役割は、ケアマネジャーの育成や地域福祉への貢献などです。
主任ケアマネジャーになるには、「主任介護支援専門員研修」の修了が必要です。厚生労働省の「「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正について(p.2)」によると、主任介護支援専門員研修を受講するには、次のいずれかを満たす必要があります。
- 専任のケアマネジャーとして5年以上の実務経験がある
- ケアマネジメントリーダー養成研修の修了または日本ケアマネジメント学会が定める認定ケアマネジャーという要件を満たしており、専任のケアマネジャーとしての実務経験が3年以上ある
- 主任介護支援専門員に準ずる者として、地域包括支援センターで働いている
- ケアマネジャーの業務に関する知識と経験があることを都道府県から認められている
ケアマネジャーとして実務経験を積み、高い専門性を身につけることで、主任ケアマネジャーを目指せます。主任ケアマネについて、詳しくは「主任ケアマネとは?仕事内容や役割、取得するメリット、資格要件を解説!」の記事もご参照ください。
出典
厚生労働省「「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正について」(2024年12月26日)
ケアマネジャーの仕事のやりがい・魅力
ケアマネジャーは、利用者さんやそのご家族に直接関わって支援できるため、感謝の言葉をもらえることもあり、やりがいを感じられる仕事です。提案したケアプランや介護サービスにより、利用者さんの生活の質が向上したり要介護度が低くなったりしたときは、喜びも大きいでしょう。
ほかにも、ケアマネジャーの仕事のやりがいとして、これまでの人生経験を活かして活躍できることも挙げられます。年齢を重ねて経験が増えることで、活動の幅が広がる場合もあるようです。また、利用者さんの気持ちに寄り添って支援するなかで、多種多様な価値観を学ぶこともできるでしょう。
ケアマネジャーは、自分のペースで業務を進められるのも魅力の一つです。複数の利用者さんの対応を同時進行で行うため、マルチタスク能力が必要ですが、仕事の順番や時間配分は自分で決定できます。また、事務作業が多く、体力的な負担が少ないのも魅力といえるでしょう。
▼関連記事
ケアマネのやりがいとは?目指すメリットや資格の取得方法も解説
ケアマネジャーの役割に関するよくある質問
ここでは、ケアマネジャーの役割についてよくある質問に回答します。ケアマネジャーの仕事に興味がある方は、ぜひご一読ください。
ケアマネジャーの役割を厚生労働省ではどう定義していますか?
厚生労働省の「介護支援専門員(ケアマネジャー)」によると、ケアマネジャーの役割は、以下のように定義されています。
介護支援専門員とは、要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者とされています。
引用:厚生労働省「介護支援専門員(ケアマネジャー)」
つまり、ケアマネジャーの役割は、要支援・要介護認定を受けている方の相談に乗り、ケアプラン作成や関係機関との連携を行うことです。
出典
厚生労働省「介護職員・介護支援専門員」(2024年12月26日)
ケアマネジャーの仕事をわかりやすく教えてください
ケアマネジャーの仕事は、高齢者の方やご家族などの相談に対応して、適切な介護サービスを利用できるように支援することです。具体的な仕事内容として、ケアプランの作成や給付管理、関係機関との連携、要介護認定の申請代行などが挙げられます。ケアマネの仕事については、この記事の「ケアマネジャー(介護支援専門員)の仕事内容」で解説しているので、チェックしてみてください。
ケアマネジャーに相談できることはなんですか?
ケアマネジャーに相談できることは、生活上の不安や問題点、介護サービスの利用について、家族介護についてなど。利用者さんからの相談が業務範囲外だった場合に、適切な相談先・支援先につなげるのも、ケアマネの役割の一つです。ケアマネジャーは、利用者さんの介護サービスへの不安や疑問を解消するために、介護サービス利用に関する手続きの代行や、関係機関への連絡も行います。
生活相談員とケアマネジャーの違いはなんですか?
生活相談員とケアマネジャーの違いは、資格要件や役割です。以下で確認してみましょう。
| 資格要件 | 役割 | |
| ケアマネジャー | ・介護支援専門員 | ・相談援助業務・ケアプランの作成・給付管理・医療機関や介護サービス事業所への連絡と調整・要介護認定の申請 |
| 生活相談員 | ・社会福祉士・精神保健福祉士・社会副主事・介護業務の実務経験など自治体ごとに設定 | ・相談援助業務・介護職員やケアマネなど関連機関への連絡と調整 |
施設によっては、ケアマネジャーが生活相談員を兼務する場合もあります。生活相談員とケアマネの違いについて、詳しくは「生活相談員とケアマネの違いを解説!仕事内容や職場、必要な資格、給与は?」の記事でご紹介し得ているので、ご参照ください。
まとめ
ケアマネジャーの役割は、介護や支援が必要な方の相談に対応して、適切な福祉サービスを利用できるようにケアプランを作成することです。自治体や医療機関、介護施設との連絡・調整も行います。また、給付管理や要介護認定の申請代行など、介護に関わる事務作業も、ケアマネジャーの重要な役割です。
ケアマネジャーは、介護施設や居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなどで活躍しており、職場によってケアマネの役割や仕事内容も異なります。
ケアマネジャーになるには、介護支援専門員の資格が求められます。資格を取得するには、「介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)」への合格と、「介護支援専門員実務研修」の修了が必要です。
「今は施設ケアマネだけど居宅の経験も積みたい」「ベテランのケアマネがいる職場で未経験から学びたい」など、ケアマネジャーとして転職したい方は、「レバウェル介護(旧 きらケア)」にご相談ください。
レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した転職エージェントです。ケアマネジャーの働き方や職場に詳しいアドバイザーがヒアリングを行い、あなたの希望に合った職場を探してご提案いたします。サービスはすべて無料なので、ぜひ気軽にご相談ください。
今の職場に満足していますか?