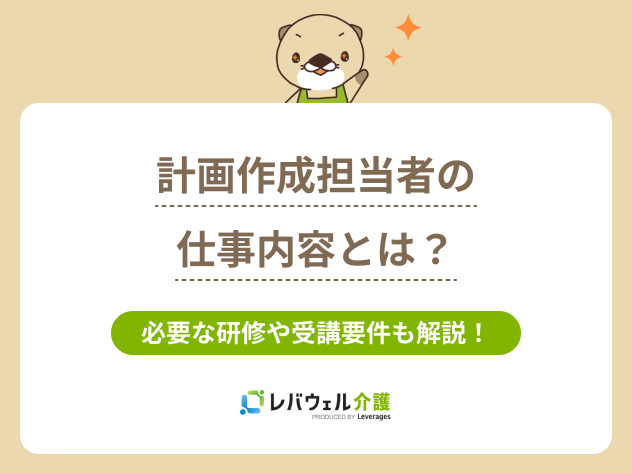
この記事のまとめ
- 計画作成担当者とは、介護施設でケアプランを作成する職員のこと
- 計画作成担当者の仕事内容は、ケアプランの作成やモニタリングなどがある
- 計画作成担当者になるには介護支援専門員資格や認知症介護実践者研修が必要
計画作成担当者の仕事内容に興味のある介護職員の方もいるのではないでしょうか。計画作成担当者の仕事内容は、グループホームや小規模多機能型居宅介護などで、利用者さんの状況に沿った計画(ケアプラン)を作成することです。この記事では、計画作成担当者の仕事内容をはじめ、従事するために必要な研修とその概要をまとめました。介護業界でキャリアアップをしたいとお考えの介護職員の方は、ぜひ参考にしてみてください。
介護業界で働く職種一覧!仕事内容から必要な資格までご紹介計画作成担当者とは
計画作成担当者とは、利用者さんが心身の状況や環境に合った介護サービスを受けられるよう、計画(ケアプラン)を作成する職員のことです。主に、グループホームや小規模多機能型居宅介護などで活躍しています。
配置基準
厚生労働省の「認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)(p.33)」によると、計画作成担当者の配置基準は以下のとおりです。
- グループホーム…事業所ごとに1人以上
- 小規模多機能型居宅介護…事業所ごとに1人以上
- 地域密着型介護老人福祉施設(老健)…施設ごとに1人以上
- 地域密着型特定施設入居者生活介護…施設ごとに1人以上
施設や事業所によって担当件数は異なりますが、計画作成担当者を1名以上配置することが義務付けられています。
資格の有無
厚生労働省の同資料(p.28)(p.33)によると、計画作成担当者の人員要件には、「介護支援専門員であって、認知症介護実践者研修を修了した者」とあります。グループホームや小規模多機能型居宅介護の場合は、さらに認知症介護実践者研修修了者であることも要件です。
詳しくは、「計画作成担当者になるために必要な研修」で後述しますが、計画作成担当者の仕事に興味のある方は、施設や事業所によって必要な資格は異なることを念頭に置きましょう。
出典
厚生労働省「第218回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2025年1月17日)
今の職場に満足していますか?
計画作成担当者の仕事内容
計画作成担当者の主な仕事内容は、利用者さんのケアプラン作成です。ケアプランを作成するために利用者さんやそのご家族と面談したり、場合によっては施設のほかの仕事を兼務したりすることもあります。
以下に、計画作成担当者の具体的な仕事内容をまとめたので、チェックしてみましょう。
1.利用者さんとご家族への面談(アセスメント)
計画作成担当者が行う仕事の一つが、利用者さんやそのご家族との面談です。ケアプランを作成する前に利用者さんやご家族にヒアリングすることで、実際に困っていること、その背景や原因、心身の状態等を把握して、問題を解決するための道筋を一緒に考えます。
2.ケアプランの作成
面談から解決すべき課題を把握したら、ケアプランを作成していきます。ケアプランを作成する際は、ほかの介護スタッフと協議しながら、援助の目標やそれを達成するために行う具体的なサービス内容を検討するのが流れです。サービスの内容について利用者さん側に説明したうえで、同意を得るのも計画作成担当者の仕事です。
3.利用者さんのモニタリング
利用者さんの心身の状態や生活状況は日々変化するため、ケアプランの実施状況をモニタリングすることも欠かせません。計画作成担当者は、定期的なモニタリングを通して、「介護計画に基づくサービスが提供できているか」「利用者さんの状況に変化や課題は見られるか」など、状況を細かく確認します。
4.かかりつけ病院や医師との連携と情報共有
計画作成担当者は利用者さんの健康状態をチェックし、かかりつけ病院や医師との連携・情報共有をします。内服薬の管理や日常生活の記録を行い、入居者さんのご家族へ報告することなども、計画作成担当者の仕事です。
5.ケアプランの見直し・評価・修正
ケアプランを実施して一定期間が過ぎたら、評価と見直しを行わなければなりません。ケアプランを作成する際に立てた目標やサービス内容を確認し、修正が必要だと思われる場合にはケアプランの修正を行います。
6.利用者さんのクレーム・緊急の対応
計画作成担当者は利用者さんやご家族からのクレーム対応を行うこともあります。また、利用者さんの急変により施設から連絡がくることも。緊急時に適切なサービスを提供できるよう、介護計画を考えるのも計画作成担当者の仕事です。
7.介護業務
計画作成担当者は、業務に支障がない範囲であればほかの職務に従事することもできます。計画作成担当者は、介護支援専門員または介護職員として介護サービスに携わってきた経験を持つ人です。そのため、計画作成担当者が介護スタッフとして介護業務を行う場合も少なくありません。
8.電話・来客応対
計画作成担当者は、業務に支障がない範囲であれば、ケアプラン作成以外の業務を行うことができます。先述した介護業務を兼任するほかに、施設への来客や電話への対応を行うこともあるようです。
▼関連記事
グループホームの仕事内容とは?役立つ介護の資格や給料事情を解説
計画作成担当者になるために必要な研修
グループホームや小規模多機能型居宅介護で計画作成担当者になるには、介護支援専門員の資格のほか、「認知症介護実践者研修」を修了していることも条件です。
また、小規模多機能型居宅介護の場合は、「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を修了する必要もあります。
ここでは、東京都の実施状況を例に、計画作成担当者を目指す方が押さえておきたい「認知症介護実践者研修」の受講概要についてまとめました。
受講要件
東京都の場合、認知症介護実践者研修を受講するには、「東京都内(除外地域あり)の介護保険施設や事業所(居宅介護支援事業所を除く)に従事している介護職員であること」や「認知症の人の介護に関する経験が原則として2年程度以上あること」などの要件を満たす必要があります。自治体によっては、認知症介護基礎研修を修了していることが受講要件となっているところもあるので、働いている地域の受講情報は必ず確認するようにしてください。
受講料
東京都の場合、受講のための受講料はかかりません(2025年1月17日現在)。ただし、自治体によっては、10,000~30,000円程度の受講料が必要な場合もあります。
受講スケジュール
認知症介護実践者研修の研修期間は、eラーニング研修による講義が2日間、集合型研修による講義・演習が4日間、自施設実習が約2週間となっています。1~2日目のeラーニング研修の受講方法は、専用サイトから配信する動画を視聴する形です。特に会場は設けられていないため、自分が所属する事業所で受講できます。3~6日目の集合型研修は、自治体が指定する会場で受講する形です。
詳しい受講方法は、申し込み後に送られてくる受講票に記載されているので、必ず確認しましょう。
認知症介護実践者研修については、「認知症介護実践者研修とは?資格の概要や取得するメリットを解説」でも解説しているので、こちらもあわせてご覧ください。
出典
東京都福祉保健局トップページ(2025年1月17日)
▼関連記事
計画作成担当者になるには?必要な資格と求人の見つけ方を紹介
計画作成担当者の活躍場所
最後に、計画作成担当者の活躍場所についてご紹介します。将来的に計画作成担当者を目指そうという方は、しっかり確認しておきましょう。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
計画作成担当者の活躍場所の一つは、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)です。グループホームで計画作成担当者として業務するためには、「認知症実践者研修」を受講しなくてはなりません。認知症実践者研修について詳しく知りたい方は、「認知症介護実践者研修は難しい?資格取得の方法やメリットを解説」をご覧ください。
地域密着型サービス施設(小規模多機能施設など)
短期滞在型の地域密着型サービス施設「ショートステイ(小規模多機能型居宅介護)」では、計画作成担当者を配置することが規定されています。小規模多機能型居宅介護は同一の介護事業者が「通所(デイサービス)」をメインにし、「訪問(ホームヘルプ)」、「泊まり(ショートステイ)」などの介護サービスを一体的に提供する介護サービスです。
地域密着型サービス施設で計画作成担当者として業務に当たるうえで、必須となる資格はありません。しかし、介護報酬の関係から、介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格保持者を求められることもあります。介護支援専門員の資格があると、転職にも有利に働くので取得を検討してみるのも良いでしょう。
▼関連記事
小規模多機能型居宅介護で働くのに資格は必要?介護職員として活躍する方法
ケアマネージャーになるには最短で何年?受験資格や取得までの流れを解説
計画作成担当者の仕事内容に関するよくある質問
ここでは、計画作成担当者の仕事内容に関するよくある質問に回答します。計画作成担当者の仕事に興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
計画作成担当者の仕事内容はなんですか?
計画作成担当者の主な仕事内容は、利用者さんのケアプランの作成です。ケアプラン作成のために、利用者さんやそのご家族との面談なども行います。施設によっては、介護職員の仕事など、ほかの業務を兼務することもあるようです。
詳しい仕事内容は、この記事「計画作成担当者の仕事内容」で紹介しているので、ぜひご覧ください。
ケアマネジャーと計画作成担当者の仕事内容の違いは何ですか?
計画作成担当者とケアマネジャーは、どちらもケアプランを作成しますが、細かい仕事内容が異なります。具体的には、ケアマネジャーに比べて計画作成担当者のほうが、ケアプラン作成以外の事務作業や介護業務の兼務をすることが多い傾向があるようです。
詳しくは、「計画作成担当者とケアマネジャーの違いを解説!必要な資格や仕事内容を比較」で解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
まとめ
計画作成担当者の仕事内容は、グループホームや小規模多機能型居宅介護などにおいて、利用者さんの心身の状況や希望、環境等を踏まえた介護サービスのケアプランを立てることです。施設や事業所によっては、介護業務と兼任する場合もあるので、介護業界で幅広い仕事を経験できます。
計画作成担当者になるには、ケアマネジャー資格のほか、施設によって認知症介護実践研修や小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修などの研修を修了しなければなりません。求められる知識が増える分活躍の場も広がり、介護業界でキャリアアップを目指すことが可能ですよ。
「計画作成担当者を目指したいけど具体的にどうすれば良いか分からない…」「将来的にキャリアアップできる職場に転職したい!」という介護職員の方は、介護業界専門の転職エージェント「レバウェル介護(旧 きらケア)」にご相談ください。専任のキャリアアドバイザーが、希望や適性に沿った介護求人をご紹介いたします。転職のサポートもいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
今の職場に満足していますか?
 グループホームの求人一覧はこちら
グループホームの求人一覧はこちら