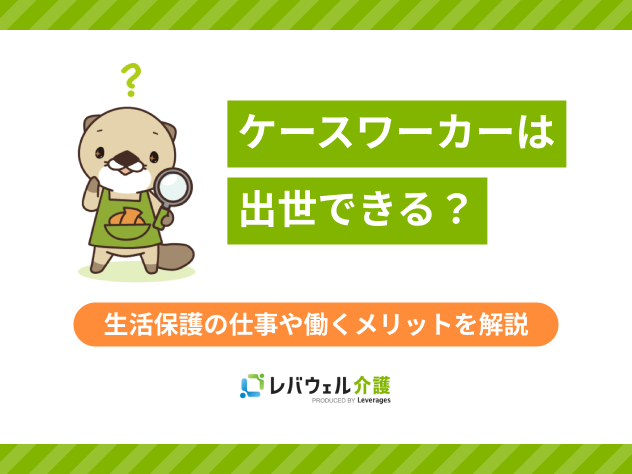
この記事のまとめ
- 自治体や年齢によって異なるが、ケースワーカーから出世するコースもある
- ケースワーカーのやりがいは、信頼関係を築けることや人の役に立てること
- ケースワーカーとしての経験を積めば、介護福祉の分野で活躍することも可能
生活保護ケースワーカーとして配属され「出世できるの?」と不安な方もいるかもしれません。生活保護ケースワーカーは、将来違う部署に配属された際に役立つスキルを積める職種です。さらに、業務で身につけた知識やスキル、保有資格は、公務員以外の仕事にも活かせます。この記事では、生活保護ケースワーカーの仕事内容や働くメリット、やりがいを解説。ケースワーカーのキャリアについてまとめたので、ぜひご一読ください。
ケースワーカーから出世する可能性は?
自治体や年齢によって異なりますが、ケースワーカーからいわゆる出世コースである財政課や人事課に異動になる人もいます。必ずしもケースワーカーから出世するとは言い切れないものの、ケースワーカーとしての経験は、コミュニケーションスキルの向上や将来のための人脈づくりに役立つはずです。
下記の見出し「生活保護ケースワーカーとして働くメリット」でも詳しく説明しますが、ケースワーカーは公務員として働くうえで貴重な経験が積める職業といえます。
▼関連記事
ケースワーカーは公務員?仕事内容や必要な資格、働くメリットも解説!
今の職場に満足していますか?
公務員の生活保護ケースワーカーの仕事内容
生活保護ケースワーカーとは、福祉事務所で働く職種です。病気やケガ、高齢になったことなどにより十分な収入がなく、生活に困っている方に対して、相談・援助を行います。主な業務内容は下記のとおりです。
- 相談を受け、支援が必要かどうか調査する
- 生活保護の申請手続きを行う
- 家庭訪問をして適切な支援が行えているかモニタリングする
- 家庭状況に応じた生活保護費を計算する
- 報告書や面接記録などの事務仕事を行う
自治体によって異なりますが、ケースワーカーは「面接担当職員」と「地区担当職員」に分かれています。「面接担当職員」が相談を受けて支援の方針を決め、「地区担当職員」が家庭訪問などでモニタリングをしつつ自立に向けた支援を行うのが基本的な仕事の流れです。
また、ほかの福祉サービスや病院と連携して必要な支援につなげたり、就労支援を行ったりもします。
▼関連記事
ケースワーカーとは?必要な資格や仕事内容、ソーシャルワーカーとの違い
生活保護ケースワーカーとして働くメリット
生活保護ケースワーカーとして働くことに不安を感じる方もいるかもしれませんが、公務員に必要な知識やスキルを身につけられるといった魅力のある職種です。ここでは、生活保護ケースワーカーとして働くメリットをご紹介します。
現場で経験を積める
生活保護ケースワーカーは、現場経験が積める代表的な仕事。新卒の場合、現場を知ることを目的に福祉事務所に配属されることもあるようです。さらに、いわゆる出世コースといわれる人事課や財政課、企画課に異動しても、ケースワーカーとしての経験は大いに役に立つはず。現場への理解が深ければ、上司からも頼りにされるでしょう。
行政職の業務は、現場に直接関わらない部署であっても、最終的には現場へとつながっています。現場のことを分かっていたほうが、スムーズに仕事ができる傾向にあるため、将来異動する場合も経験を活かせるでしょう。
医療や福祉に関する制度の知識を身につけられる
生活保護ケースワーカーには、公務員として重要な、医療や福祉といった幅広い制度の知識を身につけられるメリットがあります。
生活保護制度は「他法・他施策の優先」といって、ほかの制度では補えない場合しか受給できないのが基本です。そのため、ケースワーカーは、老齢年金や障害年金、介護保険、自立支援医療など、生活保護以外の制度についても把握しておかなければなりません。制度に関する幅広い知識を身につけられるのは、生活保護ケースワーカーの特徴です。
他職種と関わることで視野が広くなる
多角的な視点から仕事に携われるのも、生活保護ケースワーカーになるメリットです。公務員の仕事のなかでも、さまざまな経験を積める職種といえるでしょう。
生活保護ケースワーカーは各世帯が抱える課題を把握し、医療施設や児童相談所、社会福祉協議会などと連携して仕事をするのが基本です。医療従事者や児童福祉司、精神保健福祉士といった公務員以外の職種と、家庭訪問をしたり意見交換をしたりする場も多いでしょう。実際に他職種と関わることで、地域で人脈を築けたり、多様な意見を学べたりします。
生活保護ケースワーカーとしてのやりがい
生活保護ケースワーカーがやりがいを感じられる場面として、「信頼関係を築けたとき」「人の役に立てたとき」などがあります。
適切な支援を行うには、相談者の方の現状だけではなく過去も知ることが重要です。とはいえ、生活保護の相談に訪れる方の多くは、最初からすべてを話してはくれません。面談や家庭訪問を何度も重ね、深い内容まで話してくれるようになると、うれしいと感じる方が多いようです。
ほかにも、自分のサポートによって状況が良くなり、支援が必要なくなったときに、やりがいを感じるという方もいます。「誰かの生活を支える仕事をしたい」という方は、仕事にやりがいを感じられるでしょう。
ケースワーカーのやりがいは、「ケースワーカーのやりがいとは?仕事で大変なことについても解説!」でも解説しているので、あわせてご覧ください。
経験を積んでから福祉の仕事に転職する道もある
人を支える仕事にやりがいを感じる場合は、福祉系のほかの職種に転職するのも選択肢の一つです。生活保護ケースワーカーが持つ「社会福祉主事任用資格」は、福祉分野のほかの仕事にも活かせます。
社会福祉主事任用資格は、介護施設の施設長や生活相談員の要件の一つです。生活相談員とは、特別養護老人ホーム(特養)やデイサービスなどの施設で、介護サービスを利用している方の相談援助を行う職種。生活保護ケースワーカーは、幅広い年齢の方を対象にしているのに対して、生活相談員は高齢の方やそのご家族の支援を主に行います。
生活相談員の仕事内容については、「生活相談員に転職したい方必見!必要な資格や仕事内容、介護求人の探し方」の記事をご覧ください。
 社会福祉主事任用の求人一覧ページはこちら
社会福祉主事任用の求人一覧ページはこちら 生活相談員の求人一覧ページはこちら
生活相談員の求人一覧ページはこちら
ケースワーカーについてよくある質問
ここでは、生活保護ケースワーカーについてよくある質問を紹介します。「どんな仕事か詳しく知りたい」という方は、ぜひご一読ください。
ケースワーカーの仕事は忙しいの?
厚生労働省の「支援を担う体制づくり及び人材育成等について(p.16)」によると、ケースワーカーは80世帯につき1人もしくは、65世帯に1人配置するのが基準です。しかし、2021年4月時点でのケースワーカー1人当たりの担当世帯数は平均85.4世帯なので、「仕事が忙しい」と感じる方もいるでしょう。
ただし、仕事量は働く地域や自治体によって大きく異なるため、一概に忙しいとはいえません。自治体によっては、担当件数ではなく訪問回数など業務が割り振られていることもあり、必ずしも「担当件数が多いから忙しい」というわけではないようです。
出典
厚生労働省「第22回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)」(2025年1月17日)
▼関連記事
ケースワーカーは残業が多い?発生理由や対処法、辞めたい人の転職先を紹介
ソーシャルワーカーとケースワーカーの違いは?
ソーシャルワーカーとケースワーカーの違いは、含まれる職種の範囲です。ソーシャルワーカーは、相談援助を行う職種全般を指します。一方、ケースワーカーは福祉事務所などで公務員として相談援助を行う職種のことです。
「ソーシャルワーカーと社会福祉士の違いを解説!仕事内容や必要な資格とは?」の記事では、ソーシャルワーカーと社会福祉士の違いを解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
まとめ
生活保護ケースワーカーには、「現場経験を積める」「医療や福祉に関する幅広い制度の知識を身につけられる」「多角的な視点を持って仕事ができる」といったメリットがあります。
福祉事務所に配属され、「出世コースから外れたのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。しかし、生活保護ケースワーカーはほかの職種では得られないスキルを身につけられる仕事です。将来ほかの部署に異動しても、生活保護ケースワーカーとして培った知識や経験を十分に活かせるでしょう。
また、生活保護ケースワーカーのキャリアとして、「社会福祉主事任用資格」を活かしてほかの福祉系の職種に転職する選択肢もあります。
福祉の仕事の種類が知りたい方や、高齢の方を支える仕事に携わりたい方は、「レバウェル介護(旧 きらケア)」にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護・福祉業界に特化した転職エージェント。ケースワーカーとしての経験を活かせる職場をご紹介できます。スキルによっては給料交渉も可能です。アドバイザーが給料交渉を代行するので、転職活動をスムーズに進められます。
また、「介護業界のことがよく分からない」という方も、業界に詳しいアドバイザーが丁寧に説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
今の職場に満足していますか?

















