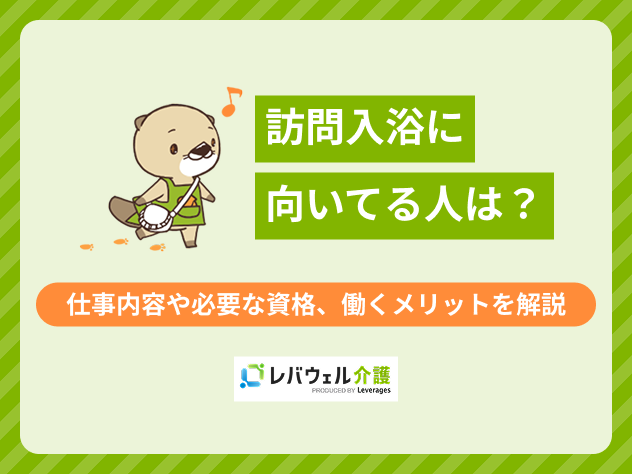
この記事のまとめ
- 訪問入浴に向いてる人は、「一人ひとりに寄り添った介護がしたい人」など
- 訪問入浴の仕事内容は、「浴槽の設置・片付け」「入浴介助」など
- 訪問入浴の仕事は無資格・未経験OKだが、資格があると安心して働ける
「訪問入浴の仕事に向いてる人はどんな人?」と気になる方もいるかもしれません。訪問入浴とは、利用者さんの自宅に浴槽を持っていき、入浴をサポートする仕事。一人ひとりの利用者さんに寄り添った介護をしたい人などに向いています。この記事では、訪問入浴に向いてる人や仕事内容を解説。1日のスケジュールや業務に役立つ資格、働くメリットも紹介するので、訪問入浴の仕事に興味がある方は参考にしてみてください。
訪問入浴とは
訪問入浴とは、寝たきりなど自力で入浴をすることが困難な利用者さんの自宅に浴槽を持ち込み、入浴介助を行う介護サービスのことです。入浴介助は、利用者さんの身体を清潔にして病気を防いだり、心身機能を高めたりすることを目的に行われます。
訪問入浴の利用者の概要
訪問入浴を利用できるのは、要支援1~要介護5いずれかの認定を受けている人です。また、要支援1・2の認定を受けている方も、予防給付として訪問入浴を利用できます。
厚生労働省の「訪問入浴介護(p.9)」によると、訪問入浴の利用者数は、2022年時点で7万人程度です(介護予防を除く)。高齢化の進行により、今後も訪問入浴のニーズはあると考えられます。
訪問入浴の種類
訪問入浴に該当する介護サービスは2種類で、「指定訪問入浴介護」と「指定介護予防訪問入浴介護」があります。
指定訪問入浴介護
指定訪問入浴介護の利用対象者は、要介護1以上の認定を受けている人です。また、訪問入浴サービスを利用するには、医師から入浴の許可を得る必要があります。
厚生労働省の「訪問入浴介護(p.11)」によると、訪問入浴を利用する方の平均要介護度は4.1でした。利用者さんの約9割が要介護3以上のため、現場で接する利用者さんの要介護度は高い場合が多いでしょう。
指定介護予防訪問入浴介護
指定介護予防訪問入浴介護の対象者は、要支援1または2の認定を受けている人です。「自宅に浴室がない」「病気によりほかの施設の浴室を利用できない」などの特別な理由がある場合に利用できます。
訪問介護と訪問入浴の違い
訪問介護でも利用者さんの自宅で入浴介助を行う場合がありますが、訪問入浴とはいくつか違いがあります。訪問入浴は浴槽を持ち込みますが、訪問介護は利用者さんの自宅の浴室を使用して介助を実施。職員の人数も異なり、訪問入浴は基本的に3人ですが、訪問介護は1人だけで業務を行います。
また、訪問入浴は利用者さんの入浴の介護が主な仕事ですが、訪問介護は身体介護全般を担うほか、生活援助など幅広いケアを実施するサービスです。訪問介護が一般的な介護全般を行うのに対し、訪問入浴は「入浴」に特化した介護を行います。
出典
厚生労働省「第220回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2025年3月6日)
▼関連記事
訪問介護とは?仕事内容や必要な資格、働くメリットをわかりやすく解説
今の職場に満足していますか?
訪問入浴に向いてる人
ここでは、訪問入浴の仕事に向いてる人の特徴を解説します。「訪問入浴に興味があるけど、自分に合う仕事かどうか分からない」という方は、自身が当てはまるかチェックしてみましょう。なお、下記に当てはまらないからといって訪問入浴に向いてないとは限らないので、参考としてご覧ください。
一人ひとりに寄り添った介護がしたい人
一人ひとりに寄り添った介護がしたい人は、訪問入浴の仕事にやりがいを感じられる可能性が高いでしょう。訪問入浴は利用者さんの自宅で介護を行うため、同時進行で複数の利用者さんに対応しません。そのため、利用者さんを一人ずつサポートしたい方に向いているでしょう。
一つの業務に特化した仕事がしたい人
訪問入浴は提供するサービスが入浴に特化しているので、一つの業務に専門的に取り組みたい方に向いています。訪問入浴で行うのは、基本的に入浴介助やそれに関連する業務のみです。そのため、「マルチタスクが苦手」「専門性を高めたいから一つの業務に集中したい」という方は、適性があるかもしれません。
体力・健康面に自信がある人
入浴介助は一定の体力がいる仕事なので、体力がある人や健康に自信がある人は訪問入浴に向いています。
入浴介助は、利用者さんの身体を支えながら、身体を洗ったり拭いたりしなければなりません。自身より身長が高い方を支えることもあり、体力的な負担があります。体力がある人や健康的な人は、それを活かして訪問入浴の仕事ができるでしょう。
協調性がありチームケアが得意な人
訪問入浴はチームワークが求められる仕事なので、協調性がある人に向いています。訪問入浴では、浴槽を組み立てたり着替えを準備したりするため、誰が何をしているのか把握したうえで、自分が何をすべきか考えなくてはなりません。チームで協力して効率良く準備できれば、利用者さんにスムーズに入浴してもらえるでしょう。
コミュニケーションスキルがある人
利用者さんと積極的にコミュニケーションが取れる人も、訪問入浴の仕事に向いています。訪問中は、職員同士だけで会話をし、作業的に入浴介助をするのはNG。利用者さんが気まずくなったり居心地が悪いと感じたりしないように、配慮あるコミュニケーションを取ることが大切です。
また、利用者さんとの会話から体調の変化に気づくことは、コミュニケーションスキルがないとできません。そのため、コミュニケーションスキルがある人や会話が好きな人は、訪問入浴に適性があるといえるでしょう。
細かいところに配慮できる人
細かなところに目が届き気配りができる人も、訪問入浴の仕事に向いています。入浴には脱衣を伴うため、利用者さんの羞恥心やプライバシーへの配慮は欠かせません。
また、利用者さんの自宅に機材を持ち込むときは、床や壁を傷つけたり汚したりしないように注意するといった配慮も必要です。
手際が良い人
手際が良ければ、利用者さんを待たせることなく入浴介助ができます。訪問入浴は、1日に5~7件程度の訪問が基本です。1訪問あたり45分~1時間以内の限られた時間で、効率良く質の高いケアをする必要があります。てきぱき動けたり先回りして行動できたりする方なら、利用者さんに必要な介助を漏れなく提供できるでしょう。
日勤のみで働きたい人
訪問入浴の営業時間帯は日中なので、日勤のみで働きたい方に向いている仕事です。「介護の仕事をしたいけど、夜勤はできない」という方は、日中のみのサービスを選べば、プライベートと仕事を両立させられるでしょう。
訪問入浴の仕事内容
ここでは、訪問入浴の仕事内容を解説します。訪問入浴をスムーズに行うには、利用者さんの心に寄り添い、気持ちを汲み取ることが大切です。
浴槽の設置・片付け
訪問入浴の浴槽は持ち込みなので、浴槽の設置や片付けの業務があります。浴槽は、2畳分程度のスペースを確保できれば設置可能です。
給湯の際は、基本的に利用者さんの自宅の水道から入浴車をホースでつなぎ、車内の湯沸かし器で準備したお湯を使用します。訪問入浴車からの給湯が困難な場合は、利用者さん宅の給湯器を利用することもあるようです。排水は、利用者さん宅の浴室やトイレなどの排水設備を利用します。
スペース確保のために家具を移動させた場合は、浴槽の片付け後に元に戻さなくてはいけません。
バイタルチェック
介護職員が浴槽の設置などの準備を行っている間に、看護職員が利用者さんのバイタルチェックを行います。体温、脈拍、血圧などを測定し、入浴しても問題がないか判断。利用者さんの体調が悪いときは、足浴や清拭などに切り替えます。
入浴中や入浴後も、体調が悪くなっていないか、肌に異常がないかを細かくチェックしなければなりません。
入浴介助
職員3人で利用者さんの入浴をサポートします。洗髪・洗顔・洗身を行う際は、利用者さん一人ひとりの要望に沿った介助を行うよう心掛けましょう。入浴中は、利用者さんに声をかけながら、ゆっくりとした動作をすることが基本です。安全に気を配りながら、利用者さんがリラックスして入浴できる環境を整えましょう。
更衣介助
利用者さんの更衣介助も訪問入浴の仕事です。入浴前・入浴後の着替えをお手伝いします。利用者さんの身体が冷えないよう、着替えをする場所の温度にも気を配りましょう。利用者さんの身体機能を維持するためにも、ズボンを上げるときの腰の上げ下げなど、できることは自分で行ってもらうことが大切です。
▼関連記事
【入浴介助マニュアル】手順や注意点、時間短縮のコツ
訪問入浴で働いている職種と人員基準
厚生労働省の「訪問入浴介護(p.4)」によると、訪問入浴に配置される職員と人員基準は以下のとおりです。
| 従業者 | ・ 看護師または准看護師を1人以上配置・ 介護職員を2人以上配置(介護予防訪問入浴介護の場合には1人以上) |
| 管理者 | 事業所に1人配置(常勤・専従が原則) |
参考:厚生労働省「訪問入浴介護(p.4)」
訪問入浴を提供する事業所では、主に介護職員や看護職員、管理者が働いています。基本的に「介護職員2人と看護職員1人」で訪問入浴を行った場合に介護報酬が算定されるため、訪問時は3人体制が組まれている場合が多いでしょう。
介護職員
介護職員は、利用者さんの入浴のサポート全般を行います。未経験から十分活躍できる可能性があり、看護職員や管理者よりも配置人数が多いので、訪問入浴介護事業所で働きたい方が挑戦しやすい職種です。
看護職員
看護職員は、利用者さんのバイタルチェックなど、健康面の管理を行うのが仕事です。看護師や准看護師の資格があり、高齢者の在宅生活を支援したい方は、訪問入浴の仕事も視野に入れると良いかもしれません。
訪問入浴オペレーター
訪問入浴オペレーターは、主に車の運転や浴槽機器など関連機材の設置・準備、メンテナンスがメインの仕事です。3人で訪問する場合、介護職員のうち1人が担います。
利用者さんの自宅までの道を把握したり、利用者さんに合わせてお湯の温度を調整したりなど、対応することが多いものの、仕事をこなすうちに慣れる方も少なくありません。運転免許を保有していれば、介護系の資格がなくてもオペレーターとして働けます。
管理者
管理者は、訪問入浴介護のサービスを管理します。人事や労務、会計、ケアマネジャーとの連携などが主な仕事です。管理業務に支障がなければ、介護職員としての兼任も可能な場合があります。
訪問入浴の管理者には資格要件がありません。介護に関する知識やスキルが求められるので、管理者を目指す方は、介護職員として実績を積んだり介護福祉士を取得したりすると良いでしょう。
出典
厚生労働省「第220回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2025年3月6日)
訪問入浴の勤務時間・1日のスケジュール
ここでは、訪問入浴の1日のスケジュール例をご紹介します。「業務の流れが気になる」という方は、以下を参考に働く姿をイメージしてみてくださいね。
| 時間 | 仕事内容 |
| 午前8時30分 | 出勤、訪問準備 |
| 午前9時 | 訪問入浴(3件程度) |
| 正午 | 休憩 |
| 午後1時 | 訪問入浴(4件程度) |
| 午後5時 | 帰社、事務作業 |
| 午後5時30分 | 退勤 |
訪問入浴は、午前8時30分~9時ごろに出勤し、午後5時30分~6時ごろに退勤する場合が多いようです。1件あたりの訪問時間は40~50分程度が多く、1日の訪問件数は5~7件程度となります。
訪問入浴で働くメリット
訪問入浴の仕事の魅力は、「やりがいがある」「夜勤がない」「チームで働ける」などです。
利用者さんやご家族から感謝されるやりがいがある
訪問入浴は利用者さんとの距離が近いので、利用者さんやご家族から直接感謝の言葉をもらう機会が多い仕事です。利用者さんの笑顔や感謝の言葉は、仕事のやりがいにつながるでしょう。
▼関連記事
ホームヘルパーのやりがいとは?仕事内容や向いている人の特徴もご紹介!
夜勤がない
前述したように、訪問入浴の仕事には夜勤がなく、日勤が基本です。2交代制や3交代制で働く必要がないため、「生活習慣を崩さず働きたい」という方におすすめといえます。
3人体制のチームで働ける
チームで協力しながら仕事ができるのも、訪問入浴のメリットの一つです。業務中に分からないことがあってもすぐに質問ができる環境なので、介護の仕事が未経験でも安心して働けます。仲間と協力して仕事に取り組み、助け合ったり喜びを分かち合ったりできるのが魅力です。
訪問入浴で働くうえで大変なこと
訪問入浴の仕事で大変なのは、人手不足で忙しいことや、利用者さんに応じた介護が難しいこと、体力を使うことです。
人手不足で忙しい場合がある
限られた人員で仕事をこなす必要があるため、多忙なときがあります。介護業界は慢性的な人手不足の状況で、訪問入浴の現場も例外ではありません。離職者がいる一方で新規採用が難しい状況なので、現職の職員に負担が偏ってしまう傾向にあるようです。
利用者さんに応じた介護が難しい
訪問入浴を利用する方は要介護度が高いことが多いため、利用者さんの状態に応じた適切な入浴サポートをすることを難しいと感じる場合があります。また、体格の大きい利用者さんの入浴介助をする場合、身体を支える際の身体的負担が大きく、大変に感じるかもしれません。
体力を使う
浴槽機器の持ち運びやセッティング、利用者さんの移乗介助など、訪問入浴は体力を必要とする仕事です。車での移動時以外は基本的に体を動かすので、体力的に大変と感じたり、腰痛でしんどいと感じたりするかもしれません。入浴介助は汗をかきやすい業務なので、こまめに水分補給を行うなど、健康管理に気をつける必要があります。
訪問入浴の仕事は経験・資格なしでも働ける?
ここでは、訪問入浴の仕事に資格や実務経験が必要なのかを解説します。
無資格・未経験から勤務可能!
訪問入浴の仕事に資格要件はありません。必要な実務経験もないので、介護の仕事に初めて就く方も挑戦することが可能です。有資格者である看護師と一緒に訪問するため、介護職員は無資格から働けます。なお、介護業務を行う無資格の方は、入職から1年以内に認知症介護基礎研修を修了することが必要です。
無資格・未経験から応募可能な訪問入浴の求人もありますが、資格を有していれば選考で有利になるので、可能なら資格の取得を検討してみると良いかもしれません。
訪問入浴の仕事に役立つ資格
ここでは、訪問入浴の仕事に役立つ資格をご紹介します。無資格から訪問入浴の仕事はできますが、介護度が高い利用者さんが多いため、資格を取得して介護のスキルを身につけると安心して働けるでしょう。
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修は、介護の入門的な資格です。取得すれば、介護の基本的な知識や技術を有していることを証明できます。受講資格はなく、誰でも挑戦できる資格です。
初任者研修は、スクールで130時間分(10科目)のカリキュラムを履修し、1時間ほどの筆記試験に合格することで取得できます。試験の内容は基礎的な問題なので、しっかりと勉強すれば不合格になる可能性は低いでしょう。
初任者研修の取得方法を詳しく知りたい方は、「介護職員初任者研修とはどんな資格?受講費用を抑える方法や取得のメリット」もあわせてご覧ください。
首都圏限定!資格取得が無料!
転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!
レバウェル介護の資格スクール介護福祉士実務者研修
介護福祉士実務者研修は、初任者研修のワンランク上に位置する資格。介護の実践的な知識・技術を身につけることが可能です。初任者研修と同様に受講資格は設けられていないため、誰でも取得を目指せます。
実務者研修を修了するには、スクールで450時間分(20科目)のカリキュラムを履修しなくてはなりません。履修後の筆記試験の有無は各スクールによって異なるので、事前に確認しておきましょう。
なお、初任者研修の資格をすでに取得している人は、130時間分のカリキュラムが免除されます。
実務者研修の取得方法は、「介護福祉士実務者研修とは?資格取得のメリットや初任者研修との違いを解説」の記事で解説しているので、気になる方はぜひご覧ください。
介護福祉士
介護福祉士は、介護の資格の中でも専門性が高く、国家資格に分類されます。介護に関する高い専門知識・技術を有していることを証明する資格なので、取得すると介護業界で大いに活躍できるでしょう。
介護福祉士を取得するには、受験要件を満たしたうえで介護福祉士国家試験を受験し、合格する必要があります。たとえば、4つの受験ルートのうち「実務経験ルート」で受験する場合、「実務経験を3年以上積む」「介護福祉士実務者研修を取得する」という2つの条件を満たすことで、介護福祉士国家試験を受けられます。働きながら取得を目指せるので、介護職としてキャリアアップしたい方におすすめの資格です。
介護福祉士の取得方法を詳しく知りたい方は、「介護福祉士とはわかりやすくいうとどんな資格?取得方法や試験概要を解説!」の記事もあわせてご覧ください。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格」(2025年3月6日)
訪問入浴に関するよくある質問
ここでは、訪問入浴に関するよくある質問にお答えします。訪問入浴の仕事に興味がある方や転職を検討している方は、チェックしてみてください。
訪問入浴で起こり得るトラブルは何ですか?
訪問入浴で起こり得るトラブルは、利用者さんの体調悪化や転倒などの事故です。利用者さんの様子に常に気を配りながら、移乗介助や入浴介助を行いましょう。また、利用者さんが入浴を拒否することもあるかもしれません。入浴のケアを行う際は、利用者さんを不安にさせたり、不快感を与えたりしないようにすることが大切です。対人トラブル以外では、入浴機器の不具合も考えられます。
訪問入浴のお湯はどこから用意するんですか?
訪問入浴で使用するお湯は、利用者さん宅の水を訪問入浴車で沸かして用意します。利用者さん宅の水道と訪問入浴車をホースでつなぎ、車内の湯沸かし器で準備。訪問入浴車からの給水が難しい場合は、利用者さん宅のお湯を使用することもあるようです。入浴後のお湯は、利用者さん宅で排水します。水自体の用意は、利用者さん宅で行うと覚えておきましょう。
訪問入浴に転職したいときに取得していると有利な資格は?
訪問入浴は、訪問入浴車で利用者さんの自宅に向かうので、自動車の運転ができると採用に有利になる可能性があります。選考時に運転免許を取得していなくても、取得の予定がある方や取得しようと考えている方は、採用担当者に伝えておきましょう。
訪問入浴の仕事を辞めた人の退職理由は何ですか?
株式会社デベロの「訪問入浴介護の実態に関する調査研究事業報告書(p.66)」によると、訪問入浴の仕事を辞めた人の退職理由は、「身体的負担」が最多の33.2%でした。「ほかに適した仕事が見つかった」が30.5%、「自身の病気等」が25.3%、「人間関係」が24.5%と続きます。身体的負担や病気を理由に退職する方が多いことから、訪問入浴の仕事は体力・健康面に自信がある方に向いているといえるでしょう。
出典
株式会社デベロ「令和3年度老人保健健康増進等事業「訪問入浴介護の実態に関する調査研究事業」」(2025年3月6日)
まとめ
訪問入浴とは、利用者さんの自宅に浴槽を持ち込み、入浴をサポートする仕事です。入浴に関係のない介助業務や生活援助は行いません。訪問入浴介護事業所では、主に介護職員や看護職員、管理者が働いています。
訪問入浴の主な仕事は入浴介助ですが、ただ入浴のサポートをするのではなく、浴槽の設置・片付けやバイタルチェック、更衣介助もしなければなりません。一人ひとりに寄り添った介護をしたい人や体力面に自信がある人、手際が良い人などは、訪問入浴の仕事に向いているでしょう。
無資格でも訪問入浴介護事業所に就職できますが、資格があると選考で有利になったり、入浴介助にスキルを活かせたりします。訪問入浴に役立つ資格は、「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者研修」「介護福祉士」などです。
訪問入浴の仕事に興味がある方は、レバウェル介護(旧 きらケア)を利用してみませんか?レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した就職・転職エージェントです。
介護業界の多種多様な求人を取り扱っているので、あなたの希望条件に合う訪問入浴の求人をお探しいたします。プロのアドバイザーが、就職・転職に関するお悩みや相談にも対応!書類選考や面接のアドバイスも行っています。サービスはすべて無料なので、お気軽にご相談ください。
今の職場に満足していますか?
 日勤のみの求人はこちら
日勤のみの求人はこちら