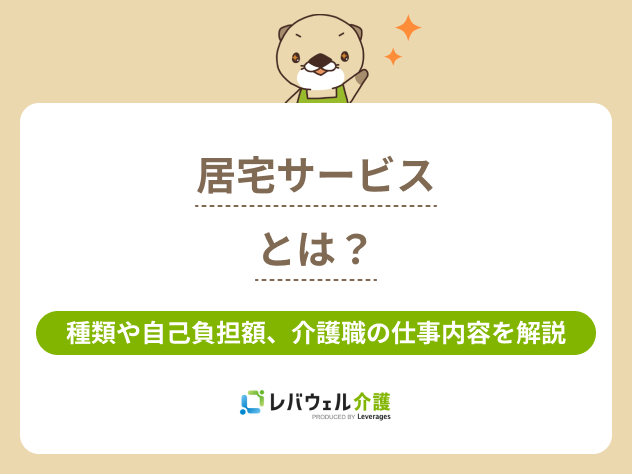
この記事のまとめ
- 居宅サービスとは、自宅で生活する方に提供する介護保険サービスのこと
- 主な居宅サービスは、訪問サービス・通所サービス・短期入所サービスの3つ
- 介護職の仕事内容は、居宅サービスの種類ごとに異なる
介護サービスについて調べるなかで、「居宅サービスって何?」と疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。居宅サービスとは、自宅で利用できる介護保険サービスのことです。この記事では、居宅サービスの種類や内容、目的を解説します。対象者や仕事内容、サービスの利用手続きについてもまとめたので、介護職に興味がある方は参考にしてみてください。
居宅サービスとは
居宅サービスとはわかりやすくいうと、自宅で生活しながら利用できる介護保険サービスのことです。介護保険で利用できるサービスは、居宅サービスのほかに、施設サービスや介護予防サービス、地域密着型サービスなどがあります。
居宅サービスの対象者
介護保険の被保険者は、介護保険制度を利用して居宅サービスを利用できます。対象者は、65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方と、45歳~64歳で特定疾病により要支援・要介護認定を受けている方です。
介護保険サービスを利用するには、自治体(市町村および特別区)へ申請し、要支援状態または要介護状態にあることを認定してもらわなくてはなりません。公的なサービスなので、客観的に必要性があると認められた場合に利用可能です。
なお、介護保険サービスは、要支援1~2・要介護1~5の区分に応じて、支給限度額(利用できるサービスの量)が決まります。例外もありますが、支給限度額の範囲内で利用する介護サービスを組み合わせるのが一般的です。
居宅サービスと在宅サービスの違い
居宅サービスと在宅サービスは、呼び方が異なるだけで大きな意味の違いはありません。利用者さんが、自宅で暮らしながら利用できる介護保険サービスという意味は同じです。
居宅サービスと施設サービスの違い
居宅サービスと施設サービスは、介護サービスを利用する場所に違いがあります。介護職が利用者さんの自宅を訪問するなど、自宅が拠点の介護サービスが「居宅サービス」。一方で、特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、特定の施設に入所してサービスを利用するのが「施設サービス」です。どちらも、介護保険制度が使える介護サービスであることは共通しています。
今の職場に満足していますか?
▼関連記事
ケアプラン(介護サービス計画書)とは?種類や作成の流れ、記載内容、文例
居宅サービスの種類・内容
厚生労働省の「介護保険制度の概要(p.13)」によると、居宅サービスは「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」「その他のサービス」に分類されます。居宅サービスを一覧表にまとめたので、確認してみましょう。
| 居宅サービスの分類 | 居宅サービスの種類 |
| 訪問サービス | ・訪問介護(ホームヘルプサービス) ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 |
| 通所サービス | ・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション(デイケア) |
| 短期入所サービス | ・短期入所生活介護(ショートステイ) ・短期入所療養介護 |
| その他 | ・特定施設入居者生活介護 ・福祉用具貸与 ・特定福祉用具販売 |
参考:厚生労働省「介護保険制度の概要(p.13)」
自宅で利用するサービスのほか、利用者さんが自宅から通う施設も居宅サービスに含まれます。また、「特定施設入居者生活介護」は、介護付き有料老人ホームや介護型のケアハウスなどのことです。介護保険上では、有料老人ホームやケアハウスは集合住宅のような扱いになるため、居宅サービスに分類されます。
以下では、居宅サービスを種類ごとに解説するので、「居宅サービスの内容や利用料を知りたい」という方は、ぜひご覧ください。
訪問サービス
訪問サービスは、介護職、看護職、リハビリ専門職などが居宅に訪問して必要なケアを提供するサービスです。
訪問介護
自宅に介護職員(ホームヘルパー)が訪問し、身体介護や生活援助を行うのが訪問介護です。身体介護とは、排泄介助・入浴介助・食事介助などを指し、生活援助とは、掃除・洗濯・買い物代行などを指します。ホームヘルパーは、「介護職員初任者研修」といった介護系の資格を持つ有資格者です。
介護保険を使って訪問介護サービスの身体介護を利用する場合の自己負担額は、以下のとおりです。なお、1割負担・1単位あたり10円の地域の場合の利用料を記載しています。自己負担額は、負担割合や居住地域のほか、介護事業所が取得する介護報酬の加算の種類によっても異なるので、参考程度にご覧ください。
| 20分未満 | 20分以上30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 1時間30分以上2時間未満 | 2時間以上2時間30分未満 | |
| 身体介護 | 163円 | 244円 | 387円 | 567円 | 649円 | 731円 |
参考:WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)(p.1)」
下記は、訪問介護サービスの生活援助を利用した場合の自己負担額の目安です。
| 20分以上45分未満 | 45分以上 | |
| 生活援助 | 179円 | 220円 |
参考:WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)(p.10)」
訪問介護については、「訪問介護とは?仕事内容や必要な資格、働くメリットをわかりやすく解説」の記事で詳しく解説しているので、あわせてご一読ください。
訪問入浴介護
訪問入浴介護は、介護職や看護職が居宅を訪問し、持ち込んだ浴槽を使って入浴を支援するサービスです。入浴介助や更衣介助、バイタルチェックを行うので、自力での入浴が難しい方や体調に不安がある方も安心して入浴できます。
WAM NETの「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)(p.62)」によると、訪問入浴の利用料は、1割負担・1単位10円の場合、1回1,266円です。
訪問入浴の仕事が気になる方は、訪問入浴に向いてる人は?仕事内容や必要な資格、働くメリットを解説」の記事で解説しています。訪問入浴で働くメリット・デメリットも紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
訪問看護
訪問看護は、看護師や准看護師、理学療法士などが居宅を訪問し、医療的ケアやリハビリを提供するサービスです。主に自宅で療養している方が利用します。
看護師が訪問した場合の自己負担額は以下のとおりです。
| 20分未満(条件付き) | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | |
| 指定訪問看護ステーションからの訪問 | 314円 | 471円 | 823円 | 1,128円 |
| 病院・診療所からの訪問 | 266円 | 399円 | 574円 | 844円 |
参考:WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)(p.63)」
訪問看護を20分未満で利用する場合、20分以上の訪問看護を週1回以上利用していることが条件です。また、夜間・早朝・深夜訪問や2人以上の訪問では費用負担が増えます。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問する場合は、1回当たり294円です。
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションでは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリ専門職が居宅を訪問し、身体機能の訓練などのリハビリを行います。
WAM NETの「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)(p.73)」によると、訪問リハビリテーション費は、1割負担で1回308円です。
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導は、通院が難しい患者さんに対して、医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理・指導を行うサービスです。
| 医師(月2回まで) | 515円 |
| 歯科医師(月2回まで) | 517円 |
| 薬剤師(医療機関) | 566円 |
| 管理栄養士(指定居宅療養管理指導事業所/月2回まで) | 545円 |
| 歯科衛生士(月4回まで) | 362円 |
参考:WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)(p.74)」
なお、上記は1割負担・1単位10円の場合です。地域や施設によって自己負担額に違いが出ることがあります。
通所サービス
通所サービスは、利用者さんが通所介護や通所リハビリテーションを提供する施設に通い、必要なケアを受けるサービスです。
通所介護(デイサービス)
通所介護(デイサービス)は、介護を必要とする方が日帰りで利用する施設です。スタッフは、健康管理や入浴介助などを行い、利用者さんが自立した日常生活を送れるようにサポートします。
| 3時間以上4時間未満 | 4時間以上5時間未満 | 5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | 8時間以上9時間未満 | |
| 要介護1 | 370円 | 388円 | 570円 | 584円 | 658円 | 669円 |
| 要介護2 | 423円 | 444円 | 673円 | 689円 | 777円 | 791円 |
| 要介護3 | 479円 | 502円 | 777円 | 796円 | 900円 | 915円 |
| 要介護4 | 533円 | 560円 | 880円 | 901円 | 1,023円 | 1,041円 |
| 要介護5 | 588円 | 617円 | 984円 | 1,008円 | 1,148円 | 1,168円 |
参考:WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)(p.75)」
なお、上記は1割負担・1単位10円の場合です。自己負担割合のほか、地域や施設によって自己負担額に違いが出ることがあります。
通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーション(デイケア)は、機能訓練を目的に通う介護施設です。スタッフは、健康管理やリハビリテーション、入浴介助などを実施。リハビリが必要な利用者さんの体調・安全面に配慮しながら、機能訓練や日常生活をサポートします。
以下は、老人保健施設に併設されたデイケアを利用する場合の自己負担額です。
| 1時間以上2時間未満 | 2時間以上3時間未満 | 3時間以上4時間未満 | 4時間以上5時間未満 | 5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | |
| 要介護1 | 369円 | 383円 | 486円 | 553円 | 622円 | 715円 |
| 要介護2 | 398円 | 439円 | 565円 | 642円 | 738円 | 850円 |
| 要介護3 | 429円 | 498円 | 643円 | 730円 | 852円 | 981円 |
| 要介護4 | 458円 | 555円 | 743円 | 844円 | 987円 | 1,137円 |
| 要介護5 | 491円 | 612円 | 842円 | 957円 | 1,120円 | 1,290円 |
参考:WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)(p.88)」
なお、上記は1割負担・1単位10円の場合です。自己負担割合のほか、地域や施設によって自己負担額に違いが出ることがあります。
短期入所サービス
短期入所サービスは、利用者さんが短期入所生活介護や短期入所療養介護を提供する施設に一時的に入所し、必要なサポートを受けるサービスです。
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護(ショートステイ)では、施設に一時的に利用者さんが入所し、身体介護や生活援助など、日常生活に必要な支援を受けます。
下記は、単独型施設と併設型施設の自己負担額です。単独型とは、ショートステイを単独で運営する事業所を指します。併設型は、特別養護老人ホームや老人保健施設など、ほかの施設に併設されたショートステイのことです。
| 要介護度 | 単独型施設(個室・多床室) | 併設型施設(個室・多床室) |
| 要介護1 | 645円 | 603円 |
| 要介護2 | 715円 | 672円 |
| 要介護3 | 787円 | 745円 |
| 要介護4 | 856円 | 815円 |
| 要介護5 | 926円 | 884円 |
参考:WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)(p.115)」
下記は、ユニット型の自己負担額です。ユニット型とは、少人数のユニットごとに個室や共用スペースを設けた居室形態を指します。
| 要介護度 | 単独型ユニット型施設(個室・多床室) | 併設型ユニット型施設(個室・多床室) |
| 要介護1 | 746円 | 704円 |
| 要介護2 | 815円 | 772円 |
| 要介護3 | 891円 | 847円 |
| 要介護4 | 959円 | 918円 |
| 要介護5 | 1,028円 | 987円 |
参考:WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)(p.116)」
なお、上記は1割負担・1単位10円の場合です。自己負担割合のほか、地域や施設によって自己負担額に違いが出ることがあります。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)では、介護老人保健施設などに利用者さんが一時的に入所し、生活介護や機能訓練、医療的ケアなどのサービスを利用します。
下記は、基本型(在宅復帰・在宅療養支援を一定程度行える施設)の老健に入所した場合の費用です。
| 要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型(個室・個室的多床室) |
| 要介護1 | 753円 | 830円 | 836円 |
| 要介護2 | 801円 | 880円 | 883円 |
| 要介護3 | 864円 | 944円 | 948円 |
| 要介護4 | 918円 | 997円 | 1,003円 |
| 要介護5 | 971円 | 1,052円 | 1,056円 |
参考:WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)(p.138)(p.140)」
なお、上記は1割負担・1単位10円の場合です。在宅強化型など、施設の特徴によって費用負担は異なります。
その他
その他の居宅サービスは、「特定施設入居者生活介護」「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」の3つです。
特定施設入居者生活介護
特定施設入居生活介護は、特定施設サービス計画に基づいて、身体介護や生活援助、機能訓練などを提供するサービス。特定施設とは、介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームです。
以下は、特定施設入居者生活介護を利用する場合の自己負担額です。
| 要介護1 | 542円 |
| 要介護2 | 609円 |
| 要介護3 | 679円 |
| 要介護4 | 744円 |
| 要介護5 | 813円 |
参考:WAM NET「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)(p.237)」
なお、上記は1割負担・1単位10円の場合です。自己負担割合のほか、地域や施設によって自己負担額に違いが出ることがあります。
福祉用具貸与
福祉用具貸与事業所は、利用者さんに応じて適切な福祉用具を選んで貸し出したり、使い方を教えたりします。介護保険を利用して福祉用具をレンタルするには、要介護認定やケアマネジャーへの相談が必要です。
| 貸与できる福祉用具 | ・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ予防用具 ・体位変換器 ・手すり ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助つえ ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり具の部分を除く) ・自動排泄処理装置 |
利用者さんの自立や介護者の負担軽減を図ることが、福祉用具を利用する目的です。要介護度によって利用できる福祉用具の種類は異なります。
特定福祉用具販売
特定福祉用具販売では、入浴や排泄に使用するなど、衛生面や消耗の面から貸与が適切ではないと考えられる福祉用具を販売します。特定福祉用具に該当するのは、以下の6つです。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
固定用スロープや歩行器など、一部の福祉用具は、貸与もしくは販売を選択して利用できます。なお、介護保険を利用して特定福祉用具を購入する場合、上限金額は1年で10万円までです。
出典
WAM NET「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和6年3月28日事務連絡)」(2025年3月11日)
厚生労働省「介護保険制度の概要」(2025年3月11日)
厚生労働省「介護保険の解説」(2025年3月11日)
居宅サービスの利用にかかる自己負担額
居宅サービスは介護保険が適用されるため、費用のすべてを自己負担する必要はありません。1~3割の費用のみ自己負担すれば居宅サービスを利用できますが、負担割合は利用者さんごとに異なります。また、介護保険の利用額には上限がある点にも留意しましょう。
自己負担額の決定の仕方
居宅サービスの自己負担額は、利用者さん本人や世帯の合計所得額によって決定されます。年金以外に所得があるか、単身・夫婦世帯かどうかによって合計所得額の設定に違いがあるので、以下で詳細を確認してみましょう。
| 介護保険の利用者負担割合 | 該当者 |
| 1割負担 | 1.本人の合計所得額が160万円未満の人 2.本人の合計所得額が160万円以上220万円未満で、年金を含めた合計所得額が下記に該当する人 ・単身世帯:280万円未満 ・夫婦世帯:346万円未満 |
| 2割負担 | 1.本人の合計所得額が160万円以上220万円未満で、年金を含めた合計所得額が下記に該当する人 ・単身世帯:280万円以上340万円未満 ・夫婦世帯世帯:346万円以上463万円未満 2.本人の合計所得額が220万円以上で、年金を含めた合計所得額が下記に該当する人 ・単身世帯:280万円以上340万円未満 ・夫婦世帯世帯:346万円以上463万円未満 |
| 3割負担 | 本人の合計所得額が220万円以上で、年金を含めた合計所得額が下記に該当する人 ・単身世帯:340万円以上 ・夫婦世帯世帯:463万円以上 |
参考:厚生労働省「給付と負担について(p.1)」
上記は、65歳以上の第1号被保険者の方を対象としたもので、第2号被保険者や住民税非課税世帯、生活保護受給者の方は1割負担です。
出典
厚生労働省「第107回社会保障審議会介護保険部会の資料について」(2025年3月11日)
介護保険の支給限度額を超えると全額自己負担
居宅サービスを利用する場合、介護保険の1ヶ月の支給限度額を超えた分は全額自己負担です。要介護度によって、下記のように介護保険の支給限度額が定められています。
| 要介護度 | 1ヶ月あたりの支給上限額 |
| 要支援1 | 5万320円 |
| 要支援2 | 10万5,310円 |
| 要介護1 | 16万7,650円 |
| 要介護2 | 19万7,050円 |
| 要介護3 | 27万480円 |
| 要介護4 | 30万9,380円 |
| 要介護5 | 36万2,170円 |
参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」
支給限度額の範囲内でサービスを利用した場合、利用料として支払うのは上記の金額の1~3割です。
なお、介護サービスの負担額を軽減するため、利用者さんの所得や資産などに応じた軽減制度が設けられています。1ヶ月あたりの負担額の合計が、所得に応じて設けた上限額を超えた場合、その超過分が高額介護サービス費などとして支給されるようです。
出典
厚生労働省「サービスにかかる利用料」(2025年3月11日)
利用者さんが居宅サービスを利用するまでの流れ
利用者さんが居宅サービスを利用するには、介護保険の利用手続きやケアマネジャーへの相談が必要です。ここでは居宅サービスを利用するまでの流れを解説するので、ぜひご覧ください。
介護保険の利用手続きをする
介護保険の利用手続きが済んでいない場合は、市区町村の介護保険の担当窓口に申請します。申請を受けた市区町村は、介護が必要かどうかを調査。自宅を訪問して聞き取り調査をしたり、主治医に意見書を求めたりするようです。
調査結果や主治医の意見書をもとに、コンピューターや介護認定審査会による判定を経て要介護認定が判断されます。要介護認定を受けると、介護保険を使って居宅サービスを利用することが可能です。
居宅サービス計画書を作成する
要介護認定を受けたら、居宅サービス計画書の作成依頼に移ります。要支援1~2の認定を受けた方は、地域包括支援センターに相談して「介護予防サービス計画書」の作成を依頼。要介護1~5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談して「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成してもらいます。
居宅サービスを利用する
居宅サービス計画書の作成や、施設・事業所との契約締結などの必要な準備が整い次第、居宅サービスを利用可能です。利用者さんは、ケアプランに基づいた介護サービスを受けます。
居宅サービス別の介護職の仕事内容
ここでは、居宅サービスを提供する介護職の仕事内容を解説します。同じ居宅サービスでも、提供するサービスが異なると業務も異なるのが特徴です。介護職に興味がある方は、どのような仕事をするのかイメージする参考にしてみてくださいね。
訪問サービス
訪問サービス事業所で働く介護職が担当する仕事は、「訪問介護」「訪問入浴介護」です。訪問介護では、ホームヘルパーとして利用者さんの自宅を訪問し、食事介助や入浴介助、排泄介助といった身体介護、買い物や料理、洗濯といった生活援助などを行います。
訪問入浴介護は、自宅の浴室での入浴が難しい利用者さんに向けたサービスです。自宅に専用の浴槽を持ち込み、利用者さんが安全に入浴できるように入浴介助を行います。
▼関連記事
訪問介護に向いている人の特徴は?仕事内容や必要資格、やりがいもご紹介
通所サービス
デイサービスの場合、食事介助・入浴介助・排泄介助などの身体介護や、健康チェック、レクリエーションなどが主な仕事です。利用者さんが施設に通うための送迎業務を担当することもあります。
デイケアの場合は、身体介護のほか、理学療法士や作業療法士のサポートを行い、利用者さんのリハビリをお手伝いすることもあるようです。
▼関連記事
デイサービスの仕事内容は?介護職の役割と1日の流れを解説
短期入所サービス
短期入所サービス(ショートステイ)は、介護者に何らかの事情があるときや、レスパイトケア(介護者への休息支援)として、一時的に利用者さんが入所する施設です。介護職は、利用者さんの状況に応じた身体介護や生活援助を行います。
短期入所生活介護は生活面のサポートが中心で、短期入所療養介護は医療的ケアが中心になるのが特徴です。
▼関連記事
ショートステイに向いている人とは?施設の種類や仕事内容も解説
その他
前述のとおり、「特定施設入居者生活介護」には、介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホームが当てはまります。介護職は、身体介護や生活援助、レクリエーションなどを行うのが主な仕事です。
「福祉用具貸与」や「特定福祉用具販売」は、介護保険の指定を受けた事業所で、利用者さんに福祉用具を貸与・販売します。適切な福祉用具を提案したり、使い方をアドバイスしたりするのが仕事のため、専門知識が必要です。介護福祉士の資格を保有する方や、福祉用具専門相談員指定講習会を修了した方などが、福祉用具専門相談員として働けます。
▼関連記事
福祉用具専門相談員とは?仕事内容や資格要件、指定講習の概要について解説
居宅サービスの目的
居宅サービスの目的は、利用者さんが居宅でできる限り自立した生活を送れるよう支援したり、身体機能・認知機能の低下を防ぐためのサポートをしたりすることです。また、介護者の負担を軽減するのも目的の一つといえます。
居宅で自立的な生活を送れるように支援する
住み慣れた自宅での生活を希望する利用者さんが自立した日常生活を送れるようにサポートするのが、居宅サービスの目的です。
利用者さんは、デイサービスで職員とのコミュニケーションを楽んだり、訪問介護で家事のサポートを受けたりなど、居宅サービスを組み合わせて利用できます。日常生活を送るうえで必要な支援を選んで在宅生活に取り入れられるのが、居宅サービスのメリットです。
身体機能や認知機能の低下を予防する
適切な介護ケアを提供することで、利用者さんの心身の機能低下を防ぐことにつながります。通所サービスでは、機能訓練をしたりレクリエーションを実施したりして、利用者さんが残存機能を維持できるようにサポート。利用者さんが1人でできることが増えれば、QOL(生活の質)の向上にも寄与できるでしょう。
ご家族の介護負担を軽減する
居宅サービスは、在宅介護をしているご家族の負担軽減を図るのも目的の一つです。居宅サービスを利用することで一時的に介護から離れられるので、ご家族の方は心身ともにリフレッシュできます。
また、介護職が、腰に負担のかからない移乗介助の方法をアドバイスしたり、役立つ情報を共有したりすれば、ご家族の方の介護をフォローすることもできるでしょう。
【参考】居宅サービス以外の介護サービス
居宅サービス以外にも、介護保険で利用できる介護サービスはあります。ここでは、「施設サービス」「介護予防サービス」「地域密着型の介護(予防)サービス」の各介護サービスを確認してみましょう。
施設サービス
介護保険サービスにおける施設サービスとは、次の3つです。
| 施設サービス | ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 |
参考:厚生労働省「介護保険制度の概要(p.13)」
入所型の施設は、介護付き有料老人ホームや介護型のケアハウスのような居宅サービスとは違い、在宅復帰を想定しているため、施設サービスに分類されます。ただし、最近は入所型の施設で看取りケアを可能としている場合も増えているため、終の棲家というイメージを持つ方もいるかもしれません。
特養や介護医療院のサービスについて詳しく知りたい方は、「介護医療院とは?特養との違いや創設された経緯・サービス内容を解説」の記事を参考にしてみてください。
介護予防サービス
介護予防とは、要支援1~2の方が自立した生活を継続できるよう支援するサービスのことです。居宅サービスと同様に、「訪問サービス・通所サービス・短期入所サービス・その他」に分類できます。
| 介護予防サービスの分類 | 介護予防サービスの種類 |
| 訪問サービス | ・介護予防訪問入浴 ・介護介護予防訪問看護 ・介護予防訪問リハビリテーション ・介護予防居宅療養管理指導 |
| 通所サービス | ・介護予防通所リハビリテーション |
| 短期入所サービス | ・介護予防短期入所生活介護 ・介護予防短期入所療養介護 |
| その他 | ・介護予防特定施設入居者生活介護 ・介護予防福祉用具貸与 ・特定介護予防福祉用具販売 |
参考:厚生労働省「介護保険制度の概要(p.13)」
すべてのサービスに「介護予防」がついていることから分かるように、サービスの中心はリハビリや生活支援です。早いうちからケアを行うことで、要介護状態への進行を遅らせる目的があります。
地域密着型の介護(予防)サービス
市町村が管轄する、地域密着型介護サービス・地域密着型介護予防サービスもあります。
| 地域密着型介護サービス | ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) |
| 地域密着型介護予防サービス | ・介護予防認知症対応型通所介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・介護予防認知症対応型共同生活介護 |
| その他 | ・居宅介護支援 ・介護予防支援 |
参考:厚生労働省「介護保険制度の概要(p.13)」
認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護は、どちらもグループホームのことです。
グループホームの入居条件や提供するサービス内容に興味のある方は、「グループホームとは?簡単に解説します!入居条件や費用、メリット、選び方」の記事もあわせてご覧ください。
出典
厚生労働省「介護保険制度の概要」(2025年3月11日)
居宅サービスに関するよくある質問
ここでは、居宅サービスに関するよくある質問に回答します。「居宅サービスって何なの?」と気になる方は、チェックしてみてください。
居宅サービスにはどんな分類があるの?
居宅サービスに分類されるのは、「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」などです。訪問サービスには訪問介護や訪問入浴などが該当し、通所サービスにはデイサービスや通所リハビリテーションが該当します。短期入所サービスは、短期入所生活介護(ショートステイ)や短期入所療養介護(医療型ショートステイ)です。また、特定施設入居者生活介護・福祉用具貸与・特定福祉用具販売も居宅サービスに含まれます。
居宅サービスの種類は、「居宅サービスの種類・内容」の見出しで詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
居宅サービスを利用するメリットは?
居宅サービスを利用するメリットは、住み慣れた環境で過ごしながら介護サービスを受けられること。「自宅から離れたくない」という高齢者の方に適した介護サービスです。また、訪問介護やデイサービスを利用することによって、ご家族の介護負担を軽減できる利点もあります。
居宅サービスの読み方は?
居宅サービスの読み方は「きょたくサービス」です。居宅とは、日常的に住んでいる家を意味します。「居宅サービスと在宅サービスの違い」の見出しで解説しているので、気になる方はご一読ください。
まとめ
居宅サービスとは、自宅で過ごしながら介護サービスを利用したい方向けの介護保険サービスです。訪問介護やデイサービス、ショートステイなどが居宅サービスに含まれます。また、介護付きの有料老人ホームやケアハウスに居住している利用者さんに提供する介護サービスも、居宅サービスです。特養や老健で提供する施設サービスとは分類が異なります。
介護職への就職・転職を検討中の方は、介護業界に特化した転職エージェントのレバウェル介護(旧 きらケア)に相談してみませんか?レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界が初めての方でも働きやすい「日勤のみ」「未経験者可」の求人を数多く取り揃えています。適性や希望に沿った求人を転職のプロの視点でご紹介するので、介護サービスに詳しくない方も安心です。サービスはすべて無料!まずはお気軽にお問い合わせください。
今の職場に満足していますか?
 訪問介護の求人はこちら
訪問介護の求人はこちら