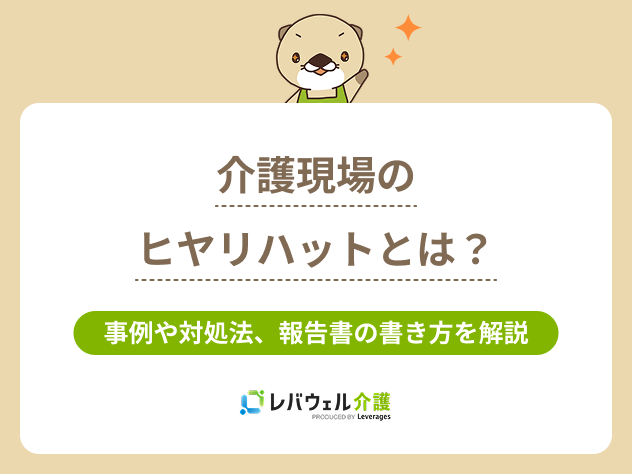
この記事のまとめ
- 介護現場のヒヤリハットとは、大きな事故につながる可能性がある事案のこと
- ヒヤリハットが発生する原因は、介護スタッフの不注意や設備の不具合など
- ヒヤリハット報告書は、5W1Hに沿って書くのがポイント
「介護現場のヒヤリハットって何?」という疑問をお持ちの方もいるかもしれません。ヒヤリハットとは、大きな事故には至らなかったものの、ヒヤリとしたりハッとしたりした事例のことです。この記事では、ヒヤリハットが発生する原因や報告書の書き方を解説します。介護現場でのヒヤリハット事例と記入例もまとめました。介護現場におけるヒヤリハットや報告書の書き方について詳しく知りたい方は、ぜひご一読ください。
介護現場におけるヒヤリハットとは?
ヒヤリハットとは、大きな事故につながりそうな「ヒヤリ」としたり、「ハッと」驚いたりする出来事を指す言葉です。介護現場においては、転倒しそうになったときや異食・誤薬しそうになった瞬間を発見したときなどが挙げられます。
ひやっとしたり、ハッとしたりしたことを放置してしまうと、重大な事故につながる可能性が高いため、事故になる前のヒヤリハットの段階で対策を講じることが大切です。
介護事故はハインリッヒの法則に従って起こる
労働災害の事故に関する法則で「ハインリッヒの法則」というものがあります。ハインリッヒの法則は、「労働災害には何かしらの予兆や原因が必ずある」という教訓を示すものです。
ハインリッヒの法則によると、1件の重大な事故の背景には、29件の軽微な事故と300件のヒヤリハットがあるとされています。そのため、ヒヤリハットを減らすことが重大事故を減らすことにつながるといえるでしょう。
また、ヒヤリハットは人の気持ちに慣れや油断、思い込みなどがあるときに起こるものといわれています。普段からヒヤリハットについて意識的に考えておくことで、ヒヤリハットに気づきやすくなります。ほかにも、ヒヤリハットの原因を放置せずに対策や防止策を考案したり、話し合いの機会を持ったりすることで、重大な事故を未然に防止することにつながるでしょう。
出典
厚生労働省 職場のあんぜんサイト「ハインリッヒの法則(1:29:300の法則)」(2025年3月24日)
介護事故とヒヤリハットの違い
介護事故とヒヤリハットの違いは、事故が実際に起きたか、未然に防げたかです。「外傷はなかったし…」「ADL自立で防ぎようもないし…」とあいまいな基準でヒヤリハットと介護事故を分けている現場もありますが、起きてしまったことに関しては介護事故、未然に防げたことに関してはヒヤリハットとして報告するのが適切です。あいまいな基準で介護事故をヒヤリハットにしてしまわないように注意しましょう。
▼関連記事
介護におけるIADLとは?ADLとの違いや生活動作を低下させない対策法を解説!
登録は1分で終わります!
介護現場でヒヤリハットが発生する原因
介護現場でヒヤリハットが発生する原因は大きく分けて3つ考えられます。
原因1:利用者さんの認知機能や身体機能の低下
認知症を患う利用者さんが多くいる介護施設の場合は、認知機能の低下に対応できていないことがヒヤリハットの原因になることも少なくありません。足が不自由であることを認識できず、一人で歩こうとして転倒しそうになったり、自分の食事と他者の食事を認識できず、盗食しそうになったりすることなどが考えられます。
介護事故やヒヤリハットを防ぐには、利用者さん一人ひとりの認知機能やコンディションを観察しながらケアをしていくことが求められるでしょう。
原因2:介護スタッフやご家族の不注意
人手不足で見守りが行き届かなかったり、スタッフ一人ひとりの業務量が多すぎて注意力が低下していたりすることも、ヒヤリハット発生の要因になり得ます。
また、面会時などでご家族がスタッフに代わって介護をする場合も注意が必要です。介護に不慣れなご家族の場合、安全に介助を行う技術が身についていないことがあるため、スタッフの目が届く場所でケアをしてもらえるように声かけをすると良いでしょう。
原因3:介護環境や施設・設備の不具合
廊下や居室が狭かったり物が多かったりすると、転倒や打撲のリスクが増える可能性があります。環境や設備が要因でヒヤリハットが起こった場合は、速やかに改善して再発防止に努めましょう。
介護現場でヒヤリハットを記録する目的
ここでは、介護現場のヒヤリハットを記録する目的を解説します。
重大な介護事故防止のため
ヒヤリハットを記録に残すことで、介護事故が起こるリスクが明確になります。リスクを把握して対策を講じれば、重大事故を防ぐことにつながるでしょう。
介護スタッフやご家族との情報共有のため
スタッフ全員で情報共有をすれば、ケアの意識や認識を統一できます。また、利用者さんのご家族にも情報を共有することで、普段の様子や現状を把握してもらえるだけでなく、事故が起きる可能性について事前に説明する機会を持てるメリットもあるでしょう。
日々の変化について綿密なコミュニケーションと情報共有を行うことが、大きなクレームの防止につながります。
ケアの質向上と安全性の確保のため
スタッフ間でケアの認識を統一することは、介護の質向上にもつながるでしょう。また、ヒヤリハット報告書をもとに対策を講じれば、利用者さんの安全を確保することが可能です。
▼関連記事
介護職のスキルアップに役立つ資格|取得方法や現場で活躍する方法も解説!
適切な介護を提供したと証明するため
ヒヤリハット報告書は、万が一事故が起きた場合に、普段の様子やケアの提供方法に問題がなかったことを、行政やご家族に証明する書類としても役立ちます。自分を守るためにも、しっかりと報告書を作成することが大切です。
ヒヤリハット報告書の基本的な書き方
ヒヤリハット報告書の基本的な書き方のポイントは、「いつ」「どこで」「誰が」「どうなったのか」を誰が見ても分かりやすい表現で記録することです。介護に携わらない人でも、報告書を見ただけでその場面を想像できるように書くのが理想とされています。
ヒヤリハット報告書の形式は施設によって異なるようです。もし所定の形式がない場合は、一般社団法人シルバーサービス振興会 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の「各種資料ダウンロード:介護事業所・施設の記録の様式例」から、フォーマットをダウンロードすることができます。
また、PCの介護記録用ソフトにヒヤリハット報告書の様式を変更・設定する箇所がある場合もあるため、お使いの介護記録用ソフトを確認してみるのもいいかもしれません。
出典
一般社団法人シルバーサービス振興会「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」(2025年3月24日)
介護現場でヒヤリハット報告書を書くときの注意点
介護現場でヒヤリハット報告書を書く際の注意点を、以下にまとめました。
5W1Hに沿って記入する
5W1Hを明記しておけば、ヒヤリハットが発生したときの状況を想像しやすくなります。ヒヤリハットが発生した状況を記入するときは、「いつ」「どこで」「誰に」「何が」「なぜ」「どのように」起きたかを、簡潔な文章にまとめると良いでしょう。
また、重大事故につながらないよう、ヒヤリハットの段階で原因を明確化し、講じた対策を記録しておくことが大切です。報告書が完成したら、同じフロアのスタッフはもちろん、施設・事業所全体で共有して事故予防に役立てましょう。
専門用語は使わず事実を客観的に書く
ヒヤリハット報告書は、介護に携わらない立場の人も目にする可能性がある書類です。行政の担当者や利用者さんのご家族が見ても内容が伝わるように、専門用語をできるだけ使わずに書きましょう。
また、事実を客観的に書くことも大切です。見ていないことを想像で書いたり、利用者さんから聞いたことを事実として書いたりしないのがポイント。たとえば、利用者さんが「リビングでふらついた」と言っていた場合は、「〇〇さんがリビングでふらついたと言っていた」と事実をそのまま記載します。
ヒヤリハットの対策を必ず立てる
ヒヤリハットは、事故と比べると扱いが軽くなりがちです。しかし、ハインリッヒの法則にあるように、重大事故につながる危険性が潜んでいることを忘れてはいけません。書いて終わりでは、報告書を作成する意味がなくなってしまうため、原因の究明と対策を立てることを忘れないようにしましょう。
▼関連記事
【例文あり】介護現場での事故報告書の書き方を解説!上手に書くポイントも
介護現場のヒヤリハット事例と記入例
介護現場でよくあるヒヤリハットについて、具体的な事例と報告書の記入例を紹介します。
食事介助・配膳時のヒヤリハット事例
本来とは異なる食形態の食事を提供しそうになった事例
| 対象者 | Aさん |
| 記入者(発見者) | 介護職員B |
| 日時 | 令和〇年〇月〇日 △時△分 |
| 発生場所 | 食堂 |
| 内容 | 隣に座っている別の利用者の食事を提供しそうになった |
| 原因 | 食札の確認不足 |
| 対策 | 食事を提供する際は、食札で名前を確認し、名前を読み上げたうえで提供する。また、食事介助を行う利用者の場合は、下膳するまで食札を目の届く場所に置いておく |
服薬時のヒヤリハット事例
同姓同名の利用者がおり、新人職員が薬を間違えそうになった事例
| 対象者 | Cさん |
| 記入者(発見者) | 介護職員D |
| 日時 | 令和〇年〇月〇日 △時△分 |
| 発生場所 | リビング |
| 内容 | 昼食後の服薬介助の際、同姓同名の別の利用者の薬を渡しそうになった |
| 原因 | 利用者の顔と名前が十分に一致していない状態で、1人で服薬介助を行ったため |
| 対策 | 十分に利用者の情報を把握できているか確認したうえで、服薬介助業務を担当してもらう |
トイレ介助の移乗に関するヒヤリハット事例
トイレ介助時、転倒リスクの高い利用者さんが自力で車いすに移ろうとしていた事例
| 対象者 | Eさん |
| 記入者(発見者) | 介護職員F |
| 日時 | 令和〇年〇月〇日 △時△分 |
| 発生場所 | トイレ |
| 内容 | ほかの利用者の対応のため、トイレから少し離れて目を離している間に、自力で車いすに移ろうと立ち上がっていた。車いすはブレーキが外されていた |
| 原因 | Eさんから目を離してしまったため |
| 対策 | トイレ介助時にほかの利用者対応が必要になった場合は応援を呼び、Eさんが1人にならないようにする |
入浴時の転倒に関するヒヤリハット事例
個浴利用中、ADL自立のため独歩していた利用者さんがふらつき、転倒しそうになった事例
| 対象者 | Gさん |
| 記入者(発見者) | 介護職員H |
| 日時 | 令和〇年〇月〇日 △時△分 |
| 発生場所 | 浴室 |
| 内容 | シャワーから浴槽に移動する際、ふらつきが見られ、転倒しそうになった |
| 原因 | 床に泡が残っていたこと。洗面器が床に置いてあり、足の踏み場が狭かったこと |
| 対策 | 浴槽に移動する際は、床をよく洗い流し、床に物を置いていないか確認する |
食事介助時の誤嚥に関するヒヤリハット事例
食事介助時、誤嚥し強いむせ込みがあった事例
| 対象者 | Iさん |
| 記入者(発見者) | 介護職員J |
| 日時 | 令和〇年〇月〇日 △時△分 |
| 発生場所 | 居室、ベッド上 |
| 内容 | 食事介助中、おかゆを提供した際に強いむせ込みがあった |
| 原因 | 姿勢保持が十分でなかった。おかゆの水分が唾液によりサラサラになり、誤嚥しやすい状態になっていた |
| 対策 | 食事介助の際は、ベッドの角度を45度以上にしたことを確認する。傾きがある場合は、クッションを使用する。おかゆの水分が多い場合は、適宜トロミ剤を使用する |
以上のように、「いつ」「どこで」「誰に」「何が起きたか」を明確に記載し、原因と対策まで明記します。また、対策が実際の業務に活かせているかを確認するために、モニタリング期間を設けるのも良いかもしれません。
介護のヒヤリハットについてよくある質問
ここでは、介護のヒヤリハットについてよくある質問に回答します。
介護のヒヤリハットの定義は何ですか?
職場のあんぜんサイトの「ハインリッヒの法則(1:29:300の法則)」によると、「仕事をしていて、もう少しで怪我をするところだった」という場面がヒヤリハットに該当します。「ヒヤっとした」「ハッとした」ことをしっかりと報告するヒヤリハットの活動は、介護事故のリスクを把握して未然に防ぐために効果的です。
出典
厚生労働省 職場のあんぜんサイト「ハインリッヒの法則(1:29:300の法則)」(2025年3月24日)
介護のヒヤリハットへの対策は何ですか?
ヒヤリハットへの対策としては、危険を把握するリスクマネジメントが有効です。リスクマネジメントを行うことで、事故を未然に防いだり、トラブルに速やかに対応して被害の拡大を防いだりすることにつながります。過去のヒヤリハット事例や事故事例を確認し、緊急度の高いものから対策を立てましょう。
リスクマネジメントについては、「介護事故を防ぐには?ありがちな事例と対処方法」の記事もご参照ください。
まとめ
ヒヤリハットとは、事故につながりかねないヒヤリとしたことやハットしたことを指します。介護現場で利用者さんの安全を守るためには、事故が起こる前にリスクを察知し、対策することが大切です。
ヒヤリハット報告書を作成することは、介護事故の予防だけではなく、情報共有やケアの質向上にもつながります。報告書作成におけるポイントは、5W1Hを押さえることや専門用語を使わないこと、客観的な事実を記録することなどです。
「今よりも働きやすい環境の職場はある?」と気になっている方には、介護業界に特化した転職エージェントのレバウェル介護(旧 きらケア)がおすすめ。介護業界に精通したアドバイザーが、ご希望に合った職場をご提案いたします。相談のみの利用もOKなので、介護の仕事についてのお悩みや疑問がある方は、気軽にご利用くださいね。
登録は1分で終わります!
 経験者歓迎の求人一覧はこちら
経験者歓迎の求人一覧はこちら