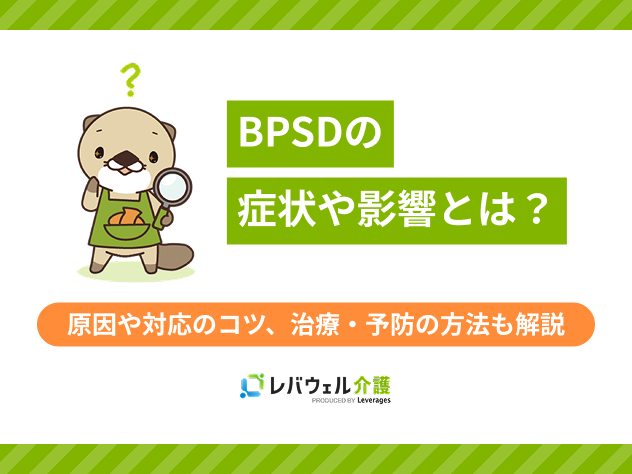
この記事のまとめ
「BPSDって何?」「治療や対応の仕方は?」という疑問をお持ちの方もいるかもしれません。BPSDとは、認知症を患う方の行動・心理症状のことです。この記事では、BPSDの具体的な症状や原因、治療法を解説します。予防法や介護をするうえで意識したいポイントもまとめました。認知症の症状に関する基礎知識や、BPSDのある利用者さんのケアの方法について詳しく知りたい介護職の方は、ぜひ参考にしてください。
BPSD(行動・心理症状)とは
BPSD(行動・心理症状)とは、国際老年精神医学会が定めた概念で(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)の略称です。
日本語では、「認知症の行動・心理症状」と訳され、認知症を患う方に認められる徘徊、暴言・暴力などの行動症状や、不安感、抑うつ状態、幻覚などの心理症状のことを指します。
▼関連記事
認知症の方とのコミュニケーション方法を解説!相手を想う言葉や行動とは
登録は1分で終わります!
認知症の方に現れる2つの症状
認知症の症状は主に「中核症状」と「周辺症状(BPSD)」の2種類に分けられます。中核症状と、環境要因・身体要因・心理要因などの相互作用によって二次的に引き起こされる周辺症状(BPSD)は、周囲の環境や対応の仕方などによって、症状の現れ方や程度が変わるのが特徴です。
ここでは、「中核症状」とされる主な症状と「周辺症状(BPSD)」についてまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
中核症状
中核症状とは、脳の神経細胞が障がいを起こすことにより発症する認知機能障がいのことです。主な症状として、記憶障がいや認知障がい、人格変化などが挙げられます。
厚生労働省の「認知症ケア法ー認知症の理解(p.11)」によると、程度の差はあるものの、中核症状は認知症を患うすべての方にみられ、認知症の進行とともに悪化していく症状のようです。
以下で、主な症状を確認してみましょう。
出典
厚生労働省「認知症ケア法ー認知症の理解」(2025年3月24日)
記憶障がい
記憶障がいとは、自分が体験した最近の出来事を覚えられなかったり、過去の記憶を忘れてしまったりする障がいです。
具体的には、以下のような症状が挙げられます。
- 最近のこと(新しいこと)が覚えられない
- 話したばかりの人の名前をすぐに忘れる
- 置き忘れが多い
- 片付けたことを忘れて、ずっと探し物をしている
- 約束を忘れる
一般的な物忘れと似ていますが、何度も伝えても思い出せなかったり、忘れる頻度が高かったりする場合は、認知症による記憶障がいが疑われます。
実行機能障がい
実行機能障がいとは、判断力の低下によって物事の判断が難しくなったり、計画どおりの行動ができなくなったりする障がいです。
具体的には、以下のような症状が挙げられます。
- 料理の手順や味付けの仕方が分からなくなる
- 段取りよく買い物ができない
- 冷房の入れ方やテレビのチャンネルの変え方が分からない
- 突発的な出来事に対処できない
実行機能障がいがあると、物事を計画的に進めることやマルチタスクをこなすことが困難になるようです。
見当識障がい
見当識障がいとは、季節・時間・場所・人などの日常生活を送るうえで必要な情報を理解する力が失われてしまう障がいです。まず、時間や季節が分からなくなり、次に場所を認識しにくくなります。症状の進行が進むと、家族や友人など、周囲の人との関係が分からなくなってしまうのも特徴です。
具体的には、以下のような症状が挙げられます。
- 夏なのに冬服を着ている(季節外れの服装)
- 今自分がどこにいるのか分からない
- 今日の日付、今が何時なのかが分からない
- 自分の年齢が分からない
- 娘を「お姉さん」と呼ぶ
季節や時間、場所などを正しく認識できないと、自分が置かれている状況を理解するのが難しくなります。
失語
失語とは、脳の損傷により、話す・聞く・読む・書くといった機能が失われた状態のことです。
具体的には、以下のような症状が挙げられます。
- 伝えたい言葉が出てこない
- 言おうと思った言葉を間違える
- 相手の言っている言葉の意味が理解できない
- 文字や文章を読んだり、書いたりできない
失語の症状がある場合、言葉による意思疎通が難しくなるため、コミュニケーション方法に配慮することが求められます。
▼関連記事
失語症の症状や原因とは?リハビリ方法やコミュニケーションの取り方も解説
失行
失行とは、運動機能に問題がないのにもかかわらず、日常生活を送るうえで必要な動作や目的に沿った行動が取れなくなってしまうことです。
具体的には、以下のような症状が挙げられます。
- 服をどう着たらいいか分からない
- 箸やスプーンなどの使い方が分からない
- お茶の入れ方が分からない
- 歯ブラシを渡されても、歯磨きができない
日常生活に必要な簡単な動作をする際に、迷ったり間違えたりするのが失行の症状です。
失認
失認とは、感覚機能に問題がないにもかかわらず、見聞きしたことや人や物を認識できなくなってしまうことです。
具体的には、以下のような症状が挙げられます。
- 鏡に映った自分が誰か分からない
- 物や人にぶつかることが多い
- 目の前に障害物があっても認識できない
- 時計が読めない
目の前にある物が見えていても、それが何か理解できなければ、「食べ物以外を口に入れる」といった危険な行動につながってしまうことがあります。
出典
厚生労働省「認知症を理解する」(2025年3月24日)
周辺症状(BPSD)
周辺症状(BPSD)とは、中核症状と環境・身体・心理要因などの相互作用によって起こるさまざまな精神症状や行動障がいのことです。
厚生労働省の「認知症ケア法ー認知症の理解(p.11)」には、周辺症状(BPSD)は認知症の重症度や進行レベルとは比例せず、症状がみられない人もいると明記されています。
次の項目で、周辺症状(BPSD)の主な症状について解説するので、チェックしてみましょう。
出典
厚生労働省「認知症ケア法ー認知症の理解」(2025年3月24日)
周辺症状(BPSD)の主な症状
周辺症状(BPSD)に該当する主な症状は、下記のとおりです。
| 周辺症状(BPSD)の主な症状 | 具体的な症状 |
| 行動障がい | 徘徊、夕暮れ症候群(帰宅願望)、不潔行為、異食、暴言・暴力、常同行動 |
| 精神症状 | 不安感、抑うつ状態、睡眠障がい(昼夜逆転)、幻覚、妄想、せん妄、感情失禁 |
周辺症状(BPSD)の主な症状は、「行動障がい」と「精神症状」に分けられ、さらに具体的な症状としていくつかの症状が挙げられます。
以下で、それぞれの症状についてまとめているので、確認してみましょう。
行動障がい
行動障がいとは、不適切なケアやストレス、不安などの心理状態が原因で現れる障がいのことです。具体的には、徘徊や夕暮れ症候群(帰宅願望)、不潔行為、異食、暴言・暴力、常同行動などが挙げられます。
徘徊
徘徊とは、認知症の中核症状やストレス、不安などの影響により、室内や屋外を絶えず歩き回ることを指します。
周りからは「目的もなくただ歩き回っているだけ」と見えてしまうことがありますが、本人にとっては「家に帰る」「そろそろ買い物に行く時間」などといった目的や理由がある場合が多いようです。否定したり無理に引き止めたりせず、安全を確保しつつ傾聴することが、安心感を与えることにつながります。
夕暮れ症候群(帰宅願望)
夕暮れ症候群(帰宅願望)とは、夕方ごろに落ち着きがなくなり、「家に帰ります」などと言って帰り支度を始めてしまうことです。ほかにも、不安から何度も同じことを繰り返したり、大声を出したりするなどの症状がみられる場合があります。
これらの症状は、「今自分がどこにいるのか分からない」「(スタッフが)夕食の準備をしているのに、自分は何もしなくていいの?」といった不安や心配から起きてしまう傾向があるようです。
▼関連記事
帰宅願望に効果的な声かけとは?認知症の方への対応方法について解説
不潔行為
不潔行為とは、排泄物を触ったり、トイレではない場所で排泄をしてしまったりすることです。ほかにも、「汚れた下着をタンスにしまう」「排泄物を触った手で壁に触れる」といった行為も含まれます。
不潔行為は、認知症を患う方に多く見られる傾向にありますが、起きてしまう原因については、はっきりと分かっていません。「オムツに違和感があった」「トイレで失敗してしまい隠そうとした」といった理由から、不潔行為に及んでしまうケースもあると考えられます。そのため、定期的にトイレの声かけをするといった配慮が大切です。
異食
異食とは、食べ物ではないものを口に運んでしまうことです。たとえば、目の前にあるティッシュや花瓶に飾られた花、レクリエーションで使用した液体のりを食べようとしてしまうことなどが挙げられます。
異食は、認知症の症状が進行し、認知機能や判断力が低下することで起きてしまうと考えられています。ほかにも、空腹や不安、ストレスなどが原因で異食につながってしまうことも。本人は、「お腹が空いた」「そろそろ食事の時間だから何か食べたい」といった気持ちで異食行動を起こしている可能性があるので、怒らずに適切な対応を行うことが重要です。
暴言・暴力
特に脳の損傷が原因で起きる認知症では、進行すると感情のコントロールが難しくなり、暴言・暴力が起きやすくなります。暴言・暴力が起きてしまう原因はさまざまですが、「不安や怒りを感じているけどうまく表現ができない」「自尊心を傷つけられた」「否定された」といった状況が、暴言・暴力につながることが多いようです。また、薬の影響や認知症のタイプなどによって暴力や暴言がみられることもあります。
なにか一つの原因によって起きてしまうというわけではなく、さまざまな状況が重なることで、介護職員や家族への暴言・暴力につながっているケースが多いようです。
▼関連記事
介護施設で起こるご利用者からの暴言暴力とは?原因や対処法を解説
常同行動
常同行動とは、同じ行動を何度も繰り返すことで、「廊下と部屋を行ったり来たりする」「毎日同じ時間に同じ物を食べる」といった行動を指します。常同行動が起きてしまう原因は、「お腹が空いたから何か食べたい」という何かしらの要求があったり、「いつもと同じ日常でつまらない」と刺激を求めたりすることで起きると考えられているようです。
また、常同行動は前頭側頭型認知症(ピック病)を患う方の特徴的な症状で、前頭葉や側頭葉に障がいがあることが原因で起きてしまうといわれています。
精神症状
精神症状とは、不適切なケアやストレス、不安などの心理状態が原因で現れる症状のことです。具体的には、不安感や抑うつ状態、睡眠障がい(昼夜逆転)、幻覚、妄想、せん妄、感情失禁などが挙げられます。
不安感・抑うつ状態
認知機能の低下によりできないことが増えていくと、不安感に襲われたり意欲が低下したりしやすくなります。意欲が低下し気分が落ち込むと、何事にも興味を示さなくなってしまい、次第に抑うつ状態となってしまうことがあるようです。
BPSDにおける抑うつ状態は、うつ病と誤解されてしまうことがありますが、うつ病は悲観的になりやすく、抑うつ状態は無関心になりやすいのが特徴です。また、抑うつ状態は認知症のなかでも、特にレビー小体型認知症の方によくみられる症状とされています。
「今までできていたことができない」「どうせできないなら何もやらない」というような状態が続いてしまうと自信をなくし、症状がさらに悪化してしまう可能性もあるでしょう。不安感や抑うつがみられるときは、本人の気持ちに寄り添い理解を示すことが重要です。
睡眠障がい(昼夜逆転)
認知症を患うと体内時計の調節が難しくなり、不眠や昼夜逆転といった睡眠障がいを引き起こしやすくなります。「眠れない」という状態は、本人や介護する人にとっても負担が大きいもの。体内時計を整えるために、朝日を浴びたり、日中の活動量を増やしたりして入眠しやすくすることが重要です。
幻覚
幻覚には、幻視や幻聴などの種類があります。幻視とは、実際にないものがあるように見えてしまう症状のことで、「家に知らない人がいる」「小さい子どもが見える」などといった言動がみられるのが特徴です。一方で、幻聴は聞こえないはずの音や声が聞こえる症状のこと。いるはずのない人の「声が聞こえる」、誰も言っていないのに「悪口を言われている」といった言動がみられます。
また、レビー小体型認知症では幻視がみられやすく、アルツハイマー型認知症では幻聴が現れやすい傾向にあります。たとえ事実とは異なっても、本人にとっては「見えている」「聞こえている」状態のため、ただ否定するのではなく、安心してもらえるようなケアを行いましょう。
妄想
妄想とは、ほかの人にとって現実にはありえないと思うことを信じ込んでしまうことです。認知症における代表的な妄想の種類としては、「被害妄想」「物盗られ妄想」などが挙げられます。
被害妄想は、「陰で悪口を言われている」「自分はみんなから嫌われている」などと思い込むことです。一方で、物盗られ妄想では、自分がしまった場所や置いたこと自体を忘れて、「盗まれた」と思い込んでしまいます。物盗られ妄想では、身近な人が疑われてしまうケースが多い傾向にあり、本人の不安や焦りが症状として現れていることもあるようです。
せん妄
せん妄とは、意識障がいを起こして混乱した状態のことです。夜間に起こることが多いせん妄のことを「夜間せん妄」といいます。幻覚や妄想、不穏、興奮などの症状が現れることがあり、薬の副作用によって症状が現れることもあるようです。
また、せん妄は、一日のなかで症状が変動する「日内変動」があるのが特徴です。体調不良やアルコール摂取、環境の変化などが原因となって起こるケースが多い傾向にあります。
感情失禁
感情失禁とは、感情のコントロールがうまくできず、ちょっとした刺激で泣いたり笑ったりすることです。脳血管性認知症の方に多くみられる傾向にあり、記憶障がいや見当識障がいといった症状とともに脳の働きが悪くなることで、感情失禁が起こると考えられています。
感情失禁は自分で簡単にコントロールできるものではないため、周囲の人が理解し、適切な対応を行うことが重要です。
▼関連記事
介護拒否が起きる状況や原因とは?無理のないケアと対応方法を解説!
BPSDを発症する原因
「そもそもなんでBPSDが起きるの?」という疑問をお持ちの方もいるかもしれません。BPSDを発症する原因には、「背景因子」と「誘因」があります。以下で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
背景因子
背景因子には、遺伝子的要因や神経生物学的要因、社会的要因などがあり、それぞれ介入が難しいものと介入可能なものに分けられます。
介入が困難なものは、脳病変や認知症状(中核症状)、地域文化や生活史などで、介入が可能なものは、薬剤、居住環境、体調、ケア技術などが挙げられます。これらは、それぞれ個人差が大きいことが特徴です。背景因子によってBPSDが起こりやすい基盤が作られ、不安や不満などが溜まっていくと考えられています。
誘因
誘因とは、きっかけのことです。上述したように、背景因子によってBPSDが起こりやすい基盤が作られ、不安や不満などが溜まっていきます。そこに、介護者からの厳しい言動や行動(誘因)が加わるとBPSDを発症してしまうのです。
つまり、BPSDは背景因子だけで発症するのではなく、周りの環境や人間関係(誘因)が大きく影響することによって起きてしまうと考えられています。
BPSDは、介護者の対応を変えたり、居住環境や体調などを整えたりすることで、次第に軽減できる事もあるようです。そのため、本人の症状に合わせた適切な対応を行うことが大切になります。
BPSDによる家族や本人への影響
BPSDは、本人だけではなく家族にも大きな影響を及ぼします。たとえば、身体的・精神的・経済的負担などの介護負担です。「身の回りのお世話が大変」「自分の時間が取れない」「経済的に介護し続けるのが厳しい」などの負担となる要素は、介護者に大きなストレスを与えるため、不適切なケアが起こりやすくなります。
この不適切なケアが続くと、ケアを受けた本人もストレスが溜まり、BPSDがさらに悪化してしまうという悪循環が生まれてしまうのです。
ほかにも、家族や本人への影響として共通することとして、QOLの低下が挙げられます。BPSDの症状によって本人が不安や焦り、戸惑いなどを感じ、やる気や生きる希望を見失ってしまえば、QOLの低下につながってしまうことも。また、介護をすることで「自由な時間が取れない」「仕事との両立が難しい」などといった状況になれば、家族のQOL低下にもつながってしまいます。
こうした状況を回避するためには、本人だけではなく、家族も含めた周囲の人たちがBPSDへの理解を深め、適切な対応やケアを行っていくことが大切です。
BPSDの治療法
BPSDの治療法には、薬物による治療と薬物以外による治療があります。以下で、詳しい内容について確認していきましょう。
薬物による治療
BPSDの薬物による治療では、「向精神薬」「抗うつ薬」「抗不安薬」「睡眠導入剤」などが使用されています。これらの薬を使用することで効果があるとされるBPSD症状は、以下のとおりです。
| 治療に使われる薬 | 効果があるとされるBPSD症状 |
| 向精神薬 | 幻覚、妄想、暴力・暴言など |
| 抗うつ薬 | 抑うつ症状、食欲低下など |
| 抗不安薬 | 不安、緊張など |
| 睡眠導入剤 | 入眠障がい、中途覚醒など |
まず少量ずつの服用から始め、副作用や症状への有効性をみながら、量の調整や薬の変更を行います。効果の出方やスピードは一人ひとり違うため、注意深く観察することが大切です。
しかし、あくまで薬物療法は、BPSD症状への適切な対応を行っても改善がみられない場合に使用するのが原則。非薬物治療が優先となるため、むやみに使わないことが重要です。使用する際は、医師から処方されたものを使用し、看護師がいる場合は看護師の指示にも従うようにしましょう。
薬物以外による治療
薬物を使用しない治療とその内容については、以下のとおりです。
| 薬物以外による治療 | 内容 |
| 認知機能訓練 | 一人ひとりの認知機能のレベルに合わせた訓練 |
| 運動療法 | 有酸素運動や筋力強化トレーニングなど複数の運動を組み合わせた療養法 |
| 音楽療法 | 音楽を聴いたり歌ったりしながら、脳の活性化を図る療養法 |
| 回想法 | 過去の思い出を振り返ったり、写真や映像を見たりして回想しながら、聞き手が否定せずに共感する姿勢で傾聴すること |
薬物以外による治療は、単に行動障がいや精神症状というBPSD症状の緩和につながるだけではありません。認知機能訓練や運動療法は、心身機能の維持・向上、音楽療法は脳の活性化、回想法は気持ちの安定やコミュニケーションの活性化につながる効果が期待できます。
薬物を使用しないこれらの治療は、一人ひとりに合わせた方法を選択することが大切です。
BPSDを悪化させないための予防法
「BPSDを悪化させないためにできることってあるの?」「介護職として求められる対応って?」と気になる方もいるかもしれません。ここでは、BPSDの予防法について詳しく解説するので、ぜひチェックしてみてください。
BPSDの予兆
BPSDにつながる予兆として、「5つの不同意メッセージ」というものがあります。この「5つの不同意メッセージ」とは、介護職員との関わりの中で起きる不安や混乱、諦めなどを態度や言動の裏にあるメッセージとして示したものです。
- 謝罪…何かがうまくできないときに謝る
- 服従…やりたくないけど介護者の言動や行動に合わせる
- 遮断…聞こえないふり、寝たふりなどをする
- 転嫁…うまくできないことを物や人のせいにする
- 苛立ち…気に入らないことに対して独り言のように怒る
これらの予兆にいち早く気づくことで、本人への適切なケアやBPSDの回避につながる可能性があります。
BPSDの発症を防ぐために介護職に求められる対応
認知症を患う方のなかには、「普段の生活での自分の行動は間違っていないか」「誰かに迷惑をかけていないか」と考えたり、不安を感じたりしながら生活している方がいます。こうした思いに気づかず放置してしまうと、BPSDの発症や悪化につながってしまうことがあるので注意が必要です。
BPSDを防ぐためには、前述した不同意メッセージを介護職がしっかり受け止め、本人の気持ちの安定につながるような寄り添ったケアや対応を行うことが大切です。「ありがとうございます」「いつも手伝っていただいて助かっています」などといった声かけをすることや、本人が「自分には役割がある」と感じられるような支援を行うことを意識しましょう。
BPSDのある方のケアで介護職が意識したいポイント
ここでは、BPSDのある方のケアで介護職が意識したいポイントをまとめています。「BPSDがある方への対応が分からない」「どんなことを意識してケアすればいいの?」というお悩みや疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。
本人のペースに合わせてケアを行う
認知症を患うと、中核症状の影響で動作が遅くなったり、今までできていたことができなくなったりします。たとえば、失行がみられる利用者さんの場合、更衣に時間がかかってしまうことなどがあるでしょう。
しかし、「自分がやったほうが早い」と介護職がすべて介助してしまうのは、利用者さんのプライドを傷つけてしまったり、できることを奪ってしまったりすることにつながります。できる部分は本人にやってもらい、難しい部分をお手伝いするなど、本人のペースに合わせたケアを行いましょう。
症状が起きている原因をしっかり考える
BPSDは、「身体の状態」「周りの環境や人間関係」「周囲の対応の仕方」など、さまざまな要因によって起こります。BPSDの症状がみられる場合は、「なんで症状が起きているんだろう?」「原因は何だろう?」としっかり考えたうえで、適切な対応を行うことが大切です。
生活環境を整える
認知症を患う方は、生活環境の変化に大きなストレスや不安を感じやすく、それが原因でBPSDが悪化してしまうことがあります。そのため、部屋の模様替えや習慣を変えるなどの大きな変化はできるだけ避けましょう。本人の希望に寄り添い、安心して過ごせるような環境を整えることが大切です。
否定や自尊心を傷つけるようなことはしない
BPSDの症状には、夕方になると「家に帰ります」と言って帰り支度を始めてしまう夕暮れ症候群や、実際はいないのに「家の中に小さい子どもがいる」と訴える幻覚などがみられます。このような症状がみられた際に、強く否定したり、自尊心を傷つける対応をしたりしてしまうと、BPSDの悪化につながりかねません。
対応に困ってしまうことがあっても、まずは本人の言動や気持ちを否定せずに受け止め、自尊心を傷つけないような対応を心がけましょう。
本人の話をよく聞く
本人の話をよく聞くことも、BPSDがある方のケアで介護職が意識したいポイントの一つです。認知症を患う方は、記憶障がいの影響で同じことを何度も言ったり聞いたりすることがあります。こうした状況では、本人は何かしら不安や混乱を抱えていることも少なくありません。
何度も同じことを言われたり聞かれたりしたときも、余裕のない対応を取ってしまうことのないように注意しましょう。本人の話にしっかり耳を傾けることで、安心感を持ってもらえます。また、その際にあいづちを打ったり共感を示したりするとより効果的です。
本人をよく観察し変化に気づく
本人をよく観察し変化に気づくことも、介護職が意識したいポイントです。これはBPSDの方だけにいえることではなく、ケアを行ううえでの基本でもあります。
たとえば、本人が「お腹が空いた」「トイレに行きたい」などと思っていても、意思表示が難しいこともあるでしょう。ちょっとした変化に気づくことができないと、本人のストレスや不満が溜まり、BPSDにつながることも考えられます。
「人手不足だし、多くの利用者さんを見なきゃいけないから大変」というケースもあるかもしれません。しかし、日ごろからしっかり様子を観察し、小さな変化に気づくことができれば、BPSDの悪化を防ぐことにつながるはずです。
▼関連記事
高齢者とのコミュニケーション方法!相手に寄り添う上手な会話のコツとは
BPSDに関するよくある質問
ここでは、BPSDに関するよくある質問にQ&A形式で回答します。「BPSDってなに?」「どう関わったらいいの?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひチェックしてみてください。
認知症のBPSDって何?
認知症のBPSD(行動・心理症状)とは、記憶障がいや見当識障がいなどの中核症状が原因で起こる、行動障がいや精神症状のことです。具体的には、徘徊や暴言・暴力、抑うつ状態、幻覚などがBPSDに該当します。BPSDの現れ方は、中核症状や居住環境、周囲の対応の仕方などによって変わるのが特徴です。
この記事の「認知症の方に現れる2つの症状」では、中核症状と周辺症状(BPSD)について解説しているので、ぜひご一読ください。
BPSDの症状にはどんなものがあるの?
BPSDの症状は、主に「行動障がい」と「精神症状」に分けられます。行動障がいの具体的な症状は、夕暮れ症候群(帰宅願望)、不潔行為、異食、常同行動などです。また、精神症状の具体的な症状としては、睡眠障がい(昼夜逆転)、妄想、せん妄、感情失禁などが挙げられます。
「周辺症状(BPSD)の主な症状」では、症状について具体的にまとめているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
BPSDのある方への関わり方は?
BPSDの方への関わり方として大切なのは、まず症状が起きている原因をしっかり考えたうえで本人のペースに合わせて対応することです。プライドを傷つけたり、できることを奪ってしまったりすると、ストレスや不満が溜まり、BPSDの悪化につながってしまうことがあります。また、頭ごなしに否定することや、生活環境を大きく変化させることも、BPSDの悪化につながる要素です。本人の話にしっかり耳を傾け、安心感を持ってもらえるような関わり方を意識しましょう。
「BPSDのある方のケアで介護職が意識したいポイント」では、ケアを行う際に意識したいポイントを詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
認知症の症状は主に中核症状と周辺症状(BPSD)の2種類に分けられます。中核症状とは、脳の神経細胞が障がいを起こすことによって発症する、認知機能障がいのことを指します。認知症を患うすべての方に、実行機能障がいや見当識障がい、失行などの中核症状がみられ、認知症の進行とともに悪化するのが特徴です。
認知症の周辺症状(BPSD)としては、徘徊、暴言・暴力などの行動障がいや、不安感、抑うつ状態、幻覚などの精神症状が挙げられます。中核症状や環境・身体・心理要因、周囲の対応の仕方などによって症状の現れ方や程度が変わるのが、BPSDの特徴です。
BPSDの発生には、周りの環境や人間関係が大きく影響するため、本人の症状に合わせた適切な対応を行うことが重要といえます。もしも、適切な対応を行っても改善がみられない場合は、医療職に相談し、薬物療法や非薬物療法の治療を取り入れることも検討してみましょう。
介護職がBPSDの方へのケアを行う際は、本人の話にしっかり耳を傾け、安心感を持ってもらえるような声かけや支援を心がけましょう。プライドを傷つけたり、強く否定したりすると、BPSDの悪化につながってしまう可能性があるので注意が必要です。本人の気持ちの安定につながるような寄り添ったケアを意識しながら、BPSDへの対応を行いましょう。
「今の施設は忙しくて利用者さんにきちんと向き合えない…」「もっと一人ひとりの利用者さんに寄り添ったケアがしたい!」といったお悩みを抱えている介護職の方もいるかもしれません。BPSDの症状がある利用者さんへの対応としても、個別ケアは重要なことですよね。
上記のようなお悩みやお考えをお持ちの方は、介護職専門の転職エージェントレバウェル介護(旧 きらケア)にぜひご相談ください。あなたの希望条件に合った職場をお探しするだけではなく、面接対策や待遇の交渉も、専任のキャリアアドバイザーがしっかりサポートいたします。サービスはすべて無料なので、ぜひ気軽にご登録ください。
登録は1分で終わります!
 グループホームの求人一覧はこちら
グループホームの求人一覧はこちら