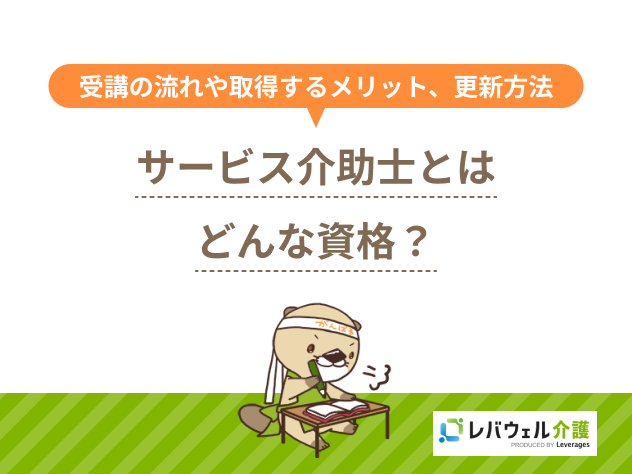
この記事のまとめ
- サービス介助士は介助の基礎を学ぶ資格で、ケアフィッターとも呼ばれる
- サービス介助士の資格講座では、自宅学習と対面形式の実技教習を行う
- サービス介助士の資格を取得するためには、計画的に学習を進めることが大切
「サービス介助士ってどんな資格なの?」と気になる方もいるかもしれません。サービス介助士は、介助や接遇のスキルを学ぶための資格で、ケアフィッターとも呼ばれます。この記事では、サービス介助士が活躍する職場や資格取得の流れを解説。実技教習の内容、筆記試験の勉強方法もまとめました。サービス介助士を取得するメリットや履歴書への記入方法もご紹介するので、資格を取ってスキルアップしたい方は参考にしてください。
介護資格の種類31選!取得方法やメリットを解説しますサービス介助士(ケアフィッター)とはどんな資格?
サービス介助士とは、公益財団法人 日本ケアフィット共育機構が認定する民間資格で、ケアフィッターとも呼ばれます。サービス介助士を取得すると、高齢者や障がいのある方に適切なサポートを行える証明になるでしょう。資格講座を受講し、「声の掛け方やタイミング」「状況に応じたサポート」「接遇」などを学ぶことで、相手に合った対応ができるようになります。
サービス介助士の取得方法は、「サービス介助士の資格取得の流れは?」で後述するので、あわせてご覧くださいね。
出典
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「サービス介助士 資格とは?」(2025年5月30日)
▼関連記事
働きながら取得しやすい介護の資格とは?必要な期間や方法、費用も解説!
サービス介助士が活躍する主な職場
サービス介助士を取得すれば、以下のような職場でスキルを発揮できるでしょう。
- 介護施設
- 病院
- 公共交通機関
- タクシー運転手
- 商業施設
- 観光・レジャー施設
- 飲食店
- スーパーマーケット
- 銀行
主にサービス業のスタッフが、サービス介助士の資格を取得しています。公共交通機関の職員も多く取得しており、車いすの方の介助を行う場面などでスキルを活かしているようです。サービス介助士の資格は、「高齢のお客さまと話すのが難しい」「障がいのある方がどのような支援を必要としているのか分からない」という方におすすめ。ケアを行う視点や技術が身につけば、すべてのお客さまに自信を持って対応できるようになるでしょう。
出典
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「導入実績・受講者の声」(2025年5月30日)
▼関連記事
福祉の仕事にはどんな種類がある?介護や児童福祉、医療に関する32の職種
働きながら資格を取る方法教えます
サービス介助士の資格取得の流れは?
サービス介助士の資格取得の流れは、次のとおりです。
サービス介助士は、働きながらでも約2ヶ月で取得できます。基本的には、受講申し込みから1年間が資格取得の期限です。最短でサービス介助士の資格を取得する方法は、「最短でサービス介助士の資格を取得するには?実技や検定試験のコツをご紹介」の記事でも解説しているので、あわせてご確認ください。
サービス介助士になるまでの流れや、資格取得後の更新手続きについて、以下で解説します。「サービス介助士になるのは難しい?」と気になっている方は参考にしてみてくださいね。
サービス介助士資格講座へ申し込む
サービス介助士の資格講座への申し込みは、サービス介助士公式サイトの「サービス介助士資格取得講座 個人でのお申し込み」から行えます。申し込みフォームに名前や住所などの情報を入力し、受講料を支払えば申し込みは完了です。受講料の支払い方法は、銀行振込とクレジットカードに対応しています。なお、サービス介助士の受講に要件はないため、社会人だけではなく、大学生や専門学校生も受講可能です。
出典
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「サービス介助士資格取得講座 個人でのお申し込み」(2025年5月30日)
資格取得にかかる費用
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構の「取得の流れ・料金」によると、2025年5月時点のサービス介助士講座の受講料は、税込41,800円です。これは、テキスト代や検定試験にかかる費用を含む金額となります。学生の場合は学割が適用されるので、受講料は税込40,700円です。サービス介助士を取得するには、受講料に加えて、実技教習の会場までの交通費がかかるでしょう。
なお、公益財団法人日本ケアフィット共育機構の「価格改定表」によると、2026年4月から、サービス介助士講座の受講料は46,200円に改定される予定です。
出典
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「サービス介助士資格取得講座 学割(学生割引)制度 導入のお知らせ」(2025年5月30日)
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「価格改定表」(2025年5月30日)
▼関連記事
介護の資格を安く取りたい!「初任者研修」と「実務者研修」を無料or割引で受講する方法
テキストで自宅学習を進めて課題を提出する
サービス介助士の資格講座への申し込みが完了すると、自宅にテキストと提出課題が1部ずつ送られてきます。まずは公式テキストを使って学習を進めることで、サービス介助士に必要な知識を網羅的に習得できるでしょう。テキストの内容を理解したら、提出課題に取り組むという流れです。
サービス介助士講座の提出課題は、計100問に3択のマークシートで解答します。テキストを見ながら解いて良いので、学習内容を振り返りながら進めましょう。提出課題は60点以上で合格で、不合格だった場合は再提出になります。課題は申し込みから6ヶ月以内に提出するのが目標です。自分が受ける実技教習までに合格しなければいけないので、計画的に勉強に取り組むことが大切になります。
スクーリングで実技教習を受講する
サービス介助士の実技教習では、講義だけではなく演習やディスカッションも行い、実践的なスキルを習得します。実技教習は全部で2日間です。受講方法は、「対面形式で2日間」「オンライン講座(約6~7時間)と対面形式での教習1日間」の2通りあるので、事前に選んで申し込みましょう。なお、対面形式で2日間の実技教習を受ける場合は、2日連続で受講するのが原則となっています。
実技教習の学習内容
サービス介助士の実技教習では、視覚や聴覚に障がいがある方の介助方法や、車いすの操作手順などを学びます。演習によって、ハンデがある方を含むすべてのお客さまに対して、スムーズにサービスを提供するスキルが身につくでしょう。実技教習の演習は、実際の介助を想定した内容なので、ズボンとスニーカーなどの動きやすい服装で臨んでくださいね。
実技教習の会場
2025年度にサービス介助士の実技教習が行われる予定があるのは、以下の地域です。
- 北海道(札幌市、帯広市)
- 宮城県(仙台市)
- 岩手県(盛岡市)※オンライン講座+1日間の教習のみ実施
- 東京都(水道橋)
- 神奈川県(横浜市)
- 新潟県(新潟市)※オンライン講座+1日間の教習のみ実施
- 石川県(金沢市)
- 長野県(長野市)
- 静岡県(静岡市・浜松市・沼津市)
- 愛知県(名古屋市、豊橋市)
- 岐阜県(岐阜市)
- 三重県(津市)
- 大阪府(東心斎橋)
- 広島県(広島市)
- 香川県(高松市)
- 福岡県(福岡市・北九州市)
- 鹿児島(鹿児島市)
- 大分県(国東市)※オンライン講座+1日間の教習のみ実施
サービス介助士の実技教習が開催される都道府県は限られています。資格講座に申し込む際は、前もって実技教習の会場や日程を確認しておきましょう。受講したい実技教習の時期から逆算して、自宅学習の計画を立てるのもおすすめです。
出典
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「サービス介助士 実技教習のお申し込み(日程確認・日程変更)」(2025年5月30日)
筆記試験を受験し合格する
サービス介助士の筆記試験は、実技教習後に各会場で行われます。筆記試験の内容を以下にまとめたので、チェックしてみましょう。
| 試験形式 | 3択のマークシート形式 |
| 合格点 | 70点以上(50問のうち35問以上の正答で合格) |
| 出題範囲 | 提出課題・テキスト・実技教習の内容 ※オンライン講座と1日間の実技教習の場合は、確認テストと模擬テストも受講内容に含まれる |
| 合否発表 | 試験の約3週間後 |
| 合格率 | 8割以上 |
参考:公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「サービス介助士 筆記試験について」
サービス介助士の筆記試験は、学習内容を理解しているか確認するための検定試験なので、難易度は低めです。もし不合格になった場合も、受講申し込みから1年以内であれば、何度でも再試験を受けることができます。ただし、再試験を受けるには、事前の申し込みと再受験料3,300円の支払いが必要です。
認定状と電子認定証を確認する
サービス介助士の筆記試験の結果は、約3週間後に郵送で届くようです。合格していれば、結果通知に認定状が同封されます。サービス介助士公式サイトのマイページから、オンラインで電子認定証を取得することも可能です。マイページへのログイン情報は、認定状と一緒に送られてきます。
資格取得後は3年に1回更新手続きを行う
サービス介助士の資格は3年ごとに更新が必要で、更新料は1,650円です。「更新料の支払い→確認テストの受験→振り返りレポートの記入」という3つの手順を踏むと、サービス介助士の資格更新手続きが完了します。
認定証に記載されている有効期限の前後6ヶ月間であれば、サービス介助士公式サイトのマイページから更新手続きが可能です。期限切れになってから7ヶ月以上経ってしまった場合は、電話での問い合わせが必要になるので注意しましょう。
出典
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「サービス介助士について」(2025年5月30日)
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「取得の流れ・料金」(2025年5月30日)
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「サービス介助士 マイページのご案内」(2025年5月30日)
サービス介助士の資格を取得するための勉強方法とは?
サービス介助士を取得するためには、テキストの内容をしっかりと理解しながら勉強することが大切です。自宅学習が中心なので、提出課題を終わらせる時期を決めて計画的に進めるのがポイント。実技教習は1~2日間の通学が必須になるため、受講したい会場の日程に間に合うように勉強する必要があります。
提出課題には、自宅学習用に送られてくる公式テキストを活用すると良いでしょう。筆記試験の対策としては、提出課題を復習するのがおすすめです。「ノートにまとめる」「声に出して覚える」など、自分に合った方法を見つけて勉強しましょう。もしも筆記試験に不合格になってしまった場合は、間違えた部分を中心に復習して再試験に挑んでくださいね。
出典
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「サービス介助士について」(2025年5月30日)
サービス介助士の資格を取得するメリットは?
ホスピタリティの精神が身についたり、接客の仕事に活かせたりするのが、サービス介助士取得のメリットです。
ホスピタリティの精神が身につく
サービス介助士を取得すると、「日常生活に障がいを抱える人もそうでない人も快適に過ごすにはどうしたら良いのか」を考えるきっかけになります。そのため、どのような関わり方をすると相手にとって心地良いのかを考え、おもてなしの心を持って他人と接することができるようになるでしょう。
高齢者との接し方については、「高齢者とのコミュニケーション方法!相手に寄り添う上手な会話のコツとは」でも解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
介護をはじめとするさまざまなサービス業に活かせる
介護業界で働く人がサービス介助士を取得すると、利用者さんの気持ちに寄り添ったケアや接遇を行うスキルが身につきます。信頼関係の構築につながったり、より質の高い介護サービスを提供できるようになったりすることが、資格取得のメリットです。
また、「サービス介助士が活躍する主な職場」で前述したように、サービス介助士の活躍の場は介護業界のみではありません。多くのサービス業では、日常的に高齢者の方や障がいを抱える方と接する機会があるため、サービス介助士のスキルが役立ちます。ケアの基本を学べば、お客さまが安心して楽しく過ごせる環境を提供できるようになるでしょう。
介護職の接遇マナーについては、「介護職の接遇マナーとは?重要性とキホンの5原則」の記事でも紹介しています。
高齢者や障がいを抱える方に対する理解が深まる
高齢化が進む日本の社会生活において、高齢者の方の気持ちや考え方などを理解することは重要です。高齢者の抱える課題やその対策を理解していると、自分や家族が高齢になったときにも役立ちます。
また、サービス介助士の資格を取得していれば、車いすを利用する方や視覚障がいがある方などを見かけたときに、サポートの必要性・方法を判断できるでしょう。障がいのある方の支援に役立つ資格については、「【障がい者支援に役立つ資格一覧】取得方法や難易度、習得できるスキルは?」でも紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。
サービス介助士の履歴書への書き方は?
サービス介助士の資格を履歴書に記載するときは、「〇年〇月 公益財団法人日本ケアフィット共育機構認定 サービス介助士資格取得」と書きましょう。履歴書の資格欄には、資格の正式名称と認定機関、取得年月を記入します。
履歴書作成の際は、「サービス介助士を履歴書に書くには?正しい記述と役立つ資格を解説!」の記事も参考にしてください。
サービス介助士の資格についてよくある質問
ここでは、サービス介助士の資格についてよくある質問に回答します。「サービス介助士ってどんな資格なの?」と気になっている方は、ぜひご一読ください。
サービス介助士は国家資格ですか?
サービス介助士は国家資格ではなく、公益財団法人 日本ケアフィット共育機構が認定する民間資格です。介護のスキルを証明する国家資格は、介護福祉士のみとなっています。サービス介助士についてもっと詳しく知りたい方は、この記事の「サービス介助士(ケアフィッター)とはどんな資格?」もチェックしてみてくださいね。
サービス介助士に関する資格の種類は?
サービス介助士よりも手軽に取得できる資格として、「准サービス介助士」や「サービス介助士ジュニア」の資格があります。准サービス介助士は、スクーリングなしで取得できるのが特徴です。また、サービス介助士ジュニアは、中学生や高校生向けの資格で、「サービス介助士ジュニア資格取得講座」を授業に導入している学校でのみ取得できます。
出典
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「准サービス介助士資格取得講座」(2025年5月30日)
公益財団法人 日本ケアフィット共育機構「サービス介助士ジュニア資格取得講座」」(2025年5月30日)
サービス介助士を取得しても意味ないの?
サービス介助士の資格講座を受講することで、介助の基礎を学べます。身につけたスキルは、高齢者の方とコミュニケーションを取るときや、障がいのある方をサポートするときに役立つため、サービス介助士の取得には意味があるでしょう。資格取得のメリットが気になる方は、「サービス介助士の資格を取得するメリットは?」もあわせてご覧ください。
まとめ
サービス介助士は、公益財団法人 日本ケアフィット共育機構が認定する資格です。資格講座を受講して身につけたスキルは、主にサービス業の仕事に役立ちます。サービス介助士になるには、自宅学習に加えて1~2日間の通学が必要です。通学での実技教習の後に行われる筆記試験に合格すれば、資格を取得できます。
ホスピタリティの精神が身につくことが、サービス介助士を取得するメリットです。また、ケアの基本を学ぶことで、高齢者や障がいのある方への理解が深まり、自身の成長にもつながるでしょう。
介護や福祉の仕事に興味がある方には、レバウェル介護(旧 きらケア)の利用がおすすめです。「高齢者と話すのが好き」「介護業界で手に職をつけて働きたい」など、福祉に興味を持ったきっかけをお聞かせください。アドバイザーと一緒に、介護業界でのキャリアを考えてみませんか?「介護業界にはどんな仕事があるのか知りたい」といった質問や、転職に関する相談も歓迎です。サービスはすべて無料なので、ぜひ気軽に利用してみてくださいね。
働きながら資格を取る方法教えます
 資格取得支援の介護求人一覧はこちら
資格取得支援の介護求人一覧はこちら