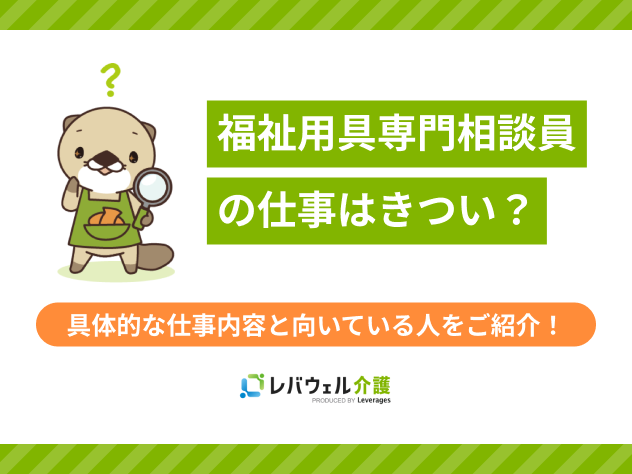
この記事のまとめ
- 福祉用具専門相談員は、福祉用具を選定して高齢者の生活を支援する専門職
- 福祉用具専門相談員は身体的な負担や営業ノルマをきついと感じることがある
- 感謝の言葉や提案が認められる達成感などが、福祉用具専門相談員のやりがい
「福祉用具専門相談員の仕事ってきついの?」と不安に思う方もいるでしょう。福祉用具専門相談員は、大変なこともありますが、やりがいも多い仕事です。この記事では、福祉用具専門相談員の仕事内容やきついと感じること、やりがいを解説。福祉用具専門相談員に向いている人の特徴や、1日のスケジュール例もご紹介します。福祉用具相談員の仕事に興味がある方は、ぜひご一読ください。
福祉用具専門相談員とは
福祉用具専門相談員とは、福祉用具の貸与や販売を行い、高齢者の生活をサポートする専門職です。福祉用具の貸与や販売を行う事業所では、福祉用具専門相談員を2名以上配置しなくてはなりません。
なお、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(第2条)」によると、福祉用具とは、「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人または心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具」を指します。
出典
e-Gov法令検索「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(2024年8月19日)
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「福祉用具専門相談員」(2024年8月19日)
福祉用具専門相談員の仕事内容
福祉用具専門相談員の仕事内容は、福祉用具の貸与や販売、事務業務などです。要支援・要介護の認定を受けた高齢者や、障がいのある方など、一人ひとりの生活や心身状況に適した福祉用具を提案。車いすや歩行器、電動ベッド、手すりなどを取り扱い、利用者さんへ福祉用具の使い方を説明します。
利用者さんの自宅に定期的に訪問し、福祉用具の状態確認や調整を行うのも、福祉用具専門相談員の仕事です。また、福祉用具サービス計画書や定期訪問後の報告書の作成も行います。
福祉用具専門相談員の平均給与
職業情報提供サイト(日本版O-NET)の「福祉用具専門相談員」によると、2023年における福祉用具専門相談員の平均年収は、3,943,000円でした。月収に換算すると、福祉用具専門相談員の平均給与は約33万円です。
なお、給与は職場や地域によって異なるので、上記は参考値としてご覧ください。職場によっては、営業ノルマの成果に応じて収入アップを目指せることもあるでしょう。また、ほかの介護・福祉に関する資格を保有していると、資格手当が支給される可能性があります。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「福祉用具専門相談員」(2024年8月19日)
今の職場に満足していますか?
福祉用具専門相談員の仕事はきつい?
福祉用具専門相談員の仕事は、身体的な負担がかかったり営業ノルマを課せられたりすると、「きつい」と感じる場合があります。ここでは、福祉用具専門相談員が「仕事がきつい」と思う理由をご紹介するので、ぜひご一読ください。
身体的な負担がかかる
福祉用具専門相談員は、身体的な負担がかかる業務をきついと感じることがあるようです。高齢者や障がいのある方の身体活動をサポートする福祉用具は、基本的に重量があります。福祉用具には鉄板や電動モーターが使われていることもあるため、搬入や組み立てに体力が必要です。
また、地域によってはエレベーターのない集合住宅で往復して作業しなくてはならない場合も。体力を消耗したり、腰痛につながったりすると、「福祉用具専門相談員の仕事はきつい」と感じてしまうことがあるでしょう。重いものを運ぶときのコツや効率的な作業方法を掴めれば、負担を軽減できるかもしれません。
幅広い専門知識が求められる
幅広い専門知識が求められるのも、福祉用具専門相談員の仕事がきついと感じる要素です。福祉用具は新商品が続々と展開されるので、その都度取り扱う製品に対する理解を深めなければなりません。福祉用具の機能や使用する際の注意点、価格帯などを頭に入れておく必要があるので、「覚えることが多くてきつい」と思ってしまう人もいます。
また、利用者さんが安全に福祉用具を活用するためには、相手が理解できるように説明しなければなりません。商品に対する理解や説明が足りていないと、利用者さんのケガや事故につながるおそれもあります。
営業ノルマを課される場合がある
職場によっては、福祉用具専門相談員に営業ノルマを課す場合があります。福祉用具専門相談員は、新規の契約件数や営業回数を課され、「ノルマを達成しなくては…」と、ストレスを感じることがあるようです。営業成果の数値がプレッシャーになると、仕事がきついと感じてしまうでしょう。
ただし、営業ノルマを達成すれば給料や賞与に良い影響を与えます。営業ノルマを仕事のモチベーションにできる人は、福祉用具専門相談員として成長していけるでしょう。
福祉用具専門相談員の3つのやりがい
福祉用具専門相談員には、「利用者さんから感謝の言葉を聞ける」「利用者さんの不安を和らげられる」「提案が認められたときに達成感を得られる」というやりがいがあります。
1.利用者さんから感謝の言葉を聞ける
利用者さんやご家族から感謝の言葉を聞けると、福祉用具専門相談員としてのやりがいを感じられます。利用者さんの笑顔が見られたり、感謝の言葉を聞けたりすることは、仕事のモチベーション向上につながるでしょう。福祉用具を取り入れることで、利用者さんの生活の質が上がれば、感謝の言葉をいただける機会が増えます。
2.利用者さんの不安を和らげられる
福祉用具専門相談員は、マンツーマンでじっくりと支援を行うことで、利用者さんの不安を和らげられます。生活環境や身体状況を理解し、課題の解決に向けて的確な提案ができれば、仕事のやりがいを感じられるでしょう。福祉用具の導入によって、ご家族の介護負担が軽減されたり、利用者さんの自立支援ができたりすると、生活の改善を図ることが可能です。
3.提案が認められたときに達成感を得られる
営業の提案が認められたときは、福祉用具専門相談員として大きな達成感を得られるでしょう。取引先と信頼を築いたり、利用者さんに充実したサポートを行ったりすると、次の契約も成立しやすくなります。成果が出るまで地道に活動することもありますが、周囲の期待に応えられると、やりがいを感じられるでしょう。
福祉用具専門相談員に向いている人
福祉用具専門相談員に向いている人は、コミュニケーション能力がある人や学習意欲が高い人です。下記の項目に当てはまる人は、福祉用具専門相談員として活躍できるでしょう。
コミュニケーションを取るのが得意
福祉用具専門相談員は、コミュニケーションを取るのが得意な人に向いています。利用者さんやご家族のニーズを汲み取って福祉用具の提案をするため、コミュニケーション能力は必須です。また、同僚や営業先の担当者とも接するため、さまざまな人と信頼関係を築くことが求められます。
周囲を観察する能力がある
周囲を観察する能力があり、利用者さんの微細な変化に気づける人は、福祉用具専門相談員に向いているでしょう。要望として伝えられた言葉以外にも、利用者さんとの会話や生活環境から、最適な福祉用具を提案することが重要です。定期訪問の際に、利用者さんが不安に感じていることはないか、福祉用具は無理なく使えているかをしっかりチェックできれば、改善案を伝えられます。
学習意欲が高い
先述したとおり、福祉用具は幅広い商品が展開されています。そのため、福祉用具専門相談員は、業界知識を意欲的に学習できる人に向いています。福祉用具専門相談員として活躍するには、福祉用具に使われる最新技術や介護業界の最新情報に、常にアンテナを張ることが必要です。学習意欲が高ければ、幅広い知識を身につけられるので、利用者さん一人ひとりの状況に応じて最適な提案や支援ができるでしょう。
福祉用具専門相談員に必要な資格
福祉用具専門相談員になるには、「福祉用具専門相談員指定講習」の修了が必要です。受講要件は特になく、50時間の講習と筆記試験をクリアすれば資格を取得できます。
なお、下記のいずれかの資格を有していれば、新たに講習を受講しなくても、福祉用具専門相談員として働くことが可能です。
- 保健師
- 看護師
- 准看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 義肢装具士
これから福祉用具専門相談員になろうと考えている方は、自分が講習免除の対象かどうかを確認してみましょう。
福祉用具専門相談員の1日のスケジュール
ここでは、福祉用具専門相談員の1日のスケジュールをご紹介します。働く事業所によって具体的な仕事内容は異なるため、あくまでも例として参考にしてください。
| 時間 | 仕事内容 |
| 午前8時 | 出勤・朝礼 |
| 午前9時 | 利用者さんA宅へ福祉用具を搬入し、使用方法を説明 |
| 午前10時30分 | 居宅介護支援事業所にて、商品の提案・説明 |
| 正午 | 休憩 |
| 午後1時15分 | 利用者さんB宅でモニタリング |
| 午後2時30分 | 利用者さんC宅でサービス担当者会議に出席。商品の提案・説明 |
| 午後4時 | 事務作業 |
| 午後5時 | 退勤 |
福祉用具専門相談員は、1日に複数の利用者さんの自宅へ訪問する機会があります。利用者さんがどのような福祉用具の利用を検討しているかをヒアリングし、最適な提案を行うことが大切です。
福祉用具専門相談員の将来性
福祉用具専門相談員は、将来性を期待できる仕事です。日本は高齢化が進み、要介護状態の人が増加しています。福祉用具を必要とする方の増加も見込まれるため、福祉用具専門相談員の需要は、今後ますます高まるでしょう。
福祉用具貸与・販売事業所はもちろん、福祉用具を取り扱うほかの職場においても、資格や知識を活かせます。近年では、百貨店やドラッグストア、通信販売サイトなどでも、福祉用具を販売しているため、福祉用具専門相談員の活躍の場は幅広いでしょう。
「福祉用具専門相談員の仕事が気になる」「高齢者の生活を支えたい」と考えている方は、介護業界に特化した転職エージェントを利用してみませんか?レバウェル介護(旧 きらケア)は、非公開求人や介護事業所の求人を多数取り扱っています。応募書類の書き方のアドバイスや面接対策にも対応しているので、転職が初めての方でも安心です。介護業界での転職を考えている方は、まずは気軽にご相談ください。
福祉用具専門相談員についてよくある質問
ここでは、福祉用具専門相談員についてよくある質問に回答します。「自分に福祉用具専門相談員の仕事ができるか心配…」と気になる方は、ぜひご覧ください。
福祉用具専門相談員の合格率はどれくらいですか?
福祉用具専門相談員の資格は、「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、修了試験に合格すれば取得できます。「福祉用具専門相談員指定講習」の修了試験は、講習内容の理解度を確認する程度のレベルです。合格率は公表されていませんが、合否を出すための試験ではなく、学習内容の定着を確認するためのテストなので、難易度は低いでしょう。福祉用具専門相談員は、受講要件がなく、研修の内容を理解していれば取得できる資格なので、「合格できないかもしれない」とあまり悩まず、挑戦してみるのがおすすめです。
福祉用具専門相談員の仕事を楽しめる人の特徴は?
コミュニケーションが得意だったり、周囲に気を配れたりする人は、福祉用具専門相談員の仕事を楽しめるでしょう。福祉用具専門相談員には、利用者さんやご家族が求める福祉用具を提案するためのコミュニケーション能力や、ニーズを汲み取る力が欠かせません。また、幅広い福祉用具の機能を把握する必要があるため、学習意欲や向上心がある方に向いています。この記事の「福祉用具専門相談員に向いている人」でも、福祉用具専門相談員に向いている人の特徴を解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
まとめ
福祉用具専門相談員の仕事は、重量のある商品を搬入したり、営業ノルマを課せられたりすることから、「きつい」と感じる場合があります。また、多種多様な福祉用具の機能や使用上の注意点など、覚えることが多いことを、大変に感じることもあるようです。
福祉用具専門相談員の仕事には大変な面もこともありますが、最適な提案によって利用者さんから感謝されたり、営業の達成感を得られたりするやりがいもあります。そのため、コミュニケーションを取るのが得意な人や、学習意欲が高い人は、福祉用具専門相談員に向いているでしょう。
「福祉用具専門相談員の仕事に興味がある」という方は、「レバウェル介護(旧 きらケア)」にご相談ください。介護経験を積みたいという方にも、専任のアドバイザーがあなたの条件に合う求人をご紹介します。アドバイザーが求人探しや施設とのやり取り、日程調整を代行するので、効率的に転職活動を行うことが可能です。「どのような求人があるか気になる」という方も、お気軽にご相談ください。
今の職場に満足していますか?
 レバウェル介護(旧 きらケア)TOPページはこちら
レバウェル介護(旧 きらケア)TOPページはこちら