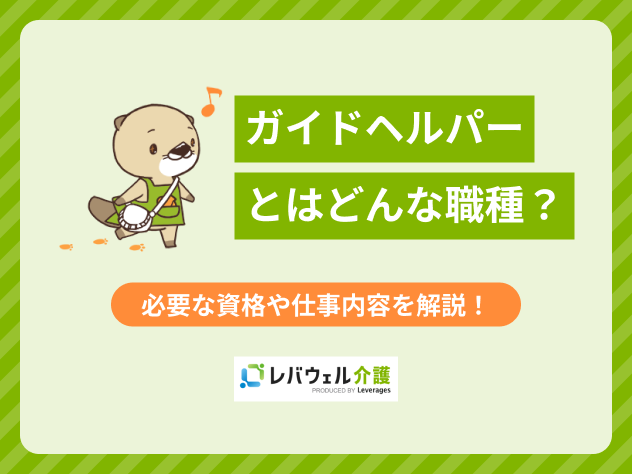
「ガイドヘルパーとはどんな職種なの?」という疑問を抱えている方もいるでしょう。ガイドヘルパーとは、何らかの障がいにより1人で移動をするのが困難な方の外出を支援する職種です。支援の対象者によって、仕事内容や資格要件が異なります。この記事では、ガイドヘルパーの仕事内容や資格要件を解説。ガイドヘルパーとして働くメリットや向いている人の特徴も紹介しているので、転職を検討中の方はチェックしてみてください。
介護資格の種類31選!取得方法やメリットを解説しますこの記事のまとめ
- ガイドヘルパーとは、障がいがあり外出が難しい方の移動を支援する職種
- ガイドヘルパーの資格要件は、支援内容によって異なる
- ガイドヘルパーに向いているのは、人の役に立つのが好きな人など
ガイドヘルパー(移動介護従事者)とは
ガイドヘルパーとは、何らかの障がいにより1人で外出するのが困難な方の外出に付き添い、移動や出先での手続きなどをサポートする職種のことです。「移動介護従事者」とも呼ばれており、利用者さんの自立と社会参加を支援します。
ガイドヘルパーが支援するのは、視覚障がいや全身性障がい、知的障がい、精神障がいがある方です。視覚障がいがある方の支援を行う人は、「同行援護従事者」と呼ばれます。知的障がい・精神障がいがある方の移動のサポートは、主に「行動援護従事者」が行い、全身障がいがある方の移動介護は「全身障害者ガイドヘルパー」が行うようです。
ガイドヘルパーの仕事内容
ガイドヘルパーの仕事内容は、利用者さんの障がいの種類・特性によって異なります。下記に、「同行援護従業者」「行動援護従業者」「全身性障害者ガイドヘルパー」の仕事内容の違いをまとめました。
| 同行援護従業者 | 行動援護従業者 | 全身性障害者ガイドヘルパー | |
| 対象者 | 視覚障がいがある方。移動を行う際に困難があり、アセスメント票の調査項目の基準を満たすことが利用の条件 | 知的障がいまたは精神障がいがあり、常時の介護を必要とする方。障害支援区分3以上かつ認定調査の基準を満たすことが利用の条件 | 四肢の機能障がいなど、全身性障がいがある方 |
| 仕事内容 | 電車やバスの乗降といった移動の手助けをする。代読や代筆など、コミュニケーションや手続きのサポートも行う | 利用者さんの不安感や問題行動の予防のほか、問題行動が起きたときの対応を実施。食事介助や排泄介助など、利用者さんに応じた外出のサポートを行う | 車いすによる移動介助などを行い、移動を支援する。利用者さんの状態に応じて、食事介助や排泄介助なども行う |
利用者さんの障がいについて理解し、一人ひとりに応じた適切な移動支援を行うのが、ガイドヘルパーの仕事です。
厚生労働省の「障害者等の移動の支援について(p.3)」によると、移動支援の目的は、「社会生活に不可欠な外出や、社会参加のための外出を支援すること」となっています。外出先は、買い物や散歩、映画鑑賞、冠婚葬祭、市役所などです。通勤など、通年かつ長期にわたる外出の支援は、基本的に行えません。
出典
厚生労働省「社会保障審議会障害者部会(第67回)」(2024年8月29日)
ガイドヘルパーの就業先
ガイドヘルパーの職場は、移動支援事業所や移動支援を行う訪問介護事業所・障害福祉サービス事業所などです。ガイドヘルパーとして働くには、移動支援を行う事業所に正社員として就職する場合や、移動支援事業事務所にガイドヘルパーとして登録する場合などがあります。
正社員として就職する場合は、ガイドヘルパーのほかに介護職員としての仕事も担当するのが一般的です。移動支援事業事務所にガイドヘルパーとして登録する場合、利用者さんの依頼に合わせてガイドヘルパーとして勤務します。事業所によって異なりますが、登録ヘルパーやパートという雇用形態で働くことが多いようです。
▼関連記事
障害者支援施設とは?仕事内容や一日の流れ、高齢者介護との違いを解説!
登録ヘルパーとはどんな雇用形態?メリットや訪問介護の仕事内容を解説!
 障害者施設の求人一覧ページはこちら
障害者施設の求人一覧ページはこちら 訪問介護の求人一覧ページはこちら
訪問介護の求人一覧ページはこちら
登録は1分で終わります!
アドバイザーに相談する(無料)ガイドヘルパーに必要な資格
ガイドヘルパーとして働くには、支援内容に応じた資格が求められます。ここでは、「同行援護」「行動援護」「全身障害者ガイドヘルパー」に必要な資格を紹介します。
同行援護従事者になるには
厚生労働省の「同行援護に係る報酬・基準について≪論点等≫(p.10)」によると、同行援護の従事者になるには、「同行援護従業者養成研修の修了」や「介護福祉士や実務研修などの修了と1年以上の実務経験」といった要件を満たさなければなりません。
同行援護従業者養成研修には、「一般課程」と「応用課程」があります。いずれかの課程を修了すれば、同行援護に従事可能です。
同行援護従業者養成研修の受講資格
同行援護従業者養成研修の「一般課程」には、受講資格が定められていないので、誰でも受講できます。「応用課程」を受講するには、一般課程の修了が必要です。
同行援護従業者養成研修のカリキュラム
厚生労働省の「同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について(p.2)」によると、同行援護従業者養成研修カリキュラムは、下記のとおりです(2024年8月時点)。
【一般課程】(2024年8月時点)
|
科目 |
時間数 |
|
|
講義 |
視覚障害者(児)福祉サービス |
1時間 |
|
同行援護の制度と従業者の業務 |
2時間 |
|
|
障害・疾病の理解(1) |
2時間 |
|
|
障害者(児)の心理(1) |
1時間 |
|
|
情報支援と情報提供 |
2時間 |
|
|
代筆・代読の基礎知識 |
2時間 |
|
|
同行援護の基礎知識 |
2時間 |
|
|
演習 |
基本技能 |
4時間 |
|
応用技能 |
4時間 |
参考:厚生労働省「同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について(p.2)」
【応用課程】(2024年8月時点)
|
科目 |
時間数 |
|
|
講義 |
障害・疾病の理解(2) |
1時間 |
|
障害者(児)の心理(2) |
1時間 |
|
|
演習 |
場面別基本技能 |
3時間 |
|
場面別応用技能 |
3時間 |
|
|
交通機関の利用 |
4時間 |
参考:厚生労働省「同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について(p.2)」
同行援護従業者養成研修の一般課程は約20時間、応用課程は約12時間です。前述したとおり、一般課程のみでも同行援護を行えますが、応用課程を修了したほうがより専門的な知識を活かした支援を行えるようになるでしょう。受講費用は研修の実施機関によって異なりますが、2万円~5万円ほどです。
なお、2025年4月からは新カリキュラムによる研修になる予定なので、受講する場合はご注意ください。
行動援護従事者になるには
厚生労働省の「行動援護に係る報酬・基準について≪論点等≫(p.21)」によると、行動援護の従事者になるには、「行動援護従業者養成研修の修了と1年以上の実務経験」などの要件を満たす必要があります。
「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)の修了と1年以上の実務経験」という要件を満たす場合も、行動援護に従事可能です。
行動援護従業者養成研修の受講資格
基本的に、行動援護従業者養成研修には、受講資格が定められていません。
強度行動障害支援者養成研修は、都道府県や研修の実施機関が、「障害福祉サービス事業所などに勤務していること」といった要件を設けている場合があります。受講を検討している方は、事前に要件を満たせるか調べておきましょう。
行動援護従業者養成研修のカリキュラム
ここでは、行動援護従業者養成研修のカリキュラムを紹介します。
|
科目 |
時間数 |
|
|
講義 |
強度行動障害がある者の基本的理解 |
1.5時間 |
|
強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識 |
5時間 |
|
|
強度行動障害のある者へのチーム支援 |
3時間 |
|
|
強度行動障害と生活の組み立て |
0.5時間 |
|
|
演習 |
基本的な情報収集と記録等の共有 |
1時間 |
|
行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解 |
3時間 |
|
|
行動障害の背景にある特性の理解 |
1.5時間 |
|
|
障害特性の理解とアセスメント |
3時間 |
|
|
環境調整による強度行動障害の支援 |
3時間 |
|
|
記録に基づく支援の評価 |
1.5時間 |
|
|
危機対応と虐待防止 |
1時間 |
参考:熊本県公式サイト「別紙 行動援護従業者養成研修 カリキュラム及び講師の基準」
行動援護従業者養成研修では、行動障がいに関する基本知識やコミュニケーション、支援方法などを約24時間で学びます。
受講費用は、研修の実施機関によって差がありますが、3万円~5万円ほどのようです。
全身障害者ガイドヘルパーになるには
全身障害者ガイドヘルパーの資格要件は、市区町村によって異なります。たとえば、大阪市で全身障害者ガイドヘルパーになるには、「移動支援従業者養成研修(全身性障がい課程)の修了」「重度訪問介護従業者養成研修の追加課程修了」などが必要です。
全身障害者ガイドヘルパーを目指している方は、自分が働きたい市区町村の資格要件を確認してみてください。
全身性障害者移動支援従業者養成研修の受講資格
大阪府は、移動支援従業者養成研修における「全身性障害者移動支援従業者養成研修課程」の受講対象として、移動支援に従事する希望や予定がある方や、移動支援に従事している方を挙げています。
研修の受講要件は、実施機関によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
全身性障害者移動支援従業者養成研修のカリキュラム
大阪府の「別紙1 研修の科目及び内容(全身性障がい課程)」によると、大阪府移動支援従業者養成研修の全身性障がい課程のカリキュラムは、下記のとおりです。
|
科目 |
時間数 |
|
|
講義 (共通科目) |
障がい者(児)福祉制度と移動支援事業 |
2時間 |
|
移動支援従業者の業務 |
1時間 |
|
|
移動支援従業者の職業倫理 |
1時間 |
|
|
障がい者の人権 |
2時間 |
|
|
講義 (障がい別科目) |
障がいの理解(全身性障がい) |
2時間 |
|
障がい者(児)の心理(全身性障がい) |
1時間 |
|
|
移動介助の基礎知識(全身性障がい) |
2時間 |
|
|
演習 |
移動介助の基本技術(全身性障がい) |
4時間 |
|
交通機関利用の介助演習(全身性障がい) |
5時間 |
参考:大阪府ホームページ「別紙1 研修の科目及び内容(全身性障がい課程)」
移動支援従業者養成研修には、「全身性障がい課程」「知的障がい課程」「精神障がい課程」があり、共通科目の講義の内容は同じです。障がい別科目の講義や演習は、身体障がいや全身障がいに関する専門知識を身につける内容となっています。
費用は研修実施機関によって異なりますが、1.5万円~5万円ほどのようです。自治体によって、移動支援従業者養成研修のカリキュラムや時間数は異なります。
▼関連記事
障害者施設で働くにはどんな資格が必要?仕事内容や働くメリットも紹介 資格取得支援の求人一覧ページはこちら
資格取得支援の求人一覧ページはこちら
ガイドヘルパーに転職するメリット
ガイドヘルパーになるメリットには、「利用者さんの意思を支援に反映しやすい」「仕事の幅が広がる」「ライフスタイルに合わせた働き方ができる」などがあります。以下で開設するので、ガイドヘルパーへの転職を迷っている方は、参考にしてみてください。
利用者さんの意思を支援に反映させやすい
ガイドヘルパーは、1対1で利用者さんの外出をサポートするため、利用者さんの意思を支援に反映させやすいというメリットがあります。施設の場合、1人で複数人を担当するのが一般的なので、利用者さん一人ひとりに合わせた支援は難しいときもあるでしょう。しかし、ガイドヘルパーは利用者さん1人を付きっきりでサポートするため、利用者さんの意思やペースに合わせた支援ができます。
仕事の幅が広がる
ガイドヘルパーの資格を取得すると、仕事の幅が広がるというメリットがあります。介護福祉士や介護福祉士実務者研修だけでは、視覚障がいや全身性障がいがある方の移動支援は行えません。支援内容に応じたガイドヘルパーの資格を取得することで、視覚障がいや全身性障がいがある利用者さんの外出を支援できるようになるため、活躍の場を広げられるでしょう。
ライフスタイルに合わせた働き方ができる
移動支援事業事務所にガイドヘルパーとして登録して、登録ヘルパーやパートとして働く場合、ライフスタイルに合わせた働き方をしやすくなります。働く曜日や勤務時間を相談して勤務できたり、正社員よりも短時間で働けたりするでしょう。そのため、「正社員のように長時間働くのは難しい」という方にとっては、働きやすい環境といえます。
キャリアアップが目指せる
介護福祉士・実務者研修の資格がある人は、同行援護従業者養成研修(応用課程)や行動援護従業者養成研修課程を修了することで、同行援護や行動援護のサービス提供責任者を目指せるようになります。キャリアアップを目指している方にとって、ガイドヘルパーへの転職は、ビジョンを実現する足がかりとなるでしょう。なお、行動援護のサービス提供責任者には、実務経験も求められます。
▼関連記事
障害者施設の仕事のやりがいとは?サービス内容や向いている人の特徴を解説
ガイドヘルパーに向いている人
ここでは、ガイドヘルパーに向いている人の特徴を紹介します。ガイドヘルパーの仕事に興味がある方は、チェックしてみてください。
人の役に立つのが好きな人
ガイドヘルパーは、障がいがある方を支援する仕事なので、「人の役に立つのが好き」という方は、ガイドヘルパーに向いているといえます。経験を積み、知識や技術を身につければ、ガイドヘルパーの仕事にやりがいを感じられるようになるでしょう。
臨機応変な対応ができる人
施設内の介助と比べて、外出先ではイレギュラーな事態が起こる可能性が高いため、ガイドヘルパーには臨機応変な対応が必要です。ガイドヘルパーが不安になると、利用者さんにも不安が伝わってしまいます。イレギュラーな事態が起きたときに冷静に判断する能力がある方は、ガイドヘルパーとして活躍できるでしょう。
方向感覚に優れた人
ガイドヘルパーがスムーズに移動支援を行うためには、方向感覚に優れていることも重要です。移動支援の際は、エレベーターやスロープを使用したり、騒音のある場所を避けたりなど、利用者さんに応じた選択をする必要があります。方向感覚や土地勘があると、適切なルートで利用者さんを案内できるので、ガイドヘルパーとして仕事をしやすくなります。
コミュニケーションスキルがある人
利用者さんとの信頼関係を築くためのコミュニケーションスキルが高い人も、ガイドヘルパーに向いているでしょう。信頼関係を築くことで、利用者さんに安心感を与えられるため、スムーズに支援ができます。
また、利用者さんのなかには、言葉によるコミュニケーションが難しい方も。表情や仕草から、利用者さんの気持ちを汲み取るのが得意な方も、ガイドヘルパーに向いているでしょう。
▼関連記事
障害者福祉に向いている人の特徴とは?高齢者介護との違いや仕事内容を解説
ガイドヘルパーがしんどいと感じること
ガイドヘルパーは、「突発的なアクシデントの予測と対応」や「利用者さんの障がいを理解すること」などをしんどいと感じることがあるようです。突発的なアクシデントとは、ほかの歩行者との接触によるトラブルや利用者さんの問題行動など。移動支援中のアクシデントには、基本的にガイドヘルパー1人で対応しなければならないため、プレッシャーが大きいようです。
また、利用者によって適切かつ安全な支援は異なります。1人の利用者さんにとって最適な支援が、ほかの利用者さんにとっても最適であるとは限りません。利用者さん一人ひとりの障がい特性や性格を把握することに、難しさを感じるガイドヘルパーは少なくないようです。
とはいえ、経験を積むことで対応方法を身につけていけるため、過度に心配し過ぎる必要はないでしょう。最初は分からないことや対応が難しいこともありますが、徐々に慣れていければ問題ありません。
▼関連記事
障害者支援施設で働く心構えとは?介護士さんが気を付けたいポイント
ガイドヘルパーに関するよくある質問
ここでは、ガイドヘルパーに関するよくある質問を紹介します。ガイドヘルパーの仕事に興味がある方は、参考にしてみてください。
介護福祉士はガイドヘルパーの資格はいらない?
介護福祉士の資格だけではできない移動支援があります。介護福祉士の資格と1年以上の実務経験がある場合は、同行援護に従事することは可能です。しかし、行動援護や全身障がいのある方の移動支援は、介護福祉士の資格だけではできません。支援内容に応じて「行動援護従業者養成研修課程の修了」や「移動支援従業者養成研修(全身性障がい課程)の修了」が必要です。なお、都道府県や市区町村によって資格要件が異なることがあるため、事前に確認しましょう。詳しくは、「ガイドヘルパーに必要な資格」をご覧ください。
出典
厚生労働省「第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年8月29日)
大阪市ホームページ「大阪市移動支援事業従事者の要件」(2024年8月29日)
ガイドヘルパーと同行援護の違いは?
ガイドヘルパーとは、何らかの障がいにより1人で外出するのが困難な方の外出を支援する職種の総称です。ガイドヘルパーには、視覚障がいのある方の移動支援を行う同行援護従事者も含まれます。障がいの種類によって、対応するガイドヘルパーは異なるのが一般的です。視覚障がいがある方の移動支援は「同行援護従事者」、知的障がい・精神障がいがある方の場合は「行動援護従事者」、全身障がいがある方の場合は「全身障害者ガイドヘルパー」が対応します。それぞれの仕事内容を知りたい方は、「ガイドヘルパー(移動介護従事者)とは」を参考にしてみてください。
まとめ
ガイドヘルパー(移動介護従事者)とは、何らかの障がいにより1人で外出するのが困難な方の外出に付き添い、移動や出先での手続きなどをサポートする職種です。視覚障がいがある方の移動支援は「同行援護従事者」、知的障がい・精神障がいがある方の移動支援は「行動援護従事者」、全身障がいがある方の移動支援は「全身障害者ガイドヘルパー」が行います。支援の対象者ごとに資格要件は異なるため、ガイドヘルパーを目指す場合は、事前に確認しておきましょう。
「ガイドヘルパーとして働きたい」という方は、介護業界に特化した転職エージェントの「レバウェル介護(旧 きらケア)」にご相談ください。介護業界の転職事情に詳しい専属のアドバイザーが、希望条件や経歴をヒアリングしたうえで、あなたに合った職場を紹介します。「必要な資格が分からない」という場合は、キャリアビジョンや就業希望エリアを伺い、必要な資格をお伝えすることも可能です。サービスはすべて無料なので、お気軽にお問い合わせください。
登録は1分で終わります!
アドバイザーに相談する(無料)