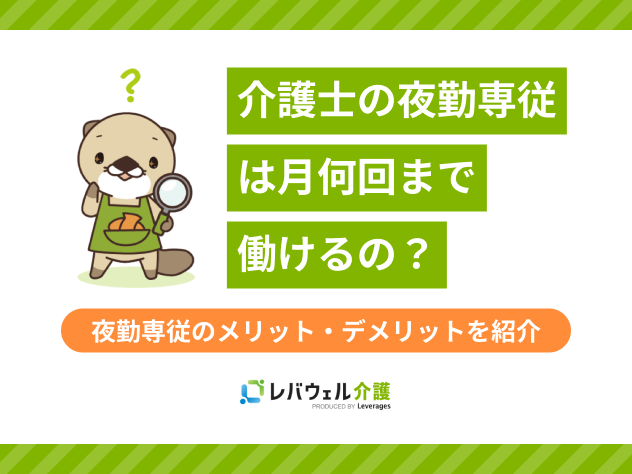
この記事のまとめ
- 夜勤専従が月何回まで出勤できるか明確な制限はなく、週2~3回程度が多い
- 夜勤専従は、変形労働時間制が適応され、週40時間以内の労働が可能
- 夜勤専従は、生活リズムを保ちやすい、夜勤手当があるなどのメリットがある
「夜勤専従は月何回まで働けるの?」と気になる方もいるでしょう。介護士の夜勤専従とは、日勤のシフトに入らず、夜勤のシフトのみに入る働き方のことです。この記事では、夜勤専従の出勤日数や1回の勤務時間を解説。労働基準法でどのように扱われているのか、「夜勤協定」とは何かについてもまとめています。夜勤専従のメリット・デメリットも整理しているので、夜勤専従の働き方を詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
介護職の夜勤がしんどいと言われる5つの理由|メリットと仕事内容介護士の夜勤専従とはどのような働き方か?
介護士の仕事には、日勤と夜勤があり、夜勤は入所型の介護施設で一般的な勤務形態です。
夜勤の中でも、「夜勤専従」は日勤のシフトには入らず、夜勤のシフトのみに入る働き方を指しています。
なお、夜勤の勤務時間は、2交代の職場は「夕方の4時から翌朝の9時まで」、3交代の職場は「夜の10時から翌朝の7時まで」がよくあるパターン。勤務時間の長い2交代の職場では、途中に2時間程度の仮眠時間を挟む場合が多いようです。勤務時間は職場によって異なるので、参考としてご覧ください。
今の職場に満足していますか?
介護士の夜勤専従は月何回まで働けるのか?
介護士の夜勤専従に具体的な出勤回数制限はありません。しかし、多くの場合は、夜勤明けとその翌日は休みというシフトが組まれるのが一般的で、連勤することは少ないでしょう。
そのため、夜勤専従では出勤回数が週に2回〜3回となり、月単位でも多くて10回ほどとなります。ただ、職場によっては夕方から翌日の朝まで仕事をすることもあるため、日勤に比べて1回の実働時間は長くなるという特徴があります。
▼関連記事
介護職の夜勤回数に上限はある?労働基準法や平均夜勤回数を解説
夜勤の法的な扱い
労働基準法では、1日の労働時間を8時間までと定めています。では、なぜ長時間に及ぶ夜勤の働き方が認められているのでしょうか。労働基準法や育児・介護休業法における夜勤の扱いをまとめました。
変形労働時間制が適用されている
労働基準法では、1日の労働時間は8時間までが基本です。しかし、夜勤では夕方から翌日の朝まで仕事をするため、その労働時間は8時間を超えてしまいます。このような働き方ができるのは、1ヶ月単位の変形労働時間制が導入されているためです。
厚生労働省の「1か月単位の変形労働時間制(p.1)」によれば、変形労働時間制は1ヶ月の労働時間を平均して、1週間あたりの平均労働時間が40時間以内であれば良いという制度です。そのため、夜勤で1日に8時間以上の労働をしていても、夜勤明けやその翌日を休日にするなどの調整を行い、1週間労働時間を40時間以内にすることで、夜勤専従としての働き方が可能となります。
出典
厚生労働省「労働基準関係リーフレット 」(2024年8月9日)
育児や介護を担う人の夜勤は育児・介護休業法で制限される
夜勤のある職場で働いている人で、育児や介護などの理由がある場合、請求すれば育児・介護休業法の規定によって夜勤を免除してもらえます。
夜勤専従として働き始めたあとに、家庭の事情で働き方を変えたい人もいるでしょう。その場合は、「小学校就学前の子どもを養育している」「要介護状態にある家族を介護している」「入社して1年以上経過している」などの条件を満たしているか確認しましょう。
なお、厚生労働省の「男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 のあらまし(p.10)」によると、特定の条件を満たす方は、午後10時から翌午前5時までの労働が免除されます。
出典
厚生労働省「男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし」(2024年8月9日)
夜勤協定を締結している施設もある
夜勤協定とは、月の夜勤回数の上限や夜勤に就く人数など、夜勤に関するルールを文書で定めて、労使間で協定として締結したものです。
介護士の夜勤専従には月の出勤回数に具体的な制限がなく、1回の勤務時間も長くなりがちです。そのため、夜勤協定には、あらかじめ夜勤に関するルールをつくって労働者と雇用者の間のトラブルを防ぐ狙いがあります。夜勤協定は夜勤専従の働き方に大きく関わる要素であるため、そもそも協定は結ばれているのか、結ばれている場合はどのような項目が定められているのかをよく確認しておきましょう。
夜勤専従の介護士の1日の仕事内容
職場によって細かな内容は変わりますが、夜勤専従の仕事では、まず日勤スタッフから仕事の引き継ぎを受けます。そして、夕食の準備と介助、就寝準備、夜間の巡回、起床準備、朝食の準備と介助などを行います。
勤務時間も勤務形態によって変わりますが、基本的には夕方から朝まで、夜から朝まで仕事をします。トラブルが起こった際には救急対応を行うことも必要です。
また、普段は夜勤ですが、研修などは日勤帯に行われることになるため、必要に応じて日勤帯に出勤することもあるでしょう。
なお、勤務時間や仕事内容は施設によって異なるので、あくまで参考としてご覧ください。仕事の流れや勤務時間について気になる方は、面接の際に質問すると良いでしょう。
▼関連記事
介護職に無資格OKの夜勤求人はあるの?仕事内容や採用されるコツを紹介
夜勤専従の介護士の5つのメリット
介護士の夜勤専従としての働き方は、給与面やワーク・ライフ・バランスのとりやすさといった面でいくつかのメリットがあります。具体的にどんなメリットがあるのか把握しておきましょう。
1.次の夜勤までのプライベートの時間が増える
夜勤の場合は、夜勤明けは休みとなり、その翌日も休日となることが多い傾向にあります。そのため、1回の出勤を終えると、次の夜勤までに長いプライベート時間を確保することが可能です。
また、副業が禁止されていない場合は、休みの時間を活かして仕事の掛け持ちをする人もいます。月の出勤日数が少ないため、その分休みの日を有効に使えるでしょう。
2.夜勤のみで生活のリズムが一定になので保ちやすい
日勤と夜勤の両方があるシフトでは、生活リズムが整えにくく、体調を崩してしまう人もいます。しかし、夜勤専従でシフトが夜勤に絞られている場合は、勤務時間がバラバラにならないため、規則正しい生活リズムを整えることができるでしょう。
3.夜勤手当があり日勤帯よりも給料が高い
夜勤専従は、毎回の勤務に夜勤手当が付くことになります。そのため、同じような仕事内容と労働時間であったとしても、日勤帯で仕事をするよりも給料が高い可能性があるようです。
また、夜勤手当だけでなく、時間帯や労働時間によっては深夜割増賃金や、法定労働時間の超過時間分の割増賃金がつきます。時間外労働に対する割増賃金や深夜割増賃金は、通常の賃金が25%割り増しされた金額です。なお、割増賃金は重複して支給されます。
出典
厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください。」(2024年8月9日)
4.自分のペースで業務に取り組みやすい
介護職に就いている人の中には、レクリエーション業務が苦手という人がいます。また、入浴介助を筋力・体力的にきついと感じる人もいるようです。しかし、これらの業務は日中に行われることが一般的で、夜勤の時間帯は記録業務や巡回などの業務をメインに行います。そのため、夜勤専従は時間に追われて仕事をすることが少なく、自分のペースで業務に取り組みやすい環境なので、日勤の時間帯に苦手な業務がある方は、夜勤専従のほうが働きやすいと感じるでしょう。
5.月の出勤回数が少ない
前述したように、夜勤専従のシフトの多くは、夜勤明けとその翌日は休みとなります。そのため、出勤回数は週に2回〜3回ほどで、月の出勤回数も10回ほどです。
1回の労働時間は長いものの、月の出勤回数が少なく、プライベート時間が確保しやすいため、仕事とプライベートのバランスが取りやすいといえるでしょう。毎日出勤するより、回数を少なくして、その分1回でがっつり働きたいという方におすすめです。 夜勤のみの求人一覧はこちら
夜勤のみの求人一覧はこちら
夜勤専従の介護士の3つのデメリット
介護士が夜勤専従として働くことにはデメリットもあります。そのため、夜勤専従で働くことを検討するのであれば、メリットだけでなく、デメリットも判断材料に含めておく必要があるでしょう。
1.体調管理に注意しなければならない
夜勤専従は夜勤のシフトのみに入るため、生活が昼夜逆転してしまうでしょう。そのため、常に夜勤で生活リズムが整えやすいといっても、体調管理に注意しなければ体調を崩してしまう可能性があります。
プライベート時間が長く確保できる分、それだけしっかりと体調管理をしなければなりません。
2.昼夜逆転で過ごすことになる
夜勤専門となることで生活リズムは整えやすいでしょう。ただし、その生活リズムは昼夜逆転したものとなります。
人によっては夜に活動することが体に合わないという場合もあるので、自分の体質を考慮したうえで働き方を考えましょう。夜型ではない人が無理に夜中心の生活にしてしまうと、体調を崩す可能性があるので特に注意が必要です。
3.未経験では採用されないことがある
施設側は、未経験の人には安心して夜勤を任せられないと考えることがあるので、介護未経験だと、夜勤専従には採用されにくい可能性があります。夜勤専従になるのであれば、日勤の仕事で経験を積んでおきましょう。
夜勤のスタッフは少人数体制の職場が多いため、職員1人当たりの仕事量が多くなります。また、職員の人数が少ない中でトラブルに対応するには知識や経験が必要であり、仕事の責任が重いと感じることがあるかもしれません。
夜勤専従で介護士として働くには資格が必要
夜勤は少人数体制の傾向があるため、1人にかかる仕事の負担が大きくなります。また、夜中に起こるトラブルへの対処には知識や経験が必要で、仕事に対する責任も大きくなるでしょう。
そのため、夜勤専従で介護士として働く場合には、資格が求められることがあるようです。特に介護度が高い利用者さんが多い施設では一定の介護スキルが必要なので、最低でも「介護職員初任者研修」の資格があると就職時のアピールにつながります。
夜勤専従の働き方についてよくある質問
ここでは、夜勤専従の働き方についてよくある質問に回答します。「夜勤専従って大変なの?」と、疑問に思う方はぜひご一読ください。
夜勤専従の職員は、月何回まで働けるの?
夜勤専従の介護職員は、週に2~3回、月に多くても10回程度働くことが可能です。夜勤は、1日の労働時間が8時間を超えるため、変形労働時間制が適応されます。変形労働時間制は、週の労働時間が40時間以内であれば、1日の労働時間が8時間を超えても働ける制度です。たとえば、1回13時間勤務の方は、週3日出勤すれば週の労働時間が39時間となるので、それ以上働けなくなります。
この記事の「介護士の夜勤専従は月何回まで働けるのか?」で、夜勤専従として働ける回数について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
夜勤専従ってきついの?
夜勤専従は、夜間に働くので生活のバランスが崩れやすく、体力的な負担を感じることがあるようです。また、夜勤の介護職員は人数が少ないので、1人で対応する可能性もあり、きつさを感じる方もいるかもしれません。
夜勤専従としての働き方は、人によって向き不向きがあるので、仕事内容や働くメリット・デメリットをしっかりと確認することが大切です。この記事の「夜勤専従の介護士の5つのメリット」「夜勤専従の介護士の3つのデメリット」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
介護士にはいくつかの働き方があり、その中に夜勤専従があります。夜勤専従には、「月何回まで」という具体的な制限はありませんが、多くても月10回程度が目安です。
夜勤専従には、「夜勤手当が出る」「自分のペースで業務に取り組める」などの魅力がある一方で、体調管理には注意が必要となります。夜勤専従の介護士として働くことを検討している方は、メリットとデメリットをよく把握しておくようにしましょう。
夜勤専従としての働き方に興味がある方は、「レバウェル介護(旧 きらケア)」にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した転職エージェントです。プロのアドバイザーがヒアリングを通して条件に合った求人をご提案いたします。「どんな夜勤専従の求人があるか知りたい」という方も、お気軽にご相談ください。
今の職場に満足していますか?