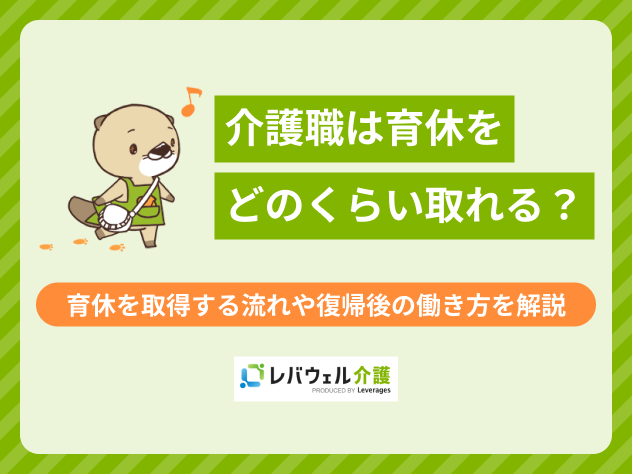
この記事のまとめ
- 産休・育休は法律で定められた制度なので、介護職の方も休業できる
- 産休・育休中の介護職は、休業中の収入や各種手当について把握しておこう
- 「肉体的に疲れる」「職場に申し訳ない」と感じる人は退職するのも一つの道
「介護職は育休が取れるの?」と心配な方もいるでしょう。条件を満たせば、介護職も育休を取得可能です。この記事では、産休・育休制度の概要や、休業中にもらえるお金の種類を解説します。育休から復帰する際に無理なく働くコツや、事業所とのやり取りのポイントもご紹介。復帰後に職場の理解が得られない場合、どうやって介護の仕事を続ければ良いかもアドバイスします。産休・育休について知りたい介護職の方は、ご覧ください。
介護士は産休・育休を取れる?
産休・育休は法律で定められた制度なので、条件を満たす女性労働者は、職種に関わらず請求する権利があります。そのため、介護職の方も、出産・育児のために休業することが可能です。産休・育休の詳しい取得条件や期間を、以下で確認してみましょう。
産休・育休制度とは
産休とは、出産を迎える労働者が、出産前と出産後に休暇を取れる制度を指します。育休は、1歳に満たない子どもを養育する労働者が取れる休暇です。
産休・育休はともに法律で定められた制度ですが、産休は「労働基準法」、育休は「育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」に基づいているという違いがあります。
産休・育休を取る条件
e-Gov法令検索の「労働基準法 第65条」によると、産休は、6週間以内に出産する予定の職員に適用され、就職・転職したばかりでも取得できます。なお、産前休業を取るかどうかは本人の意思で決められるので、希望しない場合は出産予定日ぎりぎりまで働く選択も可能です。
産前休業を取得するかは個人で選択できる一方で、産後休業の取得は必須です。産後の女性は、仕事をしたいと希望している場合も、6~8週間は休業しなければなりません。
「育児・介護休業法第5条」では、育休を取得する条件が次のように規定されています。
労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項、第九条の二第一項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
引用:e-Gov法令検索「育児・介護休業法第5条」
1歳未満の子どもを養育する場合、女性も男性も育休を取得できます。また、条件に当てはまっていても、本人が希望しない場合、育休を取得しないことも可能です。
無期雇用の職員は、入社1年未満でも、基本的には育休を取得できます。しかし、入社1年未満の方が、育休の対象にならない労使協定を結んでいる場合は、育休を取得ができないので注意しましょう。有期雇用の職員の場合、子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約が満了することが明らかでなければ、育休を取得できます。
産休・育休の期間
産前休業は、出産予定日の6週間前から取得できます。多胎妊娠(双子や三つ子など)の場合は、予定日の14週間前から取得することが可能です。
産後休業の期間は出産後8週間ですが、本人の希望があって医師が仕事をしても問題ないと判断した場合のみ、産後6週間が経過すれば就業できます。
育休の期間は、子どもの1歳の誕生日の前日までです。出産した女性の場合は、産休の翌日から育休を取得可能。男性の場合は、子どもが生まれた日から、育休を取得できます。なお、保育園に入園できないなどの特別な事情がある場合は、育休を6ヶ月~1年延長できるようです。
派遣社員やアルバイトも産休や育休を取れる
産休は雇用形態に関わらず、派遣社員やアルバイトでも取得できます。育休も、上記の条件を満たせば、雇用形態に関係なく取得が可能です。
出典
e-Gov法令検索「労働基準法」(2024年8月26日)
e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(2024年8月26日)
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」(2024年8月26日)
登録は1分で終わります!
産休・育休中の給与やボーナス
介護職として働く方が産休・育休を取る際に気になるのは、休業中の収入についてではないでしょうか?安心して出産や育児を行うために、産休・育休中のお金の事情を把握しておきましょう。
産休・育休中は基本的に給与は出ない
勤め先の介護施設によりますが、多くの職場では産休・育休中は給与が支給されないようです。
産休・育休中のボーナスは評価期間による
ボーナスには支給額を決めるための「評価期間」が設定されています。評価期間中に働いていた場合は、産休・育休中でも、ボーナスが支給される場合があります。反対に、産休・育休を取っていて、評価期間に全く働いていない場合は、ボーナスは支給されないようです。
なお、ボーナスに関するルールは職場ごとに異なります。休業中にボーナスがもらえるかどうか気になる方は、事前に上司に確認しておくのがおすすめです。
健康保険加入者は出産育児一時金・出産手当金をもらえる
産休・育休中は給与・ボーナスがゼロになることが想定されますが、代わりに社会保険の手当が支給されます。健康保険や国民健康保険に加入している場合は、出産育児一時金の支給対象です。健康保険に加入している方は、さらに出産手当金も受給できます。
出産育児一時金は、出産時に一律で支給されるお金です。厚生労働省の「出産育児一時金の支給額・支払方法について」によると、支給額は子ども一人につき50万円です(2024年8月時点)。
出産手当金は、出産による休業期間中に支給されるお金で、支給日以前の平均的な収入をもとに算出されます。具体的には、1日分の給与の3分の2程度が、休業した日数分支給されるようです。出産手当金の対象となる期間は、出産日の42日前(多胎妊娠では98日)から、出産日の56日後まで。出産日が予定日より遅れた場合は、出産予定日の42日前から手当金の対象となり、出産後56日間まで支給されます。
なお、休業中に給料が発生していて、その収入が1日の出産手当金の額を上回るときは支給されません。
出典
厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」(2024年8月26日)
全国健康保険協会「こんなときに健保:出産で会社を休んだとき」(2024年8月26日)
雇用保険加入者は育児休業給付金がもらえる
育児休業給付金は、雇用保険に加入している人が育児のために休業した場合に、支給されるお金です。出産手当金と同様に、働いていたときの収入をもとに支給額が決まります。育児休業に入ってから180日までは、休業開始前賃金の67%相当の給付金が支給され、それ以降は50%相当の金額が支給されます。
なお、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金は、健康保険や雇用保険に加入し、一定の条件を満たす場合に支給されるお金です。条件を満たせば、派遣社員やアルバイト、パートとして働く介護職も受け取れるのでご安心ください。
出典
厚生労働省「第183回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」(2024年8月26日)
▼関連記事
派遣社員は社会保険に入れる!加入条件や保険の種類、扶養内で働く方法は?
介護職が産休・育休を取るまでの流れ
ここでは、介護職が産休・育休を取得するまでの流れをご紹介します。妊娠を職場に伝える時期や申請方法が気になる方は、確認しておきましょう。
介護職の妊娠は早めに報告する
一般的な企業では、安定期に入ってから妊娠を報告する人が多いようです。しかし、介護職は、身体介護や夜勤などの体に負担がかかる業務を行います。妊娠が判明したら早めに報告しておくと、仕事中の体調に配慮してもらえるでしょう。
妊娠の報告は直属の上司にする
妊娠の報告は直属の上司に行いましょう。ほかのスタッフに伝えるタイミングは、上司と相談したうえで決めます。
産前休業の申請を行う
前述したように、産前休業は出産の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から取得できます。産前休業を取得したい場合は、上司に前もって伝えておくと良いでしょう。申請方法は職場によって異なり、申請書の提出が必要な場合もあるので、確認しておくと安心です。
育児休業の申請を行う
育児休業を取得したい場合、法律で休業開始日の1ヶ月前までの申請が定められています。産後休業に続けて育児休業を取得したい場合は、産休に入る前か産休中に申請手続きを行いましょう。
▼関連記事
【介護職が妊娠したら】報告タイミングや出産までの仕事内容、注意点を解説
介護職の育休明けの職場復帰の流れとポイント
産休・育休に入る介護職の中には、休み明けにスムーズに働けるか不安に思う方もいるでしょう。ここでは、職場復帰時の不安を減らすために、育休明けの流れや気をつけると良いポイントをお伝えします。
育休明けの流れ
育休明けは、自分自身が無理なく働ける環境を整える必要があります。育児と仕事を両立する負担が大きいと感じたら、事業所に業務内容や勤務時間を相談することも重要です。
「育児・介護休業法第23条」では、雇用主は従業員の希望に応じて時短勤務を認めることが義務付けられているので、遠慮せずに話してみると良いでしょう。
子どもが小さいうちは、急な発熱などで欠勤・早退しなければならない場面もあります。周囲の理解を得るためにも、勤務時間内にはできる限りの働きを見せることも大切です。
出典
e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(2024年8月26日)
気をつけたいポイント
事業所によっては、子どもができた正社員の職員に対して、「パートとして働かないか」と持ちかけてくることがあります。自分が納得していれば雇用形態を変えても問題ありませんが、納得できない場合は事業所と話し合うことが大切です。雇用形態を変更する場合でも、「子どもが大きくなったら正社員に戻れるのか」といった条件を確認しておくと良いでしょう。
産休・育休を取得するメリット
ここからは、介護職が産休・育休を取得するメリットを挙げていきます。産休や育休を取得しようと考えている方は、チェックしてみてください。
同じ職場に復帰できる
今の職場が気に入っている場合や、休み明けに環境を変えずに働きたい場合は、退職せずに産休・育休を取ることで、同じ職場に復帰できるというメリットがあります。子育てが落ち着いてから仕事を探し、一から仕事を覚えたり人間関係を構築したりする必要がないため、負担が少ないと感じる方もいるでしょう。
スキルを維持できる
産休・育休後、それ以上のブランクを明けずに同じ職場に復帰することで、スキルを維持しやすくなります。同じ職場であれば、仕事のやり方も大きく変わらないため、業務をすぐに思い出せる良さがあるでしょう。
各種給付金を受け取れる
出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金は、退職から一定期間が経つと受給できなくなります。健康保険・雇用保険に一定期間加入している方が、産休・育休を取得した場合は、確実に給付金を受け取れるでしょう。
子育ての時間を確保できる
育休を取ると、子どもと向き合う時間を確保できます。子どもの成長をそばで見守れる喜びや、子どもと一緒にいられる安心感を得られるのは、育休を取得する大きなメリットです。
体調や生活リズムを整えられる
産休・育休を取ると、仕事に追われず家事や子育ての時間を確保できます。仕事をしながら出産・育児をするよりも体調を管理しやすく、生活リズムを整えやすいでしょう。
復帰後に職場の託児所を利用できる
勤め先に託児所がある場合、在職していることで子どもの預け先を確保できるというメリットもあります。特に、保育園の倍率が高い地域の場合、職場の託児所が使えると心強いでしょう。 託児所ありの求人一覧はこちら
託児所ありの求人一覧はこちら
日勤のみなど融通が利く
長年勤めている施設であれば、「日勤のみで働きたい」などの要望を伝えやすいメリットもあります。特に、スキルがある介護職の場合、施設側も「辞めてほしくない」と考え、希望を受け入れてくれる可能性があるでしょう。 日勤のみの求人一覧はこちら
日勤のみの求人一覧はこちら
産休・育休復帰後の働き方の変化
産休・育休の取得にはメリットがある一方で、復帰後の働き方の変化にデメリットを感じる方もいます。休業の際は、メリットとデメリット両方を理解しておくことが大切です。
人間関係が変化する可能性がある
子育てに理解がない職場だと、復帰後に働きづらくなるおそれがあります。同じ職場でも、「子どもができる前と後では、周りの雰囲気が変わった」と感じる介護職もいるようです。
勤務体系が変化して収入が減る場合がある
「産休・育休中の給与やボーナス」で解説したように、産休・育休中は給与がなくなってしまいます。また、職場に復帰してからも、「夜勤に入らない」「時短勤務に変更した」といった勤務体系の変化があると、産休・育休前よりも収入が減る可能性があります。
体力の負担が増加する
介護職には、身体介護や夜勤など、体力を使う業務があります。産休・育休明けに、仕事と育児を両立することで、体力的な負担が増大し、疲れを感じてしまう可能性もあるでしょう。
所属や役職が変わる可能性がある
子育てによる勤務時間や雇用形態の変更があると、所属や役職が変わる可能性も生じます。産休・育休明けに同じ職場に復帰できても、思うようなポジションで働けない状況を想定しておく必要があるでしょう。
突発的な休みやシフト調整が必要になる
仕事と育児を両立する場合、子どもの発熱による突発的な休みが発生したり、早退などでシフト調整が必要だったりする場面が出てきます。子育てに理解のある職場であれば問題ありませんが、子育てに理解のない職場や人手不足の職場では、シフトを変える度に肩身の狭い思いをする可能性があります。
日勤のみなど融通が利かないケースもある
職場によっては「日勤のみ」といった働き方の融通が利かず、仕事と子育ての両立が難しい場合があります。短時間勤務は法律で定められた制度ですが、言い出せる雰囲気がない職場もあるようです。
産休・育休を取らず退職する人もいる
仕事と子育てを両立させている介護職がいる一方で、以下のような理由で産休・育休を取らずに退職を決める人もいます。
- 身体的に疲れてしまう
- 仕事と育児のを両方行うのはストレスが溜まる
- 介護職は育休がないと思い込んでいる
- 辞めなくてはいけない雰囲気がある
- 職場に申し訳ない
この中で、「介護職は育休がない」という思い込みは間違いです。前述したとおり、育休は法律で定められた制度なので、どの職場にも適用されます。
ただ、「身体的に疲れる」「仕事と育児を両立させるのが難しい」といった理由がある場合、無理をせずに退職するのも一つの選択肢といえるでしょう。介護職はブランクがあっても再チャレンジできる仕事です。「子どもが小学校に上がったらもう一度就職する」という風に、長期的にキャリアを考えることもできます。
産休・育休制度の整った施設へ転職する選択肢もある
「本当は働き続けたいのに、辞めなくてはいけない雰囲気がある」と悩んでいる方は、子育てをサポートする制度が整った施設へ転職する選択肢もあります。
産休・育休は労働者の権利ですが、取得しにくい雰囲気があったり、復帰後のサポートが充実していなかったりする職場もあるようです。出産・子育てと仕事を両立させるために大切なのは、子育てがしやすい環境の職場を見つけることです。
子育て中の職員が多い職場であれば、お互いに助け合いながら働くことができるでしょう。託児所がある職場は、子育てへの配慮があることが多く、子どもの預け先にも困りません。
求人を見る際は、「産休・育休実績多数」「託児所完備」「子育て支援制度あり」などの文言に注目してみましょう。「介護の仕事をしながら子育てをするのは大変…」と思うかもしれませんが、仕事と子育てが両立させられるか否かは、職場環境に左右される面もあります。
介護職の育休に関する質問
ここでは、介護職の育休に関する質問に回答します。育休の取得を考えている方は、ぜひご一読ください。
介護職の育休明けに注意することとは?
介護職の育休明けに注意が必要なのは、無理なく勤務できる環境を整えることです。育児と仕事を両立させるには、出産前以上の体力を要します。負担が大きいと判断した場合は、就業先に仕事内容や勤務時間の見直しの相談が必要です。病児保育など、利用できるサポートも確認しておきましょう。子どもの体調不良などで急な欠勤も生じやすくなるため、勤務中は精一杯の働きをして、周囲の理解を得ることも大切になります。詳しくは、「介護職の育休明けの職場復帰の流れとポイント」で解説しているので、ご参照ください。
介護士の男性は育休を取れない?
育休制度は、国が定める法律のため、条件を満たせば男性の介護職も取得できます。男性は子どもが生まれた日から子どもが1歳になる前日までに、2回まで育休を取得することが可能です。また、2022年10月に男性向けの新制度として、産後パパ育休が始まりました。これにより、生後8週間以内に、最長4週間の育休を最大2回に分けて取れるようになっています。男性の育休取得は増加傾向にあるとはいえ、人手不足の介護業界では取りにくいと感じる場合もあるかもしれません。家庭の状況に合わせてスムーズに育休を取れるよう、妊娠が分かった段階で早めに上司に相談しましょう。
出典
厚生労働省「育児・介護休業法について」(2024年8月26日)
まとめ
産休・育休は法律で定められた制度です。産休は誰でも取得でき、育休も同じ職場に1年以上勤務しているなどの条件を満たせば、雇用形態に関係なく取得できます。
産休・育休中は給与やボーナスが出ない職場が多いですが、健康保険や雇用保険に加入していれば、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金を受け取ることが可能です。
復帰後の働き方に不安がある場合や、職場が子育てに理解を示してくれない場合は、出産や育児のサポート体制が整った職場に転職する選択肢もあります。
「育休を取得したい」と考えている方は、介護職に特化した転職エージェントのレバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)では、キャリアアドバイザーが実際に施設と連絡を取って情報収集しています。そのため、産休・育休の取得実績や子育てに関するサポートの有無など、1人で調べるのが難しい情報をお伝えすることが可能です。
子育てをしながら介護の仕事を続けたい方は、ぜひレバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください!
登録は1分で終わります!