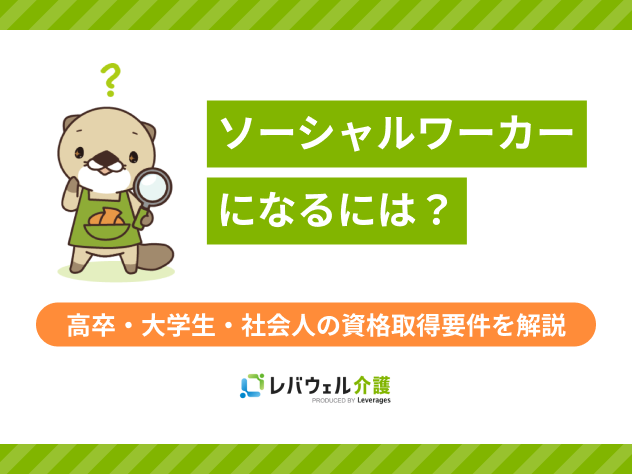
この記事のまとめ
- ソーシャルワーカーになるには、職場が定める資格要件を満たす必要がある
- ソーシャルワーカーの就職に役立つ資格は、社会福祉士や精神保健福祉士など
- 社会福祉士を目指す方は、自身の学歴や経歴に応じた受験ルートを選ぼう
「ソーシャルワーカーになるにはどうしたら良いの?」と気になる方もいるでしょう。ソーシャルワーカーの資格要件は職場によって異なりますが、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事のいずれかの資格があれば、就職に有利です。この記事では、ソーシャルワーカーの資格要件を職場別に解説。社会福祉士の学歴・経歴別の受験ルートもまとめました。ソーシャルワーカーになる最短ルートが知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
介護資格の種類一覧まとめ!取得のメリットや難易度を解説しますソーシャルワーカーとは
ソーシャルワーカーとは、社会生活や日常生活に課題がある方やその家族の相談に乗り、問題解決のためにサポートする職種です。支援の対象は、高齢者や身体が不自由な方、学校に通うのが難しい子どもなどさまざま。活躍の場も、介護施設や病院、教育機関、民間企業と幅広くなっています。
ソーシャルワーカーの種類
ソーシャルワーカーは、勤務先や支援の対象者によって呼び方が変わります。ここでは、ソーシャルワーカーの種類と勤務先を解説します。
生活相談員
生活相談員は、介護施設で活躍するソーシャルワーカーのことです。利用者さんやご家族に対して、施設のサービスに関する説明をしたり、日常生活の相談に乗ったりします。勤務先は、下記のとおりです。
- 特別養護老人ホーム
- 有料老人ホーム
- デイサービス
「身体機能が低下してできないことが増えた」「認知症が重度化して生活に不安が出てきた」など、利用者さんの状況は時間の流れとともに変化します。介護施設は、利用者さんの心身の状態に合わせて、適切な介護サービスを提供しなければなりません。
そのために、生活相談員は、ケアマネジャーや現場の介護職と連携して、必要な支援を受けられるよう調整します。社会保障制度についての知識や相談援助のスキルを活かして、利用者さんが抱える課題の解消に取り組むのが、生活相談員の役割です。
支援相談員
支援相談員は、生活相談員と同様に介護施設で利用者さんの生活のサポートをする職種ですが、勤務先が異なります。支援相談員の勤務先は下記のとおりです。
- 介護老人保健施設
介護老人保健施設とは、在宅復帰を目指したリハビリを行いながら、介護サービスを提供する施設です。介護老人保健施設に勤める支援相談員の主な役割は、入所の手続きや退所までの調整、在宅復帰後の生活状況の確認など。前述のとおり、介護老人保健施設は在宅復帰を目的とした介護施設なので、「利用者さんが快方へ向かう様子を見守れるのがやりがい」という方が多いようです。
詳しく知りたい方は、「老健の支援相談員とは?仕事内容や必要な資格、生活相談員との違いを解説」をご覧ください。
医療ソーシャルワーカー(MSW)
医療ソーシャルワーカー(MSW)とは、患者さんやご家族が抱える困りごとの相談に乗り、問題が解決するようサポートします。具体的な勤務先は下記をご覧ください。
- 病院
- 保健所
- 社会復帰施設
医療ソーシャルワーカーの主な仕事は、金銭面の不安を抱える患者さんに利用できる制度を伝えたり、退院後に必要な支援が行き届くよう調整したりすることです。ほかにも、患者さんの心理的なケアや社会復帰のサポートを担います。そのため、障がいや疾病への理解、心理学の知識などがあれば、業務に役立つでしょう。
精神科ソーシャルワーカー(PSW)
精神科ソーシャルワーカーは、精神障がいのある方やそのご家族を対象に、日常生活のサポートや社会復帰の支援を行っています。精神科ソーシャルワーカーの勤務先は、医療機関や生活支援施設、行政機関などです。具体例は、下記のとおりです。
- 精神科病院
- 自立訓練(生活訓練)事業所
- 相談支援事業所
- 介護施設
- 精神保健福祉センター
精神科病院に勤務するソーシャルワーカーは、入退院の手続きのサポートや退院後の生活の支援などを行います。自立訓練事業所では、障がいのある方が自立した生活を送るための相談対応や、社会復帰を支援するのが主な役割です。
勤務先によって仕事内容は異なりますが、精神科ソーシャルワーカーは相談者の困りごとを引き出すコミュニケーションスキルが必要とされます。
スクールソーシャルワーカー(SSW)
スクールソーシャルワーカー(SSW)は、教育の分野で活躍するソーシャルワーカーです。主に、下記のような教育機関で活躍しています。
- 公立小学校
- 公立中学校
- 高等学校
- 特別支援学校
- 教育委員会
- 教育事務所
日常生活に問題を抱えている子どもを支援するのが、スクールソーシャルワーカーの役割。いじめや不登校、虐待、暴力行為など、子どもが抱える幅広い問題の解決に向けてサポートします。
スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの違いは、課題へのアプローチ方法です。スクールカウンセラーは、子どもやご家族の心理的なケアを中心に行い、問題解決に取り組みます。一方のスクールソーシャルワーカーは、学校・地域・医療機関などへの働きかけや制度の活用を通して、子どもやご家族に社会的な支援を行うのが特徴です。
児童福祉司
児童福祉司は、子どもや保護者からの、子どもの福祉に関する相談対応や支援を行う職種です。児童福祉司は、公務員として下記の職場で勤務しています。
- 児童相談所
児童福祉司が扱う相談内容は、子どもに関する虐待や非行、健康、障がいなど。面談や家庭訪問を行い、問題の解決に向けて支援・指導をします。家庭内における、外からは見えにくい問題を主に扱っているため、サポートの方向性を見極めるのが難しい職種です。
コミュニティソーシャルワーカー(CSW)
コミュニティソーシャルワーカー(CSW)は、困りごとがあり、現状の制度では支援が行き届いていない方などに対応します。主な勤務先は、下記のとおりです。
- 社会福祉士協議会
- 障がい者施設
- 地域包括支援センター
コミュニティソーシャルワーカーは、医療や介護、障がい福祉などのサービスに繋がれずに、問題を抱えている方を対象に相談支援を行っています。たとえば、言葉が通じずに生活に困っている外国の方やホームレスの方などです。そのほか、地域福祉が抱える課題を発見し、解決に向けた新しい支援策を講じていく役割も果たします。
ケースワーカー(CW)
ケースワーカー(CW)は、生活に困りごとを抱えている人の相談に乗り、必要な支援を考えたり、公的な制度の利用手続きを行ったりします。ケースワーカーは、下記に勤務する公務員です。
- 福祉事務所
ケースワーカーは、公的機関において生活保護の受給を希望する方の対応や、相談者の自立に向けた支援などを行います。ケースワーカーについて詳しく知りたい方は、「ケースワーカーとは?資格・年収・ソーシャルワーカーとの違いも解説」の記事も合わせてご覧ください。
働きながら資格を取る方法教えます
ソーシャルワーカーになるには?
ここでは、ソーシャルワーカーの種類別の要件を解説します。「ソーシャルワーカーになるにはどうしたら良いの?」と気になっている方は参考にしてください。
生活相談員になるには
生活相談員になるには、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格のいずれかの資格が求められる場合が多いようです。ただし、生活相談員になるための条件は、地域によって異なります。なかには、介護福祉士やケアマネジャー、介護職として一定の実務経験がある人などが、生活相談員になれる自治体もあるようです。
資格を取得したうえで、特別養護老人ホームやデイサービス、ショートステイなどの生活相談員の求人に応募して採用されると、生活相談員として働けます。生活相談員の仕事に興味がある方は、働きたい地域の要件を調べておくと良いでしょう。
▼関連記事
生活相談員の資格要件は?未経験から目指せる?仕事内容や職場もご紹介
支援相談員になるには
介護老人保健施設の支援相談員になるのに、資格要件は定められていません。ただし、社会保障制度や介護保険制度などに関する専門知識が求められるため、無資格から採用される可能性は低いでしょう。社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格のいずれかの資格が求められることが大半です。また、介護施設で勤務していた経歴もあると有利でしょう。
医療ソーシャルワーカーになるには
精神保健福祉士または社会福祉士の資格を取得すると、医療ソーシャルワーカーとして働くことが可能です。精神障がいのある患者さんを支援したい場合は精神保健福祉士を、幅広くさまざまな患者さんを支援したい場合は社会福祉士を取得すると良いでしょう。就職先を調べるときは、病院や診療所、介護老人保健施設の求人を探してみてくださいね。
精神科ソーシャルワーカーになるには
精神科ソーシャルワーカーとして働くには、精神保健福祉士の資格が求められます。先述したとおり、精神科ソーシャルワーカーが活躍する場は、医療機関や生活支援施設、行政機関など。患者さんの生活を支えたい方は、精神科病院や精神科のある病院、相談者さんの日常生活や社会復帰のサポートをしたい方は、生活支援施設や行政機関の求人を探してみると良いでしょう。
スクールソーシャルワーカーになるには
スクールソーシャルワーカーになる主なルートは2つです。1つ目は、社会福祉士または精神保健福祉士を取得するルート。より専門的な知識を得るために、スクールソーシャルワーク教育課程を修了することが望ましいとされています。
スクールソーシャルワーカーになる2つ目の方法は、科目履修などの条件を満たして大学院を修了し、公認心理師または臨床心理士の資格を取得するルートです。なお、スクールソーシャルワーカーの資格要件は勤務先によって異なりますが、特定の資格や実務経験などが必要な場合が多いでしょう。
自治体が実施する書類選考や面接試験に合格すれば、公立学校のスクールソーシャルワーカーとして働けます。非常勤の職員としてではなく地方公務員として常勤勤務する場合は、公務員試験への合格も必要になるようです。
児童福祉司になるには
児童福祉司になるには、児童福祉司の任用要件を満たしたうえで、地方公務員試験への合格が必要です。児童福祉司の任用要件には、社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格を有することなどが定められています。そのほか、看護師や保健師、保育士としての相談援助業務を一定の年数を積むと、児童福祉士を目指すことが可能です。
コミュニティソーシャルワーカーになるには
コミュニティソーシャルワーカーになるために必須の資格はないので、福祉業界での実務経験があれば勤務できる職場もあるようです。ただし、相談援助を行う専門性が求められる仕事なので、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格のいずれかを保有している方が、就職や転職はしやすいでしょう。
前述したように、コミュニティソーシャルワーカーは社会福祉協議会で多く活躍しています。転職の際は、地域の社会福祉協議会のWebサイトに求人が掲載されていないか、チェックしてみると良いでしょう。
ケースワーカーになるには
ケースワーカーになるには、社会福祉主事任用資格の取得が必要です。ケースワーカーは公務員なので、資格取得と併せて地方公務員試験への合格も求められます。筆記試験と面接に合格して地方公務員になり、福祉事業所に配属されると、ケースワーカーとして働くことが可能です。
ソーシャルワーカーに必要な主要資格の取得方法
ソーシャルワーカーとして働きたい方は、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事のいずれかの資格を取得すると、就職や仕事に活かせます。ここでは、3つの資格の取得方法をご紹介するので、キャリアの参考にしてくださいね。
社会福祉士
社会福祉士は国家資格で、国家試験に合格し、資格登録をすることで取得できます。社会福祉士国家試験は、学歴や実務経験の要件を満たした人しか受験できません。「社会福祉士を目指す場合の受験ルート」では、社会福祉士になるルートを学歴・経歴別に解説するので、ソーシャルワーカーを目指す方はあわせてご覧ください。
▼関連記事
社会福祉士
精神保健福祉士
精神保健福祉士国家試験に合格して資格登録を行うことで、精神保健福祉士を取得できます。試験の受験資格を得るためには、保健福祉系の大学等で指定科目を履修したり、相談援助の実務経験を積んだりしなければなりません。学歴によって、資格取得にかかる期間は異なります。精神保健福祉士を目指す方は、自身に合った受験ルートを確認しておきましょう。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「精神保健福祉士国家試験」(2024年5月20日)
▼関連記事
精神保健福祉士
社会福祉主事任用資格
社会福祉主事任用資格を取得するには、厚生労働省が指定する大学・通信教育・養成機関・講習会などで、指定科目を履修しなければなりません。教育課程を受講するにあたり、「自治体の職員として社会福祉事業に従事している」「介護保険事業者の指定を受けた施設・事業所に従事している」などの要件が設けられている可能性があります。社会福祉主事として働きたい方は、自分が住む地域の講習の要件や日程をチェックしておくと良いでしょう。
出典
厚生労働省「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」(2024年5月20日)
社会福祉士を目指す場合の受験ルート
ここでは、ソーシャルワーカーとして働く際に求められることが多い「社会福祉士国家資格」の取得方法を解説します。社会福祉士国家試験を受験できるのは、受験資格を満たしている方と、試験がある年の3月31日までに受験資格を満たす見込みがある方です。
社会福祉士を目指す方は、下記のなかから自身の学歴や経歴に合った取得ルートを確認してみてくださいね。
高校生の場合
社会福祉士を目指す高校生には、「福祉系の4年制大学へ進学して、指定科目を履修するルート」がおすすめです。こちらのルートは、実務経験や養成施設の卒業が不要で、学校に通って単位を履修するだけで受験資格を得られます。
経済的な負担を抑えて社会福祉士を取得したい高校生は、「短大を卒業して実務経験を積むルート」も選択肢の一つです。3年制短大を卒業する場合は1年間、2年制短大の場合は2年間、相談援助の実務経験を積むことで、社会福祉士の受験資格を得られます。
社会福祉士の取得を目指す高校生は、進学の際に指定科目をすべて履修できる福祉系学校を選びましょう。基礎科目のみを履修する福祉系大学・短大を卒業して社会福祉士になる場合は、短期養成施設に6ヶ月以上通う必要があるので注意が必要です。
大学生の場合
福祉系大学に通っている場合、指定科目をすべて履修することで、社会福祉士国家試験の受験資格を得られます。福祉系大学において基礎科目のみを履修した方は、卒業後に半年以上、短期養成施設に通いましょう。
4年制の一般大学の場合は、卒業後に一般養成施設に1年通えば、社会福祉士国家試験の受験資格を得られます。また、一般短大に通う方は、卒業後に相談援助の実務経験を積んだうえで、一般養成施設に1年間通うことが要件です。受験資格を得るためには、3年制短大の場合は1年間、2年生短大の場合は2年間、相談援助の実務経験を積む必要があります。
社会人の場合
社会人の場合、最終学歴や相談援助の実務経験の有無によって、社会福祉士の最適な取得ルートが異なります。以下で社会人の選択肢を確認してみましょう。
4年制の一般大学を卒業している場合
4年制の一般大学を卒業済みの方は、一般養成施設に1年通えば、実務経験なしで社会福祉士国家試験を受験できます。養成施設は、通信教育や通学、夜間などの種類があるので、自分の生活に合わせて学習することも可能です。
最終学歴が高卒の場合
最終学歴が高校卒業で、相談援助の実務経験がない方は、福祉系大学や短大へ入学するのが社会福祉士になる最短ルートです。指定科目を履修したり実務経験を積んだりすれば、4年後に社会福祉士国家試験の受験資格を得られます。
相談援助の仕事をしたことがある場合は、通算4年の実務経験を積み、一般養成施設に1年通えば受験資格を得られるので、そのまま経験を重ねる選択肢もあるでしょう。
一般短大や福祉系大学・短大を卒業している場合
一般短大や福祉系の学校を卒業した方が、社会福祉士国家試験を受験するには、養成施設・実務経験の要件を満たす必要があります。具体的な条件は下記のとおりです。
| 学校の種類・履修科目 | 実務経験・養成施設等の条件 |
| 福祉系大学等(4年制・基礎科目のみ) | 短期養成施設等6ヶ月以上 |
| 福祉系短大等(2年制・基礎科目のみ) | 相談援助の実務経験2年 短期養成施設6ヶ月以上 |
| 福祉系短大等(3年制・基礎科目のみ) | 相談援助の実務経験1年 短期養成施設6ヶ月以上 |
| 一般短大等(2年制) | 相談援助の実務経験2年 一般養成施設等1年以上 |
| 一般短大等(3年制) | 相談援助の実務経験1年 一般養成施設等1年以上 |
参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[社会福祉士国家試験]受験資格(資格取得ルート図)」
福祉系大学で指定科目を履修していない方が社会福祉士を目指す場合、養成施設等に6ヶ月から1年以上通わなければなりません。大学や短大の通学期間が短いほど、必要な実務経験の期間は長くなります。
いずれのルートでも、社会福祉士になるには数年かかるので、試験までの道すじを立てて計画的に準備を進める必要があるでしょう。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「社会福祉士国家試験」(2024年5月20日)
▼関連記事
社会福祉士資格を取得する7つのメリットとは?取得方法やルートも解説!
資格を取得することのメリット
ソーシャルワーカーを目指す方のなかには、資格取得を迷っている方もいるでしょう。ソーシャルワーカーとして働くのに、必ずしも資格が必要というわけではありませんが、資格があると仕事の幅が広がったり質の高い支援が行えたりするなどのメリットもあります。
ここでは、ソーシャルワーカーに活かせる資格を取得することのメリットを解説するので、資格取得を迷っている方は参考にしてみてください。
仕事の幅が広がる
資格要件を定めていないソーシャルワーカーの仕事はあるものの、応募の際に資格要件を定める求人が大半を占めるのが現状です。そのため、社会福祉士・精神保健福祉士などの資格があると、応募できる求人がぐっと増えるでしょう。また、資格は専門知識を保有していることの証明になります。資格要件を定めていない職場での選考でも、資格があると有利になるでしょう。
質の高い支援が行える
資格を取得する過程で専門知識が身につくため、無資格のままソーシャルワーカーの仕事に就くよりも質の高い支援が行えるようになります。日常の業務では身につけにくい知識を得られるのが、資格を取得するメリットの一つです。試験に合格するために学んだことは、実際の業務でも活かせる場面は多数あります。
給与が上がる
職場によっては、専門的な資格を持っていることで資格手当が支給されたり、昇給することがあります。資格を持っていたほうが、無資格のままよりも高待遇で働けるでしょう。「給与を上げたい」という場合にも、資格取得は有効です。
ソーシャルワーカーと他職種との違い
ここでは、ソーシャルワーカーと混同しやすい「ケースワーカー」や「社会福祉士」「ケアマネジャー」の違いを解説します。それぞれの違いに疑問を感じている方は、参考にしてみてください。
ソーシャルワーカーとケースワーカーとの違い
ソーシャルワーカーとケースワーカーの違いは、業務内容の範囲や職場です。
ソーシャルワーカーとは、福祉・介護・医療・教育など幅広い分野において社会的な問題の解決に向けた支援や援助を行う職種のこと。一方、ケースワーカーは「ケースワーカー(CW)」で述べたとおり、福祉事務所などで公務員として生活保護などに関する対応を行う職種を指します。
ソーシャルワーカーとケースワーカーは、全く別の職種ということではなく、ケースワーカーはソーシャルワーカーに含まれているといえるでしょう。
ソーシャルワーカーと社会福祉士との違い
ソーシャルワーカーと社会福祉士との違いは、資格の有無です。
多様な分野において支援や援助を行う職種であるソーシャルワーカーのうち、社会福祉士資格を保有している人のことを社会福祉士といいます。ソーシャルワーカーは、相談業務を行っていれば名乗れる職種ですが、社会福祉士は資格がないと名乗ることはできません。
▼関連記事
ソーシャルワーカーと社会福祉士の違いを解説!仕事内容や必要な資格とは?
ソーシャルワーカーとケアマネジャーとの違い
ソーシャルワーカーとケアマネジャーの違いは、業務内容と保有資格です。医療や福祉の現場で相談や支援業務を行うソーシャルワーカーに対して、ケアマネジャーは介護施設や居宅介護支援事業所などでケアプランの作成などを担当します。ケアマネジャーとして働くには、介護支援専門員の資格が必要です。
▼関連記事
ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどんな仕事?業務内容や役割を解説!
ソーシャルワーカーの働き方
ソーシャルワーカーの働き方は、勤務先によって異なります。公的施設であれば、固定勤務で土日休みである可能性が高いでしょう。24時間体制の病院や介護施設の場合は、シフト制になることがあります。
ソーシャルワーカーは、正社員・パート・アルバイト・派遣社員など、さまざまな雇用形態で働くことが可能です。ライフスタイルに合わせて働き方を選べるのも、魅力の一つといえます。
▼関連記事
ソーシャルワーカーの仕事内容とは?役割や必要な資格、年収を解説
ソーシャルワーカーの将来性
日本では高齢化によって、医療や福祉を利用する方が増える見込みにあるため、今後ますます需要が増していくでしょう。医療や福祉だけでなく、教育の場でもソーシャルワーカーは必要とされています。活躍の場が広がっているソーシャルワーカーは、将来性のある職種です。
ソーシャルワーカーに向いている人
相手に寄り添って話を聞ける人や、専門性を磨ける人、社会貢献がしたい人は、ソーシャルワーカーに向いている可能性が高いでしょう。「自分がソーシャルワーカーに向いているのか知りたい」という方は、以下で適性があるかチェックしてみてくださいね。
相手の話をじっくり聞ける人
ソーシャルワーカーの仕事は、相談者の話を聞き、困っていることや悩んでいることを把握するところから始まります。そのため、ソーシャルワーカーには、どのような相談者の方に対しても、相手の話に耳を傾ける姿勢が必要です。
相談者は、年齢や性別、生活状況などがそれぞれ異なるため、不安や悩みもさまざま。相手の立場や気持ちに寄り添い、一人ひとりに合った支援ができる人は、ソーシャルワーカーに向いているでしょう。
新しい専門知識を学習し続けられる人
ソーシャルワーカーが受ける相談は、時代の流れや社会情勢によって傾向が変わります。特に、法律や社会保障制度は改正される場合があるため、支援に必要な知識は常にアップデートしなくてはなりません。
新しい法制度を学んだり、ソーシャルワーカーが集う勉強会に参加したりするなど、業務外でも常に情報を吸収する姿勢が求められます。相談者の抱えるリアルな課題を把握し、社会資源を活用したサポートを実践するためには、学習の継続が欠かせません。
社会のために働きたい気持ちがある人
ソーシャルワーカーは、介護や児童虐待、学校でのいじめなど、社会のあらゆる問題を解決するためにアプローチします。相談者一人ひとりへの支援は、ひいては社会全体を良くすることにもつながるでしょう。「相談者が笑顔で暮らせるようサポートしたい」「仕事を通して社会貢献をしたい」という気持ちがあると、モチベーションを保って働けます。
状況に応じて柔軟に対応できる人
ソーシャルワーカーが対応する相談者の状況は、一人ひとり異なります。マニュアルどおりに進められる業務は少なくはなく、イレギュラーが発生することも。相談者の状況を冷静に見極め、その人に合った援助を行わなければなりません。状況に応じて柔軟に対応できる人は、そのスキルを活かして活躍できるでしょう。
ソーシャルワーカーになる方法に関するよくある質問
ここでは、ソーシャルワーカーになる方法に関するよくある質問に回答します。「ソーシャルワーカーになるのは大変なの?」と気になっている方は、ぜひ参考にしてください。
ソーシャルワーカーの資格は難易度が高いですか?
ソーシャルワーカーの要件になることが多い「社会福祉士」と「精神保健福祉士」の資格は、両方とも国家資格です。これらの国家試験を受験するには、学歴や相談援助の実務経験などが必要になるため、受験のハードルは少し高いかもしれません。また、社会福祉士国家試験の合格率は4割程度と低めなので、社会福祉士は福祉業界のなかで難易度が高めの資格といえます。社会福祉士や精神保健福祉士の国家試験は、年に1回しかないので、受験の際はしっかり対策することが大切です。
国家試験の勉強方法は、「社会福祉士国家試験に合格するための勉強方法7選!独学でも取得できるの?」で解説しています。
ソーシャルワーカーは国家資格ですか?
ソーシャルワーカーは相談援助に携わる職種の総称で、ソーシャルワーカーという名前の資格はありません。ソーシャルワーカーの募集要件として指定されることが多い「社会福祉士」と「精神保健福祉士」は国家資格です。ソーシャルワーカーになるために国家資格は必須ではないものの、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を取得すれば、就職や仕事に活かせます。
高卒からソーシャルワーカーになれる?
高卒からソーシャルワーカーの仕事に就くことは可能ですが、無資格・未経験で採用されるのは難しいでしょう。ソーシャルワーカーとして採用されるには、社会福祉士の資格取得が効果的です。高卒から社会福祉士を目指すには、「4年生の福祉系大学で指定科目を履修する」「相談業務に関する実務を4年積んだうえで、短期養成施設に通う」などの方法があります。詳しくは、「最終学歴が高卒の場合」をご覧ください。
ソーシャルワーカーは資格なしからなれますか?
資格がなくてもソーシャルワーカーの業務に就くことは可能ですが、無資格で応募できる求人は非常に少ない傾向にあります。ソーシャルワーカーの仕事は、相談援助に関わる専門的な知識が求められるため、国家資格である社会福祉士や精神保健福祉士の資格があったほうが有利です。
「ソーシャルワーカーに必要な資格の取り方や難易度は?職種別の要件も解説!」では、ソーシャルワーカーの仕事に活かせる資格を紹介しているので、参考にしてみてください。
まとめ
ソーシャルワーカーとは、生活に課題を抱える方の相談に乗り、解決に向けた支援をする職種のことです。職場によって、ソーシャルワーカーの呼び方や資格要件は異なります。ソーシャルワーカーの具体例は、介護施設で働く生活相談員や、医療機関で働く医療ソーシャルワーカーなどです。
社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事などの資格があれば、ソーシャルワーカーへの就職や実務に活かせます。社会福祉士と精神保健福祉士は国家資格なので、取得するためには国家試験への合格が必要です。これらの国家試験には、学歴や実務経験などの要件が定められているため、取得には数年かかります。
また、社会福祉主事任用資格を取得するには、通信教育などで指定の科目を履修しなければいけません。社会福祉主事の教育課程の受講にも条件があることが多いので、取得したい方は事前に確認しておきましょう。
福祉業界でキャリアアップしたい方は、介護・福祉業界に特化した転職エージェントの「レバウェル介護(旧 きらケア)」をご利用ください。福祉業界に詳しいアドバイザーと一緒に、キャリアプランを考えてみましょう。「働きながら社会福祉士を取得できるの?」「介護福祉士でも生活相談員として働ける?」など、気になることを相談可能です。転職だけではなく複数の選択肢を検討して、あなたの希望に合った進路をご提案いたします。サービスは無料なので、「新しい仕事を始めてみたい」とお考えの方は、ぜひ活用してください。
働きながら資格を取る方法教えます
 生活相談員の介護求人一覧ページはこちら
生活相談員の介護求人一覧ページはこちら