Clik here to view.
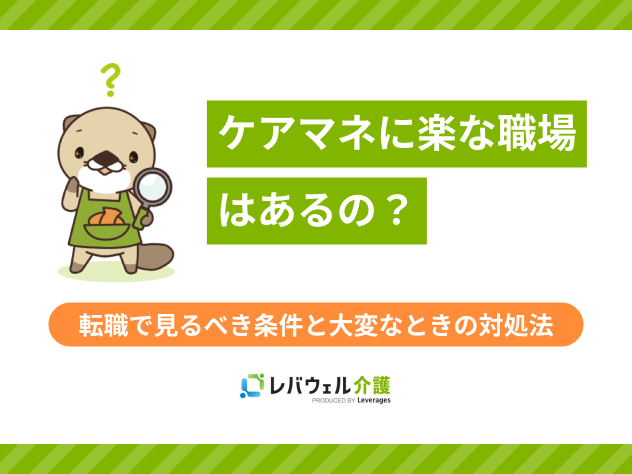
この記事のまとめ
- ケアマネの楽な職場を探すなら、雇用形態や職場の違いを理解することが大切
- ケアマネは、職場の人間関係や仕事量の多さなどを大変に感じる場合がある
- 仕事がつらいときは、課題を明確にして改善したり転職をしたりしてみよう
ケアマネジャーの仕事は、他職種との連携が多く、一定の大変さがあります。そのため、「専門知識を活かしつつ、過度なストレスや負担のない職場で働きたい」と思う方もいるかもしれません。働き方や職場を変えることで、今よりも仕事が楽になることもあります。この記事では、ケアマネが自分にとって楽な職場で働けるよう、つらいときの対処法と転職でみるべき条件などを解説します。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどんな仕事?業務内容や役割を解説!ケアマネに楽な職場はある?
ケアマネの職場で、一概に楽な職場といえるものはないかもしれません。しかし、雇用形態や勤務先によっては、比較的負担の少ない職場で働くことができるでしょう。
ケアマネの仕事が楽かどうかの感じ方は、人それぞれ。楽な職場を見つけるには、自分に合った職場を見つけることが大切です。
以下で、雇用形態と勤務先によるケアマネの働きやすさの違いについて説明するので、どのような働き方が自分に合いそうか確認してみてください。
Image may be NSFW.
Clik here to view. 介護支援専門員の求人一覧はこちら
介護支援専門員の求人一覧はこちら
ケアマネジャーの雇用形態別の働き方の違い
ケアマネジャーの雇用形態は、正規雇用の「正社員」のほか、「パート・アルバイト」「派遣社員」「契約社員」といった非正規雇用などがあります。
正社員
正社員のケアマネは、勤務時間や休日の自由度は低いものの、無期雇用で定年まで働ける安定感があります。また、職場によっては賞与が支給されることもあり、非正規雇用社員よりも効率よく稼げる点がメリットといえるでしょう。
非正規雇用社員(パート・アルバイト・派遣社員・契約社員)
「パート・アルバイト」「派遣社員」「契約社員」といった非正規雇用社員のケアマネは、正社員より勤務時間の融通が利いたり、残業が少なかったりします。そのため、プライベートを優先して働きたい人は、パート・アルバイトや派遣社員、契約社員のような非正規雇用のケアマネとしての働き方がおすすめです。
居宅ケアマネと施設ケアマネの違い
ケアマネは職場によって、それぞれ「居宅ケアマネ」と「施設ケアマネ」と呼ばれます。居宅ケアマネと施設ケアマネの違いは、職場や利用対象者、担当件数、働き方などです。
居宅ケアマネの特徴
居宅ケアマネの職場は、居宅介護支援事業所です。居宅ケアマネは自宅で暮らす方を対象にサービスを提供します。平均担当件数は35人程度。利用者さんの自宅を訪問するので移動時間が多い特徴があります。
居宅ケアマネは、施設ケアマネより担当者数が少ないので、一人ひとりの利用者さんにじっくり向き合ってケアプランを立てやすいようです。また、ケアマネ業務に専念できるので、介護業務と兼任せず働きたい人にとっては適した職場といえるでしょう。
施設ケアマネの特徴
施設ケアマネの職場は、特養や老健、グループホームなどの入居型介護施設などです。平均担当件数は100人程度。施設に入居している方がサービス対象なので、複数の利用者さんの様子をまとめて確認でき、移動時間がかからないのが特徴です。施設内でモニタリングなどのケアマネの業務が完結するので、利用者さんの自宅を一軒一軒訪れる必要がないことから、楽に感じるかもしれません。
▼関連記事
居宅ケアマネってどんな仕事?役割や施設ケアマネとの違い
施設ケアマネとは?役割の違いから求人の探し方まで詳しく解説!
今の職場に満足していますか?
ケアマネジャーが仕事で大変さを感じること
ケアマネジャーが仕事で大変さを感じることは、「職場の人間関係」や「仕事量の多さ」「自宅訪問の移動」「資格更新の負担」などです。
職場の人間関係
管理者や上司との相性が合わないと、衝突してしまい、職場の人間関係で悩んでしまうことがあります。パワハラなどが横行している場合、自分だけで解決するのは難しいかもしれません。
また、事業所と利用者さんの間で板挟みになることも。特に、理不尽なクレームに対応しなければならないときは、大変さを感じる可能性があるでしょう。ケアマネは、介護サービスと利用者さんを仲介する役割もあるので、お互いの意見が合わない場合はケアマネが間に入り調整する必要があります。
仕事量の多さ
ケアマネの仕事内容は、利用者さんの相談対応やケアプランの作成、要介護認定の代理申請、モニタリング、サービス担当者会議への参加など多岐にわたります。施設ケアマネで介護職を兼任する場合、ケアマネの仕事が後回しになることもあるようです。
ケアマネは、業務量の多さから慢性的な残業になることも。特に、介護給付費の請求のため、月末月初は多忙になる場合があります。
自宅訪問の移動
居宅ケアマネは、利用者さんの自宅を一軒一軒訪問するため、移動時間が発生します。そのため、何件も回る場合、移動時間に負担を感じることがあるようです。訪問スケジュールは自分で立てられますが、担当件数が多かったり、利用者さんの自宅同士が離れていたりすると、負担も大きくなるでしょう。
専門知識の勉強
ケアマネは最新の介護に関する知識を身につける必要があります。しかし、介護保険や制度の変化に対応するため、勉強し続けることに疲れてしまう人もいるようです。介護報酬は3年ごとに改定されるので、その都度、最新の知識を学ばなければいけません。また、利用者さんとの信頼関係を築くためにも、コミュニケーションの方法についても学ぶことが求められるでしょう。
資格更新の負担
介護支援専門員の資格は、5年ごとに更新する必要があります。研修を修了するには時間がかかるため、更新するのを億劫に感じる人もいるでしょう。
東京都福祉保健財団の「研修」によると、ケアマネジャーになってから1回目の更新研修にかかる時間は88時間です。2回目以降の更新研修は32時間と最初の更新研修より時間は短くなりますが、ケアマネとして働き続ける以上、資格の更新が必須になります。
詳しくは、「ケアマネの研修がしんどい…資格維持の費用と実態」の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
ほかにも、ケアマネが独立して自分で居宅介護支援事業所を開設した場合、集客に悩むこともあるようです。事業所を立ち上げたばかりは、運営が軌道に乗るまで大変なことも多いかもしれません。利用者さんとの信頼関係を築くことで集客につながるでしょう。
出典
東京都福祉保健財団ケアマネジャー専用サイト「研修」(2024年10月18日)
▼関連記事
ケアマネになれたけどノイローゼ寸前!限界を感じたときの解決法とは
ケアマネジャーの仕事がつらいときの対処法
ケアマネジャーの仕事がつらいときの対処法として、問題を改善するように行動したり、介護職員に戻ったりするといった方法があります。以下で、ケアマネの仕事がつらいときの対処法を解説しているので、お悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
悩みや課題を明確にして改善する
残業や業務量に悩んでいる場合は、業務のスケジュールを見直して効率化したり、業務量を上司に相談したりすると良いでしょう。自分一人でできる仕事には限りがあります。自分の限界を超えているのなら、仕事を一人でやろうとせず、上司や同僚に相談することで解決することもあるかもしれません。人に悩みを相談するだけで、気持ちが楽になることもあります。
職場の人間関係の悩みは、配置換えや社内間の異動などで解説できることもあるでしょう。どのような悩みや課題でも、一人で抱え込まないことが大切です。
介護職員に戻る
ケアマネの仕事がつらければ、介護職員として働くのも一つの手です。ケアマネの経験があれば、介護職員の仕事をする際に、新たな視点からケアを行うこともできます。
利用者さん宅への訪問や資格更新の負担からケアマネの仕事がきついと感じている方は、介護職員に戻ることで解決できるでしょう。
ケアマネの仕事のやりがいやメリットを確認する
ケアマネの仕事に対する想いを客観的に確認してみましょう。仕事で大変なことがあれば、「辞めたい…」と思ってしまうこともあるかもしれません。しかし、安易に退職するのではなく、ケアマネの仕事を目指したきっかけや仕事のやりがいを再確認してみてください。目的ややりがいを今一度確認することで、仕事へのモチベーションが上がるでしょう。
仕事とプライベートを分ける
ケアマネの仕事がつらいときは、仕事とプライベートを分けて、気持ちのオンオフを切り替えると良いでしょう。休日も仕事のことを考えてしまうと、しっかりと休息を取ることができません。休息が取れない状態が続くと疲労が蓄積し、よりストレスを感じやすくなってしまいます。休日は仕事のことを忘れ、心身ともにリラックスすることが大切です。趣味を楽しんだり美味しいものを食べたりするなど、自分らしく過ごすようにしましょう。
ほかの職場に転職を検討する
給与の低さや人間関係などの問題は、転職することで悩みを解決できる可能性があります。給与に関する悩みは、基本給だけではなく、手当や昇給制度など、長期的な視点で求人をチェックすることで転職後のギャップを減らせるでしょう。
ケアマネは介護の専門職として需要のある職種です。日本の高齢化は進んでいるので、ケアマネとして活躍できる職場も見つけやすいでしょう。
また、施設ケアマネが合わないときは居宅ケアマネへ、居宅ケアマネが合わないときは施設ケアマネへ転職するのも一つの方法です。
今の職場に満足していますか?
ケアマネが楽な職場に転職するために見るべき条件
ケアマネが楽な職場に転職するには、労働条件や働きやすさをチェックすることが重要です。ケアマネの転職を支援する現役のキャリアアドバイザーに転職時に見るべき条件を聞いたので、転職を考えている方は以下のポイントをチェックしてみましょう。
退職者数
退職者が多い場合、労働環境が悪い可能性があるので注意が必要です。もちろん、家庭の事情など職場の労働環境以外の理由で退職していることもあるので、あくまで参考程度にしましょう。退職者数は、厚生労働省の「介護事業所検索 介護サービス情報公表システム」で確認できます。
出典
厚生労働省「介護事業所検索 介護サービス情報公表システム」(2024年10月18日)
残業時間
求人に残業時間が記載されている場合は、しっかりと確認しましょう。また、記載がない場合は面接で聞いてみてください。なお、残業時間の平均は10時間程度といわれています。極端に残業時間が多い施設や、質問してもはぐらかす施設は、仕事量に対して職員が不足している可能性があるので注意しましょう。
訪問の範囲と手段
居宅ケアマネとして働く方は、訪問の範囲と手段を確認しておきましょう。居宅介護支援事業所の場合、Webサイトに対応エリアを記載していることがあります。また、対応エリアや訪問手段については面接時に説明されることが多いようです。疑問点がある方は、面接で詳しく聞いておくと良いでしょう。
休日条件
休日の条件が自分の希望条件に合うか確認します。「完全週休2日制」「土日休み」「平日休み」など、休みの取り方や日数の希望は人それぞれ。希望した休みが取れるか、面接で聞いておきましょう。
また、居宅介護支援事業所の求人には、休日120日以上の求人も多いようです。年間休日120日以上の施設は、完全週休2日制かつ祝日も休める計算になります。
給与条件
転職を成功させるうえで、給与条件が希望条件に合うか確認することも重要です。給与条件を確認する際は、地域の給与相場をチェックして比較しましょう。相場に対して安過ぎるのは良くありませんが、高過ぎるのも注意が必要です。給与が高過ぎる場合、労働環境に問題がある可能性も。離職率が高いため、高給与で職員を募集しているのかもしれません。
また、東京で働くケアマネの場合、居住支援金が手当として支給される可能性があります。支給の有無は、事業所によって異なるので確認しましょう。
出典
東京都福祉局「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業」(2024年10月18日)
インセンティブがある職場も
インセンティブがある職場の場合、一定の基準を超えるとインセンティブがもらえることがあります。たとえば、「担当35件以上は1件につき△円給与がアップする」など、働いた分だけ給与アップするので、仕事のモチベーションも上がるでしょう。
教育体制
資格取得支援や研修会・勉強会を実施しているのかチェックしましょう。ケアマネは介護の知識やスキルをアップデートしていく必要があります。前述したように、資格の更新研修を定期的に受ける必要があるので、職場でサポートしてもらえると楽になるかもしれません。
職場の方針や理念
自分の考えと施設の方針・理念が違うとストレスを感じてしんどくなってしまいます。職場の方針や理念を確認して、自分に合う職場を探すことが大切です。ケアマネは、利用者さんと介護施設との調整などをします。職場の方針や理念と考えが異なる場合、よりストレスを感じやすくなってしまうこともあるでしょう。
職場の雰囲気
面接で職場の雰囲気を確認することも大切です。また、面接官が上司になる可能性もあるので、相性が合うか確認しておくと良いでしょう。
介護施設で働く施設ケアマネであれば、職員や利用者さんの表情もチェックしておきます。笑顔があり、明るい雰囲気の職場であれば、人間関係が良好かもしれません。ほかにも、清掃が行き届いている施設であれば、人員配置に余裕がある可能性があります。
退職者数や残業時間など施設や事業所に直接聞きにくいことは、転職エージェントを利用して聞くのも効果的です。
▼関連記事
ケアマネジャーの働き方を解説!勤務時間は長い?休める?仕事内容も紹介
ケアマネは今後どうなる?AIの活用で不要になるの?将来性や需要を解説!
今の職場に満足していますか?
新人ケアマネジャーにとって楽な職場は?
ここでは、新人ケアマネジャーによって楽な職場を紹介します。「ケアマネへの転職を検討しているけど大変そうで不安…」とお悩みの方は、ぜひご一読ください。
ケアマネの人数が多い職場
新人で未経験のケアマネの場合、ケアマネが複数名在籍している職場を選ぶと負担を軽減できるでしょう。ケアマネを1人しか配置しておらず、ほかにケアマネ業務をサポートできる人がいない施設だと、教育が不十分になる可能性や気軽に業務の相談ができず困ることがあるかもしれません。
「新人で仕事が何も分からないかも…」と不安な人は、厚生労働省の「介護事業所検索 介護サービス情報公表システム」が活用できるので、職員の人数を事前に確認してみましょう。
出典
厚生労働省「介護事業所検索 介護サービス情報公表システム」(2024年10月18日)
人間関係が良い職場
ケアマネの教育は、基本的に現場での実務を通して行われます。新人ケアマネは、分からないことを周りの先輩ケアマネに質問したり相談したりしながら業務を進めていくので、仕事を覚えるためにも人間関係の良好さは大切です。面接時に未経験である自分の受け入れに前向きな雰囲気を感じられる職場は安心できるでしょう。
しかし、職場の人間関係は外からは分かりにくいものです。職場の人間関係が良好かどうかは、挨拶などのコミュニケーションがしっかりと取れているか、職員の年齢層に偏りがないかなどをチェックしましょう。
▼関連記事
新人ケアマネジャーが「何もわからない」と悩む理由は?対処法を解説
ケアマネジャーとして働くメリット
ケアマネジャーとして働くメリットは、収入アップが見込めることや経験が介護業界内で転職する際に役立つことなどです。以下で働くメリットを解説しているので、ぜひご一読ください。
ケアプランを通じて利用者さんを支援できる
ケアマネジャーは、ケアプランの作成などを通じて利用者さんの生活のサポートができます。作成したケアプランをもとに、利用者さんの健康状態が改善したり、要介護度が下がったりすることにやりがいを感じられるでしょう。また、利用者さんやご家族から直接感謝の言葉をかけられる機会があれば、仕事へのモチベーションも高まるかもしれません。
収入アップが見込める
ケアマネは、介護業界の中でも給与が高い傾向があるため、介護職員からステップアップすることで高給与が見込める可能性があります。
以下の表では、厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.119)」をもとに、介護職の職種別の平均給与をまとめました。
| 職種 | 平均給与 |
| 介護職員 | 317,540円 |
| 看護職員 | 373,750円 |
| 生活相談員・支援相談員 | 342,330円 |
| 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または機能訓練指導員 | 354,770円 |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 361,770円 |
参照:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.119)」
ケアマネと介護職員の平均給与の差は約4万円です。平均給与をもとに算出すると、年収では介護職員からケアマネになることで53万円ほど収入がアップする可能性があります。なお、給与は施設によって異なるので、あくまで参考としてご覧ください。
出典
厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2024年10月18日)
Image may be NSFW.
Clik here to view. 高給与の求人一覧はこちら
高給与の求人一覧はこちら
ケアマネの経験が転職で役立つ
ケアマネは介護保険や介護サービスなどの専門的な介護知識や介護スキルが身についています。そのため、ケアマネ経験者は介護業界で即戦力としての活躍が期待され、転職する際に選考で有利になることもあるでしょう。
また、ケアマネは安定した需要があり、希望に合った求人も見つけやすいかもしれません。
ライフワークバランスが取りやすい
居宅介護支援事業所のケアマネは、基本的に日勤のみなのでプライベートと仕事を両立しやすいでしょう。介護職との兼任でなければ夜勤に入ることもありません。その分、生活サイクルが安定するので、身体への負担も少ないといえます。
また、利用者さん宅への訪問スケジュールを自分で調整できるので、子どもの学校行事などにも参加しやすく、プライベートも充実できるでしょう。
Image may be NSFW.
Clik here to view. 日勤のみの求人一覧はこちら
日勤のみの求人一覧はこちら
ケアマネについてよくある質問
ここでは、ケアマネについてよくある質問に回答します。「ケアマネの仕事に興味はあるけど大変そう…」とお悩みの方は、ぜひチェックしてみてください。
50代未経験でケアマネになれる?
「年齢や未経験であることが気になってしまう…」という人もいるかもしれませんが、50代未経験の方もケアマネジャーになれます。ケアマネは40~50代が多数活躍しており、60代のスタッフも少なくありません。そのため、あまり年齢を気にする必要はないでしょう。未経験でケアマネに挑戦する場合、未経験者歓迎の施設や教育に力を入れている施設に応募するのがおすすめです。
詳しくは、「ケアマネ未経験からの転職は厳しいの?活かせるスキルや採用されるコツ」の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
ケアマネに向かない人はどんな人ですか?
ケアマネに向かない人は、こだわりが強い人や臨機応変な対応が苦手な人、利用者さんの視点に立って気持ちに寄り添えない人などです。ケアマネは利用者さんの悩みを解決するために、介護サービスを紹介したり、関連機関との調整をします。利用者さんを第一に考えて対応することが求められるでしょう。
まとめ
雇用形態や職場の選び方によっては、ケアマネとして働くのに楽な職場が見つかるかもしれません。楽な職場といっても、実際に楽だと感じる感覚は人それぞれ。パートやアルバイト、派遣社員などの非正規雇用の場合は、勤務時間の調整がしやすく、残業が少ない傾向にあるようです。居宅ケアマネと施設ケアマネは、訪問先や担当件数などに違いがあるので、自分に合った職場を選ぶことが大切といえます。
ケアマネの仕事がつらいと感じたときは、「悩みや課題を明確にして改善する」「介護職員に戻る」「やりがいやメリットを確認する」「転職を検討する」などの対処法を試してみましょう。楽な職場に転職するには、退職者数や残業時間、訪問の範囲と手段、給与条件などの条件を確認することが重要です。
「楽な職場で働きたい」と考えている方は、「レバウェル介護(旧 きらケア)」へご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した転職エージェントです。残業時間や具体的な仕事内容も転職エージェントがお伝えします。専任のアドバイザーが転職をサポートするので、「自分に合っている職場が分からない」とお悩みの方はお気軽にご相談ください。
今の職場に満足していますか?