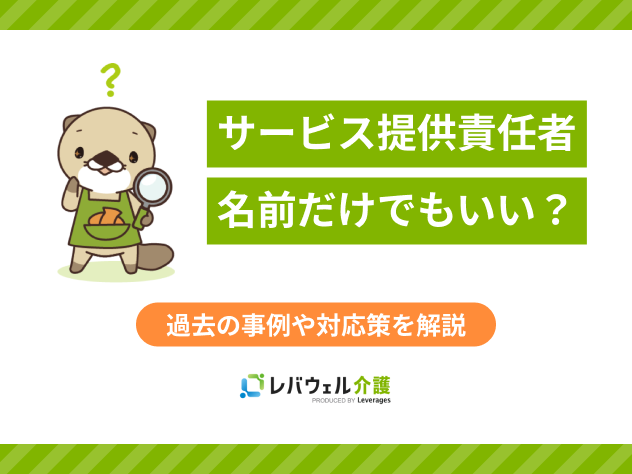
この記事のまとめ
- サービス提供責任者の名前だけを貸し借りする行為は違法
- サービス提供責任者の名前だけを貸してほしいと頼まれた場合は、毅然と断る
- サービス提供責任者の名前だけを貸し借りせず、正直に現状を報告しよう
「サービス提供責任者として名前だけ貸してほしい」と頼まれ、対応に困っている方もいるでしょう。名義の貸し借りは違法で、名前を貸した場合は処分を受けるリスクがあります。この記事では、名前だけを貸し借りするリスクや、名義貸しを頼まれたときの対応方法を解説。人員確保の方法にも言及しているので、サービス提供責任者の名義貸しについて知りたい方は、参考にしてみてください。
サービス提供責任者が名前だけを貸し借りするのは違法!
サービス提供責任者が事業所に名義だけを貸したり、事業所が名義だけを借りたりするのは、違法行為です。名義を借りて事業所指定を受けた場合、人員基準に違反するため、行政処分の対象となります。民事責任や刑事責任、行政責任を問われる可能性があり、事業所もサービス提供責任者も大きなリスクを背負うことになるでしょう。
しかし、訪問介護事業所では、過去に名義の貸し借りが発生してしまったことも。人員基準違反の背景には、サービス提供責任者として働ける有資格者を確保できないという理由があるようです。
ここでは、サービス提供責任者の名義だけを貸し借りした場合のリスクを解説します。サービス提供責任者や訪問介護事業所の運営に携わる方は、運営基準に違反したらどうなるのかを確認しておきましょう。
サービス提供責任者が名前だけを貸すリスク
実際には従事しない方が、サービス提供者責任者として名前だけを貸してしまうと、損害賠償を請求されたり、介護福祉士の資格を失ったりするリスクがあります。
名義貸しをすると、介護報酬の不正請求に加担したと判断されるリスクがあるでしょう。訪問介護事業所が、名義を借りて人員基準を満たし、介護報酬を請求することは、詐欺罪に該当するようです。名義を貸したサービス提供責任者は、不正請求への関与の程度や悪質性などによって、共犯やほう助とみなされる可能性があります。
また、サービス管理責任者が名前だけを貸すと、キャリアに傷がつくリスクも。社会福祉士及び介護福祉士法第45条では、介護福祉士の義務として「信用失墜行為の禁止」が定められています。名義貸しによって罪を問われ、介護福祉士としての信用失墜行為を行ったと判断された場合、資格登録の取り消しか、名称の使用停止命令を受ける可能性があるでしょう。
安易に名義を貸してしまうと、さまざまな責任を負うリスクが生じるので、誰かに頼まれても、サービス管理責任者として名前だけを貸してはいけません。
出典
e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(2024年10月10日)
e-Gov法令検索「社会福祉士及び介護福祉士法」(2024年10月10日)
▼関連記事
社会福祉士及び介護福祉士法とは?何が書いてあるのかわかりやすく解説!
訪問介護事業所が名前だけを借りるリスク
訪問介護事業所がサービス提供責任者から名前だけを借りた場合、以下のような行政指導や行政処分を受けるリスクがあります。
- 実地指導
- 監査
- 改善勧告・改善命令
- 事業所指定の効力一部停止
- 事業所指定の効力全部停止
- 指定の取り消し
実地指導や監査、関係者聴取を通して、名義貸しなどの不正が発覚した場合、行政処分が検討されます。行政処分を受けると、地方自治体のWebサイトなどに事業所の名称や処分内容が公示され、社会的なペナルティを受けることになるでしょう。
名義を借りて人員基準を満たし、事業所指定を受けた場合は、「不正の手段による指定」に該当します。介護保険法における行政処分の対象となるため、基本となる処分は「指定の効力全部停止」です。継続的に名義を借りている場合などは、厳重な処分が下される可能性が高いでしょう。
事業所指定を取り消されると、介護保険事業者として事業所を運営できません。つまり、介護サービスを提供できず、国民健康保険団体(自治体)から介護報酬を受け取れないため、事業所の閉鎖を余儀なくされるでしょう。さらに、事業所指定の取り消し以降5年間は、介護サービス事業者の指定を受けられなくなります。
指定の効力停止を受けると、期間を定めて介護サービスの提供に制限をかけるとともに、介護報酬の請求も停止になるようです。そのため、指定の効力全部停止となれば、休業せざるを得ないため、事業所の存続そのものが危ぶまれるでしょう。
また、人員配置基準に反すると知りながら指定の申請をすると、文書の偽造により刑事罰を受ける可能性も。虚偽の申請により、介護報酬を請求し受領すると、詐欺罪に抵触することも考えられます。訪問介護事業所の運営にあたって、サービス提供責任者が見つからないからといって、名義だけを借りてしまう行為は決して許されません。
出典
厚生労働省「介護保険最新情報掲載ページ」(2024年10月10日)
大阪府吹田市の事例
奈良県の「都道府県指定取消事案一覧(p.15)」では、訪問介護事業所の指定取消処分の事案が公開されています。大阪府吹田市のケースは、下記のとおりです。
(1)不正の手段による指定(法第77条第1項第9号及び法第115条の9第1項第8号に該当)
引用:奈良県「都道府県指定取消事案一覧(p.15)」
訪問介護及び介護予防訪問介護の指定申請において、吹田市外にある当該法人の事務所に出勤し、同法人が運営する別の事業の業務に従事する者を、指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所に常時勤務し、専らその業務に従事する管理者兼サービス提供責任者に配置するものとして申請し、不正の手段により指定を受けた。
(2)虚偽の報告(法第77条第1項第7号及び法第115条の9第1項第6号に該当)
法第76条及び第115条の7の規定に基づき実施した監査において、平成28年11月30日まで管理者兼サービス提供責任者であった者が、指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所に出勤しているかのように、虚偽の出勤簿を作成し、これを提示した。
大阪府吹田市の事例では、すでに別の事業の業務に従事している職員を、訪問介護事業所の常勤のサービス提供責任者・管理者として申請し、不正に事業所指定を受けていました。
サービス提供責任者が常勤しているかのように虚偽の出勤簿を作成したことから、悪質性が高いと判断され、指定取消という重い処分が下されたようです。
出典
奈良県「都道府県指定取消事案一覧」(2024年10月10日)
長崎県の事例
同資料(p.16)によると、長崎県の訪問介護事業所における指定取消処分の事例は、下記のとおりです。
(1)平成27年9月1日から平成27年11月30日まで、常勤かつ専従のサービス提供責任者を配置していなかった。【介護保険法第77条第1項第3号及び第115条の9第1項第2号に該当】
引用:奈良県「都道府県指定取消事案一覧(p.16)」
(2)平成27年9月1日から平成27年11月30日まで、訪問介護計画が作成されていない、訪問介護員等の業務の実施状況が把握されていないなど、サービス提供責任者の業務が行われていなかった。【介護保険法第77条第1項第4号及び第115条の9第1項第3号に該当】
(3)平成27年7月25日付け指定申請書において虚偽の記載があり、不正の手段により介護保険法第41条及び第53条の規定に基づく介護保険の指定事業者の指定を受けた。【介護保険法第77条第1項第9号及び第115条の9第1項第8号に該当】
(4)介護保険法第75条に基づく変更の届出において、虚偽の内容による届出を行った。 【介護保険法第77条第1項第11号及び第115条の9第1項第10号に該当】
長崎県の事例では、虚偽の内容を申請することにより、常勤のサービス提供責任者を配置しないまま不正に事業所指定を受けていました。
サービス提供責任者を配置していないため、訪問介護計画書の作成をはじめ、ホームヘルパーの業務把握など、さまざまな調整・管理業務が行えなかったようです。必要なサービスが提供されず、訪問介護の利用者さんに不利益が生じたといった理由から、指定取消が行われたと考えられます。
出典
奈良県「都道府県指定取消事案一覧」(2024年10月10日)
青森県の事例
青森県の「介護サービスの提供における不適正事例について(p.5)」によると、青森県における訪問介護事業所の指定の取消処分の事例は、下記のとおりです。
指定更新申請時に、退職している職員を配置していると記載し、指定を受けた。(不正の手段による指定)
引用:青森県「介護サービスの提供における不適正事例について(p.5)」
更新後、人員基準違反と知りながら、サービス提供責任者を配置せず、訪問介護員等の人員が最低基準の常勤換算2.5人以上を満たさなかった。(人員基準違反)
人員基準違反と知りながら、介護報酬を請求し、受領した。(不正請求)
青森県の事例では、すでに退職している職員の名義を利用して事業者指定を受けていました。訪問介護事業所が、名義人の同意を得ず、勝手に名前を借りて虚偽の申請をした場合、損害賠償といった責任はすべて事業所が負うことになります。
出典
青森県「介護サービスの提供における不適正事例について」(2024年10月10日)
登録は1分で終わります!
アドバイザーに相談する(無料)サービス提供責任者が名義貸しを頼まれたときの対応方法
どのような事情があったとしても、名義貸しを頼まれたら必ず断りましょう。名義を借りなければならないという時点で、不都合な事情が隠れていることは明らかです。名義の貸し借りを行うと、双方に大きなリスクが生じると同時に、利用者さんに不利益を被ってしまうおそれもあります。そのため、毅然とした態度で断ることが大切です。
また、自治体の介護保険の担当課に相談する方法もあります。可能であれば、名義を借りようとしている方にも声をかけてみると良いでしょう。自治体に相談することで、具体的な助言を得られたり、解決策が見つかったりする可能性があります。
もしも、勝手に名義を使われていることが発覚し、指摘しても対応してもらえない場合は、弁護士への相談も視野に入れてみてください。
訪問介護事業所にサービス提供責任者が新たに必要になる状況
サービス提供責任者は、訪問介護事業所を運営するために必要不可欠な人材です。事業所を新規に開設するときや、既存のサービス提供責任者に欠員が生じた場合は、配置基準を満たせるよう、人員を確保したり利用者数を調整したりする必要があります。
訪問介護事業所を開設するとき
訪問介護事業所を開設する際は、指定申請書を提出する段階で、サービス提供責任者を決めておく必要があります。そのため、事業所の開設予定日から逆算し、できるだけ早く人員確保に取りかかりましょう。
都道府県ごとに申請手順に違いはあるものの、基本的に事前相談、指定申請書の提出、審査という流れで介護事業所の指定を受けます。介護事業所の立ち上げには、事業計画書の作成や資金の調達、物件探しなど、事業所指定の申請以外にも多くの手続きが必要です。そのため、人材の確保は余裕を持って取り組みましょう。
サービス提供責任者に欠員が出たとき
サービス提供責任者が退職するなどの理由で欠員が出てしまう場合は、引き継ぎが滞りなく済むよう、早めに人員を募りましょう。サービス提供責任者を変更する場合は、自治体の福祉部に対して、変更から10日以内に変更届出書の提出が必要です。欠員が出ることが判明した時点で、変更手続きの指示を自治体に仰ぐと、スムーズに対応が進むでしょう。
サービス提供責任者の人員配置の基準
サービス提供責任者は、利用者さん40人に対して1人以上配置する必要があり、なおかつ専従職員でなければなりません。常勤の2分の1以上勤務する非常勤のサービス提供者も、時間数で換算して職員数に含められるため、柔軟な人員配置が可能です。
また、訪問介護事業所が以下の要件をすべて満たす場合、利用者さん50人につきサービス提供責任者1人の配置で運営できます。
- 常勤のサービス提供責任者を3人以上配置している
- サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している
- サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている
常勤のサービス提供者を3人以上配置するといった要件を満たしていれば、サービス提供責任者1人で利用者さん50人まで担当できます。利用者さんの人数に対してサービス提供責任者が足りないときは、上記の要件を満たせないか検討してみるのも良いでしょう。
出典
東京都福祉局「訪問介護(新規に指定を受けたい方へ)」(2024年10月10日)
▼関連記事
サービス提供責任者(サ責)とはどんな職種?仕事内容や必要な資格、お給料
事業所がサービス提供責任者を確保できない場合の対処法
職員の退職などにより、訪問介護事業所が人員配置基準を満たせない場合は、速やかに自治体の介護保険の担当課に報告しましょう。自治体にとって、訪問介護事業所は地域の介護福祉を支える大切な存在です。事業所を存続できるようにアドバイスや一時的な処置を考えてくれる可能性があるので、必ず隠さず報告しましょう。
サービス提供責任者に変更が生じた時点で、担当課に対してサービス提供責任者の変更届書を提出する必要があるほか、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」などの準備も必要です。自治体ごとに事務手続きに違いがあるため、担当課の窓口で指示を仰ぎましょう。
訪問介護事業所がサービス提供責任者を確保する方法
サービス提供責任者を確保するために押さえておくべきポイントとして、「給料や職場環境を改善する」「研修や支援制度を充実させる」の2点が挙げられます。事業所において改善できるところはないか、確認してみましょう。
給料や職場環境を改善する
給料アップや職場環境の改善を行うことで、人材確保や離職防止につながる可能性があります。
公益財団法人介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査:労働者調査(p.66)」によると、働くうえでの不満として「人手が足りない」と答えたサービス提供者が63.5%で最多。「仕事内容のわりに賃金が低い」は 34.0%と、2番目に多い回答でした(複数回答可)。
職員確保のためには、処遇改善加算を取得して処遇改善手当を支給したり、資格手当を厚くしたりするなど、前向きに給料アップに取り組み、労働条件の向上を図る必要があります。
また、同資料(p.28)の、介護関係の仕事を辞めた理由として、「職場の人間関係に問題があったため」と答えたサービス提供者は 34.3%と最も多い結果でした。訪問介護事業所で長期的に働いてもらうためには、快適な職場環境を整備することも重要です。
相談を受け付けたり、トラブルを仲介したりするなどして、職員同士や利用者さんとの人間関係にも目を配るようにしましょう。
出典
公益財団法人 介護労働安定センター「介護労働実態調査」(2024年10月10日)
研修や支援体制を充実させる
サービス提供責任者の確保・定着のためには、事業所の教育体制を充実させることも大切です。たとえば、ホームヘルパーとして勤務している職員が、介護福祉士実務者研修を取得すれば、サービス提供責任者の資格要件を満たせます。資格取得支援制度があると、キャリアの選択肢が広がるため、職員のメリットも大きいでしょう。
また、初めてサービス提供責任者として働く職員を支援するために、気軽に相談できる体制を整えることも重要です。訪問介護サービスの管理業務やマネジメント業務に、経験やノウハウがないまま取り組むのは難しいといえます。独り立ちできるまで、疑問点や不安を共有できる体制であれば、腰を据えて業務に邁進できるでしょう。
そのほか、評価制度を導入したり、昇給・昇格基準を可視化したりするなど、職員のモチベーションに働きかける取り組みも効果的です。
サービス提供責任者に関してよくある質問
ここでは、サービス提供責任者に関するよくある質問に回答します。サービス提供責任者の必須知識や人員配置について知りたい方はご覧ください。
サービス提供責任者の必須知識とは?
サービス提供責任者には、介護全般の専門知識やマネジメントに関する知識が求められます。担当する主な業務は、訪問介護計画書や介護手順書の作成といった介護サービスの管理業務と、ホームヘルパーの教育や勤怠管理などのマネジメント業務です。たとえば、訪問介護計画書を作成する際は、疾病や障がい、身体介護に関する正しい知識がなければ、利用者さんの状態や提供すべきサービスを判断できません。
サービス提供責任者の必須知識については、「サービス提供責任者の必須知識を解説!訪問介護のマネジメントに必要なこと」の記事で解説しているので、あわせてご確認ください。
サービス提供責任者は掛け持ちしても問題ない?
サービス提供責任者は、訪問介護事業所を掛け持ちしても問題ありません。ただし、配置人数としてカウントするには、常勤職員の勤務時間の2分の1以上勤務する必要があります。そのため、サービス提供責任者を掛け持ちできるのは、2事業所までとなる場合が多いでしょう。
まとめ
サービス提供責任者が名前だけ貸し借りするのは違法です。名義を貸した側も借りた側も、大きなリスクを背負う可能性があるので、もしも名義貸しを打診されても必ず断りましょう。
訪問介護事業所を開設するときや欠員が出たときなど、新たにサービス提供責任者を確保しなければならないときは、できる限り早く対応する必要があります。給料や職場環境を改善したり、研修や評価制度を充実させたりして、人材確保の対策を講じてみましょう。
もしも、サービス提供責任者が見つからず、人員配置基準を満たせない場合は、自治体の介護保険の担当課に報告してください。相談することで、解決策が見つかる可能性があります。
「サービス提供責任者として働きたいから、応募先の事業所について事前に詳しく知りたい」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)の利用をご検討ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界を専門とする転職エージェントです。
在籍職員の人数や職種、担当する利用者さんの人数など、個人では調べにくい情報を事前にリサーチ。介護業界に精通したキャリアアドバイザーが、あなたのご希望にマッチする訪問介護事業所をご紹介します。サービスはすべて無料なので、まずはお気軽にご相談ください。
登録は1分で終わります!
アドバイザーに相談する(無料)