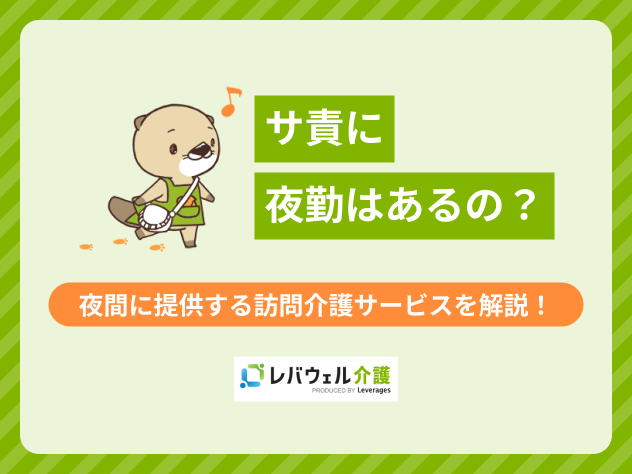
この記事のまとめ
- サ責は夜勤あり・日勤のみ両方の職場があるので、自分に合った働き方が可能
- 夜間対応型や定期巡回の事業所で働く場合、サ責も夜勤を行う可能性高い
- サ責が夜勤で担当する特徴的な仕事は、オペレーター業務や随時訪問
「サ責は日勤で働くイメージだけど、夜勤はあるの?」と気になる方もいるでしょう。多くのサ責は日勤のみで働いていますが、夜間にサービスを提供する訪問介護事業所では、夜勤を行う場合があります。この記事では、サ責の夜勤実態や、夜勤が発生する可能性のある介護サービスの種類、業務内容を解説。夜勤のメリットやデメリットにも言及します。サ責の夜勤について知りたい方は、ぜひご覧ください。
サービス提供責任者(サ責)とはどんな職種?仕事内容や必要な資格、お給料サ責には夜勤がある?
サ責(サービス提供責任者)は、夜勤あり・日勤のみ両方の働き方が可能です。日中のみ(主に8時~18時ごろ)にサービスを提供している訪問介護支援事業所に勤務する場合、基本的に夜勤はないでしょう。
しかし、「夜間対応型訪問介護」や「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に該当するサービスを提供する事業所では、サ責が夜勤を行う可能性があります。
夜勤があるサ責の割合
公益財団法人介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書(p.55)」によると、サ責の深夜勤務は「ある」が14.1%、「ない」が82.7%という結果でした。少数ではあるものの、一部のサ責が夜勤をしていることが分かります。
サ責の夜勤回数
同資料(p.56)によると、夜勤がある訪問介護事業所における、サ責とホームヘルパーの1ヶ月の深夜勤務の回数は、以下のとおりです。
| 職種 | 1~2回 | 3~4回 | 5~6回 | 7~8回 | 9~10回 | 11回以上 |
| サービス提供責任者 | 25.2% | 20.7% | 24.0% | 8.5% | 4.5% | 2.4% |
| 訪問介護員 | 13.6% | 24.0% | 27.1% | 12.8% | 3.3% | 5.4% |
参考:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書(p.56)」
サ責の1ヶ月の夜勤回数は平均4.5回、ホームヘルパーは平均5.4回でした。内訳に違いはあるものの、サ責が夜勤を行う場合、ホームヘルパーと大差ない回数だと分かります。
サ責の夜勤における仮眠・休憩の状況
同資料(p.58)を見ると、サ責が深夜勤務を行う際の仮眠や休憩の状況は、「十分とれる」が23.2%、「ある程度とれる」が48.8%、「とれない」が19.5%という結果でした。サ責は常に訪問に対応するわけではないこともあり、休憩を取れている割合が高いようです。
出典
公益財団法人介護労働安定センター「介護労働実態調査」(2024年10月16日)
今の職場に満足していますか?
夜間の支援に対応する訪問介護サービスの種類とは?
ここでは、訪問介護サービスのなかで、サ責が夜勤を行う可能性が高い、「夜間対応型訪問介護」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」について解説します。
夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護とは、夜間帯に利用者さんの自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの介護を行うサービスを指します。午後10時~午前6時までを含む時間帯に提供するのが特徴で、午前8時~午後6時までの時間は対象外です。
決まった時間に利用者さんの自宅へ訪問する「定期巡回」と、利用者さんから通報を受けて必要に応じて訪問する「随時対応」を一体的に提供します。また、利用者さんの連絡に対応するオペレーターサービスとして、相談対応をしたり、訪問の必要性を判断したりするのも、仕事内容です。なお、「夜間対応型訪問介護」は、「訪問介護」と併用できます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問介護や訪問看護を24時間体制で利用できるサービスです。「定期巡回」「随時対応」「オペレーションサービス」を提供しています。ホームヘルパーが身体介護や生活援助を行うほか、医療ケアの必要性があれば、訪問看護のサービスも一体的に提供するのが特徴です。
なお、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を利用する場合は、「訪問介護」「訪問看護」のサービスを介護保険を使って利用することはできません。
出典
厚生労働省「第228回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2024年10月16日)
サ責の夜勤の仕事内容は?
サ責が担当する主な業務は、介護サービスの管理や訪問介護です。また、夜勤の特徴的な仕事として、利用者さんからの通報に対応するオペレーター業務があります。
オペレーター業務
利用者さんからの通報を受け、アドバイスをしたり、必要に応じてホームヘルパーを派遣したりして、悩みや困りごとに対処するのが、オペレーター業務です。オペレーターを担当するには、介護福祉士や看護師などの資格もしくは、訪問介護のサービス提供責任者として1年以上従事した経験が求められます。
出典
厚生労働省「第228回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2024年10月16日)
サ責業務
サ責の主な業務は、以下のとおりです。
- 訪問介護サービスの受付・案内
- 利用者さんやご家族との面談
- サービス担当者会議への参加
- 訪問介護計画書・援助手順書の作成
- 初回訪問
- ホームヘルパーの同行訪問
- 利用者さんのモニタリング
- ホームヘルパーの管理・マネジメント
サ責は、訪問介護を希望する方からの問い合わせから、実際にサービスを提供するまでの過程に携わります。利用者さんやご家族との面談や、関係者間で情報共有や課題の検討を行う「サービス担当者会議」への出席、訪問介護計画書の作成、援助手順書の作成など、業務はさまざまです。
ホームヘルパーに同行して手順を指導したり、利用者さんの状態をケアマネジャーに共有したりと、訪問介護サービスの責任者として中心的な役割を担います。また、利用者さんの介護に直接当たるホームヘルパーの勤怠管理や業務サポートも欠かせません。
なお、利用者さんやご家族との面談、サービス担当者会議などは、日勤の際に対応する場合が多いようです。
▼関連記事
サービス提供責任者の必須知識を解説!訪問介護のマネジメントに必要なこと
訪問介護業務
サ責がホームヘルパーを兼任する場合は、訪問介護業務も担当します。夜勤の特徴的な業務としては、随時訪問が挙げられるでしょう。
訪問介護では、生活援助として夕食・朝食の調理や配膳、掃除など部屋の片づけをしたり、身体介護として食事介助、入浴介助、排泄介助、更衣介助などを行ったりします。就寝介助や就寝中の利用者さんの体位変換は、夜勤ならではの業務です。
また、定期巡回では、夜間・深夜・早朝の時間帯に定期的に巡回し、体調などに異変がないかを確認します。随時訪問の仕事内容は、利用者さんからの通報を受け、必要に応じて訪問し、身体介護を行うことです。
利用者さんの体調が急変し、緊急対応が求められる場合もあるでしょう。緊急時には、マニュアルに沿って迅速に行動することが必要です。提携先の医療機関への連絡のほか、救急車を要請した場合は到着するまでの間、利用者さんに付き添います。夜勤における訪問介護では、どのような状況下でも落ち着いて対応する冷静さが大切です。
▼関連記事
ホームヘルパーの仕事内容を解説!訪問介護員の仕事範囲や必要な資格を紹介
サ責が夜勤をするメリット
ここでは、サ責が夜勤をするメリットをご紹介します。給与・スキルアップに結びつきやすいことや、日中の時間を自由に使えるという自分自身にとってのメリット以外に、利用者さんの状態把握につながるという職務上の利点もあります。
夜勤手当がついて給与が上がる可能性がある
サ責が夜勤をすると、日勤のみより給与が上がる可能性があるでしょう。
厚生労働省の「しっかりマスター 割増賃金編(p.2)」によると、午後10時から午前5時までの勤務に対しては、基本給の25%増しの深夜割増賃金を支払うことが法律で定められています。そのため、深夜帯に勤務する場合は、確実に給与が増えるでしょう。
なお、介護職150人を対象にしたレバウェル介護(旧 きらケア)のアンケートによると、1回当たりの夜勤手当の平均支給額は、約7,000円でした(調査時期:2024年3月)。
夜間や早朝の、午後10時から午前5時まで以外の時間帯は、法律による規定がないため、給与が上がるかどうかは事業所次第です。とはいえ、多くの事業所で夜勤手当が支給されている実態があるので、高収入を目指す場合は、夜勤ありの働き方も視野に入れると良いでしょう。
出典
厚生労働省「労基法パンフレット」(2024年10月16日)
対応力が身につきスキルアップできる
夜間は限られた人数で利用者さんに対応するため、判断力や対応力が身につき、スキルアップにつながるでしょう。日勤と比較して、夜間に配置される職員は少ない傾向があります。少人数でも介護サービスを確実に提供するには、状況に応じた的確な判断が必要です。
利用者さんから、「転倒した」「体調が悪くて動けない」といった連絡があれば、自ら利用者さんのもとへ駆けつけて対処する場合も。緊急時に備え、心臓マッサージやAEDの使用方法を習得するなどの救命処置を身につければ、さらなるスキルアップにつながります。夜勤ならではの業務に接し、より多くの介護経験を積むことで、キャリアアップを図れるでしょう。
利用者さんの夜間の状態を把握できる
夜勤をすることで、利用者さんの日常生活を総合的に把握できます。日中と夜間では、利用者さんの心身の状態が異なる可能性も。1日の様子を把握することで、問題点に気づきやすいでしょう。改善すべき点があれば、ケアマネジャーに報告し、ケアプランを見直してもらうことで、訪問介護計画書も更新できます。
夜勤前後の日中の時間を自由に使える
夜勤前後の時間を有効に活用できるのも、夜勤をする大きなメリットです。役所や銀行、病院などの多くが、主に平日の日中に営業しています。日勤の場合、午前8時~午後6時ごろの時間帯は勤務中のため利用が困難ですが、夜勤であれば、出勤前や退勤後に立ち寄れるでしょう。
▼関連記事
サービス提供責任者の給料はいくら?収入アップの方法や仕事内容を紹介
サ責が夜勤をするデメリット
サ責が夜勤をするデメリットは、生活リズムが乱れたり、人員配置が少なく負担に感じる可能性があったりすることです。自身の勤務時間を考える際は、夜勤のメリットだけではなく、デメリットも確認しておきましょう。
生活リズムが乱れる可能性がある
夜勤で普段と違う睡眠サイクルになることで、生活リズムが乱れてしまう可能性があります。夜勤は、夜勤専従や2交代制、3交代制といった勤務形態です。特に3交代制勤務の場合、勤務日の翌日が必ず休日とは限らないため、十分な休養が取れないことが懸念されます。生活リズムを崩さないためには、質の高い睡眠や栄養バランスの整った食事を心がけ、疲労回復に努めるようにしましょう。
なお、生活リズムが違うことで、家族や友達との時間を確保しにくいという側面もあります。夜勤をストレスなくこなすためには、周囲の理解を得ることも必要です。
日勤よりも職員が少なく責任が大きいと感じる
夜勤は日勤より配置人数が少なく、少人数で業務に当たるため、プレッシャーを感じる可能性があります。
公益財団法人介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書(p.59)」によると、夜勤時の職員数は「1人」が 53.3%と最も多く、次いで「2人」が24.0%でした。この結果から、夜勤に対応する職員数は必要最低限であるといえるでしょう。また、1人のサ責が深夜勤務の際に受け持つ利用者数は、平均16.5人という結果でした。
日勤の場合、利用者さんが40人以上ならサ責を2人以上配置するのが原則なので、小規模な事業所以外は、サ責が複数人配置されていると考えられます。夜勤のサ責の配置人数は、日勤よりも少ない可能性が高く、相談しにくい体制に責任を感じる場合があるでしょう。
また、夜勤のサ責はオペレーター業務や訪問介護も兼務する場合があり、一人で受け持つ仕事が幅広く、大変に感じることもあるかもしれません。
出典
公益財団法人介護労働安定センター「介護労働実態調査」(2024年10月16日)
厚生労働省「第228回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2024年10月16日)
▼関連記事
介護職の夜勤はしんどいの?仕事内容やメリット、きついときの対処法を解説
サービス提供責任者に関してよくある質問
ここでは、サービス提供責任者についてよくある質問に回答します。兼務や雇用形態など、サ責の働き方が気になる方は、ぜひ確認してみてください。
サービス提供責任者は管理者やヘルパーを兼務できる?
訪問介護の提供に支障をきたさない場合、サ責は管理者やホームヘルパーを兼任できます。なお、兼務に関する規定は自治体ごとに異なる場合があるため、市区町村の窓口やWebサイトで確認すると安心です。サ責の兼務については「サービス提供責任者の兼務は認められているの?」の記事で解説しているので、参考にしてみてください。
サービス提供責任者は非常勤でもなれますか?
サ責は、非常勤でも勤務可能です。ただし、常勤職員の勤務時間の2分の1以上勤務する必要があります。サ責の要件を満たせる人材は需要が高いため、正社員だけではなく、パートといった雇用形態で働ける職場も少なくありません。
サ高住のサービス提供責任者に夜勤はありますか?
サ高住のサ責は夜勤なしが多いものの、一部の施設で夜間帯のサービス提供を行っている場合があります。サ高住のサ責が夜勤をする場合の主な業務は、相談援助や巡回、見守り緊急対応などです。サ高住の仕事について詳しく知りたい方は、「サ高住で働く職種は?夜勤はある?仕事内容や役立つ資格をご紹介」の記事もあわせてご一読ください。
まとめ
サ責(サービス提供責任者)は、「夜間対応型訪問介護」や「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を提供する訪問介護事業所で働く場合、夜勤を行う可能性があります。
夜勤で担当する特徴的な仕事は、利用者さんからの通報に対応するオペレーター業務です。また、訪問介護業務として、利用者さんの安否確認や緊急対応を行うこともあるでしょう。
夜勤には、給与アップやスキルアップにつながりやすく、新たな介護経験を積むことができるというメリットがあります。一方、「生活リズムを保つのが難しい」「少人数対応なのでプレッシャーを感じやすい」といったデメリットもあるでしょう。そのため、自分のライフスタイルやキャリアデザインを考慮したうえで、日勤のみ・夜勤ありのどちらかを選択するのがおすすめです。
「サービス提供責任者に挑戦したいけど、夜勤なしのところで働きたい」「夜勤なしのサ責に転職したら給料が減らないか不安…」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した就職・転職エージェント。介護事業所の採用担当者と直接やり取りをしているので、夜勤の有無や担当する利用者さんの人数、兼務の内容など、気になることを事前に確認可能です。就業条件のヒアリングも丁寧に実施しているので、ご希望に沿った介護求人をご紹介できます。サービスの利用はすべて無料なので、まずは気軽にお問い合わせください。
今の職場に満足していますか?
 サービス提供責任者の求人はこちら
サービス提供責任者の求人はこちら