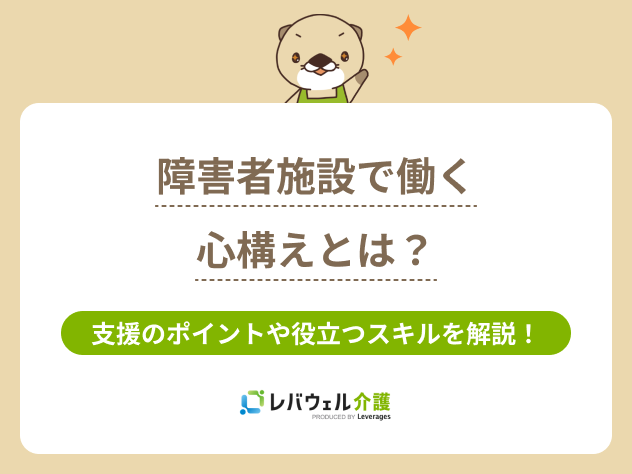
この記事のまとめ
- 障害者施設で働く心構えとして、思いやりや寄り添いを意識することが大切
- 障害者支援では、分かりやすいコミュニケーションや精神面への配慮が重要
- 福祉の知識や、ストレスを管理するスキルがあれば、障害者施設で活躍できる
福祉の仕事に興味があり、「障害者施設で働く心構えを確認したい」という方もいるでしょう。障害者支援において大切なのは、利用者さんに思いやりをもって接することや、障がいについて理解することです。この記事では、障害者施設の仕事に携わるために必要な考え方や、配慮すべき点を解説します。障害種別の支援のポイントもまとめました。障害者施設の種類や求人の選び方もご紹介するので、就職・転職の参考にしてください。
障害者支援施設とは?仕事内容や一日の流れ、高齢者介護との違いを解説! →レバウェル介護の資格スクールはこちら障害者施設で働く心構え
障がいのある方と接するうえで大事なことは、思いやりをもつことや、一人ひとりに寄り添うことです。障害者施設で働く心構えを下記にまとめたので、確認してみましょう。
利用者さんに思いやりをもつ
障害者施設で働く際は、利用者さんに思いやりをもって接することが大切です。未経験の場合、「障がいのある方とのコミュニケーションが難しい」と思うことがあるかもしれません。しかし、利用者さんにはそれぞれ個性があるため、一括りにするのは無理があるといえます。「障がいのある方」として線引きするのではなく、「〇〇さん」という個人として尊重して関わることが求められるでしょう。
障がいがあることによって日常生活に課題が生じるのは、あくまで利用者さんの一つの側面です。同じ障がいを抱える利用者さんでも、一人ひとり生活スタイルや考え方などは異なります。そのため、利用者さんの性格を決めつけたり、自分の都合を優先して対応したりせず、思いやりをもって接することが重要です。
一人ひとりの悩みや不安に寄り添う
「障がいのある方」と一口に言っても、障がいがある原因や特性、何に困っているのかは、人それぞれ異なります。そのため、画一的なマニュアルで対応するのではなく、個別にケアをしなければなりません。
たとえば、事故や病気で障がいが残ってしまった場合、自分の状況を受け入れるのに時間がかかることがあります。利用者さんが、「どうして自分が…」と悩んでいるときは、「リハビリを頑張りましょう」と一方的に声をかけるのではなく、まずは話を聞くなど、不安に寄り添って支援することが必要です。
自分本位ではなく、利用者さんを主体とし、悩みや不安を理解して支援することで、信頼関係を構築できるでしょう。
自立支援を意識する
福祉の仕事に携わるうえでは、自立支援の考え方を理解して実践することも重要です。自立支援とは、「すべて介助するのではなく、できない部分を手伝うことで、利用者さんができる限り自立した生活を送れるようサポートする」という考え方を指します。
奉仕精神が強い方は、「利用者さんのためになりたい」という気持ちから、過剰な支援をしてしまわないよう、注意が必要です。利用者さんのためと思っていても、結果的に職員に依存してしまうと、社会参加の機会を奪ってしまうことにつながりかねません。障害者施設で初めて働く場合は、周りの職員や専門書などを参考にして、自立支援を意識したケアができると良いでしょう。
利用者さんと適切な距離感を保つ
障害者施設では、利用者さんと適切な距離感を保つことも必要です。コミュニケーションを取って信頼関係を築くことは重要ですが、あくまで職員と利用者さんという立場であることを念頭に置いて関わりましょう。
利用者さんは精神的な不安を抱えている場合も多く、家族や友人のような距離感で接すると、1人の職員に依存してしまう可能性があります。依存関係になると、利用者さんの自立の機会を奪ってしまったり、ほかの職員が関わりづらさを感じたりすることにつながるでしょう。
また、利用者さんのネガティブな感情から影響を受け、精神的につらいと感じてしまう場合もあります。利用者さんに寄り添いつつも、冷静に状況を客観視するためには、適度な距離感で接することが重要です。
利用者さんに問題行動があれば上司に相談して対応することや、親しくなっても敬語を使うことなどを意識すると、一定の線引きをした適切な支援ができるでしょう。
職員間のコミュニケーションを大切にする
職員同士が十分にコミュニケーションを取ることで、利用者さんに必要な支援を行えます。障害者施設では、上司への報連相に加え、次のシフトの職員が出勤した際の申し送りも欠かせません。利用者さんの状況や業務の進捗を伝え、職員全体で協力して仕事を進めることで、スムーズな支援につながるでしょう。
障害者施設で働き始めたら、まずは自分から積極的にあいさつをして人間関係を築くのがおすすめです。自分から話しかけて関係性を築くことで、困ったときに相談しやすくなったり、相手から気軽に声をかけてもらえたりします。
施設の種類による仕事の違いを把握する
働く障害者施設の種類によって、仕事内容や勤務時間、給料などは異なります。そのため、自身のやりたい支援や希望条件、体力を考慮して職場を選ぶことが大切です。対象者や利用者さんの傾向も施設ごとに異なるため、事前に情報収集を行いましょう。
障害者施設には、利用者さんが入居して生活する施設や、通所して利用する施設があります。また、利用者さんの在宅生活や移動を支援する訪問系のサービスも、障害者支援の仕事の一つです。詳細は、「障害者施設・事業所の種類」の項目で解説するので、あわせて参考にしてください。
焦らず少しずつ業務に慣れる
障害者支援の仕事は、無資格や未経験から挑戦できますが、スムーズに業務を進めるためには専門的なスキルが必要です。障害者施設で初めて働く場合の心構えとしては、焦らず少しずつ業務に慣れることを目標にすると良いでしょう。
最初は、利用者さんとのコミュニケーションや職員同士の連携がうまくいかず、「自分には向いていないかも…」と悩むことがあるかもしれません。しかし、どのような仕事でも、就職して職場に慣れるまでの期間は、業務を完ぺきにこなせなくて当然です。
仕事が思うように進まないときも、「できない」と落ち込むのではなく、先輩からの指導や失敗の経験を前向きにとらえて次に活かすことで、スキルアップできます。一気にすべての業務を覚えるのは難しいので、「まずは利用者さんの顔と名前を覚える」「明日は1日の仕事の流れを意識する」など、小さな目標を立てながら、少しずつ慣れていくと良いでしょう。
仕事のやりがいだけではなく大変さも確認する
業務のやりがいを意識することで、働く意欲やモチベーションにつながるでしょう。また、仕事の大変な部分を理解していれば、就職後にギャップを感じず長期的に活躍できます。障害者施設で働きたいと考えている方は、やりがいと大変さの両方をチェックしておきましょう。
障害者施設の仕事のやりがい
利用者さんの成長を実感できたり、笑顔を見られたりすることが、障害者施設の仕事のやりがいです。
就労支援や相談対応、リハビリなどで自立支援に関わり、利用者さんが自分でできることが増えたときに、「頑張って支援して良かった」と感じられるでしょう。利用者さんから、「いつもありがとう」と笑顔を向けられ、仕事のやりがいを感じることもあります。
また、障害者支援のスキルが身についたり、自分自身が成長できたりするのも、障害者施設の仕事の魅力です。複数の利用者さんに直接関わることで、立場や考え方が異なる人への理解が深まり、1人の人間としても成長できるでしょう。
▼関連記事
障害者施設の仕事のやりがいとは?サービス内容や向いている人の特徴を解説
障害者施設の仕事の大変な部分
障害者施設の仕事の大変な部分は、精神的な負担を感じる場合があることや、一定の体力が必要なことです。利用者さんに暴力・暴言があったり、自傷行為がみられたりすると、対応が難しく、精神的な負担を感じやすいようです。また、身体介護や夜勤に体力を使うことを「きつい」と思う場合もあります。
精神的・身体的な負担を軽減するためには、職員同士で連携することや、正しい知識と技術を習得することが必要です。1人の職員に負担が偏らないよう配慮している職場なら、無理せず相談しながら支援を行えるでしょう。身体介護や夜勤を負担に感じるときは、正しい介護技術を学んで身体への負荷を減らしたり、疲労をため込まないよう工夫して過ごしたりすることを意識するのがおすすめです。
▼関連記事
障害者施設の職員が抱える仕事の悩みとは?解決方法もご紹介
障がいごとの特性を理解する
障がいのある方が不安や不快に感じないような支援をするためには、障がいごとの特性を理解することも必要です。
知的障がい
知的障がいとは、知的機能の障がいが18歳ごろまでに現れ、日常生活に課題を感じることです。知的障がいのある方は、「一度教えてもらっただけでは作業を理解するのが難しい」「いつもと違う状況になると、どうすべきか適切に判断できない」といった悩みを抱えていることがあります。
円滑にコミュニケーションを取ったり、臨機応変に対応したりすることが苦手な傾向にあるため、困っている部分を補う支援が求められるでしょう。
出典
東京都福祉局 ハートシティ東京「知的障害」(2024年11月13日)
新潟市「障がいや障がいのある人に対する理解を深める周知啓発」(2024年11月13日)
精神障がい
精神障がいとは、精神疾患によって精神機能に障がいが現れ、日常生活や社会生活に課題を感じることです。精神障がいの種類としては、統合失調症や気分障がい、依存症などがあります。
症状が重度になると、判断能力が低下したり、自身の感情や行動のコントロールが困難になったりすることも。医師と連携しながら、原因疾患や症状を理解したうえで支援することが大切です。
出典
東京都福祉局 ハートシティ東京「精神障害」(2024年11月13日)
厚生労働省「精神障害(精神疾患)の特性(代表例)」(2024年11月13日)
発達障がい
発達障がいとは、通常低年齢において脳機能の発達に障がいが現れ、日常生活や社会生活に課題を感じることです。発達障がいは、精神障がいの一つとして分類されることもあります。また、知的障がいを伴う場合もあるようです。
発達障がいの種類としては、自閉スペクトラム症(ASD)、 注意欠陥・多動性障がい(ADHD)学習障がい(LD)などが挙げられます。特性の内容や程度は、個人差が大きいのが特徴です。
発達障がいのある方は、コミュニケーションに困難を感じやすい傾向にあります。周りと同じように行動するのが難しく、他人から誤解されてしまい、悩むことがあるようです。
出典
東京都福祉局 ハートシティ東京「発達障害」(2024年11月13日)
e-Gov法令検索「発達障害者支援法」(2024年11月13日)
今の職場に満足していますか?
【障害種別】障害者施設における支援のポイント
ここでは、障害者施設の職員が、利用者さんの支援を行うときに心がけると良いポイントを、障害種別にまとめました。障がい特性や利用者さんの悩みは、個人差が大きいことに留意しつつ、参考としてチェックしてみてください。
知的障がいのある方の支援のポイント
知的障がいのある方の支援を行う際は、できるだけ分かりやすいコミュニケーションを取ることを心がけましょう。あいまいな表現だと判断が難しくなるので、注意が必要です。
たとえば、仕分けの作業を頼む際は、「大きいものは分ける」といった表現ではなく、「〇cm以上なら右の箱に入れる」というように、具体的な基準を示すと、伝わりやすいでしょう。実際に教える際にやってみて、視覚的に情報を覚えてもらうのも効果的です。
また、「言わなくても分かるだろう」と決めつけず、一つずつ丁寧に伝えることも意識しましょう。「漢字が読めない」「計算が苦手」「暗黙のルールを知らない」といった状況の場合、支援する側がしっかり説明しておくことで、利用者さんが対応しやすくなります。
出典
京都府「知的障害者と共に働くあるあるガイドブック」(2024年11月13日)
精神障がいのある方の支援のポイント
精神障がいのある利用者さんと関わるときは、落ち着いた態度を心がけましょう。幻聴や妄想といった症状により、話が矛盾している場合も、否定せずに傾聴することが大切です。実際の状況と違っても、利用者さんにとっては「聞こえる」「そう感じている」ということを理解すると、寄り添ったケアができるでしょう。
精神障がいのある方は、ストレスから感情的になったり、うつ状態で気分が大きく落ち込んだりすることもあります。利用者さんの感情に引っ張られて「精神的にきつい」と感じないためには、障がい特性やメンタルケアに関する知識を学び、自身の精神の健康を維持することも大切です。
出典
東京都福祉局 ハートシティ東京「精神障害」(2024年11月13日)
発達障がいのある方の支援のポイント
前述したように、発達障がいの特性は個人差が大きいので、支援にあたっては利用者さん個々の得意なことや苦手なことを知る必要があります。「発達障がいのある人」として見るのではなく、「〇〇さんが不安に感じる状況」という視点で向き合うと、利用者さんの課題の解消につながるケアができるでしょう。
発達障がいの特性の例としては、「音や光の刺激に敏感」「マルチタスクをこなすのが難しい」「読み書きが苦手」などがあります。音の刺激に敏感な場合はイヤーマフを活用する、同時進行が苦手な場合は作業を一つずつ頼むといった工夫をするのがおすすめです。また、読み書きが難しい場合は、ゆっくり読み上げて説明したり、要点だけを簡潔に書いたりすると、長文のマニュアルよりも伝わりやすくなります。
出典
東京都福祉局 ハートシティ東京「発達障害」(2024年11月13日)
身体障がいのある方の支援のポイント
身体障がいのある方の支援を行う際は、安全性を確保して身体介護をすることはもちろん、精神面にも気を配ることが大切です。
たとえば、身体に障がいがある方は、排泄や入浴にも支援が必要な場合があります。排泄介助や入浴介助において、利用者さんのプライバシーへの配慮は欠かせません。具体的には、「オムツ交換の際はカーテンを閉める」「身体的な変化について職員間で共有するときは、ほかの利用者さんに聞かれないようにする」などに気をつける必要があります。
また、身体障がいを抱えている理由も人それぞれ異なるでしょう。「生まれつき肢体不自由だった」「糖尿病の合併症で失明した」など、一人ひとりの事情があり、障がいの受け止め方にも個人差があります。利用者さんやご家族が障がいを受け入れられていない場合もあれば、特性と向き合って前向きに頑張ろうとしている場合もあるため、相手の感情を決めつけず、寄り添ったケアや声かけができると良いでしょう。
難病のある方の支援のポイント
難病のある方の支援のポイントは、どのような病気なのか、何に気をつければ良いのかなどを確認しながらケアを行うことです。難病は種類が多く、患者数が少ない疾患は対応方法を調べるのが難しい可能性もあるので、医師と連携してケアをすることが求められます。また、利用者さんの体調の安定を図るには、通院の機会を確保することも必要です。
難病の方は、「まだ若いのに急に難病になって働けなくなった」「複数の病院に通っても良くならず、今後が不安」といった不安を抱えていることも少なくありません。そのため、難病を患う利用者さんの支援では、信頼関係を築き、精神的なケアを行うことも重要です。
出典
横須賀市「共生社会実現のために~障害のある人を理解するためのガイドブック~(テキスト版)」(2024年11月13日)
新潟市「障がいや障がいのある人に対する理解を深める周知啓発」(2024年11月13日)
障害者施設の仕事に活かせるスキル
福祉に関する知識やコミュニケーション能力、ストレスマネジメントのスキルがあれば、障害者施設で働く際に活かせるでしょう。以下で解説するので、「障害者支援の仕事に向いているか知りたい」という方は確認してみてください。
障がいや福祉に関する知識
障がいや福祉に関する知識があれば、障害者施設で活躍しやすいでしょう。たとえば、身近に障がいのある方がいたり、福祉ボランティアの経験があったりする場合、障がいのある方に対する一定の理解があるといえます。
「障害者施設で働きたいけど、スキルがなくて不安…」と感じるなら、資格を取得して知識を身につけるのも良いでしょう。
身体介護に携わりたい方には、介護の公的資格である「介護職員初任者研修」や「介護福祉士実務者研修」がおすすめです。障害者支援に特化した資格としては、公益財団法人 日本知的障害者福祉協会が実施する「知的障害を理解するための基礎講座」などがあります。
出典
公益財団法人 日本知的障害者福祉協会トップページ(2024年11月13日)
▼関連記事
【障がい者支援に役立つ資格一覧】取得方法や難易度、習得できるスキルは?
首都圏限定!資格取得が無料!
転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!
レバウェル介護の資格スクールコミュニケーション能力
障害者施設で働くうえで、コミュニケーション能力は重要です。利用者さんのケアを行う際だけではなく、職員同士の人間関係を構築して連携するためにも、欠かせないスキルといえます。これまでに接客や営業の職歴があり、コミュニケーション能力を身につけている人は、スキルを活かして働けるでしょう。
また、障がいのある方は言葉によるコミュニケーションが難しい場合もあるので、簡単な単語で伝えたり、表情から感情を読み取ったりすることも必要です。育児や介護の経験がある方は、ジェスチャーや表情でコミュニケーションを取るスキルを活かすことできます。
最初は利用者さんとの接し方に迷うかもしれませんが、やわらかい口調や表現を意識し、少しずつコミュニケーションを取ることで、障害者支援の仕事に慣れていけるでしょう。
▼関連記事
介護で役立つ傾聴スキルとは。共感を示すコミュニケーションの方法
ストレスをマネジメントするスキル
障害者施設で長く働くためには、自分のストレス管理を行うことも必要です。仕事で悩んで行き詰まらないよう、プライベートの時間も大切にしましょう。また、対応が難しい利用者さんがいる場合は、1人で頑張り過ぎず周囲を頼ることも、ストレスマネジメントです。
ストレス管理ができれば、自身の負担の軽減に加え、利用者さんの精神的なケアにも活かせます。ストレスマネジメントをテーマにした本を読んだり、研修を受講したりすることで、スキルを習得できるでしょう。
▼関連記事
介護士さんにおすすめのストレス発散法は?調査してみました!
障害者施設・事業所の種類
障害者支援を行う職場には、「入居型の障害者施設」「通所型の障害者施設」「訪問介護事業所」があります。
入居型の障害者施設
利用者さんが入居して暮らす障害者施設では、生活の場としてさまざまなサービスを提供します。入居型の障害者施設の主な種類を下記にまとめました。
入所施設
入所施設では、主に夜間において、「施設入所支援」というサービスを提供します。職員の仕事内容は、入浴介助や排泄介助、相談対応などです。支援の必要性が高く、自宅での生活が困難な方が入居しています。
厚生労働省の「施設入所支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」によると、施設入所支援の利用者さんは、障害福祉サービスにおいて支援の必要性が最も高いとされる「障害支援区分6」の方が全体の半数以上です。また、利用者さんの約7割は知的障がいのある方で、次に多いのが身体障がいのある方となっています。
ショートステイ(短期入所施設)
ショートステイ(短期入所施設)は、普段は家族などの介護者のサポートを受けて自宅で生活している利用者さんが、短期的に入所して生活する場です。介護者が病気やケガを患った場合や、利用者さんのケアから一時的に離れて休息を取る場合に利用されます。
職員の仕事内容は、利用者さんの入浴介助や排泄介助、食事介助などです。なかには、看護師や医師を配置し、医療ケアに対応しているショートステイもあります。利用者さんは、障害支援区分5・6の方が多く、障がいのある子どもも利用しているようです。
出典
厚生労働省「第37回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2014年11月13日)
障害者グループホーム(共同生活援助事業所)
障害者グループホーム(共同生活援助事業所)は、障がいがあって一人暮らしをすることに不安を感じる方が、10人以下の少ないグループで共同生活を送る住居です。職員は、日常生活に必要な身体介護や家事の支援を行います。また、利用者さんの社会生活のための、相談援助や関係機関との連携、金銭管理のサポートなども仕事内容です。
ほかの入居型の障害者施設に比べ、障害者グループホームは、精神障がいのある利用者さんの割合が高い傾向にあります。また、障害支援区分なしから区分6の方まで利用しており、利用者層は幅広いでしょう。
なお、障害者グループホームは、「外部サービス利用型」「介護サービス包括型」「日中サービス支援型」の3種類に分かれています。施設の種類ごとに支援内容は異なるため、働く際は、事前に仕事内容や利用対象者を確認しておきましょう。
出典
厚生労働省「第40回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年11月13日)
▼関連記事
障害者グループホームで働く世話人の仕事内容を解説!介護の資格は必要?
通所型の障害者施設
利用者さんが日中に通うのが、通所型の障害者施設です。主に介護サービスを提供する障害者デイサービスに加え、利用者さんの就労を支援する施設もあります。
障害者デイサービス(生活介護事業所)
障害者デイサービス(生活介護事業所)は、入所施設や在宅で生活する方が、日中に通う障害者施設です。身体介護に加え、食事の提供や、工作などのレクリエーションも実施します。
利用できるのは、「障害支援区分3以上の方」「50歳以上で障害支援区分2以上の方」などで、常時の支援が必要な方が対象です。障害支援区分6の利用者さんが最も多く、50歳以上の利用者さんが4割を超えています。障害種別でみると、知的障がいのある方が最も多く、次に多いのは身体障がいのある方です。
出典
厚生労働省「第37回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2014年11月13日)
就労継続支援A型・B型事業所
就労継続支援事業所は、一般企業での雇用が難しい方に対し、就労の機会を提供する施設で、A型とB型の2種類に分かれています。
就労継続支援A型事業所の対象者は、雇用契約に基づいて働ける、障がいのある方です。精神障がいのある方が約5割で、次いで知的障がいのある方、身体障がいのある方が多く利用しています。
就労継続支援B型の対象者は、障がいがあり、雇用契約に基づいて働くのが難しい方です。利用者さんは、知的障がいのある方が約5割、精神障がいのある方が約4割となっています。
就労継続支援事業所の職員の仕事内容は、利用者さんが作業をしやすいように環境を整えたり、相談に乗ったりすることです。そのため、身体介護を行う機会は少ないでしょう。声かけや見守りによる作業のサポートや、一般就労に向けた関係機関との連携などをメインに行います。
▼関連記事
就労継続支援B型の仕事内容は?職員の1日の流れと働くメリットを解説!
就労移行支援・就労定着支援事業所
障がいのある方の就労を支援する職場には、就労移行支援事業所と就労定着支援事業所もあります。
就労移行支援の対象者は、一般就労を希望し、適性に合った職場への就労が期待できる、障がいのある方です。知識やスキルを向上させるための実習や、職場探しの支援、就職後の定着支援などを行います。
就労定着支援の対象者は、障害福祉サービスの利用を経て、一般就労に移行した方です。一般就労に移行してから6ヶ月以上経過していることや、就労に伴って生活に課題を感じていることも、利用条件に含まれます。支援内容は、利用者さんの相談に乗ったり、就業先との連絡・調整を行ったりすることです。
出典
厚生労働省「第38回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年11月13日)
訪問介護事業所
障害者支援に携わる職場として、訪問介護事業所も挙げられます。訪問介護事業所が提供する障害福祉サービスは、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・移動支援などです。施設での介護とは異なり、利用者さんの自宅を訪問し、日常生活や外出に伴う支援を行います。
サービスの種類によって、利用対象者や支援内容、職員に求められる資格は異なります。たとえば、居宅介護の対象者は障害支援区分1以上の方。主な支援内容は、身体介護や家事援助、通院介助です。居宅介護に従事するには、介護職員初任者研修などの資格を取得しなければなりません。
訪問介護事業所は、「高齢者介護にも対応している」「障害者支援のみ行っている」「重度訪問介護のみ提供している」など、職場によってサービス内容が異なります。そのため、興味がある方は、事業所名やWebサイトからサービス内容を調べたうえで応募すると良いでしょう。
出典
厚生労働省「第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年11月13日)
▼関連記事
重度訪問介護とは?簡単にサービスを説明します!障がい福祉に必要なお仕事
首都圏限定!資格取得が無料!
転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!
レバウェル介護の資格スクール障害者施設の求人の選び方
就職先を選ぶ際に、労働条件や待遇をしっかりと確認しておけば、働き始めてからミスマッチを感じることを防げます。「障害者施設への転職が初めてで、うまくいくか不安…」という方は、以下で求人の選び方をチェックしてみましょう。
給料や福利厚生などの条件に納得できる職場を探す
仕事探しの際は、給料や福利厚生などをよく調べ、自身が納得できる条件か検討しましょう。現在の年収や生活費をざっと計算して比べてみるのもおすすめです。未経験で転職する場合、最初は給与が下がってしまう可能性もあるので、昇給制度や評価制度などから、将来的な給与を予測してみるのも良いでしょう。
また、一般的な給与水準や福利厚生を知るためには、複数の求人を比較することも大切です。いろいろな求人に触れることで、「この施設は手当が充実している」「給与は低めだが、休日数が多い」など、職場ごとの特徴を理解できます。
研修や資格取得支援制度の有無を確認する
研修や資格取得支援制度の有無も、事前にチェックしておきたいポイントです。特に、無資格や未経験から転職する場合、安心して働くためには、教育制度や支援体制は非常に重要といえます。
障害者施設は、職員の定着やサービスの質向上を目的に、職場内での研修を充実させていることも少なくありません。また、介護や福祉に関する資格を取得する場合、費用補助やシフトの調整といった形で、職場が協力してくれることも多いでしょう。
「障害者施設で働きながら、スキルを身につけてキャリアアップしたい」とお考えの方は、教育体制にも目を向けて求人を選んでみてくださいね。
転職エージェントに職場環境を確認してから応募する
求人情報や応募先のWebサイトを見ていると、「書いてあることが本当なのか分からない」「給料や休日についてもっと詳しく知りたい」と思うこともあるかもしれません。求職活動を行ううえで、職場環境のリサーチは必須ですが、自分1人で情報収集を行うのには限界があります。そのため、条件の希望がある場合や、確認したい項目がある場合は、転職エージェントを活用するのがおすすめです。
障害者施設への就職や転職を検討している方は、介護・福祉業界に特化した「レバウェル介護(旧 きらケア)」にご相談ください。求人情報だけでは判断できない職場環境や、応募先に問い合わせづらい労働条件などの情報も、アドバイザーからお伝えできます。また、応募前の職場見学のセッティングや、履歴書作成のサポートなども可能なので、慣れない求職活動も安心して進められるでしょう。専任のアドバイザーが、求人の紹介から就職後の相談まで無料で対応するので、気軽にご利用くださいね!
首都圏限定!資格取得が無料!
転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!
レバウェル介護の資格スクール障害者施設で働くことを検討している方によくある質問
ここでは、障害者施設の仕事についてよくある質問に回答します。「障害者支援の仕事に携わるためには、どんな準備をすれば良いの?」と気になっている方は、ぜひ参考にしてください。
障害者施設で働くには資格が必要ですか?
障害者施設で働くために必須の資格はないため、無資格や未経験から求人に応募可能です。ただし、看護職員や管理職など、資格が必要な職種もあります。そのため、求人の応募条件を確認したうえで申し込むようにしましょう。無資格の方には、「無資格OK」「未経験者の採用実績あり」などの記載がある求人がおすすめです。無資格・未経験の職員の採用に積極的な職場は、教育体制が整っていて働きやすい可能性が高いでしょう。
障害者施設の仕事に活かせる資格が知りたい方は、「障害者施設で働くにはどんな資格が必要?仕事内容や働くメリットも紹介」の記事もご参照ください。
首都圏限定!資格取得が無料!
転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!
レバウェル介護の資格スクール知的障がいのある方の支援に携わるための心構えは?
知的障がいのある方の支援に携わる際は、シンプルで分かりやすいコミュニケーションを意識すると良いでしょう。「9時ごろに来てください」「あの辺に置いてください」のような抽象的な表現で伝えると、判断ができず、迷ってしまう可能性があります。そのため、「9時に来てください」「このカゴの中に入れてください」など、具体的に伝えることが大切です。また、障がいのある方に適切な支援を行うためには、自身の感情をコントロールしたり、利用者さんの特性を理解したりすることも大切です。
知的障がいのある方の支援については、この記事の「知的障がいのある方の支援のポイント」にもまとめています
障害者施設の利用者さんとの関わり方の注意点とは?
障害者施設で働く際は、利用者さん一人ひとりの個性や考え方を尊重することが大切です。同じ種類の障がいや特性があっても、利用者さんによって、してほしい支援や適切な対応は異なります。利用者さん本人の意思を尊重したうえで、プライバシーや権利を損わないことにも配慮することで、専門職として最適な支援を行えるでしょう。利用者さんが自分で判断するのが難しい部分に関しては、職員がしっかりケアをする必要があります。また、障害者施設の仕事はチームケアなので、利用者さんの対応で困ったときは、ほかの職員に相談することも重要です。
障害者施設における利用者さんとの関わり方については、「障害者施設で働く心構え」も参考にしてください。
まとめ
障害者施設で働く心構えとして、利用者さんに思いやりをもって接することや、自立支援の視点で考えることを意識すると良いでしょう。職員同士で密にコミュニケーションを取って連携したり、障がいに対する理解を深めたりすることで、利用者さんに適切な支援を行えます。
知的障がいのある方や発達障がいのある方は、コミュニケーションが苦手な場合があります。「言わなくても分かるだろう」と決めつけず、分かりやすく丁寧に説明することが、利用者さんの支援になるでしょう。精神障がいのある方とのコミュニケーションは、否定せずに傾聴の姿勢を心がけるのがポイントです。
障害者支援に興味がある方は、就職後にミスマッチを感じないよう、仕事内容や施設の特色、職場環境などを調べておきましょう。無資格・未経験の方には、教育体制の整った障害者施設がおすすめです。
「未経験でも働きやすい施設はある?」「自分はどの施設に向いている?」といった疑問がある方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。アドバイザーがお話を伺い、教育が手厚い施設や希望条件に合う職場をご提案させていただきます。不安や疑問を解消してから就職すれば、働き始めてから不満を感じにくいでしょう。障害者施設に就職するか迷っている方や、求人を見てみたいだけの方も、ぜひご活用ください。
今の職場に満足していますか?
先に資格を取りたい方へ
無料相談はこちら 資格取得支援の介護求人はこちら
資格取得支援の介護求人はこちら