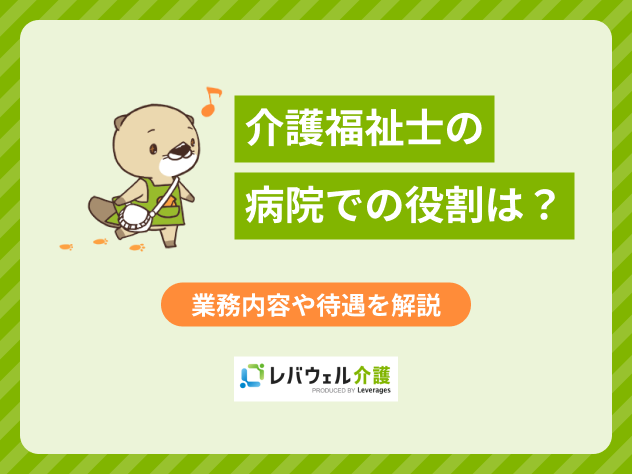
この記事のまとめ
- 介護福祉士の病院での役割は、患者さんの入院生活を支援すること
- 病院と介護施設の違いは、仕事内容や常駐する職員、利用目的
- 介護福祉士が病院で働くメリットは、身体介護が少なく負担が小さいことなど
「介護福祉士の病院での役割は何?」と疑問をお持ちの方もいるでしょう。病院における介護福祉士の役割は、医師や看護師のサポートをしながら、患者さんの自立を支援することです。幅広い年齢層の患者さんに対してケアをする点が、介護施設での仕事と大きく異なります。この記事では、介護福祉士の病院での業務内容や待遇を解説。病院で働くメリットとデメリットもあわせてご紹介するので、転職を検討中の方は参考にしてください。
介護福祉士とは?仕事内容や資格の取得方法、試験概要をわかりやすく解説! →レバウェル介護の資格スクールはこちら介護福祉士の病院での役割
介護福祉士の病院での役割は、患者さんのケアや看護師のサポートを通し、患者さんが快適な入院生活を送れるようにすることです。また、介護福祉士としての知識を活かし、退院後のことまで考えてケアを行う必要があります。患者さんの状態に合わせて介助量や介助方法を調節し、自立を支援することが求められるでしょう。
今の職場に満足していますか?
▼関連記事
病院勤務の介護士の仕事内容とは?介護施設との違いや働くメリットをご紹介
介護福祉士における病院と介護施設の違い
介護福祉士は、病院や介護施設などで働いており、職場によって求められる役割や業務内容は異なります。病院と介護施設の仕事の違いを見てみましょう。
求められる役割
病院で働く介護福祉士は、看護師の補佐的な側面が強く、主にサポート業務を行います。一方で、介護福祉士などの介護職員が主体となって利用者さんの介護を行うのが、介護施設です。
仕事内容
病院では、基本的に高齢者だけではなく、幅広い年代の患者さんに対してケアを行います。そのため、通常の介護業務だけではなく、リハビリや検査の付き添い、医療機器の片づけ、カルテ整理といった業務も介護福祉士の仕事です。
介護施設で働く介護福祉士は、主に高齢者に対して介護業務を行うほか、レクリエーションの企画・運営やご家族の対応も行います。
利用目的
病院と介護施設では、利用の目的も異なります。病院における患者さんの入院は、病気やケガの治療・回復が目的です。一方の介護施設は、日常生活に支援を必要とする方が、介護サービスを目的に利用します。
常駐する職員
病院は24時間体制で医療を提供するため、医師や看護師が常駐しています。介護福祉士が働く場合も、患者さんの体調に関する判断は、医療職に委ねることが可能です。
介護施設では、介護サービスの提供のために、介護職員や生活相談員、ケアマネジャーなどが働いています。医師や看護師が常駐していない施設では、外部の医療機関と連携し、利用者さんの体調管理を行うことになるでしょう。
介護福祉士の病院での業務内容
以下では、病院に勤務する介護福祉士の業務内容をご紹介します。「自分が働けそうか確認したい」という介護福祉士の方は、ぜひご一読ください。
患者さんの介護業務
病院に勤務する介護福祉士の業務の中心となるのは、入院中の患者さんの身体介護です。看護師と連携しながら、次のような仕事を担当します。
入浴介助
入浴介助は、病気やケガの影響で、1人で入浴するのが困難な患者さんをサポートする業務です。専用のストレッチャーに寝た状態で入浴できる浴槽や、椅子に座った状態で入浴できる浴槽など、患者さんの状態に合った浴槽を使用して介助を行います。
「ケガをしているからシャワー浴のみ行う」「血流を促すために浴槽に入るのを勧める」など、患者さんによって対応が異なるため、看護師や医師の指示をよく確認することが大切です。
食事介助
身体機能や認知機能の低下により、自分で食事をするのが困難な患者さんには、食事介助を行います。正しい姿勢で食べられるようサポートしたり、患者さんのスピードに合わせて食事を口元に運んだりすることは、誤嚥防止のために重要なケアです。
排泄介助
病院の介護福祉士は、患者さんがトイレまで移動する手伝いや、脱衣・清拭・着衣といった、排泄介助も行います。ポータブルトイレや尿器、オムツなど、患者さんの状態によって、排泄の方法はさまざまです。いずれの場合も、患者さんのプライバシーに十分配慮することを心がけましょう。
更衣介助
ケガをしている方や手術を終えたばかりの方など、身体を自由に動かせない患者さんには、更衣介助を行います。患者さんに痛みを与えないように、ケガや麻痺など身体の状態をしっかり把握したうえで介助することが重要です。
また、患者さんが認知症といった疾患により、認知機能が低下している場合も、更衣を手伝うことがあります。
整容介助
洗顔・ひげ剃り・爪切り・耳掃除・整髪・口腔ケアなど、患者さんの身だしなみを整えて清潔を保つ介助も行います。患者さんが愛用している整髪料を使用したり、好みの髪型・ひげに整えたりすることで、患者さんのストレス軽減にもつながるでしょう。
なお、爪が変形している場合の爪切りや、耳アカが詰まっている場合の耳かきは、介護福祉士は行えないので、看護師に相談してください。一般的に、カミソリを使用して行うひげ剃りも禁止されているので、ルールを把握したうえでケアを行いましょう。
服薬介助
患者さんに服薬の声掛けをしたり、薬の飲み残しがないか確認したりするのが、服薬介助です。ただし、シートから薬を取り出す行為や、容態が不安定な場合の服薬介助は、医療行為にあたるため、介護福祉士は行えません。
体位変換
ベッド上で自分で寝返りを行えない患者さんに対し、体の向きを変えるケアを行うのが、体位変換です。血行不良による床ずれや循環障がいなどを防ぐ目的で行います。介助をする際にはしっかりと声かけを行い、患者さんがベッド柵を持てる場合は、ご本人にも協力してもらうと良いでしょう。
病院の環境整備
患者さんの介護だけではなく、病院内の環境整備も、介護福祉士の仕事です。ベッドメイキングやシーツ交換、清掃、洗濯を行い、施設内を清潔に保ちます。医師や看護師が安全に働ける環境を作るとともに、患者さんが快適に過ごせる環境にすることが、環境整備の目的です。
看護師のサポート
病院で働く介護福祉士は、看護師と連携して業務のサポートを行います。介護福祉士は医療行為ができないため、行うのはあくまでも看護業務のサポートと簡単な事務作業です。看護師のサポート業務としては、次のようなものが挙げられます。
カルテ整理
カルテは患者さんごとに作成されるため、膨大な量となります。介護福祉士は、カルテの整理や運搬・伝達を任されることもあるでしょう。また、患者さんの様子や病状を、記録に記入することもあります。
医療器具の準備・洗浄
看護補助として、検査や処置で使用する医療器具の準備と、使用後の器具の洗浄・消毒も行います。器具の準備や片付けは、患者さんに安全な医療を提供するために欠かせない業務の一つです。
配膳業務
患者さんへの食事の配膳も行います。患者さんの疾患に対応した栄養バランスや、飲み込む力や噛む力に配慮した食事が用意されるので、配膳に誤りがないよう十分な確認が必要です。
備品発注
介護福祉士は、院内で使用する備品の発注を担当することもあります。マスクやガーゼ、リネン類、消毒液などを適宜補充し、不足しないようにしましょう。
介護福祉士の病院での待遇
病院で働く介護福祉士の平均給与や勤務時間を、以下にまとめました。
平均給与
政府統計の総合窓口e-Statの「職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」によると、2023年における看護助手の平均月給(賞与等を含まない)は、22万2,500円です。ただし、看護助手には無資格者も含まれるため、介護福祉士はこれよりも給与が高い可能性があります。
ちなみに、厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.157)」によると、介護事業所で働く介護福祉士全体の、2022年9月における平均給与額(賞与等を含む)は、33万1,080円でした。
出典
政府統計の総合窓口e-Stat「職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」(2024年11月18日)
厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2024年11月18日)
勤務時間
病院は24時間体制で治療・ケアを行うため、介護福祉士も土日祝日・夜勤を含むシフト制での勤務になる可能性があるでしょう。2交代制(日勤/夜勤)、3交代制(日勤/遅番/夜勤)、4交代制(早番/日勤/遅番/夜勤)など、勤務時間は病院によって異なります。
育児や介護などプライベートを優先させたい方や、夜勤に負担を感じる方は、土日休み・夜勤なしといった条件で求人を探すのがおすすめです。
介護福祉士が病院で働くメリット
介護福祉士が病院で働くメリットは、身体的な負担が少ないことや、福利厚生が充実している傾向にあることなどです。具体的なメリットを、詳しくご紹介します。
身体的負担が少ない
介護福祉士が病院で働くメリットとして、身体的な負担が比較的少ないことが挙げられます。介護施設と比較すると身体介護を行う機会が少ないため、その分身体的な負担も少ないでしょう。
「介護福祉士として働きたいけど体力に自信がない」という方は、病院での勤務がおすすめです。病院のなかでも、診療科によって患者さんの年齢層や身体の状態は異なるので、事前に特徴を確認しておきましょう。
医療知識が身につく
医師や看護師とともに仕事をするため、治療方法や医療器具の知識が自然と身につくことも、介護福祉士が病院勤務を選ぶ大きなメリットです。看護師が患者さんをケアする姿や、患者さんの回復の過程を近くで見ることで、介護の業務にも活かせるスキルを学べます。現場で積んだ経験や身につけた知識は、別の医療系・福祉系職種にキャリアチェンジする際にも役立つでしょう。
介護と医療の連携を学べる
病院でのカンファレンスに参加することで、現場で介護と医療がどのように連携するのかを学べるでしょう。カンファレンスには、医師や看護師のほか、リハビリ専門職や介護職など、さまざまな職種の職員が参加します。医療職の意見を聞いたり、連携を図ったりする場に、日常的に参加できるのは、病院ならではの魅力です。
さまざまな患者さんと関われる
幅広い年齢層の患者さんと関わることができるのも、病院で働くメリットです。介護施設では、高齢者への介護が業務の中心となります。しかし病院では、高齢者だけではなく、さまざまな世代の患者さんに対応可能です。患者さんのニーズや病状に応じたケアを行う大変さがある一方で、いろいろな経験が積めるという魅力があります。
福利厚生が充実している
資格取得支援制度があったり、退職金制度があったりなど、福利厚生が充実している病院は少なくありません。託児所完備・医療費補助といった、病院ならではの福利厚生があることも。すべての病院に共通しているわけではありませんが、医療機関は福利厚生が比較的充実している傾向にあるため、働きやすい職場といえます。
介護福祉士が病院で働くデメリット
介護福祉士が病院で働く場合、スキルアップやキャリアアップがしにくいというデメリットもあるため、事前に確認しておく必要があります。
介護職としてスキルアップがしにくい
病院で働く場合、介護施設よりも高齢者の介護をする機会が少ないことから、介護職としての経験を積みにくく、スキルアップしにくいというデメリットがあります。また、医師や看護師の指示を受けての業務や、連携を重視した仕事が多いのも特徴です。そのため、介護施設のように、介護福祉士が裁量をもってケアをするスキルは身につきにくいでしょう。
医師や看護師との関係構築が難しい
病院では、医師や看護師とのコミュニケーションが重要ですが、指示を受けて働くなかで上下関係を意識してしまい、働きにくいと感じる人もいるようです。介護の専門家である介護福祉士は、看護師から介護業務全般を任せられ、負担に思う場合もあります。
職場内でキャリアアップがしにくい
介護福祉士が病院で働くと、キャリアアップしにくいというデメリットもあります。介護施設では、介護福祉士として経験を積むことで、主任やリーダー、管理者などへのキャリアアップを望めます。しかし、病院は介護職が支援のメインではないため、長く勤めても、専門的な役職に就くのは難しいでしょう。
介護福祉士としてキャリアアップしたい方は、介護施設など病院以外の職場への転職も視野に入れるのがおすすめです。また、病院で介護福祉士として経験を積みながら、ケアマネジャーといった資格を取得し、将来的にキャリアチェンジする選択肢もあります。
介護福祉士が病院で働くために必要な資格
介護福祉士として病院で働く場合、介護福祉士国家試験の合格を経て資格を得る必要があります。看護助手の仕事自体に資格は必須ではないため、無資格・未経験で病院に就職し、働きながら介護福祉士を目指すことも可能です。
下記では、介護福祉士に興味がある方に向けて、資格取得の方法を解説します。介護福祉士の資格を取得することで、採用に有利になったり、資格手当で給料アップを目指せたりするメリットがあるので、まだ取得していない方は目標にするのがおすすめです。
介護福祉士の資格を取得する方法
介護福祉士の資格を取得するには、以下のいずれかの方法で、試験の受験資格を得なければなりません。介護福祉士国家試験に合格した後は、資格登録をすることで、介護福祉士として働けます。
実務経験の条件を満たす
「介護業務等の実務経験3年以上かつ従事日数540日以上」「介護福祉士実務者研修の修了」という2つの条件を満たすことで、介護福祉士国家試験の受験資格を得ることができます。働きながら介護福祉士を目指せるため、すでに介護職として働いている方におすすめの取得方法です。
養成施設に通う
介護福祉士国家試験の受験資格は、介護福祉士養成施設を卒業することでも満たせます。福祉系大学や社会福祉士養成施設、保育士養成施設を卒業している方は、最短1年で受験資格を得ることが可能です。それ以外の方は、最短でも2年養成施設に通わなければなりません。
福祉系高校に通う
福祉系高校を卒業した方や、福祉系特例高校に通って9ヶ月の実務経験を積んだ方も、受験資格を得られます。特例高校を卒業した方の場合は、筆記試験への合格に加え、介護過程IIIの修了も必要です。
経済連携協定(EPA)ルート
経済連携協定(EPA)に基づくEPA介護福祉士候補者が対象となる、外国人向けのルートです。「従業期間3年以上かつ従事日数540日以上の実務経験」と「実務者研修の受講」という条件を満たすことで受験資格を得られます。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格」(2024年11月18日)
▼関連記事
介護福祉士の受験資格を得るルートを解説!必要な実務経験や試験概要は?
首都圏限定!資格取得が無料!
転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!
レバウェル介護の資格スクール病院勤務の介護福祉士の求人例
病院で勤務する介護福祉士の求人の例は、以下のとおりです。
【勤務地】東京都渋谷区
【雇用形態】正社員
【勤務時間】午前9時~午後6時(休憩60分/午後5~翌午前9(休憩120分)/シフト制
【仕事内容】病院における介護業務/在宅復帰に向けた診療・看護・リハビリのサポート
【給与】月給20万円~31万円+夜勤手当4万円(1回1万円×4回)
【福利厚生】賞与年2回/交通費支給/扶養家族手当/退職金制度あり/社会保険完備/休日出勤手当/社員寮あり/研修制度・研修費用補助/健康保険組合より各種補助金あり/育児支援
【休日・休暇】年間休日数115日(生理休暇/産前産後休暇/育児休業/介護休業制度あり)
【応募条件】介護福祉士の資格を保有する方
研修制度が充実していたり、育児支援があったりと、福利厚生が充実している求人が多い傾向にあるのが、病院の介護福祉士求人の特徴です。ただし、シフト制で休みや勤務時間が不規則な場合もあるため、自分にとって働きやすい条件か、しっかりと確認をしましょう。
介護福祉士の仕事についてよくある質問
ここでは、介護福祉士の仕事についてよくある質問に回答します。「介護福祉士としてのキャリアに悩んでいる」という方は、参考にしてみてください。
介護福祉士のキャリアアップ方法を教えてください
介護福祉士としてキャリアアップするには、管理職を目指したり、違う資格を取得したりする方法があります。介護現場でリーダーシップを発揮すると、管理職になるためのアピールになるでしょう。ケアマネジャーや看護師といった資格を取得し、より条件の良い職場への転職を目指す方法もあります。介護福祉士のキャリアアップについてさらに詳しく知りたい方は、「介護福祉士のキャリアアップ方法をご紹介!資格や経験を活かせる職種は?」の記事をご参照ください。
病院以外で介護福祉士が働ける場所はどこですか?
介護福祉士は、病院以外にも、介護施設や訪問介護事業所、障がい者施設などで働くことができます。また、資格を活かして介護講師として働く選択肢もあるでしょう。介護福祉士が働ける場所については「介護福祉士の働く場所は?現場以外の就職先を含めて解説」の記事でも詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
病院に勤務する介護福祉士は、医師や看護師のサポートをしながら、介護を通して患者さんの自立を支援する役割を担っています。介護職員が主体となって高齢者の介護を行う介護施設とは異なり、看護師の補佐として、幅広い年齢層の患者さんのケアを行うのが仕事です。
介護福祉士の病院での業務には、基本的な身体介護に加えて、カルテ整理や医療器具の洗浄、環境整備も含まれます。さまざまな患者さんと関わりながら医療知識・医療現場の連携を学べる一方で、身体介護がメインではないことから、スキルアップ・キャリアアップがしにくいというデメリットもあるようです。
病院で介護福祉士として働きたい方は、ぜひレバウェル介護(旧 きらケア)をご利用ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーが、希望の条件をもとに相性の良い求人を提案します。サービスの利用は無料なので、お気軽にご相談ください。
今の職場に満足していますか?
先に資格を取りたい方へ
無料相談はこちら 土日祝休みの求人一覧ページ
土日祝休みの求人一覧ページ