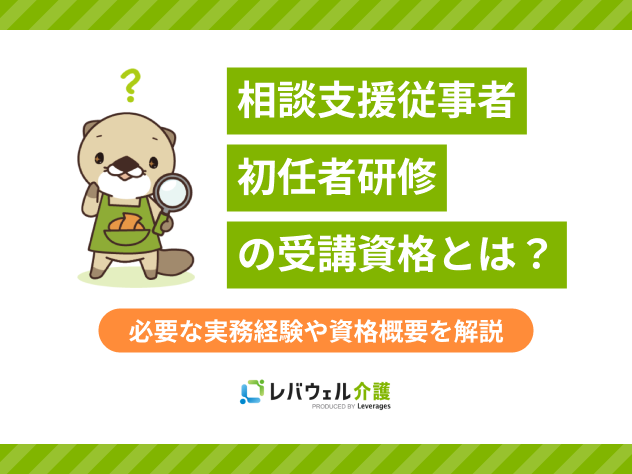
この記事のまとめ
- 相談支援従事者初任者研修とは、相談支援専門員に必要なスキルや学べる講座
- 相談支援従事者初任者研修の受講資格があるのは、相談支援専門員を目指す人
- 相談支援従事者初任者研修の内容は、42.5時間にわたる講義・演習・実習
「相談支援従事者初任者研修を受けるにはどんな条件があるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。相談支援従事者初任者研修は都道府県が管轄しているため、受講資格は実施主体ごとに細かな違いがあります。この記事では、相談支援従事者研修の受講資格や概要を解説。また、東京都・埼玉県・千葉県・大阪府を例に挙げ、開催日程や受講費用なども紹介します。相談支援専門員の仕事に興味がある方は、ぜひご一読ください。
介護資格の種類31選!取得方法やメリットを解説します相談支援従事者初任者研修とは
相談支援従事者初任者研修とは、相談支援専門員に必要な知識や相談援助のスキルを学べる講座です。厚生労働省が研修カリキュラムを定めており、自治体主導で研修が開催されています。
相談支援専門員になるには、必要な実務経験を3~10年積むことと、相談支援従事者初任者研修の修了が必要です。相談支援専門員になると、障がいがある方とそのご家族に必要な障がい福祉サービスの利用計画(サービス等利用計画)を作成し、日常生活を安心して送れるようにサポートできます。
働きながら資格を取る方法教えます
▼関連記事
相談支援専門員に必要な資格は?初任者研修や実務経験について解説
相談支援従事者初任者研修の受講資格
相談支援従事者初任者研修の受講資格を満たせるのは、相談支援専門員として従事する予定がある人です。ただし、具体的な要件は自治体によって異なります。自治体や申し込み状況によっては、相談支援専門員に必要な実務経験の要件を満たしていないと、受講が難しい場合もあるようです。
厚生労働省の「相談支援専門員の実務経験」を参考に、相談支援専門員に求められる実務経験を下記にまとめました。
相談支援業務の実務経験
相談支援業務の実務経験で、相談支援従事者初任者研修の受講資格を満たすには、以下の実務経験が5年間必要です。
- 施設などで相談支援の仕事に携わる
- 医療機関で相談支援の仕事に携わる(※条件あり)
- 就労支援に関わる相談支援の業務に携わる
- 特別支援教育の進路・教育相談の業務に携わる
- 上記4つに準ずると都道府県知事が認めた業務に携わる
障害者支援施設や児童相談所、介護老人保健施設などでの相談支援の実務経験が5年以上あることが、実務経験の要件です。
なお、医療機関で相談支援業務に従事する場合は、5年以上の実務経験に加え、下記のいずれかの条件を満たすことで、実務経験の要件をクリアできます。
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
引用:厚生労働省「相談支援専門員の実務経験」
(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
(3)国家資格等※2を有する者
(4)施設等における相談支援業務に従事した期間が1年以上である者
医療機関で働きながら相談支援専門員を目指す場合、相談支援の実務経験だけではなく、介護・福祉系の資格などが必要です。
なお、(2)の「※2」が示す国家資格等には、介護福祉士や社会福祉士、精神保健福祉士などが含まれます。下記の「国家資格に基づく実務経験」で列挙する資格と共通なので、気になる方はあわせてご確認ください。
介護等業務の実務経験
相談支援従事者初任者研修の受講資格を満たすために必要な「介護等業務の実務経験」は、10年以上です。施設や医療機関などにおける介護業務の実務経験もしくは、それに準ずると認められる業務に携わることで、相談支援専門員に必要な実務経験を満たせます。
保有資格の条件はないため、時間はかかるものの、介護職員から相談支援専門員へのキャリアチェンジを目指すことが可能です。
資格に基づく業務の実務経験
介護・福祉に関する公的資格や国家資格を保有している方は、比較的短期間で、相談支援従事者初任者研修の受講要件を満たせます。
有資格かつ介護等業務の実務経験
特定の福祉・介護系の資格を保有する方が介護等業務に携わっている場合、相談支援専門員の要件として求められる実務経験が「5年以上」に短縮されます。具体的には、社会福祉主事任用資格、訪問介護員2級以上に相当する研修、保育士、児童指導員任用資格のいずれかを保有する場合が対象です。
国家資格に基づく実務経験
指定の国家資格等に基づく業務に5年以上携わっている場合、相談支援業務や介護等業務として必要な実務経験が3年に短縮されます。指定の国家資格等は、下記のとおりです。
| 必要な国家資格等 |
| 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士 |
参考:厚生労働省「相談支援専門員の実務経験」
介護・福祉・医療などに関する専門的な資格を保有しており、相談支援や介護業務を行っている場合、最短3年で相談支援従事者初任者研修を受講できます。
出典
厚生労働省「計画相談支援のしくみ」(2024年11月26日)
 ヘルパー・介護職の求人一覧はこちら
ヘルパー・介護職の求人一覧はこちら 生活相談員の求人一覧はこちら
生活相談員の求人一覧はこちら
相談支援従事者初任者研修の概要
ここでは、相談支援従事者初任者研修の概要を解説します。詳細は自治体やスクールによって異なるので、実際に研修を受ける場合は、受講先の情報を必ずチェックしてくださいね。
研修のカリキュラム内容
相談支援従事者初任者研修は、合計42.5時間のカリキュラムで、講義・演習・実習で構成されます。カリキュラムは厚生労働省が決めているため、基本的な学習内容は全自治体共通です。
講義では、相談支援の基本的な視点や相談支援技術、障がい福祉に関する法律などについて学びます。アセスメント・計画作成の演習と現場実習を通して、基本業務や実践的な技術を習得可能です。グループワークを行い、受講者が意見交換する時間もあるため、自分になかった考え方や価値観に触れることもできるでしょう。
研修に必要な期間
相談支援従事者初任者研修は、7~8日間の日程で組む自治体が多いようです。研修の全日程を2~3ヶ月かけて実施します。Webサイトに年間スケジュールを公開している都道府県もあるので、事前に確認のうえ、全日参加できるよう計画を立てましょう。
研修の申込み方法
相談支援従事者初任者研修の申し込みは、インターネットを利用する電子申請が多いようです。あわせて申込書の郵送を求める自治体もあります。申し込み方法は自治体によって異なるので、注意が必要です。
なお、申し込みには、実務経験を証明する書類や相談支援員として配置の予定がある事業所からの推薦状、受講確認書などの書類が必要なので、漏れがないようチェックしましょう。
研修の受講方法
相談支援従事者初任者研修は、スクールが指定する会場での受講が基本です。自治体によっては、講義や演習をオンラインで実施している場合もあります。ただし、実習がカリキュラムに含まれるため、オンラインのみで修了することはできません。
研修の費用
相談支援従事者初任者研修の受講費用は、実施主体によって大きく異なります。受講費無料の自治体がある一方で、6万円以上かかる場合もあるので、受講先の情報を前もって確認することが必要です。同じ自治体でも、委託先のスクールによって受講費用が異なる可能性があります。
研修の修了要件
相談支援従事者初任者研修には、修了試験がありません。研修カリキュラムを受講してすべての指定課題を提出すれば、修了が認められ、修了証が交付されます。なお、修了証が交付されるタイミングは、自治体によって異なるようです。
相談支援従事者初任者研修の開催情報
ここでは、東京都・埼玉県・千葉県・大阪府における2024年度の相談支援従事者初任者研修の開催情報を紹介します。受講資格や研修日程、費用などを確認して、研修を受けるか検討してみましょう。
東京都の研修情報
東京都の相談支援従事者初任者研修は、東京都福祉局の東京都心身障害者福祉センターが管轄します。
研修日程
東京都の研修日程は、2024年9月9日から2025年2月5日で、講義2日と演習5日の全7日間です。講義はオンデマンド配信で、9月9日~9月19日までの間に12時間程度の動画を視聴します。
演習も、研修会場での受講とオンライン受講から選べます。7パターンの研修日程があり、受講可能な日をすべてチェックして受講日が決まるようです。時間は、おおよそ午前9時45分~午後5時15分。演習は平日に開催されるので、土日休みの方は、仕事のスケジュールの調整が必要になるでしょう。
なお、実習は、研修4日目と5日目の間と、5日目と6日目の間に、実習期間で各自実施します。
受講資格
東京都の相談支援従事者初任者研修の受講資格があるのは、以下4つの要件をすべて満たす方です。
- 1.東京都内の事業所で働いている方もしくは、働く予定の方
- 2.指定相談支援事業所などで相談支援専門員業務に携わる方か、指定重度障がい者等包括支援事業所でサービス提供責任者業務に携わる方(予定も可)
- 3.事業所から推薦がある方
- 4.東京都の事業所で実習に取り組める方
東京都で相談支援に従事している方や、従事する予定のある方が対象です。事業所からの推薦も必要なので、受講したい方は上司に相談しておくと良いでしょう。
受講費用
東京都の受講費用は、無料です。ただし、講義視聴にかかる通信料などは自己負担となります。
出典
東京都福祉局「令和6年度東京都相談支援従事者初任者研修 実施案内」(2024年11月26日)
埼玉県の研修情報
埼玉県の相談支援従事者初任者研修は、埼玉県が実施主体で、民間団体である有限会社プログレ総合研究所に委託して実施されます。
研修日程
埼玉県の研修日程は、2024年7月11日から2025年2月26日で、講義2日と演習5日の全7日間です。演習の期間中に2日間の実習があります。講義はオンデマンド配信で、2024年7月11日~7月31日の間に2日間で視聴するスケジュールです。
演習は5日間で、西部、北部、東部、南部(1)、南部(2)の5つの地域に分けて実施します。地域によって日程や会場が異なるので、間違えないように気をつけましょう。研修会場は、勤務する事業所の所在地に基づいて割り振られますが、申し込み状況によってはほかの地域での受講になる場合もあるようです。
受講資格
埼玉県の相談支援従事者初任者研修の受講資格があるのは、以下の5つの要件のいずれかに該当する方です(2024年3月31日時点での実務経験)。
- 1.相談支援従事者の要件を満たす。なおかつ、指定一般相談支援事業所・指定特定相談支援事業所・障がい児相談支援事業所のいずれかにおいて、相談支援事業に携わっているか、その予定がある方
- 2.指定重度障がい者等包括支援事業所に勤務するサービス提供責任者か、その予定がある方
- 3.2025年3月末までに相談支援従事者の要件を満たす見込みがあり、上記1か2の業務に携わっているまたは、その予定がある方
- 4.埼玉県の市町村職員で、相談支援業務に携わっているまたは、2025年3月末までにその予定がある方
- 5.埼玉県職員で、相談支援業務に携わっているまたは、2025年3月末までにその予定がある方
相談支援従事者の要件を満たす方や、相談支援業務に携わっている方が対象です。なお、人員配置の観点などから、資格の必要性が高い方が、優先的に受講できるように配慮されます。
受講費用
埼玉県の受講費用は、 3万1,500円です。期限までに受講料を支払わないと辞退扱いになるため、受講決定通知に同封される振込払込書を必ず確認して対応しましょう。また、勤務先から受講費用の補助が出る可能性があるので、確認しておくことをおすすめします。
出典
埼玉県「埼玉県相談支援従事者初任者研修」(2024年11月26日)
千葉県の研修情報
千葉県の相談支援従事者初任者研修は、千葉県が実施主体です。千葉県のWebサイトに令和6年度千葉県相談支援従事者初任者研修の情報がまとめられています。
研修日程
千葉県の研修日程は、2024年7月1日から11月26日で、講義2日・講義と演習1日・演習4日の全7日間です。講義はオンデマンド配信で、7月1日~7月5日の間に2日間で視聴します。講義と演習は7月18日のみで、研修会場での実施です。
演習は前期2日と後期2日で、それぞれ4パターンずつの日程が用意されています。いずれも平日の開催です。実地研修は8月30日から10月2日の間に実施され、受け入れ先の機関によって日程は異なります。
受講資格
千葉県における相談支援従事者初任者研修の受講資格があるのは、以下のいずれかに該当する方です。
- 1千葉県内の、指定一般相談支援事業所・指定特定相談支援事業所・指定障がい児相談支援事業所のいずれかで、相談支援専門員として働く予定の方
- 2. 千葉県内で、障がいがある方に関する相談支援に携わる市町村職員
千葉県も、県内で相談支援に携わっている方や携わる予定の方を受講対象としています。
受講費用
千葉県の相談支援従事者初任者研修の受講費用は、無料です。
出典
千葉県「令和6年度千葉県相談支援従事者初任者研修」(2024年11月26日)
大阪府の研修情報
大阪府の相談支援従事者初任者研修は、大阪府が実施主体で、大阪府障害者福祉事業団、大阪府社会福祉事業団、大阪市障害者福祉・スポーツ協会、四天王寺福祉事業団の4団体に委託して実施されます。
研修日程
大阪府の研修日程は、講義2日と演習5日の全7日間です。1~2日目は、オンライン配信で全体講義を行います。日程は委託先のスクールによって異なり、大阪府のWebサイトから確認可能です。実習は、研修4日目と5日目の間と、5日目と6日目の間に実施されます。
受講資格
大阪府における相談支援従事者初任者研修の受講資格があるのは、以下のいずれかの条件に当てはまる方です。
- 1.大阪府内の指定一般相談支援事業所や指定特定相談支援事業所で、相談支援専門員として働く予定の方
- 2. 大阪府内の指定障がい児相談支援事業所で、相談支援専門員として働く予定の方
- 3. 大阪府内の指定重度障がい者包括支援事業所で、サービス提供責任者として働く方
大阪府の場合は、受講資格に実務経験の有無は定められていません。ただし、研修定員を超える応募があったときは、実務経験がある方が優先されるようです。上記に加え、大阪府内の基幹相談支援センターで相談支援専門員として働く予定のある方も、受講対象になる場合があります。
受講費用
大阪府は、相談支援従事者研修を外部組織に委託しているため、委託先ごとに受講費用が異なります。大阪府障がい者福祉事業団の受講費用は6万2,700円、大阪府社会福祉事業団と大阪市障がい者福祉・スポーツ協会は6万円です(2024年11月時点)。
出典
大阪府「相談支援従事者研修について」(2024年11月26日)
相談支援従事者初任者研修と相談支援従事者現任研修の違い
相談支援従事者初任者研修と相談支援従事者現任研修の違いは、受講対象者です。初任者研修は、相談支援専門員になろうとしている人が対象の講座で、資格取得を目指して受講します。一方で、現任研修は、すでに初任者研修を取得している人が対象で、資格更新が受講の目的です。
相談支援専門員として働き続けるには、5年ごとに相談支援従事者現任研修を受講し、資格を更新する必要があります。
相談支援従事者初任者研修によくある質問
ここでは、相談支援従事者初任者研修についてよくある質問にお答えします。受講条件や方法についてを知りたい方は、確認してみてください。
受講資格があるのに相談支援従事者初任者研修を受けられなかった…
定員を超える申し込みがあった場合、自治体が受講者を審査して優先順位を決めるため、相談支援従事者初任者研修の受講対象から外れてしまう可能性があるでしょう。受講対象外になる人の例としては、厚生労働省指定の実務経験を満たせていない人や、県外の事業所で働いている人、相談支援専門員として配置される予定のない人などが挙げられます。
相談支援従事者初任者研修はオンラインで受講できますか?
相談支援従事者初任者研修のカリキュラムのうち、講義2日間をオンラインで配信する自治体があります。また、一部の自治体では、演習もオンラインに対応しているようです。しかし、実習は実地で行うため、オンラインのみで相談支援従事者初任者研修を修了することはできません。具体的な受講方法は自治体によって異なるので、必ず事前に確認しましょう。
まとめ
相談支援従事者初任者研修とは、相談支援専門員になるために必要な資格で、相談援助に関する知識やスキルを学べる内容です。相談支援専門員になると、障がい福祉サービスの利用計画(サービス等利用計画)を作成し、障がいのある方やご家族の援助に結びつけるサポートができます。
相談支援従事者初任者研修の受講資格は、研修を実施する自治体ごとに細かな違いがあるので、必ず事前にチェックしましょう。主な受講要件は、相談支援専門員として従事する予定があることや、実務経験を満たしていること。実務経験を必要とする場合は、相談支援業務の実務経験・介護等業務の実務経験・資格に基づく業務に従事した経験のいずれかが求められます。
相談支援従事者初任者研修は、講義・演習・実習で構成された合計42.5時間のカリキュラムです。研修日程は7~8日で、実施主体による大きな違いはありません。一方で、研修費用は、無料の自治体があったり、6万円近く必要な自治体があったりするため、確認が必要です。
相談支援従事者初任者研修には修了試験がないため、カリキュラムを受講し、すべての課題を提出すれば、晴れて資格を取得できます。
「相談支援従者初任者研修を取得して、相談支援専門員として働きたい!」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護・福祉業界に特化した転職エージェントです。豊富な介護・福祉求人のなかから、資格取得に協力してくれる職場をご紹介可能。専任のキャリアアドバイザーによるキャリアカウンセリングをもとに、希望条件に合う求人をご提案いたします。サービスはすべて無料です。ご相談だけでも大丈夫なので、まずは気軽にお問い合わせください。
働きながら資格を取る方法教えます