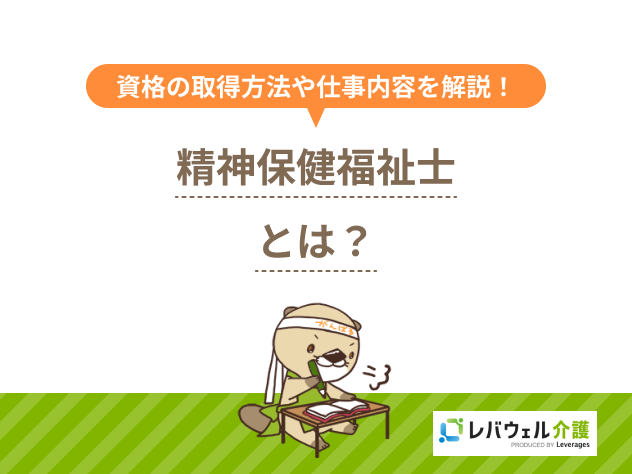
この記事のまとめ
- 精神保健福祉士は、精神障がいがある方の日常生活や社会復帰を支援する職業
- 精神保健福祉士になるには、受験資格を満たし国家試験に合格する必要がある
- 精神保健福祉士の就職先は、病院・福祉事務所・教育機関などさまざま
「精神保健福祉士とはどんな仕事なの?」「精神保健福祉士の取得方法を知りたい!」という方もいるでしょう。精神保健福祉士は、精神障がいがある方を支援につなぎ、日常生活や社会復帰を支援する職業です。この記事では、精神保健福祉士の業務内容や資格の取得方法を解説。主な就職先や働き方、資格を取得するメリットもご紹介します。精神保健福祉士への就職・転職を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
介護資格の種類31選!取得方法やメリットを解説します精神保健福祉士とは
精神保健福祉士とは、精神障がいがある方の日常生活の相談に乗ったり、社会復帰の支援をしたりする職業です。「PSW」(Psychiatric Social Worker)と略されることもあり、精神保健福祉法に基づく国家資格「精神保健福祉士」を保有する人が携わります。
公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの「都道府県別登録者数」によると、2024年10月末時点で精神保健福祉士として登録されているのは、108,713人です。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)」(2024年11月27日)
精神保健福祉士の役割
精神保健福祉士は、精神疾患や福祉の専門知識を活かして、精神障がいがある方の相談に応じます。必要なサービスと相談者をつなぐことで、安心して生活できる環境を整えるのが役割です。
担当する利用者さんや患者さんは、一人ひとり違う症状や困りごとを抱えています。精神保健福祉士に求められるのは、相談者に寄り添い、専門職として的確なアドバイスと支援を行うことです。
精神保健福祉士と社会福祉士の違い
精神保健福祉士と社会福祉士の違いは、支援対象と専門性です。社会福祉士は福祉全般について広く支援を行いますが、精神保健福祉士は主に精神障がいがある方を支援します。相談援助の仕事を通して困っている人を助けるという点は共通していますが、専門性が大きく異なるでしょう。
働きながら資格を取る方法教えます
精神保健福祉士になるには?
精神保健福祉士になるには、受験資格を満たしたうえで精神保健福祉士国家試験を受験し、合格しなければなりません。試験に合格して登録を行うことで、資格を取得できます。精神保健福祉士になるまでの流れを、下記に詳しくまとめました。
受験資格を満たす
精神保健福祉士国家試験を受けるためには、受験資格を満たす必要があります。受験資格を得る方法は、以下の11種類です。
- 4年制の保健福祉系大学で指定科目を履修する
- 3年制の保健福祉系短大で指定科目を履修し、実務経験を1年積む
- 2年制の保健福祉系短大で指定科目を履修し、実務経験を2年積む
- 4年制の福祉系大学で基礎科目を履修し、短期養成施設の課程を修了する
- 3年制の福祉系短大で基礎科目を履修後、1年間実務経験を積み、短期養成施設の課程を修了する
- 2年制の福祉系短大で基礎科目を履修後、2年間実務経験を積み、短期養成施設の課程を修了する
- 4年制の一般大学を卒業し、一般養成施設の課程を修了する
- 3年制の一般短大を卒業後、1年間実務経験を積み、一般養成施設の課程を修了する
- 2年制の一般短大を卒業後、2年間実務経験を積み、一般養成施設の課程を修了する
- 実務経験を4年以上積み、一般養成施設の課程を修了する
- 社会福祉士を取得し、短期養成施設の課程を修了する
学歴や履修科目によって、受験資格を得るルートが異なるため、注意が必要です。要件に含まれる実務経験とは、精神障がいがある方の相談援助に従事した期間を指します。また、短期養成施設の学習期間は6ヶ月以上で、一般養成施設の場合は1年以上です。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[精神保健福祉士国家試験]受験資格」(2024年11月27日)
▼関連記事
ソーシャルワーカーに必要な資格の取り方や難易度は?職種別の要件も解説!
精神保健福祉士国家試験に合格する
上記の方法で受験資格を得ることで、精神保健福祉士国家試験を受験できます。試験は年に1回のみなので、合格を目指して計画的に対策しましょう。詳しくは「精神保健福祉士国家試験の概要」で後述するので、あわせて参考にしてください。
資格登録の手続きをする
精神保健福祉士として働くためには、試験合格後に資格登録の手続きを行わなければなりません。登録申請書の提出や、登録手数料の支払いが必要です。手続きに不備がなければ、1ヶ月程度で登録証が届き、精神保健福祉士になることができます。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[資格登録] 新規登録の申請手続き」(2024年11月27日)
精神保健福祉士国家試験の概要
ここでは、精神保健福祉士国家試験の概要を解説します。試験の内容や難易度、日程などが気になる方は、チェックしてみてください。
試験内容
精神保健福祉士国家試験は、筆記試験の方式で行われます。科目や出題形式、試験地の情報を、以下にまとめました。
試験科目
精神保健福祉士国家試験の出題範囲は、下記の9科目群です。
- 精神医学と精神医療
- 現代の精神保健の課題と支援
- 精神保健福祉の原理
- ソーシャルワークの理論と方法(専門)
- 精神障害リハビリテーション論、精神保健福祉制度論
- 医学概論、心理学と心理的支援、社会学と社会システム
- 社会福祉の原理と政策、社会保障、権利擁護を支える法制度
- 地域福祉と包括的支援体制、障害者福祉、刑事司法と福祉
- ソーシャルワークの基盤と専門職、ソーシャルワークの理論と方法、社会福祉調査の基礎
精神保健福祉士に必要な、精神障がいや社会福祉、心理学などに関する知識やスキルが問われる試験科目です。
出題形式
問題数は全132問で、試験時間は230分です。五肢択一を基本とする多肢選択形式(複数の選択肢から正解を1つ選ぶ形式)で出題されます。試験時間と問題数から考えると、1問あたり1分45秒ほどしかかけられないため、スピーディーに解答する必要があるでしょう。
試験地
2024年度における精神保健福祉士国家試験の開催地は、「北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県」の全国7ヶ所です。申込時に希望の試験地を選択できるため、自分が受験しやすい地域を選びましょう。
合格基準・合格点
精神保健福祉士国家試験は、総得点の60%以上が合格基準です。実際の合格点は、合格基準を目安としつつ、その年の試験問題の難易度に応じて補正されます。
厚生労働省の「第26回精神保健福祉士国家試験の合格基準及び正答について」によると、2023年度の第26回試験では、総得点163点中95点以上が合格となりました。
なお、精神保健福祉士に受かるためには、合格点を満たすことに加え、9科目群すべてで得点することも必要です。
合格率の推移
精神保健福祉士国家試験の近年の合格率は、60~70%となっています。厚生労働省の「第26回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します」によると、第22回(2019年度)~第26回(2023年度)の合格率の推移は、以下のとおりです。
| 第22回 | 第23回 | 第24回 | 第25回 | 第26回 | |
| 受験者数 | 6,633人 | 6,165人 | 6,502人 | 7,024人 | 6,978人 |
| 合格者数 | 4,119人 | 3,955人 | 4,267人 | 4,996人 | 4,911人 |
| 合格率 | 62.1% | 64.2% | 65.6% | 71.1% | 70.4% |
参考:厚生労働省「第26回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します」
2023年度(第26回)の精神保健福祉士国家試験の合格率は70.4%で、6,978人が受験し、4,911人が合格しました。これは、社会福祉士の合格率よりも高い割合です。
試験日程
精神保健福祉士国家試験は、例年2月上旬の土日に、2日間に分けて開催されます。9月上旬~10月上旬ごろに申し込みを行い、2月に試験を受け、3月上旬に合格発表という流れです。
以下で、2024年度の試験のスケジュールを確認してみましょう。
| 受験申込期間 | 2024年9月5日(木曜日)~10月4日(金曜日) |
| 試験日 | 2025年2月1日(土曜日)・2月2日(日曜日) |
| 合格発表日 | 2025年3月4日(火曜日) |
受験に関する書類は、書留郵便で提出します。過去に試験を受験していて、受験資格が確定している方は、インターネットからの受験申込手続きも可能です。合格発表は試験センターのWebサイトで行われ、後日結果通知が郵送されます。
出典
厚生労働省「第26回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します」(2024年11月27日)
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[精神保健福祉士国家試験] 合格基準」(2024年11月27日)
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[精神保健福祉士国家試験] 試験概要」(2024年11月27日)
精神保健福祉士の仕事内容
精神保健福祉士の主な仕事内容は、精神障がいがある方の相談に乗り、助言や指導を行うことです。相談者が自立した生活を送るための支援を行い、社会復帰をサポートする役割もあります。精神保健福祉士の具体的な業務内容は、従事する分野によって異なるようです。
医療分野の仕事内容
医療分野で働く精神保健福祉士の主な仕事は、精神障がいがある入院患者さんの支援です。医療職と連携して自立支援のための援助を行ったり、退院後の生活に向けて支援の調整を行ったりします。患者さんの入院調整を担当することもあるでしょう。また、人権擁護の観点から、患者さんに適切な医療が提供されているかチェックする役割も担います。
障害者福祉分野の仕事内容
障害者福祉分野で重要となる業務は、精神障がいがある方が安心して地域生活を送れるよう、必要な福祉サービスへつなげることです。生活スキルの訓練や就労支援、退院後の住まい探しなどを行い、自立した生活を送れるようにサポートします。
行政分野の仕事内容
行政分野で働く場合は、行政の職員として勤務し、住民の相談対応を行います。具体的な業務は、利用できる公的サービスを紹介したり、利用申請の対応をしたりすることです。また、すべての人が暮らしやすい地域を作るための計画策定に携わることもあるでしょう。
学校教育分野の仕事内容
学校で働く精神保健福祉士は、児童が抱える問題を解決する役割を担います。虐待やいじめ、不登校など、対応が必要な問題はさまざまです。状況を改善するためには、教師・保護者・外部機関との連携が求められます。また、教員のメンタルヘルスや、児童を守る仕組みづくりに関わることもあるようです。
産業分野の仕事内容
産業分野における精神保健福祉士の仕事は、企業で働く職員が健康で生き生きと働けるよう、職場環境を整備することです。
過度なストレスによる精神疾患の予防やメンタルケア、ワーク・ライフ・バランスを整えるために必要な支援を実施。具体的には、ストレスチェックで高ストレス者と判定された職員との面談や、精神障がいのある職員の労働に関する助言などを行います。精神保健福祉士の専門性は、職員の相談に乗るだけではなく、労働環境を改善するための連携にも活かせるでしょう。
司法分野の仕事内容
司法分野で働く精神保健福祉士は、精神障がいがあり、更生を目指す方の社会復帰を支援するのが仕事です。適切な医療の提供や再犯防止のための訓練、外部機関との連携といった業務を担当します。
精神保健福祉士の就職先
精神保健福祉士は、精神障がいのある方を支援している医療・福祉施設や行政機関など、多くの場所で活躍できる専門職です。具体的な就職先としては、以下が挙げられます。
- 精神科病院
- 精神病床や精神科のある病院・クリニック
- 保健所
- 精神保健福祉センター
- 福祉事務所
- 地域活動支援センター
- 障害者グループホーム
- 就労継続支援事業所
- 相談支援事業所
- 教育機関
- 介護施設
- 一般企業
精神保健福祉士は、福祉事務所や相談支援事務所などの福祉関係の施設だけではなく、学校や一般企業などでも働くことができます。求人に記載される職種名も、「精神科ソーシャルワーカー」「スクールカウンセラー」など、さまざまな分類があるようです。
就職先によって、支援内容や対象者が異なるため、どのような仕事をしたいのか考えて職場を選ぶと良いでしょう。
▼関連記事
福祉の仕事にはどんな種類がある?介護や児童福祉、医療に関する32の職種
精神保健福祉士の働き方
勤務時間や休日、業務スケジュールなど、精神保健福祉士の働き方も確認してみましょう。
勤務時間や休日
精神保健福祉士は、一般的に日勤のみで1日8時間労働です。ただし、時間外労働がある場合もあり、シフト制か固定休みかは職場によって異なります。行政や一般企業は土日休みが基本ですが、医療機関や福祉施設で働く場合は、シフト制の可能性があるでしょう。
1日のスケジュール
就職先によって業務内容も異なるため、1日のスケジュールにも違いがあります。病院で働く精神保健福祉士の1日の業務スケジュール例は、以下のとおりです。
| 午前8時30分 | 出勤、申し送り、カルテチェック |
| 午前9時30分 | 入院患者の受け入れ準備 |
| 午前10時 | 電話相談、外来相談、事務処理 |
| 正午 | 昼休憩 |
| 午後1時 | 患者さんとの面談、カンファレンス |
| 午後4時 | 関係者・行政との情報共有 |
| 午後5時 | 申し送り |
| 午後5時30分 | 退勤 |
医療機関に勤務する精神保健福祉士は、患者さんの相談対応や他職種との連携をメインに、記録作成といった事務作業も行います。
精神保健福祉士の年収
公益財団法人社会福祉振興・試験センターの「令和2年度社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査結果(p.87)」によると、2019年における精神保健福祉士の平均年収は、404万円です。
同資料(p.90)をもとに、精神保健福祉士の施設・事業所別の平均年収を、以下にまとめました。
| 施設形態 | 平均年収 |
| 高齢者福祉関係の施設 | 394万円 |
| 障害者福祉関係の施設 | 386万円 |
| 児童・母子福祉関係の施設 | 416万円 |
| 生活保護関係の施設 | 455万円 |
| 地域福祉関係の施設 | 431万円 |
| 生活困窮者自立支援関係の施設 | 351万円 |
| 医療関係の施設 | 396万円 |
| 学校教育関係の施設 | 315万円 |
| 就業支援関係の施設 | 384万円 |
| 司法関係の施設 | 521万円 |
| 行政機関の施設 | 485万円 |
| その他の施設 | 373万円 |
参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「令和2年度社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査結果(p.90)」
同じ精神保健福祉士でも、職場によって年収に差があるようです。精神保健福祉士としての知識に加えて、司法や行政に関する知識も求められる職場は、年収が高い傾向にあります。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「令和2年度社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査結果」(2024年11月27日)
精神保健福祉士を取得するメリット
精神保健福祉士の資格を取得すると、就職・転職の選択肢が増えたり、高い給与が見込めたりするといった、多くのメリットがあります。
就職・転職の選択肢が多い
資格取得のメリットとして、就職・転職の選択肢が多く、自分の希望に沿った就職先を選びやすいことが挙げられます。たとえば、ケースワーカーや生活相談員、母子支援員は、精神保健福祉士が資格要件の一つです。また、福祉の分野においてできる仕事の幅が広がることや、転職の際にスキルをアピールできることも、資格取得のメリットといえます。
国家資格で専門性が保証される
精神保健福祉士は、資格を取得した人だけが名乗ることができる、名称独占の国家資格です。取得すると高い専門性が保証され、手に職をつけられます。一度取得すると資格を更新する必要がなく、一生役立つ資格です。
介護業界内で給与水準が高い
介護業界の中で給与水準が高いことも、精神保健福祉士の魅力です。介護福祉士の平均年収が292万円なのに対し、精神保健福祉士の平均年収は404万円で、100万円近く平均年収が高くなっています。
給与水準が高い理由は、行政分野など活躍の幅が広く、専門性が高く評価されているためと考えられるでしょう。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「令和2年度社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査結果」(2024年11月27日)
今後も需要が見込まれる
今後、精神保健福祉士の需要が見込まれることからも、資格を取得するメリットがあるといえるでしょう。
厚生労働省の「第13回「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」参考資料(p.2)」を見ると、精神疾患を患う方の数は年々増加していることが分かります。メンタルヘルスの問題は、医療機関だけでは解決できない場合もあり、地域包括ケアシステムが重要。連携の中心となるポジションの精神保健福祉士は、社会から必要とされる職業です。
出典
厚生労働省「第13回「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」」(2024年11月27日)
精神保健福祉士に向いている人
精神保健福祉士には、以下のような方が向いているでしょう。
- 精神障がいがある方を支援したい人
- 仕事を通じて社会貢献をしたい人
- コミュニケーション能力がある人
- 粘り強く問題解決に取り組める人
- 学び続ける姿勢がある人
障がいがある方の支援をするという仕事のため、精神障がいがある方への理解や貢献意識、責任感の強さなどがあると、やりがいを感じながら働けるでしょう。スキルは実務を通して身につけることができるので、興味がある人はぜひ挑戦してみてくださいね。
▼関連記事
福祉の仕事のやりがいや魅力とは?長く働くためのポイントをご紹介!
精神保健福祉士によくある質問
ここでは、精神保健福祉士に関してよくある質問に回答します。
社会人が精神保健福祉士になるには?
社会人が精神保健福祉士になるには、大学や養成施設に通って受験資格を満たし、国家試験に合格する必要があります。すでに保健福祉系の大学・短大を卒業し、必修科目を修了している方は、所定の相談援助の実務経験を積むことで受験要件を満たせるでしょう。保健福祉系の大学・短期大学を卒業していない方は、養成施設を卒業する必要があります。働きながら精神保健福祉士を目指す場合は、通信講座とスクーリングを組み合わせられる教育機関での取得がおすすめ。休日や仕事終わりの時間を有効活用し、効率的に資格取得を目指せます。
精神保健福祉士は通信講座で取得できますか?
精神保健福祉士は、通信講座の受講のみでは取得できません。e‐ラーニングやオンデマンド授業により通信講座を提供しているところもありますが、実習やスクーリングが必要な内容もあるため、一定日数の通学が必須となります。
精神保健福祉士は仕事がないの?
精神保健福祉士が活躍できる職場は多く、就職・転職の際にも幅広い選択肢があります。なかなか精神保健福祉士の求人が見つからないと感じている方は、「医療ソーシャルワーカー」「生活相談員」などの名称で募集を行っていることが多いため、職種名で検索してみてください。
まとめ
精神保健福祉士は、精神障がいがある方の日常生活や社会復帰を支援する職業です。専門知識をもって利用者さんとサービスをつなぎ、的確なアドバイスと支援を行います。精神保健福祉士は、受験資格を満たし、国家試験に合格することで取得できる、専門性の高い資格です。
医療・障害福祉・行政・学校教育・産業・司法など、精神保健福祉士が活躍できる分野は幅広く、就職先もさまざま。医療分野では入院患者さんへの支援、行政分野では住民の相談対応、司法分野では更生を目指す方の社会復帰の支援を行います。
精神保健福祉士として働きたい方は、ぜひレバウェル介護(旧 きらケア)をご利用ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した転職エージェントです。希望の分野や条件に合わせて、専任のキャリアアドバイザーが求人をご紹介し、就職・転職をサポートします。サービスは無料なので、ぜひ気軽にご相談ください。
働きながら資格を取る方法教えます
 精神保健福祉士の求人一覧はこちら
精神保健福祉士の求人一覧はこちら