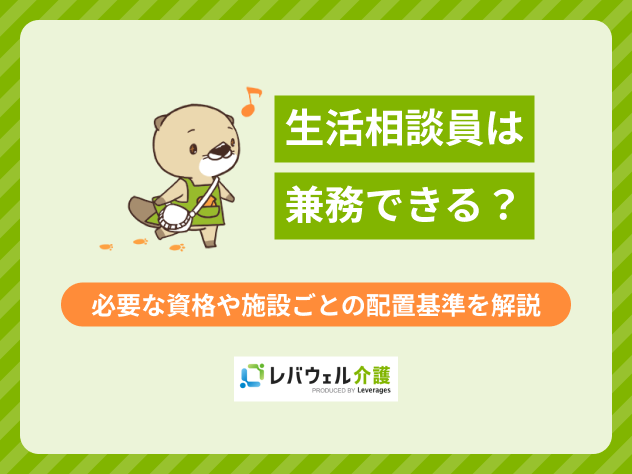
この記事のまとめ
- 生活相談員が兼務できる職種は、介護職員やケアマネジャー、管理者など
- 生活相談員がほかの職種と兼務するには、配置基準を満たす必要がある
- 生活相談員が兼務するメリットは、スキルアップにつながることなど
「生活相談員はほかの職種と兼務できるの?」と気になる方もいるでしょう。生活相談員が兼務できる職種は、介護職員やケアマネジャー、管理者などです。この記事では、生活相談員が兼務できる主な職種と要件をまとめました。生活相談員の施設形態ごとの配置基準も解説します。兼務のメリットもご紹介するので、生活相談員への転職を考えている方は、ご一読ください。
生活相談員とはどんな仕事?必要資格や給料、やりがいをご紹介!生活相談員とは
生活相談員は、介護事業所の窓口として、利用者さんと介護サービスをつなぐ役割を担っています。主な仕事内容は、利用者さんとご家族の相談対応や契約業務、他職種との連絡・調整などです。
生活相談員の仕事について詳しく知りたい方は、「生活相談員に転職したい方必見!必要な資格や仕事内容、介護求人の探し方」の記事もチェックしてみてください。
今の職場に満足していますか?
生活相談員が兼務できる職種
生活相談員は、介護職員といった職種を兼務することも少なくありません。ここでは、生活相談員が兼務できる職種をまとめました。なお、兼務の条件は介護施設や事業所、自治体によって異なるため、参考までにご覧ください。
介護職員
生活相談員は、介護職員との兼務が可能です。介護職員は、利用者さんと直接関わり、介護サービスを提供します。基本的には無資格・未経験から始められる職種です。人員確保や利用者さんの状況把握を目的に、生活相談員が介護職員を兼務する職場もあります。入所施設では、介護職員が夜勤に入るため、兼務する場合は勤務時間も調べておくと安心です。
介護職員の仕事内容について、詳しくは「介護職の仕事内容とは?資格は必要?やりがいやメリットもご紹介」の記事をご一読ください。
ケアマネジャー(介護支援専門員)
それぞれの業務に支障がなく、利用者さんの支援に影響がない場合、生活相談員とケアマネジャーを兼務できるようです。ケアマネジャーの資格があると生活相談員の要件を満たせる自治体が多いため、入居型の施設では兼務することも少なくありません。
なお、ケアマネジャーとして従事するには、介護支援専門員の資格を取得する必要があります。ケアマネジャーになる方法については、「ケアマネジャーになるには最短で何年?介護支援専門員の受験資格を解説」の記事にまとめているので、気になる方はチェックしてみてください。
管理者
生活相談員は、要件を満たしていれば、管理者を兼務できます。管理者は、施設の運営や職員のマネジメントなどを行う職種です。
管理者の要件は、施設によって異なります。たとえば、有料老人ホームやデイサービス(通所介護事業所)で働く管理者には特定の要件がないため、生活相談員が兼務しやすい傾向にあるでしょう。
また、特別養護老人ホーム(特養)の管理者にも要件はありませんが、施設長になるには「社会福祉主事任用資格の取得」「社会福祉事業に2年以上従事」「社会福祉施設長資格認定講習会の受講」のいずれかを満たす必要があるので、注意が必要です。
管理者の要件については、「介護施設で管理職になるには何が必要?仕事内容や平均年収をご紹介」の記事もご一読ください。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「施設管理者(介護施設)」(2024年12月10日)
厚生労働省「施設長の資格要件等」(2024年12月10日)
看護職員
看護師もしくは准看護師の資格を有しており、生活相談員の要件も満たしていれば、兼務が可能です。介護施設の看護職員は、医療職として利用者さんの健康を管理したり、医療ケアを行ったりします。
機能訓練指導員
機能訓練指導員と生活相談員も、両方の要件を満たしていれば、兼務できます。機能訓練指導員の資格要件は、以下のとおりです。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護職員
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- 一定の実務経験を有するはり師・きゅう師
機能訓練指導員に関しては、兼務することで加算を取得できない可能性があります。そのため、自治体や施設の要件を必ず確認しましょう。
なお、生活相談員と他職種を兼務するには、いずれの配置基準も満たす必要があるので、注意が必要です。
出典
厚生労働省「第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料」(2024年12月10日)
介護事業所における生活相談員の兼務状況
「生活相談員は絶対に兼務しないといけないの?」と気になる方もいるでしょう。
厚生労働省の「人員配置基準等(介護人材の確保と介護現場の生産性の向上)(p.20)」によると、介護事業所(施設系)で働く生活相談員のうち、およそ7割は同一事業所内で兼務をしています。施設にもよりますが、生活相談員はほかの業務と兼務する場合が多いといえるでしょう。
出典
厚生労働省「第223回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2024年12月10日)
生活相談員の配置基準
生活相談員とほかの職種を兼務するためには、介護施設や事業所の配置基準を満たす必要があります。以下で、介護施設ごとの生活相談員の配置基準をまとめました。
特別養護老人ホーム(特養)
特別養護老人ホーム(特養)とは、自宅での生活が難しい高齢者の方をサポートする、入所型の介護施設です。原則として、要介護3以上の認定を受けた、65歳以上の方が入所できます。
特養では、利用者さん100人につき、常勤の生活相談員1人以上を配置しなければいけません。基本的に生活相談員は専従配置ですが、業務に支障がない範囲であれば、機能訓練指導員やケアマネジャーとの兼務が可能です。
特養の生活相談員について詳しくは、「特養の生活相談員の仕事内容を紹介!資格要件や必要なスキルもチェック!」の記事で解説しています。
出典
厚生労働省「第190回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2024年12月10日)
デイサービス(通所介護)
デイサービスとは、日帰りで通う利用者さんに対して、介護サービスを提供する事業所です。デイサービスでは、事業所ごとのサービス提供時間に応じて、専従の生活相談員を1人以上配置しなければなりません。また、生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤であることも必要です。
デイサービスの生活相談員については、「デイサービスの生活相談員の仕事内容を紹介!必要な資格ややりがいも解説」の記事で解説しています。
出典
厚生労働省「第180回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2024年12月10日)
ショートステイ(短期入所生活介護)
ショートステイとは、普段は自宅で生活していて介護を必要とする方が、一時的に入所する施設です。
ショートステイでは、利用者さん100人につき、生活相談員1人以上の配置が求められます。生活相談員のうち1人は常勤であることも条件です。ただし、利用定員が20人未満の併設事業所には、常勤配置の規定がありません。
出典
厚生労働省「第219回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2024年12月10日)
▼関連記事
ショートステイの仕事内容とは?介護職員の1日の流れをご紹介
生活相談員がほかの職種を兼務するメリット
生活相談員がほかの職種を兼務するメリットは、「スキルアップにつながる」「現場の状況を把握できる」などです。
スキルアップにつながる
ほかの職種の業務を兼務することで、介護従事者としてのスキルアップにつながります。今後ほかの職種への転職を考えている場合、生活相談員と兼務することで、スキルや経験を活かせる可能性があるでしょう。
現場の状況を把握できる
ほかの職種と兼務することで、介護現場の状況を把握できます。生活相談員は、利用者さんと介護サービスをつなぐ職種です。介護サービスの現状を知っておくことで、生活相談員として円滑な連携・調整を行うために活かせるでしょう。
また、利用者さんと関わる時間が増えれば、信頼関係の構築にもつながります。「生活相談員の仕事に活かしたい」という方は、現場で働く職種との兼務がおすすめです。
給与アップにつながる可能性がある
施設によっては、兼務することで給与が上がる可能性があるでしょう。また、介護職員や看護職員との兼務で夜勤に出た場合、基本給に加えて夜勤手当がつきます。
生活相談員の給与については、「生活相談員の給料は安い?高い?仕事内容から平均年収まで」の記事もご一読ください。
生活相談員がほかの職種を兼務するデメリット
生活相談員とほかの職種を兼務することで、デメリットを感じる方もいるようです。「兼務は大変そう…」と不安な方は、希望の働き方に合うかチェックしてみてください。
業務量が増える
生活相談員とほかの職種を兼務することで、業務量が増える傾向にあります。特に、生活相談員としての経験が浅いまま兼務をすると、仕事に余裕がなくなる方もいるようです。「生活相談員の業務を覚えきれていない」という方には、兼務はおすすめできません。
幅広い知識やスキルを求められる
ほかの職種と兼務すると、生活相談員以外の知識やスキルも求められます。特に、看護職員や機能訓練指導員といった、資格要件のある職種は、専門的な知識が必要になるでしょう。兼務することで業務範囲が広がるので、新しいスキルを身につける余裕も求められます。
夜勤に入る可能性がある
入居型の施設の場合、介護職員や看護職員との兼務で、夜勤に入る可能性があるでしょう。夜勤に入ることで手当がつくというメリットもありますが、生活リズムが不規則になりやすいというデメリットもあります。そのため、「日勤のみで働きたい」という方は、夜勤のある職種との兼務は避けたほうが良いかもしれません。
▼関連記事
生活相談員のやりがいを解説!働くメリットや魅力、仕事内容とは
生活相談員の兼務についてよくある質問
ここでは、生活相談員の兼務についてよくある質問にお答えします。「生活相談員への転職を考えている」という方は、ご一読ください。
特別養護老人ホーム(特養)の生活相談員は兼務できますか?
特別養護老人ホーム(特養)の生活相談員は、ほかの職種との兼務が可能です。特養の生活相談員が兼務できる職種は、介護職員やケアマネジャー(介護支援専門員)、機能訓練指導員などです。生活相談員と兼務する職種の配置基準や要件を、いずれも満たしていれば、兼務できます。なお、ケアマネジャーや機能訓練指導員には資格要件があるので、兼務を考えている方は確認してみてください。
特養の生活相談員の配置基準については、この記事の「特別養護老人ホーム(特養)」で解説しているので、あわせてご覧ください。
管理者と生活相談員は兼務できますか?
働く自治体や施設にもよりますが、基本的に管理者と生活相談員は兼務できます。ただし、管理者と生活相談員の配置基準と要件を、両方とも満たさなければいけません。管理者の要件は施設によって異なります。
生活相談員と兼務が可能な職種や、管理者の要件は、この記事の「生活相談員が兼務できる職種」で解説しているので、チェックしてみてください。
まとめ
生活相談員が兼務できる職種は、介護職員やケアマネジャー、管理者などです。兼務するには、生活相談員と兼務する職種の両方で、配置基準と要件を満たす必要があります。配置基準は施設形態によって異なるため、自分の職場や希望する転職先の情報を確認しておきましょう。
生活相談員がほかの職種を兼務すると、スキルアップにつながるメリットがある一方で、業務量が増えるデメリットもあります。そのため、生活相談員の仕事をする際は、自分に合った働き方かどうか確認することが大切です。
生活相談員の仕事に興味がある方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に精通した転職エージェント。専任のアドバイザーが、あなたの希望をしっかりとヒアリングします。
そのため、豊富な介護求人のなかから、資格や経験を活かせる職場や、希望条件に合った施設をご紹介することが可能です。「生活相談員に転職したい」「生活相談員とほかの職種を兼務したい」という方は、気軽にお問い合わせください。
今の職場に満足していますか?
 特別養護老人ホーム(特養) の求人一覧はこちら
特別養護老人ホーム(特養) の求人一覧はこちら