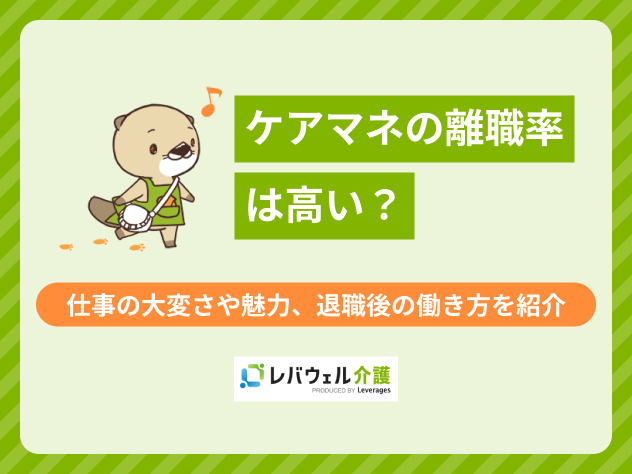
この記事のまとめ
- ケアマネの離職率は10%で、平均より高いわけではない
- ケアマネの離職率が高くなる理由には、業務量が多いことなどがある
- ケアマネの仕事の魅力は、給料が高いことや体力的な負担が少ないこと
「ケアマネの離職率はどれくらい?」という疑問をお持ちの方もいるでしょう。ケアマネの離職率は、10.0%です。退職の理由としては、業務量の多さや給料に対する不満があると考えられます。この記事では、ケアマネの離職率はほかの仕事よりも高いのかを解説します。仕事の大変さや魅力、業務内容もまとめました。ケアマネの退職後の働き方についても触れているので、転職を検討中の方はぜひ参考にしてください。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどんな仕事?業務内容や役割を解説!ケアマネジャーの離職率は高い?
ケアマネジャーの離職率は高いのか、ほかの職種と比較してみましょう。
ケアマネジャーとほかの介護従事者の離職率の比較
ケアマネの離職率は、介護従事者の中では比較的高い傾向にあるようです。
公益財団法人介護労働安定センターの「令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要について(p.6)」によると、ケアマネ(介護支援専門員)の離職率は10.0%です。訪問介護員と介護職員以外の5職種の介護従事者のなかでは、看護職員の離職率15.3%に次いで高い結果でした。
出典
公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査」(2024年11月26日)
ケアマネジャーとほかの産業の離職率の比較
厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概要:入職と離職の推移(p.1)」によると、2023年の全産業の離職率は15.4%です。
また、同調査の「産業別の入職と離職(p1)」によると、医療・福祉産業の離職率は14.6%で、ケアマネの離職率10.0%より高い割合となっています。ケアマネの離職率は、ほかの仕事と比較して、決して高いわけではないといえるでしょう。
出典
厚生労働省「令和5年 雇用動向調査結果の概要」(2024年11月26日)
今の職場に満足していますか?
▼関連記事
ケアマネを辞めてよかった?退職理由と悩みの解決策、転職の注意点を紹介!
ケアマネジャーの離職率が高くなる理由
ケアマネが定着せず離職率が高くなる場合の理由としては、業務の多忙さや、身体的・精神的な負担の大きさがあるようです。どのような大変さがあるのか、具体的にご紹介します。
業務量が多い
業務量の多さは、ケアマネにとって大きな負担となります。事務作業や利用者さんの自宅への訪問、緊急時の対応など、業務は多様です。介護施設で働く場合は、介護職との兼務が求められることもあるでしょう。
事業所にいるケアマネが少ないと多忙になりやすく、休日にも連絡が入るなど、プライベートの時間を十分に確保できなくなることもあるようです。
忙しさと給与が見合わない
ケアマネの忙しさと給料が見合わないと感じる人もいます。ケアマネは担当件数の上限が決められていますが、たとえ上限いっぱいまで働いても給料は変わりません。忙しいなか仕事をこなしても、自身の頑張りが給料に反映されないと、不満を抱くこともあるでしょう。
人間関係に悩みがある
人間関係に悩んで離職を考える方も少なくありません。ケアマネは、介護職員・医師・看護師など、さまざまな職種と連携を取りながら働く必要があります。そのため、人間関係が良くない場合、ストレスを抱えやすい立場です。
また、業務の中で、利用者さんや家族からクレームを受けたり、施設と利用者さんの板挟みになったりすることも、悩みの一つといえます。
精神的な負担が大きい
ケアマネは利用者さんに頼られる存在なので、責任感から精神的な負担を感じることがあるようです。提案するケアプランによって利用者さんの生活が大きく変わる可能性がありますが、施設にケアマネが一人しかいない場合は、相談することもできません。一人で責任を抱えることが重荷になり、退職を考えるケアマネもいるようです。
資格の更新研修が負担
ケアマネは、資格更新が負担となって離職する場合もあるようです。ケアマネに必要な介護支援専門員の資格を維持するには、5年に1度更新研修を受けなければなりません。更新費用がかかったり、忙しい仕事の合間に研修を受けたりする必要があるため、大変に感じる方もいるでしょう。
ケアマネ業務に専念できない
施設によっては、ケアマネ業務に専念できないこともあります。人手不足で介護業務との兼任を求められるなど、ケアマネ業務に十分な時間を確保できない場合、自分のやりたい仕事や理想の働き方とのギャップを感じる場合があるでしょう。ケアマネの仕事に集中したいと考える人にとっては、退職を考える理由になるようです。
担当地域の変更がきつい
担当地域が変更になることで、負担や悩みが増え、離職することもあるでしょう。事業所が複数の施設を運営している場合、異動が生じることもあります。
居宅ケアマネの場合、利用者さんの自宅を訪問しなければなりません。担当地域が変更になると、土地勘のない場所で働くことになり、移動を負担に感じる方もいます。また、異動先の市区町村独自の制度や公共施設を把握したり、スタッフ・利用者さんと一から関係性を構築したりすることが大変で、「仕事を続けるのが難しい」と考える方もいるようです。
▼関連記事
ケアマネになれたけどノイローゼ寸前!限界を感じたときの解決法とは
ケアマネジャーの業務内容
ケアマネは、ケアマネジメント業務に加えて、給付管理や要介護認定の申請代行といった業務も担当します。以下で、それぞれの業務内容を解説します。
ケアマネジメント業務
ケアマネの主要な業務が、利用者さんのケアマネジメントです。利用者さんやご家族と面談をして、ケアプランの作成・提案を行います。サービス開始後に、利用者さんやご家族の状況をモニタリングし、必要に応じてケアプランの変更を検討することも大事な仕事です。また、サービス利用を検討している方からの、申請・行政手続きなどに関する相談対応にも対応します。
介護保険の給付管理
介護報酬を受け取るための給付管理も行います。介護報酬の受け取りには、介護保険サービス利用票の作成・支払限度額の確認・国民健康保険団体連合会への請求という作業が必要です。ケアマネは、介護報酬請求に必要な、給付管理票の作成を担当します。書類に不備がないよう、注意深く行わなければならない業務です。
居宅介護支援事業所などで働く場合、ほかの介護事業所の介護報酬請求にも関わる業務のため、期日を守り正確に対応する必要があります。
要介護認定の申請代行
ケアマネは、要介護認定の申請手続きを手伝うこともあります。利用者さんやご家族が窓口で手続きすることも可能ですが、要介護認定の申請に慣れていないため、ケアマネが代行することが多いようです。
ケアマネジャーの仕事の魅力
ケアマネの仕事の魅力は、給与が高いことや体力的な負担が少ないことです。魅力ややりがいを理解することで、モチベーションを保ちながら働けるでしょう。ここでは、ケアマネの仕事の魅力を詳しくご紹介します。
介護職員よりも給与が高い
ケアマネの魅力の一つとして、介護職員よりも給与水準が高いことが挙げられます。
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.119)」によると、介護職員の平均給与が317,540円なのに対し、ケアマネ(介護支援専門員)の平均給与は361,770円。ケアマネの平均給与は、介護職員と比較して44,230円高い結果です。
業務の専門性が高いことや、資格が必須の職種であることが、ケアマネの給与の高さにつながっていると考えられます。
出典
厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2024年11月26日)
体力的な負担が少ない
体力的な負担が少ない点も、ケアマネの仕事の魅力の一つです。ケアマネの業務は、ケアプラン作成や書類の整理、相談受付が中心で、介護職員よりも介助業務の割合が少ないという特徴があります。
特に、居宅ケアマネの場合は、介護業務を兼務することがないため、身体への負担が少ないでしょう。腰痛などの悩みを抱えにくいことから、体力に自信がない人でも、長く働ける仕事といえます。
日々の業務にやりがいを感じられる
ケアマネは、日々の業務でやりがいを感じられる場面が多くあります。自分の作成したケアプランによって利用者さんの生活の質が向上したり、ご家族の介護負担が軽減されたりすることで、充足感を得られるでしょう。
また、相談援助により利用者さんやご家族と信頼関係を築けることや、仕事を通して周囲の人からの信頼を得られることも、やりがいの一つです。
ケアマネジャー退職後の働き方
ケアマネの仕事がつらいと感じている方は、転職を検討する選択肢もあります。職場や職種を変えることで、理想に近い条件で無理なく働ける可能性があるでしょう。
別の職場でケアマネとして働く
「給与や業務量に不満はあるが、ケアマネの仕事は続けたい」という方は、資格を活かして別の職場に転職することを検討してみましょう。同じケアマネの仕事でも、転職すると勤務条件が改善する可能性があります。ケアマネは需要が高い職種なので、多くの選択肢の中から希望に沿った求人を選べるはずです。
介護業界でケアマネ以外の職種に転職する
「ケアマネは辞めたいけど、介護に関わる仕事をしたい」という方は、介護職員や介護認定調査員など、別の職種へ転職するのがおすすめです。離職して職種が変わっても、ケアマネとして介護業界で培った経験や知識を活かせます。ケアマネの資格と経験を持っていることで、転職先でもスキルを活かして活躍できるでしょう。
介護業界以外の仕事に転職する
介護業界以外の仕事に挑戦したい方もいるでしょう。ケアマネの仕事で培ったコミュニケーション能力や事務スキルは、事務職・接客業・総務など、さまざまな仕事に活かすことができます。そのため、興味がある仕事がある場合は、転職を考えてみても良いでしょう。
ただし、未経験の仕事への転職は経験者よりもハードルが高い傾向にあるので、離職期間ができないよう、働きながら求職活動をするのがおすすめです。
▼関連記事
ケアマネ退職後の仕事には何がある?役立つ資格や転職活動のポイントを紹介
ケアマネジャーの退職についてよくある質問
ここからは、ケアマネの退職についてよくある質問に回答します。
ケアマネの退職時に多いトラブルと対処法を教えてください
ケアマネの退職時に多いトラブルとしては、上司から引き止められたり、引き継ぎが不十分で後任に迷惑がかかったりすることが挙げられます。トラブルを防ぐためには、相手が納得できる退職理由を伝えることや、利用者さんが困らないようしっかり引き継ぎをすることが大切です。退職に関するトラブルや対処法は、「ケアマネの退職トラブルとは?回避方法や違法になるケース、対策法を解説」の記事にもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
ケアマネの仕事で心が折れる理由は何ですか?
ケアマネは業務量が多い傾向にあるため、日々の忙しさから心が折れて離職を考える人もいるようです。また、資格更新の負担が大きく、仕事を続けることを大変に感じる人もいるでしょう。もしも、ケアマネの仕事をしていて心が折れてしまいそうなときは、周囲に相談してみるのがおすすめです。今の職場で状況の改善が見込めない場合は、転職する選択肢もあります。
まとめ
ケアマネの離職率は、平均と比較して高いわけではありません。ケアマネの離職率が高い職場は、業務量に対して給与が見合っていなかったり、人間関係に問題があったりする可能性があるでしょう。利用者さんの生活に直結する業務の責任の重さや、担当地域の変更、クレーム対応などから、精神的な負担を感じる方もいるようです。
ケアマネの仕事には大変な部分もありますが、介護職員よりも給与水準が高かったり、体力的な負担が小さかったりする魅力もあります。現在の職場環境に不満を感じている方は、資格を活かして転職を検討する選択肢もあるでしょう。ケアマネとして働くのはもちろんのこと、介護職や事務職、接客業など、ケアマネとして培った経験は幅広い仕事に活かせます。
ケアマネの資格を活かして転職したい方は、ぜひレバウェル介護(旧 きらケア)をご利用ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した転職エージェントです。ケアマネ・ケアマネ以外の職種など、希望に沿った介護求人をご紹介し、転職をサポートいたします。サービスは無料なので、ぜひ気軽にご相談ください。
今の職場に満足していますか?
 ケアマネジャーの求人一覧はこちら
ケアマネジャーの求人一覧はこちら