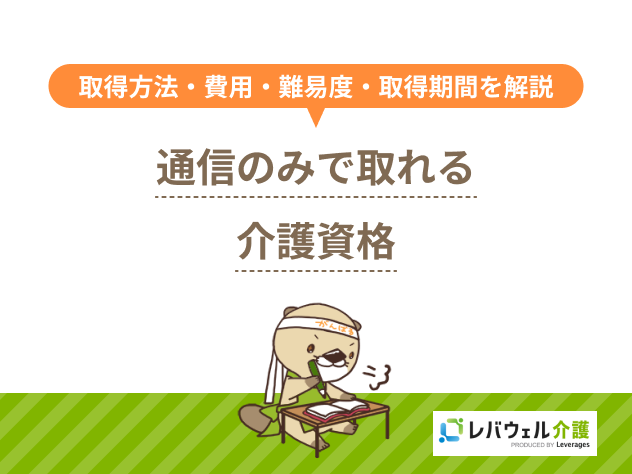
この記事のまとめ
- 通信のみで取得できる介護の資格は、「レクリエーション介護士2級」など
- 通信のみだと自分のペースで勉強できるが、計画的に学習するのは難しい
- 通信講座を利用する際は、どのように活用するか考えて資格を選ぶと良い
「通信のみで取れる介護の資格は?」と気になる方もいるでしょう。通信のみで取得できる介護の資格は、レクリエーション介護士2級や福祉用具専門相談員指定講習、認知症介助士などです。仕事や家庭の事情で通学するのが難しい方も、通信のみでスキルアップを図れます。この記事では、通信講座のみで取得できる介護の資格をご紹介。通信のみで取得するメリット・デメリットも解説するので、ぜひ参考にしてください。
介護資格の種類一覧!取得方法や特徴、メリットを解説します →レバウェル介護の資格スクールはこちら通信のみで取得できる介護の資格
通信のみで取得できる介護の資格は、レクリエーション介護士2級や福祉用具専門相談員指定講習、認知症介助士などです。通信のみで介護の資格を取得する場合、教材やインターネットを使った自宅学習がメインで、講師によるオンライン授業が開催される講座もあります。
通信のみで取得できる介護資格について以下で解説するので、スキルアップを目指す方はぜひ参考にしてみてください。
レクリエーション介護士2級
レクリエーション介護士2級は、日本アクティブコミュニティ協会が認定する資格です。講座の受講を通して、高齢者の方に喜ばれるレクリエーション企画の立て方や実施方法、コミュニケーション技術を学べます。
レクリエーションを行う機会が多いデイサービスや有料老人ホームなどで働く方は、レクリエーション介護士2級の資格を活かしやすいでしょう。
取得方法と費用
レクリエーション介護士2級の通信講座は、筆記試験と添削課題を提出し、合格することで取得可能です。試験や課題に取り組む前に、自宅でテキストを読んだりDVDを視聴したりして勉強します。受講料は3万5,000円程度です。
取得難易度と必要な期間
レクリエーション介護士2級の合格率は公表されていませんが、試験に不合格になっても再試験を受けられるため、難易度は低めのようです。標準的な学習期間は3ヶ月程度の設定となっています。
出典
日本アクティブコミュニティ協会「【公式】レクリエーション介護士:資格取得の流れ」(2024年12月19日)
▼関連記事
レクリエーション介護士とは?資格の取得方法やメリットを分かりやすく解説
福祉用具専門相談員指定講習
福祉用具専門相談員指定講習は、都道府県から指定された事業者が実施する公的な講習会です。修了すれば、「福祉用具専門相談員」として働けます。福祉用具の種類や使い方、点検に必要な知識を学ぶ内容です。受講することで、高齢者や障がいのある方に対し、適切な福祉用具の選定やアドバイスができるようになります。
取得方法と費用
福祉用具専門相談員指定講習は、50時間のカリキュラムを受講し、1時間の修了試験に合格することで修了できます。オンライン研修を採用している実施主体の講習に申し込めば、カリキュラムを通信のみで受講可能です。講習の受講にかかる費用は、4万~5万円程度が相場となっています。
取得難易度と期間
福祉用具専門相談員指定講習の修了試験は、学習内容の理解度を確認するのが目的なので、難易度は高くないでしょう。取得するには、合計51時間の講義と試験をおよそ7日間でこなす必要があります。
▼関連記事
福祉用具専門相談員とは?仕事内容や資格要件、指定講習の概要について解説
認知症介助士
認知症介助士は、日本ケアフィット共育機構が認定する資格です。認知症の基礎知識や、認知症の方に対する適切な応対方法を事例を交えて学べます。資格取得の勉強を通して、認知症の症状や心理状態に対する理解も深められるので、介護や医療現場など、認知症の方に接する機会の多い方におすすめです。
取得方法と費用
認知症介助士は、自宅学習でカリキュラム内容を勉強し、検定試験に合格することで取得可能です。検定試験は、試験会場での受験以外に、自宅からのオンライン受験も選択できます。受験料は3300円です(2024年12月時点)。
取得難易度と期間
認知症介助士の合格率は8割程度と公表されています。公認テキストや試験対策問題集を活用すれば、独学でも十分合格を目指せるでしょう。また、試験のみで取得できる資格のため、計画的に学習すれば1~3ヶ月程度で取得可能です。
出典
公益財団法人日本ケアフィット共育機構「認知症介助士検定試験」(2024年12月19日)
▼関連記事
認知症介助士とは?資格取得の流れや試験概要、勉強方法などを解説
福祉住環境コーディネーター
福祉住環境コーディネーターは、東京商工会議所が認定する資格で、福祉住環境コーディネーター検定試験(R)に合格することで取得できます。試験は、高齢者の方や障がいがある方にとって住みやすい住環境を提案するために必要な知識を問う内容です。
福祉用具専門相談員や介護職員、リハビリ専門職、ケアマネジャーが専門領域を広げるために取得することも少なくありません。
※福祉住環境コーディネーター検定試験(R)は東京商工会議所の登録商標です
取得方法と費用
福祉住環境コーディネーター検定試験(R)は1~3級があり、2級と3級は自宅からのオンラインで受験できます。2級の受験料が7,700円で、3級が5,500円です(2024年12月時点)。
取得難易度と期間
福祉住環境コーディネーター検定試験(R)は、100点満点中70点以上で合格。試験時間は90分です。2024年度の第52回試験では、2級・3級ともに40%程度の合格率となっており、ほかの介護系の資格と比べて難易度は高めといえます。何度も受験すると期間や費用が必要になるので、3ヶ月以上しっかりと対策するのがおすすめです。
出典
東京商工会議所「福祉住環境コーディネーター検定試験(R)」(2024年12月19日)
JADP認定介護食アドバイザー(R)
JADP認定介護食アドバイザー(R)は、日本能力開発推進協会が認定する資格です。通信講座で、高齢者の心身の変化や栄養学、安全で栄養バランスの取れた介護食を提供するスキルを学びます。
利用者さんの噛む力・飲み込む力に合わせたおいしい食事の作り方や、介護食レシピの考案方法を習得可能です。安全な食事介助のスキルも身につけられるので、介護職としてスキルアップしたい方に適した資格といえます。
取得方法と費用
JADP認定介護食アドバイザー(R)を取得するには、課題提出と試験への合格が必要です。まずは、自宅でテキストを使って学習し、添削課題を提出します。カリキュラムを修了し、自宅で検定試験を受けて合格することで、資格を取得可能です。
通信講座の費用は5万~8万円程度で、申込み方法やサポート期間によって変動します。検定試験の受験料は5,600円です(2024年12月時点)。
取得難易度と必要な期間
JADP認定介護食アドバイザー(R)検定試験は、正答率70%以上で合格です。合格率は公表されていないものの、テキストを見ながら受けられて何度でも再受験できるので、取得難易度は高くないでしょう。取得に必要な期間の目安は、3ヶ月程度です。
出典
一般社団法人日本能力開発推進協会「JADP認定介護職アドバイザー(R)」(2024年12月19日)
介護予防健康アドバイザー
介護予防健康アドバイザーは、NESTA(全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会)が監修する資格です。講座では、運動機能・口腔機能を向上させる方法や食事の栄養バランスなど、介護予防に必要な知識を学習します。利用者さんに合う運動の選び方や体を動かすメリット、運動をする際に注意すべきことも知れるので、高齢者の方を運動を通してサポートしたい方におすすめです。
取得方法と費用
介護予防健康アドバイザーになるには、テキストや動画講義を活用して自宅学習を進め、3回の添削課題を提出する必要があります。最終課題が認定試験になっており、合格することで資格を取得可能です。取得費用は一括払いの場合3万4,000円となっています(2024年12月時点)。
取得難易度と必要な期間
介護予防健康アドバイザーは受験資格がなく、誰でも受講できます。また、最終試験はマークシート形式で解答しやすく、仮に落ちてしまっても再受験が可能なので、取得難易度は高くないでしょう。取得期間の目安は3ヶ月程度です。
介護事務管理士(R)
介護事務管理士(R)は、技能認定振興協会が認定する資格で、介護事務管理士技能認定試験への合格で取得できます。取得すると、介護事業所で行う介護報酬請求や受付などの事務スキルがあることを証明できます。介護事務の仕事に携わりたい方や、ケアマネジャーとしてスキルアップしたい方におすすめです。
取得方法と費用
介護事務管理士技能認定試験に受験資格はありません。マークシート形式の試験を自宅で受験し、合格基準を満たせば取得できます。受験日の3日前ごろに試験問題が届くので、テキストや計算機を使いながら問題に解答し、提出期限までに郵送しましょう。受験料は5,500円です(2024年12月時点)。
取得難易度と必要な期間
介護事務管理士認定試験の合格率は70%程度です。試験は毎月1回開催されるため、受験のチャンスは多くあります。試験問題集やテキストを購入して対策する場合、2~3ヶ月程度の学習期間で取得を目指せるでしょう。
▼関連記事
介護事務管理士とはどんな資格?取得するメリットや試験概要、難易度を解説
看取りケアパートナー
看取りケアパートナーは、一般社団法人みんなのプライドが認定する資格講座です。終末期を迎える方が穏やかな最期を迎えられるよう、精神的・身体的な苦痛を取り除き、尊厳ある生活を支援する「看取りケア」について学びます。社会保障制度や緊急時の対応に関する知識も習得可能です。
身につけた知識は、看取り対応を行う特別養護老人ホームや有料老人ホーム、グループホームなどで働く方が受講すると、仕事に活かせるでしょう。
取得方法と費用
看取りケアパートナーを取得するには、テキストを使って自宅で勉強し、3回の添削課題を提出する必要があります。最終課題が認定試験となっており、70点以上で合格です。取得費用は一括の場合3万4,000円となっています(2024年12月時点)。
取得難易度と期間
看取りケアパートナーには受講要件がないため、誰でもチャレンジできます。合格率は公表されていないものの、テキストの内容を押さえていれば課題に対応できるので、取得難易度は低めといえるでしょう。もしも不合格になった場合は、2回まで再試験を受けられます。標準的な学習期間は、3ヶ月程度です。
出典
一般社団法人みんなのプライド「みんなのプライドトップページ」(2024年12月19日)
▼関連記事
看取りケアパートナーの資格取得方法とは?終末期ケア専門士についても紹介
看護助手認定実務者
看護助手認定実務者は、全国医療福祉教育協会が認定する資格です。取得すると、看護師の業務支援や患者さんの介護など、看護助手に必要な知識があることを証明できます。試験範囲には、障がいや疾病、薬物など、医療に関する専門分野も含まれるので、多職種連携を強化したい看護助手や介護職員におすすめの資格です。
取得方法と費用
看護助手認定実務者の資格は、試験を受けて合格することで取得できます。試験は自宅で受験可能です。公式テキストや過去問題集などの教材が豊富なので、試験対策はしやすいでしょう。受験料は4,500~5,000円です(2024年12月時点)。
取得難易度と必要な期間
看護助手認定実務者試験に受験要件はありません。試験は90分でマークシート形式です。合格率は60~80%程度なので、取得難易度は高くないでしょう。なお、標準的な学習期間は3ヶ月程度です。
そのほかの看護助手に役立つ情報は、「看護助手(ナースエイド)に資格は必要?取得方法や試験の合格率を解説!」の記事で紹介しています。
出典
全国医療福祉教育協会「看護助手認定実務者試験」(2024年12月19日)
准サービス介助士
准サービス介助士は、日本ケアフィット共育機構が認定する資格です。高齢者の方や障がいがある方に対する介助の知識や応対方法を学びます。
介助が必要な方をサポートする「おもてなしの心」を大切にしているので、高齢者の方や障がいがある方の気持ちに寄り添った支援方法を身につけたい方におすすめです。介護業界以外で高齢者や障がいのある方に関わることがある人も取得しています。
取得方法と費用
准サービス介助士を取得するには、自宅でテキストやDVDを使って勉強し、課題提出を1回行う必要があります。課題提出の後に検定試験に合格することで、資格を取得できます。受講料は2万2,000円です(2024年12月時点)。
取得難易度と必要な期間
准サービス介助士に受講資格はありません。受講の申込みから6ヶ月以内に検定試験の受験が必要です。2択のマークシートによる筆記試験で、60点以上で合格となります。落ちてしまっても再受験できるので、難易度は低めといえるでしょう。取得期間の目安は、1~3ヶ月程度です。
また、准サービス介助士の上位資格として「サービス介助士」があります。対面教習は必要ですが、その分専門性の高い知識を学べるカリキュラムです。詳しく知りたい方は、「サービス介助士とはどんな資格?受講の流れや取得するメリット、更新方法」の記事をご覧ください。
出典
公益財団法人日本ケアフィット共育機構「准サービス介助士資格取得講座」(2024年12月19日)
終活アドバイザー
終活アドバイザーは、終活アドバイザー協会が認定する資格です。通信講座で、高齢者の方が人生の最期を自分らしく迎えられるようサポートするための知識を学びます。エンディングノートの活用方法や財産相続、葬儀にまつわる知識など、終末期にどのように備えれば良いのかを幅広くカバーする内容です。終活の支援に興味がある方は、取得を考えてみると良いでしょう。利用者さんやご家族の相談に乗ることが多い方におすすめです。
取得方法と費用
終活アドバイザーになるには、テキストを使いながら学習を進め、添削課題を3つ提出する必要があります。最後に検定試験を自宅で受験し、合格することで資格を取得可能です。受験料は一括の場合3万9,000円となっています(2024年12月時点)。
取得難易度と必要な期間
終活アドバイザーの合格率は公表されていません。マークシート方式の試験で正答率60%以上で合格です。落ちても再受験ができるため、取得難易度は高くないでしょう。取得までに必要な期間は4ヶ月程度です。
出典
終活アドバイザー協会「終活アドバイザー講座のご案内」(2024年12月19日)
働きながら資格を取る方法教えます
通信のみで取得できる資格の特徴
通信のみで取得できる介護系の資格の特徴を、以下にまとめました。
- 1つの専門的な領域に特化している
- 受講要件がない
- 合格率が高め
- 資格手当にはつながらないこともある
- スキルアップ目的で取得する人が多い
通信のみで取得できる資格は、受講要件がなかったり、修了試験の合格率が高かったりする傾向にあります。そのため、働きながら自宅学習に取り組んで手軽にスキルアップしたい方におすすめです。
▼関連記事
働きながら取得しやすい介護の資格とは?必要な期間や方法、費用も解説!
通信のみで資格を取得するメリット・デメリット
ここでは、通信のみで資格取得を目指すメリット・デメリットを解説するので、通信講座が自分に合っているかチェックしてみてください。
通信のみで学習するメリット
通信のみで資格を取るメリットは、時間や場所を選ばず自分のペースで学習を進められることです。養成施設やスクールに通う場合はスケジュール調整が必要ですが、通信のみで取得できる資格なら、予定が空いているときに勉強できます。仕事や家庭の都合にも柔軟に対応できるので、無理なく勉強を続けられるのが通信の魅力です。
資格講座ごとに用意された公式テキストを使えば、苦手な分野を繰り返し勉強しやすいでしょう。
通信のみで学習するデメリット
通信のみで資格を取る場合、1人で計画的に勉強を進めなくてはなりません。そのため、黙々と学習スケジュールをこなすのが苦手な方や、勉強するモチベーションを保ちにくい方は、通信のみの学習方法が向いていない可能性があります。
また、自分でテキストの内容を理解しながら読み進めなければならないため、専門性の高い部分は、疑問を解消できない場合があるかもしれません。なかには、学習内容を講師に質問できる通信講座もあるので、活用してみてください。
どれが良い?通信のみで取得できる資格の選び方
通信講座のみで取得できる資格は専門性を絞ったものが多いため、取得した後にどのように活用するかを考えて選ぶのがポイントです。
「利用者さんに質の高い介護を提供したい」などの目標を定め、今の自分に足りていない知識・スキルは何か考えたうえで、勉強したい領域について学べる資格を選びましょう。目的意識を持って取り組めば、モチベーションを保ちやすく、資格の勉強を頑張れるでしょう。また、「苦手な対応を克服したい」という気持ちで取得を目指すのもおすすめです。自分の興味や関心にマッチする資格を選んでみてください。
通信のみでは取れないが取得する価値のある介護資格
ここでは、通信のみでは取れないものの取得する価値のある介護資格を3つ紹介します。取得難易度が少し高い分、キャリアアップや給与アップにつながりやすいのが特徴です。介護業界での知名度が高く評価されやすい公的資格なので、まだ取得していない方はチェックしてみましょう。
1.介護職員初任者研修
介護職員初任者研修は、介護の基本的な知識や考え方を学べる、介護職の入門的な資格です。受講資格はなく、誰でも受講できます。通信講座と通学を併用しながら130時間のカリキュラムを受講し、修了試験に合格すれば取得可能です。修了試験の難易度は高くないため、カリキュラムの内容を押さえれば合格を目指せます。
通学日数はスクールごとに異なりますが、15~16回程度が一般的です。通学頻度は週1~4日から選択可能。最短で1ヶ月、長くても3~4ヶ月程度で取得できます。
また、取得費用は講座ごとに幅があり、3万~10万円程度が相場です。「受講費用を少しでも抑えたい」という方は、「介護職員初任者研修を無料で取得する方法は?メリットや支援制度を解説」の記事もぜひご覧ください。
首都圏限定!資格取得が無料!
転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!
レバウェル介護の資格スクール2.介護福祉士実務者研修
介護福祉士実務者研修は、介護の基礎に加えて実践的な技術や知識を学ぶ研修で、介護職員初任者研修の上位資格です。初任者研修と同様、受講要件はありません。450時間のカリキュラムを修了すれば取得できますが、スクールによっては修了試験を課している場合があるようです。なお、初任者研修を取得している方は、130時間分のカリキュラムが免除になります。
実務者研修も通信と通学を組み合わせて受講できるものの、カリキュラムが多いため、無資格から取得するには最短でも6ヶ月程度の期間が必要です。働きながら取得を目指す場合、スケジュール調整などの大変さがあるでしょう。一方で、取得することで訪問介護のサービス提供責任者として働けるようになったり、介護福祉士の受験要件を一部満たせたりするメリットもあります。
実務者研修の詳細については、「介護福祉士実務者研修とは?資格取得のメリットや初任者研修との違いを解説」の記事をご一読ください。
3.介護福祉士
介護福祉士は、介護分野において唯一の国家資格です。取得することで、介護の専門知識やスキルが保証されるので、就職・転職に有利に働きます。介護福祉士の受験資格は4パターンありますが、働きながら取得を目指す場合、「実務者研修の修了+介護業務の実務経験3年以上」で受験資格を満たす人が多いようです。
介護福祉士を取得するには、年1回試験会場で開催される介護福祉士国家試験に合格し、資格登録をする必要があります。合格率は70%を超えている年も多いですが、専門性の高い出題があるため、受験対策は必須です。
介護福祉士について詳しく知りたい方は、「介護福祉士とは?仕事内容や資格の取得方法、試験概要をわかりやすく解説!」の記事もあわせてご覧ください。
通信講座の介護資格によくある質問
ここでは、介護資格の通信講座に関するよくある質問にお答えします。介護の資格の取得方法が気になる方は、ぜひご一読ください。
介護職員初任者研修は通信のみで取得できますか?
介護職員初任者研修は、通信のみでは取得できません。初任者研修のカリキュラムには演習があるので、スクーリングへの参加は必須です。ただし、通信講座を併用すれば、最大40.5時間分のカリキュラムを自宅で受講できます。通学の日程調整が難しい方は、通信講座を積極的に活用して取得を目指すと良いでしょう。
介護職向けのすぐ取れる資格を教えてください
無資格の介護職の方には、認知症介護基礎研修がおすすめです。150分のeラーニングを受講し、簡単な確認テストに合格すれば取得可能。通信のみで認知症介護の基本的な知識を学べます。認知症介護基礎研修は、介護職として働いている方が対象の資格です。また、難病患者等ホームヘルパー養成研修の基礎課程Iは4時間のカリキュラムなので、1日で取得できます。初任者研修を保有する方や履修中の方が受講対象です。そのほか、同行援護従業者養成研修や行動援護従業者養成研修も、約20~25時間のカリキュラムとなっており、3日程度と比較的短期間で取得できます。
▼関連記事
同行援護従業者養成研修とはどんな資格?取得方法やカリキュラム内容を紹介
行動援護従業者養成研修とは?受講要件やカリキュラム、メリットなどを解説
介護職員初任者研修のおすすめの通信講座は?
介護職員初任者研修を通信で受講できる講座を選ぶ際は、自宅学習のフォロー体制に注目しましょう。オンラインで講師に質問できる環境なら、分からない部分をすぐに理解できます。また、通学のしやすさや受講費用、その他のサポート内容なども、スクールを選ぶうえで大切なポイントです。レバウェルスクール介護の教室は、首都圏から通学しやすい新宿駅近くにあります。資格取得だけではなく転職支援もあわせて行っているので、仕事探しと資格取得を同時に進めたい人におすすめです。
首都圏限定!資格取得が無料!
転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!
レバウェル介護の資格スクールまとめ
通信講座のみで取得できる介護の資格は、レクリエーション介護士2級や福祉用具専門相談員指定講習、認知症介助士などです。
通信で取れる資格は、一つの専門的領域に特化しており、比較的気軽に知識・スキルアップを図れます。自分のペースで無理なく勉強できるのが、通信講座のメリットといえるでしょう。ただし、1人で学習スケジュールを立てて勉強する必要があるので、苦手な方はサポート体制が整っている講座を選んでみてください。
通信のみでは取得できないものの、介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修、介護福祉士は、目指す価値のある資格です。通信のみで取れる資格に比べて難易度は高い傾向にありますが、キャリアアップや給与アップにつながりやすいでしょう。
「介護職としてスキルアップしたい」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した就職・転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーが、豊富な介護求人のなかから、「資格取得支援制度がある職場で働きたい」といった希望に沿った求人をご提案いたします。サービスはすべて無料なので、まずは気軽にお問い合わせください。
働きながら資格を取る方法教えます
先に資格を取りたい方へ
無料相談はこちら 資格取得支援の求人一覧はこちら
資格取得支援の求人一覧はこちら