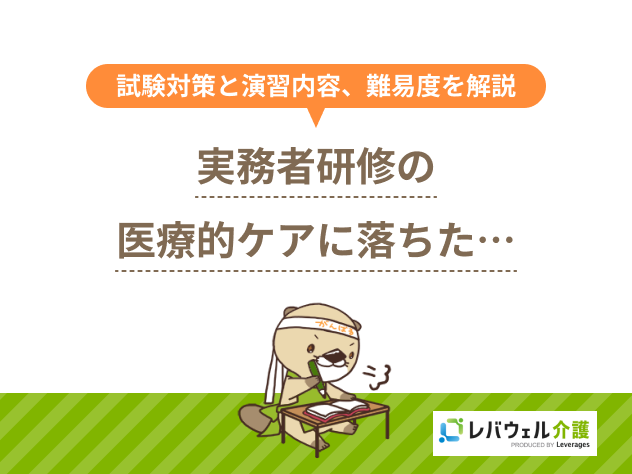
この記事のまとめ
- 医療的ケアは、介護福祉士実務者研修のなかで難易度が高い
- 医療的ケアの科目は、基本研修とスクーリング(実技演習)で構成される
- 実務者研修の医療的ケアに落ちた場合、実施手順を確認して追試に臨もう
「実務者研修の医療的ケアに落ちた…」とお悩みの方や、「落ちたらどうしよう」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。この記事では、介護福祉士実務者研修のなかで医療的ケアの難易度が高い理由や、具体的な学習内容を紹介します。実務者研修で医療的ケアの演習に合格するコツも解説するので、一度落ちた方もこれから受ける方も、ぜひ目を通してみてくださいね。
実務者研修の医療的ケアに落ちた?難易度の高さ
医療的ケアは、利用者さんの生命に関わる医療的行為のため実技の評価が厳しく、介護福祉士実務者研修のなかで難易度が高い科目といえます。知識不足で誤った手順で医療的ケアを行うと、利用者さんの身体を傷つける恐れがあるため、慎重に行わなければなりません。したがって、専門的な知識と技術をしっかり身につける必要があります。
しかし、実務者研修は、医学的な知識が少なくても基礎から学べるため、過度に心配しなくても問題ありません。実務者研修の合格率はほぼ100%といわれており、しっかり取り組めば修了は可能です。医療的ケアのテストに落ちた場合も再受験できるため、焦らず落ち着いて取り組みましょう。
今の職場に満足していますか?
実務者研修の医療的ケアの内容とは
介護福祉士実務者研修の医療的ケアの科目では、たんの吸引や経管栄養といった医療的な介助を学びます。医療的ケアの科目の構成は、「50時間以上の講義による基本研修」と「スクーリングによる喀痰(かくたん)吸引・経管栄養の知識と手順の習得」です。
介護福祉士実務者研修の概要は「介護福祉士実務者研修とは?資格取得のメリットや初任者研修との違いを解説」で紹介しているので、あわせてご覧ください。
基本研修
医療的ケアの基本研修は講義形式で、喀痰吸引・経管栄養の知識と実施手順を学ぶのが目的です。時間数は50時間以上と定められています。
厚生労働省の「介護福祉士養成施設における「医療的ケア」の追加について(概要)(p.3) 」によると、講義内容は以下のとおりです。
- 医療的ケア実施の基礎
- 喀痰吸引(基礎的知識・実施手順)
- 経管栄養(基礎的知識・実施手順)
介護福祉士が医療的ケアを行えるようになった背景や、清潔保持と感染予防など、医療的ケアに必要なさまざまな知識を身につけます。
スクーリング(実技演習)
介護福祉士実務者研修では7日間程度のスクーリングがあり、そのうち医療的ケアは2日間ほどです。シミュレーターと呼ばれる人形を相手に演習を行います。
最後に実技テストがあり、落ちた場合は修了認定されません。実際の医療的ケアを想定して手順通りに実施することが、修了評価に合格するためのポイントです。医療的ケアの演習は、合格するまで補講を受けられるので、落ちたとしても前向きに挑戦すれば大丈夫でしょう。
喀痰吸引
喀痰吸引とは、たんが絡んでも自分で吐き出せない利用者さんに対し、たんの吸引を行うことを指します。喀痰吸引は、「口腔内」「鼻腔内」「気管カニューレ内部」の3項目です。厚生労働省の「介護福祉士養成施設における「医療的ケア」の追加について(概要)」によると、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部それぞれの項目で、5回ずつ演習へ合格する必要があります。
喀痰吸引は正しい手順かつ決められた範囲で行わなければなりません。吸引チューブの挿入に失敗すると、利用者さんの呼吸状態に影響する恐れがあるため、十分な知識と注意が求められます。
鼻腔粘膜はデリケートで出血しやすいため、無理にチューブを挿入しようとせず、角度を確認しながら慎重に行いましょう。また、気管カニューレ内部の吸引時は完全な無菌状態にする必要があり、滅菌操作が必須です。作業に集中し過ぎて忘れないように注意しましょう。実際の現場では、相手の命を預かっていることを忘れず、ただの作業にならないよう声掛けをして利用者さんに寄り添うことも大切です。
経管栄養
経管栄養とは、口から食事を取ることが利用者さんに対し、胃ろうや腸ろう、鼻に挿入したチューブで栄養剤や水分を流し込む食事方法を指します。胃ろう・腸ろうとは、腹部に開けた穴に取り付けた器具のことです。経管栄養では、そこにチューブを接続して栄養剤を流し込みます。それぞれ以下の規定回数、演習への合格が必要です。
- 胃ろうまたは腸ろう:5回以上
- 経鼻経管栄養:5回以上
経管栄養は、注入する速度や利用者さんの姿勢が大切です。正しく行わないと、嘔吐や逆流、下痢などの危険が伴うため、慎重に行わなければなりません。
▼関連記事
介護福祉士実務者研修の学習内容は?資格取得にかかる時間や難易度も解説
出典
厚生労働省「介護福祉士養成施設等における「医療的ケアの教育及び実務者研修関係」(2024年12月25日)
実務者研修で医療的ケアの演習に合格するコツ
介護福祉士実務者研修の医療的ケアでは、実技演習によって理解度の確認が行われます。実務者研修で医療的ケアの演習に合格するには、以下のポイントを意識して取り組みましょう。
- 手洗い・消毒を徹底できているか
- 利用者さんへの説明が十分にできているか
- 利用者さんのプライバシーに配慮できているか
- 利用者さんの様子を十分に観察できているか
- 必要事項の報告に漏れがないか
- 作業が終わったあとの確認・片付けに漏れがないか
一つずつ確実に覚えて実践しないと、手順が抜けてしまうことがあります。もしも実務者研修医療的ケアに落ちた場合、改めて全体の流れを覚え、漏れのないよう意識して追試に臨むことが大切です。
実務者研修の医療的ケアが免除になる資格
実務者研修の医療的ケアが免除になる資格は以下のとおりです。
- 喀痰吸引等研修(第一号、第二号)修了者
- 看護師
- 准看護師
実務者研修の医療的ケアと同等以上の研修を受けている方は、知識やスキルがあるとみなされ、医療的ケアの受講が免除になります。なお、初任者研修、ホームヘルパー1級、介護職員基礎研修の資格を保有していても、実務者研修の医療的ケアは免除になりません。
出典
厚生労働省「介護福祉士養成施設等における「医療的ケアの教育及び実務者研修関係」」(2024年12月25日)
実務者研修の医療的ケアに落ちたくない方はレバウェルスクール介護で受講しよう
「実務者研修の医療的ケアに落ちたらどうしよう…」と不安な方は、現役で活躍する講師がいるスクールを選ぶのがおすすめです。
レバウェルスクール介護(旧 きらケアステップアップスクール)は、現役の医療福祉職員が講師を務めており、分かりやすい演習が受けられます。また、万が一落ちた場合も、無料で再試験を受けられるため、安心して受講できるでしょう。
実務者研修の医療的ケアに関するよくある質問
ここでは、実務者研修の医療的ケアに関するよくある質問に回答します。医療ケアの学習に不安のある方は、ぜひチェックしてみてください。
実務者研修の医療的ケアの試験問題を教えてください
医療的ケアの実技演習でチェックされるのは、「喀痰吸引」と「経管栄養」の処置です。喀痰吸引では、利用者さんを想定した人形を用いて、「口腔内」「鼻腔内」「気管カニューレ内部」からのたん吸引の演習を行います。それぞれ5回連続で成功させなくてはいけません。
また、経管栄養では、「胃ろうまたは腸ろう」と「経鼻経管栄養」での処置を、それぞれ5回連続で成功させる必要があります。詳しい内容はこの記事の「実務者研修の医療的ケアの内容とは」で解説しているので、あわせてご覧ください。
実務者研修の医療的ケアのスクーリングは難しいですか?
介護福祉士実務者研修のなかで、医療的ケアは難しい科目といえます。その理由は、利用者さんの生命に関わる医療的行為の手順を習得する内容のためです。しかし、医療的ケアのテストは追試が可能なので、過度な心配はしなくても良いでしょう。
実務者研修の合格率や難易度については、「実務者研修は難しい?資格取得の難易度やスムーズに修了するコツを解説」の記事で紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
実務者研修についていけないんじゃないかと不安です…
介護福祉士実務者研修は、基本的にカリキュラムをすべて受講すれば取得可能な資格です。週1回からの講座もあるので、無理なく続けられるコースを選ぶことが大切です。働きながら学習できるプランもあるため、自分に合ったスクールを見つけると良いでしょう。
まとめ
医療的ケアは、利用者さんの生命に関わる医療的な行為のため、介護福祉士実務者研修の科目なかで難易度が高いようです。利用者さんを危険にさらさないためには、しっかりと知識や技術を身につけなくてはなりません。
医療的ケアでは、たんの吸引・経管栄養という医療的な介助を学習します。科目の構成は、「50時間以上の講義による基本研修」と「スクーリングによる喀痰吸引・経管栄養の知識と手順の取得」です。最後に実技テストがあり、落ちた場合は修了認定されないため、集中して受講しましょう。
医療的ケアの演習に落ちた方は、作業漏れや確認不足がなかったか振り返ることをおすすめします。手洗い・消毒や片付けなどもチェックされるので、ケアの手順に抜けがないように気をつけて追試に臨みましょう。
介護福祉士実務者研修は働きながらでも受講できるため、資格取得支援制度のある職場へ転職して取得を目指すのも一つの手段。自分の状況や希望に合った職場を探すには、転職エージェントの活用がおすすめです。
介護業界に特化した転職エージェントのレバウェル介護(旧 きらケア)では、豊富な求人のなかから、あなたの希望条件に合う職場をご紹介いたします。サービスはすべて無料なので、まずはお気軽にご相談ください。
今の職場に満足していますか?
 レバウェルスクール介護の申込みはこちら
レバウェルスクール介護の申込みはこちら