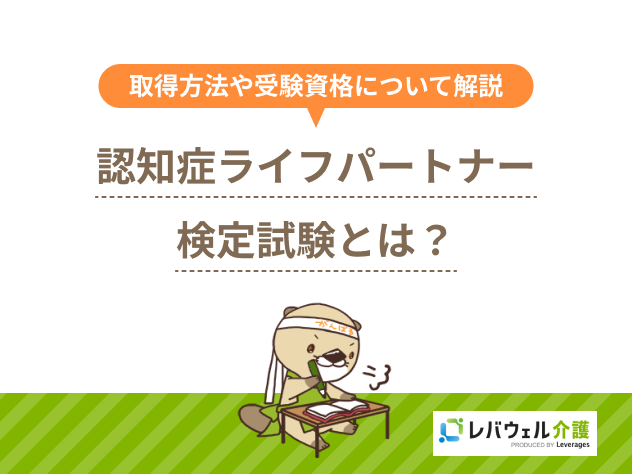
この記事のまとめ
- 認知症ライフパートナーとは、認知症を患う方の生活の支援に活かせる資格
- 認知症ライフパートナー検定試験のレベルは、1~3級に分かれている
- 認知症ライフパートナー取得のメリットは、コミュニケーションを学べること
認知症ケアに関する資格の取得を考えている方のなかには、「認知症ライフパートナーってどんな資格?」と気になる方もいるかもしれません。認知症ライフパートナーとは、認知症についての知識や対応方法を習得できる民間資格です。この記事では、認知症ライフパートナー検定試験の概要をまとめました。勉強方法や取得のメリットもご紹介するので、認知症ライフパートナーの資格について詳しく知りたい方は、ご一読ください。
介護資格の種類31選!取得方法やメリットを解説します →レバウェル介護の資格スクールはこちら認知症ライフパートナー検定試験とは
認知症ライフパートナーとは、一般社団法人日本認知症コミュニケーション協議会が認定する民間資格です。取得することで、認知症の知識や、認知症を患う方と接する際のコミュニケーション技術があることを証明できます。
認知症ライフパートナーの特徴
認知症ライフパートナー検定試験の特徴は、「アクティビティ・ケア」の手法が身につくことです。アクティビティ・ケアとは、認知症を患う方の好きなことや生活習慣を踏まえて、適切なアクティビティを提供し、心身機能の維持や生活の質向上に活かす認知症ケアの手法を指します。
認知症ライフパートナーは、認知症を患う方の尊厳を守りながら、本人らしく生活できるように支援したい方におすすめの資格です。
出典
一般社団法人日本認知症コミュニケーション協議会「検定試験:検定概要」(2025年1月8日)
認知症ライフパートナーの取得方法
認知症ライフパートナー検定試験を受験して合格すれば、資格を取得可能です。試験は1級から3級まで3つのレベルに分かれています。認知症ライフパートナー検定試験の試験日程は、2級と3級は夏季・冬季の2回で、1級は冬季のみの開催です。
2025年度の試験日程は、現時点では公開されていません。また、認知症ライフパートナー検定試験は、2024年には開催されなかったようです。受験を考えている方は、開催される予定があるか事前に確認すると良いでしょう。
出典
一般社団法人日本認知症コミュニケーション協議会「検定試験:募集要項」(2025年1月8日)
働きながら資格を取る方法教えます
認知症ライフパートナー検定試験の概要
ここでは、認知症ライフパートナー検定試験の概要をご紹介します。1~3級のどのレベルを受験するかお悩みの方は、参考にしてみてください。
受験資格
2級と3級に、受験要件は設けられていません。学歴や年齢、性別を問わず受験できます。1級を受験するには、認知症ライフパートナー検定試験2級への合格が必要です。
試験内容
ここでは、認知症ライフパートナー検定のレベルごとの試験内容をまとめました。どのような内容について学びたいか、どのような場面で活かしたいのかに当てはめながらチェックしてみましょう。
3級
3級の試験は、認知症ケアについての基礎的な知識を問う内容です。認知症を患う方とのコミュニケーションやアクティビティを用いたケアの基本、症状の基礎知識などが出題されます。入門的な内容なので、「家族のケアに活かしたい」という方も挑戦しやすいレベルといえます。なお、試験はマークシート方式です。
出典
一般社団法人日本認知症コミュニケーション協議会「認知症ライフパートナー検定試験3級」(2025年1月8日)
2級
2級は、認知症ケアの現場で必要になる、応用的な知識・技術を問われる内容です。認知症の中核症状や行動症状、心理症状などのさまざまな専門知識に加え、応用的なコミュニケーション手法などについても出題されます。また、ケアの計画・実施や、適切な住環境についてなど、専門職に必要な知識も問われるようです。
2級は、認知症ケアの現場で知識を活かしたい専門職の方におすすめです。なお、試験はマークシート方式で行われます。
出典
一般社団法人日本認知症コミュニケーション協議会「認知症ライフパートナー検定試験2級」(2025年1月8日)
1級
1級では、認知症を患う方のご家族への助言や、職員の指導・マネジメント業務の知識など、認知症ケアの専門家に必要なスキルを問われます。認知症ケアに関する制度の理解や地域包括ケアシステムの活用方法、認知症予防につながるアクティビティ・ケアなどについて出題されるようです。
1級は、現場のリーダーを目指す方や、より専門的な認知症ケアを行いたい方におすすめの資格といえるでしょう。なお、1級の試験は、前半がマークシート方式、後半が記述式で行われます。
出典
一般社団法人日本認知症コミュニケーション協議会「認知症ライフパートナー検定試験1級」(2025年1月8日)
合格ライン・合格率
認知症ライフパートナー検定試験は、1~3級いずれにおいても、100点満点中70点以上で合格です。
2023年冬季に行われた試験の合格率は、3級が82.3%、2級が68.5%、1級が35.3%でした。認知症ケアについて少しずつ学習したい方は、3級から挑戦してみるのがおすすめです。
出典
一般社団法人日本認知症コミュニケーション協議会「最新情報」(2025年1月8日)
認知症ライフパートナー検定試験の勉強方法
認知症ライフパートナー検定試験は、公式テキストや公式の過去問題集が販売されているので活用しましょう。
特に、2、3級の試験は公式テキストからのみ出題されるため、対策しやすいといえます。1級は公式テキスト以外からも出題されますが、テキストや過去問を活用することで出題傾向を掴めるでしょう。
出典
一般社団法人日本認知症コミュニケーション協議会「事業情報:関連書籍のご案内」(2025年1月8日)
認知症ライフパートナーの需要
日本は高齢化が進んでおり、今後も認知症を患う方は増えると予想されているため、認知症ケアの知識や技術がある認知症ライフパートナーは、スキルを活かして活躍できます。
内閣府の「令和6年版高齢社会白書(p.31)」によると、2022年における認知症を患う高齢者の人数は、443.2万人でした。2030年には523.1万人、2040年には584.2万人に増加すると推計されています。認知症に関する正しい知識があれば、認知症を患う方の介護や社会参加の支援に役立てられるでしょう。
出典
内閣府「令和6年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 」(2025年1月8日)
認知症ライフパートナーを活かせる職場
介護職が認知症ライフパートナーの資格を活かせる職場は、認知症を患う方が利用する施設や訪問介護事業所です。
- グループホーム
- 有料老人ホーム
- 特別養護老人ホーム(特養)
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- デイサービス
- 訪問介護事業所
グループホームは原則として認知症を患う方のみが入居する施設なので、特に資格を活かしやすいでしょう。また、有料老人ホームや特養、サ高住などの施設でも、利用者さんの対応やレクリエーションに知識を役立てられます。
認知症の症状の理解やコミュニケーションの取り方などは、自身の業務に活かせるだけでなく、ほかの職員に共有することも可能です。
 グループホーム の求人一覧はこちら
グループホーム の求人一覧はこちら 有料老人ホームの求人一覧はこちら
有料老人ホームの求人一覧はこちら 特別養護老人ホーム(特養)の求人一覧はこちら
特別養護老人ホーム(特養)の求人一覧はこちら 訪問介護の求人一覧はこちら
訪問介護の求人一覧はこちら
認知症ライフパートナーを取得するメリット
認知症ライフパートナーを取得するメリットとして、「認知症を患う方と適切に関わるコミュニケーション技術を身につけられる」「自信を持って認知症ケアに取り組める」などが挙げられます。以下で、それぞれについて詳しくまとめたので、チェックしてみてください。
認知症介護のコミュニケーション技術を身につけられる
認知症ライフパートナーを取得することで、認知症を患う方へ適切な支援を行うためのコミュニケーション技術を身につけられます。
認知症を患う方と関わる際、どのように対応するのが正解か迷い、うまくコミュニケーションを取れないこともあるでしょう。配慮すべき点や症状への対応方法を知っておくことで、より良いコミュニケーションを取ることが可能です。また、アクティビティを通じたコミュニケーションの方法も学べるので、認知症を患う方の生活の質向上も支援できます。
▼関連記事
認知症の方とのコミュニケーション方法を解説!相手を想う言葉や行動とは
自信を持って認知症ケアに取り組める
認知症ライフパートナーの取得を通して専門性を磨くことで、自信を持ってケアに取り組めるようになるでしょう。また、自分の認知症ケアが適切かどうかを振り返られることも、メリットの一つです。認知症ケアに必要な知識が身につけば、根拠に基づいて認知症ケアやご家族への対応ができます。
キャリアアップにつながる
認知症ケアを重視している職場では、資格を取得してスキルアップすることで、キャリアアップにつながる可能性があります。2級や1級は、認知症ケアの現場で活かせる専門知識を学ぶため、評価されやすいでしょう。
特に1級の取得では、認知症ケアにおける職員の育成やマネジメントについても学べるので、職員のリーダー的な役割を目指す方には大きなメリットがあります。
自分の家族の介護に活かせる
認知症ライフパートナー検定試験の学習で身につけた知識は、認知症を患う家族の介護にも活かせます。認知症介護の基礎的な知識を学べる3級は、介護・医療業界で働く方以外が受験することも多いようです。
また、介護職が取得する場合、実際に利用者さんと関わる場面だけではなく、家族介護者の相談対応や助言を行う際にもスキルを活かせます。
認知症ケアに活かせるその他の資格
ここでは、介護従事者が認知症ケアに活かせるその他の資格をまとめました。「認知症ライフパートナー以外の資格についても知りたい!」という方は、ぜひチェックしてみてください。
認知症介護基礎研修
認知症介護基礎研修とは、介護職が利用者さんに適切な介護を行うために、認知症ケアの基礎を身につけることを目的とした資格です。認知症介護における入門的な内容を学べる研修で、2024年4月より、介護業務に従事する無資格の職員に受講が義務付けられました。
認知症介護基礎研修の取得方法は、インターネットで講義動画を視聴し、確認テストに合格することです。介護職員を対象とした研修なので、基本的に職場を通じて受講を申し込みます。
出典
認知症介護基礎研修 eラーニング「認知症介護基礎研修 eラーニングのご案内」(2025年1月8日)
▼関連記事
介護職は無資格で働けなくなるの?認知症介護基礎研修の義務化について解説
首都圏限定!資格取得が無料!
転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!
レバウェル介護の資格スクール認知症介護実践者研修
認知症介護実践者研修は、認知症ケアを行う介護職を対象としており、実践的な知識・スキルを身につけられます。認知症ケアの実践に加え、施設全体の認知症ケアの向上を図るための具体的な支援方法を学ぶことが可能です。
認知症介護実践者研修は、およそ6日間の講義・演習と2週間ほどの実習を修了することで取得できます。なお、研修内容や日程、受験要件などは自治体によって異なるので、チェックしてみてください。
東京都の受講要件は、以下の2つを満たすことです。
- 東京都内の介護保険施設・事業所(居宅介護支援事業所を除く)で働いている
- 認知症介護の実務経験が2年程度以上ある
受験要件として、介護や認知症ケアの実務経験を求められる傾向にあります。
認知症介護実践者研修について、詳しくは「認知症介護実践者研修とは?資格の概要や取得するメリットを解説」の記事をご参照ください。
認知症介護実践リーダー研修
認知症介護実践リーダー研修とは、認知症介護実践者研修の上位資格です。認知症介護の専門知識に加え、職員のリーダー的な役割を担えるよう、マネジメントについても学びます。
認知症介護実践リーダー研修は、「講義・演習」「他施設実習」「自施設実習」で構成されたカリキュラムをすべて修了することで取得可能です。カリキュラムの詳細や受講要件は、自治体ごとに異なります。
東京都の受講要件は、以下のすべてを満たすことです。
- 東京都内の介護保険施設・事業所(居宅介護支援事業所を除く)で働いている
- 認知症介護実践者研修(旧 痴呆介護実務者研修)を修了し、1年以上経過している
- 認知症介護の実務経験が5年以上ある
- 介護保険施設・事業所において介護・看護のチームリーダー(主任・副主任・ユニットリーダーなど)の立場にあるか、リーダーを指導する立場にある
- 区市町村・地域での事業者連絡会などで、認知症支援の質の向上を支援する役割担うことができるまたは、その意欲がある
受講要件として、認知症介護実践者研修を修了していることや、介護職としてリーダー的な立場にあることなどが求められる傾向にあります。
認知症介護実践リーダー研修について、詳しくは「認知症介護実践リーダー研修とは?修了は難しい?受講内容なども解説」の記事をチェックしてみてください。
出典
東京都福祉局「東京都認知症介護研修の概要」(2025年1月8日)
▼関連記事
【認知症介護の資格一覧】取得方法や試験の難易度、習得できるスキルを解説
認知症ライフパートナーに関するよくある質問
ここでは、認知症ライフパートナーに関するよくある質問にお答えします。認知症ライフパートナーを取得するかお悩みの方は、ご一読ください。
認知症ライフパートナーは役に立つ資格ですか?
認知症ライフパートナーは、認知症ケアに役立つ資格といえます。認知症ライフパートナー検定試験の目的は、認知症を患う方の尊厳を守りながら、本人らしく生活できるよう支援できる人材を育成することです。認知症ケアの知識を学べるため、介護業界で働く人以外にも、福祉・医療系の企業に勤務する人や、身近に認知症を患う方がいる人も活かせる資格といえます。
認知症ライフパートナーについては、この記事の「認知症ライフパートナー検定試験とは」で解説しているので、ご参照ください。
認知症ライフパートナー検定の試験日はいつですか?
認知症ライフパートナー検定試験は、例年、夏季と冬季の2回実施されていました。1級は冬季のみの開催です。2023年度は夏季が2023年7月16日(日曜日)、冬季が2023年12月10日(日曜日)に試験が実施されました。2024年は開催されておらず、2025年度の試験日程は、現時点では公開されていません。
認知症ライフパートナー検定試験の概要について、詳しくはこの記事の「認知症ライフパートナー検定試験の概要」をチェックしてみてください。
出典
一般社団法人日本認知症コミュニケーション協議会「検定試験:募集要項」(2025年1月8日)
認知症ケア専門士と認知症ライフパートナーの違いは何ですか?
認知症ケア専門士と認知症ライフパートナーの違いは、取得によって身につけられるスキルです。認知症ケア専門士は、認知症介護のプロとして現場に活かせる知識に特化しています。一方、認知症ライフパートナーは、認知症介護の基礎に加え、アクティビティ・ケアのスキルを習得できるのが特徴です。いずれも公的資格ではありませんが、専門性の高い知識や技術を学べるため、認知症ケアのスキルを証明できる資格といえるでしょう。
認知症ケア専門士について、詳しくは「認知症ケア専門士とは?認定試験の合格率と難易度、資格の取得方法を解説!」の記事でご紹介しています。
まとめ
認知症ライフパートナー検定試験とは、認知症の知識やコミュニケーション技術について学ぶ民間資格です。認知症を患う方を支援する人材を育成することを目的としています。
認知症ライフパートナー検定試験は、1~3級に分かれています。2級と3級には受験要件がないため、家族の介護に活かしたい方や、認知症ケアの専門職としてスキルを身につけたい方など、さまざまな方が挑戦することが可能です。1級は2級を取得した人が受験できます。
「認知症ケアのスキルを磨ける職場に転職したい!」「介護職としてスキルアップしたい」という方は、「レバウェル介護(旧 きらケア)」にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界専門の転職エージェントです。
専任のキャリアアドバイザーが希望をしっかりとヒアリングしたうえで、あなたにぴったりの求人をご紹介いたします。認知症ケアに特化した施設や、資格を活かせる職場もご紹介可能です。サービスはすべて無料なので、お気軽にお問い合わせください。
働きながら資格を取る方法教えます
先に資格を取りたい方へ
無料相談はこちら