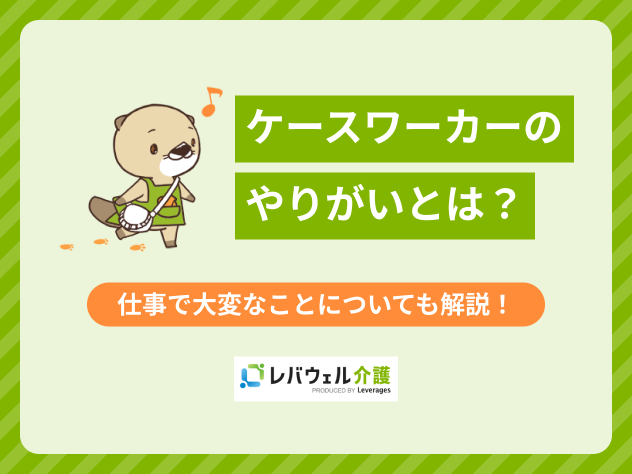
この記事のまとめ
- ケースワーカーとは、福祉事務所などの行政機関で相談支援業務を行う職種
- ケースワーカーの仕事には困っている人の役に立てるなどのやりがいがある
- ケースワーカーの仕事は、関係各所との連携や法改正への対応などが大変
「ケースワーカーのやりがいは何?」と気になる方もいるでしょう。ケースワーカーは、生活に困っている人の役に立てることや、相談者と信頼関係を築けることにやりがいを感じるようです。この記事では、ケースワーカーのやりがいを5つご紹介します。また、仕事で大変なことについても解説しているので、ケースワーカーに興味がある方はぜひチェックしてみてください。
ケースワーカーとは?
ケースワーカーとは、福祉事務所や児童相談所、国公立病院、保健所といった行政機関に在籍する公務員のうち、主に相談支援業務を行う人を指します。仕事内容は、心身面や社会面の課題があり、生活に困っている人の相談に乗り、状況を改善するために最適な支援を考えて調整することです。
ケースワーカーになるには、公務員試験を受験して合格したうえで、公務員として採用される必要があります。また配属先によって、社会福祉主事任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士、児童福祉司任用資格などの資格要件を満たしていることも、ケースワーカーとして従事する要件です。
ケースワーカーについて詳しく知りたい方は「ケースワーカーとは?必要な資格や仕事内容、ソーシャルワーカーとの違い」をご覧ください。
今の職場に満足していますか?
ケースワーカーの仕事で得られる5つのやりがい
ケースワーカーの仕事を通して得られるやりがいとしては、「生活に困っている人の役に立てる」「福祉や法律の専門知識を磨ける」といったことが挙げられます。ここでは、ケースワーカーのやりがいや楽しさを5つピックアップしました。
1.生活に困っている人の役に立てる
ケースワーカーは、個人で解決が難しい心身上・社会上のお悩みに関する相談を受け、最適な支援を行うのが仕事です。相談者によっては、「この先どうしたら良いのだろう…」と生活だけでなく人生に不安を抱えている場合もあるかもしれません。
単に相談を受けるだけでなく、解決に導くための具体的な支援もできるのが、ケースワーカーのやりがいの一つです。自身のサポートにより、相談者の悩みや不安が少しでも軽減されれば、「人の役に立てている」という実感を得られるでしょう。
2.福祉や法律の専門性を深められる
ケースワーカーは福祉分野のスペシャリストです。老人福祉法や生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などをもとに公的な支援を行うため、従事すれば福祉や法律の専門知識を深められます。
また、仕事を通して得られるのは、知識だけではありません。相談援助の業務経験を通して、個々の課題や改善策を柔軟に考えられるようになり、支援の幅が広がっていくことも、やりがいにつながるでしょう。
3.支援を重ねるうちに相談者と信頼関係を築ける
支援を重ねるうちに相談者との信頼関係を築いていけるのも、ケースワーカーのやりがいです。相談業務では、お金や病気、障がい、介護といった非常にデリケートな問題に対応します。そのため、最初はなかなか本音を話せない相談者の方もいるでしょう。
何度か面談を繰り返すうちに「この人なら話せる」と信頼を寄せてもらえれば、より詳しい状況を聞くことが可能です。信頼関係があるからこその支援ができれば、より自身の役割の大切さを実感できるでしょう。
4.自分のペースで主体的に仕事を進められる
ケースワーカーの仕事は、自分の裁量で仕事を進められ、主体的に働くことができます。「明日は○○さんの訪問だから合間に事務処理をしておこう」というように、スケジュールは自身で調整するのが基本です。
指示を待つのではなく、自分なりにどのように進めるのかを考えながら行動できるので、「仕事を通して成長したい」という向上心のある方は、大きなやりがいを感じられるでしょう。
5.人との出会いで成長できる楽しさがある
ケースワーカーは、「経済的な支援が必要な人」「介護に困難を抱えている人」など、さまざまな状況の相談者と出会います。福祉事務所や児童相談所、病院などの配属先によってある程度の分類はありますが、相談の背景は個々で異なるものです。こうした一つひとつの出会いが、自身の価値観や信念に良い影響を与えることも。多くの人との出会いによって、自身が成長できる楽しさもある仕事といえます。
▼関連記事
ケースワーカーに向いている人とは?必要な資格やスキルも解説
ケースワーカーの仕事で大変なこと
ケースワーカーのやりがいをイメージしたあとは、仕事で大変なこともチェックしておきましょう。大変さを知ったうえで目指したいと思うなら、ケースワーカーなどの相談援助を行う職種として活躍できます。
関連各所との連携・調整に一定の大変さがある
ケースワーカーのような相談援助を行う職種の特徴として、関連各所との連携や調整が複雑になりやすいことが挙げられます。相談者のお悩みによっては、ご家族や外部機関と連絡を取ったり、面談の調整をしたりしなくてはなりません。
スムーズに話がまとまらなければ、対応方針を再検討する必要もあるので、取りまとめるのに一定の大変さを感じる場合があるようです。
限られた時間に支援内容を判断しなければならない
「限られた時間で支援内容を判断すること」を大変に感じるケースワーカーもいるようです。相談援助は、相談者の自宅へ訪問して調査をすることもあるため、外出する時間が多いのが特徴です。
相談者の人数が多ければそれだけ時間をうまく使う必要があるものの、面談の時間が長引いたり調整が難航したりすれば、スケジュール通りに進まない場合もあるでしょう。
法律が改正されるたびに知識を更新する必要がある
ケースワーカーが扱う福祉や法律の知識は、制度改正や法改正によって更新されていきます。仕事を円滑に進めるには、行政機関で働く専門家として正確な知識を身につけておかなければなりません。法律は適宜見直されるので、常にアンテナを張っておくことを大変に感じる場合があるかもしれません。
ケースワーカーに関するよくある質問
ここでは、ケースワーカーに関するよくある質問をまとめました。「ケースワーカーとソーシャルワーカーは何が違うの?」など、基本的な情報が知りたい方は、ぜひご活用ください。
ケースワーカーとソーシャルワーカーの違いは何ですか?
ソーシャルワーカーが福祉に関する相談援助を行う職種全般を指すのに対し、ケースワーカーは行政機関で働く公務員を指します。ケースワーカーになるには、公務員試験に合格する必要があります。
もっと詳しく知りたい方は、「ソーシャルワーカーの仕事内容とは?役割や必要な資格、年収を解説」の記事も参考にしてみてください。
ケースワーカーとケアマネジャー(介護支援専門員)の違いは?
ケースワーカーは行政機関で働く公務員を指す言葉です。一方のケアマネジャーは、介護支援専門員の資格を保有したうえで、介護保険サービスを受けるために必要なケアプランを作成する職種を指します。
ケアマネジャーについて詳しく知りたい方は、「ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどんな仕事?業務内容や役割を解説!」の記事もご覧ください。
ケースワーカーになるために必要な資格はありますか?
ケースワーカーになるために必要な資格は、社会福祉主事任用資格や社会福祉士、精神保健福祉士、児童福祉司任用資格などで、配属先によって異なります。また、公務員試験を受け、公務員として採用されることが必須です。なお、社会福祉主事任用資格は、社会福祉士か精神保健福祉士の資格があれば取得できます。
社会福祉主事任用資格を取得するほかの方法や難易度については、「ケースワーカーの資格は難易度が高い?状況別に効率の良い取得方法をご紹介」で解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
まとめ
ケースワーカーのやりがいは、自分の仕事がダイレクトに人の役に立っていると実感できることです。相談支援業務を行うなかで、福祉や法律の専門性を深めたり相談者やそのご家族と信頼関係を築いたりできるのも、仕事の魅力といえます。
また、自分のペースで主体的に仕事を進められるのも、ケースワーカーのやりがいです。相談者のご自宅へ訪問したり、関係各所と連携したりするのには、一定の大変さがあるものの、多くの人との出会いが自身の価値観や信念に良い影響をもたらすこともあります。
ケースワーカーのような相談援助の仕事に興味のある方は、介護業界のソーシャルワーカーや生活相談員として働く道もあります。
介護・福祉業界を専門とする就職・転職エージェントの「レバウェル介護(旧 きらケア)」では、ソーシャルワーカーや生活相談員の求人をご提案可能です。専任のキャリアアドバイザーにご相談いただければ、職種ごとの必要な資格やキャリアパスをお伝えいたします。「ゆくゆくは相談援助業務に携わりたい」「自分が目指せるのか知りたい」という方も、介護転職のプロが一からご提案するので、まずはお気軽にご相談くださいね。
 ソーシャルワーカーの求人一覧はこちら
ソーシャルワーカーの求人一覧はこちら 生活相談員の求人一覧はこちら
生活相談員の求人一覧はこちら
今の職場に満足していますか?