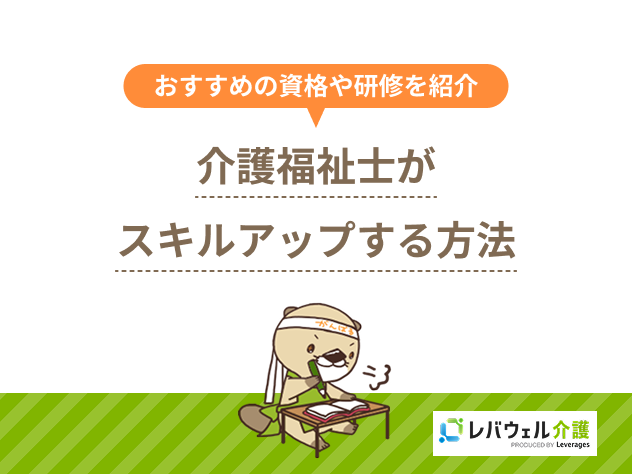
この記事のまとめ
- 介護福祉士がスキルアップするには、資格取得や研修受講が有効
- 介護福祉士のスキルアップに役立つ研修は、喀痰吸引等研修など
- 介護福祉士がスキルアップすると、給与アップにつながる可能性がある
「介護福祉士としてスキルアップしたいけど、何をしたら良い?」とお悩みの方もいるかもしれません。介護福祉士としてスキルアップするには、資格取得や研修受講で専門性を高めることが有効です。この記事では、介護福祉士としてスキルアップ・キャリアアップしたい人におすすめの資格や研修を紹介します。自分のキャリアビジョンに合った資格取得・研修受講をすることで、介護福祉士としての成長を目指しましょう!
介護福祉士とは?仕事内容や資格の取得方法、試験概要をわかりやすく解説!介護福祉士に必要なスキルとは?
介護福祉士に必要なスキルは、介護の専門知識や観察力・判断力、コミュニケーションスキルなどです。介護のプロフェッショナルとして、安全に正しく介護を行うことが求められます。利用者さんのなかには、自分の要望をうまく言葉で伝えられない人や、自分の身体の異変に気づかない人もいるでしょう。普段一番近くで接している介護福祉士が、観察眼を駆使して適切な判断を行うことが必要です。
また、介護の仕事にはチームワークも求められます。利用者さんやご家族とコミュニケーションを取ることはもちろん、職員同士の連携も仕事を円滑にするために不可欠です。
観察力・判断力やコミュニケーションスキルは、経験とともに培われる部分もありますが、知識をアップデートして新しいスキルを身につけることも大切になってきます。
▼関連記事
介護職員として身につけるべき知識を紹介!スキルアップに必要な資格も解説
今の職場に満足していますか?
介護福祉士がスキルアップする方法
介護福祉士が観察力や判断力、コミュニケーションスキルを身につけてスキルアップするには、以下のような方法があります。
資格取得・研修受講を行う
介護福祉士がスキルアップするには、資格取得や研修の受講が有効です。資格取得・研修受講を行うことで、新しい知識やスキルを身につけられます。自身が携わる分野の専門性を深めれば、介護福祉士としてケアや教育を行う際に活かせるでしょう。
資格や研修の内容をよく吟味して、自分がより極めたい分野やキャリアデザインに沿ったものを受験・受講するのがおすすめです。
管理職へキャリアアップする
介護福祉士は、実務経験を積んだり資格を取得したりすることで、施設長や管理者にキャリアアップできる可能性があります。介護福祉士としての経験を活かして管理職になれば、経営やマネジメントのスキルを身につけられるでしょう。
役職や施設の種類によって、管理職になるための要件は異なります。そのため、自身のキャリアの目標を叶えるには、計画的に資格取得や研修受講を行うことが大切です。
他職種にキャリアチェンジする
介護職以外の職種にキャリアチェンジすることで、スキルアップを実現する方法もあります。介護福祉士としての知識やスキルを活かしつつ、新しいキャリアをスタートさせることも可能です。
介護福祉士の資格を持っていると取得しやすい福祉系の資格や、介護福祉士とあわせて取得することでさらに専門性を高められる資格もあります。
キャリアチェンジの際は、介護系・医療系・保育系など、どのフィールドで活躍したいかを十分に検討して、目指す職種を選択するようにしましょう。
スキルアップしやすい職場へ転職する
現在勤務している施設でスキルアップが見込めないという方は、転職するのも選択肢の一つです。
介護施設・事業所のなかには、スキルアップのステップが明示されている職場や、資格取得支援制度を設けている職場もあります。また、「こんな利用者さんのケアをできるようになりたい」「こういう介護を実践したい」のように、やりたい支援をベースに転職先を考えるのも良いでしょう。
たとえば、「自立している利用者さんが多く、高度な介護技術が身につきにくいデイサービスから転職して、介護度が高い人のケアもできるようになりたい」というように、新たなスキルを習得するために転職する方もいます。
スキルアップのために転職する場合は、転職先の教育体制や資格取得支援制度を把握することが、転職成功のカギです。
レバウェル介護(旧 きらケア)では、専任のキャリアアドバイザーがお悩みをヒアリング。求人情報の紹介や面接対策などを通して、「スキルアップできる職場に転職したい」というあなたの希望を叶えるお手伝いをいたします。登録・利用はすべて無料なので、ぜひご利用ください。
今の職場に満足していますか?
独立する
「理想の介護施設を作りたい」という希望がある介護福祉士は、独立して施設や事業所を開業する選択肢もあるでしょう。自分で施設を立ち上げることで、経営方針やサービス内容、人員配置や設備など、理想に近い介護施設が作れます。
ただし、施設の立ち上げには資金や人脈、経営に関する知識が必要です。さらに、介護職員としての知識と経験も求められます。独立を考えている方は、まずは資格取得・研修受講でスキルアップしてから動き始めるのがおすすめです。
介護福祉士のスキルアップに役立つ資格・研修
ここまで、介護福祉士のスキルアップには資格取得や研修受講が有効であることに触れてきました。では、実際にどのような資格や研修が介護福祉士のスキルアップに役立つのか、具体的に紹介します。
喀痰吸引等研修
喀痰吸引等研修では、喀痰吸引と経管栄養の知識や手技を学びます。自力で痰を吐き出すのが難しい利用者さんや、食事を口から摂取するのが難しい利用者さんに、医療的ケアを行うための研修です。
厚生労働省の「喀痰吸引等研修 喀痰吸引等研修の概要 研修課程」によると、喀痰吸引等研修は第1号研修・第2号研修・第3号研修の3種類です。どの研修を受けるかにより、対応できるケアの範囲や、処置を施せる対象者が異なります。喀痰吸引等研修は、講義や演習、実地研修を受けたのち、医療職の審査に合格すると修了です。
受講費用は研修の種類や実施機関によって異なりますが、40,000~250,000円程度で、研修期間は1~4ヶ月ほどとなっています。なお、喀痰吸引等研修は、厚生労働省の人材開発支援助成金の対象です。
厚生労働省の「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内(p.4)」によると、喀痰吸引等研修は人材開発支援助成金の人材育成支援コースの対象になっています。勤務先の事業所が助成金を受給する場合、介護職員は自己負担なしで研修を受講可能です。
なお、介護福祉士の方は、実務者研修や養成施設での学習の際に、喀痰吸引等研修における第1号研修・第2号研修の基礎研修を修了している場合があります。第1号研修・第2号研修を受講する場合、実地研修のみで修了できる可能性があるので、自身の研修歴を確認しておくと良いでしょう。
出典
厚生労働省「喀痰吸引等研修」(2025年2月14日)
厚生労働省「人材開発支援助成金の過去のパンフレット一覧」(2025年2月14日)
▼関連記事
喀痰吸引等研修とは?講義内容や介護職員が受講するメリットも解説
介護福祉士基本研修
介護福祉士基本研修は、介護福祉士の資格を取得してからの実務経験が2年未満の人が対象の研修です。自立支援の視点や、利用者さんの生活を支えるという介護職の役割、介護計画書の作成に活かせる介護過程の展開などを学びます。利用者さんのニーズを的確に理解することで、根拠に基づく介護を実践できるでしょう。
介護福祉士基本研修は、各都道府県の介護福祉会のWebサイトなどから申し込みができ、オンラインで受講できる場合もあるようです。修了にかかる期間は4日程度。費用は介護福祉会によって異なりますが、介護福祉士会の会員は12,000~20,000円程度、非会員は25,000円~30,000円程度です。
出典
公益社団法人 日本介護福祉会「生涯研修体系」(2025年2月14日)
介護福祉士ファーストステップ研修
介護福祉士ファーストステップ研修は、実務経験2~3年程度の介護福祉士を対象とした研修です。利用者さん一人ひとりの状況に応じた介護を行えるだけではなく、小規模チームのリーダーとして指導も行える介護福祉士を育成することを目的としています。
公益社団法人 日本介護福祉会の「介護福祉士ファーストステップ研修ガイドライン(p.7)」によると、介護福祉士ファーストステップ研修のカリキュラムは、ケア領域・連携領域・運営管理基礎領域の3領域です。全200時間のうち100時間は、自職場等課題と通信学習で実施できます。
費用は介護福祉会によって異なりますが、介護福祉士会の会員は75,000~80,000円程度、非会員は100,000~160,000円程度です。
出典
公益社団法人 日本介護福祉会「介護福祉士ファーストステップ研修」(2025年2月14日)
認定介護福祉士
認定介護福祉士は、介護福祉士の上位資格として位置づけられている民間資格です。介護福祉士の資格取得後のキャリアパスの形成を目的として創設されました。認定介護福祉士は、介護サービスの質の向上や効率的な運用、関係機関との連携などを果たす役割を担うことが期待されています。
認定介護福祉士認証・認定機構の「認定介護福祉士を目指す人 AIM」によると、認定介護福祉士になるには、認定介護福祉士養成研修I類(13科目)とII類(9科目)をすべて受講しなければなりません。すべてのカリキュラムを修了し、認定介護福祉士認証・認定機構に申請の手続きをすると、認定介護福祉士を取得できます。研修時間は計600時間で、資格取得までに約1年半~2年かかるようです。
なお、認定介護福祉士養成研修には受講要件が設けられています。介護福祉士としての実務経験が5年以上あることや、介護職員が対象の現任研修を100時間以上受講していることなどの条件を満たす場合に受講可能です。
認定介護福祉士は、介護福祉士としての実務経験が長く、リーダーを任されるようになった方のスキルアップにおすすめの資格といえます。
出典
認定介護福祉士認証・認定機構「認定介護福祉士を目指す人 AIM」(2025年2月14日)
▼関連記事
認定介護福祉士とは?期待される役割や資格取得に必要な研修を解説
介護予防運動指導員(R)
介護予防運動指導員(R)は、筋力トレーニングや介護予防プログラムの作成などを学び、介護予防に関する知識を習得する資格です。
介護予防運動指導員(R)の資格を取得するには、地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所の指定を受けた事業者の講習を受講する必要があります。介護福祉士の資格があれば受講要件を満たせるため、取得を目指しやすい資格です。
講習は33時間の講義と実習で構成され、受講後の修了試験に合格することで介護予防運動指導員(R)を取得できます。講習の一部はeラーニングで受講できる場合があるようです。費用は講座を開講する事業者により異なり、60,000~90,000円程度となっています。介護予防に関する指導やケアに力を入れたい介護福祉士におすすめの資格です。
▼関連記事
介護予防運動指導員のメリットとは?資格の概要と取得方法もご紹介!
レクリエーション介護士
レクリエーション介護士とは、レクリエーションの企画・実施に関する知識や、高齢者とのコミュニケーションのポイントを習得できる資格です。
一般社団法人 日本アクティブコミュニティ協会の「レクリエーション介護士」によると、レクリエーション介護士は2級・1級・マスターに分かれており、2級には受講要件はありません。1級の受講には2級の取得が必要で、マスターの受講には1級の取得が必要です。
レクリエーション介護士2級の資格は、通信講座や通学講座、団体研修で講座を受講することで取得できます。2級の受講料は35,000~40,000円程度です。
介護業務のなかでも、レクリエーションのスキルアップを狙いたい人は、レクリエーション介護士の取得に挑戦すると良いでしょう。
出典
一般社団法人 日本アクティブコミュニティ協会「レクリエーション介護士」(2025年2月14日)
一般社団法人日本アクティブコミュニティ協会「レクリエーション介護士2級」(2025年2月14日)
▼関連記事
レクリエーション介護士とは?資格の取得方法やメリットを分かりやすく解説
重度訪問介護従業者養成研修
重度訪問介護従業者養成研修は、重度の肢体不自由や知的障がい、精神障がいがある方に訪問介護サービスを提供するための知識や技術を習得できる研修です。基礎課程・追加課程・統合課程・行動障害支援課程の4種類があります。
基礎課程は約10時間のカリキュラムで、修了すると障害支援区分4・5の方に対して重度訪問介護のサービスを提供可能です。追加課程も約10時間のカリキュラムで、修了すると障がい支援区分6の方に対してもサービス提供が可能になります。追加課程は、基礎課程を修了した方が対象です。基礎課程、追加課程ともに、費用は15,000~20,000円ほどとなっています。
統合課程は、基礎課程と追加課程の内容に加え、喀痰吸引等研修(第3号研修)の基本研修の内容も学べるのが特徴です。障害支援区分4~6の利用者さんのケアだけでなく、医療的ケアについても学べます。研修時間は20~25時間で、受講料は20,000~35,000円ほどとなっています。
行動障害支援課程は、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)と同等の内容で、強度行動障がいのある方への対応を学べるのが特徴です。カリキュラムは約12時間で、費用は25,000~50,000円ほどとなっています。
重度訪問介護従業者養成研修は、重度障がいのある利用者さんの在宅生活を支援したい介護福祉士におすすめの研修です。
▼関連記事
重度訪問介護に必要な資格とは?研修のカリキュラムや難易度、費用を解説!
介護福祉士のスキルアップに役立つ認知症特化の資格・研修
介護福祉士は認知症の利用者さんのケアを行う機会も多くあります。ここでは、認知症の利用者さんの支援に役立つ資格や研修をまとめました。
認知症介護実践者研修
認知症介護実践者研修は、認知症の利用者さんが役割をもって自立した日常生活を送るための、適切な支援を学ぶ研修です。チームケアの中心となり、認知症介護の質向上を図る人材を育成することを目的としています。
認知症介護実践者研修は、都道府県や都道府県が委託した団体が行っており、主催者により研修期間や費用は異なるでしょう。たとえば、東京都の場合、講義・演習6日と自施設実習およそ4週間で取得でき、受講料は無料です。
認知症介護の実務経験が2年程度以上あることや、介護に関する知識・技術が身についていることを要件としている傾向にあり、介護福祉士は受講対象に当てはまることも少なくありません。
出典
東京都福祉局「東京都認知症介護研修の概要」(2025年2月14日)
▼関連記事
認知症介護実践者研修とは?資格の概要や取得するメリットを解説
認知症介護実践者研修は難しい?資格取得の方法やメリットを解説
認知症介護実践リーダー研修
認知症介護実践リーダー研修は、介護施設・事業所で認知症介護の指導や地域との連携ができるリーダーを育成する研修で、認知症介護実践者研修の上位資格です。受講することで、認知症ケアを行うだけではなく、介護職員の指導や地域資源の活用なども積極的に行える介護福祉士にスキルアップできるでしょう。
東京都の認知症介護実践リーダー研修は、講義・演習8日と他施設実習5日、自施設実習およそ4週間で構成され、受講料は無料。認知症介護の業務におおむね5年以上従事した経験があることや、認知症介護実践者研修を修了して1年以上経過していることなどが要件です。
なお、研修は都道府県や都道府県が委託した団体が行っており、主催者によって研修期間や費用は異なります。
出典
東京都福祉局「東京都認知症介護研修の概要」(2025年2月14日)
▼関連記事
認知症介護実践リーダー研修とは?修了は難しい?受講内容なども解説
認知症介護指導者養成研修
認知症介護指導者養成研修は、認知症介護に関する研修プログラムの作成方法を学んだり、介護職員の指導を行うスキルや専門性を身につけたりできる研修で、認知症介護実践リーダー研修の上位資格です。取得した方は、認知症介護基礎研修や認知症介護実践研修の企画・立案や講師を務め、地域の認知症施策の推進に貢献しています。
東京都における認知症介護指導者養成研修は、9週間の講義・演習・実習です。介護福祉士を含む医療・福祉に関する国家資格を持っていることや、認知症介護実践者研修・認知症介護実践リーダー研修を修了していること、研修の受講が必要と認められることなどを満たさなければ、受講できません。
なお、研修は都道府県や都道府県が委託した団体が行っており、主催者により研修期間や費用は異なります。
出典
東京都福祉局「東京都認知症介護研修の概要」(2025年2月14日)
認知症ケア専門士
認知症ケア専門士は、一般社団法人 日本認知症ケア学会が認定する資格で、認知症介護従事者のスキルアップや学習機会の提供を目的に設けられました。認知症ケア専門士認定試験に合格することで取得可能です。受験資格は、過去10年間に3年以上の認知症ケアの実務経験があることで、試験は第1次試験と第2次試験の2段階で構成されます。
第1次試験の出題範囲は、「認知症ケアの基礎」「認知症ケアの実際I:総論」「認知症ケアの実際II:各論」「認知症ケアにおける社会資源」の4分野です。PCを使って受験するWeb試験で、各分野70%以上正答することで合格となります。4分野すべての合格が必要ですが、各分野の合格有効期限は5年間あるため、不合格となった分野のみの再受験が可能。受験料は1分野につき3,000円です。
第2次試験は、1次試験の合格者のみ受験できます。認知症ケアの事例(3題)に対する論述方式の試験で、受験料は8,000円です。第2次試験にへの合格後、倫理研修の動画を視聴して登録申請を行うことで、資格取得となります。
なお、認知症ケア専門士は5年ごとの更新制です。講座への参加や論文投稿などで30単位以上の「専門士単位」を取得して更新手続きを行わなければ資格を維持できません。
認知症ケア専門士は、認知症ケアの学習を継続できる資格なので、認知症ケアに長期間携わり、専門性を磨きたいと考えている方におすすめです。
出典
一般社団法人日本認知症ケア学会「認知症ケア専門士認定試験」(2025年2月14日)
▼関連記事
【認知症介護の資格一覧】取得方法や試験の難易度、習得できるスキルを解説
介護福祉士から管理職へのキャリアアップに活かせる資格
ここでは、介護福祉士から管理職へキャリアアップするためにおすすめの資格を紹介します。
社会福祉主事任用資格
社会福祉主事任用資格は、自治体の行政機関で相談援助に携わる際に求められる資格です。厚生労働省の「施設長の資格要件等」によると、社会福祉主事任用資格は、特別養護老人ホームの施設長の要件の一つにもなっています。そのため、特養で管理職を目指したい介護福祉士の方は、取得を検討すると良いかもしれません。
厚生労働省の「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」によると、社会福祉主事任用資格を取得するには、「指定の通信教育を1年履修する」「指定養成機関で22科目1,500時間のプログラムを修了する」「都道府県等講習会で19科目279時間のプログラムを修了する」などの要件のいずれかを満たす必要があります。また、社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格を持っている人や、社会福祉に関する科目を3科目以上修めて大学等を卒業した人も、社会福祉主事として勤務可能です。
出典
厚生労働省「施設長の資格要件等」(2025年2月14日)
厚生労働省「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」(2025年2月14日)
▼関連記事
社会福祉主事任用資格とは?活かせる仕事は?取得方法やメリットを解説!
社会福祉士
社会福祉士は、障がいがあることや高齢になったこと、経済的に困窮していることなどを理由に、日常生活に支援が必要な人に対し、相談援助を行うための資格です。相談支援の業務自体は社会福祉士の資格がなくてもできますが、社会福祉士の資格を持っているほうが、活躍できる場が広がります。
介護施設によって要件は異なりますが、社会福祉士の資格があれば、施設長や管理者の資格要件を満たせることも少なくありません。介護福祉士とのダブルライセンスとして取得することで、介護分野と社会福祉分野から利用者さんのケアにアプローチできる管理職として活躍できるでしょう。
社会福祉士になるには、社会福祉士国家試験への合格が必要です。社会福祉士試験を受けるには、養成施設などで社会福祉に関する科目を履修しなければなりません。
厚生労働省の「社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(p.5)」によると、介護福祉士が社会福祉士を目指す場合、社会福祉士の養成課程において60時間を上限に実習が免除されることがあります。ただし、養成機関によっては、介護福祉士養成課程における介護実習を履修していることが実習免除の条件になっている場合も。実務経験ルートで介護福祉士の資格を取得している人は免除を受けられないこともあるため、注意が必要です。
出典
厚生労働省「令和元年度社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて」(2025年2月14日)
▼関連記事
介護福祉士が社会福祉士になるときの免除科目は?受験資格も解説
介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護支援専門員は、ケアマネジャーとして働くための資格。ケアマネジャーとは、利用者さん個々に対してアセスメントを行い、ケアプランを作成することで、介護サービスを適切に利用できるようサポートする職種です。利用者さんやご家族と施設の間に立ち、調整役として業務を行います。
ケアマネジャーとして働くには、介護支援専門員実務研修受講試験に合格したうえで、実務研修を受講することが必要です。介護福祉士の資格を取得してから、資格に基づく業務の実務経験を5年以上(かつ900日以上)積めば、試験の受験資格を得られます。
詳しくは、「介護福祉士からケアマネになるには?受験資格や取得の流れを解説」の記事をご参照ください。
ケアマネジャーも、介護施設・事業所によっては管理者の資格要件に挙げられている場合があります。
また、厚生労働省の「居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置及び地域区分について(p.2)」によると、居宅介護支援事業所の管理者は原則、主任ケアマネジャーであることとされています。主任ケアマネジャーの資格を取得するためには、ケアマネジャーとしての実務経験が通算5年以上必要なため、居宅介護支援事業所の管理者を目指す方は、まずケアマネジャーの資格を取得しましょう。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「介護支援専門員/ケアマネジャー」(2025年2月14日)
厚生労働省「第173回社会保障審議会介護給付費分科会(ペーパーレス)資料」(2025年2月14日)
▼関連記事
ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどんな仕事?業務内容や役割を解説!
精神保健福祉士
精神保健福祉士は、精神障がいのある方の相談に応じ、日常生活や就業のための助言や調整を行うための資格です。精神保健福祉士の資格を取得することで、精神障がいのある方への相談業務に適切に対応できます。
厚生労働省の「資格取得方法」によると、精神保健福祉士国家試験を受験するには、要件を満たさなければなりません。たとえば、「保健福祉系大学などを指定科目を履修して卒業し、修業年数に応じて実務経験を積むルート」「基礎科目の履修や実務経験の要件を満たしたうえで、短期養成施設または一般養成施設で修業するルート」などがあります。
介護福祉士が精神保健福祉士を取得することで、利用者さんの包括的な支援や精神的なケアを、専門性をもって行えるようになるでしょう。また、社会福祉主事の要件を満たせるため、特別養護老人ホームの施設長の要件をクリアすることもできます。
出典
厚生労働省「精神保健福祉士について」(2025年2月14日)
▼関連記事
精神保健福祉士とは?資格の取得方法や仕事内容、社会福祉士との違いを解説
介護福祉士のキャリアチェンジにおすすめの資格
以下では、介護福祉士の資格を活かして別のフィールドで活躍したい方におすすめの資格を紹介します。
福祉用具専門相談員指定講習
福祉用具専門相談員の資格を取得するには、都道府県知事の指定を受けた研修事業者による「福祉用具専門相談員指定講習」の修了が必要です。厚生労働省の「福祉用具・住宅改修(p.38)」によると、カリキュラムは50時間で、講習の最後に修了評価(筆記試験)が実施されます。受講費用は研修事業者により異なりますが、相場は5万円前後です。なお、介護福祉士の資格を保有する方は、新たに講習を受けずに福祉用具専門相談員として働くこともできます。
福祉用具専門相談員は、福祉用具を使用する人やご家族に対し、福祉用具選びのアドバイスを行い、使用方法を伝える職種です。ケアマネジャーから福祉用具に関する相談を受けたり、利用状況のモニタリングを行ったりすることも業務に含まれます。主な職場は、福祉用具貸与・販売事業所です。
福祉用具専門相談員は、福祉用具の提供を通じて、利用者さんの社会参加や介護者の負担軽減を支援したい方におすすめの資格といえます。
出典
厚生労働省「第220回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2025年2月14日)
▼関連記事
福祉用具専門相談員とは?仕事内容や資格要件、指定講習の概要について解説
保育士
保育士は、乳幼児の保育を行ったり、保護者へ保育に関する指導・助言を行ったりするための資格です。
厚生労働省の「ハローミライの保育士 保育士になるには?」によると、指定保育士養成施設を卒業することで、保育士の資格を得られます。また、指定保育士養成施設以外の大学・短大・専門学校を卒業または、保育の実務経験を2年以上経験した人は、保育士試験に合格することで資格を得られる仕組みです。
同省の「福祉系国家資格所有者等の保育士資格取得への対応について(概要)(p.2)」によると、介護福祉士の資格を持っている人は、保育士試験の筆記科目のうち社会福祉・児童家庭福祉・社会的養護の受験が免除されます。また、指定保育士養成施設で学ぶ場合も、前述の試験科目に対応する6つの教科目の履修が免除されるため、介護福祉士は保育士の資格を取得しやすいといえるでしょう。
出典
厚生労働省「ハローミライの保育士 保育士になるには?」(2025年2月14日)
厚生労働省「福祉系国家資格所有者等の保育士資格取得への対応について (報告書)」(2025年2月14日)
看護師
看護師は、医師の診療の補助や、患者さんの療養上のお世話などを行うための資格です。医療機関や介護施設に加え、自治体の公的機関や一般企業、幼稚園など、さまざまな場所で活躍しています。
公益社団法人 日本看護協会の「看護職になるには」によると、高校卒業後に看護大学・看護短大・看護師養成所で3~4年の課程を修了したうえで、看護師国家試験に合格することで、看護師免許を取得可能です。
介護福祉士が看護師の資格を取ると、看護と介護の2分野のスペシャリストとして、業務の幅を広げられます。そのため、看護師の資格は、介護施設や医療機関でより専門性の高いケアを行いたい方におすすめです。
出典
公益社団法人 日本看護協会「看護職になるには」(2025年2月14日)
理学療法士
理学療法士は、ケガや病気、老化、障がいがあるなどの理由で身体を思うように動かせない方に対し、立つ・座る・歩くなどの基本動作の回復を目的とした理学療法を行うための資格です。介護施設や病院、リハビリセンター、障がい者福祉センターなどで活躍しています。
職業情報提供サイト(日本版O-NET)の「理学療法士(PT)」によると、理学療法士養成校で3~4年の課程を修了し、理学療法士国家試験に合格することで、理学療法士になることが可能です。介護福祉士が理学療法士の資格を取れば、介護に精通したリハビリ職として活躍できるでしょう。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「理学療法士(PT)」(2025年2月14日)
作業療法士
作業療法士は、身体障がいのある方や精神障がいのある方の日常生活・社会生活を支援するための資格です。食事や歯磨きといった日常生活の動作や、家事・芸術活動・スポーツ活動などの訓練・指導・援助を行います。医療機関や障害者支援施設、介護施設などで活躍可能です。
職業情報提供サイト(日本版O-NET)の「作業療法士(OT)」によると、作業療法士養成校で3~4年の課程を修了し、作業療法士国家試験に合格することで、作業療法士になることができます。
作業療法士は、身体障がいのある人だけではなく精神の障がいがある人へもリハビリを行えるのが特徴です。リハビリで支援できる人の幅が広いため、より多くの方にリハビリサービスを提供したい人におすすめの資格といえます。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「作業療法士(OT)」(2025年2月14日)
言語聴覚士
言語聴覚士は、言葉によるコミュニケーションや、嚥下が困難な人を対象に、問題解決に向けた支援を行うための資格です。医師や歯科医師の指示のもと問題の本質を探り、状況に応じた訓練や指導を行います。病院やリハビリセンター、介護老人保健施設などで活躍しています。
職業情報提供サイト(日本版O-NET)の「言語聴覚士」によると、言語聴覚士養成校で3~4年の課程を修了し、言語聴覚士国家試験に合格することで、言語聴覚士になることが可能です。また、指定科目を履修済みの場合は、養成校で1~2年の課程を修了すれば試験を受験できます。
介護施設の利用者さんは、老化により口腔機能が低下していることもあるでしょう。介護福祉士と言語聴覚士のダブルライセンスを取得することで、介護分野の観点を取り入れた訓練や指導を行えます。
出典
職業情報提供サイト(日本版O-NET)「言語聴覚士」(2025年2月14日)
介護福祉士がスキルアップで得られるメリット
ここまで、介護福祉士におすすめの資格や研修を紹介してきました。では、資格取得や研修受講でスキルアップした介護福祉士は、どのようなメリットを得られるのでしょうか。
提供できるケアの幅・活躍の場が広がる
介護福祉士がスキルアップすると、提供できるケアの幅が広がります。対応できる業務が増えると、介護施設以外の職場でも働けるなど、活躍の場が広がるでしょう。
たとえば、理学療法士や作業療法士などのリハビリに特化した資格を取得すれば、介護だけではなくリハビリも行える介護福祉士になれます。また、社会福祉士とのダブルライセンスを取得すると、利用者さんの身体的なケアだけでなく、生活状況に関する相談対応を行い、社会資源を活用するための適切な支援を行えるでしょう。
給与アップにつながる
介護福祉士がスキルアップすると、給与がアップする可能性があります。特に、介護福祉士より上位の資格や、ほかの国家資格を取得した場合に、介護福祉士より高い給与をもらえる場合があるでしょう。
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.157)」によると、2022年9月における介護職員(月給制・常勤の者)の保有資格別の平均給与額は、以下のとおりです。
| 保有資格(複数回答) | 平均給与額 |
| 介護福祉士 | 33万1,080円 |
| 社会福祉士 | 35万120円 |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 37万6,770円 |
| 介護福祉士実務者研修 | 30万2,430円 |
| 介護職員初任者研修 | 30万240円 |
| 保有資格なし | 26万8,680円 |
参考:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.157)」
介護福祉士よりも、社会福祉士やケアマネジャーのほうが給与が高い傾向があることが分かります。そのため、介護福祉士がダブルライセンスを取得することで、さらに給与を上げられる可能性があるでしょう。
出典
厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2025年2月14日)
▼関連記事
介護福祉士の給料は高い?安い?平均年収や給与アップの方法までご紹介
キャリアアップにつながる
介護福祉士が新たなスキルを身につけると、キャリアアップにつながる可能性があります。保有資格が多い介護福祉士は、その分知識やスキルを豊富に持っていると判断され、リーダー職や管理職に昇進できることも。介護福祉士としてキャリアを積んでいきたいと考えている人にとって、資格取得や研修受講によるスキルアップは有効です。
転職活動で有利になる可能性がある
介護福祉士がスキルアップすると、転職活動で有利になる可能性があります。「次の施設でも介護福祉士として働きたい」と考えている場合、資格や研修歴があると頑張ってきたことをアピールする根拠になるため、応募先で評価されやすくなるでしょう。
今すぐの転職を考えていない場合でも、将来に備えて資格取得や研修受講を行っておくと、転職しようと思ったときに自分の強みになるかもしれません。
資格取得前に介護福祉士が確認すべきこと
ここでは、介護福祉士が新たな資格を取得するときに、押さえておきたいステップを紹介します。資格取得を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
自分のキャリアビジョンと資格の相性
取得しようとする資格が、自分のキャリアビジョンや興味に合っているかを確認しましょう。たとえば、介護福祉士としてより介護領域の専門性を極めたい場合は、認定介護福祉士や介護支援専門員の資格が候補になります。医療系のスキルを習得したい場合におすすめの資格は、看護師や理学療法士、作業療法士などです。
自分の目指すキャリアが固まったら、必要なスキルや業務内容をよく確認して適した資格を選んで挑戦することで、理想のキャリアビジョンに近づけるでしょう。
資格取得に必要な条件
取得したい資格や受講したい研修がある場合、受験資格や受講要件がないか確認することも重要です。
資格や研修は、要件がなく誰でも受けられるものや、研修の受講が必要なもの、別の資格の有無や実務経験を問われるものなどがあります。受験資格や受講要項をすでに満たしているのか、満たすためにはどうすれば良いのかにも注目して、取得する資格を選ぶと良いでしょう。
資格取得までの費用や時間
資格取得までの費用や時間を把握することも大切です。取得にかかる費用は資格や受講先によって差があり、数十万円必要な場合も。資格取得のために養成学校に入学する必要がある場合は、学費がかかります。また、受験資格として必須の研修を受講するために、費用や時間がかかる場合もあるようです。
資格取得の際は、費用や時間を確保できるかも、事前に確認しておきましょう。資格によっては、国や自治体から費用の助成を受けられる場合もあるため、助成制度があるか、助成の条件に当てはまるかの確認も必要です。なお、助成制度に関しては、「介護福祉士がスキルアップのために受けられる支援」で後述します。
資格取得の難易度
資格取得時に試験がある場合は、難易度を把握しておきましょう。たとえば、ケアマネジャーになるために合格が必要な「介護支援専門員実務研修受講試験」の合格率は20%前後です。5人に1人程度しか合格できないため、勉強時間をしっかり確保したうえで試験に臨まなければ、合格するのは難しいでしょう。
一方、学習の到達度の確認として研修の最後に行われる修了試験は、学んだ内容を確認することが目的のため、修了試験のある資格を取得する難易度はそれほど高くないこともあります。
資格取得の難易度が高い試験に挑戦する場合は、半年以上前から余裕をもって取り組み、計画的に勉強を進めることが大切です。
出典
厚生労働省「第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」(2025年2月14日)
介護福祉士がスキルアップのために受けられる支援
ここでは、資格取得や研修受講にかかる費用などの負担を軽減するための支援制度を紹介します。資格取得や研修受講を考えている介護福祉士は、支援制度を活用してスキルアップを図るとスムーズです。
教育訓練給付制度
教育訓練給付制度は、労働者がキャリアアップや再就職のために必要な学びや訓練を受ける際に、その費用の一部を助成する制度です。厚生労働省が運営しており、雇用保険に加入している人などが対象となっています。
厚生労働省の「教育訓練給付制度のご案内」によると、教育訓練は専門実践教育訓練(給付率最大80%)・特定一般教育訓練(給付率最大50%)・一般教育訓練(給付率20%)に分かれており、対象の教育訓練は約16,000講座です。社会福祉士や保育士、介護支援専門員実務研修などの資格や研修も給付対象に含まれます。
スキルアップ・キャリアアップのために資格を取得したい介護福祉士の方は、教育訓練給付制度の対象講座を確認し、助成を受けながら資格取得を目指すのもおすすめです。
出典
厚生労働省「教育訓練給付制度」(2025年2月14日)
就業先の資格取得支援制度
介護施設・事業所のなかには、独自の資格取得支援制度を設けている職場もあります。研修の受講料や資格の受験料を事業所が負担してくれる場合があるでしょう。また、研修受講が必要な場合に勤務日を調整してもらえたり、研修日に給料が支給されたりすることもあるようです。
資格取得支援制度の対象の資格や支援内容、要件は施設によって異なるため、取得したい資格や受講したい研修がある場合は、就業先に確認してみると良いでしょう。
介護福祉士のスキルアップに関するよくある質問
ここでは、介護福祉士のスキルアップに関するよくある質問にお答えします。
介護福祉士がダブルライセンスを取るときにおすすめの資格は?
介護福祉士のダブルライセンスとしておすすめの資格は、社会福祉士や精神保健福祉士、介護専門支援員(ケアマネジャー)などです。介護分野に+αで身につけたい分野の資格や、将来のキャリアプランと照らし合わせて、取得する資格を決めると良いでしょう。
詳しく知りたい方は、この記事の「介護福祉士から管理職へのキャリアアップに活かせる資格」や「介護福祉士のキャリアチェンジにおすすめの資格」も参考にしてみてください。
資格取得のための勉強時間が取れません…
勉強の時間を確保するには、「仕事の日でも1日10分だけは必ず勉強する」「休みの日に勉強時間をまとめて確保する」「通勤や家事の合間などのスキマ時間で勉強を進める」などの方法があります。資格取得を成功させるためには、計画的に勉強することが大切です。
介護施設のなかには、資格取得のための勉強会を開催するといった支援が充実している施設もあります。「今の職場は忙しすぎて勉強時間が取れない…」という方は、資格取得支援制度が充実している職場に転職してから、資格取得を目指す選択肢もあるでしょう。
まとめ
介護福祉士がスキルアップするには、資格取得や研修受講、キャリアチェンジ、独立などの方法があります。
介護分野の専門性を高めたい方には、認定介護福祉士や介護支援専門員、社会福祉士などの資格がおすすめです。医療分野を学んでスキルアップしたい介護福祉士の方は、看護師や理学療法士のようなキャリアチェンジにつながる資格の取得に挑戦する選択肢もあるでしょう。介護福祉士のスキルアップにつながる資格は多くあるため、自分のキャリアビジョンに合うものを選択することが大切です。
「今の施設でスキルアップできる気がしない…」「資格を取りたいけど時間がない」という介護福祉士の方は、転職することでお悩みを解消できる可能性があります。介護・福祉業界専門の転職エージェントのレバウェル介護(旧 きらケア)では、職員のキャリア育成・スキルアップに力を入れている施設や、資格取得支援が充実している施設など、あなたに合った介護の求人を紹介可能です。キャリアアドバイザーが、キャリアプランや取得すべき資格についてなどの相談にも対応しています。
登録・利用は無料で、相談のみの利用もできるため、スキルアップについて考えている介護福祉士の方は、ぜひレバウェル介護(旧 きらケア)をご活用くださいね!
今の職場に満足していますか?
 資格取得支援の介護求人一覧はこちら
資格取得支援の介護求人一覧はこちら