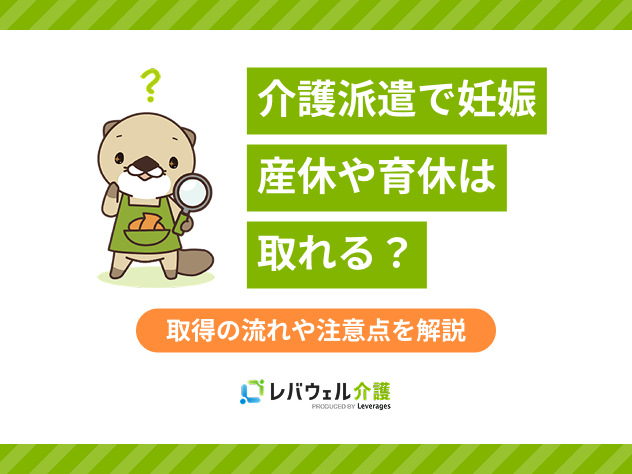
この記事のまとめ
- 介護派遣で妊娠しても、産休や育休を取得して仕事を続けることができる
- 産休や育休を取得するメリットは、一定の収入や回復の時間を確保できること
- 妊娠中に避けるべき業務は、夜勤や入浴介助など身体への負担が大きい業務
「介護派遣で妊娠しても仕事を続けられる?」と疑問をお持ちの方もいるかもしれません。産休の取得は派遣社員にも認められており、妊娠を理由にした解雇は違法であるため、妊娠しても仕事を続けることが可能です。この記事では、介護派遣社員が妊娠した場合について、産休・育休取得から復帰までの流れを解説します。妊娠中に行える業務と避けるべき業務もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
介護派遣とは?メリット・デメリットや働くまでの流れ、実際に働いている方の声もご紹介妊娠しても介護派遣の仕事はできる?
妊娠をしても介護派遣として働くことは可能です。妊娠を理由に解雇するのは違法なので、妊娠したからといって仕事を辞めなければならないことはありません。妊娠中に仕事をする場合は、派遣先の理解を得て無理のない範囲で働きましょう。
産休の取得は、正社員だけではなく、派遣社員やパート、契約社員といった有期雇用の労働者にも認められています。また、子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約が終了することが明らかでない方は、育休の取得も可能です。ただし、育休中に契約が満了する場合は、契約が更新されない可能性があります。
出典
厚生労働省「「妊娠したから解雇」は違法です」(2025年3月11日)
▼関連記事
介護職は育休をどのくらい取れる?復帰後の働き方をアドバイス
社保即日加入できます!
介護派遣社員が妊娠した場合の流れ
介護派遣社員が妊娠をして産休・育休を取得する場合、派遣会社に報告する必要があります。報告から休暇を取得するまでの流れは以下のとおりです。
妊娠を派遣会社に報告する
介護派遣社員が妊娠をしたら、できるだけ早く派遣会社に報告しましょう。派遣会社に報告し、就業先である派遣先に連絡してもらう流れです。介護の現場では、身体に負担がかかる介助も多く、妊娠中にはできない業務もあるでしょう。早めに報告することで、就業先での業務を調整してもらいやすくなります。
産休・育休を取得する
介護派遣社員が産休・育休を取得する場合は、以下の流れで申請しましょう。
産休・育休制度の内容を確認する
まずは、産休・育休制度の内容を確認しましょう。休業期間中の給与がどの程度支払われるのか、祝い金があるのかなどは、会社によって異なります。収入に関わる部分のため、就業規則を確認したり、派遣会社の担当者に直接尋ねたりして、しっかりと制度を把握するようにしてください。
休業中に派遣会社から給与が支払われない場合も、一定の要件を満たす方は社会保険の補償を受けられます。産前・産後休業は健康保険の「出産手当金」の対象で、育児休業は雇用保険の「育児休業給付金」の対象です。
業務の引き継ぎをする
産休・育休制度について確認できたら、休業に備えて業務の引き継ぎをしましょう。社会人として、産休・育休に入ることで業務に支障が出ないよう配慮する必要があります。マニュアルを作成したり、書類やデータの整理をしたりしておくと、ほかの職員へ引き継ぎがしやすくなります。
産休・育休を申請する
産休・育休に入る準備が整ったら、就業規定に従って休暇申請をしましょう。まずは産休を取得したい旨を申し出ます。その後、申請書や本人確認書類など、休業補償に必要な書類を確認し、期日までに提出しましょう。
基本的に申請を受けて会社が休業補償の手続きをしますが、対応が必要なことがないかもあわせて確認するのがおすすめです。
介護派遣社員の産休の取得方法
介護派遣社員が産休を取得する場合、派遣先ではなく、所属している派遣会社に申請をします。派遣先とは雇用関係にないため、産休の申請はできません。
労働基準法第65条によると、申請すれば出産予定日の6週間前から産休を取得できます。派遣会社によっては申請時期が定められていることもあるため、契約内容や就業規則に従い、早めに申請しましょう。
出産予定日までの6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は、希望した場合に必ず休業を取れる期間です。産後は、申請することで8週間は必ず休業を取れます。産後6週間は希望しても仕事をできませんが、6週間経過後は、本人の希望と医師の許可があれば就業可能です。
出典
e-Gov法令検索「労働基準法」(2025年3月11日)
介護派遣社員の育休の取得方法
介護派遣社員が育休を取得する場合、産休と同じく所属している派遣会社に申請します。育休は、子どもが1歳6ヶ月を迎えるまでに雇用契約が満了しないことが取得条件です。労使協定に定められている場合は、一つの派遣会社での雇用期間1年以上という条件も満たさなければなりません。
なお、雇用主は契約締結の際、更新の可能性の有無や判断条件を、労働者に明示する義務があります。
育休は取得開始予定の1ヶ月前までに申請が必要です。基本的には子どもが満1歳になるまで取得でき、状況によっては1歳6ヶ月まで、さらに休みが必要な場合は最大2歳まで延長可能です。
以下の支給要件を満たす場合、育児休業給付金の支給を受けることもできます。
- 雇用保険の被保険者である
- 1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある。ない場合は、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上の完全月が12ヶ月以上ある
- 育児休業開始日から1ヶ月ごとの期間中の就業日数が、10日以下もしくは80時間以下である
- 子どもが1歳6ヶ月に達するまでの間に契約が満了することが明らかではない
育児休業給付金は、育休を取得してから半年間は月額賃金の67%、半年以降は50%を受け取れる制度です。支給日数は原則30日間となっています。
出典
e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(2025年3月11日)
厚生労働省「育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について」(2025年3月11日)
厚生労働省「育児休業等給付について」(2025年3月11日)
介護派遣社員が産休や育休を取得するメリット
産休や育休を取得すると、以下のようなメリットがあります。
一定の収入を維持できる
産休や育休を取得する大きなメリットとして、働けない期間も一定の収入を維持できることが挙げられます。出産手当金や育児休業給付金によって収入を確保できるため、金銭的な不安を軽減させて出産・育児に専念できるでしょう。
社会保険料が免除される
産前・産後休業中や育児休業中は、社会保険料の支払いが免除されるメリットもあります。産休や育休によって一時的に社会保険料が免除されても、健康保険の給付は通常どおり受けることが可能です。免除期間分も将来受け取る年金額に反映されます。
産前・産後休業中や育休中に給与が支払われていない場合は、雇用保険料の負担もありません。
出典
厚生労働省「産前・産後休業中、育児休業中の経済的支援」(2025年3月11日)
家族との時間や体調回復の時間を確保できる
産休・育休を取得することによって、家族と過ごす時間や体調回復の時間を確保できます。妊娠中・出産後は体調が安定しない場合があり、問題なく働けるまで時間を要する方もいるでしょう。産休や育休を取得することで、焦らずに休むことができ、体調回復に専念できます。
働き慣れた環境で復帰できる
働き慣れた環境で復帰できるのも、産休・育休を取得するメリットの一つです。妊娠を機に退職してしまうと、新しい環境で働くことになり、慣れるまで時間がかかるデメリットがあるでしょう。産休や育休を取得して同じ派遣会社の利用を継続できると、仕事に関する相談もしやすくて安心です。
復帰後に勤務先があることの安心を得られる
復帰後に勤務先がある安心感を得られる点も、産休や育休のメリットです。退職した場合、休業中に就職への不安を抱えることがあります。復帰後の勤務先が確保できていれば、就活をしなくても働けるという安心感があり、精神的な負担を軽減できるでしょう。
介護派遣社員が産休や育休を取得するデメリット
介護派遣社員が産休や育休を取得すると、以下のようなデメリットを感じる可能性があります。「介護派遣社員が産休・育休を取得しても大丈夫?」と不安な方は、チェックしてみましょう。
産前とは異なる派遣先で働く可能性がある
産休や育休からの復帰後に、必ずしも休業前と同じ派遣先で働けるとは限りません。場合によっては、産前とは異なる就業先に派遣されることもあります。その場合、人間関係を一から構築しなければならないことや、新しい業務に慣れることに負担を感じるかもしれません。
復帰後の派遣先で育児の融通が利かない場合もある
派遣社員として復帰することができても、派遣先で育児の融通が利かない場合もあります。派遣先の職員の人数が十分でなかったり、忙しく休みを取りにくかったりすると、育児のための早退や欠勤に対し理解を得られないことも。育児と仕事を両立させにくい環境だと感じたら、業務量の調整や派遣先の変更ができないか、派遣会社に相談してみましょう。
ハラスメント被害に遭う可能性がある
ハラスメントは許されない行為ですが、残念ながら一部の職場では、産休や育休を取得する職員へのハラスメントが発生することがあるようです。
育児のための早退・欠勤に対してあからさまに嫌な顔をされたり、嫌がらせをされたりすることは、マタニティハラスメントにあたります。また、妊娠・出産を理由とした減給や解雇などの不利益な扱いは法律違反です。
妊娠中に行える介護業務と避けるべき介護業務
介護の仕事は身体的な負担が大きく、妊娠中に避けるべき業務もあります。妊娠中に行える介護業務と避けたほうが良い介護業務を把握しておきましょう。
妊娠中に行える介護業務
妊娠中に行えるのは、比較的身体に負担の少ない業務です。食事介助や口腔ケア、レクリエーションの実施、事務作業などは、身体への負担が少なく妊娠中でも行いやすいといえます。業務の調整をしてもらうときには、これらの業務を割り振ってもらえるように相談してみましょう。
妊娠中に避けるべき介護業務
妊娠中に避けるべきなのは、入浴・排泄・移乗・移動の介助といった、身体的な負担の大きい介護業務です。これらの業務は利用者さんの身体を支える際に負担がかかりやすく、特に入浴介助は転倒のリスクがあります。
また、夜勤は生活リズムが乱れやすく、心身のストレスが胎児に影響する可能性があるため避けるのが無難です。
▼関連記事
【介護職が妊娠したら】報告タイミングや出産までの仕事内容、注意点を解説
介護派遣社員は妊娠するといつまで働けるのか
介護派遣社員も正社員と同じく、基本的には出産予定日の6週間前まで働きます。双子など、多胎妊娠の場合は出産予定日の14週間前までです。
産前休業は、「出産予定日の6週間前」以降であれば自分で開始日を決められるため、妊娠の経過が順調な場合は出産の直前まで働くこともできます。ただし、つわりが重かったり、医師から安静の指示が出たりした場合は、無理をしてはいけません。自分の体調に合わせて、医師や派遣会社と相談しながら休業の時期を決めましょう。
介護派遣社員の妊娠中の注意点
妊娠中は、以下のような点に注意しながら働くようにしましょう。
周囲の協力への感謝を忘れない
妊娠中は周囲との協力が必須です。介護業務の中にできないものがあったり、体調や検診の都合で急な休みを取ったりすることもあるでしょう。そうした場合、ほかのスタッフに負担をかけてしまうことになります。
「妊娠中だから配慮してもらって当たり前」と思っていると、理解を得ることが難しくなってしまう可能性も。できる業務はなるべく行い、周囲のスタッフへ感謝を伝えることで、妊娠に対して理解を得やすくなります。
ストレスを抱え過ぎないようにする
妊娠中に過度なストレスを抱え込むと、胎児に悪影響を及ぼす可能性があります。仕事でストレスをため込みやすい方は、自分なりのストレス解消法を見つけたり、体調に合わせて休んだりして、できるだけストレスを抱えないようにしましょう。
介護士におすすめのストレス解消法については、「介護士さんにおすすめのストレス発散法は?調査してみました!」の記事をご参照ください。
介護派遣社員が産休・育休から復帰する流れ
介護派遣社員が産休・育休から復帰するときは、仕事を開始する前に下記のような準備をする必要があります。
復職の時期を決める
まずは、いつ復職するのかを決めましょう。出産後の体調が良好な人もいれば、なかなか回復しない人もいるため、産休・育休から復帰できる時期は人によって異なります。確実に復帰できるめどが立ち次第、早めに派遣会社に伝えましょう。
子どもを預ける場所を決める
仕事に復帰できる体力があっても、子どもを預ける場所が決まっていないと、思うように働けない可能性があります。保育施設を決めたり、パートナーや親戚と相談してお世話してくれる人を探したりと、子どもを預ける場所を確保することで落ち着いて仕事ができます。もし預け先が見つからない場合は、早めに育休延長の申請をしましょう。
働き方を決める
自身の状況に応じて、復帰後の働き方を決めることも大切です。前と同じように働く、時短勤務をする、出勤日数を減らすなど、さまざまな働き方があります。無理なく育児と仕事を両立させられる働き方を考え、それに合った派遣先を紹介してもらいましょう。
介護派遣の妊娠に関するよくある質問
ここでは、介護派遣の妊娠に関するよくある質問に回答します。「妊娠しても仕事を続けられるか知りたい」という方は、参考にしてみてください。
介護派遣社員が妊娠中に契約満了するとどうなりますか?
妊娠を報告する前に契約更新をしないことが決まっている場合は、妊娠中に契約が満了するとそのまま雇用契約が解除されます。ただし、妊娠を理由に解雇したり契約更新をしなかったりすることは法律違反です。更新回数の上限や契約を更新しない旨が明示されている場合を除き、妊娠中に契約が解除されることは基本的にはありません。また、育休の取得条件は、子どもが1歳6ヶ月になるまでに雇用契約が満了する予定がないことです。
妊娠初期の介護職は夜勤や入浴介助を行っても良いですか?
妊娠初期に体調が安定しており、妊娠前と同じような業務をしたい方もいるかもしれません。しかし、妊娠初期であっても、夜勤や入浴介助などの身体に負担がかかりやすい業務は、可能であれば避けることが望ましいでしょう。夜勤は生活リズムが乱れる可能性があり、入浴介助は転倒などのリスクがあります。妊娠中は、初期・後期に関わらず、体調に負担のかかる業務を減らすことが望ましいので、雇用主に相談するのがおすすめです。
まとめ
妊娠をしても、介護派遣として仕事を続けることは可能です。有期雇用の労働者も産休を取得でき、条件を満たせば育休も取得できます。妊娠が発覚した場合は、できるだけ早く派遣会社に報告し、業務の調整や産休・育休の取得に向けて準備を進めましょう。休業に入る前には、しっかりと業務の引き継ぎをすることも大切です。
産休や育休の取得には、補償によって一定の収入を維持できたり、家族との時間を確保できたりするメリットがあります。休業後の勤務先があることで、働き慣れた環境で復帰できる安心感も得られるでしょう。一方で、復帰後に産前とは違う派遣先で働くことになる場合もあるようです。
復帰したものの、育児と仕事の両立が難しくなったり、マタハラによって働きにくくなったりした場合は、派遣会社を変更する選択肢もあります。もし転職をお考えの場合は、ぜひレバウェル介護(旧 きらケア)をご利用ください。「また介護派遣として働きたい」「正社員を目指したい」など、ご希望に合わせて求人をご紹介します。サービスは無料なので、気軽にご相談ください。
社保即日加入できます!
 派遣の求人一覧はこちら
派遣の求人一覧はこちら