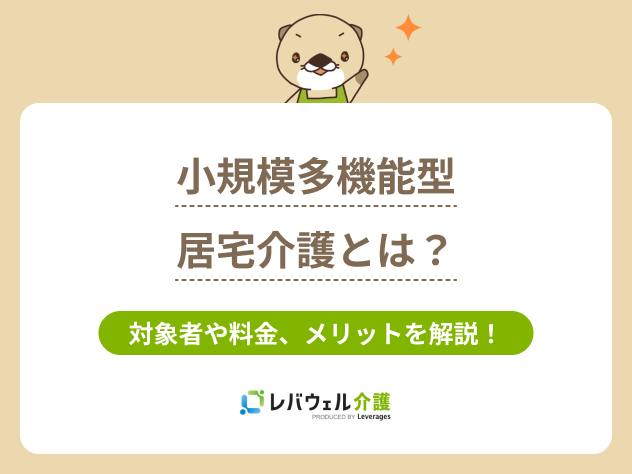
この記事のまとめ
- 小規模多機能型居宅介護とは、通い・訪問・泊まりに対応した介護サービス
- 小規模多機能型居宅介護のサービス料金は定額制で、利用回数に左右されない
- 小規模多機能型居宅介護を利用するメリットは、回数制限がないことなど
介護保険について調べていて、「小規模多機能型居宅介護とはどんなサービスなの?」と疑問に感じる方もいるでしょう。小規模多機能型居宅介護とは、「通い」を中心に、「訪問」「泊まり」を組み合わせて利用できる、地域密着型の介護サービスです。この記事では、小規模多機能型居宅介護の利用対象者やサービス内容を解説します。利用に向いている人の特徴もご紹介。人員配置や職員の仕事内容もまとめたので、参考にしてください。
小規模多機能型居宅介護とは
小規模多機能型居宅介護とは、「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせて利用できる介護サービスです。要介護や要支援の認定を受けた方が、自宅での生活を継続できるようサポートする役割があり、日常生活のケアや機能訓練を提供しています。小規模多機能型居宅介護は、省略して「小多機」と呼ぶこともあるようです。
小規模多機能型居宅介護を利用できる対象者
小規模多機能型居宅介護を利用できるのは、要介護1~5の方。要支援1・2の認定を受けた方も、予防給付として利用可能です。住み慣れた地域での生活をサポートする「地域密着型サービス」のため、事業所と同じ市区町村に住民票があることも、利用の条件となっています。
小規模多機能型居宅介護を利用している方の状況
厚生労働省の「小規模多機能型居宅介護」を参考に、実際にどのような方が小規模多機能型居宅介護のサービスを利用しているのか、ご紹介します。
要介護認定を受けている利用者さんの内訳を見ると、要介護1の方が最も多く、要介護5の方は1割を切っている状況です。自宅で暮らす方が利用する小規模多機能型居宅介護は、入居型の施設と比べ、介護度が低い利用者さんの割合が高くなっています。また、利用者さんの世帯構成は、日中独居の方が73.4%、高齢者のみ世帯の方が68.4%。昼間の見守りや日々の支援が必要な方が、サービスを活用しているようです。
小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心として、必要に応じて「訪問」「泊まり」のサービスを併用するために、2006年に創設されました。その目的のとおり、複数のサービスを組み合わせて利用している方が、7割以上です。具体的には、「通い+訪問」もしくは「通い+泊まり」という組み合わせでサービスを使う方が多くなっています。
小規模多機能型居宅介護事業所の定員
小規模多機能型居宅介護事業所は、名前のとおり小規模なのが特徴で、以下のような利用定員の規定があります。
- 事業所に登録できる定員は29人まで
- 通いサービスの1日の利用定員は15人まで(一定の要件を満たせば18人まで)
- 泊まりの1日の利用定員は9人まで
小規模多機能型居宅介護事業所の利用定員は29人で、サービスごとに定員が決まっています。通いのサービスの1日の定員は15人が基本です。登録定員が26人以上で、居間・食堂が十分な広さを確保できている場合は、通いの1日の定員を18人にできます。
なお、上記の定員数の省令は、「従うべき基準」ではなく、「標準基準」です。そのため、地域の実情に応じて、地方自治体が独自に定員のルールを策定した場合は、そちらに従うことになります。
出典
厚生労働省「第218回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2024年5月9日)
今の職場に満足していますか?
小規模多機能型居宅介護のサービス内容
小規模多機能型居宅介護を利用する場合、ケアプラン(介護サービス計画書)をもとに、「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせて利用することになります。365日24時間サービスを利用できるのが特徴です。下記では、小規模多機能型居宅介護が提供する、ケアプラン作成と3つの介護サービスについて解説します。
ケアプランの作成
小規模多機能型居宅介護を利用するにあたり、その事業所のケアマネジャーが、利用者さんのケアプランを作成します。ケアプランに記載するのは、利用者さんのニーズ、サービスの内容・頻度などです。ケアマネジャーは、利用者さんやご家族と話し合ったり、主治医の意見を参考にしたりして、サービスの利用計画を立てます。
ケアプランの作成は、サービス利用開始時に行うだけではありません。利用者さんが生活するなかで、認知機能や身体機能、家庭環境などは変化することも。常に必要なサービスが行き届くよう、ケアマネジャーは利用者さんの現状を把握し、ケアプランを随時見直します。
▼関連記事
小規模多機能でのケアマネの仕事内容は?施設形態と合わせて解説
通いの介護サービス
小規模多機能型居宅介護の通いで提供するのは、以下のようなサービスです。
- 送迎
- 健康チェック
- 食事の提供
- 食事介助
- 服薬介助
- 入浴介助
- 排泄介助
- 機能訓練
- レクリエーション
通いのサービスは、高齢者が安心して利用できるよう、車で送迎を行うのが一般的です。利用者さんは、食事や入浴、レクリエーションなどをして過ごします。「食事と服薬が終わったら帰宅する」「午後から通い、入浴やレクリエーションを行う」というように、短時間の利用も可能です。
訪問の介護サービス
小規模多機能型居宅介護の訪問で提供するのは、以下のようなサービスです。
- 健康チェック
- 食事介助
- 服薬介助
- 入浴介助
- 排泄介助
- 買い物同行
- 通院介助
- 調理
- 掃除
- ゴミ出し
- 洗濯
- 買い物代行
訪問サービスでは、身体的なケアに加え、生活に必要な家事の支援も行います。1日に複数回の服薬介助や排泄介助が必要な場合に、ピンポイントで利用しやすいのが特徴です。また、夜間や早朝の介護ニーズがある方も利用しています。
泊まりの介護サービス
小規模多機能型居宅介護の泊まりでは、宿泊に伴って必要となる介護サービスを提供します。具体的なサービス内容は、食事の提供や服薬介助、就寝・起床の介助、夜間の見守り・排泄介助などです。急な泊まりや連泊にも対応できます。泊まりのサービスは、ご家族の介護負担の軽減を目的に利用されることも少なくありません。
小規模多機能型居宅介護の利用にかかる料金
小規模多機能型居宅介護は、介護保険サービスなので、一部の自己負担で利用できます。介護保険の負担割合が1割の場合の、1ヶ月あたりの利用料金の目安は、以下のとおりです。
| 介護度 | 一般的な住居で暮らす方の場合 | 併設された有料老人ホームなどで暮らす方の場合 |
| 要支援1 | 3,438円 | 3,098円 |
| 要支援2 | 6,948円 | 6,260円 |
| 要介護1 | 10,423円 | 9,391円 |
| 要介護2 | 15,318円 | 13,802円 |
| 要介護3 | 22,283円 | 20,076円 |
| 要介護4 | 24,593円 | 22,158円 |
| 要介護5 | 27,117円 | 24,433円 |
参考:介護サービス情報公表システム「小規模多機能型居宅介護」
介護度が上がるにつれて、利用料金も高くなることが分かります。また、小規模多機能型居宅介護事業所の敷地内にある、高齢者向け住まいなどにお住まいの場合、利用料金は安くなるようです。
小規模多機能型居宅介護は、月額定額制なので、利用回数が異なる月でも同じ利用料金になります。ただし、食費やオムツ代、宿泊費(1泊2,000円~3,000円程度)などは別料金です。なお、お住まいの地域の区分や事業所が取得している介護報酬の加算によって、具体的なサービス料金は異なるので、上記は参考程度にご覧ください。
出典
介護サービス情報公表システム「小規模多機能型居宅介護」(2024年5月9日)
小規模多機能型居宅介護を利用するメリット
小規模多機能型居宅介護には、必要に応じてサービスを利用しやすいというメリットがあります。以下で解説するので、チェックしてみましょう。
サービスの利用回数の制限がない
利用回数に制限がないため、必要なときにサービスを活用できるのが、小規模多機能型居宅介護のメリットです。「1日に何度も訪問してもらえる」「訪問と通いを同じ日に利用しやすい」といった特徴があります。また、深夜の訪問や、通いと泊まりの併用も可能で、24時間サポートを受けられるのも魅力です。
介護サービスは、1ヶ月あたりに利用できる単位数が決まっています。そのため、1ヶ月ごとではなく1回ごとに単位が算定される介護サービスは、無制限に利用することができません。小規模多機能型居宅介護は、1ヶ月の単位数が決まっていて月に何度でも利用できるので、「回数を気にせず、必要なときにサービスを使いたい」という方は、メリットを感じられるでしょう。
介護サービスが定額で費用負担が分かりやすい
訪問介護とデイサービスを個別に利用する場合などは、それぞれの利用回数に応じた利用料を支払うことになります。一方、小規模多機能型居宅介護は、定額で「通い」「訪問」「泊まり」をすべて利用できるので、必要な費用が分かりやすいでしょう。前述したように、どのサービスを何回利用しても、毎月の費用負担が一定になることは、利用のメリットといえます。
状況に合わせてサービスを利用できる
小規模多機能型居宅介護は、状況に合わせて利用しやすいサービスです。融通が利くため、臨時で利用することもできます。また、3つのサービスを同じ事業所が提供するので、ケアマネジャーが利用者さんの状況を把握しやすく、サービスをうまく活用できるでしょう。
スタッフや利用者さんとなじみの関係を築きやすい
同じ事業所で複数のサービスを提供するので、スタッフと信頼関係を築きやすいのも、小規模多機能型居宅介護を利用するメリットです。3つのサービスを同じメンバーが提供するため、環境の変化が苦手な認知症の方も、安心して利用できます。
複数のサービス事業所と関わる必要がないので、コミュニケーションや手続きがラクなのも魅力です。また、施設の利用定員が少ないため、利用者さん同士もなじみの関係を築きやすいでしょう。
小規模多機能型居宅介護を利用するデメリット
小規模多機能型居宅介護の利用には、メリットだけではなくデメリットもあります。「小規模」と「多機能」という2つの性質のデメリットも確認してみましょう。
訪問介護やデイサービスなどを併用できない
小規模多機能型居宅介護を利用する場合、「通い」「訪問」「泊まり」に該当するほかの介護サービスを併用できません。利用できなくなるサービスは、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどです。
すでに介護保険サービスを利用している方は、小規模多機能型居宅介護のみに乗り換える必要があり、ケアマネジャーも変更になります。そのため、「デイサービスで仲の良い利用者さんがいる」「今のケアマネを信頼している」など、サービスを継続利用したい人は、デメリットを感じるかもしれません。
なお、福祉用具貸与、住宅改修、訪問看護など、小規模多機能型居宅介護と別の目的の介護サービスは、併用できます。
1日あたりの利用定員が少ない
「小規模多機能型居宅介護事業所の定員」でお伝えしたように、通い・泊まりのサービスは、それぞれ1日の利用者数の制限があります。希望者が多い場合、使いたいタイミングでサービスを利用できない可能性があるのが、小規模多機能型居宅介護のデメリットです。
小規模多機能型居宅介護とほかの介護サービスの違い
小規模多機能型居宅介護とほかの介護サービスの違いを以下で解説するので、チェックしてみましょう。
小多機の「通い」とデイサービスの違い
小規模多機能型居宅介護の「通い」とデイサービスは、利用条件や料金などが異なります。
| 小多機の通い | デイサービス | |
| 対象者 | 要介護1~5 要支援1・2(介護予防) | 要介護1~5 要支援1・2(総合事業) |
| 利用条件 | 事業所と同じ市区町村に住民票がある | 送迎の対応エリアであれば市区町村外の方も利用できる |
| 通所日 | 事業所と相談して柔軟に利用できる | 基本的に決められた曜日に利用する |
| 利用時間 | 短時間の利用も可能 | 1日もしくは半日といった長時間の利用が一般的 |
| 利用料金 | 月額定額(回数・利用サービスによって変化しない) | サービス料金×利用回数 ※要支援は、週の利用頻度でサービス料金が決まる |
| 活動内容 | 自宅のように比較的自由に過ごせる | 施設のスケジュールに応じた活動 |
小規模多機能型居宅介護とデイサービスは、どちらも要介護・要支援認定を受けていれば利用できます。一般的なデイサービスを利用する際に、居住地域の定めはありませんが、「地域密着型」の事業所は、市区町村に住む方が対象です。デイサービスは、入浴・リハビリ・趣味など、特定のサービスに特化した施設も少なくありません。
また、小規模多機能型居宅介護が月額定額制なのに対し、デイサービスは1回あたりの利用料金が決まっています。通いのみ利用する場合や、利用回数が少ない場合は、デイサービスのほうが安く利用できる可能性があるでしょう。
デイサービスの特徴を知りたい方は、「デイサービスとは簡単にいうとどんな施設?通所介護の種類や費用を解説!」の記事をご参照ください。
小多機の「訪問」と訪問介護の違い
小規模多機能型居宅介護の「訪問」と訪問介護は、利用時間やサービス内容が異なります。
| 小多機の訪問 | 訪問介護 | |
| 対象者 | 要介護1~5 要支援1・2(介護予防) | 要介護1~5 要支援1・2(総合事業) |
| 利用条件 | 事業所と同じ市区町村に住民票がある | 送迎の対応エリアであれば市区町村外の方も利用できる |
| 訪問日 | 事業所と相談して柔軟に利用できる。緊急時や夜間の訪問にも対応 | 基本的に決められた日時に訪問がある |
| 利用時間 | 必要な時間利用できる。数分間のみや長時間の訪問も可能 | 「30分未満」など、援助内容によって時間が決まっている |
| 利用料金 | 月額定額(回数・利用サービスによって変化しない) | サービス料金×利用回数 ※要支援は、週の利用頻度でサービス料金が決まる |
| サービス内容 | 利用者さんの生活に寄り添ったサービス。訪問介護で対応できない散歩の付き添いなども可能 | 入浴介助・排泄介助・買い物代行など、利用者さんの生活に必要不可欠と認められたサービス |
訪問介護は、基本的に決められた時間にしかサービスを利用できません。利用時間と回数で料金が決まるので、1日に何度も訪問する場合は、回数分の費用がかかります。
一方、小規模多機能型居宅介護は、短時間や急な訪問にも対応できるのが特徴です。料金は月額制なので、1日に何度も訪問してもらったり、週によって訪問回数が違ったりする場合も、料金は一定になります。
▼関連記事
訪問介護とは?仕事内容や必要な資格、働くメリットをわかりやすく解説
小多機の「泊まり」とショートステイの違い
小規模多機能型居宅介護の「泊まり」とショートステイは、どちらも要介護もしくは要支援の認定を受けていれば利用可能です。ショートステイは、デイサービスや訪問介護と同様、市区町村外の方も利用でき、利用料金は1日ごとに発生します。
また、ショートステイは事前の予約が必須ですが、小規模多機能型居宅介護の泊まりは突発的な利用が可能です。小規模多機能型居宅介護には、通い慣れている施設に宿泊できるという強みもあります。普段と同じ施設で過ごせるので、環境の変化が苦手な方も安心して利用しやすいのが特徴です。
▼関連記事
ショートステイとは?介護職員の仕事内容や1日のスケジュールなどを解説!
小多機と看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の違い
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)は、その名のとおり、看護サービスを提供するのが特徴です。運営に関する基準として、「日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を打倒適当に行う」ことが定められています。また、常勤換算で2.5人以上の看護職員の配置が必要です。
小多機と看多機は、どちらも地域密着型サービスなので、市区町村に住んでいる方が利用できます。看多機は、要介護認定を受けている方が対象で、要支援の方は対象外です。訪問看護が必要な方向けのサービスなので、要介護1・2より、要介護3以上の利用者さんの割合が高くなっています。
出典
e-Gov法令検索「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(2024年5月9日)
厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)について」(2024年5月9日)
小多機とグループホームの違い
グループホームは、入居している方に介護サービスを提供する施設です。1日ごとの利用料金だけではなく賃料を支払う必要があるため、小規模多機能型居宅介護を利用するよりも、費用がかかります。また、認知症の方のみが対象なことや、要支援1の方は利用できないことが特徴です。グループホームについて詳しく知りたい方は、「グループホームとは?簡単に解説します!入居条件や費用、メリット、選び方」の記事をご覧ください。
小規模多機能型居宅介護とグループホームの共通点は、どちらも地域密着型の介護サービスであることです。地域密着型サービスは、支援や介護が必要になった場合も、住み慣れた地域の一員として暮らせるよう、2006年に創設されました。
▼関連記事
小規模多機能型居宅介護の一日の流れは?仕事内容や他施設との違いも解説
小規模多機能型居宅介護の利用に向いている人
小規模多機能型居宅介護の利用に向いているのは、下記のような希望がある方です。
- 住み慣れた地域で在宅生活を続けたい
- 1つの事業所を利用してなじみの関係を築きたい
- 状況に応じてサービスを併用したい
- 夜間や休日にもサービスを利用したい
- 1日に複数回の服薬介助や排泄介助が必要
小規模多機能型居宅介護の利用は、「サポートが必要になったけど、できるだけ今までのように穏やかに暮らしたい」という方に向いているでしょう。ほかの介護サービスと比べて柔軟に利用できるので、自身の希望する生活を実現させやすいといえます。
小規模多機能型居宅介護の利用に向いていない人
下記のような状況の方は、小規模多機能型居宅介護ではないサービスの利用を検討してみましょう。
- ほかの介護サービスの利用を継続したい
- 複数の事業所のいろいろな人とコミュニケーションを取りたい
- 複数の介護サービスが必要ない
- 認知症の進行により自宅で生活を続けるのが難しい
- 医療の必要性が高い
すでにデイサービスや訪問介護などでなじみの関係ができている方は、特に問題がなければ、現在のサービスの利用を継続すると良いかもしれません。また、1つのサービスのみを使いたい場合や、自宅での生活を続けるのが困難な場合も、小規模多機能型居宅介護以外が適している可能性があります。
小規模多機能型居宅介護を利用する方法
小規模多機能型居宅介護を利用する流れは、次のとおりです。
- 1.ケアマネジャーに利用希望を伝える
- 2.施設を見学する
- 3.要介護認定の手続き(介護保険を利用していない場合)
- 4.ケアプランの交付・契約
- 5.利用開始
以下で解説するので、ぜひ参考にしてください。
ケアマネジャーに利用希望を伝える
すでに介護保険サービスを使っている方が、小規模多機能型居宅介護を利用したい場合、担当のケアマネジャーに相談しましょう。ケアマネジャーに相談すれば、小規模多機能型居宅介護と連携してくれるので、利用までの手続きがスムーズです。
まだ介護保険サービスを利用していない方は、小規模多機能型居宅介護事業所に直接問い合わせるか、ケアマネジャーが相談に乗ってくれる「地域包括支援センター」に相談すると良いでしょう。
施設を見学する
利用したい小規模多機能型居宅介護事業所を見つけたら、施設見学をするのがおすすめです。事前に連絡を取れば、ご本人やご家族の見学に対応してくれるでしょう。見学では、利用者さんやスタッフの様子から、施設の雰囲気が合うか確認できます。
要介護認定の手続き(介護保険を利用していない場合)
要介護認定を受けていない場合、介護保険サービスを利用するための手続きが必要です。要介護認定の申請・認定調査を経て、介護度が決定。介護度によって利用料が決まります。
小規模多機能型居宅介護事業所や、地域包括支援センターに相談すれば、ケアマネジャーが手続きの窓口になってくれるでしょう。
ケアプランの交付・契約
「ケアプランの作成」で前述したように、小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーが、利用者さんの希望を聞いてケアプランを作成します。ケアプランには、サービスの具体的な内容が記載されているので、よく確認することが大切です。
契約書やケアプランに同意し、契約が完了すれば、小規模多機能型居宅介護の利用を開始できるでしょう。
小規模多機能型居宅介護事業所で働く職種・配置基準
小規模多機能型居宅介護事業所で働く職種と配置基準は、以下のとおりです。
|
職種 |
配置基準 |
|
|
介護職員 |
日中 |
通いの利用者3人に対して1人+訪問対応1人以上(常勤換算) |
|
夜間 |
夜勤:時間帯を通じて1人以上(宿泊者がいなければ配置なし可) |
|
|
看護職員 |
事業所に1人以上 |
|
|
ケアマネジャー |
1人以上 |
|
|
管理者 |
1人以上 |
|
|
代表者 |
1人以上 |
|
参考:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護(p.4)」
小規模多機能型居宅介護事業所には、介護職員や看護職員、ケアマネジャーなどの配置が義務付けられています。日中の介護職員は、「通いの利用者さん3人に対して1人以上」という配置に加え、訪問対応に1人以上の配置が必要です。
なお、サテライト型の事業所は、本体事業所と連携することで、上記より少ない人員配置で運営することができます。
出典
厚生労働省「第218回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2024年5月9日)
▼関連記事
小規模多機能型居宅介護の人員基準とは?働くメリット・デメリットも紹介
小規模多機能型居宅介護の仕事内容
ここでは、小規模多機能型居宅介護事業所のスタッフの仕事内容をご紹介します。職種ごとに解説するので、「小多機の仕事に興味がある」という方は、参考にしてください。
介護職員の仕事内容
介護職員は、「通い」「訪問」「泊まり」における介護サービスを提供します。具体的な仕事内容は、食事介助や入浴介助、排泄介助といった日常生活の支援、送迎などです。通院・外出時の付き添いや宿泊時の見守り、夜間の訪問にも対応します。
小多機の介護職員として働くために必須の要件はないので、無資格や未経験の方も就業可能です。未経験の場合は、まず「通い」で利用者さんや仕事内容を覚え、ある程度慣れてから「訪問」や「泊まり」に対応する可能性が高いでしょう。
看護職員の仕事内容
小多機で働く看護職員は、利用者さんの体調管理、床ずれの処置や摘便などの医療的ケア、通院介助などを行います。介護職員と連携して利用者さんの状態を把握し、普段と違う様子が見られたときには、主治医に連絡して指示を仰ぐことになるでしょう。
小多機の看護職員の仕事内容は、「小規模多機能型居宅介護の看護師の業務を解説!メリット・デメリットも紹介」の記事にまとめています。
ケアマネジャーの仕事内容
ケアマネジャーは、ケアプラン作成やモニタリング、サービス担当者会議の開催、ケアプランの見直しなどを行います。小多機は、住み慣れた自宅での生活を支援する施設です。そのため、利用者さんの生活歴、できること、1人で行うのが困難なことをしっかりと理解したうえで、本当に必要なサービスが利用できるケアプランを作成する必要があります。
なお、小多機のケアマネジャーになるには、介護支援専門員の資格と、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の修了が必要です。
管理者や代表者の仕事内容
小多機の管理者や代表者の仕事内容は、サービスの管理や事業所の経営です。具体的には、シフト作成や職員の教育、見学・契約の対応などを行います。
「小規模多機能型居宅介護事業所で働く職種・配置基準」の表でご紹介したように、小多機の管理者・代表者になるには、実務経験や研修の修了が必要です。
▼関連記事
小規模多機能型居宅介護の仕事内容とは?施設の特徴と働くメリットも解説
小規模多機能型居宅介護で働くのに資格は必要?介護職員として活躍する方法
小規模多機能型居宅介護事業所で働くメリット
小規模多機能型居宅介護で働くと、介護のスキルが身についたり、利用者さんの生活に寄り添った支援ができたりします。
幅広い介護のスキルが身につく
小規模多機能型居宅介護で働くと、「通い」「訪問」「泊まり」という3種類のサービスに対応するスキルが身につきます。「まだやったことがない介護サービスに挑戦したい」など、介護職としてスキルアップしたい方にとっては、魅力的な職場です。
利用者さんのニーズに寄り添った介護ができる
一人ひとりに個別の介護サービスを提供できるのも、小規模多機能型居宅介護で働くメリットです。ほかの介護サービスよりも柔軟に対応できるので、「もっと利用者さんの意向に沿ったケアを行いたい」という方には、向いているかもしれません。
利用者さんと信頼関係を築きやすい
小規模多機能型居宅介護事業所で働くと、利用者さんの生活を総合的にサポートできます。同じ利用者さんと接する時間が長く、関係性を築きやすいのが、働くメリットです。少人数制のため、一人ひとりの利用者さんと、しっかりと信頼関係を築けるでしょう。
小規模多機能型居宅介護事業所で働くデメリット
小規模多機能型居宅介護事業所で働くと、前述のようなメリットがある一方で、次のようなデメリットもあります。
- 仕事内容が幅広く、さまざまなスキルを求められる
- 利用者さんとの関係に悩む場合がある
- 夜勤や宿直がある
3つのサービスを提供する小規模多機能型居宅介護は、仕事内容が幅広く、「やることが多くて大変」と感じる場合があります。通いの送迎に運転免許が必要な可能性もあるため、転職の際は、必須の資格がないかチェックしておくと安心です。
小規模多機能型居宅介護は、利用者さんとの関わりが密接なので、苦手な方がいる場合などは、人間関係が難しいと感じるかもしれません。また、24時間対応の事業所のため、夜勤や宿直を担当する可能性も。日勤のみを希望する場合は、事前に相談しておくと良いでしょう。
▼関連記事
小規模多機能型居宅介護で働くメリット・デメリットを解説!
小規模多機能型居宅介護事業所の給与
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.122)」によると、小規模多機能型居宅介護事業所で働く介護職員(月給・常勤)の平均給与は、287,970円となっています。介護職員全体の平均給与は317,540円なので、およそ3万円低いようです。
これは、入居型の介護施設は、介護度の高い利用者さんが多く、給与が高めに設定される傾向にあるためと考えられます。小多機の介護職員の平均給与は、デイサービスの平均給与の275,620円と比べると、約1万円高いという結果です。
介護職員として転職する際は、給与だけではなく、仕事内容や働き方もチェックすることが大切になります。なお、給与水準は地域やスキルなどによって異なるので、平均給与は参考としてご覧ください。
出典
厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2024年5月9日)
▼関連記事
介護職員の給料は今後上がる?平均給与額や年収アップの方法も解説!
小規模多機能型居宅介護についてよくある質問
ここでは、小規模多機能型居宅介護についてよくある質問に回答します。「小多機について詳しく知りたい」という方は、ぜひご一読ください。
小規模多機能型居宅介護はずっと泊まりで利用できる?
介護保険の適用が30日までのショートステイとは異なり、小規模多機能型居宅介護は、制度上はずっと泊まりで利用できます。ただし、本来は長期の入居を前提としていません。事業所には利用定員があるため、事業所のルールで連続で利用できる日数が決まっている場合もあるようです。小規模多機能型居宅介護の泊まりに興味がある方は、「小規模多機能のロングショートとは?スタッフとして働くポイントと注意点」の記事もチェックしてみてください。
小規模多機能型居宅介護とは?分かりやすく教えて!
小規模多機能型居宅介護とは分かりやすく言うと、「通い」「訪問」「泊まり」を、同じ事業所が提供する介護サービス。事業所が小規模なことや、利用者さんのその日の状況に合わせて柔軟に使えることが特徴です。小規模多機能型居宅介護については、この記事の「小規模多機能型居宅介護とは」で解説しているので、あわせてご確認ください。
まとめ
小規模多機能型居宅介護とは、「通い」「訪問」「泊まり」を包括的に利用できる、地域密着型の介護サービスです。事業所と同じ市区町村に住民票があり、要支援もしくは要介護の認定を受けている方が利用できます。
小規模多機能型居宅介護では、事業所のケアマネジャーが作成したケアプランをもとにサービスを提供。支援内容は、身体的なケアや日常生活のサポートなどで、早朝や夜間にも対応可能です。利用料金は月額定額制で、金額は介護度などによって異なります。
小規模多機能型居宅介護を利用するメリットは、回数制限がなく、必要なときに支援を受けられること。利用のデメリットは、訪問介護などのサービスと併用できないことや、1日の利用定員が少ないことです。
介護職員・看護職員・ケアマネジャーなど、小規模多機能型居宅介護事業所には、さまざまな職種が配置されています。スタッフは、「通い」「訪問」「泊まり」という3つの介護サービスへの対応が必要です。そのため、小規模多機能型居宅介護事業所で働くと、介護従事者としてスキルアップを図ることができるでしょう。
「小多機に興味がある」「介護業界での転職を考えている」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した転職エージェントです。介護業界に精通したアドバイザーから、それぞれの施設の仕事内容や条件、働き方などをお伝えすることができます。そのため、複数の介護事業所を比較したうえで、自分に合った職場の検討が可能です。面接対策や職場見学のセッティングなども行い、転職活動を全面的にサポートいたします。サービスは完全無料なので、転職前に不安を解消したい方は、ぜひ活用してくださいね。
今の職場に満足していますか?
 ヘルパー・介護職の求人はこちら
ヘルパー・介護職の求人はこちら