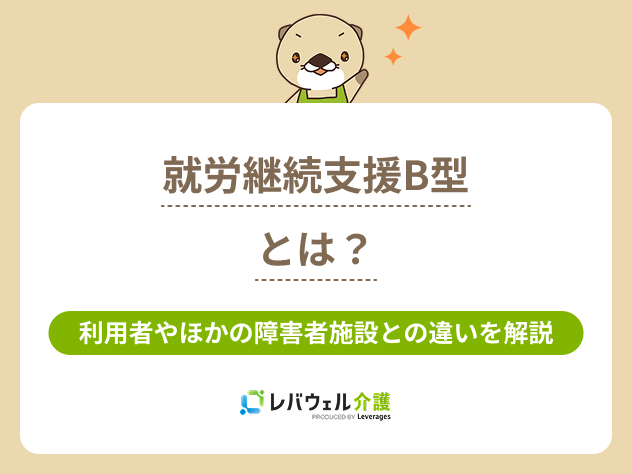
この記事のまとめ
- 就労継続支援B型とは、雇用に課題がある方に就労の場を確保する就労支援
- 就労継続支援B型の利用対象者は、障がいがあり一般企業での就労が難しい人
- 就労継続支援B型を利用するメリットは、自分のペースで就労できること
「就労継続支援B型とはどんなサービスなの?」と気になっている方もいるかもしれません。就労継続支援B型は、障がいや難病により一般企業で働くことが難しい方が、就労経験を積んだり就職に向けた支援を受けたりするサービスです。この記事では、就労継続支援B型の概要や利用対象者を解説します。就労継続支援B型を利用するメリットやほかの障害福祉サービスとの違いも紹介するので、興味がある方はぜひご覧ください。
障害者支援施設とは?仕事内容や一日の流れ、高齢者介護との違いを解説!就労継続支援B型とは
就労継続支援B型とは分かりやすくいうと、病気や障がいにより一般企業で雇用契約を結び就労することが困難な人に、就労の機会や生産活動の場を提供する就労支援サービスです。
厚生労働省の「就労系障害福祉サービスの概要(p.3)」によると、就労継続支援B型事業所は18,094事業所あり、利用者数は373,661人です(2024年年9月時点)。人員配置基準として、利用者さん10人に対し職業指導員・生活指導員のいずれか1人以上と、サービス管理責任者の配置が定められています。
就労継続支援B型は雇用契約がない
就労継続支援B型の利用者さんは、雇用契約を結ばず就労経験を積むのが特徴です。就労継続支援B型で利用者さんが行う仕事は、「生産活動」と呼ばれます。生産活動の内容は事業所によって異なり、製造作業や組み立て作業、梱包作業、パソコン入力作業などを行うようです。
就労継続支援B型の役割
就労継続支援B型は、障がいのある方に就労の支援や職業指導を行うことで、一般企業での雇用につなげる役割を担っています。一般就労が難しい方に就労の機会を提供することや、利用者さん同士や職員との交流の場をつくることも、サービスの目的です。また、支援を通じて、利用者さんの心身の健康の維持・促進に関わる事業所でもあります。
就労継続支援B型では、利用者さん一人ひとりの権利を尊重し、ご自身で意思決定できるよう支援することが大切です。
就労継続支援B型の利用期間
就労継続支援B型は利用期間が定められておらず、利用者さんは期間を気にせず就労することができます。そのため、職員は利用者さんが一般企業で就労するまで支援したり、長期的に見守ったりすることができるでしょう。
出典
厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(2025年3月17日)
内定後まで安心サポート
▼関連記事
就労継続支援B型の職員に資格は必要?仕事に役立つ研修や国家資格を解説!
就労継続支援B型の対象者
厚生労働省の「就労系障害福祉サービスの概要(p.3)」によると、就労継続支援B型の利用対象者は、サービス利用により仕事に役立つ技術の維持・習得が期待できる、障がいや難病のある方です。具体的には、以下のいずれかに当てはまる人が利用できます。
- 企業や就労継続支援A型事業所などでの就労経験があるものの、年齢や体力の面で雇用されることが困難な人
- 50歳に達している人または、障害基礎年金1級を受給している人
- 上記2つの条件に該当しないが、就労移行支援事業者のアセスメントにより、就労面の課題などが把握がされている人
- 通常の事業所に雇用されており、主務省令で定める事由により、就労に必要な知識や能力の向上のために、当該事業所で一時的に支援を受ける必要がある人
就労継続支援B型の利用条件は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
また、2025年10月からは、就労継続支援B型の利用申請前に、就労選択支援を利用することが原則になるので注意が必要です。
出典
厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(2025年3月17日)
厚生労働省「社会保障審議会障害者部会(第145回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第10回)合同会議の資料について」(2025年3月17日)
就労継続支援B型でもらえる工賃
厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)の実績について(p.1)」によると、就労継続支援B型で利用者さんに支給される平均工賃(賃金)は、23,053 円です。
就労継続支援B型事業所は、利用者さんと雇用契約を結ばないので、最低賃金が保障されるわけではありません。なお、工賃は事業所や地域によって異なるので、平均工賃はあくまで参考程度にご覧ください。
出典
厚生労働省「平均工賃(賃金)月額の実績について」(2025年3月17日)
就労継続支援B型の利用料金
就労継続支援B型の利用料金は原則1割負担です。ただし、障害福祉サービスの自己負担の上限額は世帯所得によって異なります。世帯所得は、本人が18歳以上の場合は本人と配偶者の所得です。18歳未満の場合は、本人とその両親の所得の合計で算出されます。
世帯所得別の区分と、障害福祉サービスの自己負担の上限金額は以下のとおりです。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限金額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
参照:厚生労働省「障害者の利用者負担」
低所得区分は、3人世帯で障害者基礎年金1級を受給している場合、収入が約300万円以下の世帯が対象です。一般1の区分は、収入が約670万円以下の世帯が対象。また、入所施設利用者(20歳以上)とグループホームの利用者は、市町村民税課税世帯の場合、一般2の区分になります。
出典
厚生労働省「障害者の利用者負担」(2025年3月17日)
就労継続支援B型から一般就労への移行者数
厚生労働省の「障害福祉サービスからの就職者(p.2)」によると、就労継続支援B型から一般就労への移行者は増加傾向にあります。以下に、就労継続支援B型から一般就労への移行者数の推移をまとめました。
| 時期 | 一般就労への移行者数 |
|---|---|
| 2019年(令和元年) | 4,446人 |
| 2020年(令和2年) | 3,655人 |
| 2021年(令和3年) | 3,853人 |
| 2022年(令和4年) | 4,514人 |
| 2023年(令和5年) | 5,436人 |
参照:厚生労働省「障害福祉サービスからの就職者(p.2)」
2023年度における、就労継続支援B型から一般就労への移行者は5,436人です。就労継続支援A型からの移行者は5,475人、就労移行支援からの移行者は15,675人です。A型との差はそれほど大きくありませんが、就労移行支援との差は3倍近くと大きな差があります。就労移行支援は、一般就労へ移行できる見込みが高い人が利用し、就労に向けた直接的なサポートを行うため、実際に一般就労につながりやすいようです。
就労継続支援B型以外の障害福祉サービスについては、「就労継続支援B型とほかの障害者施設との違い」でも後述するので、あわせてご覧ください。
出典
厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(2025年3月17日)
利用者さんが就労継続支援B型で就労訓練をするメリット
就労継続支援B型は、利用者さんのペースで就労訓練ができることがメリットです。障がいの状況に応じて1日数時間や週1回など、時間や日数を調整でき、短時間から少しずつ作業に慣れていくことが可能。ただし、事業所によっては勤務時間や日数の条件を定めていることもあります。
障がいへの理解がある環境で職員に見守られながら作業できるので、安心して働けることが利用者さんにとっての魅力です。
就労継続支援B型とほかの障害者施設との違い
ここでは、就労継続支援B型と「就労継続支援A型」「就労移行支援」「就労定着支援」の違いを解説します。
就労継続支援A型との違い
就労継続支援A型との違いは、利用者さんとの雇用契約の有無です。A型では、利用者さんは事業所と雇用契約を結んで働くため、最低賃金が保障されます。そのため、B型で生産活動を行うよりも多くの収入が見込めるでしょう。
ただし、勤務時間や日数の条件をある程度守りながら働くことが求められるので、安定した勤務が難しい方はB型の利用が向いているかもしれません。
▼関連記事
就労継続支援A型の職員の仕事内容は?B型との違いや職種ごとの業務を解説
就労移行支援との違い
就労継続支援B型と就労移行支援の違いは、工賃の有無です。就労移行支援は、事業所で就労機会を提供することではなく、一般企業で働くための訓練をすることが目的のため、基本的に工賃の支払いはありません。訓練としてビジネスマナーやパソコントレーニングなど就労に向けたトレーニングを行ったり、職場見学を実施したりします。
また、就労移行支援を利用できる期間は原則2年です。対象年齢は原則65歳未満となっており、B型事業所のように年齢に関わらず利用できるわけではありません
就労定着支援との違い
就労継続支援B型と就労定着支援の違いは、サービスを利用するタイミングです。就労継続支援B型は、一般企業に就職する前や退職後に利用するサービス。一方の就労定着支援は、就労支援などのサービスの利用を経て就職した方が、働きながら利用するサービスです。
就労定着支援では、一般企業に就職した人が長く働き続けるために、相談対応などのサポートを受けます。就職から6ヶ月経過した人が対象で、利用できる期限は3年間です。なお、就職後6ヶ月が経過するまでは、これまで利用してきた事業所のサポートを受けることができます。
就労継続支援B型の職員は生産活動を支援する
就労継続支援B型事業所の職員は、生産活動の支援や一般就労への移行に向けた支援、相談対応などを行い利用者さんをサポートするのが仕事です。就労継続支援B型の職員になるために必須の要件はなく、無資格から始められる仕事です。
就労継続支援B型で働く職員の仕事内容は、「就労継続支援B型の仕事内容は?職員の1日の流れと働くメリットを解説!」の記事で解説しているので、あわせてご一読ください。
▼関連記事
生活介護とは?障害者福祉施設で働く生活支援員の仕事内容と対象者を解説!
就労継続支援B型の職員についてよくある質問
ここでは、就労継続支援B型の職員についてよくある質問に回答します。「就労継続支援B型の仕事って大変なの?」と気になる方は、ぜひご覧ください。
就労継続支援B型で働く職員のよくある悩みは何?
就労継続支援B型事業所で働く職員は、仕事量の多さや利用者さんとのコミュニケーションの難しさ、昇給しないことなどに悩んでいるようです。資格を取得して専門的な知識やスキルを身につけたり、上司に相談したりすることで、悩みは解決できるかもしれません。就労継続支援B型の職員の悩みと解決方法は、「就労継続支援B型事業所の職員の悩みとは?対処法や仕事を続けるコツも解説」の記事で解説しています。
就労継続支援B型の職員の仕事ってきついの?
利用者さんの障がい特性によっては、コミュニケーションが難しい場合があります。利用者さんの不安が暴力的な言動につながることがあり、専門的な知識やスキルを求められることをきついと感じることがあるようです。就労継続支援B型の仕事にはきついこともありますが、利用者さんの成長を感じられたり、直接感謝の言葉をもらえたりするやりがいも豊富にあります。
「就労継続支援B型の職員はきつい?仕事が大変と感じる理由や対処法を解説!」の記事で就労継続支援B型の仕事できついことや対処法を解説しているので、チェックしてみてください。
まとめ
就労継続支援B型とは、病気や障がいにより一般企業で就労するのが難しい方が、サポートを受けながら生産活動などを行う障害者支援施設です。仕事に役立つ経験を積み、知識・スキルを身につけることで、通所の継続や一般就労につなげる役割があります。就労継続支援B型を利用する人は、雇用契約を結ばず就労経験を積むため、給料ではなく工賃が支給され、最低賃金は保障されません。
就労継続支援B型事業所で働く職員は、生産活動の支援や一般就労への移行に向けたサポートを行うのが仕事です。
就労継続支援B型事業所のスタッフなど、福祉のお仕事に興味がある方は「レバウェル介護(旧 きらケア)」へご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護・福祉業界に特化した転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーが、就労継続支援B型の求人をご紹介いたします。
「自分に向いている仕事が分からない…」という方もお気軽にご相談ください。ヒアリングをもとに、あなたに合った職場の求人をご提案いたします。サービスはすべて無料です。介護や福祉の仕事について知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
内定後まで安心サポート
 障害者施設の求人一覧はこちら
障害者施設の求人一覧はこちら