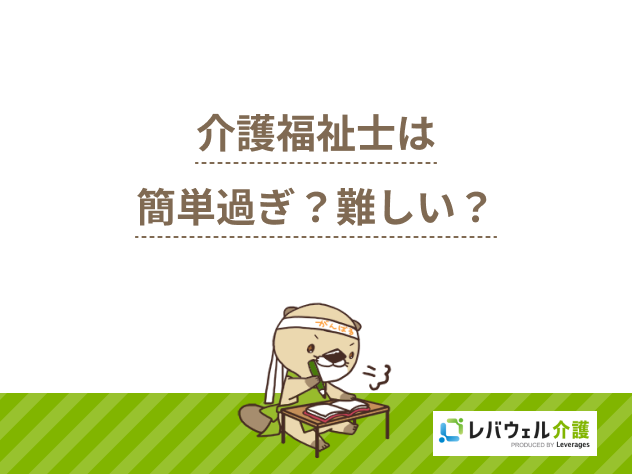
この記事のまとめ
- 介護福祉士の難易度は受け止め方次第のため、一概に簡単すぎるとはいえない
- 「介護福祉士を取るのは簡単すぎる」といわれる理由は、合格率が高いから
- 介護福祉士国家試験に合格するためには、適切な試験対策が必要
「介護福祉士になるのは簡単すぎる」という話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?介護福祉士の難易度は、簡単に感じる方もいますが、反対に難しいと感じる方もいます。この記事では、介護福祉士とほかの福祉系の資格の合格率を比較。介護福祉士の受験要件や、「簡単すぎる」といわれる理由も解説します。介護福祉士国家試験の概要や近年の変更点、合格するコツにも触れているので、ぜひご一読ください。
介護福祉士とはわかりやすくいうとどんな資格?取得方法や試験概要を解説!介護福祉士は簡単すぎるって本当?
「介護福祉士を取得するのは簡単すぎる」と感じるかどうかは人によります。
介護福祉士179人を対象にしたレバウェル介護(旧 きらケア)のアンケートによると、資格取得の難易度の感じ方は、以下のようにさまざまです。
問:介護福祉士取得の難易度をどのように感じましたか?
| 回答 | 人数 |
| 簡単だった | 21人(11.7%) |
| そこそこ簡単だった | 45人(25.1%) |
| どちらとも言えない | 62人(34.6%) |
| そこそこ難しかった | 36人(20.1%) |
| 難しかった | 15人(8.4%) |
調査時期:2023年11月
「簡単だった」「そこそこ簡単だった」と答えた方の割合が約37%であるのに対し、「そこそこ難しかった」「難しかった」の割合は約29%でした。また、最も多くの割合を占めた「どちらとも言えない」が約35%という結果からも、介護福祉士の取得難易度の感じ方は、人それぞれといえます。
今の職場に満足していますか?
▼あわせて読みたい
介護福祉士国家試験は過去問を解くだけで合格できる?過去問の選び方を解説
「介護福祉士を取るのは簡単すぎる」といわれる理由
「介護福祉士を取るのは簡単すぎる」といわれる理由としては、合格率が高かったり、養成施設の卒業が必須ではなかったりするため、ほかの国家資格よりも取得しやすいことが挙げられます。
介護福祉士国家試験は合格率が高い
厚生労働省の「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」によると、2025年に行われた介護福祉士国家試験の合格率は78.3%でした。近年の合格率は、70~80%程度です。
ほかの福祉系の公的資格と介護福祉士の合格率の違いを、下記でチェックしてみましょう。
| 資格名 | 介護福祉士 | 精神保健福祉士 | 社会福祉士 | 介護支援専門員 |
| 合格率 | 78.3% | 70.7% | 56.3% | 32.1% |
参考:厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」「第27回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します」「第37回社会福祉士国家試験合格発表」「第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」
介護福祉士の合格率は、ほかの福祉系の資格よりも高い傾向にあることが分かります。こうした合格率の高さが情報として広まり、「介護福祉士は簡単すぎる」という印象につながっているのかもしれません。
出典
厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」(2025年3月25日)
厚生労働省「第27回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します」(2025年3月25日)
厚生労働省「第37回社会福祉士国家試験合格発表」(2025年3月25日)
厚生労働省「第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」(2025年3月25日)
▼関連記事
【2025年】介護福祉士国家試験の合格率は何%?過去推移と難易度を解説
合格基準が総得点の60%程度で満たしやすい
介護福祉士国家試験の合格基準は総得点の60%程度なので、合格点を満たしやすいようです。一部難しくて解けない問題があった場合、飛ばして解答しても合格を狙えます。
ただし、実際の合格点はその年の試験の難易度によって補正されるので、確実に合格するためには、合格基準より余裕をもって得点できるよう準備することが大切です。また、11科目群すべてにおいて得点しなければいけません。科目ごとに最低1問正解しなければ、合格点を満たしても不合格となります。
▼関連記事
介護福祉士国家試験の合格点は?過去20年の推移や合格基準、難易度も解説
試験問題が五肢択一で正解しやすい
介護福祉士国家試験は、5つの選択肢のなかから1つのみを選ぶ解答方式です。五肢択一の試験問題は、記述式や五肢複択形式よりも難易度が低いため、正答しやすいでしょう。迷っても消去法で解答できたり、選択肢を見て正解を思い出せたりする可能性があります。
受験対策として実務経験を活かせる
介護職の方は、試験科目によっては実務経験を活かせるでしょう。たとえば、「介護の基本」「コミュニケーション技術」「生活支援技術」などの科目の内容は、業務を通して日常的に実践しているものが多くあります。実体験に裏打ちされた知識は、記憶として定着しやすく、試験勉強の理解がスムーズに進むようです。
受験勉強に必要な問題集や対策講座が豊富にある
試験対策を目的とした通信講座やWebサイト、問題集などが豊富なことも、介護福祉士の合格率が高い理由の一つと考えられます。
さまざまな勉強方法が展開されているので、いくつか試したうえで、自分に合った方法で学習に取り組めるでしょう。インターネットでは、無料で過去問や予想問題が公開されているので、いつでも手軽に試験対策ができます。
養成施設を卒業しなくても受験資格を得られる
介護福祉士国家試験を受験するために、大学や短期大学、専門学校などの養成施設の卒業は必須ではありません。実務経験ルートであれば、働きながら介護福祉士の受験資格を得ることが可能です。また、受験年齢や受験回数の制限がないため、自分のペースで合格を目指せます。
介護福祉士の受験資格については「介護福祉士の受験資格を得るルートを解説!必要な実務経験や試験概要は?」で詳しく解説しています。
介護福祉士の取得が難しいと思う人がいる理由
「介護福祉士になるのは難しい」と思う場合の理由としては、受験資格を得るのに数年かかることや、介護保険の専門知識を理解するのが難しいことなどが挙げられます。
介護福祉士の受験資格を得るのには数年がかかる
介護福祉士の受験資格を取得するには、主に「実務経験ルート」「養成施設ルート」「福祉系高等学校ルート」の3つの方法があります。いずれのコースで介護福祉士になる場合も、資格取得まで数年かかるため、「介護福祉士を取得するのは難しい」と思う方もいるようです。
実務経験ルート
実務経験ルートとは、「介護等の実務経験を3年以上積む」「実務者研修を修了する」という2つの要件を満たすことで、介護福祉士の受験資格を得る方法です。介護現場で実践的な技術・知識を学べるので、働きながら介護福祉士を目指したい方に向いているでしょう。
厚生労働省の「第37回介護福祉士国家試験合格発表について:参考資料(p.2)」によると、介護福祉士国家試験を実務経験ルートで受験する方の割合は9割弱と最多です。
出典
厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」(2025年3月25日)
▼関連記事
社会人として働きながら介護福祉士になるには?資格取得のルートを解説!
養成施設ルート
介護福祉士養成施設を卒業することでも、介護福祉士国家試験の受験資格を獲得できます。養成施設ルートで介護福祉士の受験資格を得る場合、基本的に最短2年の期間が必要です。福祉系大学や社会福祉士養成施設、保育士養成施設を卒業している場合は、最短1年で介護福祉士の受験資格を得られます。
福祉系高等学校ルート
福祉系高等学校を卒業し、介護福祉士の受験資格を満たす方法もあります。福祉系高校ルートは、進路を考えている中学生や、高卒学歴と介護福祉士の資格を同時に得たい方に向いている取得ルートです。指定の科目を履修して単位を修めたうえで、高校を卒業することで、介護福祉士の受験資格を満たせます。
出典
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格」(2025年3月25日)
▼関連記事
最短で介護福祉士になるには?知っておきたい3つのルート
介護の専門知識を問う問題が難しい
介護福祉士国家試験では、介護職として現場で働くだけでは身につきにくい専門知識を問う問題も出題されます。たとえば、「社会の理解」という科目は、「社会保障の理念や概念」「社会福祉六法」「社会保障の構成」など、福祉にまつわる国の制度や施策、法律などが出題範囲です。
介護保険制度に関する問題は、特に出題される可能性が高いため、事前にしっかりと対策しておく必要があります。
介護福祉士国家試験の勉強にかかる期間
介護福祉士179人を対象にしたレバウェル介護(旧 きらケア)のアンケートによると、介護福祉士国家試験の勉強にかけた期間は、以下のとおりです。
問:介護福祉士の試験勉強はいつ始めましたか?
| 試験勉強を始めた時期 | 人数 |
| 試験の2年以上前 | 6人(3.4%) |
| 試験の1~2年前 | 10人(5.6%) |
| 試験の6ヶ月~1年前 | 72人(40.2%) |
| 試験の3ヶ月~6ヶ月前 | 53人(29.6%) |
| 試験の3ヶ月前以降 | 30人(16.8%) |
| 不明 | 8人(4.5%) |
調査時期:2023年11月
介護福祉士国家試験の対策は、「試験の6ヶ月から1年前」に始めた人が最も多く、約40%でした。次いで、「試験の3ヶ月~6ヶ月前」が約30%となっています。介護福祉士を受験する場合、半年以上前から計画的に勉強することで、合格に近づけるでしょう。
介護福祉士国家試験の概要
ここでは、介護福祉士国家試験の出題形式や科目、近年の変更点をご紹介します。
出題形式と出題科目
介護福祉士国家試験は、出題数125問の筆記試験で、午前と午後の2部制です。
公益財団法人社会福祉振興・試験センターの「[介護福祉士国家試験] 試験概要」によると、介護福祉士国家試験の試験科目は以下の13科目です。
- 人間の尊厳と自立
- 人間関係とコミュニケーション
- 社会の理解
- 介護の基本
- コミュニケーション技術
- 生活支援技術
- 介護過程
- こころとからだのしくみ
- 発達と老化の理解
- 認知症の理解
- 障害の理解
- 医療的ケア
- 総合問題
コミュニケーション技術や認知症の理解など、介護職に必要なスキルが問われる内容です。総合問題以外の12科目は、さらに大項目・中項目・小項目に体系化されています。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験] 試験概要」(2025年3月25日)
受験者数の推移
厚生労働省の「第37回介護福祉士国家試験合格発表について:参考資料(p.1)」によると、介護福祉士国家試験の受験者数の推移は下記のとおりです。
| 実施年(回) | 受験者数 |
| 2025年(第37回) | 75,387人 |
| 2024年(第36回) | 74,595人 |
| 2023年(第35回) | 79,151人 |
| 2022年(第34回) | 83,082人 |
| 2021年(第33回) | 84,483人 |
参考:厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について:参考資料(p.1)」
直近5年間の平均受験者数は約79,000人で、2023年から2025年は平均より下回っていることが分かります。また、2021年と2025年の受験者数を比較すると9,000人ほど減少していることから、介護福祉士の成り手不足が懸念されているようです。
合格率の推移
同資料によると、介護福祉士国家試験の合格率は下記のように推移しています。
| 実施年(回) | 合格率 |
| 2025年(第37回) | 78.3% |
| 2024年(第36回) | 82.8% |
| 2023年(第35回) | 84.3% |
| 2022年(第34回) | 72.3% |
| 2021年(第33回) | 71.0% |
参考:厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について:参考資料(p.1)」
直近5年間の平均合格率は約78%で、2023年と2024年は平均を大きく上回る合格率でした。
出典
厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」(2025年3月25日)
受験資格や受験科目に関する変更点
2025年と2026年の介護福祉士国家試験では、受験資格や受験科目に関する変更があります。こうした背景には受験者数の減少があり、介護人材の安定的な確保を目的に、制度が改正されたようです。
2025年実施の試験からは実技試験が完全に廃止
介護福祉士国家試験の変更点として、2025年(第37回)からは、実技試験が完全に廃止されました。廃止以前から、実技試験を受ける必要があるのは一部の受験者だけだったため、現状に即した改正といえるでしょう。
2026年実施の試験からパート合格の制度が導入予定
2026年(第38回)介護福祉士国家試験からは、受験科目をパートごとに分ける「パート合格制度」が導入される見込みです。
パート合格制度では、試験13科目を3パートに分けたうえでパートごとに合否を判定します。3パートのうち不合格となったパートのみを、来年度以降に受験できるため、試験に合格しやすくなるでしょう。なお、免除期間は翌々年までで、2回再挑戦できる機会を設けています。
出典
厚生労働省「介護福祉士国家試験パート合格の導入に関する検討会」(2025年3月25日)
▼関連記事
介護福祉士のパート合格とは?受験の仕組みは?試験科目や合格基準をご紹介
介護福祉士国家試験に落ちる人の特徴
ここでは、介護福祉士国家試験で不合格となる理由について解説します。不合格となってしまう要因を把握し、介護福祉士の取得へとつなげましょう。
勉強不足により試験対策が不十分
「介護福祉士の試験は簡単すぎる」という言葉を耳にしたり、合格率が高いという情報を知っていたりすると、つい油断して勉強がおろそかになることも。対策が不十分だと、試験に合格するのは難しいでしょう。
「介護の専門知識を問う問題が難しい」で解説したとおり、介護福祉士試験では、日常では見聞きすることが少ない介護関連の制度や施策、法律などの出題があります。出題科目を網羅するためには、勉強時間を十分に確保したうえで試験対策を行う必要があるでしょう。
過去問で受験対策していない
過去問を解いていないと、出題傾向が分からなかったり、問題文を理解するのに時間がかかったりするおそれがあります。出題科目は範囲を示すものであり、実際の設問の特徴は過去問を解いてみなければ分かりません。また、問題文を読み慣れていないと、問いそのものを理解するのに時間を要する可能性があります。
せっかく正答が分かっていても、導き出すまでに時間がかかれば、125問すべてに解答するのは難しくなってしまうかもしれません。解答のペースを掴むためにも、過去問を解いて実際の問題に慣れておくと良いでしょう。
問題の出題傾向を理解できていない
公益財団法人社会福祉振興・試験センターが「介護福祉士国家試験」で公開している試験概要などを確認して試験科目を把握していないと、出題傾向を理解するのは難しいといえます。
介護福祉士試験では、暗記問題だけではなく、実際の介護現場を想定した事例問題も出題されるため、傾向を把握して対策しないと正答するのは難しいでしょう。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験」(2025年3月25日)
▼関連記事
介護福祉士国家試験に落ちる人の特徴は?あなたは大丈夫?合格のコツも紹介
介護福祉士国家試験に合格するためのコツ
介護福祉士国家試験に落ちる人の特徴をまとめると、「勉強不足」「受験対策ミス」「出題傾向の理解不足」でした。それを踏まえて、介護福祉士国家試験に合格するためのコツを解説します。
計画的に試験勉強を行う
1日に何分、何日間かけて試験勉強をするのかスケジュールを立てましょう。合格するには試験科目11科目群すべてで得点する必要があるので、出題範囲を網羅するために、勉強時間を十分に確保することが求められます。
特に、働きながら介護福祉士を目指す場合、仕事と日常生活のなかでまとまった勉強時間をつくるのは難しいことも。起床時や就寝前、仕事の休憩時間など、スキマ時間をうまく活用するのがポイントです。介護福祉士国家試験の対策アプリを活用してスマホでこまめに勉強する方法もあるので、試してみるのも良いでしょう。
▼関連記事
介護福祉士アプリのおすすめ2選!活用するメリットと勉強方法のポイント
過去問や受験対策用の問題集で繰り返し勉強する
過去問や問題集を繰り返し解き、出題傾向を理解しましょう。過去問は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターの「[介護福祉士国家試験 ]過去の試験問題」から3年分を確認できます。繰り返し解けば、出題傾向だけではなく、自分の苦手科目も把握できるでしょう。また、問題文に慣れることで、スムーズに解答できるようになります。
試験対策では、苦手科目を重点的に勉強したり、解答時間を計って過去問を解いたりすると良いでしょう。作業的に勉強するのではなく、本番のことを考えながら取り組んでみてください。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験 過去の試験問題」(2025年3月25日)
▼関連記事
介護福祉士試験の勉強にノートは有効?試験対策の方法を解説
通信講座や動画サイトを利用する
過去問や問題集の内容を理解するために、通信講座や動画サイトを利用するのも効果的な勉強方法です。
通信講座では、試験合格を目標にしたカリキュラムが組まれているため、対策漏れを心配せず勉強できます。試験対策に関するアドバイスをもらえたり、専門的な立場で質問に答えてもらえたりするため、客観的な評価や意見を活かした受験対策ができるでしょう。
また、動画サイトでは、多くの試験対策動画がアップされています。映像やイラストなどを使って分かりやすく解説しているものが多いようです。スキマ時間の活用や復習教材として、視聴してみるのも良いでしょう。
▼関連記事
介護福祉士国家試験の勉強方法とは?効率の良い受験対策と合格するコツ
介護福祉士の資格を取得するメリット
「介護福祉士になるのは簡単すぎ」という言葉を聞いたことや、介護福祉士の資格がなくても介護業界で働けることから、介護福祉士の必要性や価値に疑問を持つ人がいるようです。
ここでは、介護福祉士を取得するメリットを解説します。改めて、介護福祉士の重要性について確認してみましょう。
介護業界でキャリアアップできる
介護福祉士は、下記の介護資格の受験要件の一つになっているため、キャリアアップを目指すうえで重要な資格です。
- 認定介護福祉士
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 介護福祉士ファーストステップ研修
- 介護福祉士基本研修
また、介護現場以外では、下記のような職種を目指すこともできます。
- 介護福祉士養成施設の教員
- 福祉系高等学校の教員
- 初任者研修や実務者研修の講師
介護福祉士の資格を取得すると、介護福祉士としてキャリアを積むことも、新たな職種に挑戦しキャリアの幅を広げることもできるでしょう。
▼関連記事
介護福祉士のキャリアアップ方法をご紹介!資格や経験を活かせる職種は?
給与アップが期待できる
介護福祉士を取得すると、資格手当が付いたり昇給したりして、給与がアップする可能性があります。
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.157)」によると、介護職員の保有資格別の平均給与は、下記のとおりです。
| 保有資格 | 平均給与 |
| 介護福祉士 | 331,080円 |
| 介護職員初任者研修 | 30,0240円 |
| 無資格 | 268,680円 |
参考:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.157)」
介護福祉士の平均給与は、無資格の介護職員より6万円以上高いという結果です。また、介護職員初任者研修を取得している職員と比べた場合も、介護福祉士の平均給与は3万円以上高いことが分かります。
出典
厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2025年3月25日)
▼関連記事
介護福祉士の資格手当の相場は?取得すると給与がいくらアップするのか解説 高給与の求人一覧はこちら
高給与の求人一覧はこちら
業務範囲が広がる
介護福祉士になると、リーダーや主任など、責任ある立場を任されることも少なくありません。介護業務だけではなく、介護職員の指導・教育を担うといったマネジメント業務を任される可能性もあります。
介護福祉士の資格を取得し、幅広い業務を担当することで、介護のプロとしてさらなる経験を積むことができるでしょう。
就職や転職で有利に働く
介護福祉士を取得していることは、介護に関する専門的な知識や技術を持っている証拠にもなるため、就職や転職で有利に働きます。また、実務経験ルートで介護福祉士になる場合、すでに実務経験があり即戦力として期待できる点も、採用において有利に働くようです。
▼関連記事
介護福祉士は転職で有利に働く?資格を持つメリットと取得する方法
介護に関する豊富な知識が身につき周囲から信頼される
介護福祉士として専門的な知識を身につけることで、より具体的なアドバイスができるため、職場で信頼されるでしょう。また、利用者さんやご家族との面談でも、専門性を活かして相手に寄り添ったコミュニケーションができれば、より良い関係性を築くことにつながります。
介護福祉士は価値のある国家資格!
介護福祉士は、介護分野で唯一の国家資格。介護福祉士を取得すると、キャリアアップや給与アップの可能性が広がります。また、専門的な知識を習得することで、質の高い介護が提供でき、自信にもつながるでしょう。
現在の日本は、65歳以上の高齢者の割合が21%を超えた「超高齢社会」であり、今後も介護福祉士の需要は高まる見込みです。超高齢社会において、介護福祉士が担う役割は重要なため、今後活躍の場はますます広がるでしょう。
介護福祉士に関してよくある質問
ここでは、介護福祉士国家試験に関するよくある質問に回答します。「介護福祉士に落ちないか不安…」という方は、参考にしてください。
養成施設を卒業して介護福祉士に不合格だとどうなる?
公益財団法人社会福祉振興・試験センターの「介護福祉士「新規登録の手引」<経過措置対象者用>(p.10)」によると、2017年4月から2027年3月末までに養成施設を卒業した場合、試験の合否に関わらず5年間は介護福祉士として認められる経過措置が設けられています。試験を受けて不合格だった場合、卒業後5年以内に再度受験して合格するか、5年間継続して介護業務に従事することで、介護福祉士としての登録を継続可能です。なお、2027年4月以降に卒業する場合、介護福祉士試験への合格が必須となります。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[資格登録]平成29年4月1日から令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した方の介護福祉士経過措置登録の手続きについて」(2025年3月25日)
介護福祉士試験に10回落ちました…
介護福祉士試験の合格率は高い傾向にあるものの、一定数の不合格者は必ずいます。不合格になった場合、理由を十分に分析したうえで試験対策をすれば、合格に近づけるでしょう。試験会場の雰囲気や出題傾向など、試験全般に関する知識を活かすことで、合格を目指せます。
介護福祉士国家試験の対策方法は、「介護福祉士国家試験の内容が覚えられないときの勉強方法を解説!」の記事にまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
介護福祉士になるには、受験要件を満たして国家試験に合格することが必要です。合格率の高さから、「介護福祉士は簡単すぎる」と考える人がいる一方で、試験問題が難しいと感じる人もいます。試験の難易度や受験までの道のりなど、簡単かどうかの受け止め方は人それぞれです。
介護福祉士国家試験に合格するには、自分の苦手科目を把握して対策したり、過去問に挑戦したりして、万全の対策で臨みましょう。
「資格を取得しやすい職場で働きたい」という方は、転職エージェントに相談してみませんか?「レバウェル介護(旧 きらケア)」は、介護業界に特化した就職・転職支援を展開する転職エージェントです。専任のアドバイザーが、あなたの希望条件に合った求人をご紹介いたします。サービスの利用はすべて無料なので、まずはお気軽にご相談ください。
今の職場に満足していますか?